PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(1)読書案内「日本語・教育」
(21)週刊マンガ便「コミック」
(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(58)演劇「劇場」でお昼寝
(2)映画「元町映画館」でお昼寝
(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(109)読書案内「映画館で出会った本」
(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(25)読書案内「現代の作家」
(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(31)読書案内「近・現代詩歌」
(51)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(14)映画「パルシネマ」でお昼寝
(41)読書案内「昭和の文学」
(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(16)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(32)ベランダだより
(133)徘徊日記 団地界隈
(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(26)徘徊日記 須磨区あたり
(26)徘徊日記 西区・北区あたり
(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」
(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」
(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(13)映画 パレスチナ・中東の監督
(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(22)映画 香港・中国・台湾の監督
(36)映画 アニメーション
(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(36)映画 イタリアの監督
(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(14)映画 ソビエト・ロシアの監督
(6)映画 アメリカの監督
(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発
(5)読書案内「旅行・冒険」
(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(4)映画 フランスの監督
(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(10)映画 カナダの監督
(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督
(6)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(5)映画 トルコ・イランの映画監督
(8)映画 ギリシアの監督
(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督
(2)映画 ハンガリーの監督
(4)映画 セネガルの監督
(1)映画 スイス・オーストリアの監督
(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(1)読書案内 ジブリの本とマンガ
(5)徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり
徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり
ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり
週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)
週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)
イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249
ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり
週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)
ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248
コメント新着
キーワードサーチ
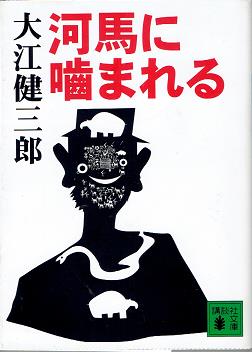 大江健三郎
なんて、若い人はお読みになるのでしょうか。まあ、年取った人もお読になるのか、ともいえるわけだですけれど、入試で使われるわけじゃないし、読んで、ああ、おもしろいとなるわけじゃないし、やたら誰も読まない西洋の古典や哲学を持ち出して、読んでいながら 「さあ、もう、投げ出しなさい、投げ出しなさい。」
と声をかけられているとでもいう展開だし、作品の中でのことではあるのですが、小説家(書き手)の周辺と思しき登場人物の、妙に道徳的な振る舞いが鼻につくし。
大江健三郎
なんて、若い人はお読みになるのでしょうか。まあ、年取った人もお読になるのか、ともいえるわけだですけれど、入試で使われるわけじゃないし、読んで、ああ、おもしろいとなるわけじゃないし、やたら誰も読まない西洋の古典や哲学を持ち出して、読んでいながら 「さあ、もう、投げ出しなさい、投げ出しなさい。」
と声をかけられているとでもいう展開だし、作品の中でのことではあるのですが、小説家(書き手)の周辺と思しき登場人物の、妙に道徳的な振る舞いが鼻につくし。
作家が映っている写真を見ると、大体、昭和の大家然とした丸メガネが胡散臭いし、本来、素朴なはずの、そのデザインが逆にわざとらしくてうっとうしい。
そんな 大江健三郎
の 「河馬に噛まれる」(講談社文庫)
を、 小林敏明
という人の 「柄谷行人論」(筑摩選書)
の中の引用だか、注釈だかに促されて久しぶりに読みました。
初めて出版されたころのことを何となく覚えています。 1985年
に 文藝春秋社
から出版された単行本の文庫版ですから、30年以上前の作品です。 「ヘルメス」
という岩波文化人雑誌に掲載された章もあったとボンヤリ記憶しています。
ぼくは当時、 「連合赤軍事件」を思想的に総括した
と評判をとり、 川端康成賞
を受賞したはずの、この小説を、読み始めはしたものの、結局、途中で投げ出したのでした。ところが今回、予想もしなかった場所に連れて行かれた、そんな感じを持ちました。 「面白かった」
というのとは、微妙ですが、少し違う場所でした。
アフリカの自然公園で飼育係をしている青年が河馬に噛まれた。そんな素っ頓狂なエピソードから小説は始まります。
革命党派の生き残りの 「河馬に噛まれた青年」
はいくつかのエピソードを経て 「大江ワールド」
の住人になっていきます。
青年をめぐる出来事と、 作家である語り手
の個人的な記憶や事件が、 語り手
の日常生活に複層的に重ねられて語り続けられていきます。どこに終着点があるのか、どこまで行っても読者であるぼくにはわからないムードが漂っていて、またもや投げ出しそうだったのですが、何とかたどり着いた
最終章 「生の連鎖に働く河馬」
の末尾でこんなフレーズが用意されていました。
河の中に緑の植生のかたまりができると、河は氾濫する。水中で盛んに活動する河馬は、植生のかたまりに通路を開き、水の流れを恢復させる働きをする。
河馬にはまたラベオという魚がまつわりついており、河馬が陸上からおとしこむ植物や、河馬自体の糞を食べる。そのようにして河馬は、アフリカの自然の生物の食物連鎖に機能をはたしている。
小原氏の記述に僕は誘われる。
ラベオと呼ぶ魚の群れをまつわりつかせつつ、水流を閉ざす緑の植生のかたまりに通路を開けるべく、猛然と泳ぐ河馬のありようが、有用なものとして排泄されるそいつの糞便ともども、人を励ます眺めではないか?
おそらくは気の荒い牡の若い河馬に噛みつかれるほどまぢかから、活動を見守っていたものにとって、河馬の働きはいかにも勇ましく奮い立たしめる体のものではなかっただろうか?
文庫
に収められた 六篇
の、それぞれ独立しているともいえる連作の中に、このフレーズは二度出てきます。
もちろん、環境保護団体のアピールではありません。れっきとした 小説のことば
です。この作品全体を、あるいは、 作家の「書く」というモチベーション
の正体を照らし出す光源のありかを、かなり遠回しではあるもののも、たしかに暗示しているとぼくは読みました。
真っ暗な何もない舞台には、あたかも、人が生きる日常の光が満ちているように設定された照明が、作家によって備え付けられていることに、読者のぼくは 「あっ、そうか」
と得心しました。で、 「得心」
と一緒に、ここまで読んできた小説の世界が上から降りかかってくるような異様な感動がやってきたのです。
二度目に、そして、作品群の最後に出てきた、このフレーズを読みながら、連赤の生き残りの青年を小説の世界に召喚する作家の手つき、手管のようなものに強い違和感を感じた初読の、 あの当時
に引き戻されながらも、一方で、小説の中の 大江のことば
を借りて言うなら、 「この項つづく」
と言いきかせながら暮らしてきた ぼく自身の日々
と、その結果たどり着いた、 ぼく自身の現在
という場所を照らし出す灯のような力が、この、いかにも大江的で大仰なフレーズにはあると感じました。
60歳
を越えたぼくが、一体、 なぜ
、 「この項つづく」
と自分自身が固執してきたと感じたのか、一体、 何を 「この項つづく」
と感じてきたのか、実は両方とも、うまく言葉にすることはできません。
しかし、この年齢の、この場所に来て、 大江
のいうように 「上向きの勢いを込めて」
かは、心もとないにしても、やはり、もう一度 「この項つづく」
とつぶやいてみようか、そんな気持ちになって本を閉じたことが不思議でした。(S)
追記2020・03・22
大江健三郎
と
柄谷行人
の対談集
「全対話」(講談社)
の第一章は詩人で作家であった
中野重治
について語り合ったものです。
大江
がこの小説で使った
「この項つづく」
は、
中野重治
の著書の中の
「この項つづく」
の引用なのだということが語られているのですが、興味のある方は対談をご覧ください。
ちなみに、ぼく自身の感想は
《大江健三郎・柄谷行人「全対話」》
に書いています。ここからどうぞ。
追記2022・11・26
大江健三郎
の この作品
を、最初に手に取ったと記憶している 1985年
、ぼくは 31歳
でした。そもそも、 大江の作品群
に夢中になりはじめたのは 1975年あたり
です。で、今、現在が、 2022年
で、 68歳
です。
最近、 「大江健三郎自選短編」(岩波文庫)
という、かなり膨大な文庫本を手に取る機会があって、ポツポツ読み始めています。キーワードは 「この項つづく」
です。とりあえず、 大江健三郎
という作家の 「この項」
とは何だったのかという関心なのですが、 「奇妙な仕事」、「死者の奢り」、「飼育」
と読み継ぎながら、20代の自分が、いったい何を 「この項」
として読んでいたのか、さっぱりわからないというのが、今のところの感想で、かなりうろたえています。
要するに、あの頃の自分が 何を
そんなに面白いと思っていたのかが、今読み返してよく分からないのですね。
マア、そういうこともあって、オタついていますが、もう少し読んでみようという、意欲は残っているようなので、そのうち感想を載せたいと思っています。


-
週刊 読書案内 小澤征爾・大江健三郎「… 2024.02.17
-
週刊 読書案内 大江健三郎「読む行為」… 2024.02.10
-
週刊 読書案内 大江健三郎「芽むしり仔… 2023.06.17













