PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(1)読書案内「日本語・教育」
(21)週刊マンガ便「コミック」
(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(58)演劇「劇場」でお昼寝
(2)映画「元町映画館」でお昼寝
(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(109)読書案内「映画館で出会った本」
(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(25)読書案内「現代の作家」
(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(31)読書案内「近・現代詩歌」
(51)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(14)映画「パルシネマ」でお昼寝
(41)読書案内「昭和の文学」
(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(16)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(32)ベランダだより
(133)徘徊日記 団地界隈
(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(26)徘徊日記 須磨区あたり
(26)徘徊日記 西区・北区あたり
(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」
(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」
(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(13)映画 パレスチナ・中東の監督
(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(22)映画 香港・中国・台湾の監督
(36)映画 アニメーション
(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(36)映画 イタリアの監督
(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(14)映画 ソビエト・ロシアの監督
(6)映画 アメリカの監督
(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発
(5)読書案内「旅行・冒険」
(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(4)映画 フランスの監督
(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(10)映画 カナダの監督
(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督
(6)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(5)映画 トルコ・イランの映画監督
(8)映画 ギリシアの監督
(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督
(2)映画 ハンガリーの監督
(4)映画 セネガルの監督
(1)映画 スイス・オーストリアの監督
(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(1)読書案内 ジブリの本とマンガ
(5) ダニエル・ゴールドハーバー「HOW TO BLOW UP」シネリーブル神戸no250
徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり
徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり
ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり
週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)
週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)
イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249
ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり
週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)
ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248
徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり
徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり
ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり
週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)
週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)
イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249
ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり
週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)
ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 読書案内「村上春樹・川上未映子」
村上春樹「アフターダーク」(講談社)
「2004年《本》の旅 その5」
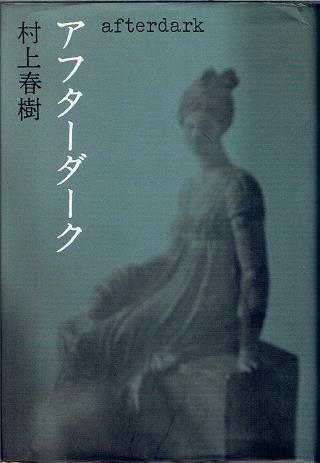
作家 村上春樹
が作家生活二十五周年と銘打って、新作 「アフターダーク」(講談社)
をこの秋(2004年)発表しました。
作家 村上春樹
が作家生活二十五周年と銘打って、新作 「アフターダーク」(講談社)
をこの秋(2004年)発表しました。
近頃の本屋さんは売れるとなると、何万部、何十万部の売上を計画しているようで、同じ本が山のように積み上げられるコトになるのですが、あれは一体なんでしょうね。大体、小説を書いているような人が、まぁ商売上の都合はあるにしてもデビュー~周年なんておかしくないですかね。なんか演歌の歌手みたいですね。ブツブツ・・・
とかなんとか言いながらチャッカリ買って読んでいるんだから、まぁ批判に性根が入っていないですね。
その上
いい年をしたおっさんが二十歳過ぎに読んだデビュー作以来、 「 1973 年のピンボール」(講談社文庫)・「羊をめぐる冒険(上・下)」(講談社文庫) から始まって、
彼を超人気作家にしたのは 1987 年 に大ブレイクした 「ノルウエイの森(上・下)」 (講談社文庫) という作品だと思うのですが、多分、百万部を超える勢いで売れたと思いますよ。小説がそんなふうに売れるという
作品の内容は互いに自意識過剰な男女が、相互理解の不可能性を確認しあった結果死んじゃうような話で暗いこと限りなしなんですが、とにかく流行りました。まあ、ケチをつけるようなことを言ってますが、そこには、やはり大勢の人の胸を打つものがあったんでしょうね。かくいうぼくも、嫌いじゃありません。
その後、この作家は 地下鉄サリン事件・オウム真理教事件 に強い関心を持つわけですが、小説で彼が描こうとしてきたこととこの事件への関心がジャスト・ミートしていたんだと、今となって気づくのですが、ちょっと、遅いですね(笑)
ボク自身 も結構ショックだった事件なのですが、 彼の小説の登場人物とあの事件の登場人物たちとの共通性が、たしかにあったんじゃないでしょうか。彼が、小説の登場人物としてしか描きようのないと考えてた人間が現実に姿を現したことに対する驚きというんでしょうか。
今、急に思い出しましたが、 ブルーハーツ の名曲 「月の爆撃機」 の中に
誰にでもあるにちがいない、他者が立ち入ることの出来ない 「心の奥」の領域 を唄っている名曲ですが、 村上春樹 が描く小説の登場人物たちはほとんど例外なく、この 「心の奥」の領域 から、ボク達が生きている生活の向こう側、あるいは壁向こう側の世界へジャンプすることで窮地を脱したり、心の奥の謎を解く場所にたどり着いたりしてきたのではなかったですかね?
それは 深い井戸の底 からであったり、偶然 転がり込んだ地下道 からだったり。 ブルーハーツ の歌の主人公が、 月に向かって飛ぶことで、黒い影となった爆撃機のコクピット に乗り込み、誰の目にも見えない宇宙の果ての世界に脱出して行くのとよく似た 小説世界 を 村上春樹 は描きつづけてきたとボクは思いますね。
主人公達は荒唐無稽な設定の中で、決して、冷静さや優しさを失わず淡々とその世界を生きていくのです。しかし、実際の生活の中で、ボク達は月に向かって飛ぶことを試みたり、心の底にどこかへの抜け道に通じる井戸があることを期待したりしません。 だからこそ人々は小説を読み、ロック・コンサートに出かけるのわけでしょ。
もしも、本当に 「〈私〉の重さ」 を ゼロ にして空を飛ぶことを試す人がいたとしたら?そして、それを信じない人たちを爆撃し始めたら?サリン事件が作家に問い掛けた事はそういうことだったのではないでしょうか。
新作 「アフターダーク」 は センスがあって音楽が好きでお人よしの男の子 と、 語学に堪能で少しエキセントリックなの女子学生 のウィットとユーモアに溢れる、この 作家 らしい会話を中心に描かれています。彼らはおたがいに、礼儀正しく、優しく、親しく、穏やかな人間関係が作品の世界を作っています。 彼ら の周りの登場人物の多くはいい人たちで、いつもの 「村上ワールド」 の住人たちです。
しかし、二人に限らず小説に登場する誰もが 「ここから誰も通さない」所 から向こう側について触れようとしません。何だか、出口なしのニュアンスがとても強い作品なんです。
作品を読みすすめながら、読者のボクは、小説そのものが深く傷ついている印象を持ちました。何ごとかが終わってしまっていて、もう始まりようがないような世界に、作品が閉じ込められているように見えるんです。
それが、当然であるかのように主人公たちは恋に落ちることも出来ないし、互いに抱きしめ合って安らぐことも出来ない。 「ここ」 から逃げ出していくほかどうしようもない感じがしてきます。何だか、作家自身が困ったところに来ているんじゃないか、そんな感じですね。とても 25周年 をノンキに寿いでいる作品とは、ボクには思えませんでした。
ボクはここで悪口を言っているつもりはないのですが、小説を読んで 「幸せ」 になりたい人にはすすめられませんね。


ボタン押してね!

にほんブログ村




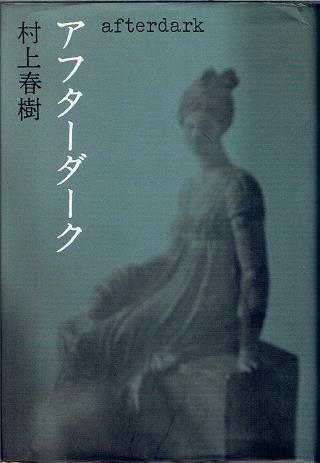
作家 村上春樹
が作家生活二十五周年と銘打って、新作 「アフターダーク」(講談社)
をこの秋(2004年)発表しました。
作家 村上春樹
が作家生活二十五周年と銘打って、新作 「アフターダーク」(講談社)
をこの秋(2004年)発表しました。
近頃の本屋さんは売れるとなると、何万部、何十万部の売上を計画しているようで、同じ本が山のように積み上げられるコトになるのですが、あれは一体なんでしょうね。大体、小説を書いているような人が、まぁ商売上の都合はあるにしてもデビュー~周年なんておかしくないですかね。なんか演歌の歌手みたいですね。ブツブツ・・・
とかなんとか言いながらチャッカリ買って読んでいるんだから、まぁ批判に性根が入っていないですね。
その上
あぁ 「風の歌を聴け」(講談社文庫) から二十五年経つんだ。 とか、なんとか感慨にふけったりするわけですから、出版社の広告が、なんというか、ちゃんとツボにはまっているんですね。
いい年をしたおっさんが二十歳過ぎに読んだデビュー作以来、 「 1973 年のピンボール」(講談社文庫)・「羊をめぐる冒険(上・下)」(講談社文庫) から始まって、
「出たら、買う。」 で、二十五年読みつづけた相手なんだから嫌いじゃないんでしょう。でも
「一番好きな作家は?」 と聞かれてもこの人の名前を出した事は一度もないから、その次くらいの作家だったし、今でもきっと、そうなんでしょうね。
彼を超人気作家にしたのは 1987 年 に大ブレイクした 「ノルウエイの森(上・下)」 (講談社文庫) という作品だと思うのですが、多分、百万部を超える勢いで売れたと思いますよ。小説がそんなふうに売れるという
「異常な出来事!」 の始まりの作品かもしれませんね。赤と緑に統一された印象的なその装丁が功を奏したわけですが、今となっては、経済成長の頂上のような 1987 年 という時代と強く関係する現象だとは思うんですけどね。
作品の内容は互いに自意識過剰な男女が、相互理解の不可能性を確認しあった結果死んじゃうような話で暗いこと限りなしなんですが、とにかく流行りました。まあ、ケチをつけるようなことを言ってますが、そこには、やはり大勢の人の胸を打つものがあったんでしょうね。かくいうぼくも、嫌いじゃありません。
その後、この作家は 地下鉄サリン事件・オウム真理教事件 に強い関心を持つわけですが、小説で彼が描こうとしてきたこととこの事件への関心がジャスト・ミートしていたんだと、今となって気づくのですが、ちょっと、遅いですね(笑)
ボク自身 も結構ショックだった事件なのですが、 彼の小説の登場人物とあの事件の登場人物たちとの共通性が、たしかにあったんじゃないでしょうか。彼が、小説の登場人物としてしか描きようのないと考えてた人間が現実に姿を現したことに対する驚きというんでしょうか。
今、急に思い出しましたが、 ブルーハーツ の名曲 「月の爆撃機」 の中に
♪♪ここから一歩も通さない という歌詞がありますが、ご存知でしょうか。
理屈も法律も通さない
誰の声も届かない
友達も恋人も入れない ♪♪
誰にでもあるにちがいない、他者が立ち入ることの出来ない 「心の奥」の領域 を唄っている名曲ですが、 村上春樹 が描く小説の登場人物たちはほとんど例外なく、この 「心の奥」の領域 から、ボク達が生きている生活の向こう側、あるいは壁向こう側の世界へジャンプすることで窮地を脱したり、心の奥の謎を解く場所にたどり着いたりしてきたのではなかったですかね?
それは 深い井戸の底 からであったり、偶然 転がり込んだ地下道 からだったり。 ブルーハーツ の歌の主人公が、 月に向かって飛ぶことで、黒い影となった爆撃機のコクピット に乗り込み、誰の目にも見えない宇宙の果ての世界に脱出して行くのとよく似た 小説世界 を 村上春樹 は描きつづけてきたとボクは思いますね。
主人公達は荒唐無稽な設定の中で、決して、冷静さや優しさを失わず淡々とその世界を生きていくのです。しかし、実際の生活の中で、ボク達は月に向かって飛ぶことを試みたり、心の底にどこかへの抜け道に通じる井戸があることを期待したりしません。 だからこそ人々は小説を読み、ロック・コンサートに出かけるのわけでしょ。
もしも、本当に 「〈私〉の重さ」 を ゼロ にして空を飛ぶことを試す人がいたとしたら?そして、それを信じない人たちを爆撃し始めたら?サリン事件が作家に問い掛けた事はそういうことだったのではないでしょうか。
新作 「アフターダーク」 は センスがあって音楽が好きでお人よしの男の子 と、 語学に堪能で少しエキセントリックなの女子学生 のウィットとユーモアに溢れる、この 作家 らしい会話を中心に描かれています。彼らはおたがいに、礼儀正しく、優しく、親しく、穏やかな人間関係が作品の世界を作っています。 彼ら の周りの登場人物の多くはいい人たちで、いつもの 「村上ワールド」 の住人たちです。
しかし、二人に限らず小説に登場する誰もが 「ここから誰も通さない」所 から向こう側について触れようとしません。何だか、出口なしのニュアンスがとても強い作品なんです。
作品を読みすすめながら、読者のボクは、小説そのものが深く傷ついている印象を持ちました。何ごとかが終わってしまっていて、もう始まりようがないような世界に、作品が閉じ込められているように見えるんです。
それが、当然であるかのように主人公たちは恋に落ちることも出来ないし、互いに抱きしめ合って安らぐことも出来ない。 「ここ」 から逃げ出していくほかどうしようもない感じがしてきます。何だか、作家自身が困ったところに来ているんじゃないか、そんな感じですね。とても 25周年 をノンキに寿いでいる作品とは、ボクには思えませんでした。
ボクはここで悪口を言っているつもりはないのですが、小説を読んで 「幸せ」 になりたい人にはすすめられませんね。
「やれやれ・・・」
にもかかわらずボクは彼の次の作品も読むにちがいないわけで、何がうれしいんでしょうね、困ったもんです。( S )2004・11・11
追記2019・10・26
村上春樹
のこの作品も 2004年
なんですね。案の定、世評は芳しくありませんでした。彼は、この5年後 「1Q84」
を書いて復活(?)します。
ぼくはこの二十年位の社会の変化と、小説作品の 「質的」
な変化に何か相関するものがあるんじゃないかという興味を最近持っています。ノベール賞のあとの 大江健三郎
や、たゆまず書き続けている 古井由吉
が忘れられているかのような文学シーンには、本屋さんが煽って、その結果、 「読者」
に媚びているかのような作品がまかり通っています。 「作家が喜ぶほめ方」
を募集する企画までありました。もう、どっちもどっちなのかもしれませんが 「作品」
はどこに行くのでしょうね。
2004年
に出た、この作品の題名が 「アフターダーク」
であることは、ちょっと考えてもいいというそういう興味です。

ボタン押してね!
にほんブログ村


お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内「村上春樹・川上未映子」] カテゴリの最新記事
-
週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻… 2024.05.25
-
週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻… 2024.05.21
-
週刊読書案内 村上春樹「騎士団長殺し」… 2024.05.20
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










