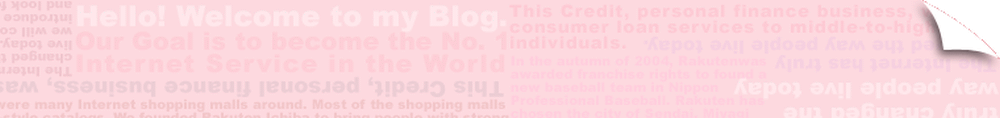全て
| カテゴリ未分類
| 競馬
| 時事ネタ?
| 2006年11月読書
| 2006年12月読書
| 身辺雑記
| 映画鑑賞記
| 2007年01月読書
| グイン・サーガ
| DVD視聴記
| 2007年02月読書
| 2007年03月読書
| 2007年04月読書
| 2007年05月読書
| 競馬MEMO
| 2007年06月読書
| 2007年07月読書
| 2007年08月読書
| 2007年09月読書
| 2007年10~12月読書
| ベストセラー
| 2008年01~03月読書
| ブックオフ105円本を読む。
| 2008年04~07月読書
| 劇も観る。
| 2008年08~12月読書
| 2009年以降の読書
カテゴリ: 2007年06月読書
[1] 読書日記
以前いつ読んだのか憶えていないが、今回読むのは、2度目である。

清水幾太郎 「本はどう読むか」(講談社現代新書)
読書論。
過去数々の類書を、好奇心として、あるいはハウトゥ目的の実用書として読んできた
が、この本が一番読みやすいし、為に成るし、何より面白い。
名著。
< 人間の意味は、いつも人間の外部にある。
人間の意味は、社会の中にある。
それが言い過ぎであるなら、
人間の意味は社会との関係の中にあると言い直してもよい。
個性も大切であろう。
独創性も大切であろう。
けれども、それは、個性や独創性が社会の中で或る優れた働きを営み、
或る客観的な成果を生んだ場合のことで、
人間の内部に眠っている個性や独創性というのは、吹けば飛ぶようなものである。
人間と社会とを繋ぐ職業の問題を真剣に考えないで、
人間や人生の意味を考えるのは、人生論業者の餌になるばかりである >
< 実用書および娯楽書については、本の読み方とか、
読書の方法とかいう問題は成り立たないものである。
実用書は、読まねばならなくなったら、読むよりほかに道はない。
娯楽書は、読みたくなったら、読めばよいのである。
それだけの話である。
面倒な問題があるのは、教養書である >
< 思想というものを最終的にテストするのは、家庭という平凡な場所であると思う。
活字という世界に生きるだけの純粋思想なら、
いくらでも急進的になれるし、いくらでも破壊的になれる。
けれども、それが社会を変革する力を持つためには、
それが家庭という場所に入り込み、そこに腰を据えなければならない >
< 書物の意味は、その書物そのものに備わっているのではなく、
書物と読者との間の関係の上に成り立っているものである >
< 有無を言わせぬ絶対の目的があって、
或る外国語の習得が、
その目的を達成すための、
これまた有無を言わせぬ絶対の手段である時、
こういう緊張関係の中でこそ外国語の勉強は身につくということである。
他に理由がなく、漠然と、語学のために語学をやっても、
決して能率の上るものではない >
以前いつ読んだのか憶えていないが、今回読むのは、2度目である。

清水幾太郎 「本はどう読むか」(講談社現代新書)
読書論。
過去数々の類書を、好奇心として、あるいはハウトゥ目的の実用書として読んできた
が、この本が一番読みやすいし、為に成るし、何より面白い。
名著。
< 人間の意味は、いつも人間の外部にある。
人間の意味は、社会の中にある。
それが言い過ぎであるなら、
人間の意味は社会との関係の中にあると言い直してもよい。
個性も大切であろう。
独創性も大切であろう。
けれども、それは、個性や独創性が社会の中で或る優れた働きを営み、
或る客観的な成果を生んだ場合のことで、
人間の内部に眠っている個性や独創性というのは、吹けば飛ぶようなものである。
人間と社会とを繋ぐ職業の問題を真剣に考えないで、
人間や人生の意味を考えるのは、人生論業者の餌になるばかりである >
< 実用書および娯楽書については、本の読み方とか、
読書の方法とかいう問題は成り立たないものである。
実用書は、読まねばならなくなったら、読むよりほかに道はない。
娯楽書は、読みたくなったら、読めばよいのである。
それだけの話である。
面倒な問題があるのは、教養書である >
< 思想というものを最終的にテストするのは、家庭という平凡な場所であると思う。
活字という世界に生きるだけの純粋思想なら、
いくらでも急進的になれるし、いくらでも破壊的になれる。
けれども、それが社会を変革する力を持つためには、
それが家庭という場所に入り込み、そこに腰を据えなければならない >
< 書物の意味は、その書物そのものに備わっているのではなく、
書物と読者との間の関係の上に成り立っているものである >
< 有無を言わせぬ絶対の目的があって、
或る外国語の習得が、
その目的を達成すための、
これまた有無を言わせぬ絶対の手段である時、
こういう緊張関係の中でこそ外国語の勉強は身につくということである。
他に理由がなく、漠然と、語学のために語学をやっても、
決して能率の上るものではない >
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[2007年06月読書] カテゴリの最新記事
-
外山滋比古 「知的創造のヒント」 2007年06月28日
-
近藤史恵 「ねむりねずみ」 2007年06月25日
-
剣持鷹士 「あきらめのよい相談者」 2007年06月21日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.