カテゴリ: 考古学・日本古代史
私は昨年北東北の3つの県を旅し、歴史的な場所を訪れました。その際の旅日記はアップしたのですが、まだ結構数多くの写真が残っていました。その大半は地中から発掘した遺物、つまり考古学資料なのです。私はそんなのが大好きだから良いのですが、大勢の読者の方々のほとんどはあまり関心がないと思われます。そこで長い間放置していたと言う訳です。でも今回は、それらの発掘物などを、「一つの美の形」として見てもらうことにしました。
まだ「空の表情」のシリーズは終わっていませんが、間に挟む形でこのシリーズと交互にお届け出来たらと考えています。では、早速始まり始まり~!!

昨年の6月25日に、私はこの「盛岡市遺跡の学び館」を訪れました。岩手のブログ友であるニッパさんが案内してくれたのです。そこにあった考古学資料の中から2点だけ紹介しますね。

土偶がついた縄文土器です。ちょっと珍しい形をしています。

これもまた、とても珍しい形をした蓋付きの土器です。模様が変わっていますね。

ここは最初にニッパさんに案内してもらった盛岡市郊外にある志波城城址公園です。志波城は平安時代の初期に建てられた、我が国で最も北に置かれた古代の城郭で、蝦夷(えみし)に備えるため征夷大将軍であった坂上田村麻呂が建造した砦です。その城址を発掘し、復元したのが上の城門(裏面)で、直ぐ傍を通る東北道からも良く見えます。

城址から発掘された鉄製の釘や斧です。このようなものを使って城が築かれました。この城によって岩手県北部や青森県東部の蝦夷が投降し、東北北部までが中央政府の支配下に入りました。つまりここは当時の日本の「最前線」だった訳です。


右側はこの城に勤務していた役人で、左側は彼らが当時使用していた円面硯(えんめんけん)で、これで墨を摺り文書を作成しました。

城内から出土した土器(浅鉢)です。城内には役人や城を護る兵士達が住んでおり、彼らが生活で使った様々な品物が発掘されています。

これは出土した土器の一部です。

これは鉄兜です。きっと兵士がこれを被って戦っていたのでしょうね。現物は「盛岡市遺跡の学び館」に陳列されていました。

これは6月26日に訪れた秋田県鹿角市にある「大湯環状列石」(サークルストーン)のうち、野中遺跡の環状列石の全体像です。写真で見ると小さいですが、現物は実に壮大なものです。これは縄文晩期のもので、当時の村人が約500年間に亘って集団墓地として使用していたもので、集落跡ではありません。

これは万座遺跡の掘立小屋で、復元されたものです。遠くに三角形の山が見え、ここが聖なる墓地だったことが分かります。小屋は住むためのものではなく、死者を弔うための宗教的な儀式に使われました。場所は川から100m以上高い台地の上にあります。縄文人の住居は飲み水が得られやすい、大湯川の傍にありました。

冬はこれだけの雪が積もると言うイメージ図です。実際にここは豪雪地帯でもあります。

出土した土偶などです。遺跡の傍にある「大湯サークルストーン館」に展示されていました。まるで骨盤と子宮のような不思議な形の土器が、とても気になります。こんな珍しい土器を見たのは初めてです。死からの再生と子孫の繁栄を祈ったのでしょうか。

3日目の6月27日には津軽半島にある2つの遺跡を訪ねました。最初に訪ねたのが半島上部の十三湖に浮かぶ中島の資料館でした。ここ十三湖には中世の豪族である安東氏の居住地があり、当時は十三湊として内外の船が出入りする貿易港でもありました。この古地図は翌日訪れた「青森県立郷土館」にあったものです。

中島遺跡から出土した縄文土器と石器。縄文時代からここにはたくさんの縄文人が住み着いていました。きっと湖には魚介類が豊富で、付近の野山にも食糧となる野獣がたくさんいたのでしょう。

美しい形をした縄文土器ですね。

これらの石器は石斧(せきふ=いしおの)と呼ばれるもので、これを木の枝に紐で縛って固定し、木を切り倒したのです。

黒曜石製の石像(左)と土偶(右)で、いずれも縄文時代のものです。鋭い刃物などが作れる黒曜石は、その性質から国内の限られた場所でしか採掘出来ません。写真のものは恐らく北海道産のものでしょう。潮流が激しい津軽海峡を、当時は小さな丸木舟で漕ぎ渡ったのです。黒曜石製の鏃(やじり)などは良く発掘されますが、このような像はとても珍しく、縄文人の宗教観、美的センスなどがとても良く分かります。
一方の土偶は一族の長命と繁栄を祈って作られたもので、人に代わって穢れを落とす意味を込めて、破壊されるのが通常です。↑の大湯環状列石の土偶の首が折れているのも、同じ理由からなのです。

十三湊遺跡出土の青磁です。これは青森県立郷土館所蔵分を載せました。安東氏によって支配されたこの中世時代の港が、日本海の海運を通じて中国大陸とも深い交流関係にあったことが良く分かります。岩手県平泉の奥州藤原氏の栄華も、この港と無関係ではありません。また源頼朝が豊かな東北を支配下に置こうとした要因の一つになったとも考えられます。
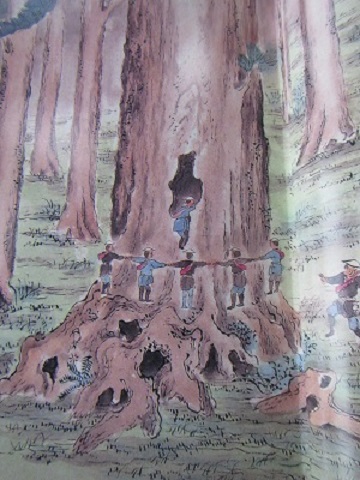
五能線のどこかの駅に張られていたポスターで、世界遺産白神山地の木こり図です。きっと江戸時代に描かれたものでしょうがが、東北の山林は昔から無限の宝庫でした。青森市の三内丸山遺跡には、高さが16mにもなる栗の丸太6本で組み立てられた櫓のような建築物や、長さが30mを超える規模のログハウスも建てられていました。趣旨に反して掲載内容がバラバラになりましたが、どうぞご容赦を~!!<続く>
まだ「空の表情」のシリーズは終わっていませんが、間に挟む形でこのシリーズと交互にお届け出来たらと考えています。では、早速始まり始まり~!!

昨年の6月25日に、私はこの「盛岡市遺跡の学び館」を訪れました。岩手のブログ友であるニッパさんが案内してくれたのです。そこにあった考古学資料の中から2点だけ紹介しますね。

土偶がついた縄文土器です。ちょっと珍しい形をしています。

これもまた、とても珍しい形をした蓋付きの土器です。模様が変わっていますね。

ここは最初にニッパさんに案内してもらった盛岡市郊外にある志波城城址公園です。志波城は平安時代の初期に建てられた、我が国で最も北に置かれた古代の城郭で、蝦夷(えみし)に備えるため征夷大将軍であった坂上田村麻呂が建造した砦です。その城址を発掘し、復元したのが上の城門(裏面)で、直ぐ傍を通る東北道からも良く見えます。

城址から発掘された鉄製の釘や斧です。このようなものを使って城が築かれました。この城によって岩手県北部や青森県東部の蝦夷が投降し、東北北部までが中央政府の支配下に入りました。つまりここは当時の日本の「最前線」だった訳です。


右側はこの城に勤務していた役人で、左側は彼らが当時使用していた円面硯(えんめんけん)で、これで墨を摺り文書を作成しました。

城内から出土した土器(浅鉢)です。城内には役人や城を護る兵士達が住んでおり、彼らが生活で使った様々な品物が発掘されています。

これは出土した土器の一部です。

これは鉄兜です。きっと兵士がこれを被って戦っていたのでしょうね。現物は「盛岡市遺跡の学び館」に陳列されていました。

これは6月26日に訪れた秋田県鹿角市にある「大湯環状列石」(サークルストーン)のうち、野中遺跡の環状列石の全体像です。写真で見ると小さいですが、現物は実に壮大なものです。これは縄文晩期のもので、当時の村人が約500年間に亘って集団墓地として使用していたもので、集落跡ではありません。

これは万座遺跡の掘立小屋で、復元されたものです。遠くに三角形の山が見え、ここが聖なる墓地だったことが分かります。小屋は住むためのものではなく、死者を弔うための宗教的な儀式に使われました。場所は川から100m以上高い台地の上にあります。縄文人の住居は飲み水が得られやすい、大湯川の傍にありました。

冬はこれだけの雪が積もると言うイメージ図です。実際にここは豪雪地帯でもあります。

出土した土偶などです。遺跡の傍にある「大湯サークルストーン館」に展示されていました。まるで骨盤と子宮のような不思議な形の土器が、とても気になります。こんな珍しい土器を見たのは初めてです。死からの再生と子孫の繁栄を祈ったのでしょうか。

3日目の6月27日には津軽半島にある2つの遺跡を訪ねました。最初に訪ねたのが半島上部の十三湖に浮かぶ中島の資料館でした。ここ十三湖には中世の豪族である安東氏の居住地があり、当時は十三湊として内外の船が出入りする貿易港でもありました。この古地図は翌日訪れた「青森県立郷土館」にあったものです。

中島遺跡から出土した縄文土器と石器。縄文時代からここにはたくさんの縄文人が住み着いていました。きっと湖には魚介類が豊富で、付近の野山にも食糧となる野獣がたくさんいたのでしょう。

美しい形をした縄文土器ですね。

これらの石器は石斧(せきふ=いしおの)と呼ばれるもので、これを木の枝に紐で縛って固定し、木を切り倒したのです。

黒曜石製の石像(左)と土偶(右)で、いずれも縄文時代のものです。鋭い刃物などが作れる黒曜石は、その性質から国内の限られた場所でしか採掘出来ません。写真のものは恐らく北海道産のものでしょう。潮流が激しい津軽海峡を、当時は小さな丸木舟で漕ぎ渡ったのです。黒曜石製の鏃(やじり)などは良く発掘されますが、このような像はとても珍しく、縄文人の宗教観、美的センスなどがとても良く分かります。
一方の土偶は一族の長命と繁栄を祈って作られたもので、人に代わって穢れを落とす意味を込めて、破壊されるのが通常です。↑の大湯環状列石の土偶の首が折れているのも、同じ理由からなのです。

十三湊遺跡出土の青磁です。これは青森県立郷土館所蔵分を載せました。安東氏によって支配されたこの中世時代の港が、日本海の海運を通じて中国大陸とも深い交流関係にあったことが良く分かります。岩手県平泉の奥州藤原氏の栄華も、この港と無関係ではありません。また源頼朝が豊かな東北を支配下に置こうとした要因の一つになったとも考えられます。
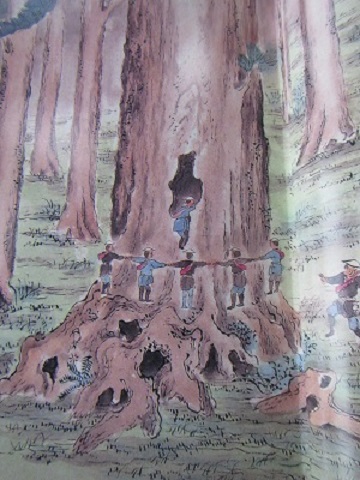
五能線のどこかの駅に張られていたポスターで、世界遺産白神山地の木こり図です。きっと江戸時代に描かれたものでしょうがが、東北の山林は昔から無限の宝庫でした。青森市の三内丸山遺跡には、高さが16mにもなる栗の丸太6本で組み立てられた櫓のような建築物や、長さが30mを超える規模のログハウスも建てられていました。趣旨に反して掲載内容がバラバラになりましたが、どうぞご容赦を~!!<続く>
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事
-
いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)
-
小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
© Rakuten Group, Inc.









