PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
コメント新着
フリーページ
カテゴリ: ヒロ散歩
山中城跡を時計回りに廻り北側の帯曲輪へ。天気が良く富士も見えていた。
4月28日(日) 8:00
山中城跡の北側の帯曲輪から富士を望む。

三島市眺望地点
右側から「富士山」手前に「三島市立 箱根の里」「愛鷹連山」「三島市街地」「駿河湾」。
平成14年12月16日指定

富士の頂上がまだ見えていた。

西櫓堀を振り返る。

西櫓の架橋
西櫓の曲輪を囲む約八二メートルの西櫓堀は、ほぼ九メートル間隔に作られた八本の畝によっ
て、九区画に区切られている。
第九区画に隣接する一段高い平坦面から四本の柱穴が検出され、この場所に西櫓へ渡る橋が架
けられていた事が推定された。
日本大学宮脇研究室では、右図のような橋の復元図を示されている。
絵は、架橋復原図
平成十二年三月 文化庁
静岡県教育委員会
三島市教育委員会

北側の帯曲輪上から左に西ノ丸、左に西櫓。
かつてはこの間に ”西櫓の架橋” があったのか。

ツツジをズームアップ。咲いていないのは他の種類か。

西ノ丸堀(にしのまるほり)
西ノ丸堀は、山中城の西方防備の拠点である西ノ丸にふさわしく、広く深く築城の妙味を発揮
しており、堀の末端は谷に連なっている。
西櫓と西ノ丸の間は、中央に丸い畝を置き、交互に両曲輪にむかって畝を出しているが、西ノ
丸の北側では東西に畝をのばして堀内をより複雑にしている。
このように複雑な堀の構造は、世に伝えられる「北条流堀障子」の変形であり、学術上の価値
も高いものである。
平成十二年三月 文化庁
静岡県教育委員会
三島市教育委員会
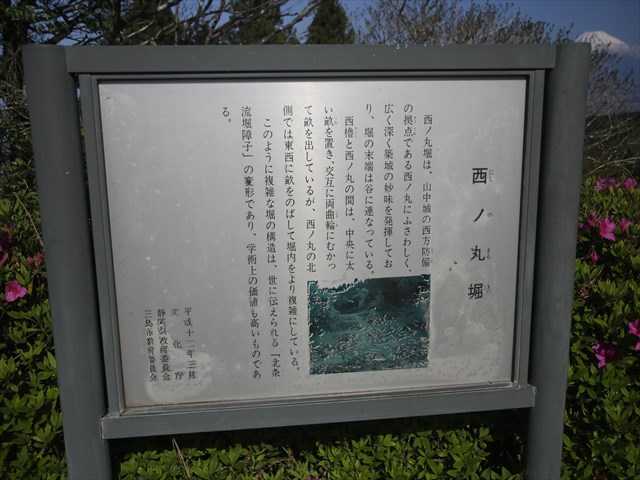
北側の帯曲輪にある休憩所(四阿)。

四阿辺りから、西櫓跡を望む。櫓下には障子堀。

杉林の中ではシイタケ栽培。

山中城跡の北側を走る ”笹原山中バイパス” 。

散策路に咲いていたオオムラサキであったか。

山中城跡の北側の傾斜地。

遊歩道に案内板。

土塁で囲まれた西ノ丸へ上る。

西の丸
西の丸は3,400㎡の広大な面積をもつ曲輪で、山中城の西方防備の拠点である。
西端の高い見張台はすべて盛土をつみあげたもので、ここを中心に曲輪の三方をコの字型に
土塁を築き、内部は尾根の稜線を削平し見張台に近いところから南側は盛土して平坦になら
している。
曲輪は全体に東へ傾斜して、東側にある溜池には連絡用通路を排水口として、雨水等が集め
られるしくみである。
自然の地形と人知とを一体化した築城術に、北条流の一端を見ることができる。
平成九年十一月 文化庁
静岡県教育委員会
三島市教育委員会
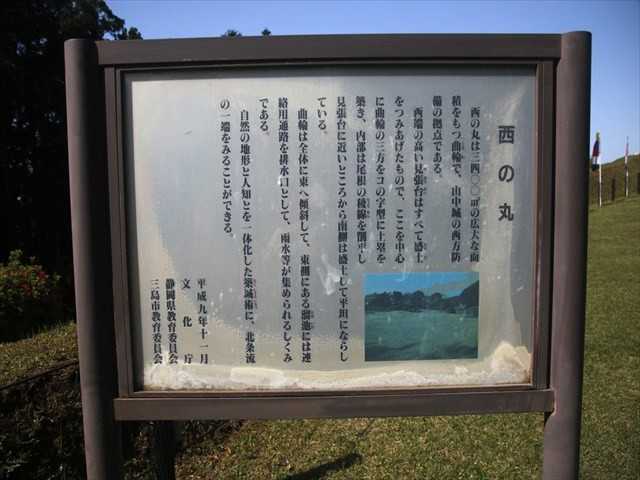
土 塁(どるい)
山中城のどの曲輪も土塁で囲まれている。石垣を使う以前の戦国時代の城は、全て堀と土塁が
築城のポイントであり、城内の何を隠すか(人・馬・槍等)によって土塁の構築が考えられた。
土塁の傾斜は堀に対して急で、内部には緩やかである。
このように自然の谷が眼下に迫っている所は、土塁も重厚なものでなく土留程度のものである。
平成八年十二月 文化庁
静岡県教育委員会
三島市教育委員会
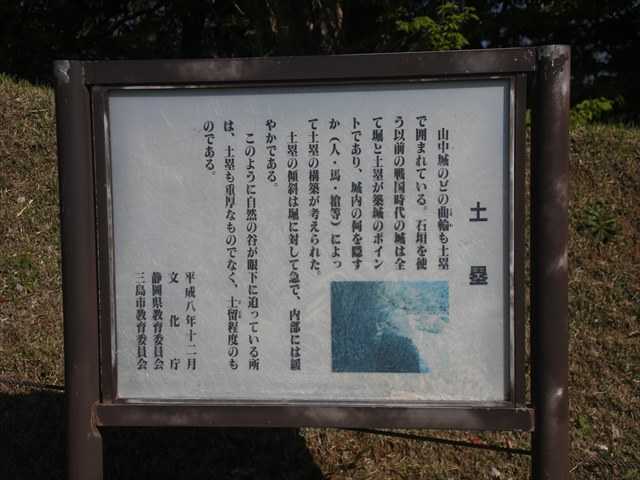
咲き始めたフジ棚があった。標高が580メートルのため開花が遅いようだ。

フジは三本あり白と紫色の二色。

白のフジは満開。

紫色はこれからの状態。
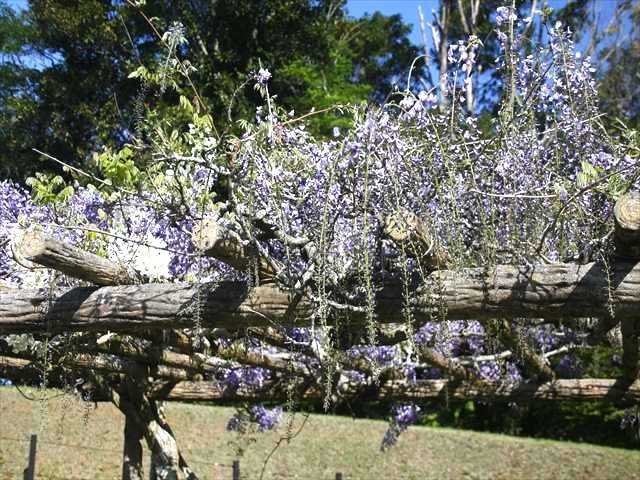
山中城の建物
西の丸を全面発掘したが、建物の遺構は確認されなかった。この地の開墾耕作で攪乱された可
能性が強く、もしあったとしても臨時の小屋程度のものであろう。
西櫓跡からは3m×2.6mの柱穴跡が、元西櫓跡からは5.4m×7m位の建物の柱穴跡が検出され、
また平らな石等も確認されているので、堀立柱の茅葺きの物置程度の建物はあったであろう。
日常生活用具である炊事道具や椀類が出土しないので、寝小屋(根小屋)は他の曲輪にあったと
考えられる。
平成八年十二月 文化庁
静岡県教育委員会
三島市教育委員会
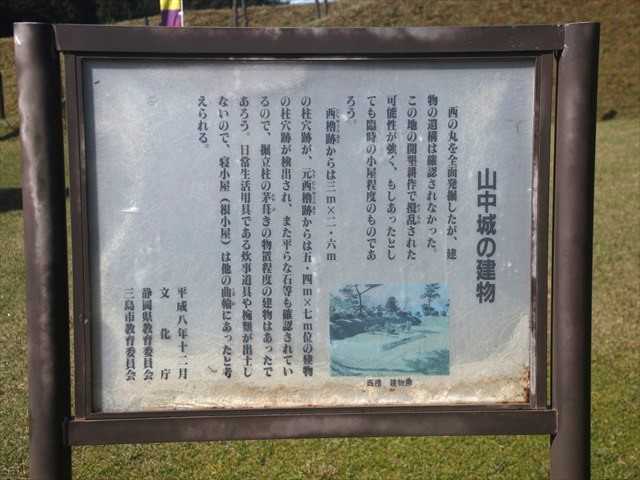
北側に富士が見えていた。

西の丸見張台
西の丸見張台は下から盛土によって構築されたものである。
発掘の結果、基底部と肩部にあたる部分を堅固にするために、ロームブロックと黒色土を交互に
積んで補強していることが判明した。
標高は約580mで、本丸の矢立の杉をはじめ、諸曲輪が眼下に入り、連絡・通報上の重要な拠点
であったことが推定できる。
平成八年十二月 文化庁
静岡県教育委員会
三島市教育委員会
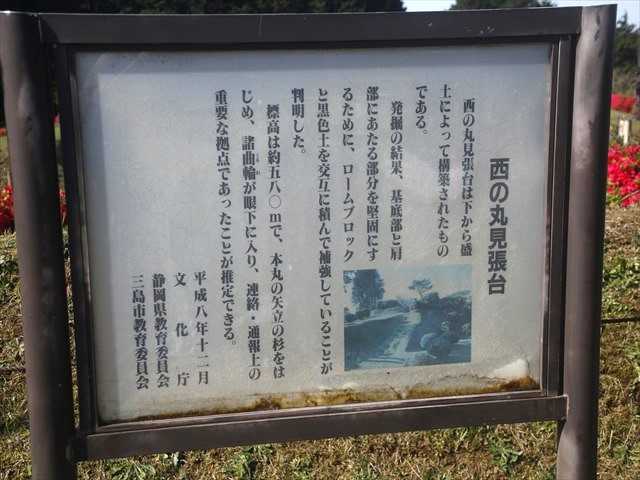
西ノ丸見張台の北側から帯曲輪、右側に四阿(休憩所)を見下ろす。

西側の西櫓跡と一段高い櫓台、西ノ丸堀、西櫓堀、北側の帯曲輪を見下ろす。

北側の帯曲輪にはサクラの木があり4月の初めには彩るのであろう。

手入れされた斜面のツツジをズームアップ。

西櫓跡の櫓台には多くの観光客が訪れていたが山中城にはまだ外人観光客の姿は見えなかった。

見張台から移動して西櫓を望む。

櫓台越しに三島市街地がうすく見える。

西ノ丸見張台から東方向の西ノ丸を見下ろす。
西ノ丸は3,400㎡の広大な面積をもつ曲輪で、東方向に向かって傾斜している。

西ノ丸に咲くフジ棚。

西ノ丸の東側から元西櫓の斜面に咲くツツジを見下ろす。

西ノ丸跡から降り、元西櫓跡へ上る。

土塁で囲まれた ”元西櫓” 。

元西櫓(もとにしやぐら)
この曲輪は西ノ丸と二ノ丸の間に位置し、周囲を深い空堀で囲まれた、640平方メートルの小
曲輪である。当初名称が伝わらないため無名曲輪と呼称したが、調査結果から元西櫓と命名し
た。曲輪内は堀を掘った土を1メートル余りの厚さに盛土し、平らに整地されている。
この盛土の下部にはロームブロックが積まれていたが、これは曲輪内に溜まった雨水を排水し
たり、霜による地下水の上昇を押さえ、表面を常に乾いた状態に保つための施設と考えられる。
しかもロームブロック層は溜池に向かって傾斜しており、集水路ともなっている。
平成十二年三月 文化庁
静岡県教育委員会
三島市教育委員会
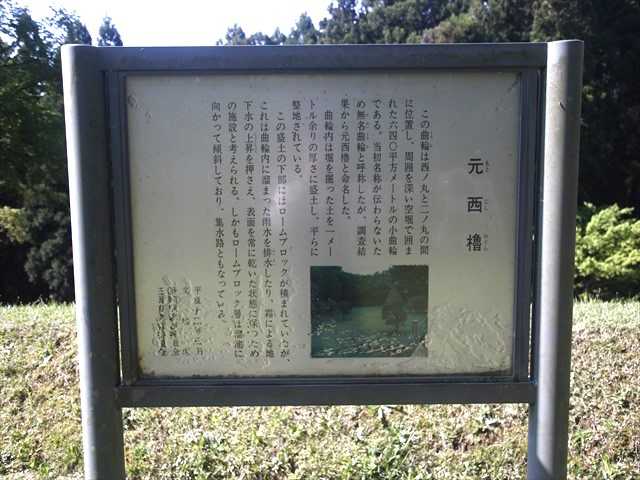
元西櫓から西方向の西ノ丸の南斜面、西ノ丸畝堀を望む。

西方向をズームアップ。

現在地は矢印の「元西櫓」。

西ノ丸への土橋に幟旗が立ち並ぶ。

元西櫓の土塁。西側の傾斜地にツツジが咲く。

モミジの若芽。

西ノ丸の入口を望む。

元西櫓から西方向の西ノ丸の南斜面、西ノ丸畝堀を望む。奥には西櫓。

8:25
西ノ丸の南斜面をズームアップ。

ー 続く ー
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事
-
藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11
-
テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10
-
日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










