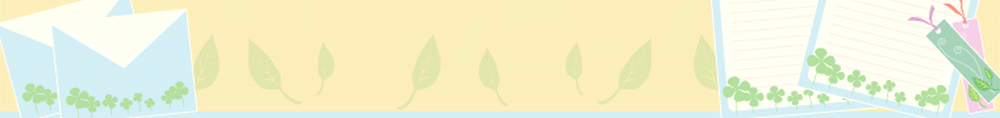カテゴリ: 旅行記


道成寺
こちらでは道成寺縁起絵巻をお坊さんが絵解きしながらお話してくれる。
何度か聞いているが独特の抑揚があってなかなか面白い。

真名古庄司の娘清姫は、安珍が熊野詣での帰りに必ず立ち寄ると約束したのに、一向に音沙汰がなく、道行く人に、このような人(安珍の風体)は通りませんでしたかと聞いている所。
その人なら大分前にあちらの方に行ったと商人に教えられ、さてはだまされたかと、足袋はだしで男を追いかける。
安珍は日高川を渡し船で渡り、女性が来たら絶対渡してくれるなと言い残す。日高川まできて渡し船に乗れない清姫は自ら川へ飛び込み大蛇となり日高川を泳ぎわたる。

安珍は道成寺の僧たちに訳を話して、鐘の中へと匿ってもらうが、大蛇は鐘に巻き付き安珍を焼き殺す。
400年後にもう清姫の執念もおさまったろうと鐘を設置した所、またも蛇が鐘を襲うと言う話は「京鹿子娘道成寺」という歌舞伎や踊りの演目になっている。
ここで以上のような絵解きの説法を聞いて、私たちは地元へと戻った。

湯浅は醤油の発祥地として広く知られるようになった。
今から約750年前・鎌倉時代、禅僧・覚心(後の法燈国師)が宋(現中国)より径山寺味噌(金山寺味噌といわれているが、正確にはこの字)の製法を伝え、帰朝後種々の改良の末、湯浅の水が良かったことから醤油が作られるようになった。これが我が国の醤油の発祥の由来である。
嘗味噌の中に、瓜・茄子などの野菜から塩の浸透圧によって水分が出てくる。
この水は当時の野菜の生産が6月~8月であったため、黴の発生や腐敗の元にもなり、捨てるだけであったのだが、昔ある時、その汁を利用してみると、これがなかなか美味しい。
そこで、初めからその汁を利用するつもりで造れば「新しい醤」つまり調味料が誕生すると考えたのが今様醤油の始まりだと言われている。
また、湯浅の水が醤油作りに適した水であった事も湯浅醤油発展の一因となっている。(角長HPより)

道成寺
和歌山県日高川町にある天台宗の寺。号は天音山千手院。俗に日高寺という。大宝1 (701) 年文武天皇の勅願により大臣紀道成 (きのみちなり) が建立。義淵僧正作の千手観音立像 (国宝) を安置する。安珍,清姫の伝説で名高く,境内にその旧跡がある。伝説とは,熊野参詣の山伏安珍が真名古庄司のもとに宿った際,庄司の娘清姫に慕われ,激しく言い寄られ,やむなく偽ってそこを逃れ,道成寺に逃げ込んで鐘の下に身を隠したが,清姫は怒りと執念のあまり大蛇と化してあとを追い,鐘に巻きついて安珍を焼き殺すという話。後日譚があり,この事件以来道成寺には鐘がなかったが,鐘を再興して鐘供養をしたところ,白拍子が現れ,舞を舞ううちに蛇体となって鐘を襲おうとしたが,僧たちに祈り伏せられたという。(コトバンクより)
こちらでは道成寺縁起絵巻をお坊さんが絵解きしながらお話してくれる。
何度か聞いているが独特の抑揚があってなかなか面白い。

真名古庄司の娘清姫は、安珍が熊野詣での帰りに必ず立ち寄ると約束したのに、一向に音沙汰がなく、道行く人に、このような人(安珍の風体)は通りませんでしたかと聞いている所。
その人なら大分前にあちらの方に行ったと商人に教えられ、さてはだまされたかと、足袋はだしで男を追いかける。
安珍は日高川を渡し船で渡り、女性が来たら絶対渡してくれるなと言い残す。日高川まできて渡し船に乗れない清姫は自ら川へ飛び込み大蛇となり日高川を泳ぎわたる。

安珍は道成寺の僧たちに訳を話して、鐘の中へと匿ってもらうが、大蛇は鐘に巻き付き安珍を焼き殺す。
400年後にもう清姫の執念もおさまったろうと鐘を設置した所、またも蛇が鐘を襲うと言う話は「京鹿子娘道成寺」という歌舞伎や踊りの演目になっている。
ここで以上のような絵解きの説法を聞いて、私たちは地元へと戻った。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[旅行記] カテゴリの最新記事
-
日帰り旅行その3醤油発祥の地を散策する 2023年12月13日 コメント(20)
-
日帰り旅行その2昼食と買い物 2023年12月12日 コメント(16)
-
日帰り旅行その1稲むらの火の館 2023年12月11日 コメント(18)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
カレンダー
医薬部外品薬用育毛…
 New!
木昌1777さん
New!
木昌1777さん
ひとり暮らしで何か… New! 岡田京さん
2024年6月22日18時41… New!
藻緯羅さん
New!
藻緯羅さん
源氏物語〔2帖帚木 … New!
Photo USMさん
New!
Photo USMさん
少し撮って帰宅でし… New!
こたつねこ01さん
New!
こたつねこ01さん
 New!
木昌1777さん
New!
木昌1777さんひとり暮らしで何か… New! 岡田京さん
2024年6月22日18時41…
 New!
藻緯羅さん
New!
藻緯羅さん源氏物語〔2帖帚木 …
 New!
Photo USMさん
New!
Photo USMさん少し撮って帰宅でし…
 New!
こたつねこ01さん
New!
こたつねこ01さん© Rakuten Group, Inc.