全408件 (408件中 1-50件目)
-
本日のバッハ 20120107
昨年の6月に本日のバッハをアップした時にはもっと頻繁に録音していくつもりでしたが、なかなかせずに、今日ふとしました。 左手の親指が痛くなってから、練習を始めるときにまず開放弦で右手だけのいくつかの練習をして、それから左手を入れた少しをして、そしてこのバッハの1番のプレリュードを弾いてみています。 特に曲を仕上げようという気もなく、毎日自分の音を丁寧に確認するためのエチュードのようにやっています。 失敗しているところ、おかしいとこ、いろいろあり、やっぱり恥ずかしいですが、恥ずかしくなくなる時がくるかどうかもわかりませんし、等身大の「本日のバッハ」ということで。 もっとちゃんと弾けるように、これからも続けていくものの中間記録。
2012.01.07
コメント(0)
-
浜辺の歌
小さな集まりでチェロを弾きますが、そのときマンドリンを弾く人がいらしてその人のピアノ伴奏をやってほしいと言われました。でももうピアノは頭と手が動かない感じでとても伴奏できる感じではないので、今日チェロ伴奏つくってみました。 どうやったかの覚書き。 歌の譜面どおりの一段の小節割で五線譜に小節線とコードを書く。各行の間に2つくらい五線をいれておいたほうがよい。そうすると修正案をその空いている下の行に書ける。いちいち消していると思った音を忘れてしまうのと、前の案に対して確かに修正案のほうがよいかどうか、すぐに比べられるのでよい。 まずコードをもとにチェロで弾いてみて、歌いながら弾いてみたりして、譜面に書く。1拍目のベースの動きをどうするかを最初に決めるほうがいいのかと思ったけどなんだかそれは結果的に私にとってはうまい手順ではなかった。 こんな感じかなと思ったら、ピアノで右手メロディ、左手チェロで弾いてみる。メロディと音がぶつかってたり、うまく混ざらないところを修正する。それから全体のダイナミズムから考えて音の動きを変える。大きなアルペジョにしたりする。コードを気にするとなんだかそのままの一番近いところに行きがちだけど広がりが欲しい時にはもっとコードの中でも大きくアルペジオを作ったほうがよい。ただし、チェロは一番下がドなのでそれが一番低音は広がった形になるのでそれを考えないといけない。ただチェロはピアノのように音が一列に並んでいるわけじゃないので、かなり音の飛んだ大きなアルペジオも意外と簡単に弾ける。 このピアノでした修正をもってチェロでもう一回弾いてみる。そうすると何だったかわからなくなっているところとかがあってそれを確認したり、コードに縛られずに経過音を使って自然なラインを作ったほうがいいと思うところを修正したりする。ピアノがこうと言ってもチェロがそれは弾きにくいぜと言う。そこの音をコードの中での別の音を使ってつなげる選択肢を検討する。この弾きにくければ音を変えることを考えると言うのはなんかすごーく新鮮な感じ。「弾けなければ弾けるようにする」という日ごろの縛りから解放される。ショパンとフランショームもこんなしてソナタを作っていったのかななんて思う(おおげさだなあ)。 このチェロが言ったことをそれでメロディとの関係もOKかどうか、またピアノで確認する。おかしなところを直して、またチェロはそれでいいか確認する。 こうやってチェロとピアノの間を何往復かした。いや、チェロとピアノの間は1歩くらいなんですけど、椅子を動かさなくちゃならないのでそのとき椅子でチェロを殴らないかが心配。 そんなして、チェロの伴奏を一応間違わずに弾ける(譜面が汚くて読みにくくて余計に間違う)ようにして、それを録音して、その録音を聴きながら、マンドリン風にチェロをトレモロ(?)で弾いてみてマンドリンの側から違和感がないだろうかとか、全体の感じとか確認してみる。 なんかいろいろ気になるところもありますが、多重録音でマンドリン部分の音も重ねて入れてみました。 もしよろしければお時間あれば聴いてみてください。こんなんになりました。 なんかチェロがうるさいように思うのは弾き方が下手だからかなあ。まあ、これから改善したいです。
2011.11.07
コメント(4)
-
クマについての覚書き
おとといの土曜日は去年もご一緒させていただいたピアノの発表会でピアノトリオを弾かせていただいた。 去年と同じ思い出のホール。 曲はピアノの先生とドビュッシーのピアノトリオ3-4楽章。 生徒さんとハイドンのジプシーと言われているピアノトリオの3楽章。もうひとりの生徒さんとルイエのソナタの2楽章。 去年に比べて新たに私にとってプレッシャーだったのは、曲数が多いことと、チェロから入るのが2曲あること。 だいたいバイオリンがいるアンサンブルだとバイオリンがリードするものがが多い。 ドビュッシーの3楽章は緩徐楽章でピアノが何小節か前奏を弾いてそれからチェロが美しいメロディを奏でる。そのあとバイオリンがそれを繰り返す。これが美しく弾けないと元も子もないわけで、もちろん美しくはできなくともとにかく失敗してはいけないという脅迫に取りつかれて、最後の合わせの練習の時もあまりうまくいかず、そのときの録音を聴くとビブラートが完全停止している。 もう一つチェロが先に出るのはルイエのソナタ。ほんとはアレグロの曲なのだけど、難しいからゆっくりということで、それでそのテーマのあり方というか、とらえ方、どう考えるかもオリジナルに考えないといけない感じだった。合わせのときもいろいろと話をした。最初にチェロがテーマを弾くのだけど、なんかしっくり行かなかった。8分休符がちょんちょん入って、その休みの扱いと言うか、その前の音をどのくらい伸ばすかとか、どこに重みを感じるかとか、なんていうかゆっくり弾いても、プツプツ切れている感じになるべきではないと思ったり、逆にこのプツプツ切れるのが孤独感を出している魅力なんじゃないかと思ったり。(とここまで書いて、8分休符のところにピアノの左手で合いの手が入っていることに気がついた。後でもこのテーマが出てくるときには必ず合いの手ある。もうちょっとそこを意識して会話させるべきだったのでは?そんなん基本じゃん。あー、バカ。と改めて楽譜を見に行ったりしてて思った。) 結局、それを何とか解決するプロセスが、個人的には今回私にとって印象深い経験となったように思う。ちょっとアンサンブルということからは外れてしまうかもしれないけど。 それははっきり言って最後の合わせが行われた後でやった。これを合わせる前にしなくてはいけないとは思っています。 いろいろな人がいるし、私のやり方はあまり音楽的ではないとも思う。でも私はとにかく納得がないとある程度落ち着いた気持ちで本番(仕上げる?)にのぞむことはできないとういうことが分かった。 フレーズに対してどう弾きたいかがはっきりしてなくても、もう時間がないのだからとにかく迷惑かけずに弾けるようにしとこうとすべきなのだろうが、よけいに遠回りになってしまうように思った。その臨機応変さがない自分に対しては諦めたほうがいいようだ。技術的に弾けない不安より、曲が自分の中に入り込んでない不安のほうがずっと大きく感じるみたいだ。 どうしていいかわからないときに、先生がいれば先生に教えてもらってそれを手がかりにできるけど、今回は先生がいないので、世間的には間違っていようがどうしようがとにかく自分が納得できるイメージと音とそれが高い確率で出せる手順とを見出さねばならない。 上の二つの部分については、エラーつぶしよりもそちらに思い切って時間を使った。2つともまず信頼できるイメージができてなかったので、自分が気に入る何かを見つける。たぶん音楽に秀でている人は音だけでできるのだろうけど、どうも私にはクマが必要なようだ。抱きしめるクマ。それがあると安心できる。 ドビュッシーは舟でした(まあ平凡です)。最初のピアノの序奏で海の地平線と自分が立っている場所、島、岩。右側の岩陰から1艘の舟が静かに出てくる。それがチェロ。そして、もう一度同じ旋律をフォルテで繰り返すところではフェリーニの「そして船は行く」みたいなおっきい船を出す(つくづく「そして船は行く」っていい題名だと思う)。この2艘の船を出すのが私の仕事。そうしたらもう自分もそれに乗ってどんどん入っていきます。バイオリンが出てきたらそれと一緒に脇で進ませる。そして、気持ちいいと思えるような音を目指して、体も寄りかかるように気持ちよくさせて。 本番は舟のことなどすっかり忘れていたかもしれません。でもある程度落ち着けるようになったと思われる段階まではこのクマを使う方法以外に今のところ私には手掛かりがない感じです。 ルイエはそんなにはっきりした視覚的イメージがあったわけではないけど、何べんも弾いて、アウフタクトの音はそれほど重要じゃないと思ったときになんとなく弾きやすくなった。アウフタクトってそういうもので当たり前のことなんだけどなかなか気がつけなかった。何度も弾いているところで、そのアウフタクトの音と一拍目の音とのくっつき具合というか離れ具合というかちょうどいいんじゃないかと思われる感覚が訪れるようになった気がする。 合わせの練習をしているときの録音を聴いていて、その全体の感じがトツトツとしていて、それは曲の魅力というより、この私たちがちょっと不器用でぎこちないけど何か真面目にやってる進み方がそうだったのかもしれないけど、なんか愛おしく感じた。それでとにかくそのトツトツとしたものを肯定することを鍵にして進めていけばいいのではないかと思った。それでなんとなく、大丈夫かなと思える感じに前日までに自分で練習しておいた。本番ではこの曲を最初に弾いたのだけど、最初のいくつかの音を弾いてそれらがホールの中で跳ね返ってきたときに、ちょっと今までとは違ったものだったので意外だったけど、瞬間的にそれが好きになった。「これでOK」と思った。それでそのまま弾き進めた。 この曲は不思議なことに本番を終えて家に帰ってきて録音も聴いて夜遅くに何とも言えない納得感が訪れた。ある16分音符のところはひき臼を回すように弾こうと思っていたのだけど、よく考えたら曲全体がひき臼のようなイメージだと思った。平凡な私はひき臼を回すように弾く。高みに行く予定もないけどでも毎日回し続け、高みへのあこがれも少しあって、でもダメで、でも答えがなくても、トツトツとそれを回し続ける。悲しいともうれしいともないかもしれないけど、でもやはりそれは美しく愛おしいとか思ったら、泣けてきた。もうその曲はその遅く回すテンポがぴったりで、アレグロなんて考えられない気分になった。 こういうことは一緒に弾いてくれる人にはあまり話す気がしません。それは話すとバカみたいな話に響くというのもあるし、それからその人たちはまた別のイメージを持っているかもしれないし、イメージそれ自体は重要ではなくて、どういう音を出すかということが重要だし、音はあくまで抽象的なものでとどまるべきだと思うし。 ただ、個人的なメモとして、書いとこうと思いました。
2011.08.01
コメント(2)
-
フェリーニ : 「8 1/2」, 「カサノバ」
音楽が興味深い映画ってありますか?ってある友達に聞かれて、とっさに浮かんで答えたのは、ヴェンダース、ゴダール、フェリーニ。 ただ自分の好きな映画監督を並べてるだけじゃん。 そうかもしれない。 でもこの3人の監督を上げて、「ちょっとさらに探させて」と言いました。 それで、昨日の夜フェリーニをYou Tubeで観ました。 You Tubeってほとんど上がってるんですね。もちろんこま切れだけど。 フェリーニとの最初の出会いは、たしか、「8 1/2(はっかにぶんのいち)」。これの読み方は私なんかは「はちとにぶんのいち」だけど、母なんかは上の読み方で習っている。この映画は「はっかにぶんのいち」という読み方と一応決まっているようだ。 マストロヤンニ、アヌーク・エーメ、クラウディア・カルディナーレ。 この種の映画に慣れていなかったころだから、「なんじゃこりゃ」って言う感じだった。白黒で、外国の温泉は日本のとは全然違うなあと思った。 サラギナ(海辺にいる大きなおばちゃん。その体で踊りを踊る。娼婦なのかな?異界の人って感じ)は印象的だった。この映画を見たのは大学のころだったけど、卒業してしばらくして、多重録音で「アルペジオ・サラギナ」という曲を作った。このサラギナがイメージだ。 そのあといろいろ、ほとんどフェリーニの映画は見たけど、やはりこの最初に見た「8 1/2」はよく覚えている。このあとも何回か劇場で観た気がする。3本立てとかみるとどうしても前に見たのが入るという都合だったかもしれないけれど。 今回は「音楽がいい映画」というテーマから考えると思い浮かぶのはこの最後のシーンだろうか。 ニーノ・ロータの音楽っていっつもワクワクする。 覚えていらっしゃる方がいるかどうか、サントリーの角瓶かなんかのCMで「時には砂漠の商人」とかいうコピー(ランボーと言っていたかどうか忘れたけど)のがありましたけど、それを見た時「これはフェリーニのパクリだ。ずるい。」と思いました。しかもフェリーニのほうがずっと美しいから、恥ずかしいと思いなさい、サントリー、という感じです。 それでそのあと思い浮かんだのは、「カサノバ」。「カサノバ」に音楽と映像という視点からすごくいいシーンがあったなあと。 ドナルドサザーランドのカサノバは女性遍歴豊富なというかその方面で旺盛な主人公。 フェリーニはサーカスが好きだし、大男、大女、こびとが好き。 大女がお風呂で歌う小さな歌。ニーノ・ロータいいし、この何か、悲しく優しくかわいらしいその空気をすごくよく覚えていた。泣けてくるほど美しい。時間のない人は、後ろのほうだけでも観てみてください。 そして、美しいと言えばこれも美しくまた音楽がすごくいい。 おお、すごいなあ、フェリーニ、ニーノ・ロータ。 ここまで自分の妄想を、人手とお金をかけて実現する体力というか、すごい。 と、ここまで来て、「でも、これ、こんな映画を観ることのない人が観たら、どう?」と思った。 やっぱり変かなあ。いいや、マックスで考えて、あとで整理しよう。
2011.05.21
コメント(0)
-

キーマカレー
けっこうおいしくできました。 オオゼキで「中村屋のキーマカレー」というお湯で温めるパックを売っていて、後ろの材料とか見て作ってみようと思いました。168円でしたが、ケチなので買いませんでした。* にんにく、ショウガ、人参、ごぼう、玉ねぎをみじん切りにする。みじん切りは結構しんどいですが、まあ炒めるので、適当でいいと思います。 * お鍋に油を少し多めに入れて、にんにくを炒める。 * そこに鶏のむね肉のひき肉としょうがのみじん切りをを入れて、まず鶏肉を炒める。 * 鶏がいたまったら、そこに人参とごぼうのみじん切りを入れる。 * そのあとに、玉ねぎのみじん切りを入れる。玉ねぎを最初に炒めると甘みがでるけれど、後で入れると甘くならないような気がします。しゃりっとした感じが残るので、私はそのほうが好きです。 * そうして、なんとなく全部炒まったら、そこにカレー粉(SBの赤い缶のを使いました)を入れて、小麦粉を少しだけ降りいれて、まぶしながら、さらに炒めます。 * 水気がなくなったら、そこにお水をうっすら入れて、かき混ぜて、お鍋の蓋をして、少し煮込む感じにします。そうするとちょっとだけとろみがつくみたいです。 * できあがり むね肉のぽそっとした感じがいいと思います。それから、中村屋の裏をみたときに思いましたが、やっぱりごぼうとショウガが魅力的な味を出しています。 おいしかった。また作りたいです。
2011.05.07
コメント(2)
-
カルメン
カルメンにはちょっと詳しかった。 カルメンと言えばビゼーのカルメンが有名だけど、それの原作メリメのカルメンを大学の2年生の原典購読というので読んだ。 2年生の原典購読はこれとカミユのシーシュポスの神話だったことは覚えている。真面目な学生だったので私はちゃんと予習していった。なので一応このメリメのカルメンを全部フランス語で読んだことになる。 でももうほとんど覚えていない。それでオペラのカルメンとこの原作のカルメンは少し話が違うのだけど、今はごっちゃになっていて、話もどうだったかわからなくなっている。 でもこの原作のカルメンはオペラよりも地味で、でももう少し深かった。 ファム・ファタル(宿命の女)。ファタルは運命だけど、よくないほうの運命を言ったと思う。私もファム・ファタルにあこがれてそうなりたいと思ったけど、どう見ても安全そうだった。今もそうだけどね。 それで、なぜかそのメリメを読んでいるときにカルメンが流行っていたのか、先日のゴダールの「カルメンという名の女」とそれからもうひとつ、スペインの監督カルロス・サウラの「カルメン」という映画が封切られた。 当時はこちらの「カルメン」に魅了された。フラメンコ。 アントニオ・ガデスは顔はちょっとえらが張りすぎているし、声もあんまり良くないけど、でも魅せられた。フラメンコの描く体の線がすごくかっこいい。 ここでの音楽はビゼーはカルメンの間奏曲が印象的だった(他のカルメンの曲は使われていなかったのではないだろうか)。そして、パコデルシアのギター。パコデルシアって風貌が武満徹とよく似ている。映画の中でもいい感じでアントニオガデスのそばにいた。 カルメンの役になった人は若くてきれいだけど、やっぱりクリスチーナオヨスは年取っているけど踊りが素晴らしい。 You Tubeにいっぱい上がっていました。いろいろあるけどこれが幕の内弁当みたいに少しずついいところあっていいかしら。アントニオガデスの踊りが少ないですね。ご興味あればYou Tubeで「Saura Carmen」で検索してみてください。 フラメンコのスタジオが窓が大きくて外の林の光が入ってきてなんとなく全体に水色に包まれていてよかった。そしてあすこにある椅子の形とかいいんですね。 何か作品を作っていく過程のようなものが物語で、そういうのがよかった。 フラメンコのステップ、群舞。私はそのころピアノを練習していて(もしかしたらリストのハンガリアン幻想曲だったかも)、私の指はフラメンコのステップを刻む足のようにリズムを刻みたいと思ったけど、このYou Tubeを観たあとチェロを練習していたらやっぱり、このステップのように刻みたいと思った。テンポとかリズムとかうまくイメージできないとき、踊りの足元を思う癖があるけど、もしかしたらこの「カルメン」を観た時から始まったのかもしれない。 今日、ほんとにすごく久しぶりに、この「カルメン」を観て思ったのは、実は、映画としてはゴダールのほうがいいなあということだった。 その、なんていうか、映画としての空気が。 でも、この「カルメン」はとても思い出深い大切な映画です。 「血の婚礼」とかはもっとフラメンコよりの映画ですね。
2011.05.06
コメント(2)
-
ジャン・リュック ゴダール
You Tubeで見つけたボロディンの四重奏を演奏していたQuartetto d´archi della Scala のビデオを見て、ゴダールの「カルメンという名の女」(この邦題は、原題の「Prenom Carmen」というシンプルさに比べて、あんまり良くないと思うけど)を思い出した。 これが私がもっているこの映画のイメージに一番近いかなあ。 弦楽四重奏をの映像は印象的だった。そのころ私はまさか自分が弦楽器をすることになるとも思っていなかったけど。そして、窓があって、海があって。カルメン自体はどうでもいい感じだった。 ゴダールはすごく好きな監督でもないけれど、映像と音遣いがいいなあと思う。はっきり言ってこのYou Tubeくらいの長さがもしかしたらちょうど良いのかもしれない。これを2時間やられるとかなりの体力が必要なのだ。 You Tubeにあげられているものは音質が悪くなっていて、MP3とかでよく聴こえるシャリシャリした音になってしまうのが残念。 ゴダールってよく覚えているけど、私が見た作品はと思って見るとそんなにないみたいだ。 監督作品一覧 いや、見ているのかもしれないけど、なんていうか、みんなおんなじなのであまりひとつひとつの作品の印象がない。 「勝手にしやがれ」は覚えている。これはでもその後のゴダール作品の前の普通の映画。ジャンポールベルモント。 映画館で映画を見ていて途中で帰りたいと思うことはなかったけど、「ウイークエンド」は私にそう思わせた唯一の映画だ。見ていて苦痛だった。席を立ちたかったのだけど真ん中のほうに座っていて出られなかった。アテネフランセ文化センターで観たことまで覚えている。 あとは「右側に気をつけろ」で飛行機の中があったな。くらいかしら。80年代の長編はほとんど見てるし、60-70年代は題名はよく覚えているけど内容の記憶がない。 「ワン・プラス・ワン」はローリングストーンズが出ていていいんだと友達に聞いたけど、みたかどうか、わからない。 「フレディ・ビュアシュへの手紙」という短編が「カルメン」と一緒に上映されたのだけどこれが結構印象的だった。黄色いラベルのレコードをかけるのだ。そうして街に坂がある。 今見たらYou Tubeにこの短編のすべてがアップされていた。 あの時もそう思ったけど、退屈なフィルムだ。そのとき面白いか退屈かということと、記憶に残るか残らないかは別なのだろう。 でも確かにこの短編に私の好きな何かがある。特に最初のほうが好き。 もしかしたら、この短編とカルメンが私の初ゴダール体験だったのかもしれない。 ゴダールの映画は光と音の感触を味わわせてくれて、そこに身を任せた時になんとも言えない恍惚感を味わわせてくれる。訳わからん言葉の挿入もときに心地良く。 100%傾倒できない何か傲慢なところがあるのだけど、透き通って硬い映像の光と音と言葉が、やはり魅力的だ。
2011.05.05
コメント(0)
-
ボロディン 弦楽四重奏 2番
2週間後にボロディンの弦楽四重奏の2番をアンサンブルで合わせる予定です。1回きりのアンサンブル。初めて弾きます。 うすうす、あのノットゥルノがある曲だとは知っていたけれど、どんな曲か知らなくて、昨日初めて譜面を見て、You Tubeを散歩していたら、「ああ、ちょっと待って。やだ。」こんなのに遭遇しました。 その音の揺らぎが素敵すぎる。 どうしよう。こんないい曲だったのに全然練習していない。間に合いません。 もうちょっと画面を広げてほしい気持ちもしますが、このファーストバイオリンの人の阿修羅のような顔が癖になりそうです。 皆1回も笑わないところがなんだかいい。 チェロの表面の色合いと木目(っていうのかしら)、光り方がすごくそそられます。 弓がきれい。 映像がなんかゴダールの「カルメンと言う名の女」を思い出させます。 それら視覚的なものから音が出ているかのような、そしてその浮遊感がなんとも言えません。 他の楽章もいいですが、この1楽章の揺らぎが好き。 ボロディンカルテット(四重奏団)のも聴いてみましたが、もっとごつくおおらか。確かにロシアだったらオリジナルはそんな感じかも。 これはごつくない。でもすごくいいと思う。 Quartetto d´archi della Scala というカルテット。イタリアみたい。
2011.05.03
コメント(2)
-
歌の記憶 - 幼い日の思い出
幼い日の思い出 竜のひげの茂みのなかは静かで 藍の実はひつそりとしてをりました 五つ六つ掌にのせて えんがはで遊びました ころころところがせば ころころところがつて とまりました また一つ ころころところがせば ころころところがつて とまりました 冬の日は障子にあたり 睡くなつてゆきました *********************************************** 小学校のときに習った歌。音楽の先生の手書きのガリ版印刷の譜面を見ながら歌った歌はたくさんありますが、これはその中でも心に残っている1つです。今もときどき心の中で歌います。 私はもう小学校のころからこういうのが好きだったんです。 すでに幼稚園を卒業間近に過去を振り返って下駄箱で涙した記憶があります。超後ろ向きだけど、仕方ないです。 今、調べたらこの詩は草野天平という、草野心平の兄弟の詩人の詩でした。 同じサイトに草野天平のこんな別の詩もありました。 妻の死 糸巻きの糸は切るところで切り 光った針が 並んで針刺に刺してある そばに 小さなにつぽんの鋏が そつとねせてあつた 妻の針箱をあけて見たとき 涙がながれた
2011.05.02
コメント(0)
-
B?chler エチュード Op.21, no.12
この曲はチェロのシュレーダー170のエチュード集の中に収められていて、レッスンでやってもう一応終っているのですが、気になる曲で今回もう一度弾いてみました。 Ferdinand B?chler <1817 ? 1891>(実際どう発音するのかも私はわからない)は、チェリストだったようです。作品21とあるので、少なくとも21曲は作っているのだと思いますが、シュレーダーのエチュード集に収められている曲以外に、楽譜があるのかどうかもわかりません。 私はこの曲が単なるエチュードに思えず、いい曲だと思っています。でもそのよさがまだまだ出せていませんね。いまいち(いまいくつ?)ですが、第一段階ということで失礼します。 映像はうちの前の桜の木とか、あれとか、これとかです。。。 とにかく音も映像ももっと進化したいと思っています。
2011.03.31
コメント(2)
-
あっという間にこういうことになってしまって
最初に揺れた時に、これはえらいことになるのか?と思って怖かった。 経験したことのないような恐怖だったはずだけど、でも初めてではないような気もした。でも思い返して、やっぱりその画像は映画の中か、夢の中しかない。 毎日、これでもかこれでもか、と最悪の事態が報道されて、しかも原発の話は終ったことというよりむしろ始まっていることのようで、これが映画ではなく本当に起こっていることだというのは、やはり不思議だ。 戦争と違って、さっきまで普通だった日常があっという間に違ったものになってしまう。地震の後のこの数日を考えると、この間の3/13の日曜日は電車も動いて晴れていてのどかだった。鷺宮の駅で友達に電話をして友達の子が生意気にも「こっちはだいじょうぶだよーー。」と割り込んできた。偶然行くことになってしまった新宿でもみんなもう地震は終ったこととしてのんびり買い物を楽しんでいた。あれが最後の普通の日だったのかもしれないと思ったりもする。 この状況の中でも、うちの中はいつもと変わらない。練習をしていても災害のことを考えたり、こんなことをしていてよいのだろうかと思ったりした。ここ数日、なんだかすごく疲れた。練習をしながら東北の津波のことを思う。いろいろ予定がキャンセルされていくのもあって、なんだかだらだらしてしまう。でも今夜、災害のことを忘れて楽器に集中して、それまでの心の日常が自分に戻ってきた気がした。 放射能も気になるけど、私は子供もいないし、なんていうか、じゃあどうしても生きなければいけないのかというと、どうかわからない。それでも密かにやっぱり気になることはあって、それを残された時間で形になるかどうかは別にして粛々とやれたらいいなあと思う。そのなかで他人にできることはして、もっと元気に生きられる人をサポートできればいいと思う。 ちょっと気持ちが整理できてきて、焦点がさだまってきたように感じる。 人には、突然襲ってきた非日常の中でも、それをまた日常と意識して、その中で普通に生きていくようなたくましさ備わっているように思う。
2011.03.15
コメント(4)
-
ポッパーとショパンとハイドン
発表会が終って、次の曲はポッパーのガボットという曲。 最初の印象は、運動会みたいで知性のカケラもない曲って感じ。でもなんだか弾いていて楽しい。ポッパーという作曲家の曲に取り組むのは初めてだけど前に他の曲をちょっと弾いた時もなんか弾いてて楽しかった。ポッパーはチェリストでもあったので、そういうことになるのかなと思った。急に高いところに飛んだりして、フラジオでとったりするところが音が出にくくてうまく弾けない。まだ2回くらいしか練習してない。 知性の部分はショパンのチェロソナタで補給する予定。今日You Tubeで聞いてみたりして、それから練習したら2時間も弾いてしまった。かっぱえびせん状態で、もうやめようと思うのだけど、もう一回だけ弾いてみたいとなる。でも練習したのは最初のページ(4分の1)だけ。 この曲は何年か前に弾いたことがあるのだけど、今日はとにかく自分の力不足を感じた。最初の出だしのフェルマータがすでにうまく伸びないし、弓が滑る感じで、きちんと音が出ない。リズムがちゃんと入らない。音程が外れる。 でもなんだか練習していて自分の中ではすごく盛り上がった。もっとこんな感じの音で弾きたいという欲求が強くあって、だから練習としては気持ちよかった。 またこの曲でいろいろな試みをして、いろいろな思いを入れていけると思うとうれしい。 あさってはアンサンブルでハイドンのひばり、モーツアルトのK421と不協和音(K465?)。なーんにもみていなかった。ひばりは初めてだと思っていたらなんとなく弾いた記憶がある。初見でちょっとやったのかしら。10分くらい練習したけど、思っていたより難しそうだった。 ハイドンをすっきり弾けるような人になりたい。 発表会の録音で、私の音はぽつぽつ切れてつながってなくて、消しゴムのかすみたいだと思った。弓を返す時に、返す前に重みが早く抜けて返しあとに圧力がかかるのが遅いということなのだと思うけど。固くならずに重みが抜けすぎずに弓を返せということか。。。 とにかく認識はしました。
2011.02.12
コメント(0)
-
おうちでアンサンブル&夕食
今日はチェロとバイオリンを弾く奈良のお友達とバイオリンとビオラを弾く四日市のお友達がうちに遊びに来てくれた。 2人とも東京に用事があって、今日の夜どこかで一緒に食事をしようといっていて、せっかくなのでうちに来てもらって、アンサンブルと夕食を共にした。 18:30にうちのそばの駅について、20:00までうちでアンサンブルして、20:00から21:30まで食事、ホテルに22:00に帰るというちょっとあわただしいスケジュールだったけど楽しかった。 アンサンブルはバイオリン2台とチェロ1台のString Trio。ベートーベン、モーツアルト、ハイドンといった有名どころではなく、あまり知られていない作曲家の小曲をIMSLPからとってきて、時間もないので、ざーっと合わせてみた。 * String Trio in G minor (Borodin, Alexander Porfirevich) http://imslp.org/wiki/String_Trio_in_G_minor_(Borodin,_Alexander_Porfirevich) * 6 Pieces for Two Violins and Cello (Wailly, Paul de) http://imslp.org/wiki/6_Pieces_for_Two_Violins_and_Cello_(Wailly,_Paul_de) * 2 Sonatas (Tartini, Giuseppe) http://imslp.org/wiki/2_Sonatas_(Tartini,_Giuseppe) ボロディンは前に1回別の人とやったことがあったけど、やっぱりいい曲だと思った。それぞれのパートに主題が出てきて、バリエーションのような曲で楽しめる。みんなもいいと言ってくれた。 Waillyはフランス人で、数少ないセザール・フランクのお弟子さんだそう。初めてだったので特に1曲目とかまだよくわからないけど、ちょっと興味深い。フランス風の和声。またやってみたい。 Tartiniはなんか名前は聞いたことがあるようなバロックの作曲家。安心して弾ける感じだけど、最後のロンドは私が数え間違えてるのかな?最後のところ合わないまま時間切れだった。 バイオリン2台とチェロ1台って、結構いろいろ曲があるみたいだ。上の3つもまたやってみたい。 私のうちでバイオリンの音が鳴ったのはこれが初めてだった。私の部屋で3人はきつきつだけど、まあなんとかできた。 夕食は、 * スペインのワイン * サーモンクレープ * にんじんサラダ * シメジのピーナツバター&味噌が入った玉子焼き * やげんの塩焼き * 昨日の残りのスペアリブのソースで和えたネジネジパスタ * 豚肉とひよこ豆のトマトソース * チョコレートアイスクリーム * コーヒー ほとんど最近開発したお料理ばかり。あらかじめ作っておけるものという条件で組み合わせてみた。 久しぶりのお客さんで、短い時間であっと言う間だったけど楽しかった。 また、来てね。
2011.02.10
コメント(2)
-
2011年の発表会 覚書
発表会、おととい終りました。 曲は2つ。グラズノフの吟遊詩人とピアッティのノットゥルノ。グラズノフは何と言っても去年の発表会が終ってすぐに始めた曲で、その前もお友達のサロンコンサートで弾いたので、思いもよらず長い付き合いになった。 グラズノフはレッスンで「いいですよ」と言われる割に終わりにはならず、次々といろいろ問題が出てきて、今の先生になって結局まだ発表会以外で曲が正式に終わりになったことはないという事実を更新することになった。 この曲からは本当に多くのことを学んだと思う。ビブラートも弾きはじめたころに比べたらずいぶんできるようになった気もする。短いのでほとんど全小節に渡って、細かく教えていただいた。こんなに細かくやってこんなに学んだ曲もないかもしれない。長くやっていても次々やらなきゃいけないと思うことがあるのでそんなに退屈しなかったし、ここで習得すべきことはこの曲に限ったことではない基本的なことなので、たくさんの曲をどんどんやるよりも今の私には必要だということも体感した。実際にはレッスン以外にいろんな曲に触れていたし。本番の3日前くらいに、最初の部分の弓順について、1年前にあんなに何べんも行ったり来たり変更して決めたはずなのに、またやはりここはダウンじゃないかと疑い出したのには自分でも笑えた。 ピアッティも長かったのだけど、言われるだけのことをやっていた時期があって、それからそういう取り組みではなく自分で心からそれが欲しいと思ってやらないと結局いつまでもだめなんだと思った。レッスンでインテンポに徹するのではなくてもっと形作って動かすということを教えていただいて、そのころから曲の構成とか動かし方とか積極的にやってみたいという気持ちが強くなった。1つの絵を描くのとおんなじだなあと思った。タッチの面白さ、色彩のバランス、全体の構図。それはちょうど例の有名なショパンコンクールのときで、それにも触発されて自分のノットゥルノを作ってみた。私の中では題して「メリーゴーランド・ノットゥルノ」。おおげさな何かがあったり、めまいがするような何かがあったり、狂気があったり、戯画的なそんなイメージだった。そんな夜想曲でいいのか?こんなのにはたしてピアノはいっしょに弾けるのか?とも思ったけど、ピアノと弾く予定もないし、そんなことはどうでもよいと思った。そして先生に「ちょっと気合いが入りすぎてませんか?」と言われて、ちょっと気を抜いてみたら、気楽に弾いても前に弾いていたよりもずっと楽に進む感じがして、ぎゅうぎゅうやっておくと力抜いたときになんていうか結構いい感じで力が抜けるんだと実感した。火がつくのが遅かったので、本番直前にもまだフレーズの流れとか、ああでもないこうでもないと行きつ戻りつした。 いままでの発表会となんとなく違った。本番に向けてなんていうか、ちゃんと弾かなきゃというより、やりたいことをできるだけ実現したいと思った。本番に実現できそうにないこともぎりぎりまで試みたいと思った。それが結果的には全体の仕上がりとしてマイナスになってもまあいいと思った。今度の発表会がゴールじゃないので、そこを最終地点としてまとめるのはおかしい気がした。たまたま本番の1週間くらいまえにレッスンを受けて、3日前に初めてピアノの方と合わせてまたレッスンという直前に変更が起きやすいスケジュールでもあったのだけど。緊張もしたけれど、失敗したらそれは今はそれまでの実力だったということで仕方ないという気持ちだった。ノットゥルノは最後のレッスンを受けた後で練習しながら、もしかしてこの曲は結構奥が深いと思って、すごーく愛おしくなって、まだ終わりにしたくないというなんかすごい恋愛感情に包まれたりもした。なんでもっと大切にしてあげなかったんだろうみたいな感じのものだった。もちろん弾きながら泣きました。 技術的に弾けないところをお百度参りのように何度もまじめに弾いて練習するようなことを今回はあまりせずに、そんな形づくりとかそんなことに直前まで時間を使っていた。そのおかげで、技術的に難しいオクターブの重音が続くフレーズとか練習が薄くて直前になって弾けなくなったりした。足固め的な練習もちゃんとしなくちゃという反省もあるし、今回のやり方がベストだとは思わないけど、なんていうか今までよりもう少し楽にとらえて、どんなことも起こってOKな感じに自分を作っていくことで今までより大きくなれるかもと思った。 ピアノの先生との合わせのときも、結構自分でどうありたいと思っているか説明して、どこをどう弾いてもらいたいかお願いしたりもして、前は自分のことだけで精いっぱいでピアノが入ったことで止まらないように弾かなきゃとか、自分が下手なのに要望なんて言ったら失礼だとか思ってたけど、気持ちに余裕ができたみたいでうれしかった。先生からも合わせるときにどんな感覚でやっていけばよいかというようなお話もいただいて、すごく楽しかった。 本番は、ああここをちゃんと弾いて聴いてもらいたかったというところの音程が変だったり、不測の事故(結局何が起こったのかよくわからない)があったりした。でも、弾くので精いっぱいです、というよりは意識がちゃんとあって、自分の中では練習しているときとほとんど変わらない感じで進められたので前よりはちょっと進歩したかなあと思う。 すごく感じたのは、よっぽどしっかり弾けてないとやっぱり緊張している中で実現するのは大変だということ。できなかったことはまだ身についていないことっていうことなんだと思う。でも将来はもっと余裕ができるようになって実現したい。 発表会のときは他の人の演奏も録音していて、自分の音を聴いて、他の上手な受験生とかの演奏を聴いて比べたりすると、音の立ち上がりが遅いとかいう最近注意されていることがどういうことかがすごくよくわかってよかった。確かに自分の演奏を聴いていると遅くてイラっとする。家で録音して自分の音だけ聴いているより、他人のと比べるとよくわかる。CDの演奏とか聴いても録音状態や響き方が違うとよくわからないけど、同じ場所で同じ時に続けて同じ録音機で録った音なので、そして自分以外のは生で聴いているので(自分のも聴いているけど弾いていると聴く側の音はわからない)、違いがだいたいつかめる。 本番にのぞむ感じって、スポーツ選手が試合にのぞむ感じと似ていて、演奏家の人の発言でも、その集中の仕方とか持っていき方とか似たことを言われる感じがするけど、私の場合それを参考にして成功したことは一度もない。 たとえば何だろう「勝つイメージしか持たない」とか。 それで今日ふと思ったのだけど、私はスポーツ苦手だし、そもそもスポーツ選手の言うことを参考にするのは間違っていると思った。どういうのかはまだわからないけど、スポーツ的ではない方法を、勝負的ではない方法を、自分で開拓すべきだと。まあそんな方法が可能なのかどうかわからないけど、とにかくああいうのをめざしてもダメと思った。 とりあえず、方法は他にもあるかもと思ってみることにする。
2011.02.07
コメント(0)
-
ノットゥルノ 妄想 覚書き
成功と失敗の違いが今一つ分かっていないかも。 音が出るときと出ないときの違いが。 だからいつも成功するようにならない。 成功率、まだ10%くらいかなあ。偶然できてるか、できてると思っちゃってるとき。 ************************************************ 出だしは少しの摩擦があることを確認して、楽にして体をのせて、ひし形を描きはじめる。 ビブラートをふりかけていく。 こんなのとか、こんなのとか、いろんなひし形を、倒れこみを交えながら、描いていく。 そして影が出て、硬くなって、それからまた最初と同じように始まる。 けど、今度はもっと前に進み、そして昇る。 頂点では気持ちよくたっぷりして戻ってきて、ちょっとしてからアニマート。 ここはまあちょっと狂っていて大げさになっていく。ねじれの位置を通り過ぎて、告白があって、一番強気の気持ちの太いがっちりがあって、それが曇って、昇って、緩んで、 そして今度は限りなく甘く最初のドルチェが始まる。長いライン。ビブラートをしみこませて、倒れこんで。 溜息混じりで昇り始め、そして頂点でゆったり気持ちよく声を出して、降りてくる。 重音でしっかり地面に足をつけたあとに、倒れこみをして跳躍して細やかに鮮やかに降りてきて、足元を整えて今度はステップで昇っていくその上がった先から、たゆたいながら降りてきて、下で渦巻いて、静まる。 それから、さようならを言って、まだ倒れこみの躍動を含んだ重音で幕をしめて、3つのピチカート、そして最後の響きで温かく終る。 ************************************************ そういう道のりを気持ちよく進めるといいのだけど。 うーん。間に合わん。 でも間に合わなくても、もうそんなことはどうでもいいので、やってみたいです。
2011.01.30
コメント(0)
-
パトリックの「リ」
ブリュッセルにいて、帰るときに、事務所のアンヌが夕食に招待してくれた。アンヌのうちにはその前にタッパウエアの会に1度行ったけど、そのあと2度目だったと思う。 タッパウエアの会でいただいた野菜スティックにつけたディップがおいしかったのであれはどうしたの?とあとで聞いたら、瓶に入って売ってる既製品でスーパーで売ってるよと言っていた。でも「○○」と言うブランドのでないとダメと若くてもベルギー人らしくがんこなこだわりをみせていた。 そのお別れのディナーのお料理はオーブンで焼いた鴨だったと思う。鴨大好き。ワインは1970年代位のブルゴーニュの赤で、くすんだルビー色をしていて、とてもおいしかった。いままでに飲んだワインの中で一番おいしかった。それでも全部飲めなくて残してしまってとても悲しかった。食べ物はどんなでも食べきれるのだけど、ワインはちょっとどんなにおいしくても飲めなくなってしまうのです。それ以来、私は安いワインでも赤はブルゴーニュのほうがおいしいと信じている。 アンヌの旦那さんはパトリックといって、フラマン系の会社に勤めていると言っていた。ベルギーにはフランス語をしゃべるワロン系とオランダ語の方言のフラマン語をしゃべるフラマン系といて、基本的にフラマン系の会社ではフラマン語がつかわれているらしく、パトリックはワロン系のフランス語の人だけどフラマン系の会社でフラマン語をしゃべって働いているとそういうことだった。 パトリックは音楽をよく知っていた。私が大げさなのはあんまりと言ったら、ワグナーのトリスタンとイゾルデの中の曲とか聞かせてくれて、ワグナーでもいいのもあることを教えてくれた。録音したカセットテープをもらった。今もあの大量のカセットテープ箱の中のどこかにあると思う。 パトリックが日本語でパトリックってどう言うの?と訊いた。日本語でもパトリックだよと思って「パトリック」と言ったら、その「リ」ってどういう発音?なんかちっちゃいもんが入っている、そのちっちゃいのがすごいいい、と言うのだ。もう一回言って、もう一回言ってと言われて、何度も「パトリック」と言った。私にとっては「り」は外国語にするとRiとLiがあって、日本語の「り」はLiと同じと思っているのだけど、そうじゃないらしい。パトリックはその「り」をすごく気に入ったようで、私にはそれがとても新鮮だった。どんなふうに聴こえるのだろうと。 チェロを弾いていて、弾きはじめの弓と弦が摩擦する瞬間は、言葉の初めの子音の音のように最近感じるときがある。この子音がうまく入ると何となく音が心地良く進むような感触がある。意味が理解できない外国語がそのいろんな形の子音をちりばめた音色でささやかれていて、それに聞き耳をたてるような。 この「パトリックのリ」を思う。
2011.01.20
コメント(0)
-
ノクターン ☆ ノットゥルノ
ショパンコンクールがなんでこんなに私の心をとらえるのか、よくわからない。 音楽の競争する面が超苦手な私は、競い合いに興味があるわけではないと思う。 たぶん、これがチェロだとこんなに楽しめないかもしれない。自分と比べたりして、あーあ、なんでこんな私がやってても意味ないじゃんとかそういう方向に思考がいって、ネガティブな気持ちに覆われてしまうと思う。 ピアノはその点、ここちよい距離感があってよい。 そして、でも音楽の展開の仕方とか、音質の選び方とか、体の使い方、気持ちの入れ方、みんなそれぞれその人のやり方でやっていて、それを見て聴くのがすごく刺激的だ。いろいろなあり方を見せてもらえる。 それで、自分で練習する時にもなんかポジティブな気持ちになれる。(君は全然関係ない人ですよ、というのはわかっていますけど) エチュードもショパンのエチュードみたいにどんだけでも高めるべきだと思って「もっとこう」とかトライする気持ちになる。 けっこう長い間やっている曲、ピアッティのノットゥルノ(ノクターン)はなかなか私にとって難しい。ただインテンポで弾くのではなく、形を出したいのだけれど、それがなんか見えてこない。 普通の夜想曲のイメージがうまくのらないのがたぶんいつまでも納得に至らない原因に思った。でもショパンでもいろいろなノクターンがあった。積極的なノクターンもあった。それでもノクターンだ。明るくてもノクターンだ。弾んでもノクターンであればいい。 ショパンコンクールの人たち、いろいろ見せてくれたけど、じゃあ私はこの曲に対して、どうアプローチするのか。このフレーズはどう主張するべきと思うか。いろいろなあり方があると思うけど。 どうするかを決めるには、今の私には、その曲に対する何か1つイメージがやっぱりないとどうしていいかわからなくなってしまう。本当は純粋に音楽だけがあるべきなのかもしれないけど。 そして、今日ひとつ来た。やっぱり、ねんねの友、くまちゃんがいると、モチベーションが上がってことがスムーズに進む気がする。 ショパンコンクールのサイトはこちらです。http://konkurs.chopin.pl/en ここのOnline Broadcastingで中継が流されます。ポーランドとの時差は7時間(日本が7時間進んでいる)です。
2010.10.08
コメント(2)
-

リズムの読み方 - フーガの技法
バッハのフーガの技法(Art of Fugue)は、結局、試作のようなものだろうか。作品として完成しているわけではなく、楽器の指定もない。(あんまり詳しいことは知らない) エマーソン・カルテットが弦楽四重奏でCDを出していて、よく聴いていた。同じテーマをもとにいろいろなフーガがあるのだけど、なんか聞いていて飽きない。 その譜面がインターネットで見つかって(IMSLPとは別のこんなサイト:http://icking-music-archive.org/ByComposer/J.S.Bach.php)、あさってのアンサンブルですることになった。コントラパンクトゥスという単位で14個のフーガがある。ほんとはもっとあるけど、このサイトにあった譜面はそれだけ。 昨日のレッスンまではやっぱり手がつけられなくて、レッスンの帰りにウォークマンで聞きながら総譜を見て、楽器を持たない練習を始めていたのだけど、譜面を読んでいくコツのようなものになんとなくその時に気がついた。 下はチェロの譜面。 これはコントラパンクトゥス1で4分の2、これを見ていくときに今まで1ト2トと数えてリズムをはめていたのだと思うけど、1小節の半分、つまり4分音符2つ分を1つの単位としてリズムの形をとらえて読み進んでいくと意外に止まらずに行けるということに気がついた。 そうすると8分音符4つ分(=4分音符2つ分)のパターンはそんなに多くなくて、タタタタ、ンタタタ、タタター、タータタ、ターター、ンーター、ターータ、タターー、タタータみたいな感じで、それをとんとん次々どの形か判断して進んでいくとそんなに読み違いがない。タイとかがあっても半小節単位で切って見てくとそんなに難しくなくなってくる。 このパターンを図形のように感じて半小節単位で読み進んでいくのだ。拍は半小節単位でトントンと打っている。 この感覚は結構役に立つように思った。これに慣れてくると頭はちょっと理解していなくても譜面から直接手が動いてうまくいくこともある。 前にもフーガの技法、ビオラ2台に四重奏でコントラパンクトゥスを3つくらいやったときはカウントがえらく大変だったけど、なんか今度はそのときより少し楽な気がするのだ。 当たり前といえば当たり前の読み方で、今までどう読んでいたの?と言われると、どう読んでいたんだろうと思ってしまう。たぶん1小節単位で読もうとしていて混乱してエラーが多かったのではないかと思う。 合わせた時にもこの間よりうまくいけば、この感覚結構正解なのだと思う。
2010.09.21
コメント(6)
-
今のしあわせがなくなっても
11月は本番(人の前で弾くこと)が4回ある。一人で舞台にのって弾くようなものではなく、少人数アンサンブルやソロでも小さな集まりだったりだけど、今までにひと月に4回なんてことは初めて。 さっき、数えて、あれ?3回かと思ったけど、やっぱり4回だった。(あぶない、あぶない) 会社に行っていたときは1年に1回の発表会だけだったのに、本当にありがたい話だ。 人前で弾くことはあまり好きじゃない(練習やレッスンのほうが好き)けど、でもそのために頑張るとやっぱりそのたびに何かが変わるようで、そういう意味でやはり機会があれば積極的に弾かせていただきたいと思う。 最近、じゃあなんで会社に行っていたときは機会がなかったのか?と思う。それがよくわからない。 本当に誘われることはほとんどなく、近所のオーケストラのエキストラだけだった。そしてそのオーケストラの練習に行ってもただ弾いて帰ってくるだけでチェロの人しかほとんど話をしないし、誰からも何も誘われなかった。あ、そうか、そこで唯一誘われたのが今も続いていて、広がっているか。 オーケストラって不思議だけど同じチェロの人がどんな音で弾いているのか聴こえない。エキストラだからいつも後ろのほうの席だからだろうか。私に余裕がなかったのかもしれないけど、前の人たちの左手のビブラートの揺れを見て「みんなビブラートできるんだ、すごい」とか思っているくらいだった。 会社に行っていたときは毎週レッスンに行っていて、それと仕事ととにかく回すのにパツパツだったから、他に積極的に何か探してグループに入ることもしなかった。 今はレッスンは行ったときに次を決めるので、いろいろなイベントを入れやすい。そういう環境になってわかったけど、レッスンも大事だけど、アンサンブルもやっぱり大事で、レッスンで習得したことがアンサンブルの場で出せると「ああ少し身に付いたかな」とか確認できる。 たぶんこうしていろいろな方とアンサンブルできて、最近は本番もあるようになったのは、仕事をやめて時間がありそうに見えるのもあるけれど、私の何かが変わったのかなあとも思う。 でもこの幸せはなくなりそうで怖くもある。こんなにうまくいくはずない、と筋金入りのネガティブ人間は思ってしまうのだ。 ただ、そう、関係あるかどうかわからないけど、今年の初めの発表会が終わったときに何か自分のなかで認識が変わった気がする。それが関係しているのかもしれない。そのとき、実力以上の気負いとかなくなって、私がチェロと何がしたいか、何を大事にしたいかについて、すっぽり納得したのだ。それからなんだか気持ちが落ち着いた。 この幸運はそのうちどこかに行ってしまうかもしれないけど、このすっぽり納得したことはどんな時でも大事に思いたい。 そして、今私の周りにいてつきあってくださっているお友達に心から感謝したい。 そう、会社に行っているときは10何年、ほとんど会社以外には新しい友達もできなかった。 4回のうち、2回は曲が決まっていなくて、1回は1度も練習していない。ん?? ほんとに? 2か月ないのに大丈夫か??? 10月にはしっかりがんばらなければ。1回1回大事にベストを尽くしたい。
2010.09.15
コメント(4)
-
ブラームスの五重奏Op.88とチャイコフスキの四重奏Op.11
今日は、ブラームスの五重奏Op.88とチャイコフスキの四重奏Op.11のアンサンブルだった。 2つとも初めての曲。 ブラームスは6重奏のシンプルなのを以前に1つやっただけ。チャイコフスキはこの間のフィレンツェの思い出で大変な思いをしたのが唯一の経験。そう、オーケストラでチャイコフスキの交響曲5番はやったけど、ブラームスはオーケストラもやったことなかった。 しかも、今日は上手な人ばかり。上手な人ばかりだと自分が弾けてなくても音楽になっていくという利点はあるけれど、やっぱり迷惑をかけたくないし、そのきれいに進んでいく音楽を自分が汚したくないという気持ちも強くなる。 ブラームスとチャイコフスキとどっちが難しかったかと言うと、今回の曲に限って言えば、ブラームスだった。まず私はブラームスの伴奏部分の語法を知らなかったというか。。シンコペーションで飾るようなところが多く、しかもメロディのファーストは4拍子の2拍目からフレーズが始まって1拍目で終わる(つまり1拍ずれている)のが多くて、下のほうでボーボーとやっているほうは今何拍目かわからなくなってしまうのだ。 事前に練習しているときもブラームスのほうが大変だったかもしれない。チャイコフスキは1楽章と4楽章は大変だけど2楽章と3楽章はカウントは難しくなくてちょっとほっとした。 今日、合わせてブラームスは他の人にも難しかったみたいだった。もう少し何度も弾けば、合わせる成功率も高まったかなあと思う。バイオリンはファーストもセカンドもとても上手で経験もある方たちだったので弾いていてぞくぞくするときもあった。なんとかして付いていきたいと思って頑張った。もちろん私には力不足なのだけど、でもすごくもったいないほどうれしいときだった。最後少し時間があって、「私、悩みがあるんですけど、」といって、ファーストから半パク遅れて強調してそれから拍の頭で合わせるところがうまくいかないことを言ったら、あまり強く弾かずにファーストのフレーズに遅れて付いて行くように弾くべきであること、拍の頭で合わせる前の音をしっかり弾いていると遅れることなどをみなさん親切に教えてくださった。このグループはみんなあまり「ここがおかしい」とか他人のことを言わないのだけど、それで私のチェロがどういう不快感を弾く人に与えているかもわからないのが不安なのだけど、そうか、こういうふうに自分から聞いてみると教えてもらえるんだと今日は得した気分になった。 チャイコフスキはまたまた上手なひとばかりで、ファーストはブラームスと同じ方、ビオラはきれいによく響いて細かい音もきちんとひかれているので、私がおぼつかないところもビオラをガイドに弾けたりもした。きれいな曲がきれいに響いて、私さえ失敗しなければ素晴らしい感じで進んでいく。最初のリズムは練習し始めた時に面食らったけど(CDなどで聞いていたイメージと全然違う楽譜だったので)、ああ、わかったかなとおもいきや、進んで展開部の盛り上がりのところで、私は一人でそれを刻むことになっていたとは今日初めて知った。いろんな音がしてくるし、しかも重音で、それへの注意も必要で、なんども止めてしまった。チェロが狂ってくるとさすがに弾き進められなくなってしまうのだ。ここが難所とは、ちょっと対策不足だった。だいたいこの変則的なリズムを弾くために、8分の9拍子を、121231212と数えていたのだけど、これはみんなおなじリズムのときはいいけど、上で別になってくるとちょっときつくなってくるのか。うーん、ここを一人でしっかり弾くための練習って一人ではどうしたらいいのだろうか。やっぱり弾きながら上の音が歌えないとダメなんだろうなあ。 そんな感じで、レッスンの曲も中断したりして、莫大な時間を費やして準備した2曲が終わった。いつも譜読みで終わりみたいになってしまうし、その譜読みが苦手な私は練習しているときにすごいストレスを感じる。こんなに大変な思いしても音楽を深めるところまではいけないんだと右上でいつもささやきが聞こえる。でも、終わってみて、もったいなくはあるけれど、やはり譜読みの練習としても有益だし、こうして合わせてくださる方がいる以上、やっぱり私は自分のベストを尽くしてのぞむべきだろうと思う。
2010.09.13
コメント(4)
-
ショパンのピアノトリオの秘密
ショパンのピアノトリオ1楽章、明日が本番前最後の合わせの練習。 この曲初めて合わせる前に緊張して一生懸命練習した後、ちょっと力抜いていた感じで、明日は最後の練習なので、もう一度気を入れなおして練習したら、まだまだぼろぼろだとういうことが分かった。 それはさておき、この曲、展開部に入ったところから、ソ-ド-ソ-レ-ソ-ミ♭という音形が続く。これが、ソ-レの部分が五度で左手の一つの指で2つの弦を押して移弦、しかもビブラート欲しいよね、レの後のソにのせるので、左手が苦しいレでクレッシェンド欲しい。そしてこの音形が延々と続いて、終わったところで再現部。初めこの音形がピアノの左手に出て、バイオリンとチェロはユニゾンでそれに応えるけど、早々とピアノは撤退して、霞のような伴奏にまわり、そのあとバイオリンとチェロで交互に延々と続ける。なんか聴いていて退屈だろうなと思っていた。 なんかどう過ごしていいのだろうかわからん時間が結構ある曲なのだが、この展開部の部分もその最たるもの。 昔、吉田秀和の番組である作曲家を取り上げて作品番号1からずーっと放送していくものがあって、ショパンもそれをやっていて、結構エアチェックしていた。その中にこの曲があって、もちろんカセットテープの録音だけど、見つかって聴いていた。新プラハトリオという今はあるのかないのかわからない演奏家のものだけど、なんかよい。それを昨日久しぶりに聴いてみて、この展開部の部分が見えるきっかけを、そしてこの曲の秘密を教えてもらった。まあまともにちょっと分析すれば秘密でもなんでもなく、今まで気がつかずに弾いているほうが恥ずかしいのだけど。 この曲のバイオリンとチェロの関係。たとえば展開部のソ-ド-ソ-レ-ソ-ミ♭のようなのをバイオリンとチェロで交互に繰り返すのだが、実は正確には交互ではなく、先にいくもの、後に続くものがあり、時にバイオリンが先に、時にチェロが先に行く。そして、追い抜きがあるのだ。追い抜きとは、ふと気がつくとバイオリンが先のはずが、チェロが先に行っている。これはちょうど2羽の鳥が空を飛んでいて旋回したタイミングで前後が入れ替わってしまうような、視覚的にいうとそういう動きになっていて、 美しい。。。。 このイメージが浮かんだときに、一気にこの1楽章、美しいと感じた。そう思って聴くと、バイオリンとチェロが一緒になる瞬間などちょうど鳥が並列に同速度で飛んで静止しているように見えるようなどっきりする時となる。 最初の部分のエスプレシーボもバイオリンから始まるけど、そのあとチェロが追い抜くのだ。追い抜いた時にはちょっと前に出ないとと思う。そのあと同じような旋律をピアノが始めるけど、そのときにはバイオリンもチェロも伴奏に回る。バイオリンとピアノが組んだり、ピアノとチェロが組んだりすることはあまりなくて、バイオリンとチェロが対になって飛んでいる感じだ。 大海原の上に2羽の鳥が大きく飛んでいる。時に海に沈みこみまた湧き上がってくる。 この曲はショパンの初期のものだと思うけどやっぱりショパンってすでにすごいなあと思った。 まあこの素敵なイメージを実現するほどの腕が私にないのが残念。 練習の最後は弾けない16分音符を弾けないと思いながら何度も敵のように繰り返す悪のパターンに陥って、今日は終わってしまった。自分でも不快なのにやめられない。 明日はいいアンサンブルができたら幸せだなあと思う。
2010.07.25
コメント(2)
-
バッハ 2番のプレリュード
バッハはやはり特別かも。 7/18にかけてバッハの無伴奏チェロ組曲の2番のプレリュードを毎朝一番に弾いた。 会社を辞めて2年。自分のチェロが少しは変わったか。6番を練習することから離れて以来、バッハを練習することはしていなかったし。少し楽に音が出るようになった気がしたし、何かここでひとつ弾きこんで確認してみたかった。 7/17にレッスンが決まってから、前にちょっと誘われていたけれどぼんやり断っていた7/18の会のことを友達が思い出させてくれて、8月にかけてのステップとしていいかなあなんて思って、参加することにした。 そもそもワンポイントレッスンという名前で聞いていたのだけど、まあ発表会であることがだんだんわかってきて、一時はもしかして舞台みたいな高いところで弾くのか?とあせったけど、そうではないことを確認したり、でも緊張した。 いつもは発表会といえば少なくとも2ヶ月くらい前には曲が決まって練習しているのに。2週間強で、ほぼ覚えている曲とはいえ、ボウイングもフィンガリングも固定していなかったので、それから始めた。 2番のプレリュードは好き。一番の山場のところで、弾きながら泣いたことは数えきれない。ひとりで曲を何度も弾いて構成を考えていく。音色を考えていく。そういう作業はとても気持ちよくて、やめられなくなる。やめようと思っても、もう一回弾き出してしまって、止まらなくなる。やめられない、とまらない、かっぱえびせん練習になる。それで他の曲の練習のスケジュールを圧迫するのだ。 そのあと、自分の弾いたのを録音してみてから、案の定、低迷期に入った。音がブツ切れ。そもそも、最近自分で弾いているとき聴いているのと録音の音がさほど差がなくなったと満足していたのに、このバッハに関しては耳になんか特殊フィルタでも付いていたのか、弾いているときは実際よりよっぽどいい感じで聴いている。 時間もないけれど、とにかく限られた時間で地道に少しでも改善しようと思った。それからは録音をよくして、確認するようにした。いつも、気に入らない変なところがあった。伸ばす音の質が悪かったり、低い音が出ていなかったり、ビブラートが最後までかかっていなかったり、移弦がうまくいっていなかったり、重音が十分に伸ばせていなかったり、ピアノになるところの音がショボすぎたり、ある音形のなかで変なところが強まっていたり。とにかくいろいろあった。それを本当は本番までに自分なりに治してのぞみたかったけど、体に身に着くまでにはなっていなかった。 暗譜が飛ぶことはほとんどないのだけど、音を違えずに通して弾くことができる確率はすごく低かった。 不安はすごく大きかったけど、私はこの曲が好きで、そしてあるイメージをちゃんと持っている。そのときに欲しい音もある。その響きを自分でも聴きたいからこれを弾く。まだまだだけど、こうありたいというものを背伸びせずに願いながら弾こうと自分に言い聞かせた。 部屋を変えたりして弾いてはいたけど、レッスンでも見てもらっていないし、誰の前でも1度も弾かずに本番はやはり不安だった。失敗はたぶんするだろうけど、失敗してもそんなに恐ろしいことにはならないとも言い聞かせた。 当日、リハーサルといって弾かせてもらえたけど、人のしゃべり声が大きくて集中できなかった。あるといった譜面台も、みんな自分の譜面台を持ってきているみたいで、なかった。覚えているからいいようなもののだけど、何かあったときに見れるという安心感は違う。ズボンが滑る感じがしてなんだかうまくチェロを安定して挟むことができなくて、椅子の高さなのかエンドピンなのか、その位置を落ち着かせるのにも時間がかかった。途中で弾きなおして音の感じを確認したりしていたら、通して弾く時間がなくなってしまってちょっと不安だった。 そのあと別の空き部屋で弾かせてもらった。そこは反響しすぎていたが、その分安心して弾けた。途中で「終わったら弾かせてほしい」とドアを開けられて、そんなことで集中力が途絶えたけど、そんなことを気にするなと言い聞かせて、心配なところを確認して、最後に1回通した。汗だくになったけどちょっと大丈夫という気持ちになれた。 本番では弾く前にいきなりしゃべることになって、適当にしゃべって、もしかしたらそれがかえってよかったかもしれない。途中で左手が浮いて音が違ったりもした。繰り返してたたみかけて上がるところでテンポが走ってしまって「急ぐな!」と引きとめたり、変におそくなっちゃったり、いろいろあった。一番の頂点で音をはずしてがっくりしたが、とにかくいつも泣くところだし、ここはベストを尽くしたいと思った。でも力まずに。そのあとのピアノで入るところは練習でよく起こっていた事故もなく、まあまあで通過した。最後の重音の終わりが弓先でかすれたのを感じた。 やっぱり緊張はしていたのだろうけれど、練習での成功率を考えると、練習と本番の差があまりなかったような気がして、それがなによりもうれしい出来事だった。 聴いていた知らない人から「よかった」とか言われてうれしかった。もしかして結構よかったのかなあと思ったけど、録音を聴いたら、物足りないところがいっぱいあった。弾いていてうまくいかないと意識したところはやっぱりそういう音になっていた。それと、やっぱりなんかつながっていない。もっとこうどんどんつながる感じにしたいのだけど。 ワンポイントの指摘いただいた点はビブラートの質。録音を聴いたら確かに伸ばす音で最後までビブラートという事前の自分への注意事項はほとんどすっとんでいてビブラートは止まっていた。やっぱり緊張するとまだビブラートはかからないのが現状かもしれない。ビブラートの質とは実音より下にかけるビブラートということ、確かに短調なので、上にかかると明るくなってしまうかもしれない。エレジーのときにもそういえば音程が明るくなっていると言われたけど、そこらへんの音感を養うべきかもしれない。 ちゃんと弾きこんだわけじゃないので、まだこれからも弾き続けなければと思っていたのだけど、終わったらなんだかちょっと気持ちが離れてしまったか、次に待っている曲が気になるのか、触らなくなってしまった。でもここで中断してしまうのはやはり中途半端。もう一息上げてみたい。 うまく弾けるとかそういうこととは別に、バッハを練習して毎日少しずつ自分の体に曲が入ってくる感覚が気持ちよくてすごく好きだ。
2010.07.21
コメント(2)
-
この1カ月の曲たち
昨日まで何だか大変だった。 記録として、6/21から昨日までにしたアンサンブルや練習の曲を書いてみようかなあ。 6/21のアンサンブル: モーツアルト5重奏 K516、K517, ベートーベン5重奏 Op.29 6/26のアンサンブル: チャイコフスキ 6重奏フィレンツェの思い出、モーツアルト6重奏 シンフォニィコンチェルタンテ 6/29と7/17のレッスン: エチュード#85(スピカート), #86, #87, 重音のエチュード、ピアッティ ノットゥルノ, グラズノフ 吟遊詩人の歌 7/4の2つのアンサンブル(この日のための事前練習はなし): モーツアルト ピアノコンチェルト#23、フルートコンチェルトのオーケストラチェロパート、モーツアルトのフルート、ピアノ、オーボエ、ビオラ、チェロの曲(K6??)、ヘンデルの歌の通奏低音、ペプシュの歌の通奏低音 7/8 -9のアンサンブル: ハイドン弦楽3重奏 Op.53-3(ピアノソナタ42番のアレンジ), ラヘナ チェロ4重奏セレナーデ, シューベルト弦楽5重奏 Op.163 1 & 3楽章の1st & 2nd cello, ライシガー 弦楽5重奏 Op.90 1,3-4楽章, ベートーベン 弦楽3重奏セレナーデOp.8より 7/12のアンサンブル: ハイドン弦楽4重奏 Op.33-2 冗談, Op.3-5 セレナーデ, ベートーベン弦楽4重奏 Op.18-4 7/13と7/19のピアノトリオ練習: ショパン ピアノトリオ Op.8 7/18のミニコンサート: バッハ 無伴奏チェロ組曲2番のプレリュード 1か月の間に私にしては記録的な量だったかもしれない。当日のための準備のスケジュールがいつも頭にあった。頭に入りきらないときはノートに書いておいた。このノートに最初に書いた日は気持ち悪くなって1時間ほど寝込んでしまった。 何といっても超プレッシャーだったのはバッハのプレリュード。他はお客様はいないけど、これは一応聴いてもらう会で、しかも出ることに決めたのは6/30で、私としては本番までの時間が一番短いものだった。 今こうやって曲目を書くと感慨深くて、その曲を通じてかかわった人たちの顔が浮かんでくる。初めて出会った人もいる。その方たちとの会話、曲への想いが、なんだか愛おしい。 一応、昨日の夜から今日くらいは「解放のとき」のはずなんだけど、疲れすぎて遊ぶ元気もない。そして次の曲を見ながらまた肩こりで気持ち悪くなっている。 でもこれは一人でやろうと思ってもできることではない。こんな機会を作ってくださったすべての方々に心から感謝。 それぞれについて、できれば記しておきたい。すべてとても貴重な時間だったのだから。
2010.07.20
コメント(0)
-
フィレンツェの思い出
あと10日後くらいに、チャイコフスキの弦楽6重奏「フィレンツェの思い出」のアンサンブルがある。 もちろんこの曲をするのは初めてで、6重奏で何をするかという選曲のときの候補にあったとき、CD聴いて、これはNGと思った曲だった。 この曲はよく昔聴いていたし、すごく素敵な曲だけど、自分が弾くという視点で聴いたら、とんでもなく何が起こってるのかわからん感じだった。 しかしながら、この曲をすることになってしまった。 最初は全楽章第2チェロのはずだったのだけど、3楽章と4楽章は第1チェロをすることになった。私にしてみれば第2チェロでも十分難しい。 難しいことは予想できるので、いつもだとアンサンブルの3日前くらいから練習するのだけど、今回はちょっと保守的に今くらいから見ている。 見ているのだけど、やはりまだ時間があると思うとのんびりムード。昨日1楽章をみて、今日2楽章を見た。まだ弾ける状態にはなっていないで、ちょっとやってみたという感じ。 1楽章はCDを聴くと速くて、また3拍子が変則風になったりするので、自分の譜面だけ見てカウントしていると入れないけど、ファーストバイオリンをガイドに考えると、ファーストバイオリンと第2チェロの関係は結構わかりやすい感じで、なんとなく見えてきた。まだ音程とかは無茶苦茶だけど。でも、そうかそうかとCD聴いたり、スコア見たりして練習していると気持ちが高揚してくる。 2楽章はほんとに美しい曲。私が聴いているCDはボロディンカルテットで第2チェロはロストロポービチが弾いている。この弾き方がすごく微妙な感じでよい。出てくるところと溶けちゃうところがちゃんとあるというか。シューベルトの弦楽5重奏も第2チェロがロストロポービチのを持っているけどすごくよい。このボロディンカルテットの演奏は他の演奏よりあまり歌いすぎていないというか、結構力強い感じ、がっちりした感じになっているかなあと思う。私はこれを聴きつけているのでこれがいいと感じる。 こういう2楽章のような曲の低音をよく響かせて弾けるようになれたらいいなあと思う。4番線を使うと音が出にくくて遅れぎみになるし、音程も取りにくい。控えめだけどちゃんと音楽を進めていくようなそういう風な響きが作れたらいいなあと思う。心地よく進めていくにはどうしたらいいのだろうと最近それに興味がある。私の場合、チェロに限らないが進んでいるものを止めてしまうほうが得意かも。 ちょっと2楽章の第1チェロのメロディも後で弾いてみたら、シンプルで美しくて泣けてきた。上がっていって、頂点のレの音を何度も弾いて、ああきれいきれいとやっていて、ラストエンペラーのときベルトルッチが坂本龍一に何度も血が出るシーンをやらせて「ベッレ、ベッレ」とつぶやいていたという話を思い出したりした。でもちょっと大げさすぎるかなあともう一度CDを聴いてみたら、もう少し上品に弾かれていた。そうだよなあ。 でもバスを弾いてからメロディを弾くとのれるような気がした。今練習してるピアッティもちょっとピアノのバスを弾いてみようかなあと思った。 3-4楽章は、ロシア風の曲。でもふとこの曲の題名「フィレンツェの思い出」だよねと思った。フィレンツェでロシアを思い出したのかなあと思ったけど、いやそうでなく思い出自体はフィレンツェのものという意味だよなあ。 今週中に3-4楽章も見ておきたい。
2010.06.15
コメント(2)
-
エリザベート王妃のコジューイン聴きました
遅ればせながら、エリザベートの1位の人、デニス・コジューインの演奏を聴いた。アレクサンドル・デデューインと名前の終わり方が似ている。 聴いたのはファイナルで、ハイドンを弾き始めた時に、やわらかい音を出す人だなあと思った。1楽章、2楽章と進んで、3楽章終ったところで目が覚めたので、たぶん2楽章の途中くらいまで聴いていたのだと思う。 Targetもぶつかる音がない。ほんとにピアノなのにひとつもぶつけるような固い音がなくて、あれピアノってこんなに空気が入った音だったっけ?と思う。今回も誰かの音について(たしか佐藤さん?)、空気が入った音と思ったけど、佐藤さんとは違って、やはりこの人も空気がたくさん入っている。だからどんなに強くなってもぶつからない。やわらかいのだけど弱いわけではなく、すごい懐深く、スケールが大きい。 その叩く音がしないために、オーケストラの音とすごくよく混ざる。そして驚いたのは、プロコフィエフのコンチェルトを聴いているときに、ピアノだけのソロになっているのに、オーケストラが鳴っているような音がするのだ。そう、なんかピアノから弦楽器みたいな音がしている。フルートが鳴りだしたのか、ピアノからフルートのような音がしているのかわからない。他の人もこんなだったかなあと何だかピアノってどんな音だったかわからなくなってしまった。 指の先に全然力が入っていないように見える。左手の小指が鍵盤の端に触れてそのまま下に落ちちゃってそれでも音が出てるらしい。 霧のような深みがあって、ロシアのロマンチシズムもあって、大きくて優しい。そう言えば、体も大きくて、顔もいつもスマイルって感じだ。 コンチェルトが終わったら、お客さんも立ち上がって拍手。やっぱりこの人すごかったんだと思った。 私なんてチェロなのにぶつかった音出してて恥ずかしいなあと思った。(比較する対象じゃないけど) その後、練習していて、このイメージが残っていて、ああもっとあんな風に、なんて思ってやっていた。馬鹿みたいだけど、まあいいか。別に害はないし。
2010.06.06
コメント(0)
-

とうもろこしのお焼き
友達のうちでタイ料理の本を見ながら最初は作ったけど、そのあとうちで何回か繰り返してずいぶん違ったものになっていると思います。 ビールによく合います。スイートチリソース(カルディコーヒーファームとかで瓶で売っているタイ製のもの)をつけていただくとよりおいしくなります。 * にんにくを刻みます。 * ごぼうをささがきにします。いつもは長ネギです。うちになかったので今回ごぼうを使いました。 * トウモロコシは今回は缶詰を使いましたが、生のものを包丁でおとして使ったほうが絶対においしいです。焼けた感じも香ばしい。今回は2本で380円もしたので缶詰でがまんしました。 * 上の3つをボウルに入れて、生卵を1つ落としかきまぜます。(全体が多ければ2つ) * ナンプラーを加えてかきまぜます。(調味料はこれだけ。塩も入れません) * 小麦粉をこれに加えます。感じとしてはてんぷらくらいのまぶし具合、とろみ具合です。 * 熱した鉄板(私は無水鍋のふたを使います)に油をひき、ティシューでふき取ります。 * 大きめのスプーンでボウルの中身を鉄板に落とします。 * 適当に裏返して、焼きます。少し焦げ目がついたら出来上がり。 * スイートチリソースをつけていただきます。 中身はトウモロコシ、ごぼうやネギでなくて、春菊とみょうが(とにんにく)で作ったこともあります。これもおいしかったです。 そういえば、今回は小麦粉の代わりに長い間使っていないてんぷら粉を使いました。どちらがいいかは模索中です。
2010.06.06
コメント(2)
-
捨てられない人の片づけプロジェクト
今日は夜8時過ぎから、すごく長い間"進行中"のステータスのままのクローゼットの片づけを少し進めた。 今も右腕がわなわなする。何だか体力がなくなっているせいか、段ボールとかの扱いが投げやりになる。 長い間、窓際に積んであった古い手紙類。たぶん私が生まれた時からもらった手紙で残っているもの全部が寄せ集めてあった。いらないものは捨てようと思ったが、この間ちょっと見たけど、捨てられなかったので、今日は靴箱とか何箱とかに入っているものを、紙袋に移してボリュームダウンして、段ボール一箱にすべてを入れて、クローゼットの一番奥に突っ込んだ。私が死にそうになったら、これをボンと捨てればいいのだ。最近はe-mailがほとんどで手紙は減った。 クローゼットの奥にあった古い段ボールの中には大学の卒業証書とか、高校のときの合唱の楽譜とか、なんだとかがあった。合唱の譜面は捨てたと思ったのにこんなところにあった。今日のところはとにかくこのまま見逃した。 それから長い間ずっと前の片づけ以来手前に出ていたおよそ60枚のLP(ロック系約30、クラッシック系約30)を、手紙の段ボールの上にのせた。これが結構、腕にこたえた。一度目は失敗して、二度目で体ごと使ってのせた。これからどんどん歳とっていくのにやっぱりこういうときに男の人がいないとつらいなあとふと思った。LPはプレーヤーがないので聴けない。誰かにあげようと思ったけど誰もいい返事をしなかった。中古レコードに持っていけばいいと言われたけど、じゃあクローゼットに入らなくなったら持っていけばいいかという結論になった。 それからこれも部屋の中にあったMD(ジュースの箱3箱)をさっきの合唱の楽譜が入っている段ボールの上にのせた。これももういらないかもしれないけど。 結局私の何年越しになるかわからない片付け作業は、ほとんど減らない。捨てられないので。 でも一応まとめてあれば順次整理できるかなあと、思うようにしている。 私はひとりっこだし、結婚もしてないし、こどももいないし、私が死んだあと、誰が私とこの物たちを片づけるのかなあとときどき思う。少しずつあんまり迷惑にならないようにしとかなきゃなあと思う。 チェコに行った時ドボルザークの博物館でドボルザークがアメリカに渡ったときの船のチケットが展示してあった。ドボルザークってちゃんと整理しておく人だったのだなあと思う。 私も飛行機のチケットとか、音楽会のチラシやパンフレットとか、ほとんどとっているけど、散乱している。お宝がゴミの中にあるような状態だ。お宝と言っても他人にはやはりゴミだけど。
2010.06.02
コメント(2)
-
エリザベート、シューベルト、ボロディン
昨日は朝やはり5時に起きてしまったけど、今起きたらアンサンブルがあるし最後まで持たないと思ったので、8時前くらいに起きて、雰囲気的にエリザベートの結果発表がそろそろじゃないかと思ってパソコンをつけた。 ベルギーではコンサートが12時くらいに終わるのは結構あたりまえだし、人を待たせることを何とも思わない人たちであることを考えると夜中の1時ごろ発表でもおかしくない。PCをつけたらLIVE画面に真夜中過ぎに発表するとあった。するとピアノぐるぐるの画面から映像が映って結果発表。 1位から発表すると思っていなかったし、2位があのまさかのブルガリア人だし、何位というあとに何か賞の名前を言っているので、本当の1番はまだこれからなのかというかすかな希望を持ったけど、やはり上位を白人が占めるそれが本当の順位だった。あまりにもあからさまでびっくり。でも1位3位の人の演奏は全然聴いていないのでなんとも言えない。 佐藤さんのどこが入賞できなかった理由なのかよくわからないけど、でもコンクールで1位をとるタイプではないという気もする。私が聴いた中での順位は、1位ファボリン、2位佐藤さん、3位キムテヒョン。うまいとか下手とかいうのではなく、アカデミックなコンクールだとキャラ的にこんな感じにことは進むのだろうという感じがした。 とにかく自分には世の中の動きや人の思考の動きを読む力はないということはよくわかった。 にわかファンだったけど、思わぬ感じでこのコンクール楽しませていただいた。まあ競争のことは無視。 でもふと聴衆が投票するコンクールってあったらどうなんだろうと思った。インターネットで見ることもできるし、たとえば会場の人は2票、インターネットの人は1票とかで、インターネットで投票とか。でもそのほうが結果発表は残酷ですね。 午後はシューベルトの弦楽5重奏 C-durのアンサンブル。私は今までに1番チェロを2回と2番チェロを1回弾いているけど、今までやった中でも1番まとまっていた感じのアンサンブルだった。自分がだんだん落ち着いた気持ちで臨めるようになっているというのもあるかもしれないけど。問題の2楽章は後半の細かいやつより、3連符で進めるほうに問題があった。それと初めと終わりのピチカートはほとんど練習してなくて音間違えたりいっぱいしてしまった。昨日はいいなあと思えた時もあったけど、コンプレックスを感じてうまく集中できず、力が入ってしまった時間があったのが残念。それはそれで置いておいて、この時間を大切に思って弾き進めるということができるようになりたい。 後半はバイオリン2人とチェロ1人のトリオの曲をやった。IMSLPで私が見つけて弾いてみたいと言ったボロディンのトリオ。 パート譜だけでスコアも音源もないので、つまらなかったらゴメンナサイという感じだったけど、民謡か何かからとったテーマの変奏曲のような曲で、3つのパートみんなによくテーマが出てきて、フーガのような趣もあり、美しい曲だった。短調のなかですっと明るくなるところがあってすてき。ターララ、ラーラーというそんなに難しくないはずのリズムが出てくるとカウントがわからなくなってしまったのが残念。バイオリンの人が言っていたけどボロディンの特徴ってこのリズムかも。「中央アジアの高原にて」もターララ、ララだ。このトリオ、私はこういう対位法的なというのか、パートが入り組むフーガ風の曲好きなのでまたぜひ弾いてみたい。 そのあとBendaという人のトリオ。時間がなくて十分弾けなかったけど、これもいい曲だった。
2010.05.31
コメント(0)
-
ピアノはみんな暗譜で弾いてますけど
すみれにローズマリーさんに教えてもらって、今まっただ中のエリザベート王妃国際コンクールのライブや録画を見た。NHKなんかでやっているクラッシックの放送はほとんど聞かない。母は美術系なので「あの人の禿げ方は」とかなんとか視覚的なことのコメントが多くて、私もそっちのほうに気がいって、ほとんど聴いてないことになるし、なんだか途中から退屈してくる。今回のエリザベート王妃はとにかく映像がすごくきれいで、音もきれい(ヘッドホンで聞いているからかも)。うちはまだアナログテレビなのでびっくり。私が裸眼で見ている世界よりもはっきりしている感じ。音もたとえば曲と曲の間の会場のざわめきやオーケストラの調弦の音が現実よりよく聴こえる(映像が遠景なのに、録音のマイクは舞台に近いところからとっているからかも)。私の視覚聴覚より細かいということだ。ベルギーは昔暮らしたことがあるところなので、たとえば演奏が終わって演奏者が入っていく部屋にある水とか、電気のスイッチとかに、ああこれこれと思う。コンクールというのは競争でなんか緊張感があってあんまり好感が持てないと思っていたけれど、このコンクールのファイナルに残っているような人たちはすでに技術的な問題などない感じでレベルが高く、学生でなくいわばすでに活動をしている演奏家が、一同に会しました、という感じで演奏が楽しめると思った。この後、順位がつけられるなんて信じられない感じ。You Tubeより長時間のゴージャスな演奏を満喫できて、すごく贅沢だと思った。そのゴージャスな感じの中でうつらうつらしながら聴くのがまたいい。久しぶりにピアノを聴いて、やっぱり上手な人のピアノを聴くと自分でも弾いてみたくなるというのは変わらないなあと思った。なんかそれほど難しくなさそうに見えるからかもしれない。ピアノは複数の音を組み合わせて浮きぼらせてなんぼで、その構成力がすごいと思った。今回改めて思ったのはみんな暗譜していること。なんでチェロの演奏会とかはみんな楽譜見て弾くのだろうと思う。ほんのちょっとしか音ないのに。譜めくりしなくてよかったりするから楽譜見るのだろうか。確かに譜面があるとなんとなく安心もする。譜面を置くと聴いている人とのあいだに小さなついたてができて、緊張が薄らぐということをこの間知った。でも今日チェロをやっている知り合いと話をしていて「楽譜をみてすぐ弾けるようになること、楽譜を読みながら弾くことは音楽をやるうえでかなり重要なことだと思う」と言われて、ああ弾く時に楽譜があってそれを読みながら弾くのが当たり前というのがあるのかなあと思った。合わせることが多いので個人作業より、楽譜読みながら弾いていくことの要求がたかいのかもしれない。私は不器用だし、楽譜を読みながら弾くとすごく不安で、楽譜にも指番号とか弓のアップダウンとかいっぱい書いて、とにかく自分の中に入れてしまいたくなる。暗譜が得意と言うより、覚えるほど弾かないと弾けない。暗譜していないエチュードなどでもなんていうか、何べんも弾いて、ここにこれがあってとか、道筋は覚えていないと弾けない。人がやっている方法とかなり違うような気もする。まあ、自分が気持ちよいと感じる方法が一番かなと思っていて、なんかどうしても初見の訓練とかに気持ちがいかない。なんか話がずれてきたかもしれない。
2010.05.28
コメント(0)
-
どうやって負けるか
硫黄島からの手紙が気になったのは「戦争が日常」とかそういうことではないような気がしてきた。気になるのは、「どうやって負けるか」ということが話題になっているからかもしれないと、今日ふと思った。「勝つことはない」ということがどうも私の遺伝子か何かには組み込まれていて、それが刺激されたような気がする。「負けるとわかっている中でどうやっていくか」というテーマは、そもそも勝つことや成功することに縁のない私にとって興味深いものなのだ。たとえば、楽器だってそうで、そんなに練習しなくても私よりずっと上手に弾くし進歩も早い人はいっぱいいる。言ってみれば負けている。チェロをやめてしまえば楽になる。「私は楽しみのためにやっている」といってまず負けることから逃れることもできる。でも今日思ったのは、戦い方にもいろいろあって、なんでもかんでも突撃するような練習でなくて、まず少しでも負けないために地下に坑道を巡らせて要塞をつくるようなそういう練習をして、持久戦に持ち込めたりするのかなあと考えた。この場合、敵ってなんだろう。「そんなことはできない」と思う私自身かもしれない。なんかロジックが狂ってきたか。
2010.05.22
コメント(2)
-
硫黄島からの手紙
クリントイーストウッドの硫黄島からの手紙をテレビで見た。正確に言うと、テレビとビデオで見た。後半からみだして、2-3日して最初から1時間を見た。そういう見かたをしたのと、画面が暗くてみんな同じようなものを着ていて顔の違いがよくわからないのと、せりふ(日本語)がよく聞き取れないのとで、なんだか理解できていない部分もある。クリントイーストウッドは日本語がわからないから、台詞をはっきり言ってなくても役者さんに注意しなかったのだと思う。そしたらほかの周りの日本人が注意すべきだと思うけど。理解できていない筋があるにもかかわらず、でも後半を見た翌日にこの映画のことを思った。前半を見てもやっぱり残った。「体に残る映画」久しぶりだった。だいたい映画館で見ると体に残りやすいのだけど、ビデオとかテレビだといい作品でもすぐに忘れちゃう。なぜだか映画館で見るとちゃんとどこか体に焼きつけられるものだ。なぜ、硫黄島からの手紙が残ったのかがまだわからない。気になっている。別に戦争の悲惨さを改めて認識したとかそういうことではないと思う。映画を見たというそういう感触が久しぶりに感じられているのだと思う。でも戦争のことを考えているのも確かかもしれない。戦争が日常であるそういう空気がちゃんと描けている戦争映画で、それが気になる原因なのかもしれない。何が異常(悲惨)かということは限定できない。今の日常もかなり異常なことがいっぱいある。食べても太らないダイエット薬とか。
2010.05.21
コメント(2)
-
ラズモフスキ3番 覚え書き
この間のアンサンブルでまたラズモフスキの3番を弾いた。3-4年前によくわけわからず弾いたのが初めてで、そのあと去年から今年にかけて、今回で3回弾く機会があった。メンバーはいつも違うけど。今回の感想をまだいつか分からないけど次回のときに忘れないように書いておきたい。1楽章は最初のほうでチェロが一人で駆け上がる2小節のためにいつも莫大な練習時間を費やす。ほかに弾けないところもあるのだけど、ここでしくじるとそのあとほかの人たちが入れなくなるし、すごく目立つ。ラズモフスキの3番をやることになるといつもこの部分で気が重い。この部分も含め、16分音符をクリアに出せるようになりたいと思う。2ページめの下のほうのアルペジオはあわてずにしっかり出したい。この曲はピアノ曲のような感じで弾けると結局一番魅力的なのではないかと思う。2楽章はチェロのピチカートで進む感じなので難しい。だいたい同じ音のピチカートを一人で練習する気にはなれないのだけど、ひとりで練習するときにピアノはどんな感じフォルテやスフォルツアンドはどんな感じと一応ちゃんと研究しておくべきだと思った。ピチカートをちゃんと聴こえるように出そうとピアノのときも大きめに出すと強弱がなくなってしまう。なんか工夫しなくちゃいけないのだと思う。アルバンベルクカルテットのを聴くとやはりかなり大きめで太鼓をたたいているような乾いているけど力強い音がする。私のは大きく出すと雑音が多くなる。研究が必要。今回アンサンブルして印象的に思ったのは、この曲は遅い曲というイメージがあったけど、遅い曲ではない。そしてスフォルツアンドが6/8の3つ目の8分音符についていてなんか弾きにくいんだけど、このスフォルツアンドで先に進めていくというイメージを持って弾くといいんじゃないかとおもった。単なる思いつきなので今度機会があったときに忘れずにやってみたい。3楽章はグラチオーゾ。とっても優雅なメヌエットで素敵。いろいろと入り組んでいるけど今回はその入り組みもわかった上で弾けてよかったかなあと思う。コーダのところはもう少し豊かに弾きたかった。4楽章は最初のフーガで私が入ったときに崩れたのは私がおかしかったのかなあ。1度ピッチリ合わせてみたい。そのあとの部分の入るタイミングが意外と難しい。これはまだただ数えて入っている域なので、もう少し構造を理解しておきたい。8分音符はスピカート気味にクリアに弾くのだと思う。自分がテーマのとき、もっとしっかり出したい。最初のフーガのテーマが終わった後の4分音符は遅くなりがち。2ページめのみんながそれぞれ順番に上がって降りるところで私は途中から走り気味?今回、いままでで一番速いテンポで最後の弾いたように思う。これくらいで弾けると楽しいかなと思う。CDのようなテンポで弾けることはまずないだろうし、あそこまで速くする必要もない気がする。
2010.05.18
コメント(0)
-
カツオ缶の食べ方例
春になってカツオのたたきをもう2度食べました。子供のころはしょうが醤油だった記憶があるのですが、今はからし醤油でいただくほうが多いです。さて、それはさておき賞味期限の切れた缶づめを片づける(=食べる)のが、いつしか私の役割となっていますが、流しの下の缶づめを見ていると「かつお油漬」というのがありました。「何をかつおの油で漬けてあるのだろう?」と思ってよくよく見ると、そういう意味ではなくて、カツオを油で漬けてあるということらしい。どんな感じで食べるんだろう?缶にはただ缶からプリンみたいにレタスの上に中身を空けた写真が"盛り付け例”としてあるだけだった。母に購入目的を聞いたら「そんなものは買った記憶がない」とのこと。どうやらツナ缶と間違えただけのようだ。開けて味見してみたら、ツナ缶と同じような感じはあったので玉ねぎみじん切りとマヨネーズ混ぜて、パンにつけて食べるというのも問題ないかとは思いました。でもせっかくなので、しょうがの刻んだのとお醤油を入れて、まぜまぜしてみました。これをご飯にのせて食べたら、おいしかったです。アボカドをわさび醤油でご飯でたべるとお刺身を食べているようにおいしいですが、それに似ています(味ではなく、お刺身もどきとして)。こちらは皮もむかなくていいし、生モノじゃないし、ちょっとおかずが欲しいときにいいなあと思いました。写真なし。
2010.04.25
コメント(2)
-
robert wyatt / shipbuilding
今朝は朝8時45分に待ち合わせなんていう用事があっていつもより少し早起きをした。朝ご飯を食べながらFMをつけたら、ラップのような曲をやっていて、最近ほとんどクラッシクばかり聞いていたから、おお、いいじゃんと思っていたら、曲が終わったら、そのあとにこれが流れて、ドッキリした。この曲が流れたらいつも私は100%何かに占められてしまう。shipbuildingピーターバラカンの番組だった。82年のベストテンのふりかえりという内容だったみたい。私は当時ほとんどをピーターバラカンから教わっていた。ロバートワイヤットのシップビルディング12インチシングルを持っていてB面はMemory of You でこちらはジャズの有名なナンバーのようだけど、ロバートワイヤットの歌で私は初めてこの曲を知った。そういえばRound Midnightも彼が初めだったかもしれない。そのあと、私はセロニアス・モンクのことを好きになったように思う。ロバートワイヤットのこののどにちょっと引っかけて出すような音が大好き。いつでもこれが聴こえてくると胸がしんとなる。(ここまで全部、You Tube 聴いてくださった方、おつきあいありがとうございます。)1982年からすでに30年くらいたっている。コンピュータなどの科学文明の進化の速度は1950年から1980年の30年と1980年から2010年までの30年では後半はウナギのぼりだと思う。でも音楽(ロックとかジャズとかだけど)は1950-1980年の30年に比べたら、1980-2010年はほとんど何も変わっていないように思うのだけど、私が知らないだけか?そういえばこの間オオゼキでレジを済ませた後、買ったものを袋詰めしていたら、トム・ウエイツの歌声が流れてきた。「そういうことがあるのか」と耳をすませたけど、そっくりさんの歌なのか、彼が歌っているのかはわからなかった。そんなオオゼキでいまどき。もしかして、今トム・ウエイツはすごくヒットしているとか?
2010.04.10
コメント(0)
-
北国の春、恐るべし
自分にその実力がないから負け惜しみを言っているということもあるけれど、プロの音楽家という職業にそんなに強い憧れを感じない。そのあとには引けないところで向き合うという環境にはあこがれるけど。私が一番最初に言った外国はバリだった。パリ(Paris)じゃなくてBALI。ちょうど坂本龍一がガムラン音楽とか言っているときで、いっしょに行った友達はそういうことには興味なかったけど、私はひそかにその方面に興味があった。バリの人は神様とともに生きている。朝、神様へのお花で作ったお供えを燃やすのだったか、道にその燃えカスが残っている。お昼もそんなに働かないみたい。よく昼寝していた。土地が豊かだからそんなにあくせく働かなくてもよい。観光の仕事をしている人以外は観光客にもあまり興味はない。仕事が終わったら、夜は夜通し神様のために奏で踊る。すごい体力だ。ガムランの鉄琴みたいなのをたたいている人は、あっちこっちよそ見しながら複雑な音の洪水の中に平気でいた。音楽をする職業というのではなく、普通に生活している人たちが夜集まって、音楽をして神様と交信するのだ。そんな音楽の在り方が本来のものだとそのとき思った。誰だか忘れたけどかなり有名なジャズミュージシャンは昼間は工場で働いていて、夜にクラブで演奏をしていて、かなり有名になっても工場で働いていたとか聞いて、かっこいいなあと思った。今度のボランティア演奏に参加して、すごく幸せだったのは、単純に、楽器を弾きたい人が集まって練習をして、ある場所に行って演奏をして、それを何の義理もなくただ聴きに来てくれる人がいて、そこで聴きに来てくれた人たちが私たちの演奏に合わせて一緒に歌ってくれたこと。私、本当にあるべきと思っていた形で音楽ができているじゃんということに気がついてすごくうれしかった。北国の春、恐るべし。「しらかばーーー」と大きな声で歌い出してくれた下町のおじさん、おばさんを前にして、北国の春というこの曲、ここまで生きてこられてこの歌を大声で歌っているおじさんおばさんに深い敬意を感じた。何かをちゃんと返さなくてはいけないと思った。何の指でどの音程をとるとか、ダルセーニョでどこに戻るんだ?とか、そういうところを乗り越えたところで弾かないと失礼だと直感的に思った。結果どういうことになっていたか?間違えが多くなったのは確かだけど、間違えているか間違えていないかはだれも気にしていないことは明らかだった。この人たちにほんとに受け止めてもらうにはどうしたらいいのか?寅さんの山田洋次監督が言っていたことなど思い出した。私レベルでは別に何ができるわけでもなく、やっぱり私の今の結論は今までと同じかなと思う。よく練習して自動でできるようにしておいて、その場ではできるだけ心を広げて音楽に集中すること。本番も終っているのに昨日の朝まで冬のソナタが頭の右上で鳴っていたけれど、実はあんなに練習した冬のソナタは弾かなかった。ちょっと残念だけど、必死にやっただけにまあよかったと思う。いつもの練習とは違って、チェロでどんな感じにそういう節回しを弾けるだろうかとやってみたり、チェロの別の可能性もあるなあと思ったりまあ楽しかった。それはさておき、ほんとに貴重な体験ができてうれしかった。
2010.03.29
コメント(6)
-
いまどき冬のソナタ
何だかえらく長い間お休みしてしまった。特に私の生活が変わったわけでもないのに、なんとなく書かなくなってしまった。もともと3日坊主の癖が強いので、この間は腰痛体操をし始めたのだけど気がついたらちょうど4日目にするのを忘れて、そのままになった。チェロもこんな感じであっさり弾かなくなってしまう可能性もあるなあと思っている。いろいろ書きたいことがあったのにやり過ごしてしまった。今、私の大部分を占めているのは、冬のソナタ。明後日の土曜日にあこがれのボランティア演奏(合奏)をすることになった。そこではクラシック以外の曲も弾いて、特に映画音楽はすごく楽しい。今までずいぶん緊張して弾いていたのだと気がつくほど、小学校の時の合奏のようなリラックスした楽しさがある。もちろん本番が近付くと緊張するけれど。そんな中で最後の練習のあと、私は弾かないと思っていた「冬のソナタ」を弾くことになってしまった。その日合わせるには合わせたけど初見だし、そのときには本番で自分は弾かないと思っていたので、今までの経験でも珍しいくらい準備なしの本番になってしまった。おとといくらいからYou Tubeからとった曲を何十回も気持ち悪くなるほど聞いている。チェロは合いの手みたいなのを入れるので実際には今聞いているものには入っていない節を入れる。シンコペーションが入って、慣れればいいのだけど、譜面から読むのはすごく大変。弾くのもチェロ2人ということで、ひとりならちょっとくらい違うこと弾いてもわからないところも正確に弾かないといけないんだろうなあとか、私の苦手な弓のアップダウンを合わせること、自分の指使いが書いていない譜面を見て弾くことなどプレッシャー。エチュードは4つともう一つ持っていて、そのうち3つは弓先を使うもので、右の肩コリがひどくて気持ち悪い。でも最近以前のような朝起きて何ともいえない不安な感じで毎日スタートすることがなくなってうれしい。たぶん不安や不具合に慣れただけかもしれないけれど、とにかく自分の大事と思うことを毎日少しでも進められればほかのことはまあいいと思えるようになった。それが今できれば、行く先がどうなっても別にかまわないと思う。
2010.03.25
コメント(4)
-
カザフスタンの吟遊詩人
吟遊詩人の練習を再びし始めているけれど、なかなか大変。前回と少し道具が変わった気もするので、そして意識も変わった気がするので、それを入れていきたいと思うのだけど。弓のアップダウンはあれだけ行ったり来たりしたので、さすがに今でも自分ではかなり納得している。フィンガリングは変えることにしたところもある。前のフィンガリングで結局弾けるようになれなかったところ、安全ではあるけれどシフトが変な所に入るので線が変になるように思うところを変えた。録音してみると、なんか頑張ってるみたいだけれど、ちぐはぐというか、何が言いたいのかわからない感じになっている。やろうと思っていることと、やっていることがマッチしていない。そんなで、昨日、今日はフランショームやモーツアルトどころではなくなっている。You Tubeにまた別の演奏が上がっているかなあと思って覗いたらずいぶん増えていた。そのなかで、最初に映った風船の印象とは裏腹にとてもいい感触の魅力的な演奏があった。録音の音も割れているのだけどたぶんこれはかなりいいと思う。こんな風に落ち着いて悠々と惹きこむ音が出せたらいいなあ。逆さ吊りになっているニコちゃん風船とのミスマッチが何とも言えない。これです。同じ人の別の演奏もすごくよい。音に品があってそしてその歌い方に惹きこまれる。Aldangor Rabbani - カザフスタンの16歳。
2010.02.09
コメント(2)
-
モーツアルトのK516とおもちゃのチャチャチャ
今日はやっぱりちょっと気になるので次回のアンサンブルの曲、モーツアルトの弦楽5重奏K516の1楽章を少し練習した。こんな曲アマデウスカルテット、すごく上手だなあ。そうしたら、いつもは何を弾いていてもほとんど何も言わない母が「おもちゃのチャチャチャ、チャチャチャおもちゃの、、、ってなるんだけど次が変になるようなの弾いているよね」と言った。母は年季の入った音痴なので、どこ?と言っていろいろ弾いてみても、全然似ていないところで「そこ、そこ」とか言っていまいちどこかは判然としない。でも同じようにチェロでおもちゃのチャチャチャを弾いてみたら、たしかに半音階が入っていて、似ていなくもない。この曲、結構難しい。弓が難しいのか、音がうまく出ない。もうちょっと練習して、もうちょっとましにしたい。進める力が出せるようになりたい。
2010.02.06
コメント(4)
-
フランショームのカプリス
2/13にも発表会がある予定だったので、今週来週はそのために時間をとっていたのが空いて久しぶりに余裕ができた。おとといは吉祥寺に行ってぶらぶらした。一度時間を気にせず、ぶらぶらしたいと思った。300円ショップを覗いて、買う予定だったものをドラッグストアや100円ショップで買って、閉店する伊勢丹のセールを覗いてきっと全店の不良在庫を集めてんだろうなあと思ったりしてみたが、買い物する資金があるわけでもないので、いまひとつなんだかつまんないなあと感じた。カルディに行って甘いコーヒーをもらって、いろんな食材を眺めていろんなことをイメージして、100円のトマト缶を買って、そうだ久しぶりにZARAに行ってみようと思って1Fで買わないけどちょっといいなあと思うような服を見て、2Fに上がったら冬物最終セールみたいなのをやっていてだんだん楽しくなってきた。すごーく安くなっていて、790円のTシャツを3つ(1つは母に)買った。それからダイヤ街で3つで525円のルームソックス(1つは母に、1つは外国の友達に)を買って帰った。ひさしぶりにやっぱりぶらぶら買い物して気持ちが開放された。発表会も終って、エチュードも再開した。それと音階などの一連のいつもやることの中にフイヤールの左手のシフト練習も入れることにした。毎日少しずつやって何度もぐるぐるやるようにしていればもう少し音程が安心してとれるようになるかと思っている。曲はなんと吟遊詩人が先生から提示された。なんかこの曲縁があるのかもしれない。それでまた弾いている。これはねむりんさんのコンサートで弾かせていただいたけど、しょぼしょぼだったので、今回グレードアップを図りたい。それに一人で一応仕上げてみたものをレッスンでみていただくのは初めてなのですごく楽しみ。きっとどういうところが自分には足りないかがよくわかるのではないかと思う。前はちょっと守りに入りすぎた感じがするのでもっと思い切って音を出すように、それと伸ばしている音の処理とか音のつながりとか、発表会で感じた課題に注意して練習するようにしている。ビブラートは前よりちょっと楽になった気がする。アンサンブルの練習をしてもいいのだけど、せっかくゆとりがあるので、前にエチュードで気になったFranchommeの12のカプリスというのをIMSLPでダウンロードしていたので、それを弾いてみた。この作曲家の音づかいがなぜか私の気を惹くのだ。こういうのがソロできれいに鳴らせるようになったらいいなあと思う。難しい曲ばかりなのだけど昨日は12曲全部弾いてみて頭が痛くなった。ぐったり疲れて、それでも少し弾けそうかもしれないいくつかの曲に印をつけた。そのあとバッハを弾いた。覚えているバッハだけだけど、前よりも少し楽に弾けるようになった気がして、そして結構積極的にいろいろやってみて、フランショームで気持ち悪くなった分がすっきり回復した。難しいフランショームに取り組むより、バッハを練習したほうが自分の土台になるのではないかとも思った。夜に廃版になっているフランショームのエチュードとカプリスの全集のCDをアマゾンで試聴して、やっぱり9番が素敵だなあと思って、もう一回やってみたくなった。今日はその9番を練習してみた。難しいけどまったく歯が立たないわけでもない。ただほんの数小節の試聴以外は、楽譜だけをたよりにどんな曲か作っていかなくてはならない。ただ弾くだけでなく音楽にするには自分だけでは無理かもしれない。でも自分でできるところまでやってみて先生に教えてもらうこともできるかもしれない。フランショームのあと、バッハの3番のプレリュードも少し練習した。昨日ちょっと弾いたときに分散和音のところがすごいいびつで情けなかったので。3番と4番のプレリュードはほかのに比べて好きじゃないかもしれない。バッハを少しずつでも弾いていくとしたらどんな風にしたらよいだろうか。3番4番5番のプレリュードはご無沙汰なのでそれにとりかかるか、それともちょっとなじんでいるものをもっと弾きこむほうがよいのか。
2010.02.05
コメント(2)
-
ちょっと立ち止まって
おととい発表会が終わった。夜だったので、とにかく長い1日だった。途中で「まだ終わってない。」と何度も思った。今回はエレジーが2週間前倒しになるということを9日前に告げられるという想定外のことがすでに起こっていたけれど、まだその場に行って何があるかはわからないと言い聞かせていた。いろいろあるだろうけど動揺しないようにしようと思った。すでにリハーサルがないことは教えていただいていたし、完璧はありえない、練習通りに弾けないのは当たり前と事前に自分に言い聞かせた。不思議なことに会の間はほんとうに予定通りに事が進められた。予定外だったのは会の後、打ち上げに行って遅くなり帰り道に地下で案内通りに駅に行こうとするとシャッターが閉まっていたり扉が閉まっていて進めなくなっていて、地上に出て見知らぬビルを見上げ、暗い中で時たま見つかる地図をにらみ、人に何度も尋ねながら、終電を気にして重い荷物を持って歩き回り、駅に着いた時には汗だくになっていたことくらいだった。ホールがちょっと寒いと思ったらちょうど暖房をあげていただいて、私が舞台に上がった時は舞台はライトの熱も加わり南国のように暖かだった。その温かさに寄りかかるように弾けばよいと思った。弾いている間はリラックスすることをこころがけて、あまり細かいことを気にしないようにした。暑さのせいか、不思議とほとんど緊張していないと感じた。でもやっぱりいつもより弓がかすれる感じもして、ここらへんだけで向こうのほうに音が行っていないような感じがした。向こうに行って返ってくる音があまり聞こえないような感じがした。たぶん自分ではそうは感じていなかったけどやはり緊張して右手がこわばっていたのだと思う。左手も細かい動きが硬直して音がくっついちゃったりゆがんだりしているのはわかった。音程もいい加減になっている感じがした。でもとにかくあんまり気にしないでとにかく音楽を進めることに集中するように努力した。大きな事故もなく終わった。一番最後のほうで左手が脱線して音をはずしてしまったのはもうすぐ終わりだなんて思ったからだ。最後の和音も一番上の音がかすれ気味で残念。もう終わりだなんて思わないようにしないと。終ったあと、終わったという喜びもあまりなく悔いもあまり感じなかった。なんか変な感じ。なんでだろうと昨日、今日と考えていた。今日は何べんも録音を聴いた。たぶん失敗もしなかったけど成功でもないことがそのぼんやりとした感じを残したのかもしれない。いろんなフレーズで頂点にいったときに張りのある音で十分に響かせたいと思ってその練習もしていたけれど、その感触を得るところまで1か所も弾けていなかったこと、録音を聴いていてもやっぱりもっと欲しいと思うことが、今の自分でももう少しはできたのではないかと思う点だろうか。あとは、ビブラートとか、音のつながりが悪く切れ切れになることとか、音の立ち上がりが遅くてあとから来ること、細かい音がはっきりしないこと、音程が悪いこと、私の合図が悪くてピアノと合っていないことなどがある。これらはまだ練習でもできていないので本番でできるようになるにはまだ意識改革や練習時間が必要だ。そんな個人的な諸問題もまとまってきたけれど、それとは別にほかの人の演奏を聴いていろいろ思うこともあって、そちらはまだ考えがまとまらない。これは今始まったことではないけどこの点についてはまだ考えがまとまらないのだ。発表会では受験生も弾くというより、そもそも受験生のためにこの時期に発表会があるのだけど、こういう若い人たちはテクニックもよくて音の処理もきれいで伸びもよくつながりもあって惹きこんでいく。これからもいっぱい勉強してもっともっと伸びていくのだろう。私にもこんな風に弾ける日が来るのだろうか(たぶん無理)、私は何をやっているのか、これからどう進めていったらいいのか、別に今気がついたわけではないのだけど、いつまでも今の生活が続けられるわけではないので、この貴重な時間を今後少しでも満足のいくように使うためにもちょっと立ち止まっている感じだ。いつもは発表会終ってもすぐにまたしゃんしゃんケチくさく練習し始めるのだけど、なんかそんなにがつがつしていない。ちょっと空気入れて、もう少しなんというかビジョンを整理する時間を持ったほうがよさそうだ。そんなに上手になれるとも考えられないけどこの程度と折り合いをつけて続けていくこともできない、それが私のかかえる問題なんだと思う。何を目指すのか、その目標を考えるだけで一生が終わりそうだけど、納得のいく目標でないとモチベーションにならないし、しかたない。そう、会が始まる前に1人だけ合わせをしてないひとのリハーサルを聴いたり、少しだけ会場でみんなが音を出しているときから始まって人の演奏を聴いているときもずっと「ああ、チェロってほんといい楽器だなあ。」と改めて思った。正直言ってそんなにいつもは心から感じていないことだった。
2010.02.02
コメント(4)
-
区切りはありがたいけど
いつも発表会の前とか、こうやって何かを書く気はしないのだけど、なぜか今回は書いている。やっぱりこういう区切りがあったからこそ一生懸命ビブラートをどうにかしようとしたり、少しでもいい感じに弾きたいと頑張るのだろうなあ、それで少しでも実力が上がればやはり本当にありがたいものだと思う。でも発表会の前って、ああ本番のこと気にせずにもっとじっくり本質的な練習したいなあなんて、生意気にも思う。でもきっと何もなかったら「いつかできるだろう」という感じでタラタラとやっているのだ。あさってには間に合わなくても、いろいろわかったこともあるし、少しできるようになったこともあるし、今後続けていったらよくなりそうな鍵ももらったし、これで本番失敗しても満足だ、なんて思った。でもそれは何か言い訳のような感じがした。やっぱり目的の場所で逃げちゃうのはすべきことではないのではないかとか。でもやっぱりこのシステム(決められた時間と場所で人前で演奏する)さえなければいいのになあと思う。本当に混乱する。オリンピック選手とか外科医とかほんとにすごいと思う。
2010.01.29
コメント(4)
-
音そのものしかない哀歌
昨日のビブラートのイメージはたぶん正しいと今日も思った。ただ自分の中に染み入れるまでにはまだ時間がかかりそう。当然2日あとの本番の緊張の中でできる確率は極めて少ないけれど、あるべきはこっちと判断したならやっぱりこれをやるしかない。本番にできるかできないかは私が決めることではない。エレジーの曲自体は私には今とても音だけのものに感じている。エレジー(哀歌)が個人のめそめそした哀歌ではないとは最初のころに思って、叙事的な何かをイメージしたけれど、それでこの曲に入っていくことは結局できなかった。たぶん私は自分にリアルなものじゃないとだめなのだ。歴史的な悲劇を体験したこともないので所詮聞いた話読んだ話では、そこまで集中できない。それで結局、この曲は特にストーリーはない。ただ音の質とか動きとかそういうもの自体をきちんと出したいという欲求があって、それがモチベーションになっている。何かを表現するとかでなく、ただそのものがあるだけという感じ。ビブラート、弓の速さ、音の長さそれをきっちり組み合わせていくと出来上がるようなそんな感じ。やっぱりフランス人だなあと、構成が論理的だと思った。やりたいことがまだうまくできないけれど、それを自分の部屋の中だけでも実現してみたい。ゴルターマンはエレジーに時間をとられて守りの感じになっているけど、やっぱりこちらもまだできないこと1つは実現できるように持っていきたいと思う。
2010.01.28
コメント(0)
-
ビブラートの新イメージ
今日はビブラートについて「あー、こういうことかも」という理解があった。あったのだけど、たぶんあったのだけど、確信に満ちた時間はそんなに長くなく、また今までのが混ざってきて、もう一度それのみを取り出すのが難しくなった。明日もう少しやってみようと思う。思ったのは、指で弦を伸ばしたり縮めたりしているとイメージすること。そこに集中すると「ああかな、こうかな」という迷いの動きがなくなって、力も抜けてくるようだ。ゆったりと大きくその動きをしたいけど、今はすぐに動きが縮れてくる。メトロノームで70にしてそこに4つ入れていくのが結構難しい。2つはできるけど、4つ入れようとすると加速して5つぐらいになる。でもこのゆったり4つがあるべき感触のように思う。力が入ってもよいのでまずゆっくりするのがよいのではないかと思う。このイメージはそもそもヴィブラートの目的の理屈にもあっているし、結構助けになるのではないかと思った。このイメージでなんとなくなんでビブラートが必要か、なんで美しいかを理解できる気がした。2-3日前にも実は「確信」は訪れていて、それは左手の指先に車がついているようななめらかさがあって、それを動かすのが腕だという、その2つの部品をイメージすると、うまくいくようン気がした。今日はそれをやろうとしていて、この新しい伸縮イメージが出てきた。明日もう少しやってみて、それからはやっぱりもう本番対策にしよう。続きは来週。でも自然にできるようになることもあるのかもしれないけど、かなり集中して自分で変えようとしないと得られないものもあるのだと今日は思った。
2010.01.27
コメント(0)
-
エレジーとの時間
エレジーの発表会は2月の予定だったのが、1月末に早まった。ゴルターマンとおんなじ日。こんなレベルの私でも一応逆算してイメージしていたのだけど、それが狂って一応また新しいスケジュールに合わせて計画をイメージしては見たものの、そうでなくても危うかったビブラートの納期を早めることはやはり無理そうで、いろいろごちゃごちゃになっている。今日くらいになって、このエレジーからは学ぶことがいっぱいあったのだと理解した。その一つをほぼ1日中やってみたけれど、なかなかうまくは行かない。一つのフレーズに、注意して弾きたいことが2つあって、その上ビブラートと音程の世話までして進めていくのはやっぱり大変。ビブラートと音程は少なくとも「自動」で行ってほしい。でも左手の指の感覚をまずビブラートに合わせて変えることを目標にしてみていたので、音程は後回しにしていた。今までの感覚で音程をとるのではないと仮定したので。あと4日。明日かあさってまではもう少し粘ってみて、それから安全対策でも大丈夫かなあと思っている。発表会で無難に弾くより、今やらなくてはいけないのはエレジーから得られるものをできるだけ吸い取ることのように思う。ああまた悪魔が来ているのかもしれないけど。
2010.01.26
コメント(4)
-

焼きナスのキノコのホワイトソースがけ
今日もお料理。これはお友達のうちで忘年会をしたときに作った品。お友達がポルチーニ茸の乾燥したのを持っていてそれを使いました。ポルチーニ茸は水で戻してオリーブオイルで炒めます。ちょっとお塩をしたかも。これとは別にホワイトソースを作ります。ホワイトソースの正しい作り方は定かではありませんが、私の言っているのはできればテフロンのお鍋にサラダオイルを少し入れてそこに小麦粉を入れてふつふつさせて木べらでなじませたものにミルクを加えたものです。炒めたポルチーニ茸をホワイトソースに加え、かき混ぜてふつふつさせて、ハーブ(このときはスイートパセリだったかな)を加えます。これでソースは終わり。なすは米なすを使いました。大きめに切って、厚めフライパンにオリーブオイルを少しひいて焼きます。油が多いとべちょべちょになるので、油はほんの少しでなすを焦がします。焼いたなすにホワイトソースをかけてできあがり。うちに帰ってきてから、オオゼキで米なすが見切り品で50円だったので、もう一回作ってみました。ポルチーニ茸はないので、エリンギを使いました。エリンギもとってもおいしかったです。エリンギってほかのものと炒めたりするとエリンギの味がわからなくなるときがありますが、このときはエリンギの香りがよくしてよかったです。ハーブはエルブ・ド・プロバンスを使いました。
2010.01.15
コメント(4)
-

納豆トースト
お昼は前の日のご飯が残っているとそれを食べますが、残っていないとき思いついたのが納豆トースト。納豆を普通にタレなど入れてかき混ぜて、それを食パンの上にのせて、オーブントースターでただ焼くだけ。納豆のオムレツのときもそうですが、ちょっと焦げた納豆っておいしいです。ネギとかのせたらどうなるのかしら。まだのせたことはありません。あったかくておいしいです。
2010.01.14
コメント(2)
-

ビブラート再び
緩やかな大きいビブラートがほしいと思ってからずいぶん時間がたつ。先生に言われたことをヒントに毎日ビブラートの練習をしているけれど、まだうまくできない。ああ、と思うほど感じよく行くときもあるけれど、それは稀で、曲の中ではうまくかかっていない。しかも人前では余計にかからない。この間のレッスンの録音でもほんのちょっとしかかかっていなかった。エレジーは大きなビブラートが欲しい。今日夜に今月中になんとかできるようにならないと2月の本番ではビブラートはかからないだろうと見積もった。安定してできるようになって、本番の緊張を差し引くとその計算になる。これでできるようになったらいいなあと思う。今は自然にかけているのではなくて頭でかけようとして左手が無理に動いてそれがぎくしゃく動いてやだなと思って、そのうち右手まで変な風になってきて、という感じになってわけわからない。たぶんビブラートのことを忘れたほうがよっぽど今は曲の出来上がりはいいのではないかと思う。でも今からあきらめるのではなくて、ぐちゃぐちゃになってもいいからとにかくやってみようと思う。そうしないとたぶんいつまでたってもできないと思う。ビブラートを欲しいという心からの欲求(歌心)がもともと希薄なのが一番の問題なのだと思うけど、前よりか欲しいと思うようになった。右手で強く出して左手のビブラートでそれを和らげるといい音になるように思う。それがやりたい。ビブラートは前は音が揺れるだけのように思っていたけれど、音質を変えることができるようだ。そしてもっと楽に弾けるようになりたい。左手の緊張をとってもっとバックリと弾けるようになりたい。今日はアンサンブルの練習を始めたらやっぱりこれもやらないと間に合わないとのめりこんでしまって、エレジーは少ししかできなかった。アンサンブルは、ベートーベンのセリオーソとモーツアルトのプロシャ王3番とハイドンの5度。難しいベートーベンとモーツアルトは両方とも初めて。お正月に下見をしていたけれどまだ弾けない。プロシャ王はのびのびとしてとても気持ちのよい曲だ。もっと時間が欲しい。下はお正月3が日のチェロ丸にした猿ぐつわ。記念に写真を撮った。重たい弱音器はあるけれど前にチェロを傷つけたことがあるので、今回はミュート+洗濯バサミでつまんだちり紙+マグネットクリップ。
2010.01.12
コメント(0)
-
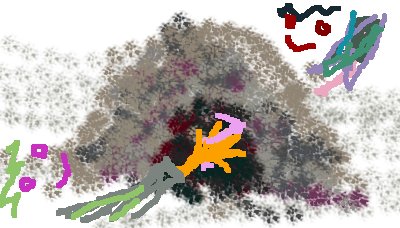
トンネルの貫通
お砂場で思い出すのは、お山を作ってトンネルを掘ったこと。お山は黒砂で作る。そうして向かい合って慎重にトンネルを掘っていく。掘り出した砂は結構遠くに掻きだして置かないと後で仕事がうまくいかなくなる。じっとりとした砂を掘り進んでいくと、やはりじっとりとしかし少し生温かい動くものに触る。それが友達の手だ。なんとなく今もその感触を覚えている。それは普通に握手するのとは違ったちょっと気持ち悪い感じがある。たとえばそれは友達の手ではなく大きなミミズだったらとか。トンネルの貫通の瞬間はいつも感動的だ。うまくいくときは山に入口が4つある四辻型トンネルもできたと思う。
2010.01.11
コメント(0)
-

砂場のプリン
振り返り専門家として思い出を。団地からこのマンションに引っ越してきて、小さな子が周りに増えた。団地は40年くらいたって住人も年配者が多くなって、遊び場にもほとんど子供の姿がなくなっていた。私の子供のころは階段もほとんど同世代の子供がいて、砂場でよく遊んだ。今日思い出したのは砂場でよくプリンを作ったこと。そこらへんに落ちている容器に黒砂をつめて、砂場の淵のコンクリの上にプリンを作る。そう、砂には黒砂と白砂がある。砂場の砂を掘っていくとしっとりとした黒い砂がある。それでないとプリンは作れない。その上に乾いたさらさらの白砂をかける。それがカラメルソース。そのプリンを見て、白黒が逆だともっとプリンらしくなるのにと思った。よくいっしょに遊んだカコちゃんは砂でなくて土を使って小さな玉を作るのが上手だった。やはりそれも仕上げは乾いた土をまぶしていたような気がする。その小さな玉はコロちゃんと言っていたと思う。
2010.01.10
コメント(4)
-

掃除
なんとなく絵日記。夜に掃除機をかけた。それと長い間廊下にあった大きなものを部屋にしまった。冬はじゅうたんにいっぱいゴミがつく。古いじゅうたんなのでシミなのかゴミなのかわかりにくい。
2010.01.09
コメント(2)
全408件 (408件中 1-50件目)
-
-
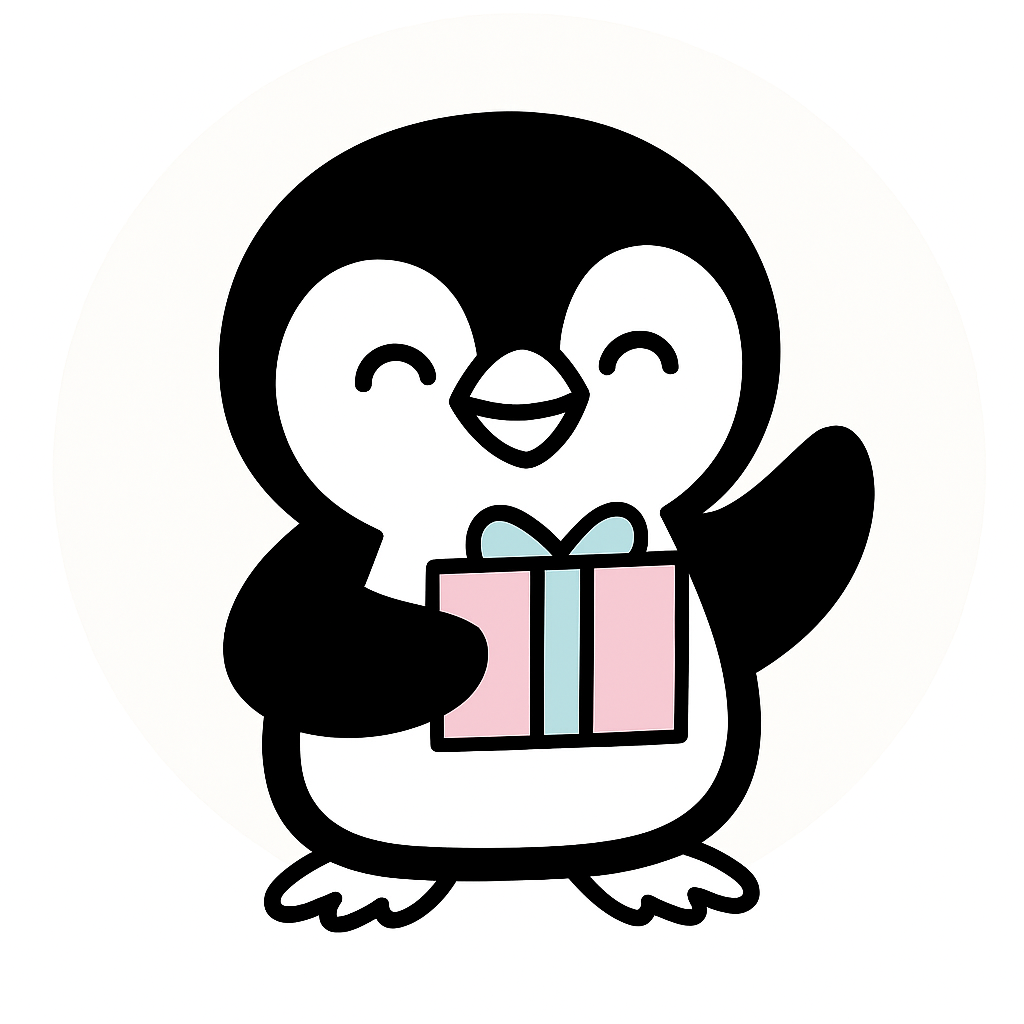
- やっぱりジャニーズ
- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…
- (2025-11-20 16:44:46)
-
-
-

- 吹奏楽
- 演奏会に行ってきた。
- (2025-11-19 16:33:12)
-
-
-

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- BTS - TinyTan Mini Speaker
- (2025-11-14 00:00:16)
-








