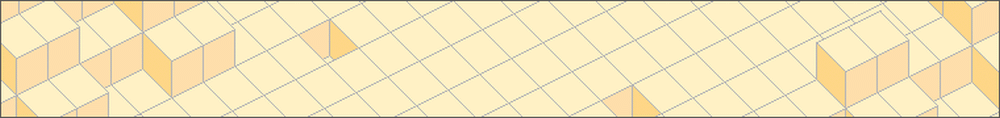『最後の早慶戦』が戸塚球場で行われたのは1943年(昭和18年)
10月16日のこと。当時は東京六大学野球こそが野球の「花形」であり、
常に注目の的だった。一方の職業野球といえば、あくまでマイナーな
スポーツであって、そのファンの数は、ほんの微々たるものだった。でも
職業野球は、その『最後の早慶戦』が行われた後も1944年(昭和19年)
9月まで続いていた。
野球連盟の名称を「日本野球連盟」から「日本野球報国会」に変え、
最後の試合の大会名を「総進軍優勝大会」(同年9月17日から3日間、
於・後楽園球場)と世情に迎合した ふり
をしながら、細々と生き永らえて
いたのだ。「総進軍」という名前こそ勇ましいものの、実情は寂しいもの
だった。
なにせ選手たちの多くは戦場にかりだされ、残っている選手は少なかった。
当時残っていたチームは巨人、阪神、阪急、産業、朝日、近畿日本の6
チーム。ところが、
(阪神を除き) どのチームも9人のメンバーすら揃って
いなかった。やむなく、「阪神・産業」「阪急・近畿日本」「巨人・朝日」と2つ
のチームが合体して3チームを作り2回戦総当たり12ゲームを行った。
この年の6月15日には米軍がサイパン島へ攻撃を開始。3週間後には
3万1629名の日本軍が、嵐のような米軍の攻撃の前に死んでいった。
(『昭和20年11月23日のプレイボール』鈴木明著、光人社刊より引用)
そんな大混乱を極めた時代だった。なのに東京のど真ん中(後楽園)で
職業野球は行われていた。いつ爆撃されるかわからない、そんな状況下
での強硬開催だった。
なぜ強硬開催されたのか。それは何人かの男たちの「職業野球を続けたい、
いや、続けなければならない」といった意地が支えたものだということを
前出の『プレイボール』でボクは知った。 市岡忠男
、 小西得郎
、 鈴木竜ニ
・・・。
※ただ、なぜ『職業野球』に彼らがそれほどまでにこだわったのか。前出の
書籍を読んでも、その理由をボクは知ることができなかった。少なくても金儲け
目当てではないだろうし、有り体の『男のロマン』などと呼んでも、ちょっと違う
気がするし。
いずれ、その点についてはもっと調べてみたいと思う。
この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。
→ (第4期)1925年(大正14年)、東京六大学リーグが成立し、早慶戦が復活した時以降
◇ 「ボクの日本野球史」
(2009.7.1) → こちら
へ。
「プロ野球、創設プラン」
(2009.7.5) → こちら
へ。
「職業野球選手の社会的地位」
(2009.7.8) → こちら
へ。
「米国遠征の夢と財布の中身」
(2009.7.9) → こちら
へ。
「三原脩、職業野球選手になった頃」
(2009.7.19) → こちら
へ。
-
【NPB2021】斎藤佑樹が引退~15年前の後ろ… 2021.12.05
-
【NPB2020春】コロナ対応で12日にオーナー… 2020.05.05
-
【2017NPB】鵜久森淳志が代打サヨナラ満塁… 2017.04.02
PR
Keyword Search
Calendar
【東京六大学2025秋】開幕カード。慶應、7点差を追いつき、同点引き分けに。
【東京六大学2025春】東京大学vs.横浜高校の歴史的一戦
【1890(明治23)年】インブリ―事件が生んだ『精神野球』
【1903年】早慶の初顔合わせの日。
【1901年】東京専門学校(後の早大)に野球部が誕生
【東京六大学1931春】八十川ボーク事件
【甲子園1927春】珍事?大阪代表校ゼロは92年ぶり。調べてたどりついた小川正太郎、そして八十川ボーク事件
【東都2024秋入替戦(1部2部)】第1戦は、東洋大がサヨナラ本塁打で先勝!
【甲子園2024夏】大社、31年ぶりのベスト8へ。昭和6年夏は映画『KANO』の題材となった中京商ー嘉義農林の決勝戦があった大会
Comments