PR
カレンダー
サイド自由欄
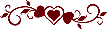

リュキア伝説・本館
☆完結しました☆
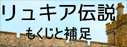

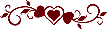

真魚子さまの絵

エメラルドeyesさんのブログ
『ねこマンサイ』
で紹介していただいた、
ふろぷしーもぷしーの過去日記
『迷い犬を保護してしまいました』2008.6.19~10.7

『いっしょに歩こう!』
2008.12~2009.1
キーワードサーチ
2024.10
2024.09
2024.07
 New!
千菊丸2151さん
New!
千菊丸2151さん小説「ゲノムと体験… マトリックスAさん
パンの日々 nako7447さん
道楽オヤジのお気楽… 車屋のオッサンさん
ゆっくりね ラブドルフィンさん
コメント新着
さあ、どこからでもかかってくるがいい。
身構えたミケの前に押し寄せてきた、黒い霧のような巨大な塊が、その奥に暗い青緑色の瞳をかすかに光らせ、ミケを押し包む。
静寂を破って、憎しみと怒りに満ちた声が、低く、深く、地鳴りのようにとどろく。
「おろかな三毛猫め、人間を信じ、裏切られた哀れな猫たちの末路を、今その身をもって見届けたであろうに、それでもまだ人を信じるとぬかすか。 人間の気まぐれに振り回され、あるいはそのゆがんだ快楽のために、犠牲となった猫たちの惨めな死に様を、見届けたばかりであろうに、まだ懲りぬのか。 人間のような気まぐれな生き物を信じるなど、どれほどばかげたことか、おまえこそもう一度しっかりと目を見開いて、あやつらの真実の姿を見るがいい」
その言葉と同時に、冷たい霧がミケを押し包んだ。
いや、霧ではない。
体の芯まで凍えるような、冷たい、雨だ。
濡れそぼった体を細かく震わせながら、また一歩、踏み出した足が、ぬかるみに取られて、まだ子猫のミケはよろめき、水たまりの中にべしゃりとしりもちをついた。
――― それは、ずっと長い間忘れていた、まぎれもなくミケ自身の、遠い遠い記憶だった。
自分が何者なのかもわからない。
どこから来たのかもわからない。
どこへ行けばいいのかもわからない。
ただ、空腹で、寒くて、耐えられず、やみくもに歩き出した、幼いミケだった。
ときどき、正体のわからない巨大な生き物が、轟音と派手な水しぶきをはねかけてミケの横を通り過ぎていった。
が、ミケに目を止める者は誰一人としてなかった。
寒くて、疲れて、もう鳴く力も失い、ぬかるみの中にべったり座り込んだまま、ただ激しく震えるばかりのミケの耳に、そのとき、かすかに、天のしらべのような明るい声が聞こえてきた。
「・・・あっ! お姉ちゃん、見て見て! 猫の赤ちゃんがいるよ!」
おぼつかない雨靴の足音とともに近づいてくるのは、今のミケにはすっかり耳になじんだ、あたたかい、優しい声だった。
――― 美緒お嬢さま!











