PR
X
カレンダー
コメント新着
コメントに書き込みはありません。
キーワードサーチ
▼キーワード検索
フリーページ
カテゴリ: 楽天グループの戦略
ご訪問ありがとうございます。
ただいま楽天グループでは楽天従業員からの楽天モバイル紹介キャンペーンを実施中です。 下記からログインして楽天モバイルにご契約いただくと、最大14,000ポイントプレゼントいたします!よろしくお願い申し上げます。
https://r10.to/hYYGNa
【楽天従業員から紹介された方限定】楽天モバイル紹介キャンペーン!回線お申し込みごとにポイントプレゼント!上記URLからどなたでもお申し込みいただけます。

Rakuten AI Optimism 2025:未来を切り拓く15のポイント
楽天グループが主催する年次カンファレンス「Rakuten AI Optimism 2025」では、人工知能を中心テーマに据えた3日間のイベントが開催されました。ビジネス領域から社会的影響まで、AIの幅広い可能性について議論された同イベントから、特に注目すべき15のポイントをご紹介します。
ポイント1. 人をつなぐエージェント型AI(三木谷浩史氏基調講演)
楽天グループ会長兼社長の三木谷浩史氏は、基調講演において「AIは人間のつながりをより良くするものでなければならない」と述べました。同氏が発表したのは、単なる生成型AIから一歩進んだエージェント型AIへの転換です。このエージェント型AIは、ユーザーのニーズを理解し、意思決定を行い、実際に行動を起こすことができるシステムとして設計されています。楽天エコシステム全体—ショッピング、旅行、金融など—にわたって統合的に機能し、楽天モバイルの強力なプラットフォームによって支えられているのが特徴です。人間を置き換えるのではなく、人間同士のつながりを強化するツールとしてAIを位置づける同氏の視点は、テクノロジーの人間中心的な活用方法を示唆しています。
ポイント2. 楽天AIの本格始動(Ting Cai氏の戦略発表)
楽天グループのチーフデータ・AI責任者であるTing Cai氏は、楽天AIの全面的な展開について詳細を明らかにしました。楽天Linkでの開始からベータ版ウェブアプリ、そして楽天市場での年内展開まで、段階的なロードマップが示されました。注目すべきは「チャットからタスクへ、研究から行動へ、人間のブラウジングからエージェントのブラウジングへ」という変革の方向性です。楽天のエンジニアチームが開発したMixture of Experts LLMと小規模言語モデル(SLM)は、日本のAI開発を加速させることを目的としています。すでにセマンティック検索の導入により楽天市場のGMS(流通総額)が10%以上向上しており、社内では15,000人以上の楽天従業員が楽天AIを活用して生産性を向上させています。蔡氏の「私たちは行う全てのことにAIを注入しています」という言葉が、楽天の包括的なAI戦略を物語っています。
ポイント3. 日本全国へのAI普及戦略(成田修造氏との対談)
起業家の成田修造氏と楽天の小林悠輔氏による対談では、中小企業に楽天の強力なデータとツールを提供することで、日本全国にAIを普及させる戦略について議論されました。特に焦点となったのは、楽天がどのようにして事業者のAI導入障壁を下げることができるかという課題です。また、楽天が推進してきた「英語公用語化」が、日本におけるエンジニア人材不足の解決にどのように貢献しているかについても言及されました。これらの取り組みは、楽天グループ全体で日々行われている最先端の研究開発業務の原動力となっているのです。
ポイント4. 全事業者向けAIプラットフォーム(Wolt Japan・Hotel Urashima事例)
「楽天AI for Business」プラットフォームは、技術的な専門知識を持たない企業でもAIツールの恩恵を受けられるようにすることを目指しています。Wolt JapanのNatalia Khizanishvili氏と浦島観光ホテル株式会社の松下哲也氏が、それぞれの企業での楽天AIツールの実践的な活用事例を紹介しました。食品配達プラットフォームのWoltでは、配達員、顧客、レストランのサポートにAIを活用しています。一方、風光明媚なホテル浦島では、日本の観光業労働力不足への対応として楽天のツールを活用し、メールの作成、レビューへの返信、さらにはビュッフェ運営まで、幅広い業務でAIの力を借りています。
ポイント5. マーケティングにおけるAIの本質的価値(Google Japan 奥山真司氏)
Google Japan社長の奥山真司氏は、GeminiなどのアクセシブルなAIツールに関するGoogleの歴史と哲学、そしてAIが同社のマーケティング戦略にどのように組み込まれているかについて共有しました。奥山氏が強調したのは、専門家だけでなく誰もが使えるAIを創造することの重要性です。また、AIをブラックボックスとしてではなく、マーケターの実践的な協力者として位置づけることの必要性についても述べました。この視点は、AIツールの普及において技術的なハードルを下げ、より多くの人々がAIの恩恵を受けられるようにするという考え方を示しています。
ポイント6. フィンテック業界におけるAIの10年史(業界リーダーパネル)
ポイント7. 楽天銀行の超個人化ビジョン(東林知隆社長)
楽天銀行の東林知隆社長兼CEOは、完全デジタル・24時間体制のモデルで1,700万口座という驚異的な成長を遂げた同行の軌跡を紹介しました。楽天ポイント、楽天ペイ、楽天証券、そして楽天エコシステム全体との統合が、この成功の基盤となっています。将来的に東林氏が描くビジョンでは、AIが個人の銀行員として機能し、ローンや予算管理をガイドし、リアルタイム詐欺検出やリスクベース認証などのスマートセキュリティ機能によってサポートされます。「私たちのビジョンは、各顧客が専用の銀行員を持っているかのような個人化された金融サービスを提供することです」という同氏の言葉が、未来の金融サービスの姿を明確に示しています。
ポイント8. 顧客体験とエンターテインメントの最前線(Decagon・Metaphysic対談)
DecagonのJesse Zhang氏とMetaphysicのTom Graham氏が楽天のTing Cai氏と共に、顧客体験のための会話型AIエージェントと、将来のエンターテインメントにおけるAIの役割について議論しました。最近大手VFX会社と合併したMetaphysicのGraham氏は、実在の俳優の年齢を上げたり下げたりするAI画像をオーバーレイするAI生成ヒューマンパフォーマンスについて説明しました。パネリストたちは、AI音声がすでに人間を欺くことができる一方で、AI視覚技術もそう遠くない将来に同様のレベルに達するだろうと強調しました。「今後数年間で、私たちは完全にAI生成されたエンターテインメントを消費することになるでしょう」という予測が示されました。
ポイント9. AI主権と次世代コンピュテーション(小柴満信氏の警鐘)
Cdots共同創設者で経験豊富な経営幹部である小柴満信氏は、国家主権におけるAIの役割について語り、権力が国民国家からテックプラットフォームへと移行しており、世界が「テクノポーラー」秩序に向かっていると論じました。同氏は、世界的な債務、紛争、その他のマクロ的な変動を、コンピュートとAI主権をめぐる戦略的競争と関連付けて分析しました。量子コンピューティングの研究の重要性の高まり、データベース経済における通信事業者の重要性を強調する一方で、外国のクラウドインフラ、AIモデル、データ権に対する過度の依存について日本に警鐘を鳴らしました。この視点は、技術的自立性が国家安全保障の重要な要素となっていることを示しています。
ポイント10. AIによるがん研究の加速(土井俊彦博士の医療AI論)
著名な研究者である土井俊彦博士が楽天の大越拓氏らと共に、AIががん研究の加速にどのように貢献できるかを探求しました。日本が労働力不足、高齢化、原材料費の上昇に直面する中、AIは国の高い医療サービス水準を維持するための不可欠なツールとなる可能性があります。医師の専門知識を向上させ、患者とスタッフ間のコミュニケーションギャップを埋めることが期待されています。しかし、これを実現するためには業界が変化を再定義することに対してオープンであることが必要です。土井博士は、AIにおける「なぜ」を忘れないことの重要性を強調し、「患者に利益をもたらすツールであれば、私たちは前進してそれを採用すべきです」と述べました。
ポイント11. Z世代のAIネイティブ思考(QuizKnock伊沢拓司氏)
QuizKnockの伊沢拓司氏は、AIブームに対するZ世代の視点を代表してステージに立ちました。ソーシャルメディアのアルゴリズムが若者にニッチな興味を深く掘り下げることを促している状況において、伊沢氏は日本の教育が学生自身の意見を表明するよう促すことで、より積極的に学生を関与させる必要があると強調しました。伊沢氏は全国の学校を回り、AIリテラシーに関する対面ワークショップを自ら実施しています。現在のAIはユーザーの言うことにすべて同意するように見えるため、AIが実際に何ができるかを適切に理解することが、次世代の将来にとって最重要になるという指摘は極めて重要です。
ポイント12. デザインの民主化とクリエイティビティ(佐藤可士和氏・永井一史氏対談)
楽天を含む数々の象徴的な日本ブランドを手がけたデザイナーの佐藤可士和氏と、博報堂デザイン社長兼CEOの永井一史氏が、経営から地域活性化、ブランド統合まで、デザインの役割の進化について探求しました。両氏は、AIによってデザインが民主化された一方で、デザイン経営が政策やビジネス戦略においてますます大きな役割を果たしていることを強調しました。また、偽物との戦いが迫っていることを指摘し、独創性の重要性を訴えました。「何ができるか、どうやってできるかはAIが担える。なぜやるかは人間が持つべきです」という言葉が、人間とAIの協働における本質的な分担を示しています。
ポイント13. AI時代の教育における「ヒューマンエッジ」(阿部守一知事・小宮山利恵子教授・岡田武史氏)
長野県知事の阿部守一氏、小宮山利恵子教授、そして伝説的なサッカー監督の岡田武史氏が楽天の小林正忠氏と共に、これまで以上に不確実な未来の時代において、子どもたちが既存のロールモデルに常に頼ることができない状況での教育アプローチについてブレインストーミングを行いました。試行錯誤、批判的思考スキル、地域資源に基づくプログラムがすべて議題に上りました。小宮山教授は、AIの手の届かない体現されたスキルを学ぶことの重要性を強調し、岡田氏は日本の出生率低下により、各子どもが受ける注目の増加を人格形成に向けるべきだと指摘しました。
ポイント14. 日本のデジタル主権と未来(村井純教授・黒住昭仁氏対談)
「日本のインターネットの父」として広く知られる村井純教授が、楽天グループCIO兼CTOの黒住昭仁氏と日本のデジタル未来について前向きな議論を展開しました。対話は国家インフラとデジタル主権をAI準備状況と結びつけ、日本が基準を輸入するのではなく、AIの倫理的・実践的境界線の定義において主導的役割を果たすべきであることを強調しました。この視点は、技術分野において日本が受動的な採用者ではなく、能動的な標準設定者となることの重要性を示しています。
ポイント15. AI時代の日本の未来(成田悠輔氏の現実論)
経済学者の成田悠輔氏は、通常のPowerPointプレゼンテーションはもちろん、演壇の椅子も使わず、硬いステージの床に座ってAIに関する厳しい現実論を展開しました。日本の人口動態と経済停滞の中で、成田氏はユニバース25実験を引用しました。これは豊富な生活資源を提供された実験用ネズミの社会の崩壊を追跡した実験です。
「ユニバース25実験」は、1972年にアメリカの行動学者ジョン・B・カルフーン(John B. Calhoun)が行った有名なマウス実験のことを指します。別名「マウスのユートピア実験」とも呼ばれます。
実験の概要
• 対象:8匹のマウス(4オス・4メス)を投入。
• 目的:資源が無限に近い環境で、マウスの社会がどのように発展するかを観察すること。
結果の経過 第1段階(適応期) マウスは環境に慣れ、繁殖を開始。
2. 第2段階(成長期)
個体数は爆発的に増加し、理想的に見える社会が構築される。
過密状態により、社会構造が崩壊し始める。縄張り争いや攻撃性が増し、弱い個体は隅に追いやられる。
4. 第4段階(崩壊期)
「行動の退行」が見られる。母マウスが子を育てなくなり、オスは攻撃的または引きこもりに。特に目立ったのが「ビューティフル・ワンズ」と呼ばれる群れで、繁殖も闘争もせず、ただ身繕いと食事だけを繰り返す無気力なマウスが現れた。
5. 最終的に
繁殖は停止し、若い個体も社会性を失い、やがてコロニー全体が崩壊して絶滅した。
社会への示唆
この実験はしばしば以下のような警鐘として語られます。
• 過密社会や資源の偏在がもたらす人間社会の崩壊モデル
• 「意味」や「役割」を失った存在の無気力化(ビューティフル・ワンズ現象)
• 物質的豊かさが必ずしも精神的豊かさや社会の持続につながらないこと
ただし、実験はあくまで「マウス」であり、人間社会に直接的に当てはめるのは単純化しすぎるとの批判もあります。
AIはエネルギーや半導体と同等の中核的資源となりつつありますが、クラウドとモデル層はわずか数社によって支配され続けています。成田氏は、自国産AIモデルへの投資と、悲観主義から実践的楽観主義への心構えの変化において、いくつかの希望の光を強調しました。
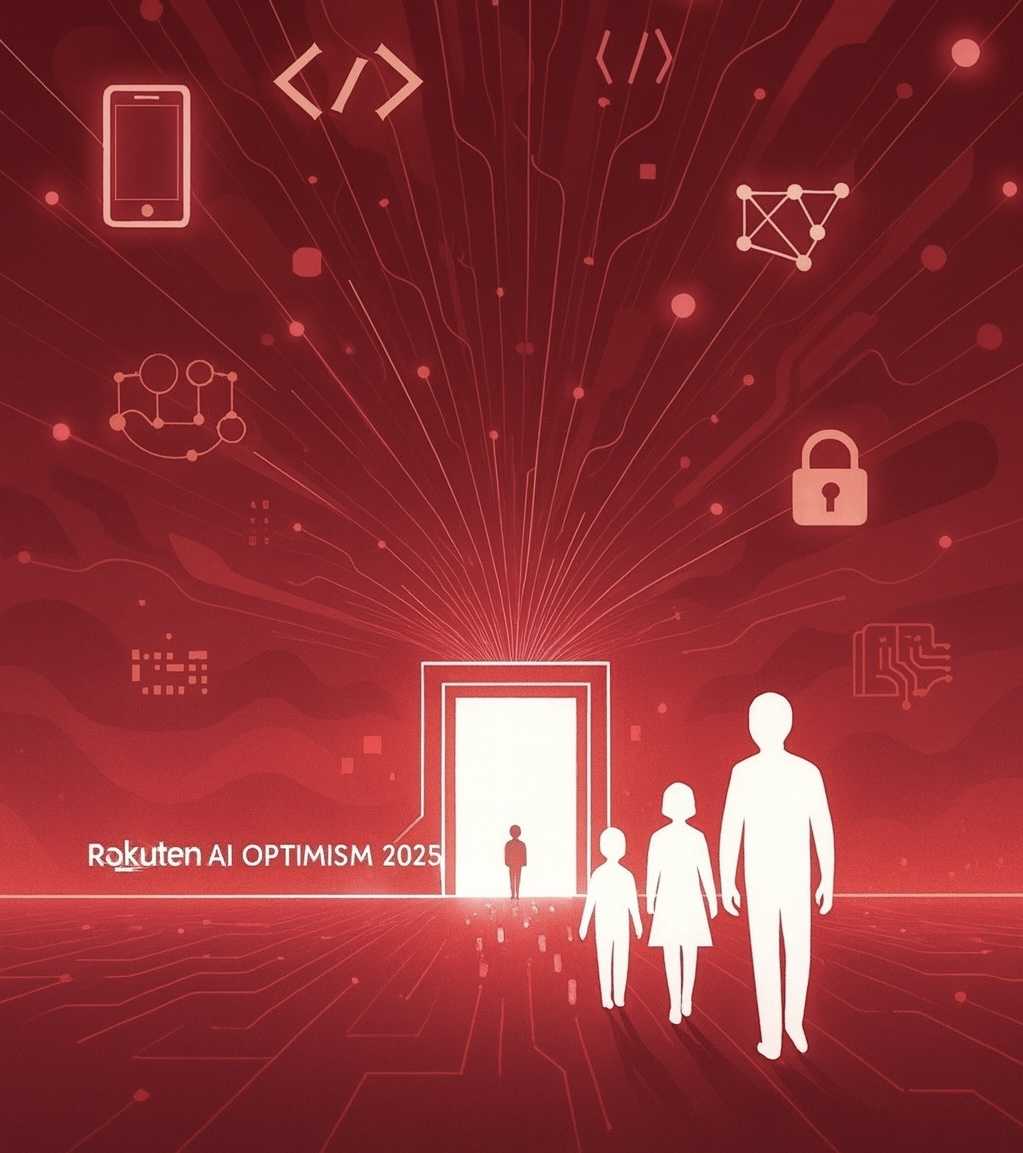
私見と考察:AI時代における日本の国際貢献
Rakuten AI Optimism 2025で示されたこれらの15の視点は、AIが単なる技術的革新を超えて、社会、経済、教育、さらには国家戦略レベルでの変革を推進していることを明確に示しています。人間中心のAI開発、技術的主権の確保、次世代教育の再構築など、多岐にわたる課題と機会が議論される中で、日本が世界のAI発展において独自の役割を果たす可能性が浮き彫りになりました。これらの洞察は、私たち全てがAI時代を生き抜く上で重要な指針となるでしょう。重要なのは、悲観主義から実践的楽観主義への転換。課題や困難を認識しつつも、具体的な行動を通じて未来を切り拓いていく姿勢かもしれません。人間中心のAI開発を推進し、教育機関が批判的思考能力の育成に注力し、政府が適切な規制と支援策を提供することで、日本独自のAI社会モデルを構築することが可能になるのかもしれません。このAI時代の転換期において日本が選択する道は、単に一国の未来を決めるだけでなく、世界のAI発展の方向性にも大きな影響を与える可能性があります。技術の進歩に翻弄されるのではなく、人間の幸福と社会の持続可能性を最優先に据えたAI活用のモデルケースを日本が示すことができれば、それこそが真の意味での「AI時代における日本の国際貢献」となるのではないでしょうか。
15 perspectives on AI from Rakuten AI Optimism
https://rakuten.today/blog/15-perspectives-on-ai-from-rakuten-ai-optimism.html
15 perspectives on AI from Rakuten AI Optimism 2025
From sovereign AI and AI-powered fintech, to building AI tools that people can actually use, these are some of the top takeaways from Rakuten AI Optimism.

ご訪問ありがとうございます。
ただいま楽天グループでは楽天従業員からの楽天モバイル紹介キャンペーンを実施中です。 下記からログインして楽天モバイルにご契約いただくと、最大14,000ポイントプレゼントいたします!よろしくお願い申し上げます。
https://r10.to/hYYGNa
【楽天従業員から紹介された方限定】楽天モバイル紹介キャンペーン!回線お申し込みごとにポイントプレゼント!上記URLからどなたでもお申し込みいただけます。
ただいま楽天グループでは楽天従業員からの楽天モバイル紹介キャンペーンを実施中です。 下記からログインして楽天モバイルにご契約いただくと、最大14,000ポイントプレゼントいたします!よろしくお願い申し上げます。
https://r10.to/hYYGNa
【楽天従業員から紹介された方限定】楽天モバイル紹介キャンペーン!回線お申し込みごとにポイントプレゼント!上記URLからどなたでもお申し込みいただけます。

Rakuten AI Optimism 2025:未来を切り拓く15のポイント
楽天グループが主催する年次カンファレンス「Rakuten AI Optimism 2025」では、人工知能を中心テーマに据えた3日間のイベントが開催されました。ビジネス領域から社会的影響まで、AIの幅広い可能性について議論された同イベントから、特に注目すべき15のポイントをご紹介します。
ポイント1. 人をつなぐエージェント型AI(三木谷浩史氏基調講演)
楽天グループ会長兼社長の三木谷浩史氏は、基調講演において「AIは人間のつながりをより良くするものでなければならない」と述べました。同氏が発表したのは、単なる生成型AIから一歩進んだエージェント型AIへの転換です。このエージェント型AIは、ユーザーのニーズを理解し、意思決定を行い、実際に行動を起こすことができるシステムとして設計されています。楽天エコシステム全体—ショッピング、旅行、金融など—にわたって統合的に機能し、楽天モバイルの強力なプラットフォームによって支えられているのが特徴です。人間を置き換えるのではなく、人間同士のつながりを強化するツールとしてAIを位置づける同氏の視点は、テクノロジーの人間中心的な活用方法を示唆しています。
ポイント2. 楽天AIの本格始動(Ting Cai氏の戦略発表)
楽天グループのチーフデータ・AI責任者であるTing Cai氏は、楽天AIの全面的な展開について詳細を明らかにしました。楽天Linkでの開始からベータ版ウェブアプリ、そして楽天市場での年内展開まで、段階的なロードマップが示されました。注目すべきは「チャットからタスクへ、研究から行動へ、人間のブラウジングからエージェントのブラウジングへ」という変革の方向性です。楽天のエンジニアチームが開発したMixture of Experts LLMと小規模言語モデル(SLM)は、日本のAI開発を加速させることを目的としています。すでにセマンティック検索の導入により楽天市場のGMS(流通総額)が10%以上向上しており、社内では15,000人以上の楽天従業員が楽天AIを活用して生産性を向上させています。蔡氏の「私たちは行う全てのことにAIを注入しています」という言葉が、楽天の包括的なAI戦略を物語っています。
ポイント3. 日本全国へのAI普及戦略(成田修造氏との対談)
起業家の成田修造氏と楽天の小林悠輔氏による対談では、中小企業に楽天の強力なデータとツールを提供することで、日本全国にAIを普及させる戦略について議論されました。特に焦点となったのは、楽天がどのようにして事業者のAI導入障壁を下げることができるかという課題です。また、楽天が推進してきた「英語公用語化」が、日本におけるエンジニア人材不足の解決にどのように貢献しているかについても言及されました。これらの取り組みは、楽天グループ全体で日々行われている最先端の研究開発業務の原動力となっているのです。
ポイント4. 全事業者向けAIプラットフォーム(Wolt Japan・Hotel Urashima事例)
「楽天AI for Business」プラットフォームは、技術的な専門知識を持たない企業でもAIツールの恩恵を受けられるようにすることを目指しています。Wolt JapanのNatalia Khizanishvili氏と浦島観光ホテル株式会社の松下哲也氏が、それぞれの企業での楽天AIツールの実践的な活用事例を紹介しました。食品配達プラットフォームのWoltでは、配達員、顧客、レストランのサポートにAIを活用しています。一方、風光明媚なホテル浦島では、日本の観光業労働力不足への対応として楽天のツールを活用し、メールの作成、レビューへの返信、さらにはビュッフェ運営まで、幅広い業務でAIの力を借りています。
ポイント5. マーケティングにおけるAIの本質的価値(Google Japan 奥山真司氏)
Google Japan社長の奥山真司氏は、GeminiなどのアクセシブルなAIツールに関するGoogleの歴史と哲学、そしてAIが同社のマーケティング戦略にどのように組み込まれているかについて共有しました。奥山氏が強調したのは、専門家だけでなく誰もが使えるAIを創造することの重要性です。また、AIをブラックボックスとしてではなく、マーケターの実践的な協力者として位置づけることの必要性についても述べました。この視点は、AIツールの普及において技術的なハードルを下げ、より多くの人々がAIの恩恵を受けられるようにするという考え方を示しています。
ポイント6. フィンテック業界におけるAIの10年史(業界リーダーパネル)
ポイント7. 楽天銀行の超個人化ビジョン(東林知隆社長)
楽天銀行の東林知隆社長兼CEOは、完全デジタル・24時間体制のモデルで1,700万口座という驚異的な成長を遂げた同行の軌跡を紹介しました。楽天ポイント、楽天ペイ、楽天証券、そして楽天エコシステム全体との統合が、この成功の基盤となっています。将来的に東林氏が描くビジョンでは、AIが個人の銀行員として機能し、ローンや予算管理をガイドし、リアルタイム詐欺検出やリスクベース認証などのスマートセキュリティ機能によってサポートされます。「私たちのビジョンは、各顧客が専用の銀行員を持っているかのような個人化された金融サービスを提供することです」という同氏の言葉が、未来の金融サービスの姿を明確に示しています。
ポイント8. 顧客体験とエンターテインメントの最前線(Decagon・Metaphysic対談)
DecagonのJesse Zhang氏とMetaphysicのTom Graham氏が楽天のTing Cai氏と共に、顧客体験のための会話型AIエージェントと、将来のエンターテインメントにおけるAIの役割について議論しました。最近大手VFX会社と合併したMetaphysicのGraham氏は、実在の俳優の年齢を上げたり下げたりするAI画像をオーバーレイするAI生成ヒューマンパフォーマンスについて説明しました。パネリストたちは、AI音声がすでに人間を欺くことができる一方で、AI視覚技術もそう遠くない将来に同様のレベルに達するだろうと強調しました。「今後数年間で、私たちは完全にAI生成されたエンターテインメントを消費することになるでしょう」という予測が示されました。
ポイント9. AI主権と次世代コンピュテーション(小柴満信氏の警鐘)
Cdots共同創設者で経験豊富な経営幹部である小柴満信氏は、国家主権におけるAIの役割について語り、権力が国民国家からテックプラットフォームへと移行しており、世界が「テクノポーラー」秩序に向かっていると論じました。同氏は、世界的な債務、紛争、その他のマクロ的な変動を、コンピュートとAI主権をめぐる戦略的競争と関連付けて分析しました。量子コンピューティングの研究の重要性の高まり、データベース経済における通信事業者の重要性を強調する一方で、外国のクラウドインフラ、AIモデル、データ権に対する過度の依存について日本に警鐘を鳴らしました。この視点は、技術的自立性が国家安全保障の重要な要素となっていることを示しています。
ポイント10. AIによるがん研究の加速(土井俊彦博士の医療AI論)
著名な研究者である土井俊彦博士が楽天の大越拓氏らと共に、AIががん研究の加速にどのように貢献できるかを探求しました。日本が労働力不足、高齢化、原材料費の上昇に直面する中、AIは国の高い医療サービス水準を維持するための不可欠なツールとなる可能性があります。医師の専門知識を向上させ、患者とスタッフ間のコミュニケーションギャップを埋めることが期待されています。しかし、これを実現するためには業界が変化を再定義することに対してオープンであることが必要です。土井博士は、AIにおける「なぜ」を忘れないことの重要性を強調し、「患者に利益をもたらすツールであれば、私たちは前進してそれを採用すべきです」と述べました。
ポイント11. Z世代のAIネイティブ思考(QuizKnock伊沢拓司氏)
QuizKnockの伊沢拓司氏は、AIブームに対するZ世代の視点を代表してステージに立ちました。ソーシャルメディアのアルゴリズムが若者にニッチな興味を深く掘り下げることを促している状況において、伊沢氏は日本の教育が学生自身の意見を表明するよう促すことで、より積極的に学生を関与させる必要があると強調しました。伊沢氏は全国の学校を回り、AIリテラシーに関する対面ワークショップを自ら実施しています。現在のAIはユーザーの言うことにすべて同意するように見えるため、AIが実際に何ができるかを適切に理解することが、次世代の将来にとって最重要になるという指摘は極めて重要です。
ポイント12. デザインの民主化とクリエイティビティ(佐藤可士和氏・永井一史氏対談)
楽天を含む数々の象徴的な日本ブランドを手がけたデザイナーの佐藤可士和氏と、博報堂デザイン社長兼CEOの永井一史氏が、経営から地域活性化、ブランド統合まで、デザインの役割の進化について探求しました。両氏は、AIによってデザインが民主化された一方で、デザイン経営が政策やビジネス戦略においてますます大きな役割を果たしていることを強調しました。また、偽物との戦いが迫っていることを指摘し、独創性の重要性を訴えました。「何ができるか、どうやってできるかはAIが担える。なぜやるかは人間が持つべきです」という言葉が、人間とAIの協働における本質的な分担を示しています。
ポイント13. AI時代の教育における「ヒューマンエッジ」(阿部守一知事・小宮山利恵子教授・岡田武史氏)
長野県知事の阿部守一氏、小宮山利恵子教授、そして伝説的なサッカー監督の岡田武史氏が楽天の小林正忠氏と共に、これまで以上に不確実な未来の時代において、子どもたちが既存のロールモデルに常に頼ることができない状況での教育アプローチについてブレインストーミングを行いました。試行錯誤、批判的思考スキル、地域資源に基づくプログラムがすべて議題に上りました。小宮山教授は、AIの手の届かない体現されたスキルを学ぶことの重要性を強調し、岡田氏は日本の出生率低下により、各子どもが受ける注目の増加を人格形成に向けるべきだと指摘しました。
ポイント14. 日本のデジタル主権と未来(村井純教授・黒住昭仁氏対談)
「日本のインターネットの父」として広く知られる村井純教授が、楽天グループCIO兼CTOの黒住昭仁氏と日本のデジタル未来について前向きな議論を展開しました。対話は国家インフラとデジタル主権をAI準備状況と結びつけ、日本が基準を輸入するのではなく、AIの倫理的・実践的境界線の定義において主導的役割を果たすべきであることを強調しました。この視点は、技術分野において日本が受動的な採用者ではなく、能動的な標準設定者となることの重要性を示しています。
ポイント15. AI時代の日本の未来(成田悠輔氏の現実論)
経済学者の成田悠輔氏は、通常のPowerPointプレゼンテーションはもちろん、演壇の椅子も使わず、硬いステージの床に座ってAIに関する厳しい現実論を展開しました。日本の人口動態と経済停滞の中で、成田氏はユニバース25実験を引用しました。これは豊富な生活資源を提供された実験用ネズミの社会の崩壊を追跡した実験です。
「ユニバース25実験」は、1972年にアメリカの行動学者ジョン・B・カルフーン(John B. Calhoun)が行った有名なマウス実験のことを指します。別名「マウスのユートピア実験」とも呼ばれます。
実験の概要
• 対象:8匹のマウス(4オス・4メス)を投入。
• 目的:資源が無限に近い環境で、マウスの社会がどのように発展するかを観察すること。
結果の経過 第1段階(適応期) マウスは環境に慣れ、繁殖を開始。
2. 第2段階(成長期)
個体数は爆発的に増加し、理想的に見える社会が構築される。
過密状態により、社会構造が崩壊し始める。縄張り争いや攻撃性が増し、弱い個体は隅に追いやられる。
4. 第4段階(崩壊期)
「行動の退行」が見られる。母マウスが子を育てなくなり、オスは攻撃的または引きこもりに。特に目立ったのが「ビューティフル・ワンズ」と呼ばれる群れで、繁殖も闘争もせず、ただ身繕いと食事だけを繰り返す無気力なマウスが現れた。
5. 最終的に
繁殖は停止し、若い個体も社会性を失い、やがてコロニー全体が崩壊して絶滅した。
社会への示唆
この実験はしばしば以下のような警鐘として語られます。
• 過密社会や資源の偏在がもたらす人間社会の崩壊モデル
• 「意味」や「役割」を失った存在の無気力化(ビューティフル・ワンズ現象)
• 物質的豊かさが必ずしも精神的豊かさや社会の持続につながらないこと
ただし、実験はあくまで「マウス」であり、人間社会に直接的に当てはめるのは単純化しすぎるとの批判もあります。
AIはエネルギーや半導体と同等の中核的資源となりつつありますが、クラウドとモデル層はわずか数社によって支配され続けています。成田氏は、自国産AIモデルへの投資と、悲観主義から実践的楽観主義への心構えの変化において、いくつかの希望の光を強調しました。
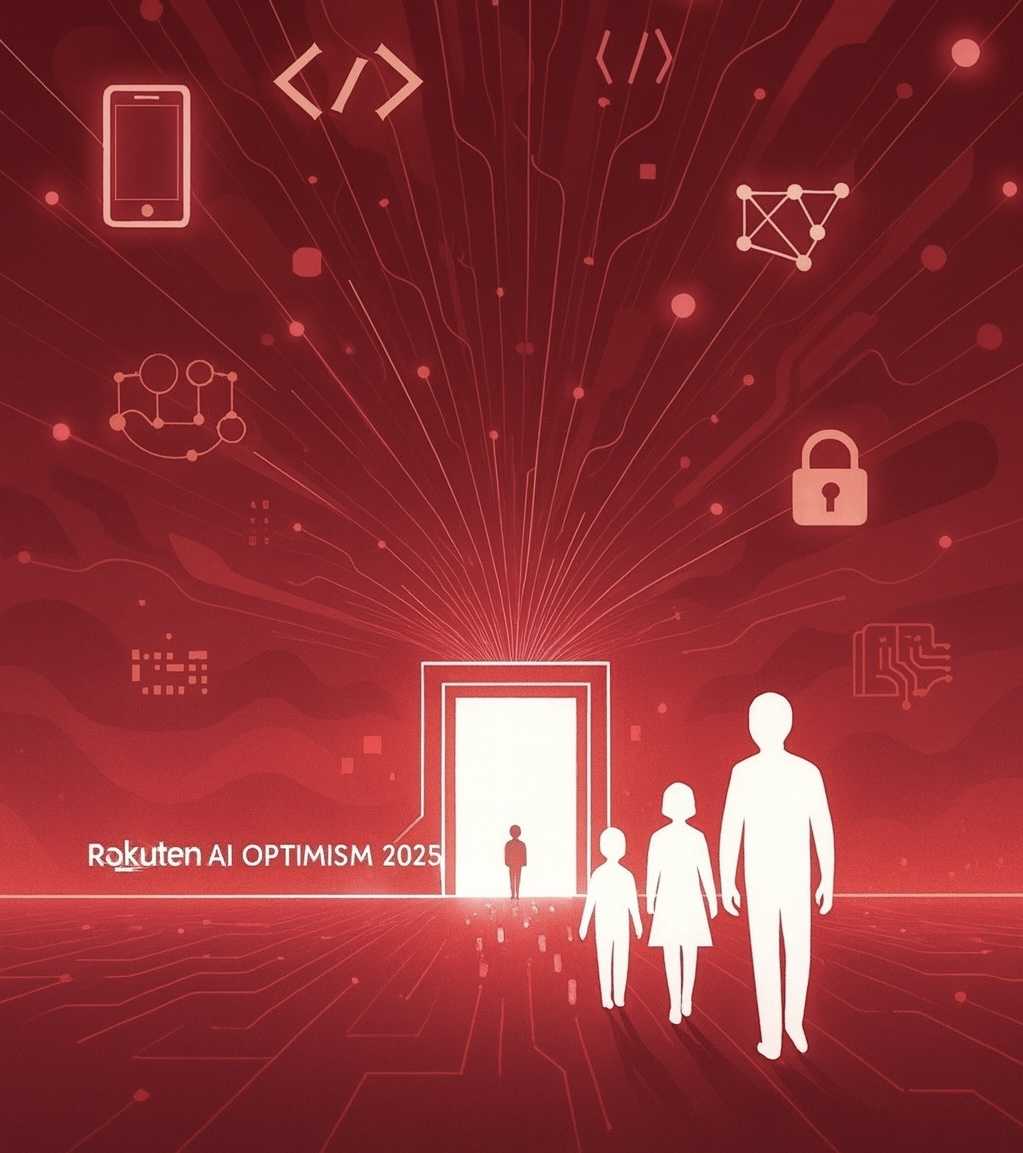
私見と考察:AI時代における日本の国際貢献
Rakuten AI Optimism 2025で示されたこれらの15の視点は、AIが単なる技術的革新を超えて、社会、経済、教育、さらには国家戦略レベルでの変革を推進していることを明確に示しています。人間中心のAI開発、技術的主権の確保、次世代教育の再構築など、多岐にわたる課題と機会が議論される中で、日本が世界のAI発展において独自の役割を果たす可能性が浮き彫りになりました。これらの洞察は、私たち全てがAI時代を生き抜く上で重要な指針となるでしょう。重要なのは、悲観主義から実践的楽観主義への転換。課題や困難を認識しつつも、具体的な行動を通じて未来を切り拓いていく姿勢かもしれません。人間中心のAI開発を推進し、教育機関が批判的思考能力の育成に注力し、政府が適切な規制と支援策を提供することで、日本独自のAI社会モデルを構築することが可能になるのかもしれません。このAI時代の転換期において日本が選択する道は、単に一国の未来を決めるだけでなく、世界のAI発展の方向性にも大きな影響を与える可能性があります。技術の進歩に翻弄されるのではなく、人間の幸福と社会の持続可能性を最優先に据えたAI活用のモデルケースを日本が示すことができれば、それこそが真の意味での「AI時代における日本の国際貢献」となるのではないでしょうか。
15 perspectives on AI from Rakuten AI Optimism
https://rakuten.today/blog/15-perspectives-on-ai-from-rakuten-ai-optimism.html
15 perspectives on AI from Rakuten AI Optimism 2025
From sovereign AI and AI-powered fintech, to building AI tools that people can actually use, these are some of the top takeaways from Rakuten AI Optimism.

ご訪問ありがとうございます。
ただいま楽天グループでは楽天従業員からの楽天モバイル紹介キャンペーンを実施中です。 下記からログインして楽天モバイルにご契約いただくと、最大14,000ポイントプレゼントいたします!よろしくお願い申し上げます。
https://r10.to/hYYGNa
【楽天従業員から紹介された方限定】楽天モバイル紹介キャンペーン!回線お申し込みごとにポイントプレゼント!上記URLからどなたでもお申し込みいただけます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[楽天グループの戦略] カテゴリの最新記事
-
楽天AI戦略の全貌:「Rakuten AI Optimism… 2025.11.16
-
誰もが手頃な価格でモバイル通信を利用で… 2025.07.04
-
楽天のロボット革命、東京を席巻 2025.06.30
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










