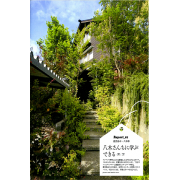PR
X
Free Space
設定されていません。
Calendar
2025.11
2025.10
2025.09
2025.08
2025.07
2025.10
2025.09
2025.08
2025.07
2025.06
2025.05
2025.04
2025.03
2025.02
2025.05
2025.04
2025.03
2025.02
Comments
六つの村の睦み合い…
New!
jinsan0716さん
渡り鳥が結ぶ友和の… gusinさん
十人十色の情文スタ… 情報文化学科さん
ポンコツ山のタヌキ… やまもも2968さん
鹿児島のマンション… かごすまさん
Homeward Ultra-7さん
何を食べようかなぁ… hiro_0503さん
おひさまニコニコ ^… *Liko*さん
渡り鳥が結ぶ友和の… gusinさん
十人十色の情文スタ… 情報文化学科さん
ポンコツ山のタヌキ… やまもも2968さん
鹿児島のマンション… かごすまさん
Homeward Ultra-7さん
何を食べようかなぁ… hiro_0503さん
おひさまニコニコ ^… *Liko*さん
Freepage List
Keyword Search
▼キーワード検索
カテゴリ: 食農教育
以前、 川上小のアイガモ農法の総合学習(アイガモのいのちをいただく会)
について、このブログでも紹介しました。しかし、残念なニュースが流れました。2007年6月28日の南日本新聞の記事です。ここに引用させていただきます。
川上小 アイガモ農法取りやめ(2007年6月28日 南日本新聞)
「アイガモ農法」による米作りに11年間取り組んできた川上小学校は本年度、同農法による実習を取りやめた。5年生の総合学習として続けてきたが、「総合学習をバランスよく実施するため」「アイガモを食べることで命の大切さを学ぶには早すぎる」などの理由を挙げる。一方、同行の保護者らは、学校側の主張を認めつつ「アイガモ農法は川上小学校の伝統」と1825人分の署名を集め、復活、存続を求めている。(地域報道部・中野督子)
同校のアイガモ農法による米作りは、環境や有機農業を学ぼうと1996年始めた。農協が補助し、PTAや地元農家などが児童とともに農作業に励む。2001年からは、成長したアイガモを食べる「食と命を考える学習」も行ってきた。今年は、アイガモを利用しない減農薬米作りに変更し、田植えは一部の高齢者が手伝った。総合学習での授業時間も短縮、英会話などを増やした。
教職員で決定
アイガモ農法をやめた理由について、同校は、
(1)総合学習が求める「調べる力を付ける学習]につなげるのが難しく、全110時間中87時間を占めた
(2)アイガモを殺すことに批判もあり「食と命の授業」は小学校の発達段階にふさわしくない
(4)学校の池で飼育したアイガモの汚物が詰まり水源地汚染も心配される
(5)アイガモ農法は教員が主体的に指導できず、学校で指導する枠を超えている
-などを挙げる。
同校の馬場盛行校長によると、教職員間で昨年11月から3回の話し合いを持ち、今年2月に変更を決めた。2月末に5年生(当時)の学年PTAで説明したほか、5月17日のPTA総会後に全学年の保護者対象の説明会を開いた。しかし現在の5年生の保護者らには個別の説明はなかったという。
命を知る機会
「PTAや地域が一体となった活動をなぜ壊すのか」-保護者らはアイガモ農法の存続を求めて4月、署名活動を行った。「食べることの大切さを知る貴重な機会。続けてほしい」「『アイガモ農法があるから川上小に行きたい』という子どももいる」との声が寄せられ、卒業生も心配しているという。保護者の一人は「今年が駄目でも来年以降復活させられないか」と望みをつなぐ。
初回から同校のアイガモ農法を指導してきた近くの農業橋口孝久さん(55)は「いまだに学校側からの正式な説明を受けていない。ともに地域で協力してきた仲間も憤っている」と話した。
教育上の効果についても、県内外でいのちの授業を行う鹿児島国際大学短期大学部の種村エイ子教授(60)は「命が見えにくくなっている現代、アイガモの命をいただくことで学べることは多い」と指摘。「学習は教師だけでなく子ども、保護者、地域が協力して行うべきでは」と、学校側の判断による打ち切りに疑問を呈し、地域や家庭との連携の大切さを訴えた。
以上ですが、皆さんいかがでしょうか?
総合学習のあり方、効果が疑問視される中、川上小の取り組みこそ、総合学習の成功例の一つということで、学生にも紹介してきました。「自分はアイガモを食べるなんてできない」と感想を述べる学生も中にいるけれど、そうした学生も含めて「すばらしい取り組み」「こんな貴重な経験ができて川上小の子どもたちは幸せだ、うらやましい」という学生が大半です。
「アイガモを殺すことに批判もあり「食と命の授業」は小学校の発達段階にふさわしくない」ことも学校側はやめる理由に挙げているけれど、私たちは生き物を殺さずに生きていけるのでしょうか。現代社会では、生き物を殺す場面は私たち自身には隠されていて見えず、そうしたことをまったく実感することなく、できあがって商品となった食品を買って食べて生きる社会になっており、だからこそ命の大切さもわからなくなっているのではないでしょうか。川上小のアイガモ農法の総合学習は、そうしたことを学ぶ絶好の機会だったはずです。いったい、他の生き物のいのちをいただくことで私たちが生かされている、ということを学ぶ絶好の機会を失って、どんな教育をするというのでしょうか。
しかし、どんな理由があるにせよ、こんなすばらしい取り組みをやめてしまうのは許せません。地域や保護者の皆さんにがんばってもらって(私ももちろん協力します)、ぜひ復活させてほしいと思います。
川上小 アイガモ農法取りやめ(2007年6月28日 南日本新聞)
「アイガモ農法」による米作りに11年間取り組んできた川上小学校は本年度、同農法による実習を取りやめた。5年生の総合学習として続けてきたが、「総合学習をバランスよく実施するため」「アイガモを食べることで命の大切さを学ぶには早すぎる」などの理由を挙げる。一方、同行の保護者らは、学校側の主張を認めつつ「アイガモ農法は川上小学校の伝統」と1825人分の署名を集め、復活、存続を求めている。(地域報道部・中野督子)
同校のアイガモ農法による米作りは、環境や有機農業を学ぼうと1996年始めた。農協が補助し、PTAや地元農家などが児童とともに農作業に励む。2001年からは、成長したアイガモを食べる「食と命を考える学習」も行ってきた。今年は、アイガモを利用しない減農薬米作りに変更し、田植えは一部の高齢者が手伝った。総合学習での授業時間も短縮、英会話などを増やした。
教職員で決定
アイガモ農法をやめた理由について、同校は、
(1)総合学習が求める「調べる力を付ける学習]につなげるのが難しく、全110時間中87時間を占めた
(2)アイガモを殺すことに批判もあり「食と命の授業」は小学校の発達段階にふさわしくない
(4)学校の池で飼育したアイガモの汚物が詰まり水源地汚染も心配される
(5)アイガモ農法は教員が主体的に指導できず、学校で指導する枠を超えている
-などを挙げる。
同校の馬場盛行校長によると、教職員間で昨年11月から3回の話し合いを持ち、今年2月に変更を決めた。2月末に5年生(当時)の学年PTAで説明したほか、5月17日のPTA総会後に全学年の保護者対象の説明会を開いた。しかし現在の5年生の保護者らには個別の説明はなかったという。
命を知る機会
「PTAや地域が一体となった活動をなぜ壊すのか」-保護者らはアイガモ農法の存続を求めて4月、署名活動を行った。「食べることの大切さを知る貴重な機会。続けてほしい」「『アイガモ農法があるから川上小に行きたい』という子どももいる」との声が寄せられ、卒業生も心配しているという。保護者の一人は「今年が駄目でも来年以降復活させられないか」と望みをつなぐ。
初回から同校のアイガモ農法を指導してきた近くの農業橋口孝久さん(55)は「いまだに学校側からの正式な説明を受けていない。ともに地域で協力してきた仲間も憤っている」と話した。
教育上の効果についても、県内外でいのちの授業を行う鹿児島国際大学短期大学部の種村エイ子教授(60)は「命が見えにくくなっている現代、アイガモの命をいただくことで学べることは多い」と指摘。「学習は教師だけでなく子ども、保護者、地域が協力して行うべきでは」と、学校側の判断による打ち切りに疑問を呈し、地域や家庭との連携の大切さを訴えた。
以上ですが、皆さんいかがでしょうか?
総合学習のあり方、効果が疑問視される中、川上小の取り組みこそ、総合学習の成功例の一つということで、学生にも紹介してきました。「自分はアイガモを食べるなんてできない」と感想を述べる学生も中にいるけれど、そうした学生も含めて「すばらしい取り組み」「こんな貴重な経験ができて川上小の子どもたちは幸せだ、うらやましい」という学生が大半です。
「アイガモを殺すことに批判もあり「食と命の授業」は小学校の発達段階にふさわしくない」ことも学校側はやめる理由に挙げているけれど、私たちは生き物を殺さずに生きていけるのでしょうか。現代社会では、生き物を殺す場面は私たち自身には隠されていて見えず、そうしたことをまったく実感することなく、できあがって商品となった食品を買って食べて生きる社会になっており、だからこそ命の大切さもわからなくなっているのではないでしょうか。川上小のアイガモ農法の総合学習は、そうしたことを学ぶ絶好の機会だったはずです。いったい、他の生き物のいのちをいただくことで私たちが生かされている、ということを学ぶ絶好の機会を失って、どんな教育をするというのでしょうか。
しかし、どんな理由があるにせよ、こんなすばらしい取り組みをやめてしまうのは許せません。地域や保護者の皆さんにがんばってもらって(私ももちろん協力します)、ぜひ復活させてほしいと思います。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食農教育] カテゴリの最新記事
-
「ブタがいた教室」と「いのちをいただく」 2009.01.01
-
人間は何を食べてきたか 2008.12.24
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.