カテゴリ: 国政・経済・法律
集団的自衛権行使を可能とする政府の憲法解釈や法律成立に関して、「違憲性」を主張する憲法学者や法制局長官OBの側の対応に対して、規範論理的な見地から大きな問題提起をしたのが、話題の藤田名誉教授・元最高裁判事の論文ということだろう。その内容については、拙ブログにても要約した。
→ 藤田論文を読む (2016年5月30日)
従来の政府見解を変えようとすることが(それだけで当然に)憲法に反する、歴代の内閣法制局長官ができないと言っているのに変更する総理の姿勢は違憲だ(or立憲主義に反する)、などの論議がなされた。たしかに内閣の姿勢は、安全保障情勢や紛争地での活動に関する認識の点でも、憲法解釈論の理論的な説明の点でも丁寧さを欠き、さらに、審議時間を重ねたからなどと強引な姿勢も残した。だが、最後まで噛み合わなかった感じがするのは、根本的に何が原因だったのだろうか。
私は、漠然とこう考えていた。久々に憲法が国民の前にクローズアップされた舞台で、憲法学者(の多く)は、集団的自衛権を(憲法改正を経ずして)解釈で導くのは無理だから違憲だという。だが、解釈にも柔軟性や変遷があっても良いはずで、70年間の世界情勢の変化をすくい上げながら(だって昔は自衛隊の存在さえ否定していたでしょ!)どこまでが(憲法の改正をしなくても)認められてどこからが憲法に反するか(やるなら憲法改正せよ)、学者にこそ明確にしていただきたいと思う。だが、国際情勢には冷淡で超然としているのか、いやむしろ、憲法解釈とは私らの専権事項とばかり、政治が(原子力ムラならぬ)憲法ムラに容喙するのを忌避しているような風さえ感じられた。そして、野党が露呈した自らの問題は、憲法学者が不得意だというのなら、政治家こそが、国際政治の現状をどう理解して国防の方向を導くかの議論をしていくべきところを、自衛隊員を危険にさらすとか、9割の学者も言っているのだから憲法を守れとか、社会党がよみがえったかのように硬直的で金科玉条的だったことにあった(だからこそ一致団結できたのか)と言っては言い過ぎか。国の守りを真剣に考えることを放擲する理由に憲法を挙げてはダメでしょう(憲法守って国滅ぶ。小林節の本の名)。
このように今回の論議の「わかりにくさ」又は「消化不良感」は、国防政策論でも憲法論としても残ったのだが、このうち憲法論の側面で、より個別的な問いかけで具体化するとすれば、例えば、
・憲法解釈は誰か(例えば内閣法制局長官の答弁で)行ったら、そこからどこまで変えられる/変えられないのか。
・国会で何度も答弁した憲法解釈だとして、そのことから解釈を変えるのは憲法(立憲主義)に反するのか。
・内閣法制局長官がダメと言ったら総理も従うのか。
これを思い出したのは、3月の読売新聞の記事だ。憲法学界でも、(ダメだからダメ、ではなく)この問題を理論的に考える見解が出ている。当ブログでも勉強した。
( 安保法制をめぐる立憲主義や違憲の論議を考える(その1) (2016年5月22日))
藤田論文は、私自身のような一般人の漠然とした問いかけを含めて、今回の事態を法律学が規範論理的にどう考えるべきかを論じたものだと自分では理解した。もとより私には憲法も行政法も理論的な知識は薄いが、氏の意図を一言でいえば、(おそらく一般国民も安倍政権は不誠実だと思う一方で感じていた)憲法学の側の硬直性、言い換えれば、現実(国際)社会の問題の解決を導くために理論の発展を目指すという、およそ法解釈学や法律学者の存在意義ともいうべきものを、皆さんは(長らく)忘れておられるのではないか、の点を指摘するものだと言えよう。
藤田名誉教授は、今回の法制が憲法に反するのかの結論については慎重にして言及しておらず、あくまで規範論理的な議論がしっかりと行われるべきだという立場から論じている。ただし、「憲法学界は戦略的に違憲論を振りかざすだけではなく、法案が現実に成立したのだから、(基本は反対だとしても)運用上の具体的な問題について学者として責任を持って見解を示す姿勢をとるべき」(この表現は私の意訳含む。)というのは、挑戦的ではある。
省庁再編に携わり、最高裁判事も務められた氏が、(違憲合憲の結論に言及しないまでも)行政法分野での法解釈学の努力の事例をわざわざ引用しながら(憲法学者だって知らないはずもない)、憲法学界の(努力不足との)姿勢を批判するものである。従って、伝統的(?)憲法学者からは煙たがられる可能性があり、野党や一部マスコミからは「御用学者」とレッテルを貼られるかも知れない。もちろん、氏はそんなことは織り込み済みだろう。
かくいう私も、かつて藤田教授の行政法の講義を聴いた。定義すら確定しない行政法(総論)の深みに戸惑ったが、例えば行政行為の公定力とは何か、行政裁量とは何か、民事法関係の適用の有無など、現実に事は進んでいるのに理論的には未だ整理されていない問題をどう考えていくかの点が、(理解がどこまで追いついたかは別として)興味深かった。とにかく論理的に考えること。現実の問題があるとすれば、さしあたりどのような理解や整理ができるか提示しながら検証していくこと。そんな印象があった。
その後、行政関係をめぐる法整備は飛躍的に進んだ。通則的な部分では、手続法や救済法が格段に整備されてきた。戦後の公害問題、都市の土地利用と収用問題、情報公開、財政問題、住民訴訟などなど、社会や国民意識の変化とともに、行政法学も現代的に発展してきたと言えるだろう。個人的には、いまでも実定法規や行政法理論が本当のあるべき姿(住民の権利救済、行政コストの極小化など)に沿っていないと思う点は少なくないと思う。それでも、様々な法益のバランスを踏まえながら真剣に議論して、立法や運用に反映させてきたことは間違いない。その点で、憲法学の分野とは全く雲泥の格差なのではないか。(森羅万象の実定法規を対象とする行政法学と異なり、改正すらされていない実定憲法法規を扱う憲法学は事情が異なるという面はあろう。しかし、だからこそ、行政法学の場合と比べてあまり多くないはずの「現実世界」と接する機会に、学問の側がまさに学問の成果として、解釈論を丁寧かつ真剣に紹介する姿勢であるべきだということでないか。)
憲法学者はどう受け止め、とりわけ集団的自衛権を違憲と結論づけている論者はどう反応・反論するのだろうか。9条の解釈を踏み越えることは説明済みだ、安倍内閣の行動は立憲主義に反することは十分に明らかになったはずだ、と主張するような気もする。しかし、具体的争訟に至らないと憲法判断に踏み込まれず、また統治行為とされる可能性もあることから、現実の権利救済や国のあるべき形に責任をもった議論を避けて、むしろ気安く違憲だと決めつけてきた風潮もあるのではないか。少なくとも、藤田論文の提起する規範論理的な検討の枠組にどうコメントし、あるいはその枠組じたいをどう批判できるのか、(非才ながら憲法学者の主張に)関心を持っていきたい。そして、学界論議のメディアによる正しい解説などを通じて、我が国の根本constitutionをどう考えるかが、本物の国民的論議として深まっていくとすれば、藤田先生の本当の願っておられることなのでないか。
久しぶりに先生の下で勉強させていただいた気分である。そして、社会と学問のあり方を真剣に考えた学者としての良心と気概には、深く敬服申し上げたい。
■藤田宙靖「覚え書き - 集団的自衛権の行使容認を巡る違憲論議について」
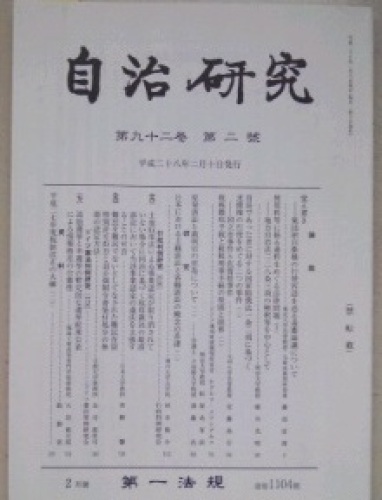
■関連する過去の記事
藤田論文を読む (2016年5月30日)
安保法制をめぐる立憲主義や違憲の論議を考える(その1) (2016年5月22日)
気仙沼の九条 (2015年9月19日)(安保法案成立に寄せて)
新安保法制と憲法学者 (2015年6月6日)
→ 藤田論文を読む (2016年5月30日)
従来の政府見解を変えようとすることが(それだけで当然に)憲法に反する、歴代の内閣法制局長官ができないと言っているのに変更する総理の姿勢は違憲だ(or立憲主義に反する)、などの論議がなされた。たしかに内閣の姿勢は、安全保障情勢や紛争地での活動に関する認識の点でも、憲法解釈論の理論的な説明の点でも丁寧さを欠き、さらに、審議時間を重ねたからなどと強引な姿勢も残した。だが、最後まで噛み合わなかった感じがするのは、根本的に何が原因だったのだろうか。
私は、漠然とこう考えていた。久々に憲法が国民の前にクローズアップされた舞台で、憲法学者(の多く)は、集団的自衛権を(憲法改正を経ずして)解釈で導くのは無理だから違憲だという。だが、解釈にも柔軟性や変遷があっても良いはずで、70年間の世界情勢の変化をすくい上げながら(だって昔は自衛隊の存在さえ否定していたでしょ!)どこまでが(憲法の改正をしなくても)認められてどこからが憲法に反するか(やるなら憲法改正せよ)、学者にこそ明確にしていただきたいと思う。だが、国際情勢には冷淡で超然としているのか、いやむしろ、憲法解釈とは私らの専権事項とばかり、政治が(原子力ムラならぬ)憲法ムラに容喙するのを忌避しているような風さえ感じられた。そして、野党が露呈した自らの問題は、憲法学者が不得意だというのなら、政治家こそが、国際政治の現状をどう理解して国防の方向を導くかの議論をしていくべきところを、自衛隊員を危険にさらすとか、9割の学者も言っているのだから憲法を守れとか、社会党がよみがえったかのように硬直的で金科玉条的だったことにあった(だからこそ一致団結できたのか)と言っては言い過ぎか。国の守りを真剣に考えることを放擲する理由に憲法を挙げてはダメでしょう(憲法守って国滅ぶ。小林節の本の名)。
このように今回の論議の「わかりにくさ」又は「消化不良感」は、国防政策論でも憲法論としても残ったのだが、このうち憲法論の側面で、より個別的な問いかけで具体化するとすれば、例えば、
・憲法解釈は誰か(例えば内閣法制局長官の答弁で)行ったら、そこからどこまで変えられる/変えられないのか。
・国会で何度も答弁した憲法解釈だとして、そのことから解釈を変えるのは憲法(立憲主義)に反するのか。
・内閣法制局長官がダメと言ったら総理も従うのか。
これを思い出したのは、3月の読売新聞の記事だ。憲法学界でも、(ダメだからダメ、ではなく)この問題を理論的に考える見解が出ている。当ブログでも勉強した。
( 安保法制をめぐる立憲主義や違憲の論議を考える(その1) (2016年5月22日))
藤田論文は、私自身のような一般人の漠然とした問いかけを含めて、今回の事態を法律学が規範論理的にどう考えるべきかを論じたものだと自分では理解した。もとより私には憲法も行政法も理論的な知識は薄いが、氏の意図を一言でいえば、(おそらく一般国民も安倍政権は不誠実だと思う一方で感じていた)憲法学の側の硬直性、言い換えれば、現実(国際)社会の問題の解決を導くために理論の発展を目指すという、およそ法解釈学や法律学者の存在意義ともいうべきものを、皆さんは(長らく)忘れておられるのではないか、の点を指摘するものだと言えよう。
藤田名誉教授は、今回の法制が憲法に反するのかの結論については慎重にして言及しておらず、あくまで規範論理的な議論がしっかりと行われるべきだという立場から論じている。ただし、「憲法学界は戦略的に違憲論を振りかざすだけではなく、法案が現実に成立したのだから、(基本は反対だとしても)運用上の具体的な問題について学者として責任を持って見解を示す姿勢をとるべき」(この表現は私の意訳含む。)というのは、挑戦的ではある。
省庁再編に携わり、最高裁判事も務められた氏が、(違憲合憲の結論に言及しないまでも)行政法分野での法解釈学の努力の事例をわざわざ引用しながら(憲法学者だって知らないはずもない)、憲法学界の(努力不足との)姿勢を批判するものである。従って、伝統的(?)憲法学者からは煙たがられる可能性があり、野党や一部マスコミからは「御用学者」とレッテルを貼られるかも知れない。もちろん、氏はそんなことは織り込み済みだろう。
かくいう私も、かつて藤田教授の行政法の講義を聴いた。定義すら確定しない行政法(総論)の深みに戸惑ったが、例えば行政行為の公定力とは何か、行政裁量とは何か、民事法関係の適用の有無など、現実に事は進んでいるのに理論的には未だ整理されていない問題をどう考えていくかの点が、(理解がどこまで追いついたかは別として)興味深かった。とにかく論理的に考えること。現実の問題があるとすれば、さしあたりどのような理解や整理ができるか提示しながら検証していくこと。そんな印象があった。
その後、行政関係をめぐる法整備は飛躍的に進んだ。通則的な部分では、手続法や救済法が格段に整備されてきた。戦後の公害問題、都市の土地利用と収用問題、情報公開、財政問題、住民訴訟などなど、社会や国民意識の変化とともに、行政法学も現代的に発展してきたと言えるだろう。個人的には、いまでも実定法規や行政法理論が本当のあるべき姿(住民の権利救済、行政コストの極小化など)に沿っていないと思う点は少なくないと思う。それでも、様々な法益のバランスを踏まえながら真剣に議論して、立法や運用に反映させてきたことは間違いない。その点で、憲法学の分野とは全く雲泥の格差なのではないか。(森羅万象の実定法規を対象とする行政法学と異なり、改正すらされていない実定憲法法規を扱う憲法学は事情が異なるという面はあろう。しかし、だからこそ、行政法学の場合と比べてあまり多くないはずの「現実世界」と接する機会に、学問の側がまさに学問の成果として、解釈論を丁寧かつ真剣に紹介する姿勢であるべきだということでないか。)
憲法学者はどう受け止め、とりわけ集団的自衛権を違憲と結論づけている論者はどう反応・反論するのだろうか。9条の解釈を踏み越えることは説明済みだ、安倍内閣の行動は立憲主義に反することは十分に明らかになったはずだ、と主張するような気もする。しかし、具体的争訟に至らないと憲法判断に踏み込まれず、また統治行為とされる可能性もあることから、現実の権利救済や国のあるべき形に責任をもった議論を避けて、むしろ気安く違憲だと決めつけてきた風潮もあるのではないか。少なくとも、藤田論文の提起する規範論理的な検討の枠組にどうコメントし、あるいはその枠組じたいをどう批判できるのか、(非才ながら憲法学者の主張に)関心を持っていきたい。そして、学界論議のメディアによる正しい解説などを通じて、我が国の根本constitutionをどう考えるかが、本物の国民的論議として深まっていくとすれば、藤田先生の本当の願っておられることなのでないか。
久しぶりに先生の下で勉強させていただいた気分である。そして、社会と学問のあり方を真剣に考えた学者としての良心と気概には、深く敬服申し上げたい。
■藤田宙靖「覚え書き - 集団的自衛権の行使容認を巡る違憲論議について」
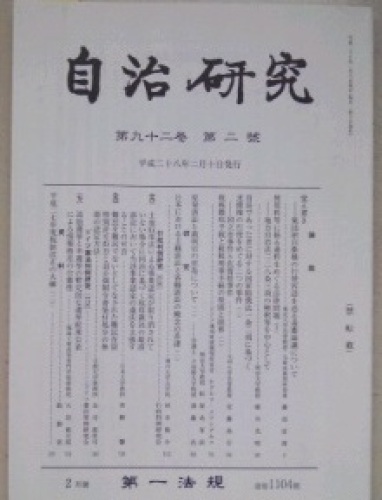
■関連する過去の記事
藤田論文を読む (2016年5月30日)
安保法制をめぐる立憲主義や違憲の論議を考える(その1) (2016年5月22日)
気仙沼の九条 (2015年9月19日)(安保法案成立に寄せて)
新安保法制と憲法学者 (2015年6月6日)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[国政・経済・法律] カテゴリの最新記事
-
得票同数の場合のくじを考える(神栖市長… 2025.11.12
-
選挙の告示(公示)日を早める事例 2025.07.20
-
大手葬儀会社のティア 2025.07.11
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
フリーページ
東北情報ソース
〔記事リスト〕仙台・宮城に関するもの

(1)仙台>地域・経済・都市・政治行政ほか

(2) >教育文化・ひと・事件事故

(3) >シリーズ仙台百景

(4)宮城>地域

(5) >経済・政治行政

(6) >教育・文化・ひと・事件事故

(7)交通・仙台空港・宮城スタジアム

(8)防災・東日本大震災

(9)近現代の仙台・宮城(鉄道敷設史含む)

(10)戦国・藩政期の仙台・宮城

(11)古代・中世の仙台・宮城
〔記事リスト〕東北に関するもの

(1) 東北 >歴史・民俗・産業・政治行政・教育文化

(2) >地域・事件・統計比較・県民性

(3) 青森

(4) 岩手

(5) 秋田

(6) 山形

(7) 福島

(8) 東北博学クイズ!
〔記事リスト〕政治・経済・司法など
〔記事リスト〕その他(教育・文化etc)
編集長のイーグルス応援戦績
カテゴリ
カテゴリ未分類
(42)仙台
(563)宮城
(663)東北
(1234)教育
(52)国政・経済・法律
(135)がんばれ楽天イーグルス
(341)グランディ21・宮城スタジアム
(13)庭の風景・小鳥
(54)雑感
(478)コメント新着
【望子成龍】-Wang Z…
sendai1997さん
おいしいブログページ dnssさん
地方暮らしが変える1… かじけいこさん
徒然なる五星亭 五星亭さん
野球!BASEBALL!!e-EA… barbertakeshiさん
おいしいブログページ dnssさん
地方暮らしが変える1… かじけいこさん
徒然なる五星亭 五星亭さん
野球!BASEBALL!!e-EA… barbertakeshiさん
© Rakuten Group, Inc.










