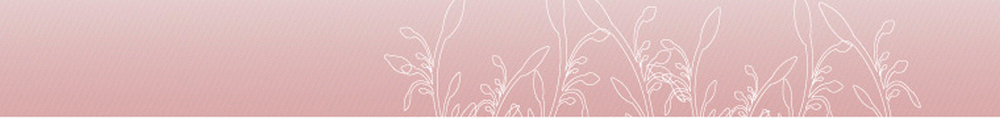2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年10月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-

帰国
この日、2泊4日のありえない!くらい短い、スケジュールから戻ってきました。 行ったのは高級ホテルの視察や、テロの現場など。あまり街中に出たり、現地の人と話す機会はなかったけど、最後の日に、ガイドさんと1時間ほど話しました。文化のこと、生活のこと、日本との違い。バリの人と日本人が結婚した場合、なぜうまく行かないことが多いか、など。ガイドをしている時は、驚くほど、日本人の感覚にあわせて話すのに、実際に話してみると、同じ部分もあり、違う価値観の中で生きているんだと感じる部分もあり。こんなことが楽しくて、学生の頃、もっと、もっと、、と気付いたら、違う文化や、考え方を持った人と出会うため、度々海外へ行ってました。そして友人と話しながら、まだ同じことをしてる!と昨日気付きました。面白かったこと★街中の犬は日本の犬と違うこと。みな顔立ちガ整って、スマートで、毛が薄い!★お供え物など合わせていたるところに花。心が豊かな気がする。
2005.10.31
コメント(2)
-

バリ島3日目
この日はウブドへ。ウブドの王宮跡は現在ホテルとなっているそう。王宮前の広場では、休日とあって、子供達が踊りの稽古。芸の世界はなかなか厳しい!長髪の男性は、タイミングがずれた子どもをビシッと扇子で叩きます。 ウブドの王宮の近くには、お土産屋が集まった市場があります。と~ってもかわいい兄弟。 市場近くの寺院です。お供え物が山のように積まれています。商売がうまく行くように、そして木に対しては、木の精霊に。朝、お供え物を捧げる姿は本当に美しいのです。
2005.10.30
コメント(0)
-

バリ島2日目
クタ地区で2002年10月12日に起きたテロの慰霊碑です。死者202名、負傷者300以上の大きなテロでした。死者の名前を国別に記載しています。 バリの人の信仰は深く、またどこでもお供え物を見かける。お供え物をする場所により意味があり、家の前へは悪魔避け、木へはその木の精霊に、車へは無事祈願など。このお寺はテロ現場のすぐ近く。テロが起きた際、壁などは壊れたのに、屋根だけが無傷で残っていたそう。ガイドさんは、「本当に不思議でありえないことです。」と力説。神がかったことの説明には特に熱が入る。バリ島は不思議なことが、多いのだそう。実は旅行中も1度、説明のつかない不思議な出来事があった。島を強く覆う、この信仰心の強さから生じているのではないかと思う。夜はスパでアロママッサージ。極楽、極楽。でも、身に付けるのは紙パンツのみ。か・・紙パンツって。。
2005.10.29
コメント(0)
-
バリ島1日目
日本からバリ島まで7時間!午前中に出発して、夕方に到着しました。一緒に参加したのは、旅行業界の人達。人を対象にしたサービス業なので、あったか~いハートの、人好きの人達ばかり。そして、冒険談を、語る語る!この人達、何人分の人生を生きてきたんだろ。。この日はクタ通りの、テロ現場を見ました。爆破された「ラジャス」は、そのままで、周囲にお祈りのための、テントのようなものが張られていました。ラジャス前の通りは、人がちらほら。でもテロ前は、まっすぐ歩けないほどの、混みようだったみたい。
2005.10.28
コメント(2)
-
明日から
明日から海外視察旅行でバリ島です。といっても超ショートステイ。すぐに戻ってきます。大学を卒業してから、信じられないことに、海外には行っていませんでした。急に目の前にひょっこり現われた、こんな機会。期間に関係なく、バックパックに2~3枚のTシャツを詰め込むだけでよかった学生時代の旅に比べ、日数は少ないのに、パンパンの荷物。そして、以前はあれほどシュミレーションしまくっていた、防犯対策も今回は国内旅行に毛が生えた程度。学生時代は、自分のためだけを向いて旅していたけれど、立場が異なると、対象となる範囲も広がり、違った緊張感。こんな機会とそれを与えてくれた人に感謝。そして、行ってきま~す。
2005.10.27
コメント(6)
-
ショートスリーパー
「ショートスリーパー」という言葉を知った。要は、短時間睡眠者のことで、例えば1日の平均睡眠時間が、エジソンは4時間、アインシュタインは3時間だったそう。私はどこでも眠れることと、寝つきの良さが得意技。フフホト行きの夜行列車で、オーバーブッキングだったため、通路で朝までぐっすり眠っていたこともある。最近はさらに極め(?)、短時間睡眠もマスター中(否応なく。。)。深い睡眠を得るためには、寝る前の環境が暗い方が良いらしい。最近、電球が切れたため、ここしばらく間接照明で繋いでいることが、マスターしつつある一因かも。
2005.10.26
コメント(2)
-

本のイベント
日曜日は、前回に引き続き、ブック★エクスチェンジに参加しました。いや~、面白いです。持っている本から、話が広がっていく。本は、その時の、その人の興味の縮図のようです。こんなことがあったらいいのになと、ふと思うことが、現実になり、さらに楽しさを加えたイベントでした。この中で「ナルニア国物語」を持ってきている方がいました。これは小学生の頃、大好きだった本。「大人になると見えなくなる世界」という記述を読んで、大人になりたくない!と思ったものでした。ちなみにその時と今で、そう違いはないような。。あまりにも大好きだったので、設定をそのままパクってお話を書いてみた本でもあります。今では、内容もほとんど覚えてないのに、なぜかワクワク感だけは残っていたりして。2006年3月映画が公開されるとのこと。観にいこう。ナルニア国ものがたり
2005.10.24
コメント(0)
-
クオリア
銀座で隙間時間ができたので、ソニータワーへ。『「脳」整理法』を読んでいたため、クオリアシリーズが目に留まりました。9月22日に開発停止されましたが、その質感や、画像は本当にスゴイです。カップルの女の子が、26万円の銀の艶やかなMDプレーヤーを見ながら、目をまん丸にしていました。●クオリアとはクオリアとは、「赤の赤らしさ」や、「バイオリンの音の質感」、「薔薇の花の香り」、「水の冷たさ」、「ミルクの味」のような、私たちの感覚を構成する独特の質感のことです。「クオリアは、脳を含めての物質の物理的記述と、私達の心が持つ様々な属性の間のギャップを象徴する概念です。(クオリアマニフェスト)●茂木さんは、このように書いている。経済が成熟するほど、人々はより繊細で高度なクオリアを求める。脳が肥大化した人間の欲望は、クオリア自体に向かうのである。レストランに行くこと、旅に出ること、ドライヴすること。これらの全ては、脳がクオリアを消費する行動であると見なすことができる。人々が求めるクオリアを提供するクオリア産業が、これからの成長産業となることが期待される。(クオリアマニフェスト)モノより思い出、なんていう言葉があてはまりそうだ。今後はさらに、モノやサービスそのものよりも、得られる満足感や、充実感をもたらすものに人はお金を払うようになる、ということだろう。●そして、クオリアに気づいたいきさつはこう書いている。1994年の2月、電車に乗っていて、突然、「ガタンゴトン」という音が、それを周波数で分析したのでは決して到達できないような生々しい質感として感じられているという事実に気がつきました。この体験によって、いわゆる定量的な方法では説明できない「世界観に開いた穴」があることに気づいたのです。(クオリアマニフェスト)参考:Sony Japan QUALIA世界は無数のクオリアに満ちている(PDF)
2005.10.23
コメント(1)
-

「脳」整理法
「脳」整理法「世界一受けたい授業」の先生でもある、茂木健一郎さん。この本では、従来のような脳の「外」にある情報の整理ではなく、脳の「内」にある情報の整理を扱っています。発売されてから約1ヵ月半で、5万部を超え、増刷(5刷、計6万部)になったとのこと。これほど売れているけれど、私にとってはちとわかりにくい本でした。理由としては言葉使いが独特で、抽象的なこと、“整理法”という言葉をメカニズムとして捉えていること、などでしょうか。この本では、統計的、科学的な知識を「世界知」、1人の人間が充実した人生を送るために必要な知識を「生活知」、このように分けています。私達が生きている世界のほとんどは、ある程度予測は付くが、最終的には何が起こるかわからないといった“偶有的”な状態です。この“偶有的”な状況を生きるための知識を付ける上で、「生活知」と「世界知」を結びつけ、整理していく脳の働きが、ポイントとなるのです。いくつか、面白かった言葉を…■覚悟を決める不確実性を楽しむという「生活知」は、そもそもこの世界の本質、とりわけ生の本質は「偶有的」なものであり、不確実性は避けられないものであるという認識のもと、「覚悟」を決めることによって得られる■セレンディピティ「行動」、「気づき」、「受容」が「偶然を必然にする」セレンディピティを高めるために必要な要素なのです。ただしこれらの3つの能力がすべてそろっていても、それだけでは偶然の幸運に出会う準備ができたに過ぎません。略セレンディピティとは「それを生かす準備ができている」、また「事後にそれを生かすことができる」能力を指すのです。■アハ!体験脳の中で何かを思いついたときに、脳の神経細胞が短い時間、同時に活動し、たった一回で本質的な変化を生み出す学習体験が起きるのです。■ディタッチメントとパフォーマティブディタッチメントとは自らの立場を離れて世界を見ること。パフォーマティブとはそれが論壇において、あるいは現実社会において、どのような効果を与えるのかを、予め計算して言葉を選ぶこと。それにしても、茂木さん、裏表紙の著者紹介の写真が、1,000円札の野口英世とそっくり。。茂木健一郎さんのクオリア日記「あすへの話題 「脳」整理法」
2005.10.20
コメント(0)
-
朝のカフェイン
本日ABCでお話していただいたのは、国連やアジア女性基金で活躍してきた女性の方でした。自分が普段普通だと思って接している、社会や、日常生活そのものが、ふと外から見てみると、なんとも滑稽に見える。そんな強烈な体験。それまで良いと思っていたことが、いかにちっぽけなことか。話を聞きながら、ここでコーヒーを飲んでいる自分ではなく、日本の中の自分、アジアの中の自分、さらにその先からみた自分へ。視点が移っていく感覚でした。
2005.10.19
コメント(0)
-
教育フォーラムやります
1人の行動は、10000人に影響すると聞いたことがあります。はじめはたった1人のことでも、水面に、しずくが落ちた時、さざ波をたてて広がるように、情熱や行動が広がっていきます。1月8日に大阪で行う、教育フォーラムも、まずは私達が動き出してみよう、そして、"教育"のさざ波の元になろう、そんな機会です。●詳しくはこちらから●---------------------------------------------次世代型教育フォーラム2006~「考える」から「行動する」へ~★開催日時・概要 日時: 2006年1月8日(日) 10:00~17:30 場所: アピオ大阪(大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5) 参加費:1,000円★お申込みはこちらからhttp://kf2006.com/index.html---------------------------------------------
2005.10.17
コメント(0)
-

情熱の人
失礼ながら、その売り方ではモノは売れません7月に国際女性ビジネス会議でお話を聞き、もっと知りたいと購入したものの、今まで寝かせていました。この本からは、現在ダイエー会長となった林文子さんが、国際女性ビジネス会議に参加で見せた“熱さ”がそのまま伝わってきます。・採用で断られても、レポートを提出して、熱意で採用される。・本気で怒る人に対して、その姿が切なく愛おしい、と思う。・プロとは1度、2度限界を超えた経験を持つ人。・現場の慣習に捕らわれず、おかしいと思ったことを行動に移す。熱いハートを持ち、先のことを見据えた強引さと、あふれんばかりの愛情を持った人。●なるほど!林さんは芸術好きなのだそう。喜劇に通ったり、歌舞伎やコンサートなど仕事以外での+αを持ち、そのことを仕事にも活かしている。すなわち点と点が、線となり面となって、総合的に、人そのものを押し上げている。そういえば周囲の魅力的な人って、仕事以外の+αを持っているな。
2005.10.16
コメント(0)
-

個体発生は系統発生を繰り返す
「個体発生は系統発生を繰り返す」という言葉があります。例えば、人の卵から成体になるまでの発生は、人の進化の道をたどるというもの。ちょうど3年前に、シャープが手のひらサイズのポータブルMPEG-4プレーヤー「ケータイビデオ」を発売した時、新聞の社説でこの言葉が取り上げられていました。記憶が定かではありませんが、ラジオからテレビのように音声から映像、録画再生の流れが、ポータブルプレーヤーの中でも起きている。そんな記事でした。13日に発表された、動画再生に対応した第五世代iPodは、まるで3年前のデジャヴ。記憶容量も格段に増加して、最大150時間のビデオを収録できるのだとか。3年前との違いは、スペックのみに留まらず、iPodは、ハードを楽しむ土壌である、ソフトをセットで提供していることが鍵。この日は、アップルストアに行き、iPodを見てきました。見たのはiPod nanoでしたが、その薄さに驚き。折れてしまいそうなほどの、一枚のカードでした。「個体発生は系統発生を繰り返す」は、以前よりかなり速いスピードとなり、しかもスペックを変えて、何度も繰り返されている。そんな印象を受けました。ケータイビデオiPod
2005.10.15
コメント(0)
-
ヨロコビ
“ヨロコビ”にも色々とあるようで、困難が伴っていたり、人との関係があったりすると、より深くて広いものになるようです。私の場合、ヨロコビは大きく2つに分類できます。●無条件のヨロコビ・友人の結婚式や、人のHAPPYの疑似体験など・人の役に立ったと思えるときなどなど。これらはワクワク感にも感じる、継続性があり、やみつきになるヨロコビです。イメージにすると、浅くて広いものです。●条件付のヨロコビ・何かを達成した時・評価された時などなど。これらは、一過性のもので、のどもと過ぎると、案外あっさりと過ぎてしまうヨロコビです。イメージにすると深くて狭いものです。特に深さが深いものは、印象的で忘れられません。で、なぜこのようなことを書いたかというと、今日は小さな“条件付のヨロコビ”があったからなのです。番号で開ける鍵つきの郵便受け。ここ一ヶ月ほど、鍵が閉まってしまい、ちゃんと条件どおり番号をあわせるのに、開かずの扉。郵便物が取れなくなり、今日こそは、とぐるぐる回していたら、なんと、“パカッ”と音がして、開きました。とっても爽快。のどもと過ぎると…、のヨロコビ。落ちはないけど、必要に迫られているのも、ヨロコビの深さを決める一要因のようです。
2005.10.14
コメント(0)
-
仕事を楽しく
この日参加させていただいた、ある会社の社内勉強会で、バーチャルハリウッドの事例を聞きました。社内で手を挙げた人がディレクターとなり、部門の枠を超えて、メンバーを募り、新しいサービスを作り出すというもの。実際にディレクターをされた方のお話が印象的でした。様々な経営者やトップクラスの人の話を聞いたとき、全ての人に共通していたのが、失敗の話なども含め、仕事を楽しそうに話していたとのこと。この経験から自分の仕事を振り返り、ディレクターに応募されたとのことでした。誰しも自分のやったことが役立ったり、それが認められたり、達成感があったりするとうれしいもの。社内、社外限らずこのような場が多くあることが、自分自身のストックを作ることになり、ひいては経営者などにもなっていったのだろうと思います。会社内でこのような場を、制度により作り出していることは素晴らしいし、それがなければ社外に求めていもいい。ただ、社外に求める場合は、求める力を予め明らかにし、どのような力をつけようとしているのか、目的を持つことが必要です。今はストックを蓄える時期。そう思います。
2005.10.12
コメント(0)
-

情報を多角的・多面的視点で捉える
渋井真帆の日経新聞読みこなし隊渋井真帆さん書いたこの本の、一番のポイントは、わかりやすさだろう。この本のことを知ったのは、日経新聞主催の講演会。その講演でも話のわかりやすさ、そのことから来る共感を集める話が、キラリと光っていた。この本でも講演で感じた“キラり”が存分に、メタファーや、ラベリングといった形で活かされている。例えば「日経新聞」は「世界経済欲望ドラマ新聞」、「国・企業・個人」を3つのマルに分ける、国と国との問題を欲望達成のための3つの視点から考えてみるなど。情報をラベリングし、ヨコ読みして、関連付けすることで、情報を「多角的・多面的」に捉える。こうすることで自分と国や世界の出来事を関連付け、さらに先読みができそう、とワクワクしてくる。これまでの読み方は、タテ読み&つまみ食い程度だった。視点の違いで、同じものなのに、これほど捉え方が異なるのは、驚き。●なるほど!『「経済」とは「人間の欲望や行動を貨幣という単位で数値化したもの」』企業も、国も、人に置き換えてみると、まさにドラマの登場人物そのもの。人の欲望や感情を知ることは、世界の動きを知ることだったのか。
2005.10.10
コメント(2)
-
マイ聖地論
“マイ聖地論”を書く、という記事を見つけました。聖なる感覚を抱ける場所はどこか、という問いだそう。人それぞれの“マイ聖地”を考えるのは、楽しいですね。私の“マイ聖地”は、・朝5時の薬師寺~1度しか見たことがないのに、心に焼き付いている色彩~・六本木ヒルズの展望台~見方の視点が変わる場所~・ネパールのゴルカという村~美しい段々畑と、素敵な出会いのあった場所~ちなみに、大学の授業で問いかけた著者によると、「自室」「体育館やグランド」が2、3割、森の中や海など、自然環境も2、3割、その他、「新宿のある交差点」「池袋のAビルとBビルの間」、「彼女との思い出の場所」など具体的だったり、自分が幸福な体験をした場所をあげる人も、少しずついるそう。(日経プラス1 聖なる地は様々 鎌田東二・京都造形芸術大学教授)誕生しては消えていくのが聖地。日々、聖地を見つけ出していくのも良さそう。
2005.10.09
コメント(2)
-
アートスクール
2ヶ月ぶりの完全オフ。それで、前回から2ヶ月ぶりに、アートスクールへ。音楽や美術などの芸術は、人間に一番近いものだと、つい数日前に聞いた。きっと人の心に働きかける大きな要素の一つが、感動を感じる感受性の部分で、芸術は、感受性を現しているからなのだろう。これは、芸術を見ている側の見方。絵を描いている時は、マラソンと同じ感覚。高校時代は、5分描いたと思って時間を見ると5時間だった、なんてこともあったけど、さすがに今は、体力がなくなったのか、そんなことはなくひたすら妄想しながら、描いている。大学の心理学の授業で、そしてつい先日たまたま、コラージュをする機会があったのだけど、きっと絵を描いている時と、脳内には同じ物質が出ているんじゃないかと思う。頭は別のことを考えているのに、手が勝手に動いて作りだしている感じ。頭の中は、先日のドラマのこのシーンが浮かんでいるのに手先はちゃんと、明暗が足りないとか、形がゆがんでるとか、勝手に判断しながら、頭の中とは違う場所で、進めていく。頭と手先が同じことを見ていると、かえって集中できない。2ヶ月ぶりに見てみると、ぜ~んぶ、描き直したくなって、かなり描きなおした。前回は、ほぼ出来上がって、あと一息、と思っていたのに。煮詰めて、期間を置いて見直してみる。そんなことも大事。
2005.10.08
コメント(0)
-
人が変化する家
逆転の発想、とでもいうのだろう。事実を疑ってみる。そうすると、いつもと同じものが、違う見え方をする。こんなもんだ、と思ったときから、成長は止まってしまう。人が止まると、政治も経済も止まってしまう。荒川修作さんの「三鷹天命反転住宅」を始めて知ったのは、「課外授業ようこそ先生」だった。すっとんきょうな形や色の住宅。不安定、段差、などを取り入れることで生まれる、身体の行為や動き。これを毎日知覚することで人の可能性が開かれ、長生きできる家、なのだそうだ。住宅への構想は、共感できる。ベトナムやミャンマーで乗り合いバスで移動したとき、いずれも高齢のおばあさんが乗り合わせていたことがあった。外国から輸入した中古バスで、上り口が高いのも意に介せず、一晩中、3人がけの座席に、5人詰め込まれても平気。人は、環境に適応していくのだと思った。そして快適な環境ほど早く適応し、しかも後戻りできない。住宅自体への評価はさておき。私の荒川さんへの共感は、その考え方。日々を無目的にただ過ごすのではなく、人を取り巻く環境を変えることで、人間自体に働きかけ、地域、経済の底上げをしていくこと。簡単に言ってしまえば、せっかく存在しているんだから、世の中にプラスになることをする、ということ。今日また、ワールドビジネスサテライトで、見かけてしまった。
2005.10.06
コメント(0)
-

常に意識すること
自分の姿は常に見られて、評価されている。朝ドッキリする言葉と出合った。普段見られていると意識していないところで、周囲の人は、自分を判断している。姿勢、声音、生産物、全てから。この日、同僚からもらった誕生日プレゼントは、歯磨きセットの“袋”だった。よくコンビニに売っている歯磨きセットの、入れ物の部分。あまり、持ち物にかまわないため、歯磨きセットはビニール袋に入れていて、突っ込まれても、笑い飛ばしていたんだけど、ちゃんと評価されていたよう。ありがたく使わせていただきます!
2005.10.04
コメント(2)
-
今日の花
今日の花はガーベラです。会社近くの花屋のお兄さんとは、すっかり顔見知りになってしまいましたが、今日は、近所のスーパーで100円ナリ。一度しか会ったことのない人から、「感謝」と書かれたはがきが届きました。見ていてあたたかくなるこの言葉は、以前は軽く、「ありがとう」の代名詞として使っていましたが、最近では、湧き出てくるものとなりました。どんなものからでも、そう見るから、それが見えてくる。見出す視点を持ち続けることが、自分の心を創っていくことです。
2005.10.03
コメント(0)
-
この日。
恒例のように、同じ日に、ケーキを買いに行っている、パティシエの友人。この日もひょっこり夕方に尋ねたら、「来るかと思ってた~」と迎えてくれました。細い体で、大きなオーブンや泡だて器を動かし、かすり傷の痕が見える、筋肉質になった腕で、手際よく次々とケーキを作りだしていく。ケーキは“感謝”の気持ち、と言っていたことを思い出しました。この日、一つ歳を重ね、昨年からの1年間を振り返ってみました。この1年間に得た宝は、出会った人達。刺激や喜びや、気づきやそしてもっともっと、本当に多くのものを得た1年間でした。歳を重ねるということは、多くの仲間、人達と会うということ。ありがとうございました。
2005.10.02
コメント(2)
-
新しい働き方
ここ数年、年上の方、それも退職後の年齢の方と話す機会はなかったと思います。この日は久しぶりに、既に退職されて、NPOをされてる方と、じっくりとお話しする機会がありました。ボクのこんな話を聞けば、渋谷で、おへそ出して歩いている若い子達も、きっと居住まい正しくなるだろうにね~、なんて笑いながら、色々とお話をしていただきました。それまでの経験、知識、そして長年の生活から編み出された生き方の姿勢。そんなものが感じられるその人の前では、なんてちっぽけな自分なんだろう、そう感じてしまいました。と同時に、プロジェクトごとに集まり、コミットに対する報酬を決める、NPOの働き方に関心を覚えました。コミットが達成されなければ、報酬ももらえない。厳しいけれど新しい働き方。この働き方はもっと広がっていきそうです。
2005.10.01
コメント(0)
全23件 (23件中 1-23件目)
1