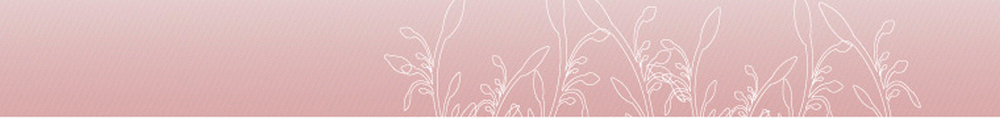2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年01月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

ロスチャイルド家
ロスチャイルド家ヨーロッパで最大の財閥を築いたロスチャイルド家。その事業はワイン、スエズ運河、鉄道、そしてツタンカーメンの発掘にまで及んでいるのだから、驚くばかり。ヨーロッパの5つの国に分散したロスチャイルド家の5人の息子は、国債の発行を手がけていたために、国々の争いを避け、ヨーロッパ全体として国の価値を上げて行くような、EUさながらの仕組みを作っていた。ビジネスをうまく行かせる方法として、このような体制をとっていたのだろう。ロスチャイルド家の三男ネイサンの逸話は興味深い。ワーテルローの戦いの際、イギリスが勝ったにもかかわらず、逆に公債を売りたたき、底値になった時を見計らって買い占めた。さらに興味深いのは、5人の兄弟が誰を出し抜くでもなく、協力し合って訪れる危機に対応していること。その財力や、国の力に大きく影響を及ぼし、市場を変動させるものだった。一つ一つがばらばらに動けばすぐに折れてしまうが、結束してこそ、強い力を発揮できる、とした初代マイヤーの教え。それを守った結果だったという。ロスチャイルド家の強さは、ヨーロッパ中に張り巡らされた、情報網からもたらされる情報とその速さ、結束力、目的に沿った客観的な目を事業に持っていたことだろう。世の中の動きに対して、予測に基づく準備をしておくこと。ストーリーを持っておくこと。まだまだ知らないことだらけだ。
2007.01.26
コメント(0)
-

ダーウィンの悪夢
13日の「世界一受けたい授業」の3時間目。「武田鉄矢流 物語を100倍楽しく読む方法!」で、武田さんが、桃太郎やかさ地蔵などの御伽噺の意外な捉え方の授業をしていた。桃太郎はぐれていた、おじいさんは行きはお地蔵さんが見えていなかったなど、御伽噺の捉え方を変える面白い内容だった。どれだけ目の前のことに想像力を働かせられるか、という点では、この「ダーウィンの悪夢」は現実が想像をはるかに超えている。先日のエンロンに引き続きこちらもドキュメンタリー。普段食べている白身のフライがどこから来たか、どんな社会的影響を持っているのか、なんて想像したことがあるだろうか?この映画に出てくる“白身魚”ナイルパーチは肉食で、もともとヴィクトリア湖にはいなかった。生態系を壊して大繁殖したが、輸出に重宝されたため、人々に漁業での益をもたらした。ヨーロッパが第1位、日本は第2位の輸出先だという。映画館の出口で「問題がいっぱいあるのは分かったけど、ありすぎて何もできないね」との会話が聞こえたが、まさにそんな感じ。まずは知ることが大切なんだ、ということだろう。音楽もなく、とても近い距離で撮影され、次第に本音を聞きだしていく。始めは口の堅かった人が、少しずつ悲しい感情を話してくれる。一人一人が苦しんでいて、でも生きるために生きている状態。世界中のどこでも、魚がダイヤモンドに変わったり、バナナに変わったりするものの、同じことが起こっているという。だれかが得をするように、できているようだ。
2007.01.14
コメント(2)
-
iPhone
以前「個体発生は系統発生を繰り返す」とブログで書いたけれど、こうなるんじゃないかという想像を、スッと横切った「iPhone」。こちらのサイトに「iPhone」の発表のことが掲載されています。・Macworld 2007 - たっぷり見せます、携帯電話を変える「iPhone」 - 基調講演後編・Macworld 2007 - Appleからコンピュータが消えた日 - 基調講演前編PDAのようなものなのだけど、ポイントはソフト(iTunes)が使いまわせること。iPodの時も、同様のハード機器は既にあったのに、これほどの広まりを見せたのは、アップル製品であれば共有できる、ソフトがあったから。そういえば、一度お蔵入りしかけたiPod nanoくん。最近面白くなり復活です。
2007.01.13
コメント(2)
-

エンロン-巨大企業はいかにして崩壊したのか?
朝出勤したら、会社が破綻したから、荷物をまとめてすぐに出て行ってくれと言われたら。退職直前に、自社株購入で積み立てていた年金が紙切れ同然になったら。エンロン-巨大企業はいかにして崩壊したのか?この映画は、エンロンの元幹部や、フォーチュン紙の記者、アナリストらの証言によるドキュメンタリー。内部の視点による生々しい心理状態や、この大きな企業に煙に巻かれていた、外部の視点などが取り入れらており、引き込まれてしまった。エンロン社のキャッチフレーズは「Ask Why」。既成の概念を疑い、常に知恵(と金と権力)を絞って売上げを上げてきた。業績が上がると社内は生き生きと活気付く。一方、会社に貢献しないと判断された人が年に15%も解雇される人事制度や、モラルより売上げ、安定より冒険を重視する姿勢があり、社内も弱肉強食、マッチョカルチャーとなっていたそうだ。映画の中でカリフォルニアの停電の話が出てくるのだけれど、(参考記事:エンロンが仕掛けた「自由化」という名の金権政治)惨事を見てトレーダー同士が交わす会話に背筋が凍る。皮肉なことに「Ask Why」は社内では行われなかった、または気付いた人は辞めてしまったのかもしれない。嘘がゆきだるま式にふくらみ、嘘に対する感度が回数を重ねるごとに鈍っていく。一方、人はやっていることと言っていることの矛盾に、精神が支障をきたしてくる。人は誰でもこのような心理状態に陥る可能性があるということ。人ごとではないと思う。
2007.01.08
コメント(2)
-
初めての…
ホットヨガの体験に行ってきました。理由は年末に激しくヨガを勧められたことと、正月にたっぷりと蓄えてしまった体に危機感を覚えたから、という特に主体性のないもの。ホットヨガはその名の通り、温められた部屋で行うヨガなのですが、入った途端、もわっとした熱気に包まれ、思わず「暑いですね」というと、「今日は今年初めの回なので寒い方なんです」との答え。行く前までは正直、多くの人に広まっているんだし、ストレッチの一種だろう、くらいの甘い認識しかなかったのです。やってみると体は動かないし、足はプルプル……。終わってからもしばらく足はわなないていました。これで、かなり本気でヨガに取り組むことに。体験してみると、もっと知りたいことや欲しい環境も浮かんできたので、他の教室も行ってみることにしました。最近、知らないことを知ることが多かったけど、自分の体についてもいえるんだなぁ。
2007.01.06
コメント(0)
-
振り返ってみる
年末に大掃除をしていたら、2005年の自分年表が出てきました。1年間のやったこと、思い出深いものをピックアップしたもの。おぼろげながら、書き出した記憶がある!こりゃ面白い、ということで、2006年版も作ってみました。2005年のテーマは“広げる”。多い時で1ヶ月に100人以上の人と会い、その中からずっと付き合っていきたい大切な人達にも出会いました。見返してみると、コーチングを始め、自分の価値観が明確になったことがきっかけでした。2006年のテーマは“深める”多くの人と出会うと、不思議と会うべき人はその後もどこかで出会い、つながるもの。人との関係を“深める”ことに焦点を置くことにしました。半年かけて準備した教育フォーラムが終了したのが、ちょうど1年前。そして4月から環境が変わり、情報のインプットとアウトプットの、バランスのとり方についても考えた年でした。あまり変わりばえのしない道を歩いていたと思っていたのに、ふと振り返ると以前いた場所がはるか向こうに見えるときがある。そして1年あれば何でもできちゃうものだ。これから今年の行動計画を作ろう。
2007.01.03
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1