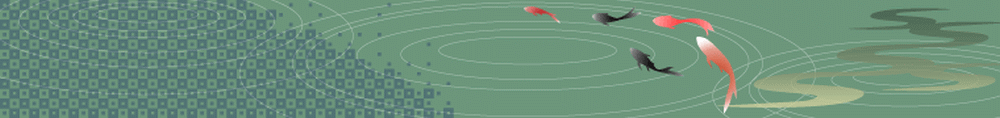PR
X
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 民族楽器について(63)
カテゴリ: 沖縄関係
「音の基準」
ある一定の〔絃長〕又は〔筒(竹筒)〕から発する音高を基準「基準音」とし、その基準音の長さを四分の三、又は二分の三に分割し、新音を作ります。
基準絃音の四分の三弦音は、元音から完全四度低い音です。
基準絃音の二分の三絃音は、元音から完全五度高い音になります。
さらに、完全五度低+完全四度高=完全九度となります。
これはオクターブの関係にあるという事ですね。
三線の場合、
中弦(真ん中の絃)基準と考えると、
その二分の三倍の長さの絃音が女絃(高音絃)の音
「本調子」調絃(ちんだみ)「C-F-C」(中間調律)となります。
高音域調律「D-G-D」
低音域調律「A-D-A」
しかしこんな理論がありました。
『基準の長さの弦または管を三分して、その一を現ずると(三分損一)、完全五度上野音が得られ、その長さを再び三分して一を加えると(三分益一)、完全四度下の音、すなわち最初の基準の音の長二度上の音が得られる。この三分損一と三分益一を交互にくり返すので、三分損益の法と呼ばれる。』(小泉文夫著「日本の音」参照)
この方法ですと、「三分損一と三分益一を交互に行って、基準音より高音を順に作り出していく事で音階を作る」と、書いてあります。
しかし、この方法では無限にオクターブの関係になる2音が発生することはありません。
三線のちんだみ(調絃)は「三分損益の法」という厳密な音楽理論を用いたものではなく、「三分損一」と「三分益一」で高音・低音が得られ、その高低がオクターブとなり、三絃の調律が可能になります。
この三分損一と三分益一による完全五度高・完全四度低の音程作りはピタゴラスによっても確認されており、ピタゴラス音階の基礎ともなっています。
東洋西洋にある3本絃楽器の調律にこの方法を使う事は極めて自然なことなのかもしれませんね。
ある一定の〔絃長〕又は〔筒(竹筒)〕から発する音高を基準「基準音」とし、その基準音の長さを四分の三、又は二分の三に分割し、新音を作ります。
基準絃音の四分の三弦音は、元音から完全四度低い音です。
基準絃音の二分の三絃音は、元音から完全五度高い音になります。
さらに、完全五度低+完全四度高=完全九度となります。
これはオクターブの関係にあるという事ですね。
三線の場合、
中弦(真ん中の絃)基準と考えると、
その二分の三倍の長さの絃音が女絃(高音絃)の音
「本調子」調絃(ちんだみ)「C-F-C」(中間調律)となります。
高音域調律「D-G-D」
低音域調律「A-D-A」
しかしこんな理論がありました。
『基準の長さの弦または管を三分して、その一を現ずると(三分損一)、完全五度上野音が得られ、その長さを再び三分して一を加えると(三分益一)、完全四度下の音、すなわち最初の基準の音の長二度上の音が得られる。この三分損一と三分益一を交互にくり返すので、三分損益の法と呼ばれる。』(小泉文夫著「日本の音」参照)
この方法ですと、「三分損一と三分益一を交互に行って、基準音より高音を順に作り出していく事で音階を作る」と、書いてあります。
しかし、この方法では無限にオクターブの関係になる2音が発生することはありません。
三線のちんだみ(調絃)は「三分損益の法」という厳密な音楽理論を用いたものではなく、「三分損一」と「三分益一」で高音・低音が得られ、その高低がオクターブとなり、三絃の調律が可能になります。
この三分損一と三分益一による完全五度高・完全四度低の音程作りはピタゴラスによっても確認されており、ピタゴラス音階の基礎ともなっています。
東洋西洋にある3本絃楽器の調律にこの方法を使う事は極めて自然なことなのかもしれませんね。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[沖縄関係] カテゴリの最新記事
-
新築記念に唄われる歌 2009年03月30日 コメント(4)
-
懐かしき故郷(沖縄民謡) 2008年06月22日
-
かいされー(沖縄民謡) ジントヨー 2008年06月15日 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.