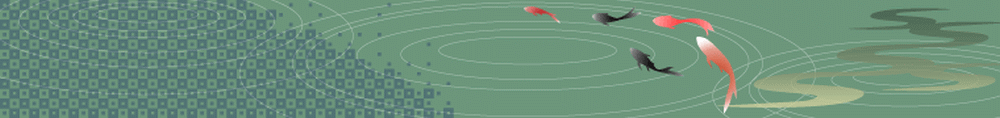PR
X
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 沖縄民謡(152)
カテゴリ: 沖縄関係
「まつぃんがねーゆんた」 甲乙交互に謡い合い〔 〕は合いの手 三拍子
甲、松金(まつぃんがねー)ぬ 〔ヒハーヒ〕舞富名(まいふなー)ぬ 〔ヒヤサー〕 家(やー)建てぃや 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈松金と言う マイフナー(偉く賢い者・男性。現在では「お利口さん」と解釈されています)が居て、家を新築した。(ヤラムツィムツァイとは、大器晩成の意)〉
乙、いみしゃから 〔ヒハーヒ〕 穴掘(アナフ)るぃ家(ヤー)どぅ 〔ヒヤサー〕 やだそぅぬ〔ヤラムツィムツァイ〕
〈幼少の時から(穴堀るぃ家)掘建て小屋で生活していたが〉
甲、くゆさから 〔ヒハーヒ〕 掘(フ)るぃ建てどぅ 〔ヒヤサー〕だそぅぬ 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈小さい時から掘建て小屋で生活していたが〉
乙、内家戸(ウツィヤドゥ)や 〔ヒハーヒ〕つぃにふ家戸(ヤドゥ)〔ヒヤサー〕 やだそぅぬ 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈内側の戸は、葦(アシ)の戸であったそうな〉
〈外側の戸は、茅(カヤ)の戸であったそうな〉
乙、身形(ならふどぅ)ぬ 〔ヒハーヒ〕丈きふどぅぬ 〔ヒヤサー〕 いくだら 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈身形(みなり)や背丈が伸びて、成長していった〉
甲、於茂登山(ウムトゥヤマ) 〔ヒハーヒ〕 照(ティ)らすぃ頂 (ツィズィ) 〔ヒヤサー〕 登(ヌブ)りょうり 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈於茂登山(石垣にある沖縄県下一の高山標高525m)に登り〉
乙、キャン木ば 〔ヒハーヒ〕 白身(シルミ)じょう木ば 〔ヒヤサー〕 出(イ)だしょうり 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈キャン木の白い部分の木を切り出し〉
甲、時(トゥクィ)いらな 〔ヒハーヒ〕 暇(ピマ)いらな 〔ヒヤサー〕 家持(ヤーム)ちき 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈無駄な時間を掛けず、休憩もせず、家に持ち帰り〉
乙、島々(スィマズィマ)ぬ 〔ヒハーヒ〕 村々ぬ 〔ヒヤサー〕 内(ウツィ)から 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈島々・村々の中から選ばれた〉
〈大工達は、腕が冴え、見立ても良く〉
乙、大工主(ダイクシュ)ぬ 〔ヒハーヒ〕 手勝(ティマサ)りゃーぬ 〔ヒヤサー〕 考(カンガ)いぬ 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈大工達の腕利きの創意工夫によって〉
甲、五(イツィ)ぬ貫(ヌクィ) 〔ヒハーヒ〕 七(ナナ)ぬ貫(ヌクィ)ぬ 〔ヒヤサー〕 くい建てぃよぅり 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈五つの貫木を入れ、七つの貫木をいれ、建てた家は〉
〈内側の戸は、キャン木の上質材で造り(いぬ槙・マキ)〉
甲、外家戸(フカヤードゥ)や (ヒハーヒ〕 白身上質(シルミジョウシ) 〔ヒヤサー〕 はい建て 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈外側の戸は、イーク材の上質材で造り〉
乙、うんから 〔ヒハーヒ〕 まつぃんがねーや 〔ヒヤサー〕 名通(ナトゥ)らり 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈それから、松金の名前は、世間に轟いた。(広まった)〉
この唄は、八重山の新築祝いの席で唄われています。
【唄の背景】
石垣島の大川村に、「松金」と言う若者が居た。
16歳で両親と死に別れ、75歳の祖母と弟二人、妹二人の六人家族で、大変貧しい暮らしをしていた。
「ムイアッコン」と言う、畑主が掘り残した芋を捜す、そんな生活(当時の風習)だった。
ある日、「松金」は「嘉手川松・筑登之」の畑に入って居る所を見つかり捕えられる。
有らぬ疑い(麦・粟等も盗む)をかけられ、決め付けられムチ打ちに遭う。
血だらけになりながら、家に帰り、祖母に話した。
すると祖母は、
「その嘉手川が生きてる間に、勉強して出世して、頭職になれ」
の言葉に従い、教練所(役人になる為の学校)の下人(雑用係)として働きながら、そこで教本を譲り受け、作業の合間に聞こえる授業に聞き耳をたてて、読み書きから計算を必死に覚えていき、下級役人に合格。
その後も昇格試験を片っ端から受けて、
とうとう最高官の頭職になった。
その松金は、家族のために家を新築する。
家も完成し、新築の祝いと頭職昇進の祝賀会を開く事になり、その席上で、
「嘉手川松・筑登之」は存命かを確認させた。
嘉手川は生きていた。
祝賀会に招き入れ、会場まで案内し、上座に座らせて、感謝し御礼を述べた。
「頭職まで昇進できたのは、貴方様のおかげ」
「ムイアッコンのおかげ」
と、公衆面前で、その経緯を話した。
会の献立は全て芋料理。
「嘉手川松・筑登之」は、即興歌を唄わせて欲しいと、願い出て「松金」の生い立ちを唄い「松金ゆんた」として後、新築祝いの席で、必ず謡われる様になった。「1791年」作
この時代、仕官役人に成る事は大変難しく、新築出きる様になるまでは、どの人も苦労を重ねた。
その労をねぎらい唄われた。
三拍子であることも、唄いやすい理由の一つかもしれませんね。
【時代背景】
この時代、士族・平民の差が、かなりあった。
男性士族は、黄色の鉢巻。
着物は黒朝衣、カンザシは銀製もしくは べっ甲製。
帯は赤・黄の緞子。
白足袋に草履下駄・竹皮の草履。
男性平民は、鉢巻なし。
着物は黒木綿・黒苧麻無地・丈が短い。
カンザシは真鍮製。
帯はミンサー。
下駄・草履・雨の日でも傘は許されず、褌は黒。
特別の時のみ、アダン葉の草履。
ふだんは裸足。
見るだけで、身分が判る様になっていました。
甲、松金(まつぃんがねー)ぬ 〔ヒハーヒ〕舞富名(まいふなー)ぬ 〔ヒヤサー〕 家(やー)建てぃや 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈松金と言う マイフナー(偉く賢い者・男性。現在では「お利口さん」と解釈されています)が居て、家を新築した。(ヤラムツィムツァイとは、大器晩成の意)〉
乙、いみしゃから 〔ヒハーヒ〕 穴掘(アナフ)るぃ家(ヤー)どぅ 〔ヒヤサー〕 やだそぅぬ〔ヤラムツィムツァイ〕
〈幼少の時から(穴堀るぃ家)掘建て小屋で生活していたが〉
甲、くゆさから 〔ヒハーヒ〕 掘(フ)るぃ建てどぅ 〔ヒヤサー〕だそぅぬ 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈小さい時から掘建て小屋で生活していたが〉
乙、内家戸(ウツィヤドゥ)や 〔ヒハーヒ〕つぃにふ家戸(ヤドゥ)〔ヒヤサー〕 やだそぅぬ 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈内側の戸は、葦(アシ)の戸であったそうな〉
〈外側の戸は、茅(カヤ)の戸であったそうな〉
乙、身形(ならふどぅ)ぬ 〔ヒハーヒ〕丈きふどぅぬ 〔ヒヤサー〕 いくだら 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈身形(みなり)や背丈が伸びて、成長していった〉
甲、於茂登山(ウムトゥヤマ) 〔ヒハーヒ〕 照(ティ)らすぃ頂 (ツィズィ) 〔ヒヤサー〕 登(ヌブ)りょうり 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈於茂登山(石垣にある沖縄県下一の高山標高525m)に登り〉
乙、キャン木ば 〔ヒハーヒ〕 白身(シルミ)じょう木ば 〔ヒヤサー〕 出(イ)だしょうり 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈キャン木の白い部分の木を切り出し〉
甲、時(トゥクィ)いらな 〔ヒハーヒ〕 暇(ピマ)いらな 〔ヒヤサー〕 家持(ヤーム)ちき 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈無駄な時間を掛けず、休憩もせず、家に持ち帰り〉
乙、島々(スィマズィマ)ぬ 〔ヒハーヒ〕 村々ぬ 〔ヒヤサー〕 内(ウツィ)から 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈島々・村々の中から選ばれた〉
〈大工達は、腕が冴え、見立ても良く〉
乙、大工主(ダイクシュ)ぬ 〔ヒハーヒ〕 手勝(ティマサ)りゃーぬ 〔ヒヤサー〕 考(カンガ)いぬ 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈大工達の腕利きの創意工夫によって〉
甲、五(イツィ)ぬ貫(ヌクィ) 〔ヒハーヒ〕 七(ナナ)ぬ貫(ヌクィ)ぬ 〔ヒヤサー〕 くい建てぃよぅり 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈五つの貫木を入れ、七つの貫木をいれ、建てた家は〉
〈内側の戸は、キャン木の上質材で造り(いぬ槙・マキ)〉
甲、外家戸(フカヤードゥ)や (ヒハーヒ〕 白身上質(シルミジョウシ) 〔ヒヤサー〕 はい建て 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈外側の戸は、イーク材の上質材で造り〉
乙、うんから 〔ヒハーヒ〕 まつぃんがねーや 〔ヒヤサー〕 名通(ナトゥ)らり 〔ヤラムツィムツァイ〕
〈それから、松金の名前は、世間に轟いた。(広まった)〉
この唄は、八重山の新築祝いの席で唄われています。
【唄の背景】
石垣島の大川村に、「松金」と言う若者が居た。
16歳で両親と死に別れ、75歳の祖母と弟二人、妹二人の六人家族で、大変貧しい暮らしをしていた。
「ムイアッコン」と言う、畑主が掘り残した芋を捜す、そんな生活(当時の風習)だった。
ある日、「松金」は「嘉手川松・筑登之」の畑に入って居る所を見つかり捕えられる。
有らぬ疑い(麦・粟等も盗む)をかけられ、決め付けられムチ打ちに遭う。
血だらけになりながら、家に帰り、祖母に話した。
すると祖母は、
「その嘉手川が生きてる間に、勉強して出世して、頭職になれ」
の言葉に従い、教練所(役人になる為の学校)の下人(雑用係)として働きながら、そこで教本を譲り受け、作業の合間に聞こえる授業に聞き耳をたてて、読み書きから計算を必死に覚えていき、下級役人に合格。
その後も昇格試験を片っ端から受けて、
とうとう最高官の頭職になった。
その松金は、家族のために家を新築する。
家も完成し、新築の祝いと頭職昇進の祝賀会を開く事になり、その席上で、
「嘉手川松・筑登之」は存命かを確認させた。
嘉手川は生きていた。
祝賀会に招き入れ、会場まで案内し、上座に座らせて、感謝し御礼を述べた。
「頭職まで昇進できたのは、貴方様のおかげ」
「ムイアッコンのおかげ」
と、公衆面前で、その経緯を話した。
会の献立は全て芋料理。
「嘉手川松・筑登之」は、即興歌を唄わせて欲しいと、願い出て「松金」の生い立ちを唄い「松金ゆんた」として後、新築祝いの席で、必ず謡われる様になった。「1791年」作
この時代、仕官役人に成る事は大変難しく、新築出きる様になるまでは、どの人も苦労を重ねた。
その労をねぎらい唄われた。
三拍子であることも、唄いやすい理由の一つかもしれませんね。
【時代背景】
この時代、士族・平民の差が、かなりあった。
男性士族は、黄色の鉢巻。
着物は黒朝衣、カンザシは銀製もしくは べっ甲製。
帯は赤・黄の緞子。
白足袋に草履下駄・竹皮の草履。
男性平民は、鉢巻なし。
着物は黒木綿・黒苧麻無地・丈が短い。
カンザシは真鍮製。
帯はミンサー。
下駄・草履・雨の日でも傘は許されず、褌は黒。
特別の時のみ、アダン葉の草履。
ふだんは裸足。
見るだけで、身分が判る様になっていました。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[沖縄関係] カテゴリの最新記事
-
懐かしき故郷(沖縄民謡) 2008年06月22日
-
かいされー(沖縄民謡) ジントヨー 2008年06月15日 コメント(2)
-
ざ-っとの続きです。 2008年05月04日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.