2008年09月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
デトロイト・メタル・シティ
大分の農家の息子がおしゃれ系のミュージシャンを夢見て上京したけど心ならずも悪魔系のバンドのリーダーとして活躍してしまい葛藤する様子を描いたコメディ映画「デトロイト・メタル・シティ」を見てきました。 原作はヒットしているコミックスだそうですが、私は読んでいません。8月23日封切りで、30日間の興行収入が20億円突破だそうです。6週目の日曜日、朝9時30分(日曜の朝そんな時間に誰が映画見に行く?)ではさすがにすいてました。客のほとんどが若者で、おじさん比率がかなり低い映画です。 小沢健二あたりに憧れるおしゃれ系ミュージシャンになりたい根岸崇一(松山ケンイチ)、Mステに出るのが夢のミーハーの和田真幸(細田よしひこ)、不気味なブルマオタクの西田照道(秋山竜次)の3人の悪魔系ヘビメタバンド「デトロイト・メタル・シティ」としての活動と実生活の落差が、映画の基本的な見せ所となっています。特にリードヴォーカルのヨハネ・クラウザー2世と根岸崇一の対比・落差がかなり戯画的に描かれています。 それを受けて、大学時代、人に夢を与える音楽活動をやりたいと言って、おしゃれ系のミュージシャンを目指し、大学卒業後街頭で歌うが見向きもされず、しかし自分の本意ではない悪魔系バンドでは大ヒットしている根岸のやりたいこと・なりたい自分とやってること・現実の自分のギャップへの悩みが基本的なテーマとなります。ただ、映画の最初の段階から繰り返される根岸のスローガン「No Music No Dream」(音楽で夢を与えたい)と、デス・レコーズの新人募集のスローガンが同じことに示唆されているように、たくさんの熱狂的なファンを獲得している悪魔系バンドもまた人に夢を与えているわけで、自己イメージの問題はあるものの根岸の場合、解決の道は見出しやすそうな気はしますが・・・ 根岸の恋のライバルになるおしゃれ四天王の1人アサトヒデタカも、ちょっと・・・。代官山のおしゃれなカフェをプロデュースしてる人が、雑誌記者の相川由利(加藤ローザ)を口説くのにデートの行き先がとしまえん(でしたよね?)って・・・。意外にこの人にもアイデンティティ・クライシスがあるかも。僕がやりたいのはこんな気取ったプロデュースじゃない、とか。 その点、表裏のギャップが出て来ないのが、デス・レコーズ社長(松雪泰子)。これだけの壊れっぷりで裏がないってすごい。タバコは自分の舌や人の額で消す、根岸を殴る、蹴る、部屋はめちゃめちゃに破壊してスプレーで落書きすると、やりたい放題。最初の事務所でのシーンではわざとらしく聞こえた高笑いも、後半になるに従い、コンサートのバックではピタリとはまってきます。(あぁ来週「容疑者Xの献身」を見てこの松雪泰子の高笑いがダブらないでしょうか・・・) これに対して、根岸の憧れの相川由利(加藤ローザ)も裏がないんですが、こちらは天然ボケというか・・・。音楽雑誌の記者やってるんだから、少しは状況判断できるだろうに、コンサートの真っ最中に舞台に駆け上ってリードヴォーカルに「根岸君でしょ」なんて聞く?(こっちは「天国はまだ遠く」の千鶴もそういうタイプだからいいけど) クラウザーを「クラちゃん」と呼ぶ母親やバンド仲間やファンのメッセージに背中を押されて、デトロイト・メタル・シティも人に夢を与えている、デトロイト・メタル・シティにしか与えられない夢があると気づいた根岸/クラウザーがコンサート会場に駆けつけて悪魔バンド勝負に勝った後、突然クラウザーの姿で「甘い恋人」を歌い出してファンの頭を抱えさせ、ここでイメージを崩壊させて終わるかと思ったら、また社長の一撃で悪魔バンドに戻りと、ラストでも揺れを見せています。方向はもう見えたはずなのに、でも悟りきれず、しかし捨てられない。この葛藤が今後も続くことを示唆しています。まぁ、自己イメージを、頭ではわかっても、そう簡単には変えられないということでしょうね。 ラストシーンにも、エンドロールの後のクラウザー信者の叫びにも、そのあたりが現れているように感じます。 根岸/クラウザーの両面が描かれ、時間的には根岸サイドの悩みの方が長い感じですが、映像としてはクラウザーサイドのバンド演奏(ただ、会場のファンが今ひとつ陶酔してない感じでテンション下がりますが)と、デス・レコーズ社長の壊れっぷりの方が遥かに魅力的です。 ところで、最初の頃はクラウザーと根岸の間に化粧を落としたりのシーンを強調していましたが、遊園地のトイレでは根岸が手ぶらで入ってクラウザーが出てくるの、これ「変身」でしょうか。別にいいですけど。
2008年09月28日
コメント(0)
-
言えない秘密
台湾のポップスタージェイ・チョウ主演・監督の青春恋愛映画「言えない秘密」を見てきました。8月23日封切りで6週目土曜日、東京では新宿武蔵野館単館上映・一番小さなスクリーンで27・28日は入場者全員にフィルムしおりプレゼント付きではありますが、8割くらいの入りでした。 フィルムしおりって、予告編のフィルムの裁断なんですね。私はシャオユーがシャンルンに「あなたが好き」って言ってるシーンが当たりました。本編では同じシーンの字幕が「私はあなたが好き」でしたから・・・ 音楽学校の転入生シャンルン(ジェイ・チョウ)が、古い演奏室でピアノを演奏するミステリアスな女学生シャオユー(グイ・ルンメイ)とたちまちのうちに恋に落ち、学校にたまにしか現れないシャオユーを心配し、喘息によいと父から聞いて林檎を毎日1個持って登校するがなかなか会えずに林檎が15個もたまり、そのことからせっかく久しぶりに会えたシャオユーと口げんかになり、仲直りしようとして待ち合わせた演奏室にシャンルンに思いを寄せるチンイー(アリス・ツォン)が先に演奏室に現れてシャンルンにキスしたところをシャオユーが見てシャオユーがそのまま学校から姿を消し、2人の運命は・・・というようにストーリーが展開します。 前半は、甘い甘いひたすら甘いラブストーリーです。互いに一目惚れに近い形で恋に落ちてしまうのは、もう少し序盤を作れよと言いたくなりますが(まぁ後からそれが宿命という説明がなされますけど)、それは映画だからねで納得はできます。 おじさんの目からは、何と言ってもグイ・ルンメイです。少しはにかんだ笑顔の愛らしさ、キュート!チャーミング!それだけで多少のことは、いやかなりの部分まで許してしまえます。(今にして、百恵ちゃんに熱狂したおじさんたちの気持ちが少しわかるような・・・) 基本的にこの映画は、映像部分ではセピア色というか黄褐色の柔らかめの光に満ちた映像と爽やかな光の映像の切り替え、音楽部分ではピアノ演奏のすばらしさが売りだと思います。その美しい雰囲気が、前半ではグイ・ルンメイの笑顔と、甘いラブシーンとマッチしてとてもいい気持ちで見ることができます。とりわけ2人の連弾演奏のシーンは見ている側まで幸福感いっぱいになれます。もちろん、気恥ずかしくなる人もいるでしょうし、すねる人もいるでしょうけど。 ところが、後半、シャオユーの失踪あたりから話は暗転し、そして終盤は、どう言えばいいでしょう。SFというか、オカルトというか。私の感じではオカルトですが・・・。公式サイトにも「この秘密は決して明かさないでください」と書かれていますから、何のことかは書きませんけど。 シャンルンの父親が、音楽学校の教師で、それも20年前から勤務しているのに、シャンルンが最終学年から転入してくるのは何故でしょう。ピアノバトルの相手(ピアノ王子)は先輩と紹介されていたのにシャンルンが1年とたたずに卒業する(だから最終学年と判断しました)のは? 秘密を明かさないと、見てない人には何のことかわかりませんが、それにしても・・・。シャオユーは家の鍵が替えられていて入れないと言っていたのに、母親がシャオユーは今寝ているとか今音楽を聴いているとか言うのは何故? シャオユーの姿が見えないはずのチンイーがピアノバトルの場面でシャオユーと会話してるのは何故? 終盤に明かされる秘密を知ると、前半不思議に思えたことの多くがなるほどと思いますが、同時にそれと同じくらいじゃあこれはどうして?と思うことが増え、頭が混乱します。 そういうことは気にせず、特に前半のピアノ演奏とグイ・ルンメイの笑顔が見られれば十分と思ってみた方がいいかなと、おじさんとしては思います。
2008年09月27日
コメント(2)
-
シャカリキ!
自転車ロードレースに青春を賭ける高校生たちのスポーツ根性物「シャカリキ!」を見てきました。原作は往年のヒットコミックスだそうですが、私は全然読んでいません。 宣伝ぶりと内容からして200名規模のスクリーンの映画と思いますが、588席の新宿ミラノ2では、封切り2週目平日夜ですが、1割も入っていない惨状でした。 名門だが、エース指名に不満を持ったナンバー1選手ユタこと由多比呂彦(鈴木裕樹)が転校し有力選手がそれに追随したために凋落し、インターハイ出場さえ危うくなった亀が丘高校自転車部に、子どもの頃から自転車で坂を登るのが好きな「坂バカ」野々村輝(遠藤雄弥)が入学、亀が丘高校自転車部のエース鳩村大輔(中村優一)らとぶつかりながら、ユタの加入により抜群の強豪となった鳳帝高校の打倒を目指すというストーリーのスポーツ根性物です。 自分がユタに勝つことしか考えないテルのおかげで、亀が丘高校はインターハイで失格、自転車部は廃部と、散々の序盤から、もう一度ユタと戦いたいというテルと他の部員やマネージャー、監督らが再起を誓い、特訓とチームワークで戦うことを学んでいきます。見せ場は最後の「石渡山ロードレース」。ここで、アシストを申し出る鳳帝高のメンバーに、アシストは要らない、これはオレのレースだと言って最初から先頭をぶっちぎるユタと、5人が一体となって献身的に風よけとなってレースを進める亀が丘高校自転車部という展開になります。 見終わっての一番の感想は、スポーツ根性物は得だなということ。序盤から若いタレントのぎこちない台詞、不自然な間が続いても、最後のロードレースの展開1本で感動を与えられる、これぞスポーツ根性物の強みというしかありません。国内で負け知らずの敵役ユタに個人の力では勝てない亀が丘高校自転車部がチームワークで闘いを挑むという展開から、スポーツ根性物なら結果は予測されますが、それでも1人1人がそれぞれの個性を生かしてチームのために献身的に闘う姿はやはり打たれます。ラストには、自分のことしか考えなかったテルもチームのために闘う姿が描かれ、単純ではありますが、素直に感動してしまいました。 でも、亀が丘高校自転車部の特訓、しばらくは自転車に乗らずに相撲をやらせたりエアロビクスをやらせたり、スポーツ根性物には実はよくあるパターンですが、半年先に試合があるならともかく試合まで1ヵ月の設定でそんなのあり? 冒頭と中盤でテルの子ども時代の自転車特訓の映像で自転車が空中に舞いあがるシーンは、おいおいE.T.かよと思いますし・・・ 自転車ロードレースのルールは知りませんが、自転車を担いで走ったり、仲間がサドルを押したりして失格にならないんでしょうか・・・ いろいろ疑問を感じますし、前半は役者の演技とかしっくりきませんが、最後のロードレースで気分盛り上げてスッキリできますので、後味はいいと思います。
2008年09月18日
コメント(0)
-
闇の子供たち
タイでの子どもの臓器移植や児童買春のために行われている児童人身売買をテーマとした映画「闇の子供たち」を見てきました。 8月2日封切りで上映館を拡げながらの7週目祝日朝一番でしたが6割程度の入りでした。重い堅いテーマの作品としては大健闘でしょう。 「日本新聞社」(タイで自己紹介するシーンでは”Japan Times”と言ってましたが、大丈夫でしょうか)バンコク支局の記者南部浩行(江口洋介)が、日本人の子どもの心臓移植手術のための臓器提供者がタイの子どもで生きたまま臓器をえぐり取られる(殺される)ことを掴み、取材の過程で知り合った社会福祉センターのボランティア音羽恵子(宮崎あおい)らも絡んで、手術を受ける子どもの親やタイの人身売買組織に接触し、事実の解明や人身売買の阻止に向けて行動していくストーリーを軸として、いくつかのグループの物語が綴られていきます。 まず冒頭シーンから登場するチェンライの売春宿に売られてエイズに罹りゴミ袋に入れられて捨てられる少女ヤイルーンと、同じ頃人身売買組織に買われた妹のセンラーら人身売買された子供たち。ゴミ袋から自力で脱出したヤイルーンが故郷にたどり着いたときには、この映画で一番の安堵を感じましたが、ヤイルーンが呼びかけ続けるセンラーの運命、そしてヤイルーンのその後の運命には涙します。テーマから考えればそう描くことになるでしょうけど、この2人は救って欲しかったなと思います、感情的には。水遊びのシーンが挿入されているのがあまりに切ない。 続いて、通っていた子どもの1人アランヤーが売られたと知りその救出のため奔走するタイの社会福祉センターの所長ナパボーン(プライマー・ラッチャタ)と職員たち。この中で、最初は日本人ボランティアの音羽が浮いていますが、直情径行の音羽が囚われた子どもの救出のために行動していく中でまわりの職員たちにとけ込んでいきます。 そして、メインストーリーを担う南部ら日本新聞社の記者と、現地で雇われた隠し撮り専門のフォトグラファー与田博明(妻夫木聡)ら取材グループ。移植手術のために殺されるタイ人の子どもを救うために手術を受ける子どもの親を翻意させようと罵る音羽に対し、目の前の1人を救ってもシステムがそのままなら次の子どもが殺されるだけだ、事実を明らかにして見たことを書くのが自分たちの使命だと断言するのですが・・・ 日本では子どもの臓器移植ができず、アメリカでは順番待ちで間に合わず、タイでの心臓移植でしか救えない放置すれば8ヵ月の命の8歳児を持つ梶川夫婦(佐藤浩市、鈴木砂羽)。もちろん、5000万円の手術費用を出せる大企業の課長です。 社会福祉センターのチェンライでの代理人でありながら人身売買組織と通じるゲーオや警察に潜む密告者ら一筋縄ではいかない/裏切り者のタイ人たち。 そして、自らも人身売買の被害者だった過去のトラウマを持つ人買いチット(プラパドン・スワンバーン)。 前半は、南部ら取材グループと音羽の対立から、目の前の命の救出か真実の報道かの選択がテーマに見えます。取材グループも苦悩を感じつつも、議論は圧倒的に取材グループの方に説得力があり、音羽の行動はあまりに子供じみた自己満足にしか見えません(現に目の前の命を救うという観点でも、梶川夫婦を罵っても事態は何一つ改善しないわけですし)。この争いは明らかに勝負あったと見えるのですが・・・ しかし、意外にも後半、売春宿のゴミ出しを張り続けた音羽が危険を顧みず飛び出してゴミ袋からアランヤーを救出し、警察内の密告者の情報で社会福祉センターの職員が暗殺された後集会で事実をアピールするナパボーンの決然とした態度、警察の摘発といった流れで、むしろ音羽側に正義がほほえみます。このことを決定づける衝撃の事実も登場しますし。 自己満足的行動をとっていた自分探しのお嬢さんに正義が微笑み、着実な大義を実行しようと大人の対応をとっていた記者が敗北し、手術を受ける子どもの親も苦渋の選択を迫られ、人身売買組織の人買いも被害者としての過去を持つというように、様々なことを考えさせられ、簡単には答えが出ない問題提起がなされています。どうにも救いようがなく悪いのは人身売買組織のボスと児童買春する客(欧米人ともちろん日本人)くらいです。単純な勧善懲悪ではなく、スッキリしませんが、深い。罪深い。業が深い。 さすがにあんまりなネタバレなので明言しませんが、ラスト間際に登場する衝撃の事実は、しばらく茫然とし、見間違いかとさえ思ってしまいます。このラストには、日本人(男)にはいい格好させないという制作側の執念をも感じました。 ただ、南部の最後の行動と、ゲーオがすぐに逃げずに集会場にとどまり続けたことについては、見ていて疑問を感じました。 非常に重いテーマですが、映像的には予想したほど生々しい(グロテスクな)シーンはなく、ドラマとしてのできでもけっこういい線を行っていると思います。上映館を増やして2009年1月までの上映が決まっているそうですが、こういう映画にたくさんの人が足を運ぶということは、とてもいいことだと思います。
2008年09月15日
コメント(0)
-
イントゥ・ザ・ワイルド
裕福な家庭に生まれ大学を優秀な成績で卒業した青年クリス・マッカンドレスが放浪の果てにアラスカで餓死するまでを描いた青春映画「イントゥ・ザ・ワイルド」を見てきました。 封切り2週目日曜で朝一番でもわりと客が入っていました。 クリス(エミール・ハーシュ)は大学卒業とともにアパートを引き払い1人で放浪の旅に出ます。在学中の親からの仕送りでたまった2万4000ドルを慈善団体に寄付し、クレジットカードや持ち金を焼き捨てて、最初はヒッチハイクの旅に出て、その後農場等で働いて金を貯めては次の旅に出て行きます。 この放浪の動機は、映画の流れとしては父親への反発が強調されています。別居した正妻と離婚できずに母と結ばれてクリスと妹が生まれたけど父(ウィリアム・ハート)と母(マーシャ・ゲイ・ハーデン)の諍いが続き、子どもたちの行動も厳しく抑圧し続けてきた父に、クリスは大学卒業時に、新車を買ってやるという父親に対して新車は要らない、何も要らないと反発し、その後すぐ行方をくらまします。妹(ジェナ・マローン)のナレーションでは、兄が放浪を始めたのは父への反発だけではないと、フォローし、兄は子どもの時から放浪癖があったと述べてはいます。しかし、放浪中に火をたくシーンで、クリスが、子どもの頃にバーベキューの火をつけさせてくれと言ったら父親にダメだと拒否された会話を1人2役で再現しているのを見ると、映画としては父親への反発をかなり重要な要素と位置づけていることが明らかです。大学卒業した後までこだわり続けるかねと思いますが、三つ子の魂百まででしょうか。アラスカに持っていった本がトルストイの「家庭の幸福」というのも・・・ 公式サイトでは「ジブンをぶっこわす旅」とか書いてますから、自分探しの旅ということでもあります。真実の発見という言葉も出てきますが、思想的・宗教的確信はないようです。 それに加えて、クリスの気の短さも旅の行方に影響しているように思えます。一旦メキシコまで行ってアメリカに舞い戻ったとき、身分証明書の発行を待っていて、(父)ブッシュがイラクへの侵攻をもう待てないと演説するテレビ映像の後、クリスがすぐ部屋を出て貨物列車に潜り込むシーンが象徴的に感じられました。 父親への反抗から、父親からもらった金をすべて捨てること、父親の援助で得た大学卒業の資格と無縁に肉体労働をして生きることまでは、比較的理解しやすいところです。しかし、それが、アラスカへ、1人の人間の力だけで生きぬくことへとつながるのは、理解できません。人の憧れや思い込みは他人が理解できないことは少なくありませんが。結局、なぜアラスカなのか、荒野なのかは映画を見てもよくわかりませんでした。 クリスはアラスカに行って、荒野にうち捨てられたバス(クリスは「マジックバス」と名付けます。字幕は「不思議なバス」)を見つけ、そこで3ヵ月あまりを過ごします。魚を捕り、獣を撃ち、木の実を取って生活しながら、日記を綴り、持ってきた本を読み続けます。そのうちに幸福が実現するのはそれを誰かと分かち合えたときと悟り、9週目に戻ろうとしますが、来るときには渡れた川が増水していて渡れず、またマジックバスに戻ります。その後間違って毒草を食べてしまい体力を失い、ついにはバスの中で餓死してしまいます。 アラスカに行ったのは春先で雪深かったわけで、それから夏になって雪が溶ければ川が増水するのは当然ですし、野草を取って喰うからには、しかも医者もいないし薬もないのだから毒草に気をつけるのは当然です。毒草を食べてしまったのも、川の増水を予想できなかったのも判断力不足、準備不足というしかありません。クリス自身、食べられる草と食べられない草の図鑑を持ち歩いていたわけですから、気にはしていたわけですが。 それにしても、ラストで上空からの映像を見ると、マジックバスは川から本当にすぐの丘の上にあります。マジックバスを拠点に周囲を狩猟して回っていたクリスが川の増水に気がつかなかったのは不思議ですね。 クリスが餓死に至るシーンを際だたせるため、上半身裸のシーンが多数登場します。たくましかった体がやせ衰えていく映像は鬼気迫るものがあります(公式サイトの説明では、撮影中に18kg落としたそうです)。ただ上半身裸で荒野を歩き回っていてかすり傷1つないのはちょっと・・・。
2008年09月14日
コメント(0)
-
幸せの1ページ
無人島に父親と2人で暮らす11歳の少女ニムが父親が遭難して帰らないピンチに襲われるアクションコメディ「幸せの1ページ」を見てきました。 封切り2週目の土曜日ですが、かなりガラガラ。アクション/ファンタジー・コメディとしてはいいできだと思うんですが、配給会社の売り方のミスがたたってると思います。 予告編では「ジョディ・フォスター最新作」「この秋、ジョディ・フォスターがすべての女性に贈る最高のハートフル・アドベンチャー」なんて言っていて、映像的にもジョディ・フォスター扮する冒険小説作家アレクサンドラ・ローバーが少女の危機を救いに冒険の旅をするというストーリーを流しています。こういう予告編を見て、ジョディ・フォスター主演の映画と信じて見に来たジョディ・フォスターファンは、ほぼ確実に失望して帰ると思います。はっきり言って、この映画でジョディ・フォスターは、極論すればいなくてもストーリーが成立する程度の存在です。敢えて言えば、不潔恐怖症・外出恐怖症の引きこもり女性作家が、11歳の子どもに教えられて「成長」するという、普通の成長物とは違う(成長物のパロディか)ストーリーの主役とも解釈できますが、そう見るとしても、完全に子どもに喰われてると思います。 この映画の主役は、明らかに11歳の少女ニム(アビゲイル・ブレスリン)ですし、映画の魅力もこの少女自身の魅力と、ニムと父親のジャック(ジェラルド・バトラー)の親子愛に尽きると思います。 何といっても、ニムがかわいくてけなげでたくましい!アシカとダンスしたりアシカに乗って泳いだり、キュートなお転婆ぶりがすごく魅力的です。かわいいだけじゃなくて、1人で火山の絶壁(「クライマーズ・ハイ」の衝立岩並み!)を登ったり、嵐で壊れたソーラー発電システムを1人で修理したりというシーンもあります。 そして父娘関係のほほえましさが至るところで描かれています。ジャックは小舟でプランクトンの観察に行って嵐にあって遭難しても、娘のために絶対に帰りつくと執念を見せ、娘に持ち帰ると約束した新種のプランクトン(新種だったら学名に娘の名前をつける約束)を入れた容器を離しません。この父娘の信頼と愛情に打たれます。 とにかく、ニムのキュートな魅力と父娘の絆が、宣伝は別として実際の映画では一番の見どころの映画です。娘(特に小学生)を持つ父親か、娘が欲しいなぁと思っている成人男性が見ると、きっとハマルと思います。 予告編と映画の印象がかなり違う映画ですが、私は、よかったと思います。ふつう、予告編と映画が違うときは、予告編の方がよくて映画はつまらないのですが、この映画は逆です。また、最近は予告編にいい映像がほとんど取り込まれてて、映画本編を見ても予告編以上の見どころがなかったなんてことがありがちです。しかし、この映画の映像の魅力は、ほとんど予告編以外にあります。予告編はジョディ・フォスターを前に出すために、ニム(アビゲイル・ブレスリン)の魅力的な笑顔のシーンも、アシカのセルキーやトカゲのフレッド、ペリカンのガリレオら動物たちのフレンドリーな映像も使っていません。どう見たって、ジョディ・フォスターが青ざめてる映像よりこれらのニムと動物たちのシーンの方がずっと魅力的です。そういう意味で、予告編では今ひとつだなと思ったけど、行ってみてよかったと思う映画でした。 タイトルも、原題は”Nim’s island”で、原作本の日本語タイトルも「秘密の島のニム」で、元からニムが主役のタイトルなんです。これをむりむり「ジョディ・フォスター主演」にするためにアレクサンドラ・ローバーの成長物語の印象に持ち込もうとして「幸せの1ページ」なる日本語タイトルがつけられています。こういう小細工するから客が入らないんだと思います。ニムの魅力と動物たちと父娘愛の感動物語で十分売れたはずなのに。 魔法は出て来ないものの、設定はかなり荒唐無稽です。海洋生物学者の母親はシロナガスクジラの胃の中に平穏に入れてもらったが海賊船に驚いて鯨が逃げたとか、アレクサンドラ・ローバーがメールで島の位置を「南緯20度、西経162度」と聞いただけでニムの島にたどり着けたり、アレクサンドラ・ローバーやジャックが嵐の中でも方向がわかったり、ジャックが4日間も水なしでどうやって生き延びたかとか、気にしだしたらきりがありません。(ちなみに「南緯20度、西経162度」は地図に落としてみると南クック諸島の主島ラロトンガ島の北西、地図上は何も書かれていない海です) そういうところは気にしないで、ファンタジー・アドベンチャーとでも割り切れれば、そしてジョディ・フォスターのことは気にしなければ、とても楽しく見られる作品だと思います。
2008年09月13日
コメント(1)
-
敵こそ、我が友 戦犯クラウス・バルビーの3つの人生
ナチスの戦犯で戦後アメリカのスパイとなり南米の独裁政権下でも暗躍したクラウス・バルビーをめぐるドキュメンタリー映画「敵こそ、我が友 戦犯クラウス・バルビーの3つの人生」を見てきました。 映画は、かなりシンプルに、記録映像、写真、関係者のインタビューを中心に、時代順に進んでいきます。 ナチスの親衛隊(SS)のメンバーとなり、ナチス支配下のフランスのリヨンでゲシュタポとして多くのレジスタンスの闘士を尋問・拷問し、ユダヤ孤児院の子どもたちまで強制収容所に移送した時期。バルビーに直接拷問された被害者は、バルビーがペンチを片手に尋問し答えないとペンチで歯を折ったと証言し、切れている腱に手を突っ込み折れている骨を押し付けて尋問したとも証言します。レジスタンスの英雄ジャン・ムーランもバルビーに尋問され、バルビーの通訳はバルビーがムーランの足を持って地下室に引きずっていくところを見たと証言しています。ジャン・ムーランはその後移送中に死亡します。子どもたちについては、遺族が、レジスタンスさえしていない子どもたちに何の罪があったというのかと追及します。 しかし、戦後、ナチスの残党よりも共産主義との闘いを重視したアメリカは、バルビーらナチスの残党をソ連の共産主義者の情報を持っていると考えて陸軍情報部に所属させてスパイ活動に従事させます。戦後、他の戦犯が裁かれていく中、他の戦犯の裁判で証人出廷しながら自らは起訴されないバルビーに対して遺族らから不満の声が出てフランス政府が身柄引き渡しを求めると、アメリカは、バルビーらを南米に移送します。 南米では、独裁政権の下で民衆を弾圧するすべを教え、南米共産主義の英雄チェ・ゲバラ暗殺計画にも関わったとされます。ボリビアで海運会社を作って武器輸出などで暗躍して偽名ではありますが表に出てきたバルビーを、ナチスを追い続ける人たちが発見し、フランスからボリビアに引き渡し請求があり紆余曲折の上、1983年にボリビアからフランス領ギアナに移送されて逮捕・フランスに移送されて裁判が行われることになります。4年にわたる予審の上、1987年に人道に対する罪で終身刑となり、収監されたバルビーは1991年ガンで獄死します。 ナレーションもなく、音声は記録映像部分以外はインタビューでつなぎますので、統一感がなく、テーマミュージック(フランス映画らしく、ちょっと哀愁の漂う洒落た感じのシャンソンです)も最初だけで本編の間ほとんど音楽なしです。インタビューには英語もありますがフランス語も多く、字幕をジッと見つめていないとすぐ置いて行かれます。それでいて映像もドラマティックに作った部分がないので、内容に強い興味がないと、見続けるのがちょっと辛い。フッと居眠りして目を開けたら話が見えなくなっていたりします。 記録映像の残り具合やインタビューの取りやすさからでしょうけど、南米に行ってから、それもフランスの引き渡し要求以後の部分が長くなっています。3つの人生というサブタイトルから見ても、3つめが長くなってバランスを崩している感じがしますし、後半をもう少しまとめた方がよかったかも。 バルビーの娘のインタビューで、自分には優しい父だったとか、リヨンの虐殺者(Butcher of Lyon)なんて言う人がいるが精肉業者(butcher)にも失礼だとか言わせています。戦犯法廷での弁護人は、彼は命令に従っただけだとか、当時のフランス法上合法だったと弁論しています。バルビーは法廷で子どものアウシュビッツ送りは否認し、レジスタンスとは戦ったがそれは戦争だった、そして戦争はもう終わったと述べ、映画のラスト近くでは、世の中は皆自分を望んだのに裁かれるのは自分一人だと言わせています。 そういう面はあるとは思いますが、でも拷問の被害者や遺族の証言の前にはその言葉はむなしい。 最後にアメリカの元国会議員には、アメリカの政策は今もアフガニスタンでもイラクでも同じ、敵の敵は友だと語らせています。そのあたりが、この映画のコンセプトです。 率直に言って、もう少し見せる工夫をして欲しい映画ですが、こういう堅いドキュメンタリーをいまどき8週間上映する(今日から7週目。9月19日まで)銀座テアトルも立派かなとも思います。
2008年09月06日
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 今日からのクーポンとエントリーめっ…
- (2025-11-20 11:25:21)
-
-
-
- 自分らしい生き方・お仕事
- 🧭【働き方の探求】クタクタで土日は…
- (2025-11-20 12:00:10)
-
-
-
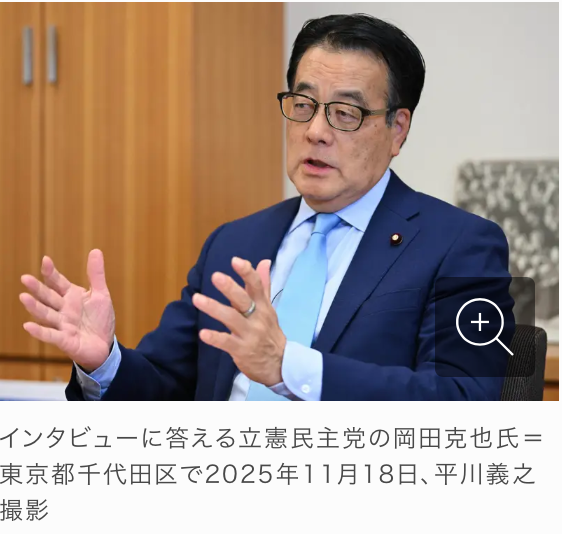
- ニュース
- ・立憲岡田氏「国民にはその意味を考…
- (2025-11-20 08:49:23)
-







