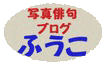2011年05月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
ブラック・スワン
ナタリー・ポートマンがアカデミー主演女優賞を射止めた映画「ブラック・スワン」を見てきました。 封切り5日目日曜日、ヒューマントラストシネマ渋谷の午後0時10分の上映はほぼ満席。 ニューヨークのバレエカンパニーに属するニナ・セイヤーズ(ナタリー・ポートマン)は、新シーズンの「白鳥の湖」で、監督のトマ(ヴァンサン・カッセル)がプリマドンナのベスを引退させることから、プリマに登用されるチャンスを獲得する。しかし、新作の「白鳥の湖」では、白鳥だけでなく、王子を誘惑する黒鳥ブラック・スワンの役もこなさなければならず、元バレリーナの母親の下でバレエ一筋に打ち込んできた優等生タイプのニナには、高いハードルとなった。同時に現れた奔放で小悪魔的な新人バレリーナリリー(ミラ・クニス)がブラック・スワンにふさわしい踊りを披露し、トマに近づく姿を見て、ニナは焦りを感じる。苛立つニナはいつのまにか背中に傷を受け、手が血にまみれ、近づいてくるリリーやトマに不審を感じ・・・というお話。 大役を張り、またその役を競い合う激しい緊張とストレスの下での恐怖と狂気を描いた映画で、見どころも、基本的にそれに尽きます。10か月に及んだというバレエの特訓をこなし、その過程を共にした振付師とできちゃった婚(まだ婚約らしいですが)してしまうほど役になりきったナタリー・ポートマンの演技は、さすがと言えるでしょう。 サブテーマとしては、母親の下で優等生として育ってきたニナが、心理的に母親から独立し優等生らしさを踏み越える成長物語としての側面もないではない、というところでしょうか。 しかし、王子を誘惑する悪魔的なブラック・スワンの表現について、ニナの演技の不足を指摘するのに、王子役の男性ダンサーに「おまえ、やりたくなったか?」と聞いて失笑させたり、監督が俺が王子と思えといってキスをし胸を揉みしだき股間をまさぐり固まっているニナにおまえが誘惑する側だろと言い捨てて立ち去り、とやりたい放題。アメリカでこんなことやってセクハラで訴えられたら懲罰的賠償いくらになるんだろ。だいたい、バレエで観客が「やりたくなる」ような踊りが要求されるのでしょうか? ブラック・スワンを演じるために命じられて一人Hするナタリー・ポートマン、リリーとの愛憎をめぐる妄想に耽るナタリー・ポートマンの、ヌードは見せないものの濡れ場が少なからずあり、そのあたりがR15+指定の理由でしょう。 基本は心理サスペンスで、アカデミー主演女優賞だし、メジャー作品なんですが、親子とか純情カップルで見るにはちょっとしんどいかなと思います。
2011年05月15日
コメント(2)
-
100,000年後の安全
フィンランドで建設中の世界最初の原発の使用済み燃料の最終処分場をめぐるドキュメンタリー「100,000年後の安全」を見てきました。 封切り7週目土曜日、東京で2館の上映館の1つヒューマントラストシネマ有楽町の午前9時50分の上映は2~3割の入り。 フィンランドのオルキルオトで岩盤を深く掘り抜いて建設中の世界最初の原発の使用済み燃料の最終処分場の建設計画と工事の映像に、関係者のインタビュー映像、イメージ映像+ナレーションで構成されています。 強い放射線のため近くに寄る者は放射線障害で死亡する危険があり、しかも放射線は五感の作用で検知できないので放射線に気付く前に致死量の被曝をする危険が高く、無害になるまでに10万年かかる使用済み燃料を岩盤深く埋めて埋め戻す施設について、主として何万年も後の人類に危険物の存在を、そして決して掘削すべきでないことをどうやって知らせるかが主要な論点として提示されます。 果たして10万年後の人類は、どのような文明を持っているか、現在の文字を解読できるか。10万年前と言えばネアンデルタール人の時代、今からそれだけの気の遠くなるような年月を経た後のことをどうやって予測するというのか。6万年後にはまた氷河期がやってきて文明は壊滅するかも知れない。この岩盤を掘削できる技術があれば、放射能も検知できるだろう。いや、掘削は高度の文明がなくても可能で、放射性物質を扱う技術がなくて掘削はできる文明の状態が最も困る・・・ 文字が読めたとして、危険だと告知されて掘削をやめるだろうか。ピラミッドは封印されていたが、盗掘を免れなかった。古代ルーン文字で「不届き者、触るべからず」と記載された石碑を学者はまったく無視して遺跡の発掘を続けている。 映画で議論されているのはこのあたりですが、そもそも数万年後の人類に原子力発電に関する知識が承継されている可能性はほとんどないでしょう。なぜなら高速増殖炉が行き詰まりプルトニウムサイクル技術の完成が絶望視されている以上、原子力発電はウラン資源に依存し、そのウラン資源は数十年程度で枯渇するのですから、原子力発電という技術は、大事故が起こってもなお反省せずに推進し続けたとしても今世紀いっぱいの過渡的な技術に過ぎないわけです。そのような過去の一時期になされた、成功したとは言えず控えめに言ってもその後の世界では有用性のない技術に関する知識を、何世代も語り継いでいくことはおよそ期待できません。 推進側の連中は、有用な資源のない最終処分地を掘り返す動機はないと主張しています。しかし、数万年後の人類にとって何が有用な地下資源か、誰にわかるというのでしょう。現在の原発推進派が有用と考えるウランが原子力発電(というより核兵器)に使えると人類が考えるようになったのはせいぜい数十年前です。岩盤を数百メートル掘削する技術ということなら、現在石油を得るためには数千メートルの掘削が行われています。数万年後どころか数百年後に、どのような技術が開発され、今は利用価値のない地下資源が貴重な資源と目されるようになるか、その頃の掘削技術がどのようなものか、今の知識でどうやって判断するというのでしょうか。わずか数か月前には、日本の太平洋側のプレート境界でマグニチュード9の地震が起こることはあり得ないと言っていた連中が、数万年後のことをどうして自信を持って予測できるのでしょうか。 ちょっと映画で触れていないことに話がそれましたが、原子力発電という技術が、仮に事故を起こさなかったとしても、いかに不毛でやっかいなものかを考えさせる、時宜を得た映画だと思います。
2011年05月15日
コメント(0)
-
ミスター・ノーバディ
人生の選択をめぐるたらればパラレルワールドノスタルジー映画「ミスター・ノーバディ」を見てきました。 封切り2週目土曜日、全国5館、東京23区では唯一の上映館のヒューマントラストシネマ渋谷の午前10時の上映はほぼ満席。観客の年齢層はばらけてましたが、なぜか同性の組み合わせが多く、若者カップルは少数でした。 2092年、人間が不死を獲得し、最後の「死ぬ」人間となった118歳のニモの最期に注目が集まっていた。ニモにインタビューするため病院に忍び込んだ記者を前に、ニモは過去を語り始めるが、ニモの話は、9歳で両親の離別に際して父親の元に残ったのか、列車に乗った母親を追いかけて列車に乗り込み母親に付いていったのか、幼なじみのアンナ、エリース、ジーンのうち誰と結婚したのか、夫婦生活の転機でどのような選択をしたのか、はっきりせず、それぞれの選択に沿った複数の物語が展開する。記者は、結局どちらの選択をしたのか、あなたの話は矛盾していると迫るが・・・というお話。 枠組みは、2092年、不死のテクノロジー、火星観光(しかし、90日で行けるなら人工冬眠までさせるか?)、バタフライ・エフェクト、ビッグ・バン宇宙と超ひも理論の9次元の宇宙、膨張する宇宙の終焉と、大仕掛けのSFで、こういう構想だとエンディングは、古い感覚でいえば、アインシュタインの舌を出した笑顔でも入れたいような気がします。 膨張する宇宙が収縮する宇宙に転換し、そのとき時間が逆行するとか、そのターニング・ポイントが2092年2月12日午前5時50分とかいうのは、SFとしてもちょっと厳しいかなという気はしますけど。 しかし、その大仕掛けな枠組みで語るパラレルワールドの分岐点というのが、9歳の時に両親が離別する際に父親を選んだか、母親を選んだか、幼なじみ3人のうち誰と結婚したかという点にほぼ限定されるのは、羊頭狗肉というか、ちょっと拍子抜けしてしまいます。もちろん、個人の人生では重大な選択で人生の分岐点というのは、重々、実感としてもわかりますけど・・・ それぞれの選択、それぞれの人生には同じ価値・意味があったというのですが、全然同価値には描かれていません。何が真実だと、記者は問いかけ、ニモはそれに答えませんが、私には見え見えに思えます。その点は人により見方が違うのかも知れませんけど。あえていえば、現実には父親の元に残り、介護に追われて鬱屈した青春時代を送り、わがままなエリースと結婚したものの家庭生活はうまくいかず、それ故にそうでない選択を空想するけれども、父親の元に残った場合の第2選択のジーンとは自分がそれほど好きだったわけではないから不本意な選択をしたという思いが残るだろう、やはり幼い頃憧れていたアンナが恋しいけれども現実には9歳の頃以降会っていないからどうなっているのかわからないために様々なパターンを空想してしまうと、私にはそう読めてしまいます。 誰もが感じている、もしあのときこうしていたら、という思いを扱うことでノスタルジーに浸る観客の共感を集めつつ、それを非現実的な過剰に大仕掛けの枠組みで扱うことであくまでも劇場限りの幻想なのだよと示すことで安心なエンターテインメントを目指したというところでしょうか。
2011年05月07日
コメント(0)
-
八日目の蝉
不倫相手とその妻の間の乳児を誘拐して4年間逃亡生活を続けながら育てた女性と育てられた娘の生き様を描いた映画「八日目の蝉」を見てきました。 封切り5日目水曜日祝日、池袋東急午前10時の上映は3~4割の入り。 不倫相手の男秋山丈博(田中哲司)から、いずれ妻とは別れるからそれまで待ってくれと中絶を求められ子どもを産めない体となった野々宮希和子(永作博美)は、秋山の妻(森口瑤子)が産んだ生後4か月の乳児恵理菜をひと目見ようと秋山の家に忍び込むが、希和子の前で笑った乳児を見て、この子は自分が守ると決意してとっさに連れ出してしまう。希和子は乳児を薫と名付け、友人宅や新興宗教団体のホームやそこで知り合った友人の実家を頼って逃亡生活を続けながら薫(渡邉このみ)に寄り添い愛情を注ぎ育ててゆく。4年後希和子は逮捕され、薫は秋山夫妻の元に戻されるが父母と実感できず、逃げ出したり、苛立つ母に脅え、人に心を開けないままに育った。21歳になった恵理菜こと薫(井上真央)は、アルバイトをしながら一人暮らしをしていたが、妻子ある予備校教師(劇団ひとり)の子を身籠もる。恵理菜に誘拐事件のことを聞きたいと近寄ってきたライターと名乗る千草(小池栄子)に、恵理菜は相談するが・・・というお話。 恵理菜=薫が育った秋山家は、父親は誘拐犯と愛人関係だったことがマスコミに報道されて会社を辞めざるを得ずその後も仕事ができずに酒に溺れ、母親は娘とうまく行かずにいらだち仕事を始めて遅くまで帰らず食事はスーパーで買ってきたお総菜ばかり、誕生日とかクリスマスとか楽しいお祝いをしてもらったことはない・・・そしてその原因は自分にあると幼い恵理菜は自分を責めて育った。 それ以前の逃避行の中も含め、私のように幼い子が哀しい目に遭うシーンには無条件で涙腺が緩む人はもちろん、ふつうの人にも泣きどころ満載の映画です。 幼い子どもが関係する場面で法律家業界では、「子の福祉」つまり子どもの幸せを最優先にというのですが、実父母の元に戻すことが子どもの幸せにつながらないことがままあるのが悩ましい。 妻子ある男の子を身籠もったことを、千草に向かって、希和子と同じことしてるって思ってるでしょっていう恵理菜。しかしこの映画のテーマは、虐待の連鎖から抜け出し、生まれてくる子どもには世の中のきれいなものをすべて見せてやりたい、それが自分の義務だと思える恵理菜の前向きな姿と希望にあります。それが、わずか4年間でも、誘拐犯でも逃亡生活でも、慈しんで育ててくれた希和子との思い出に起因するのか、実母の姿勢を反面教師としてかは、さておいても。 そしてその裏側では、「いつか妻と別れるからそのときまで待っていてくれ」と無責任な決まり文句を言い続ける不倫夫たちの情けなさと罪深さ。秋山丈博はそのために家庭を崩壊させ、自分はもちろん自業自得として、妻も愛人も娘も不幸にしてしまう。娘が父親と同じタイプを好きになるというのは、父親にとっては誇らしいはずですが、無責任な妻帯者の子を身籠もって「相手はお父さんと同じような人」って言われるのでは身の置き所もない。もしも子どもができたらと聞かれただけでうろたえ、恵理菜から見限られる予備校教師に至っては、存在感もない。「キッズ・オールライト」と続けて見て、男って、夫って、父親って何だろう、存在意義は・・・って考えさせられました。 陰のある大人の役に挑戦した井上真央の成長と、子役のけなげなかわいさが光っています。 永作博美も哀しげな表情がいいんですけど、最初の方の乳児が泣き叫んで乳房を含ませようとするシーン、別に永作博美の乳房が見たいって思ったわけじゃないけど、ああいうシーンはがむしゃらに人目を気にせずに(そもそもホテルの室内で人目はないという設定だし)胸をはだけないとそれらしくなくて、最初の方で気持ちがつまづいてしまいました。 魔法使いのおじさんみたいな写真館の主人も捨てがたい魅力がありましたが。
2011年05月03日
コメント(0)
-
キッズ・オールライト
同性夫婦と子どもたちの絆を描いた映画「キッズ・オールライト」を見てきました。 封切り3日目日曜日、シネリーブル池袋午前11時55分の上映は3~4割くらいの入り。観客の多数派は若者層でした。 医師のニック(アネット・ベニング)と仕事がうまく行かずにいるジュールス(ジュリアン・ムーア)は、レズビアンカップル。精子バンクで同一人物の精子を買ってニックは娘のジョニ(ミア・ワシコウスカ)、ジュールスは息子レイザー(ジョシュ・ハッチャーソン)を産んで育てている。18歳になり大学進学を控えるジョニは、15歳のレイザーに頼まれて、精子バンクに連絡して精子提供者を知り、連絡する。ジョニとレイザーの生物学上の父親ポール(マーク・ラファロ)は、レストランのオーナーで、若い恋人と気ままな独身生活を謳歌していたが、ジョニとレイザーと会い、レイザーの母親ジュールスにジュールスが新たに始めた造園の仕事を依頼し、ジョニの家族に接近し、ジュールスと肉体関係を持ってしまう。家族に割り込んできたポールに対してニックは不快感を持ち・・・というお話。 レズビアン夫婦とその子どもたちという、「ふつうと違う」家族と、「生物学上の父親」という異分子を通じて、同性愛、家族の絆、(生物学上の)父親の存在意義といったことを考えさせられる映画です。 「ふつうと違う」家族については、すでに「ふつうの家族」というもの自体が少なくなり一種の幻想とも思える今日ですが、実子を育てるレズビアンカップルという設定には、まだこういうフロンティアがあったかという思いがします。その家族愛を描くことで、様々な家族のありようをあるがままに受け止めていこうという制作意図が感じられます。 同時に、そのレズビアンカップルに、ニックが長時間労働で家族を養いジュールスは定職に就かずすねをかじっているという関係と、エリートで厳格な性格のニックと仕事がうまく行かず拗ね気味でルーズな性格のジュールスという組み合わせで、男女の夫婦にありがちな関係を持ち込んだのは、レズビアンカップルも多くの夫婦に似ているという、親近感からも揶揄的な視点からも考えられる安心感を狙ったものでしょうか。 レズビアンのジュールスがポールと簡単に肉体関係を持ってしまうのも、レズビアンに対する、本当は男とやりたいんだろというような偏見からとも、その後のジュールスの選択を際立たせるための布石とも、まぁ読めます。 レズビアンのニックとジュールスのカップルがセックスのムードを盛り上げるために(レズビアンのではなく)ゲイのポルノビデオを見ていたのも、やはり本当は男が欲しいんだろという、レズビアンに対する抜きがたい偏見(というか男性側の願望)からなされた設定とも考えられますし、映画の中でレイザーの質問に対してニックとジュールスが答えているようにレズビアンのビデオは本物じゃない・レズビアンでない女優がやっている(つまりゲイのポルノビデオはゲイの視聴者のために作られ、本物のゲイが演じているが、レズビアンのポルノビデオはレズビアンの視聴者ではなく男性視聴者のために作られ、レズビアンでない女優が男性に裸を見せるために演じている)からむしろゲイのポルノの方が同性愛者にとって親近感を感じるからかも知れません。 このように一応レズビアンについて好意的な意図という説明も不可能ではない形にはなっていますが、私にはどうも制作サイドにレズビアンを扱いながらレズビアンに対する抜きがたい偏見があるように感じられる点が少なからずありました。それが「ふつうと違う」家族をあるがままに受け止めようという方向性とマッチしない感じがして、ちょっとすっきりしませんでした。
2011年05月03日
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- ファジーについて考察します。
- (2025-11-20 07:39:53)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 【2025年11月】楽天市場ブラックフラ…
- (2025-11-20 12:50:09)
-