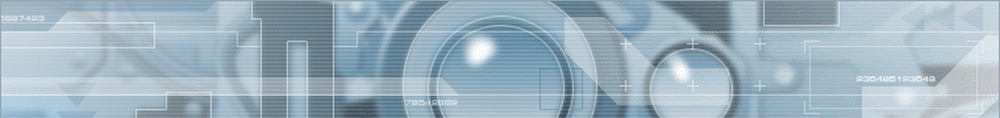関西、名古屋の2日間の1日目の夜は 昼の紅葉の京都
から移動して大阪でのワイン会でした。関西と言えば屈指のドイツワインマニアの緑家さんで、来ることを伝え都合があったので会をセッティングしていただきました。緑家さんとお会いするのは三度目で場所は 4月の時
と同じところです。今回はdoniekさん夫妻も加わり4人での宴となりました。
書かなければいけない記事がたまっていることと曖昧な記憶の部分が多いのでさらっと書かせてもらうことをお許しください。
近いうちに 緑家さん
と doniekさん
もブログで書かれると思うので興味のある方はそちらもあわせてお読みください。
4人で9本となりました。翌日は二日酔いで大変でしたが、事前にある程度打ち合わせしたこともありバラエティ豊かなラインナップとなりました。
一番右はワインではなくベルギービールです。
doniekさんがビールにも精通されているということでこの味がわかる人と飲みたいと思っていた瓶詰めから10年以上経過しているドゥリー・フォンティネンのランビック(自然発酵)のグーズ(樽熟成の年月が異なる数種類のランビックをブレンドして味を調えたもの)を持っていきました。枯れていなくて発泡感もまだしっかりしていてdoniekさんにも気にいっていただけたようでよかったです。
doniekさんはドイツ以外のワインも持ってこられました。
一番左はオーストリアのピヒラーのスマラクト(シュペートレーゼ・トロッケンに相当)です。
6年経過していますが熟成しているオーストリアワインはあまり飲んだことがないので良い経験となりました。ドイツとは異なる変化を遂げていてさすが上級ワインにはそれ相応の魅力があると感じさせる味わいでした。少しまったりとしていて熟成した価値を感じられ楽しめるワインでした。
その右はシャンパンです。酸を強く感じて骨格もしっかりしていてシャンパーニュにもこういものがあるのかということを知れる良い機会となりました。
ピノ・ワールの要素が強いなーという感想を抱いたのですが、撮った写真を見たらシャルドネと書いてあってその感想をその場で言わなくて本当によかったです・。
クヴェアバッハに関しては興味のある方は 僕が醸造所を訪れた時の記事
をお読みください。今回持ってきたのはDoosberg2008です。
緑家さんがあまりラインガウぽくないと言っておられたのですがたしかにここの畑はまわりと多少性質が違うようです。そういう話を当主から聞いたし僕もあらためて飲んでそう感じました(細かいことは書けなくてすみません)。
ラベルがはがれているのはdoniekさんが持ってこられたドクダーローゼンDr.Loosenのエルデナー・トレプヒェン1997シュペートレーゼです。
最初はブラインドで飲んだのですが、モーゼルだとは感じても畑まではわからなかったのですがこの畑と聞いて納得する味わいでした。全くこの畑が頭の中の候補に浮かんでこなかったのですが、この畑の特徴が出ていお手本のような作りです。まだローゼンが素直な味わいだった頃だということもその要因だと思います。
クリーンできれいで心地よい甘みもあってすねていない味わいです。お二人は若いころにも飲まれていてその頃と印象が変わらないという事でした。それは良いヴィンテージで酸もしっかりあったからこそ15年経過しても輝きを保っているということだと考えられます。
緑家さんの持参はファルツのクリストマンA.Christmannの代表的な畑IDIGのグローセス・ケヴェックス(辛口の最上級)の2011と1999で12年差の飲み比べとなりました。
共通点を感じたりするまでじっくりと考察をできなかったことが悔やまれますが(お二人のブロでの感想に期待!)、両方ともそれぞれ魅力のあるワインだったということは間違いないです。
2011は若さを感じる桃の風味が広がるのですが甘みがなくてドライな味わいでそのバランスが秀逸でした。
このワインはゴーミヨ2013で94点とかなりの高得点なのですが、それが今の評価とポテンシャルどちらの評価の割合が高いのかが気になります。どちらもだから高得点だとは思うのですが、今の僕が飲んだ印象ではそこまで突出した点数でなくてもよいのではと思いました(ゴーミヨの点数に疑問を抱く人は多くて僕も鵜呑みにはしていませんが)。とはいえ個性のある唯一無二のワインなのは間違いないです。
1999は香りは熟成を感じさせる深いものなのに味わいはそこまで古さを感じなくそのギャップが面白かったです。まだまだ寝かせても楽しめそうだと思いました。うーんあまりはっきりと憶えていないのが悔やまれます。
シュロス・リーザーは通常のとラベルが違うのですが、このワインはトリアーのとあるワインバー兼ワインショップ専用に作られたものです。こういう特注ものはある程度大きな醸造所ではけっこう存在しているようです。今回のドイツではペーター・ラウアーでも発見しました。
このワインはファインヘルプなのですが甘さはあまり感じません。シュルス・リーザーのワインらしくて洗練されている、というほどではありませんがエレガントさはありました。シーファーの要素もしっかり感じられて適当に作ったのではないことがわかる10ユーロしないものにしてはおいしいと思えるよくできたワインでした。
最近リーザーに注目している緑家さんのお土産にと持ってきたのですが好印象だったみたいでこれを購入して持ってきた甲斐がありました。飲まないで購入したものなので内心怖かったのですが。
左から二番目は醸造名はChat Sauvageだしピノ・ノワールと書いてあるしブルゴーニュの赤ワインに見えるのですがラインガウ、アスマンズホイザーと書いてあってドイツワインなのです。
親戚がラインガウに畑を持っていた人がブルゴーニュのような赤ワインがこの産地でも造れるということを証明するという信念のもとにワインを造リ始めたそうです。
ドイツ中心に飲まれている方と最近はフランスを多く飲まれていお二人の感想が全く異なっていたのがとても面白くて興味深かったです。ドイツ寄りの緑家さんはバリックが効いていてラインガウっぽくないと感じ、一方のdoniekさんはブルゴーニュではなくあきらかにラインガウ、ドイツの味わいだと言っていました。
お二人の言うことはぢちらもよくわかります。僕の印象としてはアスマンズハウゼンらしい味わいがあるけれどブルゴーニュぽさも感じるなあというものでした。
そう思わせているのは造りの狙いどおりなのだと思いました。
ただこのワインは20ユーロちょっとなのですが日本で販売するとなると5000円前後になると思われるのですが、だとしたらもっと安くておいしいブルゴーニュ・ルージュを選ぶという意見には僕も同意します。ラ
インガウでこういうワインを造っているという付加価値と興味では惹かれるワインですが質と値段のバランスでいうと他の国とは争えないというものなのです。その問題はこのワインに限らずドイツの多くのシュペートブルグンダー(ピノ・ノワール)にいえる問題なのですが。
この造り手はラインガウにいくつかの畑を所有していますが(ヨハニスベルクやリューデスハイムなどリースリングからピノ・ノワールに植え替えたところもあるそうです)同じ畑でワンランク上の40ユーロ前後のも造っているのですがそのクラスのワインを飲んでこの醸造所を判断したいです。120ユーロのも存在するのですがさすがにそれは飲みたいとも思いません。
以上です。この日は辛口が多く食事とマッチしやすいものばかりなので、ドイツワインが範囲の人以外にも比較的気に入られやすい、親しみやすいラインナップになっているかと思います。
料理のことは書きませんでしたが緑家さんがきっと書いてくださると思います(すみません)。
今回もワインをさらにおいしくさせてくれるすばらしい料理でした。
5時間はあっという間にすぎてしまいました。
それぞれブログの文章からは想像できないユニークな方たちなので冗談が飛び交う堅苦しくない楽しい会となりました。
また関西を訪れる際にはお仲間に入れていただきたいです。
-
トリッテンハイマー・アポテーケTrittenhe… 2015.03.14
-
ブロイヤーのトロッケンではないトップキ… 2013.08.18
-
池袋の東武でドイツワインフェアが開催中… 2013.07.26
コメントありがとうございます!
お店では酔ってたかんじはあまりなかったのですが、宿に着くまでの記憶がなく三つ折りの布団の上でコートを着たまま寝ていました。美味しいワインは飲みすぎちゃうんでしょうがないです。ただ翌日の甘口中心の会ではほぼ酔わなかったのが不思議です。
ぜひぜひまたお会いしたです。もっと色々とお話を聞きたいです。京都のおいしい店も知りたいです。 (2012.12.16 01:25:43)
書き忘れました。
お土産でいただいたチョコレート美味しくいただきました。感謝です。
ラインガウの甘口とあわせて幸せな気持ちで食べていました。
(2012.12.16 01:54:13)
クヴェアバッハ、とても綺麗な造りで愉しめました。改めてじっくり1本と向き合ってみたいなと思いました。ソヴァージュも面白い造り手ですね、これからどう進化していくか楽しみです。リーザーの半辛口は初めてでしたがこれまたなかなか高品質でしたね。リーザーは年々良くなってる気がします。
ということでまた是非御一緒出来るのを楽しみにしています。今度は大丈夫かな?(汗) (2012.12.16 03:02:17)
文字数多いとそのむねが表示されるので、もしかしたら迷惑コメント用に30近く設定している禁止ワードにひっかかったのかもしれません。ご足労おかけしました。
ここで書けなかった内容はメールにてお待ちしております(笑)。
リーザーは僕は2010年産からさらに劇的に変化しているよう気がしています。VDPの方向性とは異なる唯一無二のベクトルへ向いているように感じています。インポーターの人にも勧められたので近いうちにトーマスさんにメールで質問しようと思っています。
またお相手よろしくおねがいします。
(2012.12.16 08:03:40)
カテゴリ
カテゴリ未分類
(54)ラーメン
(60)ドイツワイン
(119)東京ドイツワイン協会(ケナー関係含む)
(42)役にたつであろうワインの知識
(17)ドイツワイン 2010年ヨーロッパ旅行編
(29)2010年 ヨーロッパ旅行ドイツワイン以外
(14)ベスト3 ヨーロッパ旅行 土地
(14)ベスト3 ヨーロッパ旅行 体験
(10)ヨーロッパ旅行 08年12月編
(8)ヨーロッパ旅行 08年1月編
(3)ヨーロッパ旅行 実践編
(11)2012ヨーロッパ旅行 ドイツワイン編
(22)2012ヨーロッパ旅行 (ワイン以外)
(6)日本の土地
(28)ベルギービール
(17)その他酒
(10)音楽
(48)プロレス
(18)日本で買えるおすすめドイツワイン
(7)sakae
(3)2013年ヨーロッパ旅 ワイン以外
(3)2013年9月ヨーロッパ ドイツワイン
(4)2014年9月ヨーロッパ
(2)・2025.10
・2025.09
・2025.07
キーワードサーチ
コメント新着
モーゼルだより mosel2002さん
ドイツワインならメ… 店長@ユースケさん
Loving PURORESU hirose-gawaさん
youi's memo youi1019さん