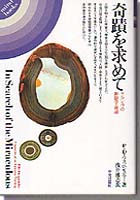
「奇蹟を求めて」
グルジェフの神秘宇宙論<1>
P・D・ウスペンスキー /浅井雅志 1981/02 平河出版社 単行本 606p
Vol.2 No.485 ★★★★★
二人の巨人が 出会う経緯、ウスペンスキーが学んだグルジェフのワークやスクール、エニアグラムと言った特異な教えについて、小森健太朗 「Gの残影」 でダイジェストのように読み込んだ。小森はその改題版「グルジェフの残影」2006/07では、ウスペンスキーの側近として書かれているオフロフは架空の存在だと明かしている。
小森 ただ、書き手としては、ミステリを使ってかろうじて読者と通路を持てるかなという気がしています。読み手としては、十代のころにミステリにはまってかなりの冊数を読んだのですが、ある程度読んだら飽きてしまい、大学時代は哲学書ばかりで、ミステリはほとんど読まなくなりました。今回の「グルジェフの残影」でも、大学時代に夢中で読んだウスペンスキーやグルジェフの思想で一気に走ってしまって、ミステリは必ずしも主眼でなくなったところがある。(中略)だから、僕の中にある興味関心の半分くらいはミステリなんですけど、半分くらいは精神世界に関するものですね。 「グルジェフの残影」文庫本p415
古書中心ですこしアナクロになっている当ブログだが、このように2006年代に書かれた文章を読むと、ほっとする。
小森 こと「グルジェフの残影」に関してはウスペンスキー、グルジェフへの興味関心が強すぎて、ついそっちのほうへ暴走してしまった(笑)。たとえば他にも大好きな思想家、ニーチェとかコリン・ウィルソンなどをもし小説で扱ったとしたら、それらがミステリーを喰ってしまうだろうという気はします。そういうテーマさえ避けられれば(笑)、こだわりを持ってミステリを書けると思う。 同上p417
このへんに、当ブログが小説を読みこまない理由と連なる部分がある。「仕掛け」を追っかけて小説を読みつづけるよりも、人生の神秘をみつめて、自らの生を生きることのほうが、はるかに面白い。
さて、「奇蹟を求めて」だが、この一冊を持ってして、ウスペンスキーもグルジェフも終わりにしてもよいくらいだ。3の法則、7の法則、エニアグラムの「ショック」、スクール、ワーク、エクササイズなど、グルジェフの思想の紹介もふんだんだ。
「現代心理学についてどう思いますか」と、私は一度、最初に耳にしたときからどうも信用できなかった心理分析という問題を持ち出すつもりで、Gに聞いてみた。しかし、Gはそこまで私をいかせてくれなかった。
G---心理学について話す前に、それは誰を扱うのか、また誰を扱わないのかをはっきりっさせておかなければならない。
”心理学”は人々、つまり人間、人類を扱っている。機械を扱う”心理学”(彼はこの語に力を入れた)はあるのだろうか? 機械の研究には、心理学ではなくて力学が必要なのだ。だからこそ、我々は力学から始めるのだ。心理学までは、まだまだ先が遠い。
p41
ウスペンスキーの 「人間に可能な進化の心理学」 は、示唆に富んでいるが、全面的に賛成することはできない。 「超宇宙論」 において、日本語翻訳者は、心理学を「魂理学」と「意訳」して、 一部批判 を浴びているが、私は受容的だ。しかし、単語もアルゴリズムも、あまり凝りすぎないでいただきたい。
人間は一人では何一つすることができないのだ。
人間はなによりもまず助けを必要としている。しかし、助けは一人の人間にだけやってくることはありえない。助けを与えることのできる人たちは自分の時間を非常に大切にする。だから当然、目覚めたい人を助けるのなら、一人よりは2,30人の方が都合がいいわけだ。
p344
この辺は、当然ながら J・クリシュナムルティ のアルファべットとは大きく違ってくる。Oshoのアルファベットに云い直せば、瞑想と愛がふたつの翼だとして、クリシュナムルティは大きく瞑想を強調し、グルジェフ+ウスペンスキーは愛を強調していた、ということだろう。
私はGの示した特徴の芸術的仕上げに驚嘆した。それは心理学でさえなかった。まさに芸術であった。
G---それに、心理学は芸術であるべきだ。心理学はとても単なる科学などで終わることはできない。 p417
トランスパーソナルな流れも、この点には気づいている。もし、心理学が、科学の域を脱して、芸術の域に到達しても、まだブッダたちの心理学は完成したことにはならない。既知、未知、不可知の三つ、つまり、不可知の部分を取り入れることができなければ、ブッタたちの心理学とは呼べない。
誰かが少しでも宗教に関連したことを質問すると、Gはきまって、宗教の問題に対する我々の通常の態度には、確かに何かまちがったところがあると強調することから始めるのだった。
G---まず第一に、宗教は相対的な概念だ。それは人間の存在(ビーイング)のレベルに相応している。だから、ある人の宗教は他の人には全く適さないかもしれず、言いかえれば、ある存在(ビーイング)のレベルにいる人間の宗教は他の存在(ビーイング)レベルにいる人間には適さないのだ。 p461
当ブログのサブタイトルを「New Man : One Earth One Humanity」から変えようとは思わない。それぞれの人間のいまあるところから、問題を解決するための”心理学”であるならば、それぞれ症状に合わせて療法や薬剤が調合される必要がある。しかし、症状に合わせるのではなく、人間のありようのもっとも基準となるものが見えてくるなら、地球上のすべての問題は、「ひとつの人間性」において解決し得る。
当ブログが、チベット密教であれ、トランスパーソナル理論であれ、あるいはグルジェフワークであれ、それぞれの仔細なアルファベットにはこだわりをもたないことにしているのは、その辺に理由がある。
Gの行動や方法が間違っていたとか、それが期待に応えてなかったとか言っているのでは全くない。私自身がそのエソテリックな性格を認めているワークの指導者に関してそんなことを言うのはおかしいし、全く的はずれでもある。 p572
と、ここではウスペンスキーはジェントルマンを演じているが、死後発行された 「人間に可能な進化の心理学」 では、もっと率直な意見が吐露されている。グルジェフ+ウスペンスキーの大いなる実験、大いなるワーク、大いなるエクササイズは、未完のままその輪を閉じた、と言える。不可知部分を扱わざるを得ないスクールは、いまだ未完のまま存在し続けている。スクールはそのように存在せざるを得ないことは最初から運命づけられているのである。
彼(グルジェフ)の主著「全体とすべて」は、しかしながら非常に難解である。その第一シリーズ「ベルゼバブの孫への話」は、量的に膨大だけでなく、凝った寓話の形をとり、そおの英語はかなり難解で、おまけに彼の造語が頻出する。 p602
グルジェフのアルファベットのひとつクンダバッファーは、別なところでグルジェフはきちんとクンダリーニという言葉を使っているのだから、完全な造語と言える。言葉だけでなく、その意味、その働き、そのコンセプトも、グルジェフのアナロジーで組み直されているが、当ブログは、あまり仔細な部分には拘泥しない予定である。
第二シリーズは「注目すべき人々との出会い」で、普通グルジェフの自伝と考えられている。しかしまた多くの者が指摘している通り、これを純粋な自伝とみなす必要はなく、むしろ彼はこれをもって真理探究者のたどる道の一例を示そうとしたのではあるまいか。 p602
江本嘉伸 「西蔵漂泊」 には、ダライ・ラマ13世の信を得て側近になったとされるガワン・ロサン・ドルジェ、なる人物の全身像の写真が掲載されている。経緯からして、この記事の信ぴょう性は低くはないが、この写真を史実として確実視することはできない。この写真をみるかぎり、このドルジェ、あるいはドルジェフと、G・I・グルジェフの伝えられている写真とを比較すると、同一人物のものとは認めがたい。
Osho のアルファベットに従えば、グルジェフは「何年間もチベットにいた」し、「チベットどころか、何年間もラサの宮殿に住んでいた」という。グルジェフは多重人格者的なところがあり、また変装の達人でもあったという。この写 真がグルジェフでは「ない」と断定することは、まだまだ早計だ。
第三シリーズは「生は<私が存在する>ときにのみ真実である」で、長いプロローグとイントロダクション、ニューヨークのオレージのグループのメンバーになされた5つの講話、そして「人間の内的世界と外的世界」から成る。文章は第一シリーズにもまして極度に難解になる。この中で彼は、それまでのワークの経緯を詳しく述べ、それが成功しなかった理由を述べつつ新しいワークの方向を模索している。 p603
この「奇蹟を求めて」が発行された1980年初頭にはこのグルジェフ三部作は日本語訳がなかったが、その後すでにすべて翻訳されている。
-
グルジェフ伝 神話の解剖 2009.01.14
-
ミルダッドの書<1> ミハイル・ナイーミ 2009.01.13
-
グルジェフ・ワーク 生涯と思想 2009.01.12 コメント(1)
PR
Freepage List
Category
目次
(6)22番目のカテゴリー
(49)バック・ヤード
(108)osho@spiritual.earth
(108)mandala-integral
(108)agarta-david
(108)スピノザ
(108)環境心理学
(108)アンソロポロジー
(108)スピリット・オブ・エクスタシー
(108)マーケットプレイス
(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2
(108)チェロキー
(108)シンギュラリタリアン
(108)レムリア
(108)2nd ライフ
(108)ブッダ達の心理学1.0
(108)マルチチュード
(108)シンギュラリティ
(108)アガルタ
(108)ネットワーク社会と未来
(108)地球人スピリット
(108)ブログ・ジャーナリズム
(108)Comments




