PR
X
Comments
Category
カテゴリ未分類
(191)英語・言葉
(33)長女はっち☆(大4)
(117)次女☆ヤッピー☆(専門2年)
(116)三女わっち☆(高2)
(369)ポンチョ♪
(535)PTA関連
(140)HP作成用語を英語で検証
(16)介護関連
(160)発達障害関連
(140)我が家の日常
(201)職場での子どもたちとの日常
(226)学習の工夫
(10)本の紹介
(45)どうでもいい話
(25)料理
(36)LD児にやさしいグッズ
(13)子どもの言葉
(5)親の会
(21)良かったもの
(3)ちょっとした話
(3)Freepage List
一枚目の葉っぱ

お勧め洋書(英語)・英語版翻訳書16冊

英語参考書(25冊)

英語辞書(10冊)

お勧め本(英語以外)(22冊)

お勧めメルマガ(英語)(5本)

お勧めメルマガ(英語以外)(3本)

お勧めビデオ・DVD(英語学習用)3点

お勧めビデオ・DVD(その他)

Diaries

Diaries2

Diaries3

HP作成用語を英語で検証 目次
二枚目の葉っぱ

アトピーとアレルギー

アレルギー食品取り扱い店(2店)

アレルギーに 試した療法(患部編)

アレルギーに試した療法(サプリメント編)

アレルギーの ためのグッズ

LDについて (まえがき)

LDとは?

LD関連本 (40冊)New!

教材・グッズ(24点)New!

サプリメント(2種3点)

学習お役立ちサイト集

小さな工夫シリーズ

サプリメント

学習の工夫 もくじ

学習の工夫#1

学習の工夫#2
三枚目の葉っぱ

炊飯器で作るケーキ

ホットケーキミックスでクッキー

ヨーグルトドリンク

紫芋のプリン

きなこ飴
四枚目の葉っぱ

H's Gallery

Y's Gallery

W's Gallery

cho

私が飲んでるサプリメント
キリ番ゲッターさん!

カウプレ置き場

ダウンロードお持ち帰り方法

素材を使用するときの注意

カウプレの文字入れ方法

いただきもの

お世話になっている素材屋さん
はじめにお読み下さい
テーマ: 軽度発達障害と向き合おう!(2969)
カテゴリ: 発達障害関連
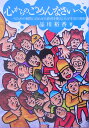
中央法規 刊
品川 裕香 著
副題が
「一人ひとりの個性に合わせた教育を導入した少年院の挑戦」
と,あります。
これは,宇治少年院での取り組みを丁寧に取材したものです。
この少年院に入所している少年達は中学生の年代です。
以前の少年院の矯正教育では,再犯率を低下させることができなかったのに,軽度発達障害の教育法や視点を導入することによって,効果的な教育ができるようになり,再犯率も低下して行ったと言う実践記録です。
少年院に入所している子ども達がみな発達障害と言うわけではありませんが,LD・ADHD・アスペルがー症候群などの「傾向を持つ」子ども達が半数くらいいるというのです。
はっきりと診断されなくても,認知に偏りが見られると言う視点で,それに合った指導方法の改革をしたことで,指導の入りにくかった子ども達が,変わっていったと言うのです。
ここで注意しなくてはいけないのは,そういった傾向の子ども達が,直ちに犯罪を犯すことになると言っているのではありません。
本書の中にも再三出てきますが,それは因子の一つであって,それだけで危険と言うことではなく,他の色々な因子が重なることが問題を引き起こすことにつながると言うことです。
実際に目の前の子ども達に合った指示の出し方を工夫するにあたって,聴覚処理が苦手な子や,視覚処理が苦手な子など,一人ひとり困難なことが違うのに,一斉に一方的に指示を出すだけでは,理解ができず,理解ができないから行動できない。
と言う事に気づいたことが,この少年院の原点になります。
まさに特別支援教育の実践です。
アメリカでも少年院でLD教育的アプローチを始めている地域があるそうです。
そのLD向けメソッドを開発した教育企業のスタッフの一人の言葉を要約すると,次のようになります。
私達はそういった子ども達のことを発達障害と言わずに,’teaching disability’(指導障害)だと捉えます。つまり 「指導のされ方」に問題がある のであって,一人ひとりの認知に応じた指導方法を実践すれば,問題は最小限に抑えることができる。子ども達が抱える問題は, 子どもの側の問題ではなく,教育する側の問題だと捉えている。
すばらしい発想と実践です。
とにかく,この本を一読することを強くお勧めしたいです。
私ももう一度読み返したいと思います。
特学**学級の先生に,今こう言う本を読んでいることを話したら,
「読み終わったら,ぜひ貸して!」
と言われたので,とりあえず月曜日に持っていくつもりです。
全国の先生方にも読んで欲しいくらいです。
素材: ももかん
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[発達障害関連] カテゴリの最新記事
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









