2015年01月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-

ユゴー『レ・ミゼラブル』(全5巻、新潮文庫、佐藤朔訳)
■ユゴー『レ・ミゼラブル』(全5巻、新潮文庫、佐藤朔訳)わずか一片のパンを盗んだために、19年間の監獄生活を送ることになった男、ジャン・ヴァルジャンの生涯。19世紀前半、革命と政変で動揺するフランス社会と民衆の生活を背景に、キリスト教的な真実の愛を描いた叙事詩的な大長編小説。本書はその第一部「ファンチーヌ」。ある司教の教えのもとに改心したジャンは、マドレーヌと名のって巨富と名声を得、市長にまで登りつめたが……。(アマゾン内容案内)◎人道主義の代表的な作品 幼いころに『ああ無情』というタイトルの本を、読んでいる人は多いと思います。最近の児童書では『レ・ミゼラブル―ああ無情 (新装版) 』 (講談社青い鳥文庫)となっていました。岩波少年文庫では『ジャン・ヴァルジャン物語』 (上下巻)というタイトルになっています。 文藝春秋編『少年少女小説ベスト100』(文春文庫ビジュアル版)では、『レ・ミゼラブル』が第17位になっています。『レ・ミゼラブル』は子ども向けとしても、不動の地位を獲得している作品といえます。また『レ・ミゼラブル』は、「銀の食器」のエピソードのみに編集され、小学生向けに教科書に掲載されてもいるようです。 新潮文庫で全5巻という長い作品ですので、つまみぐいなら子どもの教科書や児童書にふれてみてください。なぜなら『レ・ミゼラブル』では、つぎのくだりが骨格ですので。 ◎叙事詩的な小説 1815年、司教館をひとりの男が訪れます。男は46歳のジャン・ヴァルジャン。貧困に耐えられずパンを盗み、その罪で19年も服役していました。出獄した彼にたいして世間は冷たく、宿泊も食事もままならない状況でした。 そんな彼を、76歳の司教は暖かく迎えてくれます。しかしジャン・ヴァルジャンは、司教が大切にしていた銀の食器を盗んでしまいます。翌朝、彼を捕らえた憲兵にたいして、司教は「食器は私が与えたもの」といってかばいます。 町をでたジャン・ヴァルジャンは、貧しい少年と出会います。そして少年の全財産である銀貨1枚を強奪します。少年は泣きながら走り去ります。少年の後姿を見送りながら、ジャン・ヴァルジャンの胸のなかでなにかが炸裂します。彼は号泣し、突然さとります。それまで社会にたいして憎悪をいだいていたジャン・ヴァルジャンは、まじめな人間として生きていくことを誓います。 『レ・ミゼラブル』について、『新潮世界文学小辞典』では、次のように解説しています。 ――著者が抱いていた人道主義や、「この世に絶対的な悪は存在しない」という彼一流の楽観的な世界観、それにキリスト教的な愛をまじえて書き上げた作品である。主人公の超人的な性格、激しくうたい出すような調子によって、叙事詩的な小説になっている。 人道主義とは「人種間や階級間の差別をなくし、人類全体の幸福の実現を最大の目的とするもの」です(三省堂新明解国語辞典)。ロマン・ロラン(推薦作『ジャン・クリストフ』全5巻、岩波文庫)や日本では山本有三(推薦作『女の一生』上下巻、新潮文庫絶版)などが、人道主義作家といわれています。 あたかも「V」の字のようにジャン・ヴァルジャンの贖罪の物語は、「銀の食器」と「貧しい少年の銀貨」以降からはじまります。悪から善。まるで別の物語のように、新たな幕があけられるのです。 ◎前科者は社会復帰が認められていない時代 数年後、ジャン・ヴァルジャンはマドレーヌと名前を変えて、実業家となります。彼はかっての司教のように私財を投げ出して、市や貧しい人々のために寄付をします。学校をつくり、病院をつくります。市を豊かにした功績により、彼は市長に任命されます。 前科者は社会復帰が認められていない時代です。ある日ジャン・ヴァルジャンは、馬車の下敷きになった老人を助けます。とてつもない怪力で、馬車をもちあげたのです。それを警視のジャヴェールに、見られてしまいます。警視は少年から銀貨を奪った罪などで、ジャン・ヴァルジャンを執拗に追っていました。ジャヴェールは、マドレーヌ市長がジャン・ヴァルジャンではないかと疑います。 そのころある前科者が、ジャン・ヴァルジャンだとして捕えられます。それを知った本人は一晩悩みぬいたすえに、自らジャン・ヴァルジャンであると正体を明かします。彼は捕えられます。しかし彼には、一刻も早く助けなければならない人がいました。 不幸な星のしたに生まれた、コゼットという娘を救いださなければなりません。それは死の床で交わした、母親との約束でした。ジャン・ヴァルジャンは脱獄を試み、コゼットを救出します。彼はコゼットとともに、パリでひっそりと暮らします。コゼットは美しい娘に成長します。 しかし警視ジャヴェールは、追跡の手を休めません。ジャン・ヴァルジャンとコゼットが散歩しているとき、マリウスという青年に出会います。コゼットはマリウスに恋をします。ジャン・ヴァルジャンは嫉妬に苦しみ、マリウスを憎悪します。 そして物語は終局へと向かいます。ここから先については、触れないほうが賢明かと思います。 鹿島茂に『「レ・ミゼラブル」百六景』(文春文庫)という著作があります。19世紀の美麗な木版画230葉から106のシーンを抽出してはさみこまれた、『レ・ミゼラブル』の解説書です。『レ・ミゼラブル』をお読みになった人には、感動を新たにしてくれるすばらしい1冊だと断言できます。(山本藤光:2014.10.11初稿、2018.01.03)
2015年01月31日
コメント(0)
-
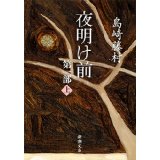
島崎藤村『夜明け前』(全4巻、新潮文庫)
山の中にありながら時代の動きを確実に追跡する木曽路、馬籠宿。その本陣・問屋・庄屋をかねる家に生れ国学に心を傾ける青山半蔵は偶然、江戸に旅し、念願の平田篤胤没後の門人となる。黒船来襲以来門人として政治運動への参加を願う心と旧家の仕事にはさまれ悩む半蔵の目前で歴史は移りかわっていく。著者が父をモデルに明治維新に生きた一典型を描くとともに自己を凝視した大作。(アマゾン内容案内)■島崎藤村『夜明け前』(全4巻、新潮文庫)◎木曽路はすべて山の中である――木曽路はすべて山の中である。あるところは岨(そば)づたいに行く崖の道であり、あるところは数十間の深さに臨む木曽川の岸であり、あるところは山の尾をめぐる谷の入口である。一筋の街道はこの深い森林地帯を貫いていた。(本文より) これは『夜明け前』の冒頭部分です。あまりにも有名な書き出しで、私は「知っている、知ってるぞ」との軽いノリで全4冊に挑みました。ところが、木曽路は、楽には進めませんでした。物語の展開が遅く、途中から歴史書を読んでいるような錯覚を覚えてしまったのです。 途中で何度も、読むのをやめようと思いました。こんなに退屈な作品だったのなら、『破戒』(新潮文庫)をとりあげるほうが無難だったかな、と後悔もしました。しかし島崎藤村の長編『夜明け前』(全4巻、新潮文庫)を読まずして、代表作を選ぶことに恥じる気持ちがありました。 篠田一士が『21世紀の十大小説』(新潮文庫)にあげた作品です。日本にはドストエフスキーやトルストイのような長編小説が存在しません。世界に通用する唯一の長編小説として、選ばれた作品が『夜明け前』なのです。 島崎藤村は『若菜集』(新潮文庫)に代表されるように、元詩人でした。「まだあげ初めし前髪の/林檎のもとに見えしとき/前にさしたる花櫛の/花ある君と思ひけり」(『藤村詩抄』岩波文庫の「初恋」より)というフレーズは、だれもが知っていると思います。 島崎藤村は、詩人から散文家への転身をはかりました。文章修行として、エッセイに挑みました。そして生まれたのが、『千曲川のスケッチ』(新潮文庫)でした。 詩人だったゆえに、『夜明け前』の文章は巧みでした。島崎藤村が目指したのは、時代の変化に色あせない文章を書くことでした。美文体は風化しやすい。そんな信念から、エッセイによる文章修行をおこなったのでしょう。 島崎藤村の生涯は、周到に準備をされたものでした。敬愛する花村太郎の著作から引用してみたいと思います。島崎藤村は「人生を7年くぎりで考えよ」と、自らの生涯を振り返った遺訓を残しています。(以下はじめ) 1.二〇歳で明治学院を卒業、女学校教員――失恋による関西漂白の旅、2.二六~二八歳で第一詩集『若菜集』刊行(詩人として確立)――『一葉舟』『夏草』刊行――信州の小諸義塾へ赴任、足かけ七年ここで過ごして、3.三四~三五歳では、東京へ出てきて『破戒』を刊行(小説家への転向)、4.四二歳でフランスへ、5.四八歳で『新生』発表、6.それから五八歳で書きはじめた『夜明け前』を足かせ七年間で完成させる。 (花村太郎『知的トレーニングの技術』(JICC出版局、P7より) しかしその人生は、ゆううつそのものだったようです。『夜明け前』のモデルだった実父は、郷里で牢死していますし、母は過ちで生を受けた人だったのです。『新生』(上下巻、新潮文庫)は姪との不倫を描いた作品です。◎ズーム機能のあるカメラ『夜明け前』は、島崎藤村の父親をモデルにした作品です。島崎藤村が生まれた家は、木曾街道馬籠宿の本陣・問屋・庄屋を兼ねた旧家で、父親は17代目の当主でした。島崎藤村は、東京の泰明小学校へ入学しました。それ以来、実家とは離れて暮らしています。『夜明け前』の舞台に木曾街道馬籠を選んだのは、故郷喪失者たる島崎藤村の、ふるさと回帰への熱い思いからでした。 主人公の青山半蔵は、馬籠の本陣・問屋・庄屋を兼ねた家の長男として生まれます。この設定も、父親・青山吉左衛門が17代目の当主であることも、現実とまったく同じです。青山半蔵は、生後間もなく生母と死別します。 舞台の馬籠は木曾11宿の1つです。青山半蔵が生まれたのは、大名などが泊まるもっとも格式の高い本陣でした。『夜明け前』には、多くの高名な固有名詞や史実が登場します。 嘉永6年、浦賀に黒船が来航したとの噂が、半蔵の耳に入ります。当時半蔵は23歳。妻籠宿の本陣の娘・お初と結婚しています。結婚後、半蔵は江戸へ出て、国学者・平田篤胤や本居宣長に学びます。 明治維新のころを、島崎藤村は青山半蔵の生涯と重ねてみせます。父親の背中を見つめつづけていた半蔵。結婚し、こどもを授かった半蔵。そして、半蔵の暮らす木曾街道をとおる人々。本陣に泊まる人々。島崎藤村は多くの人群れを描き、青山半蔵を浮かびあがらせます。活気にあふれる明治の人々。ペリーの来航、明治維新、大政奉還、東京遷都、廃藩置県、華族令、開国を迫る外国人。幕府の動乱と村人の生きるための闘い。『夜明け前』は壮大なドラマだったのです。 ――『夜明け前』というのは、時に応じて、かって読んだときには気づかなかったような描線が構図のなかから突然現れてくるといった不思議な奥行きをもつ重層的な作品だ。(朝日新聞学芸部編『読み直す一冊』の井出孫六「夜明け前」より) 島崎藤村『破戒』(新潮文庫)と夏目漱石『こころ』(新潮文庫)が、明治以降の小説で売れている双璧のようです。『破戒』を紹介しているガイドブックは数多くあります。しかし『夜明け前』は長すぎるがゆえに、敬遠されがちです。私も苦労して読みました。ちょっと重厚ですが、日本を代表する長編小説に挑戦していただきたいと思います。 島崎藤村の作品は、映画監督になった気持ちで読むのがいいようです。これは加賀乙彦(推薦作『宣告』全3巻、新潮文庫)が教えてくれました。『加賀乙彦が語る島崎藤村』(「カセット文芸講座・日本の近代文学2」C・B・エンタープリズ、絶版)で、加賀乙彦はつぎのような解説をしてくれています。カセットで聞いたことの箇条書きになりますが、おもしろい読み方だと感心しました。――島崎藤村の作品は、全体的な展望からはじまる。『破戒』もそうだが、カメラを高いところにすえて映し出し、少しずつ登場人物に迫る。――『破戒』は、家の構造、住人、一人の人物へとズームアップされている。――『夜明け前』では、主人公の半蔵に焦点をあてるのは、最後の方になる。(引用おわり) なるほどと思います。ズーム機能のついたカメラをもって、『夜明け前』の美しい文章を楽しんでいたたきたいと思います。ドストエフスキー(推薦作『カラマーゾフの兄弟』全5巻、光文社古典新訳文庫)やトルストイ(推薦作『戦争と平和』全4巻、新潮文庫)の作品のような感動を覚えることは、保証させていただきます。◎ちょっと寄り道『夜明け前』は、司馬遼太郎『街道をゆく』(全43冊、朝日文庫)の影響を受けたという論評もあります。残念ながら、司馬遼太郎『街道をゆく』は読んでいません。また小説の構造は、トルストイ『戦争と平和』と似ているという人もいます。しかしそれらは、些細なことです。(山本藤光:2010.06.14初稿、2014.10.04改稿)
2015年01月30日
コメント(0)
-
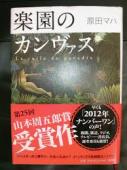
原田マハ『楽園のカンヴァス』(新潮文庫)
ニューヨーク近代美術館のキュレーター、ティム・ブラウンはある日スイスの大邸宅に招かれる。そこで見たのは巨匠ルソーの名作「夢」に酷似した絵。持ち主は正しく真贋判定した者にこの絵を譲ると告げ、手がかりとなる謎の古書を読ませる。リミットは7日間。ライバルは日本人研究者・早川織絵。ルソーとピカソ、二人の天才がカンヴァスに篭めた想いとは―。山本周五郎賞受賞作(「BOOK」データベースより)原田マハ『楽園のカンヴァス』(新潮文庫)◎原田マハが化けた 原田マハを読みはじめたきっかけは、原田宗典(推薦作『優しくって少しばか』集英社文庫)の妹がデビューしたという情報からでした。さっそく「日本ラブストーリー大賞2006」に輝いた『カフーをまちわびて』(初出2006年宝島社、宝島文庫)を読んでみました。残念ながら「山本藤光の日本現代文学125+α」には、入れられる作品ではありませんでした。軽いな、というのが素直な感想です。その後何冊か読んでみましたが、私の評価は同じでした。 ある日ともだちから「原田マハって知っている?」と質問されました。「うん、何冊か読んだけれど……」とつまらなそうに答えました。「『楽園のカンヴァス』はいいぞ。奥泉光の『シューマンの指』を超えているよ」と、ともだちは目を輝かせていいました。私は書評を書くたびに、本好きのともだちに送りつけています。ともだちが胸を張って、原田マハの名前をいったのは、私が奥泉光『シューマンの指』(講談社文庫)を絶賛した直後のことでした。 読んでみました。驚愕しました。これがあの原田マハだろうか、と疑ったほどでした。原田マハが化けた、と思わず叫んだほどです。『楽園のカンヴァス』(新潮文庫)はのちに、「本屋大賞2013」の第3位に選ばれました。 私が若い作者を追いかけるのは、「化ける」瞬間を見届けたいためです。以下期待の女流作家が、化けたときをならべてみます。2段で紹介していますが、上の段がデビュー作です。【大島真寿美】(デビュー作から19年目)1992年『宇の家』(角川文庫)2011年『ピエタ』(ポプラ文庫)【赤坂真理】(デビュー作から15年目)1997年『蝶の皮膚の下』(河出文庫)2012年『東京プリズン』(河出文庫)【金原ひとみ】(デビュー作から7年目)2004年『蛇にピアス』(集英社文庫)2011年『マザーズ』(新潮文庫)【原田マハ】(デビュー作から4年目)2008年『カフーをまちわびて』(宝島文庫)2012年『楽園のカンヴァス』(新潮文庫) 原田マハが「化けた」のは、異例の早さでした。不覚にも私はその予兆すら感じとれなかったのです。反省。◎なんて下手くそなんだろう 主人公・早川織絵(43歳)は、若いころにパリで美術の研究をしていました。未婚で出産して帰国し、大原美術館の監視員をしています。ある日大手全国紙が、アンリ・ルソー展を企画しました。目玉は最晩年に描かれた「夢」の展示でした。 ニューヨーク美術館に貸し出しを依頼すると、交渉役としてオリエ・ハヤカワをあてるようにいってきました。返信者はチーフ・キュレーターのティム・ブラウン。早川織絵とティム・ブラウンは、17年前にアンリ・ルソーの「夢をみた」の真贋を鑑定するため、7日間の緊張する時間を共有したことがあります。7章からなるルソーの日記を毎日1章ずつ読み、「夢をみた」の謎に迫るのです。 ストーリーにふれるのは、原田マハの描いたピュアなキャンバスに泥を塗るようなものです。かわりに本書が書かれた、いきさつについてふれておきます。 原田マハは小学2年のときに、倉敷美術館でピカソの「鳥籠」を見て衝撃を受けています。「なんて下手なんだろう。これならあたしでも描ける」と思いました。大学3年のときに、アンリ・ルソの画集をみて「なんて下手なんだ」と思いました(「波」2012年2月号を参照しました)。それらのきっかけから、原田マハは『楽園のカンヴァス』の誕生秘話をつぎのように語っています。――ルソーの作品世界とミステリアスな人生を、自分の手でつまびらかにしたいといった欲望。主人公の二人が少しずつ読み解いていくルソーの謎は、私自身が知りたかったことでもあります。(「波」2012年2月号のインタビュー記事より)『楽園のカンヴァス』は、原田マハが歩んだ人生の集大成だったのです。これまで高い評価をしてきた奥泉光『シューマンの指』よりも、ひとつ高い場所に『楽園のカンヴァス』をおくことにしました。(山本藤光:2014.08.08初稿、2015.01.28改稿)
2015年01月29日
コメント(0)
-
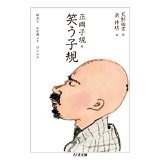
正岡子規『笑う子規』(ちくま文庫、天野祐吉編・南伸坊絵)
二万四千ほどある俳句の中から天野さんが選びコメント(これがまたユニーク)をつけ、南伸坊さんが粋な絵を描いた子規の可笑しな俳句集。正岡子規は冗談好きの快活な若者でもあった。(「BOOK」データベースより)■正岡子規『笑う子規』(ちくま文庫、天野祐吉編・南伸坊絵)◎おかしくて楽しい本 正岡子規について、短くまとめられた文章があります。まずは病気と子規について、おさらいしておきたいと思います。――子規が喀血したのは二十一歳で、漱石との交友が始まった二十二歳のときはすでに体調が悪く、したがって漱石は、まったく健康状態にある子規を知らない。三十歳で腰痛の手術をして、三十一歳で病床につき、三十五歳で生涯を終える子規は、つねに死の影と対座していた。(嵐山光三郎『追悼の達人』(中公文庫より) 正岡子規については、『病床六尺』(岩波文庫)を推薦本としてリストアップしていました。しかし正岡子規『笑う子規』(ちくま文庫、天野祐吉編・南伸坊絵)を読んで、正岡子規を伝えるにはこれしかないと確信しました。タイトルどおり、とにかくおかしくて楽しい本です。正岡子規というと、病気と背中合わせの歌人のイメージがあります。本書はそんなイメージを払しょくしてくれます。 正岡子規は司馬遼太郎『坂の上の雲』(全8巻、文春文庫、「山本藤光の文庫で読む500+α」推薦作)の、主人公の1人として登場します。最近では伊集院静が、『ノボさん・小説正岡子規と夏目漱石』(講談社2013年)という著作を刊行しています。それらを読むと、死を覚悟した正岡子規の毅然とした態度にふれることができます。正岡子規は衰えつつある自身を、客観的に見つめつづけた卓越した人でした。『病床六尺』には、少しも暗い部分も感傷的な記述もありません。 正岡子規は、野球殿堂入りをしている人でもあります。バッター、ランナーなどの外来語を、「打者」「走者」と訳した功績をたたえられてのものです。「正岡子規記念球場」(東京都台東区上野恩賜公園内)という名の、草野球用施設もあるようです。「草茂みベースボールの道白し」 この句は本書にはありません。本書を引いた池内紀の解説を紹介させていただきます。――正岡子規は若いころ、当時はじまったばかりの野球に熱中していた。主にキャッチャーだった。(中略)原っぱでやっていて、ランナーの走ったところの土がむき出しになっていたのだろう。(池内紀『文学フシギ帖』岩波新書より) 本書の編集者である天野祐吉(1933-2013)は、松山市立子規記念博物館の名誉館長でもあります。天野祐吉は本書について、こんなふうに書いています。――凄まじい痛みにさいなまれながらも、彼の想像力が生んだ世界には、生き生きとした生気があった。そこから生まれる明るさがあった、とぼくは思っています。そう、ぼくの中にいる子規さんは、「明るい子規さん」「笑う子規さん」なんです。(本書「はじめに」より) 正岡子規は病床のなかで、俳句や短歌の革新にも挑みました。俳誌「ホトトギス」の編集もし、新人の発掘もしました。与謝蕪村は子規が見出した俳人です。正岡子規と夏目漱石との関係についても、紹介させていただきます。――多くの弟子に囲まれた漱石だが、先生と呼ぶ人が一人いた。それは一高以来の友人でもある正岡子規だ。漱石のデビュー作『吾輩は猫である』は、正岡子規が主宰した「ホトトギス」に連載されたものである。漱石は俳人でもあった。多くの句を残し、子規の指導を仰いだ。子規は写生俳句を唱え、近代俳句を確立した人だから、漱石が師と仰いだのは当然のことだと思う。(新藤兼人『老人読書日記』岩波新書P96より)◎裂け目とズレ「柿くえば鐘がなるなり法隆寺」 だれもが知っている句です。修学旅行で法隆寺を訪れた生徒は、必ずこの句を口ずさんでいます。天野祐吉はこの句につぎのような解説をつけています。なるほど、と思いました。――子規のこの句を成り立たせているのも、おかしみの感情です。「柿を食べる」ことと「鐘が鳴る」ことの間には、なんの必然的な関係もないし、気分の上の関連もない。つまり、二つのことの間には、はっきりした裂け目が、ズレがあります。/もともとおかしみというのは、裂け目やズレの間からシューッと吹き出してくるものだとぼくは思っているのですが、(後略)(天野祐吉「はじめに」より)『笑う子規』は「新年」「春」「夏」「秋」「冬」という構成で、それぞれに20句ほどがそえられています。少しだけ紹介させていただきます。「蒲団から首出せば年の明けて居る」――ひょいと蒲団から顔を出したら/年が明けていたなんて、/落語の八っつぁんみたいに粋だろ?/ほんとうは蒲団から出られない病人なんだけど、/ここは正月らしく、粋に気取らせてくれよ。(天野祐吉・文より)「おそろしや石垣崩す猫の恋」――猫の恋ははげしい。/とくに雄猫の執念はすさまじい。/「恋猫の眼ばかりに痩せにけり」(漱石)/一念岩をも通す。石垣くらい屁の河童だ。(天野祐吉・文より)『笑う子規』に収載されている最後の句を引かせていただきます。この句は「死の前日、明治三十五年九月十八日に書かれた」(『ドナルド・キーン著作集・第1巻』新潮社P289より)ものです。「糸瓜(へちま)咲て痰のつまりし仏かな」――みてごらん、あれがわしだよ。/ことしも糸瓜は咲いたのに、/水を取るより先におさらばしちまった。/痰をつまらせて。/息をとめて。/痛みともおさらばだ。/やれやれ、あれがわしだよ。(天野祐吉・文) 坪内稔典『正岡子規の〈楽しむ力〉』(NHK出版生活人新書)のカバーに、子規のベースボール写真があります。子規の写真はいずれも横向きのものばかりですが、カバー写真はしっかりとレンズをみています。(山本藤光:2015.01.26)
2015年01月28日
コメント(0)
-
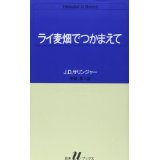
サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』(白水Uブックス、野崎孝訳)
インチキ野郎は大嫌い! おとなの儀礼的な処世術やまやかしに反発し、虚栄と悪の華に飾られた巨大な人工都市ニューヨークの街を、たったひとりでさまよいつづける16歳の少年の目に映じたものは何か? 病める高度文明社会への辛辣な批判を秘めて若い世代の共感を呼ぶ永遠のベストセラー。(アマゾン内容紹介)■サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』(白水Uブックス、野崎孝訳)◎文体でひっぱる2010年2月2日、共同通信の記事「世捨て人ではなかった」という、サリンジャー死去のニュースを読みました。長いのですが、興味深い記事なので全文を紹介します。(引用はじめ)――軽食堂で食事を取り、気軽にあいさつを交わすなど「もの静かな田舎の人」で世捨て人ではなく、住民の間では私生活を口外しないことが暗黙の了解だった。同氏は1953年ごろに東部ニューハンプシャー州の田舎町、コーニッシュに転居、死去まで人口約1700人のこの町で過ごした。 サリンジャー氏は町で「ジェリー」と呼ばれ、数年前まで選挙や町民会議にも参加するなど完全に「町の住民」だった。買い物はほとんど町の雑貨店で行い、一人で軽食堂で食事を取り、「あいさつにも気軽に応じる気さくな人」。自宅近くに住む子供と学校の話をし、自宅の庭でそりをしたいという頼みにも快く応じていたという。 教会の夕食会を気に入り、毎週土曜に12ドル(約1090円)のローストビーフを食べに来ていたが、昨年12月が最後だった。(引用おわり)サリンジャーは、ニューヨークのマンハッタンで生まれています。彼の独特の文体を、都会生まれだからと書いている批評家もいます。私は生まれと文体は、必ずしも一致しないと思っています。むしろサリンジャーは、16歳の主人公の内なる感情を、この文体でしか書くことができなかったとみるべきでしょう。『ライ麦畑でつかまえて』(白水Uブックス、野崎孝訳)を読むのは、今回で2度目です。2度とも野崎孝の訳で読みました。村上春樹訳がでたので、それも読んでみました。タイトルもカタカナで『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(白水社)となっていました。翻訳作品って、訳者によってまったく異なるものになります。そんな実感をもっています。『ライ麦畑でつかまえて』は、文体で読ませる作品です。どちらを選ぶかは、個人の好みの問題になります。私は村上訳よりも、どっしりとした野崎訳の方が好きです。『ライ麦畑でつかまえて』の文体の大切さにふれた説明を引用したいと思います。。――『ライ麦畑でつかまえて』は、成績不良で退学になった高校生の言動を通して、その清純犀利な感覚と思考がとらえた人間社会の「いやらしさ」を描いた作品だが、50年代ハイティーンの用語を的確に写しとっていると評される文体のさわやかで歯切れのよい語り口と相まって、圧倒的な人気を呼び、ベストセラーになるとともに、ティーン・エージャーの心理の研究資料として学校の教材に利用されたりするまでになっている。(「新潮世界文学小辞典」より) 翻訳は時とともに、陳腐化するといわれます。そんな意味では、新しい訳書のほうが、時代にマッチしているかもしれません。このあたりは好みの問題ですから、だれの訳書がいいと強要するつもりはありません。◎揺れる少年の心主人公のホールデン・コールフィールドは、成績不振で名門高校を3度目の除籍となります。彼は自宅のあるニューヨークへ戻りますが、両親の逆鱗にふれることを恐れて、3日間街をさ迷い歩きます。『ライ麦畑でつかまえて』は、クリスマス休暇直前の3日間を、少年の日常的な言葉でつづられた青春物語です。ホールデン少年は、タバコを吸い大酒を飲みます。背伸びしたそうしたおこないとは裏腹に、人を恋しがる幼い感覚をもってもいます。大人の社会にたいしての反発と、戸惑い揺れ動く感情の表現は、常に少年の肉声として描かれています。寂しさをまぎらわせるために、ホールデンは、売春婦、ポン引き、女ともだち、教師などに近づきます。しかし金と欺瞞に満ちた彼らは、彼の孤独感をいやしてはくれません。そのかわり彼は、修道女、こども、池のアヒルに親近感を抱くことになります。ケンカばかりしていた寮生活から抜けだしたものの、ホールデンは外社会でも自分の居場所を発見することができません。ホールデンはこの間、自分にとって唯一の理解者は妹のフィービーであることを実感します。相手の目に映っているのは、まぎれもない少年・ホールデンです。しかし彼は年齢を偽り、娼婦を部屋に迎え、バーに出入りもします。本人は大人を演じているつもりですが、いたるところで幼さが露見します。目いっぱい爪先立つと、やがて疲れて体が揺れる。そんな瞬間が微笑ましくもあります。最終的には自宅に戻り、唯一の理解者である妹・フィービーともケンカをしてしまいます。行き場を失ったホールデンは、ふたたび家を出ようと決心するのですが……。この場面は圧巻です。 懐疑、嫌悪、憎悪などの渦巻く汚水のなかから、突然少年はある感覚を抱くことになります。ちなみに「ライ麦畑でつかまえて」というタイトルは、スコットランド民謡「ライ麦畑で会うならば」から借りたものです。この曲は聴いたことがありませんが、本文中からその場面を拾っておきたいと思います。野崎歓訳と村上春樹訳をならべてみます。――子供がすてきだったんだよ。歩道の上じゃなくて、車道を歩いているんだ。縁石のすぐそばのところだけどね。子供はよくやるけど、その子もまっすぐに直線の上でも歩いていくような歩き方をしているんだな。そして歩きながら、ところどころにハミングを入れて歌ってるんだ。僕は何を歌ってんだろうと思ってそばへ寄って行った。歌ってるのは、あの「ライ麦畑でつかまえて」っていう、あの歌なんだ。(野崎歓訳P180より)――でもその子どもはなかなか良かったね。その子は舗道を歩かずに、車道を歩いていた。舗道の縁のすぐわきのところを歩いていたんだけどさ。彼はまっすぐな一直線をたどって歩こうと必死にがんばっていた。そういうのって小さな子どもがよくやるじゃないか。そしてそのあいだずっと唄を歌ったり、ハミングをしたりしているんだ。何を歌っているのか知りたくて、ぼくはその子の近くに寄ってみた。その子の歌っているのは、「ライ麦畑をやってくる誰かさんを、誰かさんがつかまえたら(If a body catch a body coming through the rye)」という歌だ。(村上春樹訳P191より) 2冊の訳書とも、すばらしい読後感でした。耳にしたことのない「ライ麦畑」のメロディが聴こえているように思われました。(山本藤光:2010.12.08初稿、2014.10.17改稿)
2015年01月27日
コメント(0)
-
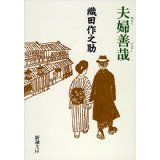
織田作之助『夫婦善哉』(新潮文庫)
芸者上がりと所帯を持った化粧品卸問屋の息子柳吉は、勘当され、家を出る。剃刀屋、関東煮(かんとだき)屋、果物(あかもん)屋、カフェーと転々と商売を変えるがちっとも長続きしない。こんな男になぜ蝶子は惚れるのか。たくましい大阪人の、他人には窺い知れない男と女の仲を描く『夫婦善哉』ほか、人間の切ない感情を見事に謳い上げた『木の都』など6編。早世が惜しまれる織田作之助の代表短編小説集。(アマゾン内容案内より)■織田作之助『夫婦善哉』(新潮文庫)◎無頼派の作家といわれているが 長編だとばかり思っていました。新潮文庫『夫婦善哉』には、表題作のほかに5つの短編が収められていました。織田作之助は短命の作家でした。文学活動は7年間とわずかで、その間に50編ほどの短編小説を書いています。 織田作之助は、1934年に第3高等学校(新制京都大学教養学部)に合格しています。しかし肺疾患で喀血し、療養生活を余儀なくされ退学しました。1935年宮田一枝と出会い同棲、のちに結婚しています。織田作之助に関する論文には、きまってこの2つの事例が載っています。彼の文学作品に、大きな影響を与えたできごとなのです。 織田作之助は、当初劇作家を目指していました。しかしスタンダール(推薦作『赤と黒』新潮文庫)の影響を受けて、小説家に転向しました。初期作品「雨」(収載されている文庫は見つかっていません)は、スタンダールの影響を強く受けており、のちに「青春の逆説」(岩波文庫)としてまとめられたようです。 織田作之助といえば「夫婦善哉」が代表作です。しかし私は初期作品、特に「俗臭」(『世相/競馬』講談社文芸文庫所収)を高く評価しています。この作品は、室生犀星の推薦で芥川賞候補となっています。 文学史のうえで織田作之助は、坂口安吾や太宰治とともに「無頼派作家」と呼ばれています。今回「夫婦善哉」のほか収載作5つの短編(「木の都」「六白金星」「アド・バルーン」「世相」「競馬」)を読んでみて、「無頼派作家」という呼称に違和感をもちました。 織田作之助の描く舞台の大半は、大阪になっています。人間模様のスケールも、こじんまりとしたものです。そのぶん、小説の構成はしっかりしています。劇作家志望だったのが、うなずける組立てなのです。いずれの作品も、結末が印象的でした。すべての作品は、どうしようもない男が主軸となっています。寄生虫のような、こんにゃくみたいな、流れに身をまかせる男。これが許されるのは、大阪の下町が舞台だからかもしれません。 文庫本の解説(青山光二、3高の1年先輩)によれば、戦後に書かれたのは「世相」と「競馬」だけとのことです。あとは戦中に執筆されています。織田作之助は戦争の影を、文学の舞台に引きずりこんでいません。それゆえ、「無頼派」といわれたのかもしれません。 織田作之助の著作に『可能性の文学』(初出1946年、岩波文庫)があります。まだ読んでいません。この著作のなかで織田作之助は、「こじんまりとまとまった私小説を批判している」(長谷川泉『戦後文学史』明治書院より引用)と書いています。思わず笑ってしまいましたが、織田作之助はそうした理想と戦いつづけたことだけは確かです。 晩年は病いに悩まされ、ヒロポンを打ちながら創作に打ちこみました。そして壮絶な死をとげます。織田作之助は「無頼派」と呼ばれる太宰治(推薦作『斜陽』新潮文庫)、坂口安吾(推薦作『堕落論』新潮文庫)と、同じ運命をたどったのです。◎大阪人にしか書けない『夫婦善哉』 蝶子は、うだつの上がらない天婦羅屋・種吉とお辰の娘です。店には客よりも、借金取りがくる数の方が多い状況でした。小学校を終えると、蝶子は奉公に出されます。父親は蝶子の手が赤ぎれて血がにじんでいるのを見て、家へ連れ戻します。そしてすぐにおちょぼ(芸者の下地っ子)としてお茶屋にやってしまいます。種吉の手元に50円の金が入りましたが、すぐに借金で消えてしまいます。 蝶子は17歳のときに、芸者になります。陽気で座持ちのいい芸者として、たちまち売れっ子となりました。そんな蝶子のところに、安化粧品問屋の息子・柳吉が通ってきます。妻子のある柳吉は父親に勘当されて、一本立ちした蝶子のところに転がりこんできます。柳吉はおいしいものに目がなく、蝶子を安いうまいもの屋へひんぱんに連れてゆきます。 2人は剃刀屋、関東煮屋、果物屋、カフェなどの商いをしますが、どれひとつとして軌道に乗せられません。蝶子はヤトナ(出張中居)をしながら、懸命に家計を支えます。意思薄弱な夫を、蝶子は気丈に支えます。 この構図は、またたく間に崩れてしまいます。そのあたりについては読んでのお楽しみ、ということにさせてもらいます。とんでもない男・柳吉の破天荒ぶり。それを柳に風と受け止める蝶子。2人のやりとりもおもしろいのですが、この作品には漫才でいう間(ま)が存在しています。行間に2人の息遣いを感じられるほど、みごとなやりとりが展開されます。2人の関係は、つぎのように表現されています。――柳吉は二十歳の蝶子のことを「おばはん」と呼ぶようになった。「おばはん小遣い足らんぜ」そして三円ぐらい手に握ると、昼間は将棋などして時間をつぶし、夜は二ッ井戸の「お兄ちゃん」という安カフェへ出掛けて、女給の手にさわり、「僕と共鳴せえへんか」そんな調子だった……。(本文より) 文庫本の解説で青山光二は、織田作之助を「結末が浮かばなければ書かない作家」と語っています。この点については、織田作之助自身が「郷愁」(「青空文庫」で読むことができます)のなかで、そう書いているそうです。なるほど『夫婦善哉』のラストはすばらしいものでした。(山本藤光:2009.09.23初稿、2014.09.05改稿)
2015年01月26日
コメント(0)
-
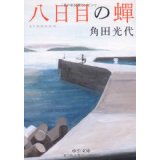
角田光代『八日目の蝉』(中公文庫)
逃げて、逃げて、逃げのびたら、私はあなたの母になれるだろうか…。東京から名古屋へ、女たちにかくまわれながら、小豆島へ。偽りの母子の先が見えない逃亡生活、そしてその後のふたりに光はきざすのか。心ゆさぶるラストまで息もつがせぬ傑作長編。第二回中央公論文芸賞受賞作。(「BOOK」データベースより)■角田光代『八日目の蝉』(中公文庫)◎「純推文学」の隆盛 角田光代の代表作は、『対岸の彼女』(文春文庫)として書評を発信してきました。ところが角田光代はいとも簡単に、もう一段高いところに立ってしまいました。『八日目の蝉』(中公文庫)は発売時から評判となり、すでに映画化もされています。文庫本の帯(初版)には、4月29日公開と刷り込まれ、割引券までついていました。「山本藤光標茶六三500+α」は、1作家1作品の紹介を原則としています。しかし若手作家はときどき、書評の差し替えをすることになってしまいます。うれしい悲鳴です。おおいに悩みましたが、角田光代の推薦作を『八日目の蝉』に切り替えることにしました。『対岸の彼女』を抹消するのはしのびがたく、「+α」作品として残させてもらいます。 吉田修一『悪人』(朝日文庫)が評判になったとき、私は『最後の息子』(文春文庫)を推薦作として、書評を発信していました。世間の評判ほど、私は『悪人』を評価していませんでした。サスペンスに逃げたな、という思いこみもあり、辛口になってしまったのかもしれません。ただし、純文学作家・吉田修一という既成概念を除去して読めば、味わい深い高水準な作品なのでした。 角田光代の『八日目の蝉』も、やはり「逃げたな」との思いこみで読みました。ところが反発は瞬時に溶解してしまいました。時間を忘れて、夢中で読みふけったのです。純文学作家がミステリー小説を書くことは、昔からありました。しかしどの作品も、推薦作を超えることはありませんでした。しかし吉田修一、伊坂幸太郎、そして角田光代は、あっさりと純文学系の代表作を超えてしまったようです。3人は世代的にはきわめて近く、私はいつも新作を楽しみにしています。3人の生まれ年と主な作品の、上梓時期をならべてみます。【吉田修一】1968年生まれ。1999年『最後の息子』(文春文庫)2007年『悪人』(朝日文庫)。【伊坂幸太郎】1971年生まれ。2003年『アヒルと鴨のコインロッカー』(創元推理文庫)2007年『ゴールデンスランバー』(新潮文庫)【角田光代】1967年生まれ。2003年『対岸の彼女』(文春文庫)2007年『八日目の蝉』(中公文庫)。 私はいま純文学が推理小説のジャンルに、すり寄りはじめていると感じています。いい加減な命名ですが、「純推文学」なる可能性の萌芽すら感じます。直木賞を受賞した中島京子(推薦作は『FUTON』講談社文庫と『小さなおうち』文春文庫)や売り出し中の朝倉かすみ(推薦作は『田村はまだか』光文社文庫)にも、その予兆を感じています。「純推文学」ジャンルには先輩作家がいます。列記しておきます。奥田英朗:1959年生まれ。『最悪』(講談社文庫)佐藤正午:1955生まれ。『バニッシングポイント』(集英社文庫)奥泉光:1956年生まれ。『「吾輩は猫である」殺人事件』(新潮文庫) そうした意味で『八日目の蝉』は、前走していた走者をひとつに巻き込む、前奏曲なのかもしれません。角田光代には『キッドナップ・ツアー』(新潮文庫)という作品があります。こちらはダメな父親が実の娘を誘拐する話です。『八日目の蝉』はその作品をひとひねり以上させた、作品として完成形に近くなっています。◎角田光代の2人目の赤ん坊『八日目の蝉』に話を戻します。主人公・野々宮希和子は不倫相手のこどもを中絶した、30歳の平凡な女性です。彼女が中絶したのち、不倫相手の妻に赤ん坊が生まれます。希和子は赤ん坊を一目見たいと、不倫相手の留守宅に忍びこみます。――今、赤ん坊はベビーベッドのなかで顔を赤くして泣いている。希和子は爆発物に触れるかのごとく、おそるおそる手をのばした。タオル地の服を着た赤ん坊の、腹から背にてのひらを差し入れる。そのまま抱き上げようとした瞬間、赤ん坊は口をへの字に曲げ、希和子を見上げた。(本文P9より) 希和子は赤ん坊を抱え、そのまま立ち去ります。希和子は赤ん坊に、「薫」という名前をつけ溺愛します。指名手配をされますが、希和子は薫を連れて各地を転々と逃げます。4年間におよぶ逃亡生活の終焉をむかえたのは、小豆島でした。連行される希和子は、最後に薫になにかを叫びます。ここまでが第1章です。日記形式でつづられたこの章では、逮捕されなければこの子の母親になれるのか、という問いかけがくりかえされています。 逃亡する希和子の薫にそそぐ愛情。希和子を迎えいれてくれる人たちの愛情。角田光代がこれまでの作品で描いてきた、「共同体」への志向に寄り沿うような展開がつづきます。第2章は成長した薫の視点で、描かれます。こんな具合です。――そのときのことを私は覚えている。ほかの記憶は本当にあいまいなんだけれど、その日のことだけは、覚えている。だれもいないフェリー乗り場で、あの人は缶ジュースを買ってくれた。チケットを買って、船着き場にしゃがみこんで海を見ていた。私をぎゅっと強く抱きしめた。せっけんと卵焼きのまじったようなにおいがした。私はあの人を笑わせるために何か言ったはずだ。あの人は声を出さずに静かに笑った。(本文P219より) 成長した薫には、安住すべき場所がありません。薫は誘拐犯・希和子と同じような、不倫をはじめます。そしてものがたりは、感動的なラストへと向かいます。「八日目の蝉」の意味についてはふれません。『対岸の彼女』を角田光代の推薦作として紹介していましたが、『八日目の蝉』はその作品を超えていました。脱帽。すばらしい作品をありがとうと結びたいと思います。デビュー作『幸福な遊戯』(角川文庫)からのおつきあいですけれど、初々しかった角田光代は2人目の大きな赤ん坊を、生み落としたとお祝いしたいと思います。(山本藤光:2011.02.18初稿、2014.08.28改稿)
2015年01月25日
コメント(0)
-
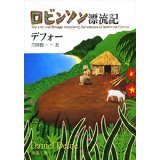
デフォー『ロビンソン漂流記』(新潮文庫、吉田健一訳)
難船し、ひとり無人島に流れついた船乗りロビンソン・クルーソーは、絶望と不安に負けず、新しい生活をはじめる。木材をあつめて小屋を建て、鳥や獣を捕って食糧とし、忠僕フライデーを得て、困難を乗りきってゆく。社会から不意に切り離された人間が、孤独と闘いながら、神の摂理を信じ、堅実な努力をつづけてゆく姿を、リアリスティックに描いたデフォーの冒険小説である。(「BOOK」データベースより)■デフォー『ロビンソン漂流記』(新潮文庫、吉田健一訳)◎『ロビンソン漂流記』誕生の秘話 タイトルは、新潮文庫にならいました。「ロビンソン・クルーソー」とされている翻訳の方が、多いのではないでしょうか。幼いころから慣れ親しんだ作品を読んでみて、記憶のひだから断片的な映像が間延びした感じで落ちてきました。おおまかなストーリーは、だれもが知っています。しかし意外にも本格的に読まれていないのが、『ロビンソン漂流記』なのかもしれません。 本書が発売されたとき(1719年)の本には、著者・ダニエル・デフォーの名前はどこにもありませんでした。ロビンソン・クルーソーという人が、自らの無人島暮らしを書いたように装われていたのです。タイトルは「ヨークの人、ロビンソン・クルーソーの生涯と、不思議な驚くべき冒険」とされており、著者名は「彼自身によって書かれた」と記されていました。(伊集院静訳『ロビンソン・クルーソー』講談社「痛快・世界の冒険文学19」の解説・小池繁を参照しました) 著者・デフォーは父親から、「人間は中間くらいがいちばんいい」といわれて育ちました。しかし彼はそれにあきたりませんでした。デファーはいまでいうフリージャーナリストとして浮沈をくりかえしました。向上心が強かったのです。1712年、デフォーはある体験記を読みました。 アレクサンダー・セルカークという男が、たった一人で南太平洋の無人島で4年間以上をすごしたという内容でした。デフォーは閃きました。彼には船乗りの経験はありませんでしたが、ロビンソン・クルーソーという想像上の人物を生み出したのです。 さて『ロビンソン漂流記』ですが、主人公・「私」(ロビンソン・クルーソー)は、父親から安定した生涯を送るようにいわれていました。しかし父親の反対を押し切って、「私」(以下カギカッコを省略)は船乗りになります。何度か航海をした私は、一攫千金を夢見てギニアに向かいます。そのときに大嵐に巻きこまれ、仲間はすべて遭難してしまいました。 私はたった一人で、見知らぬ島に漂着します。人食い人種が住んでいるかもしれません。凶暴な獣に襲われるかもしれません。浜辺に着いて無事を知った私は、真っ先にそんな不安にとらわれました。 食べるものも飲み水もありません。もっているのはナイフと煙草を吸うためのパイプだけでした。私は木に登り、落ちないように体をゆわえて、一晩をあかしました。 ここで読者も木に登って考えることになります。そして今後のことに思いをめぐらせます。現地人や猛獣といかに闘うのか。どうやって彼らから身を隠すのか。真水や食料を調達するための危険を、いかなる手段で克服するのか。武器はナイフしかありません。 ◎生きるための孤独な毎日 翌朝、私は1マイル(1.6キロほど)ほど先に、座礁している自分たちの船を発見します。私は潮が引くのを待ちます。苦労して船に乗りこみ、人の姿がないのを確認してから、必要な物資をもち出しました。 ビスケットとラム酒。むさぼるように飲み食いします。その後簡単ないかだを造って、乾燥山羊肉、葡萄酒、大工道具、武器と弾薬、火薬、衣類などを積みこみます。島に戻った私は、さっそく武器をもって水や食料を求めるかたわら、探検をはじめます。小高い丘に登り、そこが「島」であることを認識しました。便宜上標茶六三は、最初から「島」と書きましたが、主人公の私(クルーソー)にはその認識はなかったのです。――私は猟銃と短銃を一挺ずつと、角製の火薬入れを一つ持って、非常な困難を冒してその丘の頂上まで登った。私はその時私がどういう場所に来たか、初めて解った。そこは島で、周囲の海には遠方にいくつかの岩と、九マイルほど西にこれよりも小さな島が二つ見えるだけだった。(本文P60より) こうして孤島での28年と2ヶ月の生活がはじまります。標茶六三の記憶の襞には、もっと短い期間の生活と刻まれていました。クルーソーは外敵から身を守り、豪雨から逃れるための住居を造ります。たった数粒の麦の種から、麦の栽培をはじめます。野生の山羊を飼いならし、家畜として育てます。脱出用のボートの建造に、船から持ち出した斧だけで挑戦もします。 生きるための孤独で単調な、毎日がつづきました。私はいつしか神に祈る習慣を、身につけはじめます。『ロビンソン漂流記』は、無からの創造の喜びに満ち満ちています。大木から板をつくり、それをテーブルにします。岩肌を掘り進めて、食料庫に仕上げます。数粒の種を増やし、4年がかりでケーキをつくります。山葡萄から葡萄酒を製造します。そんな創意工夫の生活を見つめつづけたのが、いままで見向きもしなかった神の存在でもあったのです。 読みながら私(筆者)は、不思議だなと思ったことがあります。ロビンソン・クルーソーは魚や貝を食べていません。豊富であるはずの魚介類は、まったく食料の対象として描かれていないのです。見たこともない鳥を、打ち落として食べます。そんなクルーソーが、なぜ魚や貝を無視したのでしょうか。わかりません。少なくともこの点にふれた、論評の存在は知りません。 やがて私は島で、人骨を発見します。そして人食い人種が、ときどき来島していることを知ります。ここから先は、また記憶のスイッチがはいりました。フライデーという現地人の存在です。 ◎絶望から希望へ 火薬が底をつきはじめました。私は狩猟生活から、畜産や農業に思考を切りかえます。日記も書きはじめました。「絶望の島」といっていた空間が、少しずつ変化をとげるようになります。 その後何度か、野蛮人は島にやってきました。人肉を食い、踊り、海へともどってゆきます。私は見知らぬ世界の人種たちの奇習を、自分と同化させて考えてみたりするようになります。獣肉を何のちゅうちょもなく食べている自分。人肉を食べてはいけない、という倫理観のない野蛮人たち。どこにちがいがあるのでしょうか。やがてインクがなくなり、日記を書く習慣は頓挫せざるを得なくなります。 ある日5艘のボートが、着岸しているのを発見します。野蛮人たちが人肉を食べて踊っていました。そのとき捕虜の一人が、猛烈な勢いで脱走をはかります。私は追っかけてきた野蛮人を撃ち殺し、捕虜を救います。それがフライデーでした。 私はフライデーに、言葉や宗教も教えます。聖書を読み聞かせます。フライデーが住んでいた島には、17人の白人が捕虜生活をしていることを聞きました。フライデーの存在は単調だった毎日に、アクセントをつけてくれました。同胞の捕虜がかなたの島にいることが、私の心を救出へと駆り立てます。『ロビンソン漂流記』は、けっして単なる児童書ではありません。生きるということの根源を示してくれる、哲学書だとすら思います。つくる、そだてる、くふうする、しんじる。そんな大切なことを教えてくれる、指導書だとも思うのです。 1686年12月19日クルーソーは、27年2ヶ月19日滞在した「絶望の島」と別れを告げます。本書は組織に不満をもつ方には、必読の1冊です。「絶望の島」に希望を見出すヒントを、本書のいたるところから発見することができるからです。 2度目に本書を読んで、はじめて安部公房『砂の女』(新潮文庫)との類似点を発見しました。『砂の女』の主人公は、絶望の砂のなかから毛細管現象という希望を発見しています。無神論者だったクルーソーは、絶望のなかから神の存在を見出しました。 ◎ちょっと寄り道 私は本書を読み終えると同時に、伊集院静・文『痛快世界の冒険文学19・ロビンソン・クルーソー』(初出1999年講談社、文庫なし)を手にしました。伊集院静の冷静でいて、はじけるような文章には味があります。挿絵(長友啓典)もすてきです。ただし完訳と違い本書には、植民地主義のイギリスの思想が書きこまれていません。クルーソー自身にも完訳とは異なり、未開人蔑視の思想は目立ちません。 私は『痛快世界の冒険文学』シリーズを大切にしています。孫が大きくなったら、ひざの上に乗せて読んであげたいと思っているほどです。本シリーズは、一部文庫化されているようです。注目の作品と筆者を紹介しておきます。志水辰夫『十五少年漂流記』、阿刀田高『アーサー王物語』、嵐山光三郎『水滸伝』、眉村卓『タイムマシン』、立松和平『ハックルベリィ・フインの冒険』など全24巻。(山本藤光:2009.11.28初稿、2014.08.31改稿)
2015年01月23日
コメント(0)
-

永井荷風『腕くらべ』(岩波文庫)
誠と意地に生きる新橋の芸妓駒代は、一切の義理人情を弁えない男女の腕くらべに敗れ去る。この女性に共感を寄せる講釈師呉山や文人南山。長年の遊蕩生活に社会の勝利者への嫌悪を織りこみ、失われゆく古きものへの愛惜をこめて書かれた荷風中期の代表作。佐藤春夫は浮世絵風の様式描写があると絶賛した。(岩波文庫コピーより)■永井荷風『腕くらべ』(岩波文庫)◎大正時代の代表的作家 まずは永井荷風の時代を整理しておきます。大正時代の文豪といえば、真っ先に名前があがるのが永井荷風と谷崎潤一郎(推薦作『痴人の愛』新潮文庫)です。明治時代に隆盛をきわめた自然主義文学が読者にあきられて、登場したのが2人に代表される「耽美派」文学でした。――自然主義文学が「作者の体験をリアルに」といった方法論に固執した結果、いずれも平板で陰うつな作風になってしまったのに対し、耽美派は、官能の世界を努めて繊細に描こうとした。(長尾剛『早わかり日本文学』日本実業出版より)『腕くらべ』は1916年8月から翌年10月まで、13回にわたって「文明」に連載されました。「文明」は慶應義塾大学の教授を辞任し、三田文学の編集からも手を引いた、永井荷風が創刊した雑誌です。つまりなにを掲載するのも自由でしたし、「腕くらべ」のために創刊した雑誌ともいえます。『腕くらべ』は、谷沢(たにざわ)永一『性愛文学』(KKロングセラーズ)に取りあげられています。そこには昔の検閲で削除された第3章「ほたる火」(これは誤植だと思います。第3章は「ほたる草」なのですから)の後半が転載されています。長くなるので引用は控えますが、高校時代に男子のあいだで回し読みされていました。 永井荷風は知識人を両親にもち、上流の名家に生まれました。このことに永井荷風は一生反抗し、その感情が文学へ投影されています。ただし父親への恩を忘れることはありませんでした。放蕩、寄席への出入り、文学と、若いころの永井荷風は青春を謳歌しています。ゾラ(推薦作『居酒屋』新潮文庫)やモーパッサン(推薦作『女の一生』新潮文庫)の文学に刺激を受けた永井荷風は、しだいに創作へと集中しはじめます。 そんなときに父の勧めで、アメリカに渡ります。ちょうど日露戦争のときでした。その後荷風は、念願のフランスへ渡ることになります。フランス滞在中の荷風は、歴史・文化の重さを体感しました。それがハイカラ思考を嫌悪し、江戸文化を礼賛する思考としてあらわれます。 海外遊学の収穫としては、『あめりか物語』(岩波文庫)や『ふらんす物語』(新潮文庫)にいかんなく発揮されています。いっぽう永井荷風は、東京の作家でもありました。烏山で生まれ、向島と今戸を『すみだ川』(岩波文庫)に描き、新橋を『腕くらべ』に、玉の井を『墨東綺譚』(新潮文庫)に、そして『断腸亭日乗』(岩波文庫)は膨大な東京の地誌になっています。(『図解永井荷風』河出書房新社を参考にしました)◎花柳界を描いた稀有な作品『腕くらべ』は永井荷風の代表作であり、花柳界を描いた稀有な作品でもあります。しかし文壇上の同期(衰退する自然主義に変わってあらわれた耽美派作家)である谷崎潤一郎は、厳しい評価をくだしています。 谷崎潤一郎は『腕くらべ』について、「円熟の美はあり、斉整の美はあるが、その題材が為永春水以来の花柳界という古めかしい世界に限られ、あまりにも粋になり過ぎたために現代離れのした気味合いがあって、これでは結局紅葉あたりの綺麗事の境地から一歩も進んでいない」と書いています。(『新潮日本文学5・永井荷風』解説・河盛好蔵を参考にしました) いっぽう佐藤春夫は「かって、『腕くらべ』の描法を評して浮世絵的技法と呼び、人物に配するに風韻豊かな情景をもってしていることを指摘し」ています。(奥野信太郎『荷風文学みちしるべ』岩波現代文庫P48)また『腕くらべ』の創作意図について、永井荷風は明確に述べています。――時世の好みは追々芸者を離れて演劇女優に移りかけてゐたので、わたくしは芸者の流行を明治年間の遺習と見なして、其生活風俗を描写して置かうかと思ったのである。(「正宗・谷崎両氏の批評に答ふ」、『図解永井荷風』河出書房新社より) このあたりについて、湯川説子はつぎのように補足しています。――新橋の花柳界は、江戸の文化を内在させた特別な土地であるとともに、新時代の紳士たちが羽振りをきかせたため、明治に入って柳橋に代わる隆盛をきわめた地域でもあった。新橋の二重性が、作品の舞台として格好の場であることに荷風は目を留めていた。(『図解永井荷風』河出書房新社より) つまり永井荷風は、江戸の文化が廃れるのが忍びなかったのです。それを文章に書きとどめたい、と思ったのでした。必然、描写は細やかになります。『腕くらべ』は、芸者同士の手練手管の争いをイメージしたタイトルです。 主人公は、新橋尾花屋の芸者・駒代。江戸の伝統的な気質を備えた自我の強い芸者です。7年ぶりに以前なじみだった実業家・吉岡と出会います。吉岡は駒代の身受けを申し出ます。しかし「あなたには力次姐さんや浜町の内儀さんがいる」と駒代はちゅうちょします。 そのうちに駒代は昔なじみだった女形の瀬川一糸とねんごろになります。うわさを耳にした吉岡は、同じ尾花屋の菊千代に入れこみはじめます。吉岡を奪われた力次は、瀬川一糸と駒代の仲を引き裂こうと画策します。結局瀬川一糸を、君龍という後輩芸者に奪われることになります。 明治時代の権化みたいな吉岡の残酷さ。芸者同士の駆け引き。『腕くらべ』は明治のはざまでおぼれかける駒代の悲哀を、克明に活写しています。著者・永井荷風をほうふつさせる人物は、呉山という頑固老人として姿をみせます。尾花屋を切り盛りする妻が亡くなり、呉山は駒代にやさしい言葉をかけます。 物語はそれだけのことなのですが、永井荷風はみごとに花柳界を描ききっています。高校時代に回し読みされた『腕くらべ』は、32の連作集になっていました。それぞれを単独で読んでも、りっぱに独立した掌編になっています。永井荷風ならではの流れるような美文が、全編をみごとに融合させています。◎ちょっと寄り道 永井荷風は丸谷才一が、もっとも尊敬している作家でした。その理由を孫引きになりますが、紹介させていただきます。――私(補:丸谷才一)が一番尊敬している文学者は永井荷風です。永井荷風は近代の文学者の中で最も軍人、兵隊が嫌いな文学者でした。(菅野昭正編『書物の達人・丸谷才一』集英社新書P40)「永井荷風」という冠のついた文庫・新書は意外にたくさんあります。紹介しておきます。――秋庭太郎:考証・永井荷風(上下巻、岩波現代文庫)――磯田光一:永井荷風(講談社文芸文庫)――江藤淳:荷風散策・紅茶のあとさき(新潮文庫)――奥野信太郎:荷風文学のみちしるべ(岩波現代文庫)――川本三郎:荷風語録(岩波現代文庫)――川本三郎:荷風好日(岩波現代文庫)――菅野昭正:永井荷風巡歴(岩波現代文庫)――小島政二郎:小説・永井荷風(ちくま文庫)――佐藤春夫:小説永井荷風伝(岩波文庫)――半藤一利:荷風さんの昭和(ちくま文庫)――半藤一利:荷風さんの戦後(ちくま文庫)――松本哉:永井荷風という生き方(集英社新書) まだあるはずですが、書棚から引き抜いた関連本です。永井荷風は小説で楽しませてくれ、関連本でも楽しませてくれています。(山本藤光:2010.03.14初稿、2014.09.12改稿)
2015年01月22日
コメント(0)
-
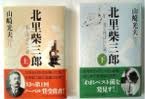
山崎光夫『ドンネルの男・北里柴三郎』(上下巻、中公文庫)
第一回ノーベル賞を受賞するはずだった男、北里柴三郎。その波瀾に満ちた生涯は、医学を志した時から始まった。「肥後もっこす」そのままに、医学に情熱を傾ける柴三郎は渡欧後、世界的細菌学者コッホの下で破傷風菌の発見・培養と血清療法の確立に成功する。日本が生んだ世界的医学者の生涯を描く。(「BOOK」データベースより)■山崎光夫『ドンネルと呼ばれた男・北里柴三郎』(上下巻、中公文庫)◎医療小説という下地 山崎光夫『ドンネルと呼ばれた男・北里柴三郎』(上下巻、中公文庫)をどのジャンルにするのか、迷ってしまいました。本書は、ビジネス雑誌である「週刊東洋経済」に連載されていました。だから、ビジネス書とも考えられます。ところが、単行本の帯には「著者渾身の長編小説」とあります。読んでみると、ノンフィクションそのものでした。迷った末に、私は「知・教養・古典」へとジャンル分けすることにしました。 2012年に日本医師会により「日本医療小説大賞」が新設されました。第1回の受賞作品は帚木蓬生の『蝿の帝国』と『蛍の航跡』(ともに新潮文庫)でした。ちなみに第2回は該当なしで、第3回は久坂部羊『悪医』(朝日新聞社)が受賞しています。この賞の創設が早ければ、『ドンネルの男・北里柴三郎』は間違いなく受賞していたと思います。 山崎光夫は、医学薬学関係の作品を中心にして書いています。処女作『ジェンナーの遺言』(初出1986年文藝春秋、祥伝社文庫)は、根絶された天然痘が東京を襲う話でした。私はこの作品で、山崎光夫ファンになりました。 第2作『安楽処方箋』(初出1986年講談社)は、デビュー作の2日後に発売されています。私はほぼ同時に、2冊の山崎光夫作品集を読んだことになります。表題作「安楽処方箋」は、医師に見破られずに自殺する方法をあつかった秀作です。本書には直木賞候補になった「詐病」と、「サイレント・サウスポー」が収載されています。残念ながら小説家としての山崎光夫初期作品は、ほとんど文庫化されていません。山崎光夫は3度直木賞候補になっています。しかし受賞には至らず、次第に影が薄くなってしまいました。 そんなときに書店で、山崎光夫『ドンネルの男・北里柴三郎』を発見しました。本書にふれたときの喜びを、当時の「読書ノート」から引用してみます。(引用はじめ) 『ドンネルの男・北里柴三郎』(単行本のタイトル)は、医学小説という下地のある著者だから書きえたテーマです。タイトルのドンネルは、ドイツ語で雷の意味。北里柴三郎は頑固一徹な人でした。それゆえ、組織内では浮き上がっていました。しかし、弟子からの信頼は絶大であったようです。 本書には、さまざまな歴史上の人物が登場します。この時代に海外留学を果たすのは、ほんの一握りの人だったでしょう。そういう人たちが作品を引っ張ります。福沢諭吉は北里の恩師であり、北里柴三郎はその教えを守って、慶應義塾大に医学部を創設することになります。森鴎外(林太郎)は、北里のライバル。赤痢菌を発見した志賀潔は、北里の弟子にあたります。 いまから150年前に生を受け、ドイツ留学を経て日本の公衆衛生をリードした北里柴三郎。その生きざまにふれて、人を動かすことの本質を知らされました。自分に正直であること。部下の成長に熱心であること。受けた恩義を忘れないこと。久しぶりに読んだ、山崎作品に拍手。(「読書ノート」2003年11月6日より)◎日本ではじめてのノーベル賞候補 北里柴三郎に関する著作は、意外に多くはありません。野口英世の伝記は、少年文庫にもなっています。北里柴三郎は、本来なら第1回ノーベル賞を受賞しているはずでした。破傷風、コレラ、ペストなど、未知の病に挑んだ人なのに、あまりスポットがあてられていないのが現状です。『ドンネルの男・北里柴三郎』の詳細説明は、山崎光夫の「あとがき」ですべてを網羅しています。単行本の初版本の帯コピーを紹介させていただきます。――2003年(平成15年)は北里柴三郎・生誕150周年にあたる。この節目に、幕末から明治、大正、昭和と生き抜いた〈気骨一貫〉の人生を振り返るのは格好といえるだろう。(中略)わたしは医学・薬学の世界を執筆の分野と決めてから、明治期の医人像をいずれ描いてみたいと考えてきた。日本ではじめてのノーベル賞候補にのぼった北里柴三郎については、特に興味を覚えていた。(「上巻」より)――北里は象牙の塔に安住した単なる細菌学者ではない、というのがわたしの抱いている北里像である。わが国の公衆衛生をリードした指導者であり、多くの研究者を育てた教育者でもある。日本に近代簿記を紹介したのは福沢諭吉だが、北里はその福沢の〈弟子〉でもあり、遺志をついで慶應義塾大学・医学部を創設した。また、日本医師会の初代会長も務め、オーガナイザーとしての才も発揮している。幅広い視野を持った桁外れの人物である。(「下巻」より) 山崎光夫には、文庫書き下ろし『名人伝・長く強く生きる』(講談社+α文庫)という著作があります。そこには北里柴三郎ほか80余名の名人たちが登場します。山崎光夫は、彼らの共通点を「健康力」「没頭力」「楽天力」だとしています。 直木賞に縁のなかった山崎光夫が、ノーベル賞に縁のなかった北里柴三郎を描いた作品。そんな単純な図式ではなく、本書は傑作です。医療従事者はもちろん、企業のトップにはぜひ読んでもらいたいと思います。 山崎光夫にはほかに、芥川龍之介自殺の謎を解く『藪の中の家』(中公文庫)があります。ノンフィクション的小説として新境地をひらいた、山崎光夫の奮起を喜んでいます。山崎光夫は、あと80名ほどの「名人伝」を書かなければなりません。(山本藤光:2010.05.29初稿、2014.08.26改稿)
2015年01月21日
コメント(0)
-
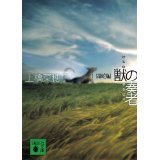
上橋菜穂子:獣の奏者(全4巻+外伝、講談社文庫)
リョザ神王国。闘蛇村に暮らす少女エリンの幸せな日々は、闘蛇を死なせた罪に問われた母との別れを境に一転する。母の不思議な指笛によって死地を逃れ、蜂飼いのジョウンに救われて九死に一生を得たエリンは、母と同じ獣ノ医術師を目指すが―。苦難に立ち向かう少女の物語が、いまここに幕を開ける。(「BOOK」データベースより)■上橋菜穂子:獣の奏者(全4巻+外伝、講談社文庫)◎第1巻から圧倒された 上橋菜穂子が「国際アンデルセン賞」作家賞を受賞したというニュースに接して、はじめはその重みを理解できませんでした。そのうちに、トーベ・ヤンソン(推薦作『ムーミン』講談社文庫)やアストリッド・リンドグレーン(推薦作『長くつ下のピッピ』岩波少年文庫)なども受賞していることを知りました。さらに1994年に、まど・みちお(推薦作『まど・みちお詩集 』ハルキ文庫)が受賞していることも知りました。「国際アンデルセン賞」の選評では、文化人類学者としての視点で名誉と義務、運命と犠牲が描かれている点をあげられています。選評を紹介させていただきます。――彼女のファンタジー世界は中世の日本に大枠で基づいているが、彼女が独自に創りあげたものである。しかも、それはただその土地や神話的な景観を創りあげるものではなく、その世界の階級制度への問いかけや、精神性や道徳的視点の相互関係をも含めた世界である。(『IN POCKET』(2014年4月号より)――彼女には、他者とは異なるファンタジー世界を構築する並外れた力がある。そして彼女の作品は、自然や生物に対する優しさと、深い尊敬の念に満ちている。(『IN POCKET』(2014年4月号より) 上橋菜穂子は若いころに、トールキン『指輪物語』(補:全7冊、評論社)を読んで、「人間は何て面白いことを考える生き物なのか」(「朝日新聞」2014.9.27)と衝撃を受けたと語っています。 うかつでした。上橋菜穂子は、ノーマークの作家でした。あわてて上橋菜穂子『獣の奏者』(全4巻+外伝、講談社文庫)を買い求めました。そして第1巻『獣の奏者1闘蛇編』を読んで、圧倒されました。幼いころにわくわくして、冒険小説を読んでいたことを思い出しました。還暦をすぎてからは、ページをくくるたびに五感をふるわせたことはありませんでした。 主人公は緑の瞳をもった、少女エリンです。彼女は母親ソヨンとともに、闘蛇衆たちが暮らすリョザ神王国の村に住んでいます。闘蛇とは戦に駆り出される戦闘獣として、国から委託をうけて飼育されている巨大な蛇のことです。エリンの母親は「獣ノ医術師」の資格をもつ、腕のよい闘蛇衆です。 エリンの母ソヨンも、緑の瞳をもっています。彼女は〈霧の民〉という一族の出身ですが、闘蛇村の男と愛しあい生まれた土地を離れました。 ある日、飼育していたすべての〈牙〉(最強の闘蛇)が全滅しています。〈牙〉の飼育責任者だったエリンの母ソヨンは、全責任を負わされることになります。ソヨンは別の闘蛇の〈イケ〉に投げこまれます。幼いエリンは母を救出するために〈イケ〉に飛びこみます。2人のもとに闘蛇がせまってきます。 母ソヨンは指笛を吹いて、闘蛇の動きを制圧します。母ソヨンはエリンを1頭の闘蛇の背に乗せ、自らは闘蛇の餌食となります。闘蛇の背に乗ったエリンは、蜂飼いのジョウンに助けられます。 天涯孤独となったエリンは、やがて自然のなかに生息している王獣の生態に出会います。エリンは母と同じく獣ノ医術師になることを決意します。ジョウンはエリンを、昔なじみのエサルが教導師長をしている、カザルム王獣保護場の学舎へいれます。◎王獣リランと竪琴――物語がひらめく時は必ず、ひとつの光景が胸の中に生まれるのだと上橋菜穂子は言う。『獣の奏者』の場合、それは養蜂の本を読んでいる時に起こった。/断崖絶壁の上に立つひとりの女性が竪琴を奏でている。その向こうに翼を広げた大きな獣が見えた。それは物語という大河の最初の一滴だ。決して人に馴れぬ孤高の獣は永遠の他者だ。わかりえぬものをそれでもわかろうとする少女エリンの物語が、こうして生まれた。(『IN POCKET』(2013年10月号より)『獣の奏者2王獣編』は、エリンが学舎で傷ついた王獣の子・リランと出会う場面から幕があきます。エリンは献身的にリランの世話をします。エリンは竪琴をつかって、リランと簡単な会話ができるようにまでなります。 そんなとき母ソヨンの一族である、「霧の民」から警告をうけます。「王獣を操ると、大きな〈災い〉を招く」といわれるのです。王獣を馴らしてしまったエリンは、やがて王国の命運をにぎる存在となってゆきます。 闘蛇の背に乗った戦士たちが、「真王」を暗殺するために押しよせてきます。真王の護衛士・イアルたちは必死に防戦しますが、なすすべもありません。そんな危機を救ったのは、王獣の背にまたがったエリンでした。やがてエリンは真王の護衛士・イアルに魅せられてゆきます。『獣の奏者』は、ここまでで完結する予定でした。ところが本書がアニメ化されるのを手伝いながら、構想がふくらみはじめたのです。『獣の奏者3探究編』では、エリンは愛する人と結婚しています。こどももいます。これ以降については、ふれません。ただし第1巻、第2巻で不明瞭だった部分の謎が解けはじめます。 おそらく多くの読者は、夢中になって『獣の奏者4完結編』『獣の奏者・外伝』へと読み進むことになるでしょう。「国際アンデルセン賞」のニュースがなければ、おそらく上橋菜穂子の著作にはふれていなかったと思います。出会いに感謝。(山本藤光:2015.01.18)
2015年01月20日
コメント(0)
-
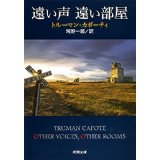
カポーティ『遠い声遠い部屋』(新潮文庫、河野一郎訳)
父親を探してアメリカ南部の小さな町を訪れたジョエルを主人公に、近づきつつある大人の世界を予感して怯えるひとりの少年の、屈折した心理と移ろいやすい感情を見事に捉えた半自伝的な処女長編。戦後アメリカ文学界に彗星のごとく登場したカポーティにより、新鮮な言語感覚と幻想に満ちた文体で構成されたこの小説は、発表当時から大きな波紋を呼び起した記念碑的作品である。(「BOOK」データベースより)■カポーティ『遠い声遠い部屋』(新潮文庫、河野一郎訳)◎生きることと書くことは一体のもの 大学時代に友人から薦められて読んだ『冷血』(新潮文庫)の衝撃は、いまだに忘れられません。それまで「ノンフィクション・ノヴェル」というジャンルは知りませんでした。その著者・トルーマン・カポティは処女作「ミリアム」(『夜の樹』新潮文庫所収)で、「アンファン・テリブル(恐るべき子供)」と呼ばれました。 米国南部のニューオーリンズに生まれたカポーティは、両親の離婚で親戚の家を転々としています。父親探しのテーマは、そうした体験と無関係ではないといわれています。『冷血』で絶大なる評価を得たカポーティは、名士として華やかな生活をおくるようになります。しかし薬物(コカイン)とアルコール中毒となってゆきます。 カポーティ『冷血』は、日本の作家に大きな影響を与えています。カポーティの小説作風は、『遠い声遠い部屋』(新潮文庫、河野一郎訳)で確立されました。「現実と幻想を交錯する地点を華麗な想像力によって描いた、高度に洗練された技巧は高く評価され」ました。(「新潮社世界文学小辞典」より) 村上春樹は、「クリスマスの思い出」を翻訳しています。沢木耕太郎、山田詠美なども、作品に影響を受けています。三島由紀夫もカポーティと会っています。三島は「あいつは自殺する」と予言したようです。まさにその予言は的中しました。自殺といってもよい、壮絶な晩年だったのですから。 晩年のカポーティは、『ティファニーで朝食を』(新潮文庫)に代表されるように、新たな作風になってゆきます。この作品は、オードリー・ヘップパーン主演の映画にもなっています。「生きることと書くことは一体のもの」と、いいつづけたカポーティ。私はあえてカポーティの人生を予見させる『遠い声遠い部屋』を推薦作品として選びました。◎廃墟の村へ父を探しに『遠い声遠い部屋』は南部の廃墟の村へ父親を探しにゆく、少年の成長を描いた意識下の物語です。当時の米国文壇は、ヘミングウェイに代表される写実主義が主流でした。そこに繊細でみずみずしい感性の、風穴を開けたのがカポーティだったのです。 主人公・ジョエル少年13歳は、早くに母親を亡くして叔母の家に住んでいます。1通の手紙が届きます。青い封筒の差出地は、ランディングとなっていました。ジョエルはニューオーリンズから、父を訪ねる旅に出ます。おじいさんのものだという、古いトランクを引っさげて。 ジョエルが最初に着いたのは、米国南部の田舎でした。そこから先へは行けないといわれます。唯一の手段は、ヌーン・シティに物資と郵便物を届けるトラックに便乗することでした。ジョエルが父と暮らすために、ランディングというところに行きたいと告げます。運転手は不自然な反応をしました。 運転手の好意でトラックに乗せてもらったジョエルは、ヌーン・シティで降ろされます。目的地ランディングまでは、まだ2、3マイルは離れています。今度は御者・ジーザス・フィヴァーの馬車に乗せてもらうことになります。◎メモを取りながら読み進める ここから先は、メモを取りながら読んでもらいたいと思います。現実と幻想が交錯しますが、メモは「現実」だけを追いかけてもらわなければなりません。さもなければ、登場人物の出入りがひんぱんで、流れが掌握できないのです。『遠い声遠い部屋』の魅力は、カポーティがつむぎだす言葉の魔術にあります。ストーリーは、あまり重要ではありません。それゆえ登場人物に惑わされて、先に進めなくなるのはつまらないことです。 私のメモを紹介します。私は書店からもらったブックカバーを、裏返しにして使用しています。ブックカバーの裏はいずれも無地なので、メモはそこに書き留めます。重複を避けるために、目的地・ランディングに到着したところから紹介します。 ミス・エイミ:出迎えてくれた女性。父親の再婚相手。45歳から50歳。ランドルフ:ジョエルのいとこ。34、5歳。画家志望。ジョエルモデルになる。不可解な写真(P165)ミスター・サムソン:父。ジョエル本を読んであげる。ズー(ミズーリ・フィーヴァー):屋敷のお手伝い。14歳。御者・ジーザス・フィーヴァーの孫か子。同居している。 これでランディング邸の人物整理は終了です。このあたりを理解しておけば、カポーティが織りなす言葉の玉手箱を開けても、十分に堪能できるはずです。私は図を描きながら、読んだりもします。ランディング邸の大きな四角のなかに、上記の人物を囲ってしまいます。そして作品を読み進めながら、そのなかに小さな四角を描きます。そこにズーと御者のジーザス・フィーヴァーをいれてしまうのです。これで住まいの位置関係がわかります。 ◎うならせられた情景描写 カポーティの情景描写は、実に巧みです。私はブックカバーの裏メモに、単語とページだけを記入して読み進めます。あとからじっくりと、鑑賞し直すためです。 ――艶消しガラスの明り取り窓が、雨の日に部屋をひたす真珠のような光で、細長い二階の廊下を明るくしている。壁紙もかってはおそらく真っ赤な色だったらしいが、今では濃紅色にぶくぶくふくれ上がり、地図のような汚点(しみ)に飾られている。(本文より、標茶六三のメモ「二階の窓・壁」P61)――金色に塗られた藤色ビロードの二人がけの椅子や、大理石の暖炉の横におかれたナポレオン時代風のソファ、あるいは陶器の人形や象牙の扇子、骨董品などで光っている飾り棚も見える。飾り棚は全部で三つあるが、他の二つははっきりと見えない。彼のちょうどまん前におかれたテーブルの上には、日本の五重塔と、凝った装飾を施した羊飼いのランプがのっていて、ランプのゼラニウム色のほやからは、シャンデリア風のプリズムが宝石になった氷柱のように下がっている。(「ランディング邸の客間」P81)『遠い声遠い部屋』は、私に新たな読書の楽しみを与えてくれました。『冷血』では、カポーティの息もつかせぬ文章に引きずられました。『遠い声遠い部屋』では、現実と非現実のはざまを彷徨わせてもらいました。カポーティについては、この2冊をはずさずに読んでいただきたいと思います。 小説界ではカポーティに肩を並べる、日本人作家はいません。村上春樹がちょっと近いかもしれません。ノンフィクション・ノベルでは、佐木隆三『復讐するは我にあり』(上下巻、講談社文庫、直木賞)をあげたいと思います。(山本藤光:2009.09.16初稿、2014.09.11改稿)
2015年01月19日
コメント(0)
-
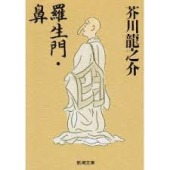
芥川龍之介『羅生門』(新潮文庫)
ワルに生きるか、飢え死にするか、ニキビ面の若者は考えた……。 京の都が、天災や飢饉でさびれすさんでいた頃の話。荒れはてた羅生門に運びこまれた死人の髪の毛を、一本一本とひきぬいている老婆を目撃した男が、生きのびる道を見つける『羅生門』。あごの下までぶらさがる、見苦しいほど立派な鼻をもつ僧侶が、何とか短くしようと悪戦苦闘する『鼻』。ほかに、怖い怖い『芋粥』など、ブラック・ユーモアあふれる作品6編を収録。(アマゾン内容紹介より)■芥川龍之介『羅生門』(新潮文庫)◎芥川龍之介のこと 電子書籍に『芥川龍之介作品集成155』(kindle)がはいりました。短篇小説を150作品収載しており圧巻です。300円で購読できます。私は1日1篇ときめて、寝ころびながら再読しています。「羅生門」は7日目に読みました。経営していた会社を譲渡し、素浪人の心境だったので、追い詰められた老婆と下人の心情が手にとるように理解できました。まったくちがった作品として、「羅生門」がよみがえりました。『羅生門』は高校の教科書にのっていました。感想文を書かされた記憶もあります。おそらく下人のエゴイズムを糾弾した内容だったと思います。5年前に書いた『羅生門』の書評を読み直してみました。味気のないものでした。高校時代に読んだときと、寸分違わぬ感想の羅列でした。全面改稿することにしました。 自分の読書力の貧しさに恥じて、識者はいかに『羅生門』を読んでいるのか、それを検証してみることにします。書棚から30冊の関連本を引き抜いてきました。全部を読み通すのに1か月を要しました。 芥川龍之介の生涯を手短にまとめてありますので、阿刀田高の著書から引用させてもらいます。――大学在学中に『鼻』という名作をかいて夏目漱石に認められ、さらに『羅生門』によって、一気に文壇の寵児としてデビューしました。それからは一貫して人気作家としての道を歩み続け、最後はいろいろな意味で行き詰まって自殺という形で自らの生涯を閉じました。(阿刀田高『日曜日の読書』新潮文庫P15) 朝日新聞の特集(「はじめての芥川龍之介」2012.1.16朝刊)に、芥川に関するわかりやすい図解がありました。ちょっと紹介します。図は芥川龍之介を中央にして、上下左右に文人の似顔絵が配されています。・上段芥川→室生犀星:自分とは異なる才能を高く評価芥川→泉鏡花:芥川の葬儀で先輩代表として弔辞芥川→谷崎潤一郎:小説の「筋」をめぐる文学論争芥川→高浜虚子:句の添削を受ける・左右芥川→菊池寛:同級生芥川→夏目漱石:師と仰ぐ(夏目と高浜は親友)・下段芥川→堀辰雄:芥川を慕う。芥川文学を継承した人芥川→萩原朔太郎:その詩に感激し寝間着姿で家を訪ねる芥川→川端康成:後輩作家。関東大震災後,共に市中を見て回る芥川→宇野千代:送られた小説を厳しく批評 芥川龍之介の実母は、彼が10歳のときに死去しています。母親の愛情を知らないことが、芥川龍之介作品に大きな陰を落としているとする文献は数多くあります。新潮文庫の解説でも、「生いたちの秘密を隠そうとする禁忌の感覚は、実生活の告白をこばむ虚構性を芥川文学の本質として決定することになった」(三好行雄)と断言しています。◎『羅生門』のこと 芥川龍之介の小説『羅生門』は、『今昔物語集』を素地にした作品です。映画「羅生門」(黒沢明監督)は、国際グランプリを獲得した作品です。ここまではだれもがご存知のことと思います、 正確に記せば、『羅生門』は、「今昔物語集」の「羅城門の上層に登りて死人を見たる盗人のこと」(巻29第18)からヒントを得た作品です。黒沢明映画は、芥川龍之介『羅生門』を映画化したものではありません、と書かなければなりません。 そのあたりについて紹介している、文章を引用します。――この話(補・今昔物語巻29第18)に取材して、芥川龍之介は傑作『羅生門』を書いた。そこでは男の屈折した心理が細密に解剖されているが、『今昔物語集』は、彼が老婆の懇願を無視して、奪い取った品物を淡々と書き並べるだけである。まるで取り調べの調書のような、無味乾燥が、かえって不気味なほど迫真力を感じさせる。(ビギナーズ・クラッシックス日本の古典『今昔物語集』角川ソフィア文庫P216) 芥川龍之介は素材を『今昔物語集』に求めたものの、まったく異なった作品を書き上げています。関口安義は著書のなかで、「素材は古典に求めながらも、そこには近代人の心理が描かれている」(「関口安義『芥川龍之介』岩波新書P51)と書いています。また黒沢明監督もまったく同様で、タイトルのみ借用し、別物の『羅生門」という映画を完成させました。――これは(補:黒沢映画)『今昔物語集』の本話や芥川龍之介の『羅生門』とは別のものだ。ただプロローグとエピローグの舞台として、この羅城門が使用されている」(ビギナーズ・クラッシックス日本の古典『今昔物語集』角川ソフィア文庫P216)『羅生門』の舞台は、平安時代です。下人は「盗人の道」と「餓死の道」の二者択一を迫られています。賞味期限が切れた、食料が棄てられている現在とはちがいます。ホームレスなどという「第三の道」などは考えられません。私はあえて、二者択一と書きました。しかし、常識的に考えるなら、「餓死」などという道を選ぶ人間はいないと思います。 死体から髪の毛を抜く老婆がいてもいなくても、下人は「盗人」の道を選んでいるはずです。今回読み直してみて、このような一本道であるべき展開に、芥川は下人の微細な感情で揺れを巧みに操り、朦朧としたものに仕上げていることを理解しました。また『羅生門』関連の本を読んでいて、つぎのような記述ともであいました。――老婆の行為に「あらゆる悪に対する反感」を抱く下人の感情は、合理的には割り切れない。「悪」そのものへの反応であり、死体損壊という具体的な行為に還元され得ないものだった。そこにはカニバリスムのタブーを侵犯するものへの憎悪が見て取れる。(黒田大河「カニバリスムの彼方へ・芥川龍之介と我々の時代」、『国文学解釈と鑑賞』2010年2月号) 芥川の小説からテーマを概念的に抽出する傾向については福田恒存がつぎのように警告しているそうです。孫引きになります。図書館で原書を探しましたが、見つけられませんでした。少し長いのですが引用させていただきます。――「初期の作品を見てもすぐわかることは、人間の善良さとその醜悪さとを両方同時に見てとる作者の眼であります。ぼくが読者諸君にお願いするのは、さういう龍之介の心を味わっていただきたいといふ一言につきます。『羅生門』や『偸盗(ちゅうとう)』に人間のエゴイズムを読みとってみてもはじまりません。(中略)多くの芥川龍之介解説は作品からこの種の主題の抽出をおこなって能事をはれりとする。さういふ感心のしかたをするからこそ、逆に龍之介の文学を、浅薄な理智主義あるいは懐疑主義として軽蔑するひとたちもでてくるのです。(『名指導で読む筑摩書房なつかしの高校国語』ちくま学芸文庫P042、福田恒存「芥川龍之介」) 短篇小説はさらさらと読み流してはいけない。それをしみじみとかんじさせてくれたのが、今回の関連本30冊の完全読破でした。(山本藤光:2009.06.02初稿、2015.01.18改稿)
2015年01月18日
コメント(0)
-
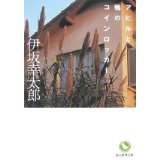
伊坂幸太郎『アヒルと鴨のコインロッカー』(創元推理文庫)
引っ越してきたアパートで出会ったのは、悪魔めいた印象の長身の青年。初対面だというのに、彼はいきなり「一緒に本屋を襲わないか」と持ちかけてきた。彼の標的はたった一冊の広辞苑!?そんなおかしな話に乗る気などなかったのに、なぜか僕は決行の夜、モデルガンを手に書店の裏口に立ってしまったのだ! 注目の気鋭が放つ清冽な傑作。第25回吉川英治文学新人賞受賞作。(「BOOK」データベースより)■伊坂幸太郎『アヒルと鴨のコインロッカー』(創元推理文庫)◎現在と2年前の出し入れ『アヒルと鴨のコインロッカー』(創元推理文庫)を高く評価します。緻密なストーリ展開、味のある会話、ユーモアという香辛料、仙台という魅力的な舞台。どれもこれも一級品でした。もっと早くに読んでおけばよかったと後悔したほどです。『アヒルと鴨のコインロッカー』を読んでいて、村上春樹を重ねてしまいました。ディテールを描く巧みさは、村上春樹よりも上かもしれません。後日「北上次郎×大森望『読むのが怖い!』(ロッキング・オン)を読んでいると、『アヒルと鴨のコインロッカー』についてこんなやりとりがありました。追記しておきます。北上:つかみがすごくうまいんだよね。広辞苑を盗みに書店に入る話っていうだけで、「何それ?」って思うじゃない。大森:まあそこは村上春樹の『パン屋再襲撃』(文春文庫)が下敷きだと思いますけど。 さらに私の脳裏を、ちらついた作品があります。カミュ『異邦人』(新潮文庫)です。脇役の個性がそっくりなのです。【『異邦人』の脇役】・老犬を散歩に連れ出す老人・サラマノ・女を食い物にしていると噂されるレイモン 老人は引きこもりの外国人と重なりますし、レイモンは河崎と似ています。 伊坂幸太郎は、『あるキング』(徳間文庫)のエピソードをつぎのように語っています。――「早く出てくればいい」というセリフは、書いた時にはほとんど忘れていたけれど、今思うと、打海文三さんの『ぼくが愛したゴウスト』(補:中公文庫)の影響があるのかもしれません」(木村俊介『物語論』講談社現代新書のインタビュー記事P248より) 打海文三のこの作品が伊坂作品に、どのような影響をおよぼしているのかの、検証はまだおこなっていません。おそらく短い会話に、共通点があるのかもしれません。 本書は「カットバック」といわれている形式で書かれています。カットバックとは、2つの場面を交互に挿入して、劇的効果を高める映画の技術のことです。評論家も誤用することがありますが、「フラッシュバック」とは違います。「フラッシュバック」は映画で物語の進行中に、過去のできごとを挿入する技術のことです。 文学用語としては、カットバックはあまりなじまないかもしれません。 伊坂幸太郎はみごとに「現在」と「過去」を書き分けていました。独立したものとして、2つを書くのは簡単なことです。それらをいかにつなげるかが、作家としての手腕なのです。 間違えないように読んでいただきたいと思います。私も少し混乱しましたので、読書メモからポイントをおさえておきます。 僕(椎名):関東から仙台へ引っ越してきたばかりの大学生河崎:僕のアパートの住人(103号室)。引きこもりの外国人:アパートの住人(101号室)。私(琴美):ペットショップでアルバイト。ドルジ:ブータンからの留学生。琴美と同棲。麗子:ペットショップの店長。 主な登場人物は、これだけです。乗船準備はできましたか。いざ過去と現在の荒波のなかへ、出航です。◎味わい深い文章『アヒルと鴨のコインロッカー』は、ストーリーを紹介してしまうと興ざめになります。したがってポイントだけのつまみぐいでお茶を濁すことにします。 読者はプロローグでぐいぐい作品のなかへと引きこまれることになります。3箇所ほど書き抜いてみます。――「僕はモデルガンを握って、書店を見張っていた」(本文P7)――「椎名のやることは難しくないんだ」河崎はそう言っていた(本文P8)――当の河崎はすでに、閉店直前の書店に飛び込んで、「広辞苑」を奪いに行った(本文P9)『アヒルと鴨のコインロッカー』の映画(監督:中村義洋)は、2008年1月に公開されました。その案内パンフレットにはこんな文章がならんでいました。――「人生を変えるほどの切なさが、ここにある」――「誰かが来るのを待ってたんだ。ディランを歌う男だとは思わなかった」――仙台に越してきたその日に、ボブ・ディランの「風に吹かれて」を口ずさみながら、片付けをしていた椎名は、隣人の河崎に声をかけられた。/「一緒に本屋を襲わないか」/同じアバートに住む引きこもりの留学生・ドルジに、一冊の広辞苑を贈りたい、という。(映画パンフレットからの引用) 「伊坂幸太郎WORLD&LOVE!」(洋泉社MOOK)は、伊坂幸太郎の世界を網羅した、ファン必見の1冊です。そのなかからいくつかを書き抜いておきます。――心に残るセリフ:(補:悪戯電話があった琴美だが河崎に気を遣わせないようにいう言葉)「楽しく生きるには、二つのことだけ守ればいいんだから。車のクラクションを鳴らさないことと、細かいことを気にしないこと、それだけ」(本文P258)――(補:ブータン人は自分のためでなく他人のために祈るのか? という琴美の質問に対する川崎の答え)「世の中の動物や人間が幸せになれればいいと思うのは当然だろう。生まれ変わりの長い人生の中で、たまたま出会ったんだ。少しの間くらいは仲良くやろうじゃないか」(本文P350) つまみぐいだけで、おなか一杯になったかと思います。伊坂幸太郎の文章には、シンプルゆえの味わいがあります。私はその後、『SOSの猿』(中公文庫)『死神の精度』(文春文庫)なども読みましたが、『アヒルと鴨のコインロッカー』を1著者1作品の推薦作であることは揺るぎませんでした。(山本藤光:2009.08.05初稿、2014.08.30改稿)
2015年01月17日
コメント(0)
-
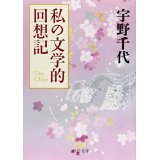
宇野千代『私の文学的回想記』(中公文庫)
大正、昭和初期の流行作家である芥川龍之介や菊池寛などが集まるレストランで十八日間だけ働いた宇野千代は、後に自らも筆を執り、女流作家の地位を確かなものにしていく…。尾崎士郎・東郷青児との愛情や、梶井基次郎・萩原朔太郎を始めとする作家たちとの友情に彩られた、彼女の鮮やかな半生を綴る貴重な文壇史随筆集。(「BOOK」データベースより)■宇野千代『私の文学的回想記』(中公文庫)◎単なる情痴作家ではない 宇野千代の代表的な小説は、『色ざんげ』と『おはん』(ともに新潮文庫)と明言できます。両作品を読んだ私は、宇野千代のとりこになりました。作品の中身はもちろんですが、宇野千代の織りなす文章のみごとさに魅せられました。――この作家は一般に考えられているような単なる情痴作家ではない。彼女の筆致はふくよかで、感覚的で、女らしい情感にあふれ、恋する人たちの微妙な心理のニュアンスを描くのに巧みであり、とくに恋に身を焼く女の、純粋で一本気な情熱を描くのを得意とする。(『新潮日本文学小辞典』新潮社より) もうひとつだけ、宇野千代の文章を評したものをご紹介します。――宇野千代が実人生をそのまま書けば、生ぐさく、どろどろした愛欲小説になるだろう。だが、宇野の私小説では、そうした生ぐささはきれいに捨象されてしまって、なにか人形浄瑠璃を思わせる、この世ならぬ美しさを創出し得ているのである。(百目鬼恭三郎『現代の作家一〇一人』新潮社P45)それ以来、彼女のエッセイばかりむさぼり読んでいます。エッセイの代表作は『生きて行く私』(中公文庫、初出1983年)であり、ベストセラーになりました。今回とりあげるのは、それよりも10年前に上梓された『私の文学的回想記』(中公文庫、初出1972年)のほうです。待望の文庫化が実現しましたので、入手は容易だと思います。本書を読んでおもしろかったら、ぜひ『生きて行く私』も探し求めていただきたいと思います。角川文庫版ならまだ店頭にならんでいます。 宇野千代が痴情作家のラベルを張られるのは、自由奔放な若いころの略歴にあります。以下、四半世紀のぶんのみ抜粋しておきます。・1897年:誕生。父が宇野千代より12歳上の女性と再婚。・14歳:義母(父の再婚相手)の姉の子・藤村亮一に嫁入り、10日間で戻る。・19歳:亮一の弟・忠(京都第2高等学校生)と同棲。・22歳:忠と結婚。札幌に住む。・24歳:「脂粉の顔」が「時事新報」の懸賞で当選。次点が尾崎士郎で、選外が横光利一。・25歳:夫を残して上京。尾崎士郎と同棲。その後結婚。 その後は梶井基次郎、東郷青児、北原武夫らとの恋、同棲、結婚をくりかえします。詳細は本書にゆずりますが、自由奔放な生涯を、宇野千代は激走しています。『私の文学的回想記』にはほかに、芥川龍之介、川端康成、萩原朔太郎、村岡花子、室生犀星、三好達治などの固有名詞がふんだんに盛りこまれています。◎カマトトに徹しきった美しさ 宇野千代の文体について、前出の百目鬼恭三郎はつぎのようにも書いています。宇野千代の性格にも言及していて、ひじょうに興味深く思いました。――この特色は結局、モラリストの影響よりも、もっと根源的なもの、すなわち宇野自身の性格に由来しているのではあるまいか。簡単にいうと、宇野は、いやなもの、つごうのわるいことは見たくない、聞きたくない、という弱者の防衛本能に忠実に従っているのであり、つまりはカマトトに徹しきった美しさ、というべきものであろう。(百目鬼恭三郎『現代の作家一〇一人』新潮社P46) 自由奔放、放埓(ほうらつ)、本能のおもむくまま……。さまざまな言葉が宇野千代の冠として用いられています。しかし私には百目鬼恭三郎がいうように、ピュアでシャイであっけらかんとした宇野千代像しか浮かびません。 宇野千代にまつわる愉快な話を紹介します。――その日、私は宇野さんに一枚の紙に書いた人々の名前を机に置いて聞いてみた。年譜や作品に出てくる宇野さんの交渉のあった男性の名簿だった。/「伺っていいですか? 先生、この方とは……」/どういう御縁で、先生の小説にどんな影響を与えたかというようなことを訊くつもりだった。ところが、間髪もいれず宇野さんの高い声が返ってきた。/「寝た」/私はど肝を抜かれて、次の人の名をあげた。/「寝た」/前より速さが加わっていた。(瀬戸内寂聴『奇縁まんだら』日本経済新聞社) 私はみていないのですが、黒柳徹子の『徹子の部屋』に出演したときにも同様の「寝た」連発があったようです。 森まゆみ『断髪のモダンガール』(文春文庫P336)のなかで、宇野千代の恋愛名語録が紹介されています。思わず笑ってしましましたので、引用させてもらいます。――男にとって自分が重荷だと感じたとき別れてやるのが武士のたしなみです。――男にだまされるという楽しみもあるのですよ。――1晩泣いて、カラリとして、いい着物きて表へ出れば、また違う男がめっかるのよ――傷はうけたひとがこしらえるものです。 宇野千代が『おはん』(新潮文庫)を上梓したのは60歳(1957年)のときでした。その後、4番目の夫・北原武夫と別れます。離婚後の宇野千代はつぎつぎに名作を書き上げました。そして98歳での大往生をとげたのでした。『私の文学的回想記』には、宇野千代が「寝た」人たちの多くが登場しています。瀬戸内寂聴『奇縁まんだら』によると、小林秀雄とは雑魚寝はしたけれど、寝なかったと書かれていました。念のため。(山本藤光:2014.08.26)
2015年01月16日
コメント(0)
-

シャーロット・ブロンテ『ジェーン・エア』(上下巻、光文社古典新訳文庫、小尾芙佐訳)
シャーロット・ブロンテ『ジェーン・エア』(上下巻、光文社古典新訳文庫、小尾芙佐訳)幼くして両親を亡くしたジェイン・エアは、引き取られた伯母の家で疎まれ、寄宿学校に預けられる。そこで心を通わせられる人々と出会ったジェインは、8年間を過ごした後、自立を決意。家庭教師として出向いた館で主のロチェスターと出会うのだった。ジェインの運命の扉が開かれた。(「BOOK」データベースより)■シャーロット・ブロンテ『ジェーン・エア』(上下巻、光文社古典新訳文庫、小尾芙佐訳)◎『ジェーン・エア』は自伝小説『ジェーン・エア』をはじめて読んだのは、おそらく高校時代、角川文庫(田部隆次訳)だったと思います。エミリー・ブロンテ『嵐が丘』(新潮文庫)を読んで、お姉さんのほうにも関心がむいたのでしょう。実際にはブロンテ3姉妹ですが、残念ながら3女・アンの著作は住まい(北海道標茶=しべちゃ町。私の筆名標茶=しるべちやは、ここから拝借しています)の図書館にはありませんでした。 今回新訳(光文社古典新訳文庫、小尾芙佐訳)がでたので、再読してみました。再読といっても、ほとんど記憶に残っていませんでしたので、初々しい気持ちで読むことができました。『ジェーン・エア』は「自伝」と明確な副題がついています。そのあたりについて、小説と現実を重ねてみたいと思います。小説1:幼くして両親を失ったジェーン・エアは、冷酷な伯母の家に預けられます。現実1:C・ブロンテは1816年、イギリスのヨークシャーの牧師パトリック・ブロンテの長女として生まれました。5歳のときに母を失い、伯母に育てられます。小説2:その後ジェーンは、ローウッドというひどい環境の寄宿舎に送りこまれます。ジェーンはここで生徒として6年、教師として2年をすごします。現実2:1824年、ランカシャーのカウアン・ブリッジ校に入学します。その学校は施設・教育ともにひどく、2人の姉は学校の不衛生が原因で肺炎のために死去しました。小説3:18歳になったジェーンは、ロチェスター家に家庭教師として雇われます。ジェーンは醜男の主人と恋におちいり結婚の約束をします。現実3:1842年、教師資格を得るためにブリュッセルの学校に入学します。そこで妻帯者のエジェ氏に特別の感情を抱きます。 ところが結婚式の当日、ロチェスターは精神を病んだ妻を、屋敷の奥に幽閉していることが明らかになります。深い悲しみのなか、ジェーンは屋敷を去ります。 そして牧師をしているセント・ジョンに救われ、プロポーズされます。しかし彼の生き方に同調できず、ジェーンはその申し出を断ります。ある夜のことです。ジェーンは遠くで自分を呼んでいる声を耳にします。不吉な思いのなか、彼女は屋敷へと飛んでかえります。そこでジェーンが目のあたりにしたのは、火事で妻を亡くし、片腕を失い盲目となったロチェスターの姿でした。 C・ブロンテのおいたちから、作品を照射した解説があります。――ジェーン・エアは「ちびで、血色がさえない上に、不細工で、ひと癖もふた癖もある顔」をした家庭教師だったが、真の意味の愛と自由を求めつづけていた。この愛と自由を追求する姿勢は、「なぜわたしがこのように苦しまなければならないのか、という問いかけ」を発した子供時代から一貫している。(知の系譜明快案内シリーズ『イギリス文学・名作と主人公』自由国民社)◎少年少女小説ベスト45位意外に思われるかもしれませんが、『ジェーン・エア』は老若男女から親しまれています。『少年少女小説ベスト100』(文春文庫ビジュアル版)という本があります。各界の著名人143名が選んだものです。私の読書の道しるべになっている本のひとつです。『ジェーン・エア』は、トゥエイン『ハックルベリの冒険』とともに45位にランクされています。ちなみに第1位はダニエル・デフォー『ロビンソン漂流記』、つづいてアレキサンドル・デュマ・ベール『岩窟王』、ジュール・ベルヌ『十五少年漂流記』、スティーブンスン『宝島』、バーネット『小公子』となっています。日本の作品では、中勘助『銀の匙』11位、宮沢賢治『風の又三郎』20位、下村湖人『次郎物語』22位となっています。夏目漱石『吾輩は猫である』は57位でした。落合恵子は『ジェーン・エア』を中3のときに読み、ひどく暗いものがたりだと思ったそうです。映画『帰郷』を観て、『ジェーン・エア』の再読を思い立ちました。そして「ヒロイズム」についておおいに考えることになりました。落合恵子が引用している文章を、孫引きになりますが2つ紹介します。あまりにも的確に、本書を語ってくれているからです。――もし男性が、私たち女性の実際の姿を見ることができれば、彼らは少々驚くでしょう。どんなに賢いどんなに洞察力のある男でも、女性について錯覚に陥っていることがしばしばあるのです。(落合恵子執筆、朝日新聞社学芸部編『読みなおす一冊』朝日選書、エレン・モアズ『女性と文学』(青山誠子訳、研究社出版からの引用)――『女性と文学』(青山誠子訳、研究社出版)の著者・エレン・モアズは、ジェーン・エアの愛情の選択について、次のような解釈を加えている。「ジェーンが自尊心を持って」見つけだし、「自分を委ねることができるのは」、あらゆるものを失ったロチェスターのような男に対してだけなのである」と。(落合恵子執筆、朝日新聞社学芸部編『読みなおす一冊』朝日選書) 夏樹静子が『ジェーン・エア』を読んだのは中1のときで、「私はたちまちヒロインに感情移入した」と書いています。そしてクライマックス・シーンについて、つぎのような文章を寄せています。――深夜に「ジェーン」という叫び声を聞いて、馳せ戻るあたりで、私は魂がふるえるような感動を覚えた。ああ、これが愛なのだと、十三歳の私は生まれてはじめてそれをありありと疑似体験した。(夏樹静子の寄稿、文藝春秋編『青春の一冊』文春文庫より) 最後にジェーン・エアの人物にせまっている文章を、紹介させていただきます。――恋愛における男女の対等性を強く主張する彼女は、人間は感情に支配される存在であるという基本的な人間観をもっている。虐待には怒りを、愛情には情熱をもって応えることが人間として当然の行いであると信じている。(日本イギリス文学・文化研究所編『イギリス文学ガイド』荒地出版社P101より)『ジェーン・エア』は、中学校の図書館に常備しておかなければならない作品のようです。私は異なる訳書で3回読んでいますが、いつも新鮮な感動を覚えています。もっとも私の記憶力の欠如が、そうさせているのかもしれませんが。今回、小尾芙佐訳に接して、私は「標茶六三の海外文学100+α」の順位を、少しだけ上に修正しました。(標茶六三:2011.04.23初稿、2014.08.22改稿)
2015年01月15日
コメント(0)
-
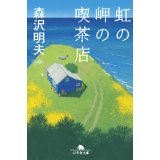
森沢明夫『虹の岬の喫茶店』(幻冬舎文庫)
小さな岬の先端にある喫茶店。そこでは美味しいコーヒーとともに、お客さんの人生に寄り添う音楽を選曲してくれる。その店に引き寄せられるように集まる、心に傷を抱えた人人―彼らの人生は、その店との出逢いと女主人の言葉で、大きく変化し始める。疲れた心にやさしさが染み入り、温かな感動で満たされる。癒しの傑作感涙小説。(「BOOK」データベースより)■森沢明夫『虹の岬の喫茶店』(幻冬舎文庫)◎吉永小百合さん「映画にしたい」 朝日新聞(2014.9.5)で、「吉永さん『映画にしたい』主演も」の見出しをみつけました。それだけで胸が高鳴りました。森沢明夫『虹の岬の喫茶店』(幻冬舎文庫)は、ウルウルさせられた作品でした。作品を読みながら、行ったことのない岬の喫茶店はしっかりとイメージできました。 舞台となった喫茶店は、一度火災で焼失しましたが、現在再建されているようです。千葉県鋸南町の明鐘岬の「音楽と珈琲の店・岬」は、著者の森沢明夫が雑誌の取材で訪れたところです。岬の風景と店主の玉木節子さんの人柄に、ほれこんだ森沢明夫はものがたりをつむぎだします。――岬は陸のいきどまりだが、そこから海が無限に広がっており、終着点のような出発点のような場所。人間って目の前に絶景があると感動して、変われると思う。最近、友人があの店でプロポーズして、OKをもらったのですよ。(朝日新聞の記事、森沢明夫談より) 本書の初出は2011年ですから、吉永小百合が3年目に種火に火をつけたことになります。ちなみに映画のタイトルは、「ふしぎな岬の物語」となっています。 著者の公式ページをのぞいてみました。森沢明夫のブログがありました。こんなことが書いてあります。「幸せってなんだろう?そんな根源的な問いかけの答えになればいいな」 傷をかかえて岬の喫茶店を訪れる人たちは、店主・悦子さんが「おいしくなぁれ、おいしくなぁれ」と呪文をかけたコーヒに癒されます。悦子さんが選んだ音楽で元気をもらいます。そしてなによりも、悦子さんの真心のこもった言葉で新たな世界を発見するのです。 私は個人的に、本書は第1章だけの作品だったらよかったのに、と思っています。幼い娘を残して世を去った妻との思い出。幼い娘の無邪気さ。夫を亡くした悦子さんの喫茶店。この章をふくらませたものを、読んでみたいと思います。◎虹を探す冒険と旅『虹の岬の喫茶店』は、喫茶店をめぐるオムニバス形式の人情ドラマです。本書は6章の構成で、仕立てられています。しかもバトンリレーのように各章がつながっています。それぞれの章には、「第1章〈春〉アメイジング・グレイス」というように、季節と音楽のタイトルがつけられています。 第1章は妻を失って、途方にくれる若い父親と幼い娘の話です。男は陶芸作家ですが、暮しは楽ではありません。香典返しのリストをチェックしたり、娘の食事をつくったりとてんてこ舞いの毎日をすごしています。 マンションのベランダでみた虹を追って、車を走らせた親子は偶然、岬の喫茶店にたどり着きます。虹はみつけられませんでしたが、お店に壁に飾った絵のなかに虹を発見します。――光の粒子をちりばめたような見事なオレンジに染まった夕空と海。そこに、神々しいような虹が架かっている。虹は、空と海よりも一段と輝いていた。額のなかの世界は、とても絵画的で、現実離れしたような光彩を放っているのだが、しかし海の向こうに描かれた半島の形や富士山の配置からすると、この店の窓の外に広がる風景を写生したことは明らかだった。(本文P55より) 絵を描いたのは、岬の喫茶店の初老の店主・柏木悦子さんの亡き夫です。悦子さんは夫の描いた虹をみたいと、喫茶店を開いたのです。悦子さんが親子に「どうしてここへ?」と質問します。「パパとね、虹さがしの冒険をしてたの」と幼い声が答えます。悦子さんはつぶやきます。「じゃあ、私と同じ旅をしてたのね」と。 第2章は就職活動がうまくいっていない、大学生の話です。乗っていたバイクがガス欠をおこし、やっとの思いで岬の喫茶店にたどりつきます。第1章と同じように、片足のないコタローという白い犬に迎えられます。大学生はそこで、画家の卵のみどりさんと出会います。悦子さんの話を聞き、みどりさんの姿をみて、大学生はフリーライターになると自らの進路をきめます。 以下はつぎのような話がつづきます。悦子さんに恋する初老の建築会社重役の話。生涯独身をつらぬき、子会社へ流される前にお店に顔を出します。 泥棒がはいります。そしてずっと悦子さんを気遣う甥の浩司の話。終章で浩司は、いつの間にか2児の父親になっています。 森沢明夫は寂しい舞台で、心温まるものがたりを提供してくれました。いまごろ悦子さんはどうしているのでしょうか。行ってみたいお店が、また1軒増えたようです。(山本藤光:2014.12.18)
2015年01月13日
コメント(0)
-
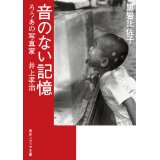
黒岩比佐子『音のない記憶・ろうあの写真家・井上孝治』(角川ソフィア文庫)
生きることに希望と誇りをもち続けた日本一のアマチュア写真家、井上孝治。父から聾学校の卒業祝いにカメラを贈られると、一気に才能を開花させ、人、街、生活のスナップショットを撮り続けた。百貨店の広告に起用された写真は、誰もがもつ「あの頃」の記憶を蘇らせ、大反響を呼ぶ。その反響は海を越え、世界で最も伝統のあるアルル国際写真フェスティバルに招待される―。異色のろうあ写真家の生涯を追う。(「BOOK」データベースより)■黒岩比佐子『音のない記憶・ろうあの写真家・井上孝治』(角川ソフィア文庫)◎黒岩比佐子のこと 八重洲ブックセンターで「追悼・黒岩比佐子」のコーナーに遭遇しました。思わず「嘘だろう」と叫んでしまいました。黒岩比佐子とはずっと、メールでのやりとりをしていた間柄です。会社の後輩の友人ということもあり、気安く日常のできごとを交換していました。それが突然の訃報。 2010年52歳の若さで、すい臓がんのために世を去ってしまいました。その後遺作ともいえる『パンとペン・社会主義者・堺利彦と「売文社」の闘い』(講談社文庫)で読売文学賞(評論・伝記部門)を没後受賞しています。 黒岩比佐子について書いた、古い原稿を転載させてもらいます。(PHP研究所メルマガ「ブックチェイス」1999年11月15日号)(引用はじまり) 黒岩比佐子の趣味(実益をかねているけれど)は、古書収集です。自ら「古書の森日記」というホームページを立ち上げています。毎回写真入で、ゲットした古書を紹介してくれます。 杉森久英『天才と狂人の間・島田清次郎の生涯』(河出文庫)を読んでいて、島田清次郎『地上』を読みたくなっていました。古書店を探さなければ見つかりません。ネット検索してみました。ヒットしたのが、黒岩比佐子のページでした。 黒岩比佐子は、島田清次郎『地上』をゲットしていました。写真つきで「安く手に入れた」と書いています。さっそくHPのメッセージ欄に書き込みをしました。しばらくメールをしていませんでした。「おひさぶりです」と返信が返ってきました。私と黒岩比佐子の出会いは、『伝書鳩・もうひとつのIT』(角川ソフィア文庫)の書評を書いて以来のことです。この本については「山本藤光の文庫で読む500+α」の番外(+α)でとりあげるつもりです。 島田清次郎が、10年間のブランクを埋めてくれたのです。それ以来ひんぱんに古書のことや日常のことをメールしあうようになりました。(引用おわり)◎たった1冊、ひっそりと 黒岩比佐子『音のない記憶』(初出1999年文藝春秋、現・角川ソフィア文庫)は書店の新刊本コーナーに、たった一冊だけ背を向けて置かれていました。なにげなく手にとってみました。そしてパラパラとめくってみました。白黒のスナップ写真が、目に飛び込んできました。圧倒されました。著者・黒岩比佐子も写真家・井上孝治の名前も、聞いたことがありませんでした。 海を見ている2組のカップルを、背後から撮った写真には「1956年3月・福岡・西公園展望所」と書かれていました。ふたつのベンチに、カップルは均一な距離で坐っています。眼前には白い湾が広がっています。クレーンのそばからは、白い湯気が立ち上がっていました。 音の存在しない沈黙の写真。船舶の音も、クレーンの音も、湯気が立ち上る音も、ましてや2組のカップルの会話も遮断してしまった写真。私は長いこと、そのスナップ写真に見入りました。そして心底すごいと思いました。 ――言葉を操って、自分の思いを自由に語ることができない孝治は、そのもどかしさを常に心の中で感じていたに違いない。そんな時、彼は写真を通じて自分の感じたことや伝えたいことを表現できる、ということを発見したのだろう。(本文より) 黒岩比佐子は、こうも書いています。要約してみます。――写真は「目」で撮るのだから、「耳」が聞こえなくともハンディキャップはない、と考える人がいるかもしれない。静物写真ならそうかもしれない。しかし一般的には、風の音、会話の音、通りを走る車の音などを、写真のなかに写し取る。井上孝治の写真が衝撃的なのは、すべてが「その一瞬」で停まっているように見えることにある。 たとえば、ソフトボールに興ずる投手と打者の写真があります。写真は打者の背後から撮られています。2人とも婦人です。投手がボールを放した瞬間に、シャッターが切られています。ピントは投手にあてられています。ボールは、打者と投手の間で「停まって」います。 著者・黒岩比佐子は、フリーランスのライター。彼女が70歳になる井上孝治と出会ったのは10年前。そのとき井上孝治は、ただの年寄りでした。福岡の老舗の百貨店がキャンペーンのために、1950年半ばころの庶民の生活を撮った、写真を探していました。 報道写真は数多く存在していましたが、イメージに合うものは見つかりませんでした。そんなとき偶然にも、百貨店の広告写真を手がけていた井上一が、父親のことを思い出します。そして処分されかけていた、膨大なネガが甦りました。 キャンペーンで使われた写真は、たちまち評判になりました。写真家・井上孝治の誕生です。井上孝治に魅せられた黒岩比佐子は、彼の生涯を実に丹念に描いています。また本文の間に挿入されている、スナップ写真も魅力に富んでいます。 3歳のときに階段から落ちて、聴力を失った井上孝治。写真を唯一の自己表現手段として、挑戦し続けた生涯。私の書棚には、井上孝治の写真集が2冊ならんでいます。『想い出の街』と『こどものいた街』(ともに河出書房新社)です。黒岩比佐子も井上孝治もこの世にはいませんが、私の大切な記憶のなかでは生きています。(山本藤光標茶六三:2009.05.29初稿、2014.09.03改稿)
2015年01月12日
コメント(0)
-
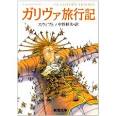
スウィフト『ガリヴァー旅行記』(新潮文庫、中野好夫訳)
船員ガリヴァの漂流記に仮託して、当時のイギリス社会の事件や風俗を批判しながら、人間性一般への痛烈な諷刺を展開させた傑作。(文庫案内より)■スウィフト『ガリヴァー旅行記』(新潮文庫、中野好夫訳)◎知らなかった本当の『ガリヴァー旅行記』『ガリヴァー旅行記』(新潮文庫、中野好夫訳)は、小人国と大人国の話だけだと誤解していました。実際には4部よりなりたち、こどものころから親しんでいたのは、そのなかの1部と2部だったのです。さらに記憶の片隅にもなかったことがあります。『ガリヴァー旅行記』には、日本も登場していました。――われわれは日本の東南部にあるザモスキと呼ぶ小さな港町に上陸した。町は、狭い海峡が北の方へ向かってちょうど長い腕のように伸びている。その西端にあるわけだが、さらにその腕の北西部にあたるところが首都のエド(江戸)があった。我輩は上陸すると、まず税関役人にラグナダ王からこの国の皇帝に宛てた親書を出して見せた。(本文より) 日本に関する記述は、きわめて短いものです。詳細な見聞録は、書きこまれていません。日本は『ガリヴァー旅行記』のなかで、唯一の現存する国です。作者のスウィフトが来航したという記録はありません。当時日本は江戸中期であり、鎖国のまっただなかでした。それゆえ、日本人の容姿や風俗に関する記載は、遠ざけたのでしょう。 主人公のガリヴァーは、1662年にイギリスの片田舎で生まれます。ケンブリッジで寮生活を送り、ロンドンで医学を学びます。23歳のときに船医となり、その後17年間未知の国をめぐることになります。結婚はしていました。 第1部は小人国。第2部は大人国。第3部は宙に浮いている島や日本。第4部は馬が主人で、ヤフーと呼ばれる人間が家来という島への渡航記となっています。『ガリヴァー旅行記』は、著者スウィフトの絶望的な生い立ちを、社会に向けた刃でした。◎絵本で知っている世界 サマセット・モームは著書『世界文学読書案内』(岩波文庫)で、『ガリヴァー旅行記』をつぎのとおり絶賛しています。――『ガリヴァー旅行記』は、機知あり、皮肉あり、さらに巧みな思いつきあり、淫らなユーモア、痛烈な諷刺、溌剌とした生気をもつ作品である。その文体は感嘆のほかはない。わたくしたちの国語であるこの厄介な英語を用いて、スウィフトのような、簡潔で明快で、素朴な文章を書いた者はほかにない。(本文より) 私が『ガリヴァー旅行記』を読んで苦労したのは、マイルやヤードやフィートなど単位の表記でした。とっさに判断できないので、いちいち頭のなかで換算しなければ、情景が浮かんできませんでした。本書を読むときは、単位の換算表を常備しておくことをお薦めします。 小人国リリパットは、いまの世の中をミニサイズにした世界です。人間の平均身長は約15センチメートル(6インチ)です。動物も自然も家屋も、同じ比率で小さくなっています。ガリヴァは宮廷に仕え、数々の試練に立ち向かいます。海を歩いて渡り、敵の国から軍艦50隻を根こそぎ奪いとります。王妃の御殿が火災になったときは、放尿で炎上を食いとめました。 大人国ブロブディナグでは、小人国と真逆の世界が待ち受けています。すべてが桁違いに大きく、鳥獣に襲われたり、降ってきた雹(ひょう)に傷ついたりします。 ここまでが絵本で知っている『ガリヴァー旅行記』でしょう。諷刺もそんなに鋭くなく、なぜこの作品が諷刺文学といわれるのだろうか、などと疑問に思ってしまうほどです。前記のように、モームが指摘しているスウィフトの毒矢は、第3部以降に大量放出されることになります。 第3部では、抽象的な思考しかできない人間が住む、宙に浮かぶ島・ラピュタです。そこには不死の人間が住んでいます。さらに前記の日本が登場します。ガリヴァーは長崎から江戸へとたどり、踏み絵を免除してもらいます。寂しいのですが、日本に関する描写はそれだけでした。 第4部は、馬が人間(ヤフー)を統治するフウイネムへの航海日誌となります。ヤフーは剛毛に覆われ、知能もなく醜悪な存在として描かれています。ガリヴァーの姿かたちは、ヤフーと似ています。しかし彼は衣服を身につけており、体毛もありません。馬が統治する国でのガリヴァーは、外見と知性のちがいが顕著に描かれています。『ガリヴァー旅行記』は、人間に対する諷刺に満ちています。大人国でガリヴァーが読んだ、「人間」に関する本の説明を引用してみましょう。この本は婦女子や通俗読者以外には、省みられないとの前提がついています。――生まれながらの人間というものが、いかに矮小な、卑しむべき、そして無力な動物であるか、天候の酷烈、野獣の怒りに対してさえ身を衛(まも)ることができないではないか、強さにおいても、速さにおいても、先見能力においても、はたまた勤勉においても、それをはるかに凌ぐ動物があるといった風なことを論証している。(本文より) 詳細については、これ以上ふれません。よくぞここまで書いた、と圧倒されました。この作品は、激しい憎しみがなければ書くことができなかったでしょう。それほど、スウィフトの怨念は激しいものだったのだと思いました。 ◎ちょっと寄り道 『ガリヴァー旅行記』の第4部に、刺激されたのか否かはわかりません。1970年に日本で、沼正三『家畜人ヤフー』(角川文庫)が発表されて大騒動になったことがあります。日本人の後裔ヤフーが白人女性に隷属される話です。いまでは明らかになっていますが当時は、沼正三とはなにものなのか、とんでもなく日本人を侮蔑している、など大騒ぎになりました。書棚から引っ張り出してみると、ページは黄色く変化していました。この作品は一読をお薦めしたいと思います。また原爆文学で知られる原民喜(推薦作『夏の花』新潮文庫)に、『ガリバー旅行記』(講談社文芸文庫)という著作があります。絶版で入手は難しかったのですが、「青空文庫」(無料の電子書籍)にはいっていることを知りました。私は神田の古本屋で高価な1冊を購入しましたが。 不思議に思ったことがあります。以前(1998年ころ)、講談社から『痛快世界の冒険小説(全24巻)』が発売されています。ここには『ガリヴァー旅行記』の姿はありません。志水辰夫が『十五少年漂流記』を訳出したり、楽しい企画だったのですが。(山本藤光:2013.04.27初稿、2014.08.31改稿)
2015年01月11日
コメント(0)
-
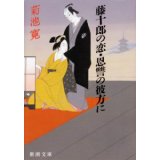
菊池寛『恩讐の彼方に』(新潮文庫)
元禄期の名優坂田藤十郎の偽りの恋を描いた『藤十郎の恋』、耶馬渓にまつわる伝説を素材に、仇討ちをその非人間性のゆえに否定した『恩讐の彼方に』、ほか『忠直卿行状記』『入れ札』『俊寛』など、初期の作品中、歴史物の佳作10編を収める。著者は創作によって封建性の打破に努めたが、博覧多読の収穫である題材の広さと異色あるテーマはその作風の大きな特色をなしている。(「BOOK」データベースより)■菊池寛『恩讐の彼方に』(新潮文庫)◎罪を背負って 菊地寛『藤十郎の恋/恩讐の彼方に』(新潮文庫)には、ほかに「入れ札」「俊寛」など10短篇が所収されています。そのなかで私のいちばんのお気に入り、「恩讐の彼方に」をとりあげることにしました。 市九郎は旗本家の奉公人です。主君・中川三郎兵衛の愛妾・お弓との姦通が露見してしまいます。市九郎は成敗しようとする主人を、逆に切り殺します。市九郎はお弓を連れて、江戸からの脱出をはかります。 2人は悪行をくり返しながら、やがて木曾の鳥居峠で茶店をかまえます。表向きはまともな客商売をし、裏では強盗をはたらきます。市九郎は主君殺しの罪に、たえず良心の呵責をおぼえています。――けんぺき茶の女中上りの、莫連者お弓は、市九郎が少しでも沈んだ様子を見せると、「どうせ凶状持ちになったからには、いくらくよくよしても仕様がないじゃないか。度胸を据えて世の中を面白く暮らすのが上分別さ」と、市九郎の心に、明暮悪の拍車をかけた。(本文より) 隠遁生活から3年目のある日、若夫婦が茶店に立ち寄りました。市九郎は間道で待ち伏せ、2人を切り捨てて金品を巻き上げます。ところが茶屋に戻った市九郎を、お弓は口汚くののしります。市九郎がかんざしを奪い忘れて、戻ったからでした。お弓は自ら、2人の亡骸のある場所へと向かいます。 あさましいその行状に嫌気がさして、市九郎はお弓を捨てて出家しようときめます。市九郎は仏道に帰依し、了海と名乗ります。厳しい修行を続け、やがて市九郎(了海)は立派な僧侶となります。 旅人や病人に手を差し伸べ、川に橋をかけ、悪路を修復し、市九郎は罪を悔いながら、ひたすら諸国行脚の旅をつづけます。豊前の国に入った市九郎は、旅人を苦しめる巨大な岸壁に遭遇します。ここでは年に10人ほどの旅人が、命を落としています。岸壁をくりぬいてトンネルを掘る。それがあたえられた贖罪である。市九郎は、巨大な岩壁に立ち向かいます。 ◎作品のベースは実話 ものがたりは前記のとおりです。あえて後段は、紹介しないでおきました。この作品には、モデルがあります。実話をもとにした作品なのです。大分県の「青の洞門」といえば、知らない人はいないでしょう。 以下は大分県中津市のホームページに紹介されている、「青の洞門」に関する記事です。(引用はじめ) 「大正8年に発表された菊池寛の短編小説「恩讐の彼方に」で一躍有名になった、禅海和尚が掘った洞門(トンネル)で、耶馬渓を代表する名勝である競秀峰の裾野に穿たれている。」(中略)「諸国巡礼の旅の途中に耶馬渓へ立ち寄った禅海和尚は、極めて危険な難所であった鎖渡で人馬が命を落とすのを見て、慈悲心から享保20年(1735)に洞門開削の大誓願を興したと伝えられている。」(引用おわり) 菊池寛作品の特徴は、戯曲でつちかった構成の妙だと思います。そこに著者自身の人生観が重なり、短編作家として高い評価を受けました。菊池寛の小説でのデビュー作『無名作家の日記』(岩波文庫)は、本人はもちろん芥川龍之介、久米正雄、上田敏がモデルとして登場します。 当時の「同人誌」事情に興味があれば、ぜひ読んでもらいたいと思います。菊池寛は「文芸春秋」創刊や、芥川賞・直木賞の創設で有名ですが、作品にも当時の作家たちとは異なる味わいがあります。 芥川賞・直木賞について、おもしろい記述があるので紹介させていただきます。――菊池(寛)は素直に「亡友を記念すると云うよりも、芥川、直木を失った本誌(文芸春秋)の賑やかしに、亡友の名前を使おうというのだ」と書いている。(『芥川賞事典』所収の小田切進「芥川賞の半世紀」より引用) 菊池寛は戯曲からの転換、事業への手腕など、柔軟な思考の持ち主でした。(山本藤光:2009.07.29初稿、2014.08.28改稿)
2015年01月10日
コメント(0)
-
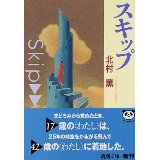
北村薫『スキップ』『ターン』『リセット』(新潮文庫)
昭和40年代の初め。わたし一ノ瀬真理子は17歳、千葉の海近くの女子高二年。それは九月、大雨で運動会の後半が中止になった夕方、わたしは家の八畳間で一人、レコードをかけ目を閉じた。目覚めたのは桜木真理子42歳。夫と17歳の娘がいる高校の国語教師。わたしは一体どうなってしまったのか。独りぼっちだ―でも、わたしは進む。心が体を歩ませる。顔をあげ、『わたし』を生きていく。(「BOOK」データベースより)■北村薫『スキップ』『ターン』『リセット』(新潮文庫)◎何束ものワラジをはいて 北村薫は早稲田大学を卒業後、13年間高校の国語教師をしていました。仕事のかたわら、創元推理文庫「日本探偵小説全集」の編集もしていました。そうしたなかで北村薫を執筆に駆り立てたのは、友人・折原一のデビューでした。 折原一は高校、大学と、北村薫の後輩として同じ道を歩いてきました。折原一のデビュー作『五つの棺』(創元推理文庫、初出1988年)を追いかけるように、先輩北村薫は1年後、『空飛ぶ馬』(創元推理文庫)で文壇の門をたたきました。 北村薫のデビュー作『空飛ぶ馬』は、女子大生の「私」がワトスン役、落語家の春(しゅん)桜亭(おうてい)円(えん)紫(し)がホームズ役を務めるミステリーです。その後北村薫は「円紫シリーズ」として続編を発表しました。このほかには、「覆面作家シリーズ」があります。私は北村薫が心境地をひらいた、「時と人の3部作」(『スキップ』『ターン』『リセット』いずれも新潮文庫)を高く評価しています。今回はここにフォーカスをあてて、ご紹介させていただきます。 さらに北村薫は、エッセイストやアンソロジストとしても活躍しています。宮部みゆきとの共著『名短篇ここにあり』(ちくま文庫)や『鮎川哲也短編傑作選』(創元推理文庫)では、すばらしい編集力を発揮しています。 2009年には「ベッキーさんシリーズ」第3弾、『鷺と雪』(文春文庫)で直木賞を受賞しました。女子学習院に通う士族令嬢・花村英子と女性運転手(ベッキーさん)が活躍する、このシリーズの完結を待ちかまえていたかのような直木賞受賞でした。ちなみに「ベッキーさんシリーズ」の第1弾は、『街の灯』(文春文庫)。第2弾は『玻璃の天』(文春文庫)です。◎『スキップ』と『ターン』の魅力 「時と人の3部作」の『スキップ』は17歳の真理子が、突然25年後の自分になっていたという話です。未成熟な10代の意識のまま、40代の環境や肉体のなかに投げ出された真理子。彼女の戸惑いと挑戦を描き、タイムトラベル小説の頂点に立つ作品です。 『ターン』(新潮文庫)の主人公は「君」こと真希で29歳。短大を卒業して入社した会社は、あっさりと倒産しました。その後、週2回こども相手の美術教室の手伝いをしながら、趣味のメゾチント(銅板版画)の売りこみをおこなっています。『ターン』は「わたし」の独白と、わたしを「君」と呼ぶ陰の声で構成されています。こんな具合です。――「だから、時間っていうのは、ぱらぱら漫画みたいなものなんじゃないかしら」/ぱらぱら漫画? /「ずらした絵を描いて、めくるやつよ。それで動いて見える」/ああ、あれか。/「だから一瞬一瞬が存在していて、それが無限に続いた連続体なのよ。一瞬がなかったら、全体もない。その絵の一枚に、わたしが止まったの」(本文より) ある日、「君」は一定の時間になると、時計が1日戻ってしまう異次元にはいりこみます。そこにはだれも存在していません。だれもが「昨日」として、消化してしまった時間だからです。したがって『ターン』に陰の声を用いるのは、必然的な手法といえます。それでなければ、小説としてなりたちようがありません。「君」は自分がおかれた境遇を「ロビンソン・クルーソー」になぞらえます。形こそ違えこの作品は、孤独からの脱出をテーマにしています。孤島にとり残されるのと、過ぎ去った時間の中にとり残されるのとのちがいがありますが。『スキップ』と『ターン』は、独立した別の作品として読むこともできます。しかし2つの作品の根底にあるのは、〈時間の流れ〉と〈孤独〉なのです。ミステリーのなかで、もっとも難しいといわれるタイムトラベルものを、北村薫は鮮やかに料理してみせました。 逆境におかれた、主人公の孤独と恐怖感。それに立ち向かいはじめる、主人公の姿勢。北村作品の主人公たちは、常に打開策を熱心に考えます。そして動きだします。動いてみてはまた考えます。計画・行動・検証のサイクルがしっかりしているから、北村作品は安定しているのです。プラン・ドウ・チェック・リサーチのサイクルは、何も営業マン向けハウツー本の専売特許ではありません。◎『リセット』で「時と人」が完結「時と人」の3部作が、6年間の時空を超えて完結しました。『スキップ』『ターン』につづく『リセット』は、見事なアンカー役を果たしました。個人的に私は、『リセット』をいちばん高く評価しています。『スキップ』は10代の少女が、突然40代の自分にスキップしてしまう話。『ターン』は信じ難い環境に封じ込められた20代後半の女性が、未来を探す話。そして『リセット』は、戦時中と現在の2つの空間を描いた作品です。 第1部は、太平洋戦争末期の神戸が舞台。主人公の真澄は女学生で、セーラー服に別れを告げ、もんぺ姿になっています。真澄はひそかに、友人・八千代の兄に思いを寄せています。この時代はまだ男女の間に封建的な壁があり、容易に接近することはできません。 第1部では、防空壕・学徒勤労動員・配給品・B29・疎開・空襲などの用語が踊ります。その隙間をうめるように、獅子座流星群・啄木かるた・「愛の一家」という本などが呼吸しています。 北村薫は渾身の力で、この作品を書きあげました。残されていた父親の日記と自分自身の少年時代の日記を、はじめて作品のなかにとりこみました。(「波」2001年1月号を参照しました)それだけに現実感あふれる作品に仕上がっています。一つひとつの情景が鮮やかに描かれており、そこに生きている登場人物の呼吸や鼓動が聞こえるほどです。 第2部以降は、説明しないほうがいいと思います。ぜひ読んで感動していただきたいと思います。『リセット』は、ほのかで淡い恋心という色を、過去と現在の2つのキャンパスに均一に塗った完成された作品でした。(山本藤光:2009.07.30初稿、2014.08.26改稿)
2015年01月09日
コメント(0)
-

中西進『日本人の忘れもの』(全3巻、ウェッジ文庫)
二十一世紀は心の時代―。かつての日本人は、心の豊かさを持っていた。だが、物質文明の発達によって、多くの日本人が心のゆたかさをどこかに忘れてきたのではないだろうか。人間を尊重する心ゆたかな社会をつくってゆくために、私たちが心がけるべきことは何か。古代から現代をつらぬく日本人の精神史を探求し続けてきた中西進が、すべての日本人の贈る言葉の花束二十一章。(「BOOK」データベースより)■中西進『日本人の忘れもの』(全3巻、ウェッジ文庫)◎大切な先生を得た 中西進との最初の出会いは、新幹線のなかでした。本人と出会ったわけではありません。目の前にあったポケットから何気なく手に取った雑誌「ウェッジ」に、著者の連載随筆が掲載されていたのです。味のある文で、忘れていたものを思い出させてくれました。随筆のわきに、『日本人の忘れもの』(ウェッジ)の宣伝がありました。 買い求めて、読んでみました。平易な文章で、鋭く「日本人の忘れもの」を諭してくれていました。この言葉には、こんな意味があったのだよ、と教えてくれました。 現在は文庫で読めますが、単行本の帯を紹介したいと思います。文庫版にはこのコピーがありませんでした。――たとえば『まけるが勝ち』といいます。勝つためには、いったん負ける。そして相手に生かされる道を探るのが、日本人の生き方でした。生かされて生きること、忘れていませんか? 文庫本には、かわりにこんな帯がつけられています。――二十一世紀は心の時代。「お下がり」は神さまからのいただきもの、神棚は聖なる場所、心のよりどころだった。神棚をなくし、よりどころを失った日本人が心ゆたかに生きるために、思い出すべき言葉の花束二十一章。 第1巻の21の花束は、ざっとこんな具合です。――まける・おやこ・はなやぐ・ことば・つらなる・けはい・かみさま・ごっこ・まなぶ・きそう・よみかき・むすび・いのち・ささげる・たべる・こよみ・おそれ・すまい・きもの・たたみ・にわ。 そしてそれぞれに、一行の添え文がつけられています。単行本の帯コピーで紹介した「まける」には、「相手に生かされる道をさぐる」などとなっています。ページをくくるたびに、目からはらはらとウロコが落ちました。 私は本書を、1週間かけて読みました。一文一文を味わいながら、読み進めました。そして、忘れものだらけの自分を発見しました。読み終えてから、心のなかで著者に「ありがとう」といっていました。こんな体験は、はじめてのことです。 著者は、古代文学比較研究の第一人者です。なるほどと思いました。いままでに読んだ文章とは、明らかにちがっていたのです。大切な先達をえたと狂喜しました。 すでに、本書は第3巻も文庫化(ウェッジ文庫)されています。1日1章をゆっくりと、読みつないでゆきたいと思っています。そんな大切な本が、また1冊増えました。◎いつでも取り出せる場所に 中西進の著作には、いつも深い感銘を受けています。私は『日本人の忘れもの』を宝物のように、いつでも取り出せる場所においてあります。ページをくくっていると、心が安らぎますし豊かにもなります。文学博士などと聞くと、難しい話ばかりなのだろうと思いがちです。ところが一般読者に向けた著作は、すこぶるわかりやすく書かれています。 つぎに引用するのはインターネットでひろった、「THE GUEST」という対談記事(2004年6月28日)です。聞き手は女優の早見優さん。以前から中西進の愛読者だったようです。(引用はじめ)早見 「先生は、全国の小学校や中学校に出向いて、万葉集を素材にした授業を行っているそうですが、生徒さんたちの反応が非常に良いそうですね」 中西 「皆さん、想像以上に興味を持ってくれて本当に嬉しくなってしまいます。多分それは、私が教えようとしていないからだと思うんですよ。教えるというのは、オトナの知識を伝達しているだけの一方通行ですから、彼らからは何も返ってこないのは当然。つまりね、物事の基本には、必ず心があって、気持ちがある、そして感情がある。それをお互いに共有しようとすれば子供たちはどんどん発言できるんですね。ですから私は、万葉集を教えようなんてこれっぽっちも思っていない。万葉集を媒体にして、みんなで感動しようとしているだけなんです」 (中略)早見 「お話を伺っていると、私も子供を教育していかなければならない親としての責任を感じます」 中西 「その通りですよ。特にお母様というのは大変です。昔は<たらちねの母>と言いましてね、これはお乳がいっぱいある、愛情が豊かということ。<ね>というのは<動かない、デーンとしている>という意味なんです。つまり、悩んでいたりフラフラしていたら母親は失格。それとね、お乳の<ち>は<血>と同じ言葉でしょう。つまり、命を養う根源のものを昔は<ち>と呼んだんですよ。そして、<ち>そのものを<力>と呼んだ。(引用おわり) いかがでしょうか。私がなにを書くよりも、対談のなかに中西進のエキスが含まれています。中西進は日本語の奥深さを、あますことなく伝えてくれます。少しばかり引用が多くなりましたが、中西進は私の稚拙な日本語では紹介できません。 とにかく読んでみていただきたい。体調が悪い時期に、大阪への出張でグリーン車を利用していました。そのときに座席前のポケットに入っていたのが、「ウェッジ」という雑誌だったのです。それが中西進を知ったきっかけでした。体調の悪さに感謝。(山本藤光標茶六三:2010.05.16初稿、2014.11.30改稿)
2015年01月08日
コメント(0)
-
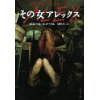
ピエール・ルメートル『その女アレックス』(文春文庫、橘明美訳)
おまえが死ぬのを見たい―男はそう言ってアレックスを監禁した。檻に幽閉され、衰弱した彼女は、死を目前に脱出を図るが…しかし、ここまでは序章にすぎない。孤独な女アレックスの壮絶なる秘密が明かされるや、物語は大逆転を繰り返し、最後に待ち受ける慟哭と驚愕へと突進するのだ。イギリス推理作家協会賞受賞作。(「BOOK」データベースより)■ピエール・ルメートル『その女アレックス』(文春文庫、橘明美訳)◎こんなすごいミステリは初めてピエール・ルメートル『その女アレックス』(文春文庫、橘明美訳)の帯コピーが、どんどん誇らしげになっています。私の文春文庫は2014年9月10日第1刷で、橙色地に「あなたの予想はすべて裏切られる!」とあります。やがて書店に平積みされている帯は、赤地で「第1位!」と大書されたものにかわりました。そして最近では「1位・6冠」のコピーが踊っています。破竹の快進撃といってよいと思います。私が本書を買い求めたのは、『このミステリがすごい!2015年版』(宝島社)で「海外部門第1位」になっていたからです。当時はひっそりと、書店の棚に背表紙だけを向けて、1冊あっただけでした。ところがあっというまに、赤い帯にかわって平積みされていました。6冠の内訳はつぎのとおりです。――『この女アレックス』が海外ミステリ史上初の6冠を達成! 「このミステリーがすごい!」や「週刊文春ミステリーベスト10」など、日本のミステリ・ランキング4つを全制覇。本国フランスでも、英訳刊行されたイギリスでも高く評価され、賞を受けています。(『本の話WEB』より)読んでみました。圧倒されました。納得の第1位です。著者のピエール・ルメートルは、もちろん知りませんでした。前記の『本の話WEB』の記事で紹介させていただきます。このサイトは充実しています。6冠達成を祝って、三橋暁、大矢博子、千街晶之、瀧井朝世が書評をならべています。ただし書評のプロたちだけあって、ネタバレにならないような自制した文章になっています。――作者紹介によれば、この作品はパリ警視庁犯罪捜査部のカミーユ・ヴェルーヴェン警部を主人公としたシリーズの第2作にあたるようだが(第1作は未紹介)、警察小説としてもその出来映えは出色である。捜査陣の要である警部のカミーユは、癇癪を破裂させたかと思うと、自分に自信が持てずに落ち込むという周囲には扱い辛い人物だが、捜査官としては優秀で、閃きと持ち前の粘り強さで自らの捜査班を率いる。並外れて小柄な身体的コンプレックスもご愛嬌だ。(三橋暁、『本の話WEB』より)ルメートルの第1作は、2009年に『死のドレスを花婿に』(柏書房)というタイトルで邦訳されています。書店を探しましたが、見つかりません。◎読者を翻弄しつづける展開 本書のストーリーについては、ネタバレになるので多くについてふれることができません。簡単に紹介させていただきます。アレックスは30歳で男を引きつけるような美人です。「ヘアウィッグとヘアピースがいくらでもある店」で試着を楽しんでいます。通りから自分を見ている、男の存在に気づきます。アレックスは店を出ます。そして突然が路上で拉致され、車で運ばれて、廃屋の倉庫のようなところへ軟禁されます。アレックスは全裸にされて、狭い檻に監禁されます。身を屈めたままの状態で、檻は空中に吊り上げられます。 本書は拉致された女性アレックスの視点と、誘拐事件を追うパリ警視庁の視点が交互にくりかえされます。アレックスは、誘拐犯がだれなのかがわかりません。なぜ誘拐されたのかもわかりません。いっぽう警察は、だれが誘拐されたのかを知りません。若い女が強引に車に押し込まれた、という目撃情報があるだけなのです。 誘拐犯はアレックスに、「お前が死ぬところを見たい」といったきりです。誘拐の動機を話そうとしません。パリ警視庁犯罪捜査部に、事件解決のための緊急チームが編成されます。大男の上司ル・グエンは、身長145センチの小柄なカミーユ・ヴェルーヴェン刑事を現場責任者に指名します。彼には妻が誘拐され殺害された、という忌まわしい過去があります。とても新たな誘拐事件を、任せられる精神状態ではありません。相棒として指名されたのは、ハンサムで金持ちのルイと、しみったれでドケチなアルマンでした。この4人がなんともいえない、味のあるやりとりをくりかえします。 檻に閉じ込められたまま、何日も経過します。アレックスの衰弱は、危機的なものになっていきます。ドブネズミが、アレックスの死を待ちかえています。地道な捜査にもかかわらず、誘拐された女の身元はわかりません。もちろん軟禁場所も、特定できません。アレックスは、会社を辞めたばかりでした。捜索願を出すような、家族や恋人もいません。 交互にあらわれるアレックスの章と警察の章は、さしたる進展のないままページを重ねます。死を意識するようになったアレックス。誘拐され虐殺された妻の像を振り払うちびのカミーユ。捜査の停滞をなじる上層部。アレックスは必死になって、脱出の方法を思い描きます。強靭な精神力です。そして突然、転機がおとずれます。 私をふくめて多くの読者は、先を予想しながらストーリーを追いかけています。ところが『その女アレックス』は、何度も予想とは異なる世界へと読者をいざないます。そして衝撃のラスト。とてつもないミステリーの世界に、私はほんろうされつづけました。「超一級品です」という帯を巻いて、「標茶六三の文庫で読む400+α」の棚に、本書を入れることにしました。そのために1冊を専用棚から外さざるをえませんが。 お薦め。ただし残虐シーンに弱い方は、第3部から先を読んではいけません。(標茶六三:2015.01.07)
2015年01月07日
コメント(0)
-

志賀直哉『暗夜行路』(新潮文庫)
祖父と母との過失の結果、この世に生を享けた謙作は、母の死後、突然目の前にあらわれた祖父に引きとられて成長する。鬱々とした心をもてあまして日を過す謙作は、京都の娘直子を恋し、やがて結婚するが、直子は謙作の留守中にいとこと過ちを犯す。苛酷な運命に直面し、時には自暴自棄に押し流されそうになりながらも、強い意志力で幸福をとらえようとする謙作の姿を描く。(文庫内容案内より)■志賀直哉『暗夜行路』(新潮文庫)◎芥川、夏目に評価されていた 志賀直哉が実質的な処女作「ある朝」(『清兵衛と瓢箪/網走まで』新潮文庫所収)を発表したのは、25歳(明治41年)のときでした。その後『網走まで』(新潮文庫)などを発表し、28歳(明治43年)のときに武者小路実篤(推薦作『友情』新潮文庫)、有島武郎(推薦作『生れ出づる悩み』新潮文庫)らと雑誌「白樺」を創刊しました。それから2年で明治が終わり、大正時代を迎えます。夏目漱石(推薦作『吾輩は猫である』新潮文庫)が死去したのは大正5(1916)年です。 大正時代は、漱石に共鳴していた作家たちが「白樺派」に集い、「第四次新思潮派」とともに文壇の主流をなすようになります。「白樺派」は学習院出身者をを中心とした、お坊ちゃん作家の集まりといわれていました。いっぽう「第四次新思潮派」は、帝国大学出身者が大勢を占め、白樺派の甘い体質に反旗を翻していました。前者の代表的な作家が志賀直哉であり、後者の代表格は芥川龍之介(推薦作『羅生門』新潮文庫)です。2人の関係についてふれた文章を紹介しましょう。――あの頃(補:大正初期)は、世間一般に自然主義系統の作品に嫌厭を感じていたためか、微温的な明るみある「白樺」一派の文学が、文壇に地歩を占めた。ことに、志賀氏は新進作家の仲間に敬畏されていたようであった。広津和郎氏も、会うたびに、私に向かって、志賀直哉讃美の語を放っていた。芥川龍之介は,あれほどの才人でありながら、志賀氏の前へ出ると頭があがらなかったそうだ。(正宗白鳥『新編作家論・高橋英夫編』岩波文庫、P377より) いっぽう志賀直哉は夏目漱石を敬愛していました。――僕が一番好きな作家は、、やはり夏目さんであった。夏目さんは大学で講義を聴いたこともある。向こうからも僕の作品に好意をもっていてくれ、朝日新聞に続き物を出すよう云ってくれたりしたので二度程訪ねた事があり、人間的に敬意を持っていた。(「新潮日本文学8・志賀直哉集」月報の「志賀直哉・書き初めた頃」より) 志賀直哉は、芥川龍之介からも夏目漱石からも一目置かれていました。志賀直哉の文体は、芥川龍之介が修練を重ねた西欧流に近いものでした。それは夏目漱石の流れるような文体とは、まったく異質なものです。そのあたりのところを、吉本隆明(推薦作『日本近代文学の名作』新潮文庫)は著作のなかでつぎのように書いています。――この人(補:志賀直哉)の感性や生活感覚自体が一般の庶民のものとは違うところが、そのまま文体になっている。それが飾り気なしに、素直に表現された作品になっているのではないか。余計な情念や飾りがないと思えるのは、そのためではないだろうか。だから、志賀直哉を「自然な無意識の作家」と呼ぶこともできる。(吉本隆明『日本近代文学の名作』新潮文庫、P182より)◎父親との不和がテーマ『暗夜行路』は、志賀直哉唯一の長編小説です。志賀直哉は短編小説の名手として名高いのですが、長編でもまったく破たんはありません。志賀直哉は父親との不和をテーマにした、私小説「時任謙作」を温めていました。そのあたりのことは、『和解』(新潮文庫)に書かれています。父親との不和が解消し、それまで未完のまま眠っていた「時任謙作」が頭をもたげてきました。その点について、阿川弘之(推薦作『雲の墓標』新潮文庫)はつぎのように書いています。――尾道で独り暮らしをしていたころ、志賀氏は四国へ旅をして屋島の宿で寝つかれぬまま、もしかしたら自分は父の子ではなく祖父の子ではないかしらという想像をした。それは氏と氏の父、氏の祖父の三人の一種複雑な関係から自然に出たものにちがいないが、むろん根の無い単なる空想で、「翌日起きた時には自身それを如何にも馬鹿馬鹿しく感じた」と志賀氏も書いている。(「新潮日本文学8・志賀直哉集」解説:阿川弘之より)『暗夜行路』を自伝的小説とくくる文献もありますが、私は本人が否定していることを信じたいと思います。『暗夜行路』は自伝小説から脱皮し、長編にはじめて挑んだ志賀直哉の記念碑的な作品なのです。 主人公の時任謙作は、父がドイツに留学中に母と祖父との間に生まれました。母を幼いころに亡くした謙作は祖父に引き取られ、愛人のお栄に育てられます。父からの送金もあり、成人した謙作は、気ままな生活をしながら小説を書いていました。 謙作には兄・信行がおり、彼のよき理解者でした。芸妓との遊びにあきた謙作は、幼馴染の愛子と結婚したいと兄・信行に伝えます。しかし断られ、乱れた生活のなかで、謙作はしだいにお栄にひかれてゆきます。 その後自己再生をするため、謙作は尾道で独り暮らしをはじめます。落ち着きをとりもどした謙作は、お栄と結婚したいと兄に告げます。そのとき、彼は自分が父の子ではなく、愛する亡き母と祖父との不義の子であることを知ります。 ショックを受けた謙作は東京にもどり、再び放蕩生活をはじめます。そんななかで、謙作は直子という女性をみそめます。2人は結婚し、直子は男の子を出産します。しかし、幼い命は丹毒のために消えてしまいます。さらに謙作が不在のおりに、直子はいとこと関係を結んでしまうのです。 謙作は心の平穏をとりもどすために、独り山里の寺で暮らしはじめます。謙作が病に伏し、直子が駆けつけてきます。結末についてはふれません。私は日本の近代小説の頂に、『暗夜行路』をすえたいと思います。最後に、志賀直哉らしい大好きな文章を引用しておきます。なんでもない朝をこれほど見事に描いた文章を、私はほかには知りません。――翌朝、軒に雨だれの音を聴きながら眼を覚ました。彼は起きて、自ら雨戸を繰った。戸外は灰色をした深い霧で、前の大きな杉の木が薄墨色にぼんやりと僅にその輪郭を示していた。流れ込む霧が匂った。肌に冷々気持ちがよかった。雨と思ったのは濃い霧が萱屋根を滴となって伝い落ちる音だった。山の上の朝は静かだった。鶏の声が遠く聴えた。庫裏の方ではもう起きているらしかった。彼は楊枝と手拭とを持って戸外へ出た。そして歯を磨きながらその辺を歩いていると、お由が十能におき火を山と盛って庫裏から出てきた。(本文P524より)(山本藤光:2012.10.02初稿、2014.08.13改稿)
2015年01月06日
コメント(0)
-

朝倉かすみ『田村はまだか』(光文社文庫)
深夜のバー。小学校のクラス会三次会。男女五人が、大雪で列車が遅れてクラス会に間に合わなかった同級生「田村」を待つ。各人の脳裏に浮かぶのは、過去に触れ合った印象深き人物たちのこと。それにつけても田村はまだか。来いよ、田村。そしてラストには怒涛の感動が待ち受ける。2009年、第30回吉川英治文学新人賞受賞作。傑作短編「おまえ、井上鏡子だろう」を特別収録。(「BOOK」データベースより)■朝倉かすみ『田村はまだか』(光文社文庫)◎朝倉かすみは中島京子と並走中 若い作家だとばかり思っていました。生年を知って驚きました。どこから若やいだ作品が生まれてくるのでしょうか。『田村はまだか』(光文社文庫)を読んでから、一気に他の文庫本を買いあさりました。朝倉かすみが作家デビューしたのは、40歳を過ぎてからです。朝倉かすみを小説へと突き動かしたのは、結婚という人生のステップでした。30歳の後半、結婚を意識したつきあいをするようになってから、朝倉かすみは「源氏物語」を読みまくっています。与謝野晶子、円地文子、瀬戸内寂聴、橋本治の「源氏物語」に没頭しました。 結婚したのは39歳のときであり。それを機会に創作教室で学びはじめます。つまり結婚という願望が現実となり、もうひとつの夢である「小説家になる」が頭をもたげてきたわけです。 創作教室の先生が「藤堂(とうどう)志津子みたいになれ」といって彼女の背中を押してくれました。藤堂志津子も北海道出身の作家で、直木賞(1989年『熟れてゆく夏』文春文庫)を受賞しています。男女の微妙な心理を描くのに長けた作家です。創作教室の先生が与えた目標は、朝倉かすみの細やかなディテーリング力を評価してのものなのでしょう。『田村はまだか』『ほかに誰かいる』(幻冬舎文庫)『夫婦一年生』(小学館文庫)をつづけて読んで、藤堂志津子というよりも、直木賞作家の中島京子(推薦作『FUTON』講談社文庫)と重なってしまいました。作品の奥行きはおよばないものの、朝倉かすみには中島京子よりも優れた登場人物の造形力がありました。 2人の女流作家をならべてみます。中島京子:1964年生まれ。2003年『FUTON』により野間文芸新人賞。2010年『小さなおうち』(文春文庫)で直木賞。朝倉かすみ:1960年生まれ。2003年『コマドリさんのこと』(『肝、焼ける』講談社文庫所収)で北海道新聞文学賞、2009年『田村はまだか』で(吉川栄治文学新人賞)。 朝倉かすみは中島京子と、ほぼ同様の作家履歴であることがわかります。私は近い将来、朝倉かすみも中島京子と肩をならべることになると信じていますし、すでにそうなりつつあります。ついでに前記の藤堂志津子についてもふれておきます。朝倉かすみとは15年のギャップはあるものの、北海道新聞文学賞受賞とスタートラインは同じです。しかも札幌在住の作家として活躍しています。藤堂志津子:1949年生まれ。1988年『マドンナのごとく』(新風舎文庫、講談社文庫)で北海道新聞文学賞、1989年『熟れてゆく夏』で直木賞。◎田村はこない『田村はまだか』には、特別収録作を含めて6つの連作短編が所収されています。いずれも舞台は、札幌ススキノ場末の小さなスナック「チャオ!」です。主な登場人物は、小学校の同窓会から流れてきた40歳の男女5人とスナックの主人・花輪晴彦46歳です。男女5人の客は、ひたすら同窓会に欠席した同級生の田村を待っています。 5人の客はかなり酔っています。「田村はまだか」とつぶやきながら、懐かしい過去と苛酷な現在を語りつつ飲み続けます。田村久志は悪天候のために、交通が寸断されてなかなかやってきません。時計は午前2時をまわり3時になります。田村はきません。 ものがたりはそれぞれの登場人物を柱に、今と昔がパッチワークのようにつながります。この作品はストーリーにふれない方が賢明でしょう。あなたにはススキノの片隅で、偶然に隣り合わせた客の一人として、ものがたりに参画してもらいたいからです。 待っている5人の時間は、一向に前には進みません。いっぽう待たれている田村は悪天候のなかを、必死にススキノを目指してもがき前進しています。そんな場面はいっさい書かれていませんが、その情景が自然に浮かびあがってきます。不思議な感じの作品なのです。 舞台上にいない田村だけが、クラスメートの集う3次会という場へと匍匐(ほふく)前進しています。もはやアルコール浸けになった男たちの、のど仏は動いていません。女たちもテーブルに突っ伏して眠っていたり、思い出したようにグラスを持ちあげています。マスターはいつものように、客の会話をノートに書きとめています。グラスの氷が、解け落ちる音だけが響いています。 朝倉かすみは平凡な柄と色の端切れを、張り合わせる名人です。未読のかたはどこからでもいいですから、1ページを立ち読みしてもらいたいと思います。単調な素材が張り合わされる華麗な技を、堪能できることでしょう。ただし間違っても、最終ページは開かないでください。松田哲夫らも、最後の大きな感動についてふれています。――昔の思い出話の間に、それぞれの人生が語られていきます。そこに、合いの手のように「田村はまだか」という台詞がはさまれていく。それでも、田村はやってこない。しだいに酔っていくうちに、彼らが、どうして、こんなに田村に会いたがっているのかがわかってきます。そうして、思わぬ異変が起こるのですが、それでも、最後には、気持ちのいい感動が訪れる。(松田哲夫『王様のブランチのブックガイド200』小学館新書P93より)――物語が進むと、田村の輪郭が浮かび上がってくるが、最終話「話は明日にしてくれないか」には、意表をつく結末が待ち受けているので、それは実際に読んで確認して欲しい。(『文蔵』2014.04「小説で味わう北海道」のP20より) 朝倉かすみは、なんでもない世界をみごとなハーモニーにまとめあげました。『ほかに誰かいる』『夫婦一年生』も、同じような傾向の作品です。とりあえずは、『田村はまだか』にふれていただきたいと思います。きっと私が薦めなくても、あなたはつぎの作品も読んでみたくなるでしょう。(山本藤光:2012.12.22初稿、2014.08.19改稿)
2015年01月05日
コメント(0)
-
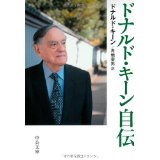
ドナルド・キーン『ドナルド・キーン自伝』(中公文庫)
日本文化を世界に紹介して半世紀。ブルックリンの少年時代、一人の日本兵もいなかったキスカ島、配給制下のケンブリッジ、終生の友・三島由紀夫の自殺…。齢八十五に至るまでの思い出すことのすべて。(「BOOK」データベースより)■ドナルド・キーン『ドナルド・キーン自伝』(中公文庫)◎「The Tale of Genji」との出会いドナルド・キーンは1922年アメリカで生まれました。アメリカの日本文学研究の第一人者で、2012年日本国籍を取得しています。同年に新潮社から『ドナルド・キーン著作集』(全15巻)が刊行され、現在11巻まで配本になっています。『ドナルド・キーン自伝』は「自叙伝・決定版」として、第10巻に所収されています。今回紹介させていただくのは、『ドナルド・キーン自伝』(中公文庫)です。「決定版」が出たので旧版となってしましましたが、すばらしい著作です。 キーンは日本の作家との親交も深く、三島由紀夫、安部公房、谷崎潤一郎、川端康成、吉田健一、石川淳、司馬遼太郎、丸谷才一、篠田一士、瀬戸内寂聴などとの対談も数多くあります。『KADOKAWA道の手帖・ドナルド・キーン』(河出書房新社)のなかに、「キーンの寸鉄人物評」というコラムがあります。キーンのユニークなコメントを、いくつか紹介させていただきます。安部公房(補:安倍と誤植されています):日本が生んだ最高の作家の一人です。作品が素晴らしいだけではなく、一人の人間としても立派でした。素直に自分の意見をいう男性的な魅力がありました。また、自分の見解に間違いがあると認めたときは、素直にそれを認める誠実な一面がありました。三島由紀夫:真の友と言える人でした。一度として喧嘩や不和はありませんでした。共に過ごす時は最高に楽しい会話に満ちていました。彼の自決を大変残念に思います。私は作家と緊張関係に陥ることはほとんどありませんが、三島さんはいろいろな人との摩擦や問題を抱えていました。キーンはコロンビア大学時代(1940年)に、アーサー・ウェイリー訳『源氏物語』に出会い、心を奪われました。訳者アーサー・ウェイリーと著者・紫式部についても「キーンの寸鉄」を紹介します。アーサー・ウェイリー:私の偶像でした。彼の手による英訳の『源氏物語』を読んだのが、私の人生の始まりです。何とか〈第二のアーサー・ウェイリー〉になりたいと青年の私は思っていました。ただ、残念なことに、彼は中国語が嫌いでした。紫式部:会ったことありませんが、よく知っている人です(笑)。彼女に日記がなくても、大傑作の『源氏物語』を読むと、どんな作家で、どんな人間であったかがわかります。必ずしも優しい人ではなかったかも知れません。しかし、優れた才能に恵まれた、明晰な人だったでしょう。『源氏物語』には数多くの人物が登場し、その一人一人が個性に溢れています。他の文学、ロシア文学などでは、それも普通ですが、日本の文学には大変珍しいことです。『ドナルド・キーン自伝』(中公文庫)には、少年時代から84歳になるまでの、日本や日本人、日本文学とのかかわりについてくわしく書かれています。『源氏物語』との出会いについて引いておきます。キーンはその時期のことを「私の中で戦争に対する憎しみと、ナチに対する憎しみが衝突していた最悪の時期」(本文P50)と書いています。――ある日、The Tale of Genji(『源氏物語』)という題の本が山積みされているのを見た。こういう作品があるということを私はまったく知らなくて、好奇心から一冊を手にとって読みはじめた。挿絵から、この作品が日本に関するものであるに違いないと思った。(本文P50より) 偶然に手にした『源氏物語』に、キーンは心を奪われてしまいます。それまでキーンが日本にたいして抱いていた印象はつぎのとおりです、――私はそれまで、日本が脅威的な軍事国家だとばかり思っていた。広重に魅せられたことはあっても、日本は私にとって美の国ではなくて中国の侵略者だった。(本文P51より) そんな時期にキーンは、友人から日本語を勉強しようと誘われます。それまでキーンは、日本語を勉強しようとは思っていません。『源氏物語』との出会いと同様に、日本語を学びはじめたのも偶発的なものだったのです。その後キーンは海軍の日本語学校で、本格的に日本語を学びます。そして戦場通訳あるいは、日本人の遺留品の解読などの任にあたります。戦地についてふれている文章を、紹介させていただきます。――かなりの数の日本兵がレイテ島で投降した。彼らは、ハワイで知っている捕虜たちよりも暗い感じがした。たぶん、生きて捕虜になった自分をまだ許していなかったからだと思う。あるいはその中にミンドロ島で捕虜となり、レイテ島での収容所体験を忘れ難い文章で書いた大岡昇平がいたかもしれない。(本文P83より) 大岡昇平についての「キーンの寸鉄」もおもしろいので、紹介させていただきます。大岡昇平:初めは大嫌いでした(笑)。それは文学の問題ではなくて、私への言葉づかいが丁寧すぎて、馬鹿にされていると思ったからです。それ以降のキーンについて、簡単にまとめておきます。1945年に沖縄へきています。日本人捕虜の通訳のためです。戦後はハーヴァード大学で日本語を学びます。そしてつぎのケンブリッジ大学で、源氏物語の翻訳者・アーサー・ウィリーと出会います。1953年京都大学大学院に留学します。◎キーンの恋愛小説見つかる「朝日新聞DIGITAL」(2014年6月26日)に、びっくりするニュースが掲載されていました。ドナルド・キーンが若いころに書いた「恋愛小説」が発見されたのです。以下その記事を引用します。――日本文学者のドナルド・キーンさん(92)が、57年前に恋愛小説を執筆していたことを、「ドナルド・キーン著作集 第10巻 自叙伝・決定版」(新潮社)で明かしている。当時は作品の出来に納得がゆかずお蔵入りに。その後本人も忘れていたという。/執筆は1957年、英文で80枚ほどの短編で……(後略) つづいて『ドナルド・キーン著作集』(第10巻「ドナルド・キン自叙伝・決定版」から、キーン自身の新たな追加文章を引用させてもらいます。――その快適な環境(補:1957年夏休み、富豪の別荘地)の中で、私は小説を書くことに専念した。そして、かなりのスピードで一作品を書き上げた。題は付けていない。あるアメリカ人女性が、失恋し、旅先のフランスで景色のいいところから身を投げようと、南仏へ就く。そこには、同じ目的でやってきた一人の男――日本人がいた。二人は出逢い、ともに自殺を思いとどまり、彼女も日本へ……といった筋の純文学だった。(『ドナルド・キーン著作集』(第10巻「ドナルド・キン自叙伝・決定版」P212より)知人の編集者に小説を見せると、「いい」との評価がされました。しかしキーンは発表しませんでした。これは東日本大震災を機に、日本国籍を取得して、日本に移住準備中の2011年夏に発見されました。養子となった誠己さん(64)が、ニューヨーク市の自宅を整理していて見つけたものです。この小説は著作集第15巻に収録する予定とのことで、いまから楽しみにしています。◎日本人捕虜との再会 キーンが恋愛小説を書いたのは、1957年に開催された国際ペンクラブ東京大会の直前です。キーンは大会の代表として来日しています、このときいっしょに来日したなかには、ジョン・スタインベッグ、ラルフ・エリソンなどがいました。キーンの自伝には「一番無名の代表の一人だったにもかかわらず、私が日本の新聞記者に人気があったのは日本語が話せたからである。」と書かれています。そしてキーンが尋問をした、捕虜とも会場で出会うのです。。――私は記者の一人を知っていて、それは高橋潭、昔の捕虜だった。高橋は、グアムで同盟通信の記者をしていて餓死寸前のところを捕虜となった。私はハワイで彼を尋問し、その後、何度か日本でも会っていた。(本文P197より)『ドナルド・キーン自伝』には、たくさんの日本文学者が登場します。安部公房と大江健三郎の確執や、三島由紀夫の自殺など、未知のエピソードがたくさんありました。キーンは「あとがき」のなかで、書ききれなかった人たちにたいする謝罪をしています。このあたりの細やかな心配りは、日本人ドナルド・キーンらしい一面です。『ドナルド・キーン自伝』ではふれられていない、キーンの文章ともよく遭遇します。最近ではつぎの一文を、キーンが書いていたことに驚きました。一読のときには気にもとめていなかったのでしょう。――『近代能楽集』にはいろいろのテーマが展開するが、すべての曲に一貫しているのは三島氏の古典文学に対する尊敬と挑戦である。これによって彼は能を現代化することに成功したに止らず、新しく、すばらしい二十世紀の文学を拵えた。(三島由紀夫『近代能楽集』新潮文庫、ドナルド・キーン「解説」より)坪内祐三『ストリート・ワイズ』(講談社文庫)を読んでいたら、キーンのことがでてきました。キーンが書く日本語の文章について、たいへん興味深い内容です。とにかくキーンの日本文は、日本人の作家レベルに近いようです。『ドナルド・キーン自伝』のなかで、おもしろいエピソードが紹介されています。――日本での生活に一つ不満があるとしたら、それは私の本を読んだことのある人も含めて多くの日本人が、私が日本語を読めるはずがないと思っていることである。(中略)東大の某教授などは、私が書いた『日本文学の歴史』を話題にして、「あなたが文学史で取り上げた作品は、翻訳で読んだのでしょうね」と言ったものである。(本文P346より) 日本人ドナルド・キーンは、日本人以上に古典から文学史まで精通しています。『ドナルド・キーン自伝』は、日本のことすら知らなかった外国人が、ひょんなきっかけから日本や日本人、日本文学の世界へ入りこむ長いドラマです。私の知るなかでは、超1級の自伝であると結ばせていただきます。(山本藤光:2015.01.02)
2015年01月04日
コメント(0)
-
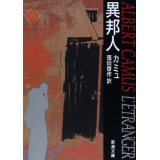
カミュ『異邦人』(新潮文庫・窪田啓作訳)
母の死の翌日海水浴に行き、女と関係を結び、映画をみて笑いころげ、友人の女出入りに関係して人を殺害し、動機について「太陽のせい」と答える。判決は死刑であったが、自分は幸福であると確信し、処刑の日に大勢の見物人が憎悪の叫びをあげて迎えてくれることだけを望む。通常の論理的な一貫性が失われている男ムルソーを主人公に、理性や人間性の不合理を追求したカミュの代表作。(「BOOK」データベースより)■カミュ『異邦人』(新潮文庫・窪田啓作訳)◎不条理という哲学 カミュの作品を読むとき、「不条理」について理解しておかなければなりません。解説を引用させていただきます。――実存的な用語で、人生に意義を見出す望みがないことをいい、絶望的な状況、限界状況を指す。特にフランスの作家カミュの不条理の哲学によって知られる。(「広辞苑」第五版) カミュは文学辞典だけではなく、「広辞苑」にまで掲載されています。それゆえ小難しい作家だなどと食わず嫌いをせずに、肩の力を抜いて読んでいただきたいと思います。私は向こう見ずにも、「広辞苑」に異議ありと主張させてもらいます。 『異邦人』の主人公・ムルソーは、けっして人生に絶望していません。限界状態でもありません。ヤボな芸人のように、「そんなの関係ない」と思っているだけなのです。養老院から母の死亡を知らせる電報を受け取ります。ムルソーは勤め先の主人に、休暇を申し込みます。不満そうな主人にムルソーは、「私のせいではないのです」といいます。『異邦人』の冒頭の一文は、あまりにも有名です。「きょう、ママンが死んだ」。なぜか私は、「きのう」だとばかり思っていました。それは冒頭の一句を、あまり重視せずに読んでいたことによるものです。この一文のあとに続く「もしかすると、昨日かもしれないが、私にはわからない」の叙述に、まぎらわされてしまっていたのでしょう。 ムルソーにとって母の死は、今日でも昨日でも、どうでもいいことなのです。バスに揺られて養老院に着いたムルソーは、母の顔を見ようともしません。涙を流すこともありません。平気で煙草を吸い続けています。しかも葬式から戻り、喜劇映画を見て、女と情交までしているのです。 著者カミュは、これでもかといわんばかりに、ムルソーを非人間的に描き抜きます。多くの読者は腹立たしく思いながら、ムルソーの無軌道ぶりに唖然とすることになります。 そして第1部の結末を迎えます。ムルソーは友人の海辺の別荘に行き、アラビア人とケンカとなります。ムルソーは友人から預かった拳銃で、5発の銃弾を撃ち放ちます。◎なぜ「無関係思想」が生まれたのか 呼称はどうでもいいのですが、私はムルソーを「無関係思想者」と表現したいと思います。ずっと「不条理」という哲学に呪縛されてきましたが、再読してみてひらめいたのです。 電車のなかで、若い女性が化粧をしていました。平気で携帯で会話をしている若者がいました。これらの場面には何度も遭遇しています。そのつど私は「非常識なやつだ」と心のなかで吐き捨てています。ところが当人は、いたって平気なのです。車内の冷たい視線は、まったく意に介していません。 殺人のたとえとして化粧では、あまりにも迫力不足かもしれません。化粧女は明らかに、批判的な視線は意識しているはずです。でも「そんなの関係ない」のです。時間がないから電車のなかで化粧をする。その行為に、常識などという論理が入り込む余地はありません。 ムルソーの葬式前後の行為も殺人も、世間の常識などとは無関係なのです。殺人の理由を明快に答えられないために、ムルソーは単に太陽を持ち出したに過ぎません。ではなぜ、カミュはムルソーなる主人公を描いたのでしょうか。それはカミュ自身の生い立ちが影響しています。このあたりは、専門家のいうとおりだと思います。 カミュはフランス領アルジェリアで生まれました。第1次世界大戦で父を失い、カミュは貧困生活を余儀なくされました。私は作品と作者の生い立ちを、極端な形で結びつけて書かないようにしています。これは意図的なことなのですが、結婚興信所みたいな展開を好まないからです。 しかしカミュだけは別です。カミュが生まれたとき、アルジェリアはフランスの植民地でした。亡くなった父はフランス系であり、母はスペイン系でした。つまりカミュは、フランスというよりどころを失った状態で育っています。 カミュは、地中海のきらめく光景を好みました。なにかに「私の怨恨のすべてを漂白してくれた」と書いているほどです。カミュの履歴に関しては、詳細はあえて書きません。『異邦人』(新潮文庫)には、白井浩司の懇切丁寧な解説が掲載されています。それを読んでもらいたいと思います。◎自由になるということ 私の「無関係思想」は、どうでもいいことです。単なる思いつきで、薄っぺらなものです。だからもう少し本家の「不条理」について学んでおきたいと思います。愛用している辞典から引用してみます。――不条理:人間が存在の根元から切り離されて、自分とも、周りの環境とも意味のある関係を結ぶことができずに、阻害状況にあるという意味。フランスの作家アルベール・カミュの『シシュポスの神話』に盛られた哲学である。(後略)(『最新文学批評用語辞典』研究社出版) この辞典には「不条理」を作品に実践したのは、T.ビンチョン(推薦作『スローラーナー』ちくま文庫)、K.ヴォネガット(推薦作『タイタンの妖女』ハヤカワ文庫SF)などと書かれています。また、S.ピンター、S.ベケットなどの作品も「不条理」と向き合ったものだと書かれています。 人は阻害状況にあるか否かと問われたら、だれもが「はい」と答えるのではないでしょうか。もしも「いいえ」なる人がいたら、よほどノー天気だと思います。問題は阻害状況を脱出または克服する意思があるか否かだと思うのです。 サルトルのいう、「自由であるということは、なにごとも自分で決め、選び、自分についての全責任を一身に背負うということだ」(白鳥春彦監修『哲学は図でよくわかる』青春出版社新書)に注目したいと思います。 虐げられている。阻害されている。そう感じたら、脱出や克服などは考えられません。これらの対象物である組織や人などは、完全に無視してしまうのが関の山です。そこに「自由」が生まれます。つまり「不条理」なる人は、闘わないのです。自由」を手に入れるということは、組織や他人の存在を消し去ることなのです。『異邦人』の第2部は、裁判の場面が延々と続きます。第1部のできごとが、くりかえし陳述されます。ムルソーの葬儀前後について、必要に問い詰められます。「なぜアラビア人を殺したのか。動機はなんだ」「なぜ5発も打ち込んだのか」。執拗な問いかけに、ムルソーは「太陽のせいだ」と答えます。 この答弁が簡単な事件を、複雑なものに変えてしまいます。神を冒涜している。人間性のカケラもない。検事側の態度が、しだいに頑ななものになってゆきます。ムルソーは、いかなる対応をするのでしょうか。第2部はあなたも化粧女となって、読んでみてもらいたいと思います。(山本藤光:2009.08.11初稿、2014.09.04改稿)
2015年01月03日
コメント(0)
-
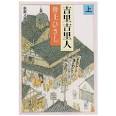
井上ひさし『吉里吉里人』(上中下巻、新潮文庫)
ある六月上旬の早朝、上野発青森行急行「十和田3号」を一ノ関近くの赤壁で緊急停車させた男たちがいた。「あんだ旅券ば持って居だが」。実にこの日午前六時、東北の一寒村吉里吉里国は突如日本からの分離独立を宣言したのだった。政治に、経済に、農業に医学に言語に……大国日本のかかえる問題を鮮やかに撃つおかしくも感動的な新国家。日本SF大賞、読売文学賞受賞作。(文庫案内より)■井上ひさし『吉里吉里人』(上中下巻、新潮文庫)◎『吉里吉里人』は井上ひさしの集大成 井上ひさし死去の訃報にふれ、大きな衝撃をおぼえました。井上ひさしの幅広い活躍は、だれもが知っています。私は「文章の手ほどき」に関する多くの著作から、学ばせていただきました。『私家版日本語文法』(新潮文庫)、『自家製文章読本』(新潮文庫)、『ニホン語日記1・2』(文春文庫)、『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室』(新潮文庫)などには、特にお世話になりました。 井上ひさしの代表作を1つ選ぶなら、ちゅうちょすることなしに『吉里吉里人』(上中下巻、新潮文庫)をあげます。この作品は日本国、日本語などを諷刺した、現代文学を代表するSFユートピア小説です。『吉里吉里人』の発表で井上ひさしは、小説デビュー作『ブンとフン』(新潮文庫)から約10年で、文壇に確固たる地位を築いたことになります。 『吉里吉里人』は『ひょっこりひょうたん島』(全13巻、ちくま文庫)で高い評価を受けた井上ひさしの、2度目の開花でもありました。戯曲、エッセイ、文章論、そして小説。しかし井上ひさしの原点は、「戯作者」であることでした。『吉里吉里人』は、幅広い活動の集大成ともいえる作品といえます。 今回読み返してみましたが、現代社会や風俗から違和感を覚える部分もあります。ただ作品の崇高さはまったく色あせていませんでした。福田和也は『作家の値打ち』(飛鳥新社)で、『吉里吉里人』をこう切り捨てています。――東北小村の独立譚。標準語にたいするプロテキストでもある。さまざまなエピソードが、「どうです、おかしいでしょう」とばかりに展開するが、ただただ痛ましいばかりである。同じ独立問題を扱った作品として、面白さでも批評性でも、獅子文六の『てんやわんや』の足元にも及ばない。(本文P28より) がちがち頭の批評家・福田和也は、28点しかつけませんでした。お受験で横道をそれることは悪、という性癖がしみついているからでしょう。『吉里吉里人』は多くの若者に受けいれられました。お受験でテレビを封印されていた人たち以外は、「ひょっこりひょうたん島」を見て育っているのです。◎物語は快調に滑り出す 舞台は東北の、人口4187人の村落です。日本国のでたらめな中央集権体制に反発して、独立宣言をしてしまいます。農業は近代化しなければなりません。誤った政策のなかに埋没することを恐れて、吉里吉里村は過激な選択をしたのです。 急行十和田3号には、売れない小説家・古橋健二が乗車していました。雑誌「旅と歴史」の取材のためです。下車した古橋は不法入国のかどで、収容所に連行されてしまいます。『吉里吉里人』は、この古橋健二が「記録係(わたし)」となって語られています。 ――ある六月上旬の早朝五時四十一分、十二両編成の急行列車が仙台駅のひとつ上野寄りの長町駅から北へ向かって、糠雨のなかをゆっくりと動きはじめた。/というところから事件の記録をはじめることにしよう。(『吉里吉里人』上巻P11-12より) その後、十和田3号の乗客の様子などの描写が延々とつづきます。物語は快調に滑り出すかに思われました。 ――じつはグリーン車に男装した女とも、女装した男とも見分けのつかない正体不明の五人組がいて、彼らの、あるいは彼女たちの性別が判然としないのだ。記録係(わたし)には厳正に、また忠実にこの事件を記録する義務があるが、しかし、彼らの、あるいは彼女たちのはいているパンタロンを引っ剥(ぱ)いで性器を確かめるのはやはりやりすぎだろう。それにちかごろではたとえ性器を見極めたからといって油断はできない。なにしろ性器を改造してまで自分の性を曖昧にしておこうとする有耶無耶(うやむや)趣味の持ち主がすくなくないからである。(『吉里吉里人』上巻P12-13より) 物語はなかなか前へ進みません。言葉遊びの天才は、十和田3号の乗客(「男が四百三十九名、女が三百六十四名」)と書いてから、前記5名の扱いに悩んでみせたりします。とにかく、400字詰め原稿用紙で2500枚の長編ユートピアSF小説です。読者は笑いながら、つきあうほかはありません。◎日本文壇の最高傑作である 吉里吉里国が目指すのは、農業立国・医学立国・好色立国です。最終的には、国際的に独立国としての承認を得たいと考えています。「憲法」が制定され、「イエン」という金貨も流通させます。記録係(わたし)は、そのなかで八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍をします。しかし口が軽いことが災いし、彼のやることはことごとく失敗に終わります。 本書には無数の固有名詞や商標が登場します。世界中の国々をも俎上にのせ、陳腐な日本語も氾濫します。井上ひさしはみちのくの風土に江戸文学を重ね、まるで「いも煮会」会場のごとく、紙面を賑わわせます。 本書は吉里吉里国独立から崩壊までの、たった2日間を臨場感あふれる誇張で、記録係(わたし)が語りまくるものです。全編、洒落、諷刺、言葉遊び、誇張、比喩、擬声語、擬態語に満ち満ちた本書は、井上ひさしでなければ書けないものです。 たび重なる転校で、方言をばかにされた少年時代。ストリップ劇場で、笑わせることだけに集中した文芸員時代。連続ドラマ「ひょっこりひょうたん島」でのこどもに向けた目線。てんぷくトリオの台本を書いていたときの、笑いへの間(ま)のとりかた。江戸文学に没頭した経験。それらの知的財産が、一挙に花開いた作品こそ『吉里吉里人』なのです。 ――井上ひさしは、たとえば『ブンとフン』(補:新潮文庫)のような誇張、『青葉繁れる』(補:文春文庫)のようなからかい、『ドン松五郎の生活』(補:新潮文庫)のような諷刺、といったさまざまな笑いの文章体を苦心してつくりだしている。(「国文学・現代作家110人の文体」1978年11月臨時増刊号より) 本書は日本文壇において、稀有(けう)な名作です。だれもマネができません。方言にルビが振られ、糞尿描写もたくさんあります。これほど翻訳に不適当な作品は珍しいでしょう。最後に海外文学との比較で、『吉里吉里人』を論じている一文を紹介します。 ――井上ひさしは主人公・古橋健二をあたうかぎり演戯的人間に仕立てているが、彼の運命の急激な転変、その性格の「知的退廃(いいかげんなところ)」、その猥褻なところ、軽佻浮薄なところ、言語遊戯(地口、駄洒落、ギャグ、語呂あわせ)に淫するところ、等々において、ジョイス『ユリシーズ』(補:全4巻、集英社文庫)、とりわけ夜のダブリンを徘徊するレオボルド・ブルームをほうふつとさせる。(曽根博義『現代小説を狩る』中教出版1986年。赤祖父哲二、森常治の共同編著より) 私は『吉里吉里人』を高い評価で、「標茶六三の400+α」の1冊に加えました。読書って楽しいものです。教養のために読むわけではありません。井上ひさしのガハハハが聞こえています。(山本藤光:2012.01.27初稿、2014.08.05改稿)
2015年01月02日
コメント(0)
-

中島京子『FUTON』(講談社文庫)
日系の学生エミを追いかけて、東京で行われた学会に出席した花袋研究家のテイブ・マッコーリー。エミの祖父の店「ラブウェイ・鶉町店」で待ち伏せするうちに、曾祖父のウメキチを介護する画家のイズミと知り合う。彼女はウメキチの体験を絵にできるのか。近代日本の百年を凝縮した、ユーモア溢れる長編小説。(「BOOK」データベースより)■中島京子『FUTON』(講談社文庫)◎本歌取りの最高峰 中島京子のデビュ作『FUTON』(講談社文庫)を読んで、才気あふれる新鋭の登場を確信しました。その後、『イトウの恋』と『均ちゃんの失踪』(ともに講談社文庫)を読んで、中島京子の追っかけをはじめました。 中島京子が直木賞を受賞(『小さいおうち』文春文庫)したのを知ったとき、意外に思ったのは私だけではないと思います。中島作品には、大きな事件は起きません。小さな日常をたくみに積み上げて、独特のうねりを生む作風なのです。つまり従来の直木賞作家とは違って、読者にわくわく感を与えるものではありません。 それゆえ地味な作品かというと、そうではありません。新しいのです。人物造形が巧みですし、筆運びが軽妙です。しかも中島京子は「再現」の名人かもしれません。直木賞受賞作『小さいおうち』でもみせたように、古きよき時代をみごとに再現してみせる力量は並はずれています。 『FUTON』はタイトルどおり、田山花袋『蒲団』の再現を試みた作品です。文庫解説の斎藤美奈子がこの作品を、「本歌取り」と書いています。もともとは和歌などで用いられた言葉ですが、最近の小説界でも目立ちはじめました。古くは芥川龍之介の一連の作品や中島敦の作品などは「本歌取り」の代表格です。 最近では、水村美苗『続明暗』(新潮文庫)、奥泉光『「吾輩は猫である」殺人事件』(新潮文庫)などのほかに、小谷野敦が二葉亭四迷の「浮雲」に迫った『もてない男訳・浮雲』(河出書房新社)、森見登美彦『新釈・走れメロス』(祥伝社文庫)などが目立ちます。 これらの作品のなかで、私は中島京子『FUTON』を、本歌取り小説の最高峰と位置づけたいと思います。 ◎蒲団に顔を寄せる場面 主人公のデイブは、アメリカの大学の日本語学科教授です。田山花袋の『蒲団』を翻訳しています。翻訳文は「蒲団の打ち直し」というタイトルで、原作と近い展開になっています。 『FUTON』では、田山花袋『蒲団』の視座を、夫である竹中時雄から妻の美穂(田山花袋『蒲団』の妻には、名前があったでしょうか。私の記憶ではいつも「細君」と表現されていました)に入れ替えられています。「蒲団の打ち直し」は、本文にはさみこまれるように、いくつもに分けて展開されます。 『FUTON』では有名な最後の場面など、思わず笑い転げてしまうほどのできばえでした。たとえば弟子の芳子の蒲団に、竹中時雄が顔を埋める場面は、こうなっています。――木枯らしが去り、冬晴れの青い空に風もない朝。竹製の蒲団叩きを一寸の間地面に置いて、美穂はその天鵞絨(ビロード)の襟をつけた掛け蒲団に、そっと顔を寄せた。(『FUTON』P345より) 参考までに、田山花袋『蒲団』の場面を再現してみましょう。竹中時雄が押入れから、芳子が使っていた蒲団を引き出す場面です。――大きな柳行李が三箇細引で送るばかりに絡げてあって、その向こうに、芳子が常に用いた蒲団――萌黄唐草の敷蒲団と、綿の厚く入った同じ模様の夜着とが重ねられてあった。時雄はそれを引き出した。女のなつかしい油の匂いと汗のにおいとが言いも知らず時雄の胸をときめかした。夜着の襟の天鵞絨(ビロード)の際立って汚れているのに顔を押付けて、心のゆくばかり懐かしい女の匂いを嗅いだ。(田山花袋『蒲団』新潮文庫P110より) 明治時代の、古きよき女性の象徴である「細君」。田山花袋の小説では、ハイカラな若き女性・芳子に恋する、くたびれた中年男性・竹中時雄にフォーカスがあたっています。中島京子は、「細君」と片づけられていた存在感の希薄な女性に、美穂という現代的な名前をあたえました。脇役を主役に抜擢し、新たな物語をつむぎだしたのです。 ◎二重構造をもった「ふとん」ものがたり 『FUTON』の主人公・デイブは、日本人留学生・エミに恋をし同棲をはじめます。デイブは離婚しており、ティムという息子がいます。エミには日本に100歳になろうとしている曾祖父・ウメキチがいます。祖父はタツゾウといって、鶉町でサンドイッチ屋を経営しています。 ある日エミは、同じ日本人留学生・ミュージシャン志望のユウキという軽薄な男に誘われて、日本へと旅立ちます。デイブは学会を理由に、エミを追いかけて日本に向かいます。――デイブは飛行機の上で、己の一年間について思いを巡らせていた。離婚、エミとのアフェア、花袋に関する論文のこと、ティムのこと。日本で出会った奇妙な女たちのこと。(本文P365より) うだつのあがらない文学者・竹中時雄は、若いハイカラな弟子・芳子に惚れます。芳子は京都の田中という男と恋をします。これが田山花袋『蒲団』の構図です。 中島京子『FUTON』も、現代版にアレンジされて同じ構図をとっています。デイブはエミに惚れます。エミはユウキという男と連れ立って日本へ行ってしまいます。 つまり『FUTON』は、二重構造をもった「ふとん」ものがたりなのです。ただし中島京子は、さらにもうひとつのものがたりまで挿入しています。 100歳になろうとしている曾祖父・ウメキチの存在です。ウメキチは画家志望のイズミという女性に介護されています。ウメキチはイズミに、戦時中に知り合ったツタ子の話をします。うそなのかまことなのかは定かではありません。もうろくしているウメキチの心を、一人の女性が支配しているという構図は、さらに現実のものがたりに厚みを加えています。 さらに『FUTON』のおもしろいところは、永井荷風の『蒲団』をこきおろすこんな台詞にあらわれます。――あの、変態の先生が、弟子の寝ていたフトンに顔を埋めて泣く話でしょう。(本文P367より)『FUTON』は、一級品の小説です。先にもふれましたが、大きな事件は起きません。小さな日常の積み上げが、中島京子の魅力なのですから、じっくりとそれを堪能していただきたいと思います。(山本藤光:2010.08.18初稿、2014.08.26改稿)
2015年01月01日
コメント(0)
全29件 (29件中 1-29件目)
1










