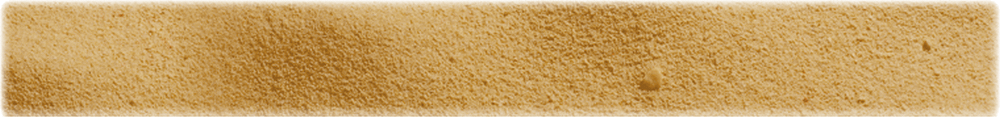全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
謹賀新年。
明けましておめでとうございます。同じタイトルでブログを書いたのが1年前。。。1年経ってしまったのですねぇ。さて、昨年1年間で、どれだけ自分が成長できたかはさておき、年賀状を書くために、頂いた名刺などを整理してみたりしていたのですが、驚くほど多くの方々、特に近隣地域ではない、全国各地の方々にお会いしていたことが分かりました。中には、「あれ?昨年初めて会ったんだっけ?」と思うほど、仲良くさせて頂いている方もいます。人脈の大切さをリアルに感じた1年間でした。あと「類は友を呼ぶ」という言葉も。。。皆様、本年もよろしくお願いいたします。そして、今年お会いする方々??どうぞよろしくお願いいたします。
2009.01.01
-
謹賀新年。
みなさま、あけましておめでとうございます。半年以上放置状態のブログですが、本日久しぶりに管理記録を見たところ、多くの方のアクセスがあったことを知りました。こんな状態で申し訳ありません。。。今年もこんな状態になるかもしれません。。。ブログの更新を除いて、昨年は、まずまずの「ぐっばる」な年だったと思います。萎まず・・張りつめず・・ただ、風船自体がまだまだ小さいため、「かわいい風船ちゃんね~」状態でしたので、今年はもう少し大きな風船になることを目標にします。萎まず・・張りつめず・・そんなことを繰り返して行くうちに、いわゆる「器が大きい」人間になれるのでしょうね。。。(なれのるかなぁ・・)さて、本日は新年早々、会社の設立登記をオンラインで申請しました。本年1月1日より、新たな租税特別措置法が施行となり、オンラインで申請する場合に限って、会社設立の登記の登録免許税額が¥5,000―安くなりました。1月1日から新法施行と言っても、法務局が受付をしてくれるのは本日からですので、本日が減税措置実施の初日ということになります。過去何度か登記申請オンラインシステムがパンクしていますので、今日も申請が殺到して繋がらなかったらどうしよう・・と思っていたのですが、スイスイ申請が完了してしまいました。よかった・・。ちなみに管轄法務局の商業登記の本年第1号の申請でした。なんだかとっても勝利者気分!どっかの神社?の一斉にダーッと競争して走る「福男」の勝者になったような気分です。昔は「2」という数字が好きで、ゴレンジャーでも青レンジャーが好きだったのですが、最近は「1」という数字の方が好きになりました。でも1番目の「1」よりも、オンリーワンの「1」がいいですねぇ。オンリーワンの司法書士目指して精進したいと思います。
2008.01.04
-
コンプライアンス専門家に求められるもの。
「ビジネス法務の部屋」のエントリーとそれに対するコメントがありまして、改めてコンプライアンス経営の難しさを感じると共に、いかに現場が混乱しているかを伺い知ることができます。そもそも、コンプライアンス経営とは、様々な要素が複雑に絡み合っているものですから、一概に「こうだ!」とは言えないのですが、現場が混乱を起こす要因には次のようなことが挙げられると思います。(1)コンプライアンスの定義が使う人によってバラバラこれは以前から指摘されていたことですが、J-SOXの話題がではじめてから、ますます統一感がなくなった気がします。私の勝手な意見ですが、コンプライアンスは、「法令遵守」とされますが、その「法令」の部分は、文字通り「法令」というものと、法の上にまたひとつ「法」という一つの文字が重なって乗っていて、その「法」というものは、人間として「どう生きるか」「どう働くか」といった、自問自答を繰り返し、「こうすべきだ」と決めたことを守り抜くというものであり、その姿勢を経営に生かすのが、コンプライアンス経営ではないかと思っています。(2)コンプライアンス経営と内部統制システム構築の混同内部統制の「統制環境」の中に、コンプライアンス経営が含まれますので、ややこしいかもしれませんが、内部統制をシステム化していない会社でも、コンプライアンス経営は必要です。(当然ですよね・・。)ところが、内部統制対応やJ-SOX対応のために、コンプライアンス経営をしなければいけないと理解している方も多いようで、このことが、「コンプライアンス経営=面倒なマニュアルや手順の作成」という、間違った図式で捉えられてしまっているような気がします。確かにそういった作業が必要な場合もあるとは思いますが、それを行う理由が理解されていないので、誤解を招いているのではないでしょうか。(3)推進する側と実行する側の視点の違い経営トップや役員と、現場のマネジャーや社員の議論が噛み合わないときは、この場合がほとんどではないでしょうか?根本的な違いは、視点の違いです。経営トップや役員等は、管理する側の視点、現場のマネジャーや社員は統制される側の視点です。同じ絵」を見ながら意見や感想を述べあっているつもりでも、見る方向によって、見え方が違ってきますから、お互いの言っていることが理解できないのだと思います。こうして見ると、コンプライアンスの専門家に求められるものは、1、「コンプライアンス」という名称に左右されない、 企業の持続的存続と発展をサポートできる能力と方法を持ち合わせていること。2、上記(3)の「絵」を、 双方に同じように絵が見える状態にしてあげることができること。ではないかと思ったりしています。もっとも、私は中小企業のコンプライアンス経営を念頭に色々と考えていますから、大企業のコンプライアンス経営について議論をするなら、また違った要素が加わってくると思いますけどね・・。
2007.05.18
-
審査終了!
学生ビジネスアイデアコンテストの最終審査会が終わりました。企業ソリューション部門の一次審査合格者6名(組)、フリーテーマ部門の一次審査合格者5名(組)に、2日間に渡ってプレゼンテーションをしてもらい、各部門の最優秀賞、優秀賞各2名(組)を選出いたしました。審査員一同の感想は、皆さんしっかりとした考えをお持ちで優秀!そして皆さんプレゼンが上手!おかげで審査が難航しましたよ。また、両部門とも面白い現象が起こりまして、一次の書類審査でギリギリ選考に残った方が優秀賞に選ばれました。書面だけで表現するのは難しいし、また書面だけで判断するのも難しいです。ただ、こういったビジネスコンテスト等は、まずは書類審査で審査対象の絞り込みをしなければなりませんので、いかに書面だけで自分の考えを伝えられるかがポイントになりますよね。コツは、誰が読んでも分かるようにすることです。専門用語ばかりだったり、あまり深くまで話が展開してしまうと、せっかくのアイデアが一体なんなのか分からなくなり、審査員の印象に残らなくなってしまいます。ともあれ受賞された皆さん、おめでとうございます!11月25日開催の湘南ビジネスコンテストの中で、受賞者の発表もあるそうですから、お時間のある方は是非とも会場に足をお運びください。組織再編の案件が進行中です。組織再編関係は、企業会計基準や会計処理等と深く関わる部分が多いので、公認会計士の先生や税理士の先生との連携なしには進められません。いい例が計算規則第81条第1項。新設分割の際の株主資本等の定め方が規定されている条文です。「分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式である場合には、 新設分割設立会社の次に掲げる額は、適当に定めることができる。 ただし、適当に定めることが適切でない場合は、この限りでない。」続いて同じ項に、設立時資本金額等が各号毎に列挙されているのですが、何度読んでも狐につままれた気分になる条文です。勢いで、ほんとうにテキトーに決めてしまいそうになりますが、分割会社側の処理との対応関係を考慮しなければなりません。適当でいいけどテキトーでは駄目だという規定です・・??
2006.10.08
-
一次審査会。
ビジネスコンテストの学生部門の審査員をやらせて頂いております。本日、第一次の審査会に出席してまいりました。事前に審査員各自が評価票を提出しており、その点数の集計を参考にしつつ、協議で第二次審査へ進む者を決定します。概ね自分の評価と審査員の皆さんの評価とは一致していたのですが、細部の議論となると、自分とは違う視点で評価されていることが分かったりして、非常に勉強になります。また、自分が高い評価をつけた事業案が、集計の点数では下位にあったりして、「うーむ。これはどう結論づけたらいいのか・・。」と頭の中で考えたりもしました。ともあれ印象深いのは、学生達のビジネスに対する意欲や、社会に対する問題意識の高さです。ほんとうに関心するばかりで、事前の評価票の書き込みでは、つい評価を忘れて、私も一緒になって考えてしまったりしました。私が学生だった頃は、かなりボヨーンとした学生生活をしていたと思うのですけれど、企業が学生を接待していたような時代ですから、今の学生はとは「危機感」が違うのでしょうね。いい意味で「将来を疑っている」学生が多いと感じます。もっとも、ビジネスコンテストに応募してくるような学生達ですから、彼らが標準ではないのかもしれませんけどね。二次審査は提案者直々のプレゼンテーションなので、非常に楽しみです。
2006.07.25
-

ビジョナリー・カンパニー
本の整理をしていたら、「ビジョナリー・カンパニー」がひょっこり出てきました。私のお気に入りの一冊です!このBlogの題名も、大いに影響を受けているところです。ということで、本日は気分を換えて書籍のご紹介です。筆者が書いているとおり、「この本を読んでしまったら、会社というものを真剣に考えずにはいられない。」ようになりますよ。・・多分。邦訳の副題は「時代を超える生存の原則」となっていますが、原則であるかどうかはともかく、「生き残れる会社」についての、非常に有益な研究結果が記されています。・・と書くと堅苦しい印象を与えますが、非常に読みやすい本です。ちなみに、MBA取得等を目指している方は、全部の勉強を終えた後に読むことをお薦めします。一生懸命マーケティングの勉強をしている最中に、この本を読むと、多分ヤル気を無くすと思いますので・・。また、本書は1994年に発表されて日本では翌年に翻訳されたものですけれど、「ここ10年の間、経営理念の作成というものが流行りになっているが・・」と、「お飾りの経営理念」が一人歩きしていることについて、警鐘を鳴らす記述があります。今、日本ではまさにこれが「流行」になりつつあると思いませんか?私は、素晴らしい経営理念を掲げておきながら、まったくそれに反する行動をとって、市場から追放された、ある企業のことが忘れられません。経営理念を読んで「いいこと言っているなぁ。」と感心したので、とても印象に残っています。(笑)きっと腕のいいコピーライターに書かせていたのでしょうねぇ・・。「一度、この理念を掲げた社長に会ってみたいなー。」と思った自分が、情けないやら、悲しいやら・・。「経営」に関して日本は米国より10年くらい遅れていると表現されていますから、今後、ますます「偽経営理念」が氾濫することになるでしょうね。私が紹介するまでもなく、有名なベストセラーですので、まだ読んでない方は、是非ご一読を・・。
2006.07.18
-
セカンド・オピニオン
危ういところでした!もう少しで入院生活を余儀なくされるところでした。しばらく耳鳴りが続く日がありまして、耳鳴り自体は、たまにあることでしすし、寝不足なんかでも起きますから、あまり気にしていなかったのですね。ところがある日、片方の耳が塞がれたような感じになってしまったのです。声も聴きづらくなってしまったので、さすがに異常を感じて耳鼻科に行ったのですが、診断結果は「中耳炎」。治療をしてもらい薬も飲んで、耳が塞がれたような感じはちょっと改善したのですが、相変わらず耳鳴りが止らない。数日後、就寝中に起きてしまうほどの耳鳴りに襲われ、「これは中耳炎なんかじゃない・・。」と感じた私は、翌日に別の病院に行きました。診断結果は「突発性難聴」。治療が遅れると耳が聞こえなくなってしまう恐ろしい病気です。難病の一つに挙げられいる病気だそうで、一番の原因はストレスだとか・・。(泣)いわゆる現代病ですね。とりあえず3日間治療薬を出すので、改善が見られない場合は入院だと宣告されました。診断してもらった時の状態だと即日入院してもいいくらいだと言われ、かなり落ち込んでいたのですが、本日、経過を診てもらったところ、回復に向かっているので、薬も減らすとの、嬉しい診断をいただきました。めずらしいほどの回復ぶりだそうで、寝ると嫌なことはすべて忘れてしまう自分の性格が吉と出たようです。(笑)ストレスは怖いですね。自分では溜め込んでいる自覚がないのが難です。この「突発性難聴」という病気はけっこうメジャーになってきているようですから、もし、耳鳴りが続いたり、耳の聞こえが悪くなったと感じたら、直ぐに病院に行くことをお薦めします。発病して2週間以上経ってしまうと、治療が困難になってしまうそうです。それと、セカンドオピニオン。必ず取れとは言いませんけど、何か気になることがあったら、取るべきだと思います。実は、私は過去にも同じような経験をしておりまして、学生の頃に腹痛と吐き気に襲われ、最初に行った診療所では「風邪」と診断され、それ用の薬をもらいました。ところが、次の日になっても腹痛が続く・・。これはおかしいと思い、総合病院で診断してもらったところ、なんと「サルモネラ菌」による食中毒でした。専門の治療薬を投与してもらったら、直ぐに治りました。医者も人間ですから判断を誤る場合もあります。ここで信用問題、責任問題云々を語るつもりはありませんし、医者の診断を鵜呑みにするなと言うつもりもありません。ただ、自分の体は自分がよく分かっているわけですから、治療開始後も、自分の体が発する信号には注意を向けて、なにか嫌な感じがした場合は、他の病院で診てもらう姿勢が必要かもしれません。当然、体の不調が精神不安を煽るわけですから、あまり神経質になり過ぎるのも、よくないと思いますけどね。
2006.07.01
-
コンプライアンス・オフィサー・フォーラム
コンプライアンス・オフィサー・フォーラムに参加してまいりました。ここ数ヶ月は会社法の登記実務対応に追われて、こちら関係はすっかり疎遠?になっていましたので、情報交換と刺激をうけるべく、また八田進二教授の講演も聴けるとあって、張り切って参加してまいりました。私は、初めて八田教授にお会いしたのですが、思ったよりお若く、そしてその迫力のある口調にとてもビックリです。会計プロフェッション研究科の教授というイメージから、学者肌で論理的な話しをされる方だろうと勝手に思っていたのですが、システム構築云々よりも、精神論を説く、非常に「熱い」方でした。是非、またお話しを聴いてみたいです。私は、内部統制システムについて、非現実的だと思うことが多々ありました。主に中小規模の企業に関することですが、こんなことしていたら、かえって日常業務に支障が出ると・・。しかし、今回の講演で昨年10月に、COSOが中小企業向公開草案を発表していたことを知り、不勉強であることを恥じるとともに、ちょっと安心しました。こりゃ無理だよ・・と思っていた心の霧が少し晴れた感じです。草案を読んでみたいと思うのですが、当然英文でしょうね・・(泣)。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、入手先を教えてください。レセプションでは、第1回目のフォーラムに参加されていた方々とも再会でき、また新たに交流も広まったのですが、前回同様、もう少し時間が欲しかったですね。前例のない話題も多いため、挨拶をして話が始まると、ついついディープな方面に行ってしまい、多数の方と交流する時間がない・・。某企業の法務部長さんや監査部長さんも参加されていたので、色々と話しを聞いてみたかったですね。フォーラム終了後は有志で2次会へ行きました。実際に内部統制の関連部署で活躍されている方々の体験談は、大変勉強になりました。製品回収の話題も出ましたが、なかなか厳しい世界です。一個人に戻ってしまえば、「そんなの、いいじゃん!」という意見が大半でしたが。(笑)大変有意義な時間を過ごすことができました。認定機構のみなさん、オフィサーのみなさん、どうもありがとうございました。
2006.06.25
-
これは大変会社法。
まったく“ぐっばる”状態でなかった先週1週間でしたが、あまりにキリの無い作業に追われていたため、先週の木曜日は思い切って5時で仕事を切り上げて帰ってしまいました。そしたら金曜日の仕事が捗ること、捗ること!リフレッシュとはこのことか、とういう感じでした。次の仕事が数件控えていると、なかなか区切りをつけづらいですけど、メリハリは必要ですよね。水曜日は、商工会議所で会社法のセミナーがありました。施行前にお話しがあり、予定日は施行後1ヶ月目くらいとのことでした。きっとその頃には大変なことになっているだろうということで、タイトルは「これは大変会社法!」としたのですが、ふたを開けてみれば「オレが大変会社法!」となっていて、セミナーの冒頭にこの話しをしたら、ややウケしていました。(欽ちゃん、ばかウケでなくて残念・・。)しかし、定員80名のところ、120名もの来場となり、相当数のお断りもしたとのことで、いよいよ施行後の危機感を身近に感じ始めた経営者の方々が増えてきたのでしょうね。税理士さんも多数来場されていたようでした。今回のセミナーは実際の登記事項証明書を用いたり、定款記載例を参照しながらやりましたので、より実践的な理解を深めていただけだのではないかと思っております。アンケート結果にまだ目を通していないので、満足度が気になるところですが・・。これからの時期は、いよいよ大会社の対応や、定時総会に合わせた会社法への対応がメインになります。新株予約権を発行している会社や種類株式を発行している会社は、例えば定時総会で役員の再選等がある場合は、その変更登記と同時に経過措置政令による変更登記も必要になるので注意してください。ただ、新株予約権に関しては「消却事由及び消却の条件」を、会社法の規定に沿って「取得事由及び取得条件」に整理するだけで、それほど問題ないのですが、種類株式については厄介です。整備法、経過措置政令で変更登記をしろと言っても、みなし規定でカバーできないもの、例えば「商法の規定に従う」とあるものを「会社法の規定に従う」とは簡単に置き換えられない事態等が発生して、登記申請の添付書面は委任状のみとされてはいるものの、結局は定款変更決議を余儀なくされ、株主総会議事録の添付が必要となる場合もありそうです。
2006.06.11
-
登記費用振り込め詐欺。
なんと!会社法施行に便乗して、司法書士を名乗る者の振込み詐欺が発生しているようです。以下法務省のHPの抜粋です。最近,司法書士等を名乗る者から,会社法の施行に伴い登記が必要なので,そのための登記費用の振込みを求められたとの情報が寄せられています。 すでに登記をしている会社のうち,資本金の額が5億円以上の会社等の一部の会社を除き,会社法等の施行に伴う必要な登記については,登記官が職権で登記をしますので,新たに登記の申請をしていただく必要はありません。 会社法施行に伴い登記官が職権で登記する内容等については,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html)をご覧になるか,管轄の法務局にお尋ねください。【関連リンク】 架空請求に関する情報 http://www.moj.go.jp/kaku.html まぁ、よくビジネスチャンスを逃さないものですね・・。その才能を是非ともマジメな経営活動に生かして欲しいものです。しかし、登記懈怠(おそらく罰則規定を強調して)をネタにするとは、かなりマニアックな手法ですよね。誰かが入れ知恵でもしたのでしょうか。そのうち「おたくの会社は決算公告してないから過料を支払ってください。」という架空請求も出回るんじゃないですかね。引っ掛からないためにも、ちゃんと決算公告をしておきましょう。法令遵守とリスクマネジメント、いっぺんに出来ちゃいます。
2006.05.17
-
会社法・整備法の問題。
すっかり1週間ごとの更新ペースになっていまいました。いつも訪問してくださっている方々、申し訳ありません・・。5月1日付で申請した新法下の登記が数件完了し、今後の予定の見通しも立ってきたので、すこし余裕が出てきた感じです。ただ、相変わらず現場の方は混乱状態ですね。表現があまりよろしくないとは思いますが、最前線で働く衛生兵になった気分です。事例がどんどん発生するのですが、どうも条文通りでは処置ができない。しかし、どうやって処置すればいいのかを聞いて、その正式な回答を待っていては手遅れになってしまうので、とにかく対処法を考えて措置をする。そんな状態です・・。先日の役員会でも、「特例有限会社を、取締役会を置く株式会社に移行する場合」の問題が話題になりました。以下、事例を説明します。特例有限会社を株式会社に移行するには、整備法の規定に基づき、「商号変更」の「定款変更」手続きをする必要があります。実態は商号変更ですが、手続きとしては「新株式会社の設立登記」と、「特例有限会社の解散登記」を同時に行い、この「登記」をもって商号変更の定款変更の「効力が生じる」ことになります。つまり決議が成立しても、登記をしなければ効力が生じないということです。上記手続きの中では、新株式会社の定款を新しく作成することになるのですが、移行後の株式会社に取締役会を設置したい場合は、定款中に「取締役会を置く」旨の規定が必要となります。そして取締役会設置会社では、代表取締役は取締役会で選定することになるのです。さて、ここで問題が発生します。「特例有限会社は、取締役会を設置できない」ことになっています。つまり取締役会を置く株式会社に移行したい特例有限会社は、代表取締役を選定できないという事態に陥ってしまうのです。旧商法下では、有限会社が株式会社となるためには組織変更の手続きを行いました。その場合の効力の発生は組織変更の「決議時」であったので、決議後すぐに取締役会を開催し、代表取締役を選任できたわけです。しかし、整備法下では「登記が効力要件」となりましたので、内部意思では代表取締役が決定しているにもかかわらず、登記が完了(実際には登記官の交合)をするまでは正式な選定手続きができないのです。一つの方法として、とりあえず取締役3名のみを選任しておき、登記完了後に取締役会設置の旨の定款規定を置く決議と、取締役会を開催して代表取締役を選定するということも考えつきますが、この場合、登記事項は一旦「全員が代表取締役」として表示されてしまい、以後、代表取締役が選定された場合には、「取締役会設置の旨の登記」と、代表取締役に選定された者意外については「代表権喪失の旨の登記」を再度し、なければなりません。余計に費用もかかりますし、登記事項の表示が、ややこしくなってしまいます。もう一つの方法は、とりあえず取締役会で選定する方法以外の定款規定で代表取締役を置くことにし、登記完了後、上記のように再度定款変更をするという手もありますが、この場合でも費用の問題は解決できません。では、何とか従前のようにできる方法がないかということになるのですが、結局のところ、法務局と協議の結果では、「定款の附則に新株式会社移行後の代表取締役を選定しておく。」という扱いがなされることになりました。(実際に協議したのは他の先生ですが・・)もう一度事例を整理しますと次のようになります。会社法326条2項により「定款で取締役会を置く旨の規定を設けた」。この定款変更は、整備法45条2項により「定款変更の効力は登記をもって生じる」ことになっている。株式会社へ移行した後の代表取締役を選定しておく必要があるのだが、「特例有限会社は取締役会を置くことはできない」という整備法17条1項の規定があるので、代表取締役を選定する手段がない。しかし、なんらかの方法で、従前のように新株式会社移行(商号変更)と同時に代表取締役1名を選定しておく必要がある」ので、「定款附則において、代表取締役を選定する」という方法でとりあえず対処することにした。ということになります。ただこの方法も全く問題が無いとが言い難いので、ほんと、応急措置だと認識しておいたほうがよろしいかと思います・・。
2006.05.14
-
職権登記
あっという間にゴールデンウィークが過ぎてしまいました。なんだかんだで、休みの半分くらいは仕事関係の準備等に費やすことになり、なんだか休暇をとったという気がしませんでした。まぁ、もともと混んでる場所が嫌いなんで、連休中に遠方に足を運ぶ予定はなかったんですけどね。(・・ひがみに聞こえますよね。)さて、5月1日に施行された会社法ですが、いくつか登記事項証明を取得しまして、職権で変更登記がなされる部分を確認してみたのですが、私が見たものに関しては、全て職権登記済みでした。特例有限会社では、発行可能株式総数、発行済株式総数、公告方法、株式譲渡制限規定などが、株式会社では、株券発行の旨、取締役会設置会社、監査役設置会社などが、申請手続きをしなくても、自動的に登記されています。当初、件数が多い法務局では作業が間に合わない可能性があるので、施行後数日間は従前の登記事項証明が発行されるかもしれないという話だったのですが、今のところそうような事態は起きていないようです。驚いたのは、商業登記のメッカである東京法務局港出張所が、きっかり5月1日付で職権登記がなされていたことです。近隣の法務局では5月2日付のところもありましたから、さぞかし大変な作業だったろうと思います。もっとも、応援隊が多数駆けつけていたでしょうから、逆に、近隣の法務局の方が大変な作業だったかもしれませんね。でも本当に大変なのは、これから。私もどこまで“ぐっばる”でいられるか、ちと心配です。
2006.05.09
-
経営相談会
コンソーシアムの経営相談会に出席してまいりました。とある事業について、事業計画、資金計画の妥当性について検討し、更にはプロモーションについても話が及びました。一見、よくある事業なのですが、コンセプトがなかなか面白く、中心となる方の起業家としての素質もあって、結構期待できるのではないでしょうか。ただ競合企業も多く、価格競争も厳しい市場に参入することになるので、芽が出る前に埋もれてしまう危険性が大きいということで、プロモーションについて様々な意見が出ました。私も議論に加わりながら、自分の頭の中でも様々な考えを巡らせていたのですが、アプローチの仕方を変ると、同じ事業内容でもまったくインパクトが違うことが分かり、相談を受けつつも自分の方がかえって勉強になったりして、ビジネスというものの奥深さを、あらためて感じました。まだまだ発見がありそうです。
2006.04.19
-
会社を考える。
会計事務所のスタッフさん向けに、会社法への対応について、1時間ほど話をしてまいりました。みなさん、担当の企業を思い浮かべながら、具体的な対応についての質問をされていましたが、質問内容は相当バラエティーに富んでいました。答える私も勉強になります。やはり、なんと言っても一番の関心事は、特例有限会社の株式会社への移行です。現在の経営者の代で事業を辞める会社は、そのまま特例有限会社で、多少なり将来像がある会社は、新株式会社へと、大まかな流れは固まりつつあるようですね。特例有限会社について、法定役員任期がないことや、決算公告をしなくていいことを、「メリット」と考える方々もいるようですが、私は、そのような考え方は捨てた方がいいと提言します。肝心なのは「あなたは、その会社をどうしたいのか?」ということです。事業を大きくしたいのか?現状で充分と考えるのか?自分の寿命と会社の寿命を同じに考えているのか?後生に続く会社としたいのか?そして会社を通じて何を実現したいのか?今回の会社法改正は、もう一度「会社について考える」絶好の機会だと思います。
2006.04.11
-
対策はOKですか?
今日は行く先々でWBCのTV中継をやっていました。某市役所で証明書の発行を待っているとき、待合フロアーのTVを観たときは、まだ7回でスコアは0対0でした。そして某法務局に着いたときは、ちょうど9回裏の日本の最後の攻撃時。思わず足を止めて観てしまいましたが、試合が決まった瞬間、「あぁー。」という溜息と共に、TVが置いてある待合フロアーにいた人達が、殆どいなくなってしまったのには笑いました・・。今日は法務局が混んでるなぁーと思っていたんですけど、そういうことだったんですね。さて会社法の話題になりますが、最近の官報を見ていると、「いよいよ来るなー」という気になります。何故かといいますと、株式譲渡制限規定の設定を行う旨の公告が非常に多いのですね。どうやら会社法施行と同時に監査役が任期満了することを回避するために、現行商法特例法の小会社に該当する多くの株式会社が、譲渡制限を設定する方向に動いているようです。しかし、このように株式譲渡制限規定のない小会社の監査役が、会社法施行と同時に任期満了退任するということを知らない会社も相当数あるのではないでしょうか?今、このことを知って手続きをしようとした場合、株主総会招集手続きや、官報の公告期間等を考えますと、手続きが間に合わない場合も考えられます。対応が間に合わなかった場合は、会社法施行後直ぐに後任監査役を選任するか、思い切って監査役を置かない会社とするか等を選択しなければならないのですが、後任監査役を選任する場合は、業務監査も監査範囲に含まれますので、直ぐに適任者が見つかるかどうかという問題がありますし、監査役を置かないとした場合は、取締役会設置会社にはなれないという問題が発生します。この辺の仕組みは、しっかり押さえていないと後になって思わぬ痛手を負うことになりますので、早めに、会社法に精通する専門家に相談して、対策を立てておくことをお薦めします。是非是非・・。
2006.03.16
-
水分不足は恐ろしい・・。
本日も忙しいです。忙しくて目が廻りそう・・と思ったら、本当にグルグルと目が廻ってしまいました。イカン!水、水!!水飲まなきゃー。一体何を言っているのかって?水分不足は非常によろしくないのですよ。・・って人に忠告している場合じゃないか。昨年末頃でしたかね。私は、仕事の最中に突然はげしい眩暈を起こしました。急に目の前がグルグル廻りだして、字を見ていられない。歩いても酔っ払いのようにフラフラしてしまい、真っ直ぐ歩けない。「わぁー、これは脳の血管が一本切れたに違いないっ!」と、慌てて脳神経外科に行ったんですけど、診断結果は、なんと水分不足・・・。笑っていいんだか悪いんだか・・。私は、乗ってしまうと?徹底的に仕事をしてしまう癖があるので、気が付くと全く水分を口にしないまま半日が過ぎるといったことが結構あります。そんな状況で更に空気が乾燥してたりすると、血液中の水分が不足してグラッとくるんだそうです。本日は、久し振りにそれをやってしまった・・。ちなみに、お医者さんのアドバイスによると、一日1.5リットルの水分を摂らなきゃいけないそうです。1.5リットルって、結構な量ですよね。そして効率よく水分補給ができる飲み物は、ウーロン茶やほうじ茶など。コーヒーは利尿作用のせいで、飲んでもその分また外に出てしまうので効率が悪いそうですよ。確かに・・コーヒー飲むとトイレに行きたくなるよなぁ。一番好きな飲み物だけど。そういえば今日は食後にコーヒーを一杯飲んだだけだった。というわけで皆さん、水分不足にはくれぐれも気をつけましょう!!
2006.03.09
-
五感と六感。
今日は久しぶりにコートが不要な天気でしたね。「月曜日」そして「温暖な気候」となると、だいたい忙しい一日となります。登記が完了して連絡済みのクライアントが、一斉に受領にやって来ます。(笑)そして来所する時間が不思議と重なるんですよね。まるで申し合わせたかのように、何人かのお客さんが同時にやってくる。そして、パタッと誰も来なくなる。面白いものですね。「そうだ書類を取りに行かなきゃ。」と思い立った人の波長が、同じ事を考えていた人のアンテナがキャッチしてるんですかね。そういえば、口には出さないけど、頭の中で曲がグルグル回っているとき、ふと隣の席の人が、いきなり同じ曲を口ずさむということってありますよね?自分の波長が相手に伝わったのかな?それとも飛び交っているラジオか何かの電波を二人ともキャッチしたのかな?なんて考えたりしてしまいます。本来、人は第六感が一番発達していたそうですから、現代では、あまり使わなくなってしまった感覚も、たまに目を覚ますのかもしれません。ちなみに、色彩感覚は男性よりも女性の方が優れているらしいです。これは本当でしょうね。以前、何かの宝石展に行ったとき、ダイヤモンドの作品を見ている男性と女性の表情の違いが面白かった。男性は皆、綺麗だねぇーという表情。女性はといえば、それはもう恍惚に近い表情・・。そんなことを観察しつつ、自分も、綺麗だねぇーとしか思えなかったので、「きっと女性には、男には見えないものが見えているに違いない。」と確信しましたから・・・。
2006.03.06
-
会計監査人と登記
ちょっと登記業務に偏った話題になってしまいますが、会計監査人について書いてみようと思います。会社法では第911条第3項第19号により、会計監査人についても、「会計監査人設置の旨及び会計監査人の氏名又は名称」が登記事項となりました。そして会社法第338条に任期に関する規定があり、第1項で「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時まで。」とされています。ユニークなのは、同条第2項の規定。「定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。」という、他の会社機関(株主総会を除く)とは違った扱いがなされています。つまり、何も起きなければ毎年重任登記(会計監査のルールは別として)が必要となるわけです。大体、会社の変更登記を受託するにあたっては、まずクライアントから変更決議等の概要の説明を受け、議事録等を受け取った後に変更決議の内容がきちんと記載されているかをチェックすると同時に、説明を受けた事項の他に登記すべき事項がないかどうかも見てゆくのですが、(例えば、役員選任があったことのみ説明をうけたが、議事録には責任限定契約に関する定款変更決議もされていた等・・。)これらの作業は「何が記載されているか」を注意して進めて行くことになります。ところが、この会計監査人に関する登記につていは、「なにも言及されていないこと」も登記原因になりますので、司法書士としては、当然のことですが登記事項証明書を確認のうえで、さらに固定観念を捨てた作業が必要となってくるわけです。また、会社の法務部や総務部の方も、定時総会で決算報告のみ行った場合でも、「今回は特に変更事項はないから司法書士には連絡しなくてもいいや。」ということにはなりませんので、どうかご注意ください。以上、会計監査人と登記のお話しでした・・。
2006.02.24
-
代表取締役と登記
さて本日は「代表取締役と登記」について書いてみたいと思います。株式会社については、新会社法では第349条により原則として「各取締役が株式会社を代表する」ことになっています。そして「ただし書」として、「他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合はこの限りでない。」として、別途取締役の中から代表取締役を定めることを認めているわけです。(ただし書の後半部分については、今回はちょっと頭の隅に追いやっておいてください。)この規定は、内容は現行有限会社と同じだと考えると難しい話ではないのですが、登記に関してはちょっと厄介なことが起こります。有限会社が会社法施行後も何も手続きをしない場合は、特例有限会社となります。この会社に「取締役A」,「取締役B」,「取締役C」の3名が選任されていると、登記上に現れる役員の名称は、同じくA、B、C全員が「取締役」です。従前の例と変わりませんよね。では、会社法が施行された後に設立された、「取締役X、取締役Y、取締役Z」と同じく3名取締役のみが選任された「株式会社ぐっばる」はどうなるでしょうか。この場合はX,Y、Z全員が「代表取締役」になります!?正確に言うと取締役と代表取締役が併記して記載されるのですけど、とにかく、みんな代表取締役!「スゴイですねぇー。華やかですねぇー。」・・・じゃなくてちょっと混乱が起きそうですよね。まず会社の取引関係にあっては、取締役が1名の会社法下の株式会社であれば、名刺等に「代表取締役」という名称が使用できるので、大変いい効果が生まれるのですけど、上記のように取締役を3名選任したとしますと、なにやら変なことになります。例えば役員の紹介の時に、「こちら代表取締役Xです。」「こちらは、代表取締役のY。」「そして私は、代表取締役のZです。よろしくお願い致します。」といわれたところで、「誰が一体代表者なんだよ!」と思ってしまいますよね。本当は文字通り全員代表者なんですけど、「代表取締役」という肩書きの強烈なイメージが先行しますから、ちょっと特異な印象を与える可能性があります。ただ、実際のところは、定款規定を工夫して代表取締役が3名並んでしまう事態を避けることになるでしょうが、中にはこういう会社も出て来るかもしれません。では、上記の例で挙げました「株式会社ぐっばる」が現行の中会社で、Xが代表取締役に選任(会社法だと選定になりますね。)されている場合について考えてみましょう。会社法が施行されると整備法の規定により、定款に「取締役会を設置する旨の定めがある」ものとみなされます。このままだと、引き続き取締役3名以上の選任が必要になりますが、実はZが名目取締役なので、人数を減らして取締役2名にしたいと考えた場合、どのような手続きをしたらよいでしょうか?「名目取締役Zの退任」と定款の「取締役会設置の旨の規定の廃止」が頭に浮かびますが、さて、そのまま手続きを進めて登記をした場合、どういうことが起きるかといいますと、「代表取締役X」「代表取締役Y」という登記が出来上がってきます。そう、取締役会の設置を廃止したところで、各自が代表権を持つことになり、代表権をもつ取締役は「代表取締役」として登記されるのです。突然現れたもう一人の代表取締役・・。この実態を避けたいのであれば、やはり互選規定を設ける等の、もう一つの定款変更等、他の手続きが必要となりますので、どうかご注意を!
2006.02.23
-
SBIR・会社法概要説明会
SBIR・会社法概要説明会に行ってきました。前半のSBIRの事例発表での社長さんのお話しは感動でした。まさにプロジェクトXの世界!電気技術が専門だったにもかかわらず、日航ジャンボ墜落事件を目の当たりにし、「なんとか墜落しない航空機をつくれないか。」という心の叫びから、油圧制御装置の開発に取り組み(まったく他の分野への進出)、社員には呆れらつつも、数年の歳月を経て、装置を完成させたというスゴイ話。今では、最新鋭航空機にも使用されているそうです。やはり経営トップの熱い思いが、事業を成功させるのですね。その製品名に「ハイブリッド」という名が入っているのですけれど、これを考案したのは昭和60年代だというのも驚きです。いまでこそ流行のフレーズになっていますけど、その当時なんて誰も知りませんよね。何度も書きますけど感動ですっ!!後半の会社法概要説明会は、講義を担当された公認会計士さんが、非常に丁寧に分かりやすく説明してくださいましたので、私が担当した質疑応答については、お1人しか質問がありませんでしたけど、みなさん、講義と配布資料で、概要はマスターしていただけたのだと思っております。ただ、私が作成した資料の中で、「資本金0円でもOK」としたところが、ちょっと混乱を招いてしまったようでした。いままでの商法とは違うということうを強調する意味で極端な例を挙げてみたのですけれど、あまりいい例ではなかったかもしれません・・。ちょっと反省です。その後慰労会を設けていただき、楽しいひと時を過ごさせていただきました。おいしい日本酒をついつい飲みすぎてしまったようで、今もちょっと酔っ払っています。(笑)明日は、東京司法書士会主催の研修に参加してきまぁーすっ!
2006.02.21
-
会社法施行規則
スーパー・ボウルVTR観戦しました。モメンタムが二転三転して結構面白い試合でしたね。優勝した時のビル・カウアーHCの涙が印象的でした。15年近く同じチームを率いて、ついに頂点に立ったわけですから、観ているこちらまでウルウルしてしまいました。さて、表題のとおり、ついに「会社法施行規則」が公布されました。正確に言いますと「会社法施行規則」「会社計算規則」「電子公告規則」の三本立てです。昨年11月末から12月末まで、法務省令案としてパブリックコメントに付されて、このたび内容が確定したものですが、事前の情報があったとおり、かなり大胆にパブリックコメントの意見を取り入れて様変わりをしてのお披露目となりました。まだ全条文に目を通していませんが、私がパブリック・コメントを出した、「株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令案」いわゆる「内部統制システムの構築」について、ちょっと触れてみたいと思います。当初、法務省令案では次のような条文案が提示されていました。(取締役の責務)第3条 取締役は、この省令に規定する事項を決定するに際しては、 次に掲げる事項に留意するよう努めるものとする。 1 株主の利益の最大化の実現に寄与するものであること。 2 取締役その他の株式会社の業務を執行する者が法令及び定款を 遵守し、かつ、取締役が負うべき善良な管理者としての注意を 払う義務及び忠実にその職務を行う義務を全うすることができ るようなものであること。 3 株式会社の業務及び効率性の適正の確保に向けた株主又は会社 の機関相互の適切な役割分担と連携を促すものであること。 4 株式会社の規模、事業の性質、機関の設計その他当該株式会社 の個性及び特質を踏まえた必要、かつ、最適なものであること。 5 株式会社をめぐる利害関係者に不当な損害を与えないようなも のであること。これに対しで、次のようなコメントが寄せられました。(1)省令に委任された事項であるか否かが疑問であるとする意見。(2)1号は、従来から「会社は誰のものか」、「会社法の目的は何か」 という深遠な学問論争が繰り広げられてきた重要問題に関わるもの であり、このような規定を設けることは相当ではないとする意見。(3)株主の利益が他のステークホルダーに優先するとの誤解を招くおそ れがある等の意見。前記(3)は、私も強調してコメントを付した部分、(1)もガバナンスに関する部分が含まれるので、内部統制システムとは違うのではないかとコメントした部分でした。そして、これに対する法務省の考え方が次のように示されました。「上記の意見等を踏まえて、省令案3条の規定を削除した上で、 省令案4条以下の内容を会社法施行規則に統合することとした。」スゴイです。きっと多くの方が内部統制に関心を寄せ、コメントを付した結果だと思いますが、こんな大胆な変更をされるとは!法務省の「会社法」に対する意気込みとでもいいましょうか、理解しやすい、よりよい制度にしようと努力されている姿勢が伝わってきて、かなり感動しました・・。ちなみに内部統制に関する部分は次のように規定されました。(業務の適正を確保するための体制)第100条 会社法第362条第4項第6号に規定する法務省令で定める体制は、 次に掲げる体制とする。 一 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規定その他の体制 三 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため の体制 五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団におけ る業務の適正を確保するための体制2 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前項に規定する体制 には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含む ものとする。3 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する 旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第1項に 規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。 一 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお ける当該使用人に関する事項 二 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 三 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役 への報告に関する体制 四 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制お気づきかと思いますが、2項で規定のあるとおり、監査役を置かない会社、つまり取締役会を置かない会社であっても、義務化はされていないものの、内部統制システムの構築が必要であることが明言されました。内部統制システムの目的は、一般的に「業務の有効性・効率性」「計算書類の信頼性」「関連法規の遵守」とされていますが、私見としては是非とも、第一の目的に注目して頂きたいと思います。どうしても堅苦しいイメージが先行してしまいますが、内部統制システムは、何よりも円滑に会社の運営を進め、成長を手助けするためのシステムであり、特に持続的成長を望むのであれば、構築が不可欠であることを理解して頂けると、すんなり受け入れることが出来るのではないでしょうか・・。
2006.02.07
-
東横インの違反
東横インの偽装工事についての西田氏の会見をニュース番組観ましたけど、言葉がありませんね・・。女性スタッフを中心としたホテル運営等、今後の発展を期待していただけに、とにかく失望しました。特に記者会見での社長の姿勢は、見るに耐えなかったです。「違反は承知だった。ばれちゃ仕方ない。」という発言は、いまさら言い訳はしないという潔さ?のつもりだったのでしょうか。あの発言を聞いた従業員の方々は、どんな気持ちだったでしょう?ガッカリしたんじゃないですかね・・。非を認めるにしたって、もうちょっと言い方があるんじゃないかと。感情的な話はここまでとして、次に、コンプライアンスの視点から今回の事件を分析したいと思います。この会社が「何故あのようなことをしていたか。」ということは、経営体質よりもトップの考え方によるところが大きいと思うのですが、それを象徴する、「東横インの経営理念」と称するものを読みますと、その姿が見えてきたりします。「東横インの経営理念」1、東横インは、聖徳グループの中核企業として過剰なサービス を省き、清潔と安心感と合理性を追求する独自の運営方法に より、お客様のホテルニーズにお応えする世界規模のビジネ スホテルチェーンである。2、東横インは、地主の土地有効活用ニーズに立脚した建物賃借 方式を原則とし、オーナー様を第一に考え、初期投資を抑え ることにより、好立地でかつ低料金の宿泊施設を市場に供給 する。3、東横インは、女将さんである支配人が、フロント、メイクと 一体となって切り盛りし、本社の人員は少数精鋭で支配人を 支援するという地方分権的経営により、一人ひとりの人間的 な成長を支援する。これが 経営理念 といえるものであるかどうかはさておき、「合理性」「初期投資を抑える」「オーナー第一」「人員は少数精鋭」という文字が目に付きます。もちろん「経営戦略」として捉えるならば、これらは当たり前のことですけど、経営理念に掲げているんですからねぇ。経営トップの考えが、「利益至上主義」であるという印象を私は受けます。また視野にあるものが「聖徳グループ」「オーナー」「社員」であり、ステークホルダーをかなり狭く捉えているという点も特徴です。行政の確認申請の後に、客室数を増やすという手法は、まさに「他のステークホルダーを軽視」した「利益至上主義」の典型的な行動といえます。この会社には、アイデンティティーと称されるエシックス・コードのようなものも存在するようですが、お飾り的なものみたいですし、コンプライアンスについては戦略の片隅にひっそりと置かれているようです。こうしてみると、この会社が今回の事件を起こしたことについて、妙に納得してしまいますね・・。
2006.01.28
-
会社法って・・Part2
再び会社法についてです。現行の商法(株式会社編)・有限会社法と、このたび成立した新会社法を比べますと、「全くと言っていいほど性格が違う」と前回のエントリーでも書きましたが、どういう風に違うのか、また別の方向から見てみようと思います。この現行法と会社法の違いを知るヒントは、どこにあるのかと申しますと、会社法成立の際に、衆・参両議院でなされた附帯決議にあったりします。法案を通すときに政府に対して、「賛成するけどさ、注文もあるんだよねぇ。」といったことが書かれているんですね。それでは、どんなことが附帯決議されたのか、次に大雑把な内容を書いてみます。尚、項目の番号は原文と一致していません。ちなみに、実際の附帯決議は衆議院13項目、参議院16項目あります。原文を読みたい方は、末尾に参議院の決議をアップしておきますのでご参考まで。(衆議院の決議もほぼ同じです。)1、会社法は自己責任によるところが多い。 その内容をちゃんと知って貰うようにフォローをすべきだ。2、株主総会の招集地は、何処でもいいことになったけど、 悪用されないように適切な措置をとるべきだ。3、取締役の責任が原則として過失責任になったけど、 その分監視の強化が必要。 問題が多発したら、見直しをすべきだ。4、取締役の任期規定が大きく緩和されたけど、 よろしくない事態になったら、見直しをすべきだ。5、種類株式については、悪用されるかもしれないので、 場合によっては使用の制限をするべきだ。6、敵対的企業買収防衛策について、 経営者の保身とならないような仕組みを提案すべきだ。7、M&Aの規制緩和につき、 利害関係人に損害が発生しないように今後も検討をすべきだ。8、類似商号規制の廃止については、 運用状況をみて、救済制度の創設も検討をすべきだ。9、会社設立時の出資額規制の廃止については、 悪質な会社が乱立しないよう注視し、 必要によっては対応措置をとるべきだ。10、合同会社(LLC)については、 株式会社の計算に関する規制逃れのために利用されることが 多発した場合や、課税の問題が発生した場合は、 制度の見直しをすべきだ。・・・こんな感じです。項目ごとに注目すれば、1、が会社法の性質を示していますよね。さて、今度は全体的に観察してみた場合はどうですか?注文が多いなぁーと思うと同時に、「随分と法律の縛りが無くなったんだなぁー」と思いません?そうです。そのとおり!これがいわゆる、「事前規制から事後救済へ」という会社法の性格を現すものなんですね。私なんかは、附帯決議のすべてに「うん、うん。」と大きく頷いてしまいます。ただ、1の役割などは、私達専門家の責務でもありますよね。このBlogでもいろいろ情報発信して行きたいと思ってます。------------------------------------------------------------------「会社法案に対する附帯決議」(参議院)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。1、本法が、我が国の経済社会において会社が果たす役割の重要性にかんが み、その利用者の視点に立った規律の見直し、経営の機動性及び柔軟性の 向上、経営の健全性の確保等の観点から、会社に係る様々な制度を抜本的 かつ体系的に見直し、企業の多様なニーズへの対応を可能とした趣旨を踏 まえ、各会社において、それぞれの実情に即した適切な管理運営の在り方 を選択することができるよう、本法の内容の周知徹底を図ることをはじめ として、適切な措置を講ずること。2、株主総会の招集地に関する規定の変更については、株主総会が株主の権利 行使の重要な一局面であることにかんがみ、その招集に当たって、株主の利 便性を損なう恣意的な招集地の決定がされることがないよう、株主総会の招 集通知の記載事項の在り方等について適切な措置を講ずること。3、会社に対する取締役の責任を原則として過失責任に再編成することに伴 い、会社財産の流出を防止し、株主や会社債権者を保護するという観点か ら、会社内部で適正なコーポレートガバナンスが確保されるよう、周知徹底 に 努めるとともに、今後の状況を見ながら、必要に応じ、会社に対する取 締役の責任の在り方について見直しを行うこと。4、破産手続開始の決定を受け復権していない者を取締役として選任すること を許容することについては、そのような者に再度の経済的再生の機会を与え るという目的について十分な理解が得られるよう、その趣旨の周知徹底に努 めること。5、株主による取締役の直接の監視機能として、定期的に取締役の改選手続を 行うことが重要であることにかんがみ、取締役の任期の在り方については、 今後の実務の運用状況を踏まえ、必要に応じ、その見直しを検討すること。6、拒否権付株式等、経営者の保身に濫用される可能性のある種類株式の発行 については、その実態を見ながら、必要に応じ、これを制限するなどの法的 措置も含め、検討を行うこと。7、企業再編の自由化及び規制緩和に伴い、企業グループや親子会社など企業 統合を利用した事業展開が広く利用される中で、それぞれの会社の株主その 他の利害関係者の利益が損なわれることのないよう、情報開示制度の一層の 充実を図るほか、親子会社関係に係る取締役等の責任の在り方等、いわゆる 企業結合法制について、検討を行うこと。8、株主代表訴訟の制度が、株主全体の利益の確保及び会社のコンプライアン スの維持に資するものであることにかんがみ、今回の見直しにより、この趣 旨がより一層実効的に実現されるよう、制度の運用状況を注視し、必要があ れば、当事者適格の見直しなど、更なる制度の改善について、検討を行うこ と。9、類似商号規制の廃止については、その運用状況を注視し、必要があれば、 既存の商号に対する簡易な救済制度の創設を含め、対応措置を検討するこ と。10、会社設立時の出資額規制の撤廃については、企業家のモラル低下、会社 形態を悪用したペーパーカンパニーの濫立、会社設立後の活動資金不足など の問題が生じることのないよう注視し、必要があれば、対応措置を検討する こと。11、会計参与制度の創設については、会計参与が主として中小会社における 計算の適正の確保に資する任意設置の機関として設けられた趣旨を踏まえ て、制度の周知徹底に努めること。12、有限会社制度が廃止されることに伴い、既存の有限会社が新しい株式会 社や新たに創設される合同会社等に移行するに当たり、不利益を被らないよ う配慮し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。13、合同会社制度については、今後の利用状況を観察し、株式会社の計算等 に係る規制を逃れるために株式会社から合同会社への組織変更等が顕在化し た場合は、必要に応じ、その計算に関する制度の在り方について、見直しを 検討すること。14、合同会社に対する課税については、会社の利用状況、運用実態等を踏ま え、必要があれば、対応措置を検討すること。15、五外国会社による我が国への投資が、我が国経済に対してこれまで果た してきた役割の重要性及び当該役割が今後も引き続き不可欠なものとして期 待される点にかんがみ、会社法第821条に関して、その法的確実性を担保 するために、次の諸点について、適切な措置を講ずること。(1) 同条は、外国会社を利用した日本の会社法制の脱法行為を禁止する趣 旨の規定であり、既存の外国会社及び今後の我が国に対する外国会社を通 じた投資に何ら悪影響を与えるものではないことについて、周知徹底を図 ること。(2) 同条は、外国の事業体に対し、特定の形態を制限し又は要求する趣旨 のものではないことについて、周知徹底を図ること。16、会社法第821条については、本法施行後における外国会社に与える影 響を踏まえ、必要に応じ、見直しを検討すること。
2006.01.20
-
公認コンプライアンス・オフィサー
ビジネス法務の部屋のToshi先生からトラックバックを頂きました。ありがとうございます!そういえばToshi先生とご縁が持てたのも、Blogがきっかけでした。私より全然すごい方なのに、私の稚拙な意見なんぞを聞いてくださいます。器が大きい人は違いますね。Toshi先生とは公認コンプライアンス・オフィサーという資格と通じて、お付き合いが始まりました。ちょうど私がCSR(企業の社会的責任)について、あれこれ考えていた時期に、この資格試験が実施されることを知りました。制度趣旨に共感し、また試験委員が信頼のおける方々でしたので受験したんです。昨年末には国内初のフォーラムが開催され、私も参加してまいりました。「結果よりもプロセスが大事」だとフォーラムでも言われていたとおり、資格取得の目的は皆さんそれぞれお持ちのようでしたけど、「問題意識を持つ」ということは、非常に大事なのではないかと思います。私も、この資格取得のプロセスの中で、今まで疑問に思っていたことや、モヤモヤと考えていたことについて、多くの答えを見つけることができました。そして新たな問題発見があったりもします。「コンプライアンス」というフレーズは、未だに解釈がバラバラのようで、「遵法」と訳されることも度々見かけますが、正しくは「倫理・遵法」であり、「遵法の前に倫理がつく」ことがポイントです。勉強されている方には、そんなの百も承知だと言われてしまいそうですが、案外これを理解していない方もおられるようです。今後この辺りのこともアップしてゆきたいと思っています。
2006.01.14
-
会社法って・・
2月にお手伝いする予定の、SBIRと会社法セミナー用の配付資料なんぞを作りました。SBIRの活用法や事例発表に重きを置いているので、会社法関係はごく簡単な説明しかできなさそうです。そういった事情を踏まえ、ごく簡単な資料にしました。当日は公認会計士さんと一緒に担当する予定です。本当に今回の会社法と関連法の改正はボリュームがありまねぇ。戌年は変革の年だそうですから、それに相応しい大改正ですよ。ちなみに会社法の施行日は5月初旬もしくはゴールデンウィーク明けぐらいとか・・。うちの近くの書店では法律書のコーナーの平積みは、ほぼ会社法関係の書籍で埋まっています。会社法の本を読んだ方はいらっしゃいますでしょうか?感想はいかがですか?「大筋は分かった様な気がする。」とか「具体的にはどうしたらいいのか今ひとつ理解できない。」と思われた方も多いのではないでしょうか?でもこれは、著者がどうこうという問題ではなくて、その理由はおそらく2つあると思います。まず紙面の制約があるということ。新会社法の内容は、1冊の本でまとめられるものじゃーありません。紙面を気にしないでいいから全部説明してと言われたら、一体何分冊になることか・・。私は、昨年の夏に朝から夕方まで6時間に及ぶ会社法の研修を受けたのですが、それでも時間が足りませんでした・・。もうひとつの理由は(これが主な理由ですけど)、会社法は自分で考えて活用するように出来ているからです。活用例の提示はできても、実際に活用するときは個々の会社の実情に合わせてもらうしかありません。条文の中に、いろいろパーツが転がっているので、それを自分で組み立てなければならないんです。例えば機関設計について説明しますと、今までの商法(株式会社編)や有限会社法では、「必ずできる!会社組立キット」があって、説明書を読みながら組み立てると、それなりの会社ができるようになっていました。別売りのオプションパーツは高額でなかなか手がでないので、できあがった「会社」は、株式会社と有限会社という違い以外は、ほぼ似たような感じだったんですね。ところが会社法では、最低限の「スタートアップキット」だけあって、組立説明書はついていません。自分で好きなようにパーツをくっつけたりして会社機関を設計して作るのです。そして組立説明書の代わりに、「このキットは別売りのパーツを取り付たり外したりすることで、色んな会社が出来上がるようになっています。Let‘s Enjoy!」みたいな紙しか入っていないと思ってください。もちろん、できあがる会社は個性豊かになりますけど。ちょっと分かって頂きました?既に会社経営をしている方、これから会社を立ち上げようかと考えている方は、頭の中で、「どんな会社がいいかなぁー」と構想を練っておくことをお勧めします!!(・・というか、練っておかないと差が付いちゃいますよ・・)
2006.01.12
-
ぐっばる-その2-
”ぐっばる”な状態で大切なキーワードは「余裕」です。今までの色々な経験から、適度な余裕を持つことが大事なんだと確信しております。私、とある武道をやっていまして(今は休眠中ですが・・)、高段者の方と乱捕り(試合形式の練習)をしたりしますと、礼をして向かい会った瞬間に、もう勝てないという気持ちになるということを何度か経験しました。それは相手に隙がないからなんですけど、その「隙がない」とういうのは、なんと言いましょうか、ガッチリとバリヤが張られているというのではなくて、どんな攻撃もかわされてしまうような余裕を持っている感じなのです。きっと、そんな時の私の方は全く余裕のない”ばっばる(Bad Balloon)状態ですから、エイヤーとやられてしまう訳です。仕事をしていても、”ばっばる”な状態ですと、こちらは余裕がなくて、パンパンに膨らんでいる風船ですから、接触した相手をボーンと跳ね返してしまったりします。相手も”ばっばる”ですとお互いに遠くに跳ね返ってしまったりします。会社経営にしても、一杯一杯の状態ですと、日ごろの業務に追われてしまい、次の経営戦略に考えが及ばなくなったり、今そこにある商機に気づくことができず、見過ごしてしまったりします。とは言え”ぐっばる”な状態でいるには、結構難しかったりします。「余裕」はできるものではなく、作らなければできないものですから、私は、たまに自分を省みて、「今はどんな状態かな?」と確認してみたりしています。結構”ばっばる”な状態の時が多いので、「イカン、イカン」と、ちょと気分転換したり、趣味に走ったりなんかしています。言うは易し、行うは難しですね・・。
2006.01.09
-
”ぐっばる”について
さてさて、ブログの題にもなっている”ぐっばる”という言葉についてですけど、プロフィールにもちょこっと書いていますが、「適度に膨らんだ風船=Good Balloon」という私が造った言葉の略語です。本来の英訳ですとWell-Shaped Balloonとかになるんでしょうけど、これですと風船の外見しか表現できていない感じがして、他の英訳にしても、フレーズとして使うのにはピンと来るものがなかったので、この言葉を使うことにしました。空気が入り過ぎている風船って、ちょっとした外力が加わってだけで破裂してしまいますよね。その風船を見ている人にしたって、いつ破裂するか分からないような状態なので心も落着きません。反対に、空気が足りなくてしぼんだ状態の風船は、ちょっと寂しいですよね・・。適度に膨らんだ状態の風船は、弾力があって、風船自身も余裕があって、外力が加わっても、やんわり吸収できたりします。この”ぐっばる”の状態は、日常生活、仕事、その他色々な事態に対しても、うまく対処してゆけると思っています。これは、何年か前に、「どういう生き方をするか」という題材だったと思うんですけど、とある論文を書くことになりまして、その際にあれこれ考えた末にたどり着いた答えです。このブログも、題名からもお分かりになると思いますが、私の仕事に関することや、法律、会社経営といったものをメインにするつもりですが、仕事とはまったく関係のない趣味のことや、関心ごと等も書いて行きたいと思っています。ですので、司法書士の仕事のことを知りたくてアクセスして頂いた方が、NFL(米国のプロのアメリカン・フットボール)の試合の事などが書いてあるのを見て「なんじゃこりゃ?」と思われることもあるかもしれませんが、そこは”ぐっばる”でやさしく受け止めて頂きたいと思っております。(笑)それでは本日はこの辺で・・。
2006.01.07
-
ごあいさつ。
いよいよブログを始めることにしました。機能をマスターできないまま、ノロノロと設定を行っていたら、すでにアクセスが15件も来ていてビックリです!私のブログに寄っていただいた方、なにも書いていなくて申しわけありません。。仕事のこと、会社のこと、関心事など、毎日とはいかないでしょうけど、何かある度に書いて行きたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
2006.01.06
全28件 (28件中 1-28件目)
1