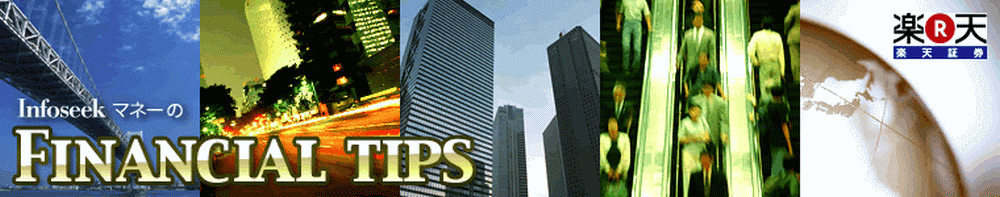カテゴリ: 投資信託
アクティブ運用を行うファンドの運用成績は、一般的には、日経平均株価や東証株価指数といった株価インデックスをベンチマークとして、それをどの程度、上回ったかによって、その良し悪しが評価される。
こうした対ベンチマークとの相対評価においては、たとえファンドの基準価額が下落していたとしても、ベンチマークの下落率よりも小さく押えられれば、それは評価の対象になる。
ただ、一部から「ファンドの購入者は相対評価を望んでいない。いくら利益が上がってナンボだろう」という声が上がったのも事実だ。もちろん、大勢の個人投資家の資金を預かって運用しているのだから、その程度の意気込みはあった方が良いだろう。でも、株式などの価格変動商品を投資対象にしながら、いつ、どの時点で投資しても、ほぼ確実に一定のリターンが得られることを期待するのは、やめた方が良い。
いつ、どの時点で投資しても、一定のリターン確保を目指すことを「絶対リターン」という。実は、絶対リターンの実現を標榜して運用される投資信託があるのも事実だ。
なかでも代表的なものが、売り買い両建てのポートフォリオで運用される「ロング・ショートファンド」あるいは「マーケット・ニュートラルファンド」だ。
たとえば、マーケット・ニュートラルファンドの場合、基本的な売りと買いの比率は50%対50%というように、両者の比率を同じにする。現物株式を組み入れる一方、株価指数先物取引などを売りたてることにより、価格変動リスクをヘッジするというものだ。
基本的に株価の動きは、企業の個別要因だけでなく、マーケット全体の値動きに引きずられる側面もある。株価指数先物取引を、組み入れた現物株式と同比率で売ることの意味は、現物株式がマーケット全体の下落に引きずられて値下がりするリスクを相殺するところにある。つまり、純粋に個別要因を源泉とするリターンのみを取り出す。
このロジックを額面どおりに受け止めれば、いかにも絶対リターンが実現しそうだ。
しかし、実際のリターンはどうかというと、これがなかなか厳しいというのが現実だ。たとえば2006年11月末時点において過去1年間騰落率をチェックすると、日経平均株価が9.42%の上昇だったのに対して、基準価額の騰落率がマイナスになったファンドがかなりの部分を占めている。
これは結局のところ、ファンドに組み入れられた現物株式の選択に失敗したとしか、言いようが無い。
株価が上昇すれば、確かに株価指数先物取引を売り建てた部分には、損失が生じる。しかし、ポートフォリオに組み入れられた現物株式は、そもそも市場平均よりも高い付加価値が得られるという前提で銘柄選択をしているのだから、両者の投資比率が50%ずつであれば、多少なりともプラスが出るはずだ。それが、11%超もマイナスになったということは、それだけ良い銘柄を選べなかった証左でもある。
両建てで運用している限り、マーケットの上昇局面において、ファンドのパフォーマンスがベンチマークに追いつけないのは仕方がない。しかし、ブルマーケットで、マイナスリターンしか出せないというのでは、お話にならない。
絶対リターンという言葉が独り歩きしているが、実体に目を向ければ、このように厳しい現実があることを、頭に入れておくといいだろう。
(金融ジャーナリスト:鈴木雅光)
こうした対ベンチマークとの相対評価においては、たとえファンドの基準価額が下落していたとしても、ベンチマークの下落率よりも小さく押えられれば、それは評価の対象になる。
ただ、一部から「ファンドの購入者は相対評価を望んでいない。いくら利益が上がってナンボだろう」という声が上がったのも事実だ。もちろん、大勢の個人投資家の資金を預かって運用しているのだから、その程度の意気込みはあった方が良いだろう。でも、株式などの価格変動商品を投資対象にしながら、いつ、どの時点で投資しても、ほぼ確実に一定のリターンが得られることを期待するのは、やめた方が良い。
いつ、どの時点で投資しても、一定のリターン確保を目指すことを「絶対リターン」という。実は、絶対リターンの実現を標榜して運用される投資信託があるのも事実だ。
なかでも代表的なものが、売り買い両建てのポートフォリオで運用される「ロング・ショートファンド」あるいは「マーケット・ニュートラルファンド」だ。
たとえば、マーケット・ニュートラルファンドの場合、基本的な売りと買いの比率は50%対50%というように、両者の比率を同じにする。現物株式を組み入れる一方、株価指数先物取引などを売りたてることにより、価格変動リスクをヘッジするというものだ。
基本的に株価の動きは、企業の個別要因だけでなく、マーケット全体の値動きに引きずられる側面もある。株価指数先物取引を、組み入れた現物株式と同比率で売ることの意味は、現物株式がマーケット全体の下落に引きずられて値下がりするリスクを相殺するところにある。つまり、純粋に個別要因を源泉とするリターンのみを取り出す。
このロジックを額面どおりに受け止めれば、いかにも絶対リターンが実現しそうだ。
しかし、実際のリターンはどうかというと、これがなかなか厳しいというのが現実だ。たとえば2006年11月末時点において過去1年間騰落率をチェックすると、日経平均株価が9.42%の上昇だったのに対して、基準価額の騰落率がマイナスになったファンドがかなりの部分を占めている。
これは結局のところ、ファンドに組み入れられた現物株式の選択に失敗したとしか、言いようが無い。
株価が上昇すれば、確かに株価指数先物取引を売り建てた部分には、損失が生じる。しかし、ポートフォリオに組み入れられた現物株式は、そもそも市場平均よりも高い付加価値が得られるという前提で銘柄選択をしているのだから、両者の投資比率が50%ずつであれば、多少なりともプラスが出るはずだ。それが、11%超もマイナスになったということは、それだけ良い銘柄を選べなかった証左でもある。
両建てで運用している限り、マーケットの上昇局面において、ファンドのパフォーマンスがベンチマークに追いつけないのは仕方がない。しかし、ブルマーケットで、マイナスリターンしか出せないというのでは、お話にならない。
絶対リターンという言葉が独り歩きしているが、実体に目を向ければ、このように厳しい現実があることを、頭に入れておくといいだろう。
(金融ジャーナリスト:鈴木雅光)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年01月11日 10時38分03秒
[投資信託] カテゴリの最新記事
-
クラスB受益証券の落とし穴 2007年10月26日
-
金商法の施行で投資信託はどう変わるか 2007年10月04日
-
バイオバブルの終焉:ジーエヌアイの初値… 2007年09月27日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
カレンダー
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年07月
コメント新着
コメントに書き込みはありません。
© Rakuten Group, Inc.