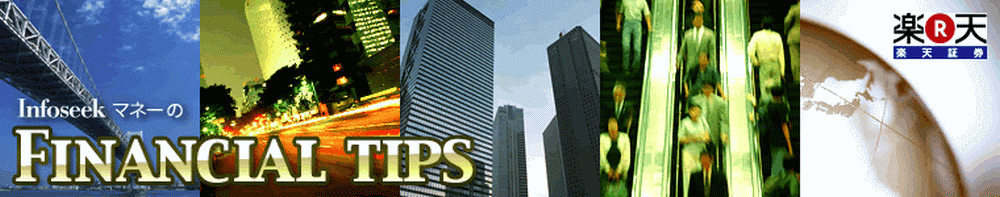カテゴリ: 投資教育
■投資教育の必要性
普通の消費財、例えば食料品やPCなどを購入するためには、賞味期限表示やスペックの意味するところの理解が必要なように、投資にあたっては投資のリスクの理解が必要になります。商品知識を身につけるための消費者教育(=投資家教育)の必要性が、ますます強く感じられるようになってきました。
■販売する側による教育の限界
現状では、一般の個人投資家向けには、銀行、証券や郵政公社などの販売業者が自ら、商品知識の教育にあたることが多いのですが、当然のことながら自らの商品の宣伝も兼ねていますので、商品に対する批判的な視点が養われないことが一番の問題です。その典型的な例は、毎月分配型の投資信託でしょう。投資家にとって明らかに不利だと思われる、この形の投資信託が、販売会社が売りやすいからという理由から隆盛を極めています。投資家の知識不足からくる錯覚を、運用会社や販売会社の販売上の都合に利用されている例です。
■学校での投資教育の必要性
ここで、中立的で公的な立場から、特に学校の現場での早期投資教育の必要性は明らかなのですが、現実には学習指導要領の合間をぬって、金融や投資の教育の十分な時間を採るのには困難な状況があるようです。
東京証券取引所などを中心とした NPO連絡協議会 が、一昨年の段階で中学校・高等学校に金融教育に関してアンケートをとっています。それによると、9割が金融教育を必要と回答していますが、実際に実施しているのはその半分程度にとどまるようです。実施のための問題点としては、「時間が取れない」、「教員が学ぶ機会がない」、「適切な教材・指導書がない」などがあげられています。
■カリキュラム:不確実性をどう教えるか
現場では、経済の授業や消費者教育に絡めて、お金の使い方、クレジットカードの扱い方といった知識やルールのレベルから、複利計算の仕方といった数学の簡単な応用を教えることから始めることになりそうです。
中級以上になると、教えるとき一番苦労しそうなのが、株式の価格変動などにともなう不確実性をどう生徒に伝えるかという問題です。価格にとどまらず、企業やビジネスプロジェクトの収益など、経済の様々な局面に「期待外」のことが起こるという不確実性を理解し、それを取り扱う技を身につけることは、投資教育の根幹です。
■株式運用ゲームと適切なサポート
不確実性の具体的な感覚は、教育現場だけで生きてきた先生達には理解が難しいかもしれません。適切な教材とビジネス経験のある人のサポートが必須であると思われます。
東京証券取引所のホームページ には、学校向けの株式運用ゲームが教材として提案されています。一定の仮想所持金をもとに、現実の株式売買と同様に、実際の株価に基づいて模擬売買を行い、あらかじめ設定されたゲーム期間終了時の保有株式の時価と所持金残高の多寡により投資成果を競うものです。
このような方法は、米国などの例でもよく行われているようで、たしかに株式市場価格が変動し、期待通りには価格が変動しないということを体感するには最も良い方法だと思います。
ただ、教育の現場だと十分な時間がとれず、短期の株価変動を体験するだけに終わってしまう可能性もあります。短期の結果に一喜一憂するだけであれば、ラスベガスにいってルーレットを楽しむのと、ゲームとしてはほとんど同じことになります。
短期のトレーディングゲームで一番であった生徒に、天才であると思い込ませないように、また最下位であった生徒に、長期であれば儲かる可能性もあることを的確に指摘する必要があります。学校の先生の補佐として、ビジネスや証券投資の経験のある人のサポートが重要なところです。
(株式アナリスト:杉岡秋美)
普通の消費財、例えば食料品やPCなどを購入するためには、賞味期限表示やスペックの意味するところの理解が必要なように、投資にあたっては投資のリスクの理解が必要になります。商品知識を身につけるための消費者教育(=投資家教育)の必要性が、ますます強く感じられるようになってきました。
■販売する側による教育の限界
現状では、一般の個人投資家向けには、銀行、証券や郵政公社などの販売業者が自ら、商品知識の教育にあたることが多いのですが、当然のことながら自らの商品の宣伝も兼ねていますので、商品に対する批判的な視点が養われないことが一番の問題です。その典型的な例は、毎月分配型の投資信託でしょう。投資家にとって明らかに不利だと思われる、この形の投資信託が、販売会社が売りやすいからという理由から隆盛を極めています。投資家の知識不足からくる錯覚を、運用会社や販売会社の販売上の都合に利用されている例です。
■学校での投資教育の必要性
ここで、中立的で公的な立場から、特に学校の現場での早期投資教育の必要性は明らかなのですが、現実には学習指導要領の合間をぬって、金融や投資の教育の十分な時間を採るのには困難な状況があるようです。
東京証券取引所などを中心とした NPO連絡協議会 が、一昨年の段階で中学校・高等学校に金融教育に関してアンケートをとっています。それによると、9割が金融教育を必要と回答していますが、実際に実施しているのはその半分程度にとどまるようです。実施のための問題点としては、「時間が取れない」、「教員が学ぶ機会がない」、「適切な教材・指導書がない」などがあげられています。
■カリキュラム:不確実性をどう教えるか
現場では、経済の授業や消費者教育に絡めて、お金の使い方、クレジットカードの扱い方といった知識やルールのレベルから、複利計算の仕方といった数学の簡単な応用を教えることから始めることになりそうです。
中級以上になると、教えるとき一番苦労しそうなのが、株式の価格変動などにともなう不確実性をどう生徒に伝えるかという問題です。価格にとどまらず、企業やビジネスプロジェクトの収益など、経済の様々な局面に「期待外」のことが起こるという不確実性を理解し、それを取り扱う技を身につけることは、投資教育の根幹です。
■株式運用ゲームと適切なサポート
不確実性の具体的な感覚は、教育現場だけで生きてきた先生達には理解が難しいかもしれません。適切な教材とビジネス経験のある人のサポートが必須であると思われます。
東京証券取引所のホームページ には、学校向けの株式運用ゲームが教材として提案されています。一定の仮想所持金をもとに、現実の株式売買と同様に、実際の株価に基づいて模擬売買を行い、あらかじめ設定されたゲーム期間終了時の保有株式の時価と所持金残高の多寡により投資成果を競うものです。
このような方法は、米国などの例でもよく行われているようで、たしかに株式市場価格が変動し、期待通りには価格が変動しないということを体感するには最も良い方法だと思います。
ただ、教育の現場だと十分な時間がとれず、短期の株価変動を体験するだけに終わってしまう可能性もあります。短期の結果に一喜一憂するだけであれば、ラスベガスにいってルーレットを楽しむのと、ゲームとしてはほとんど同じことになります。
短期のトレーディングゲームで一番であった生徒に、天才であると思い込ませないように、また最下位であった生徒に、長期であれば儲かる可能性もあることを的確に指摘する必要があります。学校の先生の補佐として、ビジネスや証券投資の経験のある人のサポートが重要なところです。
(株式アナリスト:杉岡秋美)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年02月22日 10時47分20秒
[投資教育] カテゴリの最新記事
-
子どもと一緒に考える“おこづかい” 2007年10月11日
-
インフレリスクと長生きリスク 2006年12月28日
-
体験が一番の近道! ~子どもとお金~ 2006年11月09日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
カレンダー
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年07月
コメント新着
コメントに書き込みはありません。
© Rakuten Group, Inc.