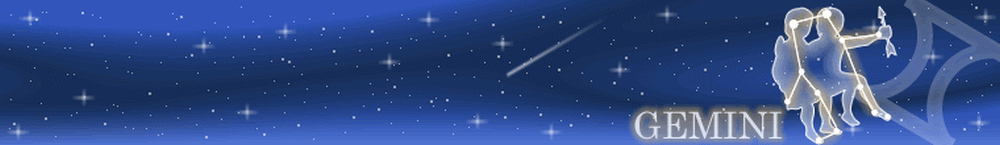「常識」とは 他人との普遍的共通項という事なのかも知れず、常識が豊かという事は 様々な種類の他人と分かち合う事のできる共通項を豊富に用意している人、誰とでもなめらかにつきあっていける人物 という事になります。
そして ひとつのことに偏執的に集中して ほかの事には興味を示さない人は 現代では一般に毛嫌いされる傾向が現れるようになりました。
「共通の話題を探す」立場のほかに「共通の新しい経験を作る」という立場も考えられます。
ひとつの目的にむかって二人以上の人間が協同作業をする場合の事です。
どんな目的であれ 一人ではできない事を何人かで知恵を出し合えば、その作業とその成果が新しい共通項になります。
現代では 都会のマンションでは同じ階の人たちでさえ互いに顔も名前も知らない と言われるほど地域社会の空洞化が進みました。
このような状況のなかで コミュニティ作りが叫ばれ、さまざまな形で運動が展開されるようになっています。
コミュニティの概念は HR の心理学で注目されています。
その理由は 住民同士のインフォーマルな関係が 心の健康の増進に大きな意義も持つことが知られるようになってきたからです。
(1 )日常生活の緊張をときほぐす「息抜き」
(2 )心情的な共感による「励まし」
(3 )適切な行動基準の提示
(4 )適度な距離を持った「ヨコの関係」
これらの点で コミュニティは精神衛生の上で 援助的な機能を持つのです。
夫婦関係、親子関係で様々なひずみが起きる場合があり 夫婦関係、親子関係のひずみは、離婚や家庭内暴力につながることがあります。
また 主として 若い女性では、極度の体重減少や無月経などの症状が出る「思春期やせ症」を起こす場合があります。
これは諸説が有り 思春期やせ症の背景には 第2 次性徴の目立つ身体になりたくないという 成熟拒否、女性性拒否の心理が働いていて 月経停止が必発症状なのだといわれます。
そのような女性には 家庭内で母親に対して反抗と依存のアンビバレントな態度、関係が見られると いいます。
校内暴力、いじめ、登校拒否などが社会問題として取り上げられるようになって久しいですね。
学校での問題行動は 量的増減を云々することよりも、問題行動を生み出す背景や発生のメカニズムの質的変化に焦点をあてる必要があるでしょう。
学校の病理的問題を要約すると 次のようになると言われます。
1. 知的教育への偏重。詰め込み作業
全人格の発達をうながす教育が行われにくいこと。
2. 進学中心の教育体制
就職希望者には場違いな感を与えること。偏差値による序列化。
3. 過度の受験競争により ライバル意識のみが育ち 友情や連帯感が育たない
教師と生徒の間には、評価する者と評価される者の関係のみが強調され 温かい血のかよった関係が育ちにくい。
4. 教師の威信が低下
教師と生徒の関係が希薄化し 学校の管理体制が強化され、多くの禁止事項が押し付けられている。
Comments
 New!
alisa.さん
New!
alisa.さん「風景美術館・日本…
 New!
曲まめ子さん
New!
曲まめ子さん知的障害の男性が児…
 New!
elsa.さん
New!
elsa.さん11月2回目の3連休… New! a-chan8684さん
北海道・道北の旅・… teapottoさん