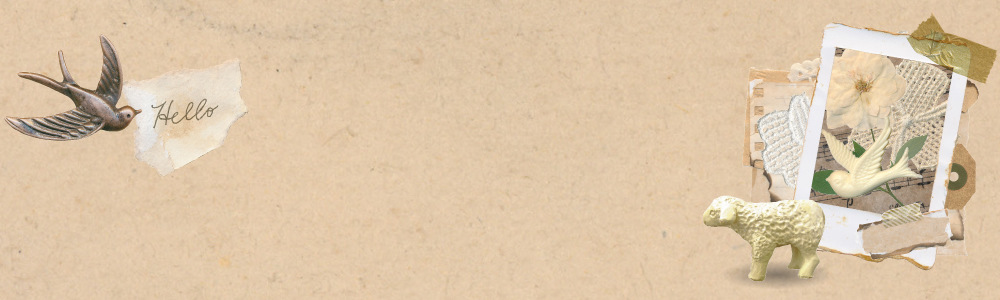全124件 (124件中 1-50件目)
-
楽天も色々変わったね(回顧録的な、何か)
前回の更新から随分長い時間が経った。メインPCは重くてよく固まるNECから、薄くて軽いMac Bookへ。通信状況も格段に進歩した(インターネット老人会か!)。楽天から離れていた時間、mixi→Twitterへ移行してた。mixi、コミュニティ機能は便利だったし、美術展等のレビューにも良い反応がもらえたり、楽しかったな(アクティブユーザーが少なくなっているようだけど)。過去ログの整理をしていたら、美術や音楽、映画(DVD)のレビューが多く、基本的に私のツボは変わってないことに気付かされる。アフィリや買い物レビューは・・・決して裕福ではなかった子供時代の反動から買い物依存気味だったけど、価格に合った「良い物」の価値を知り「自分の本当に好きな物しかいらない」と、自分の中に軸ができ始めた頃から買い物の頻度も変わった。また転属等もあり、レビューする時間も取れなくなったのが遠かった真相。でも、売り上げなりなんなりで反応があるのは楽しかったな。少し前にRoomに登録した。まだあまり使い方がわからないのだけど、楽天でもこんな素敵なものがあるんだ(失礼)と再発見。
2020.05.19
-
生で「戦メリ」聴いちゃったよ!~坂本龍一:PLAYING THE PIANO/05~
と言うわけで行ってきました!「世界のサカモト」のライヴへ。むかーし、ミュージックビデオでライヴの様子などをちょっと見た事が有りますがやはり、生はスゴイ!!!!昔、緊急入院で聞きそびれたフジコ・へミングのライブのリベンジを、ここでようやく果たせた気がします(違;)この日の岡山は妙に寒かった。とにかく寒いので、毛皮のジャケット(ウサギ)を羽織って、いざ出陣。会場の外の風の冷たさと反比例するような熱気が、もう入り口からしてムンムン。。さらに入り口ではカメラチェックが。私は思いっきりスルー(というか、スタッフに何も言われなかったのだ、何故か。)したけど、何人かはバッグの中をチェックされてました。入り口で捕まった人たち、そんなに怪しそうなナリじゃないのにね。本当に不思議。どういう基準でチェックしてるんだろう・・・?さておき、会場には例によって屋台が建ち関連グッズの販売ブースがあって、まだ何も聴いてない状態なのに、スゴイ大繁盛!今回のツアーグッズをさくっと紹介すると・エコロジーと環境保全を現すリボン型ピンズ(ライブツアーのポスターなどで教授が胸につけてるヤツ。白とグリーンの2色展開)・グリーン燃料カレンダー(購入すると週1回は「グリーン燃料」を使うという約束付き。しかし誰が・誰に対して約束するのかが、何回読んでも理解できなかった;)・布製エコバッグ(買ったその場で、ライブ限定の特製スタンプを押して自分なりにカスタマイズできる。結構売れてた)・雑誌「ソトコト」の、坂本龍一のコメント掲載号・ピアノ版スコア(これはライブ後に完売)・CD各種などなど・・・ライブが始まるまでの間、ピアノの背後に置かれたスクリーンに、貧困についてのキャンペーンのビデオ(これまた有志の有名芸能人多数!教授の他、小雪・松島奈々子・菅野美穂・玉置浩二などなど・・)が流されたり、来年春に発売されるDVDのプロモーションなどが流されて、ボンヤリ見てるだけでも時間が潰せました。そしていよいよ、ライブの開幕。照明が全部落されて、このライブにかかったエネルギー量を示すテロップが流れて(化石燃料換算でどの位使ってるかと言う事を伝えるもの。因みにライブの電力そのものは、全てグリーン発電で賄ってるらしい)、いよいよ教授登場!小さくぺこっとお辞儀をしてから、そそくさとピアノに向う。ピアノと教授がライティングされて、後ろのスクリーンにはCGのアニメーション(黒字に白い直線がリズムに乗って動く、という単調なものが多い)や静止画像(青空の中に薔薇が写ってるものとか、何気ない木のドアとか)などが映写されて、音楽+映像の絡み合いによる不思議なステージでした。(つづく)
2005.12.13
-
「ギュスターヴ・モロー展」に行ってきました!
・・・GW中に行こうか、でも高速は混んでるだろうなぁ。でも、土曜なら少しはマシかも??・・・と迷いながらも午後(午前中は病院に行くかどうか悩んでた)に出発して、行ってきました。島根まで。実はギュスターヴ・モローの展示を観に行くのは2度目。10年前に大回顧展があって、京都まで巡回して来てまして。今回は、その時の展示を「プレイバック」するような感覚でした。岡山を出たときは暑いくらいの陽射しでしたが、鳥取に近くなるにしたがって段々雲行きが怪しく・・・でも、雨にはなりませんでした。なんでも今回の展示は・・・パリのモロー美術館(もともと彼の邸宅兼アトリエ。遺言により、作品と邸宅は国に寄贈され、美術館となった。因みに、初代の館長は愛弟子のルオー。)の改修工事のため、作品のまとまった借用が可能になった、という経緯らしいです。合計172点で構成された展示品の中には、10年前に見た「出現」(踊るサロメと洗礼者ヨハネの首を現したもので、出典は旧約聖書のエピソード)も含まれていました。また、10年前にはお目にかかれなかった、サロメのための何点かの習作や、「エウロパ」「ヘラクレスとヒュドラ」(出典は2点ともギリシャ神話)「一角獣」も見られたので、やっぱり来て良かった~と実感しました。(思っていたよりもデッサンが沢山あったので、製作の背景なんかも想像できて楽しかった)自らの作品の散逸を恐れ、遺言までして作品を自宅の中に閉じ込めたモロー。しかしながら、どういう経緯で収蔵されたのかは謎ですが、上野の国立西洋美術館と倉敷の大原美術館で作品を観ることが出来ます(どちらも小さな作品ですが、上野には「声」倉敷には「雅歌」があります。どちらも素敵です)。鑑賞後。ココの美術館の中のレストランがなかなか美味なので、軽く何か食べていこうかと思いきや、生憎の貸切。しかも中の団体が美術館の雰囲気にそぐわないくらい騒いでたので(エントランスに声響いてるんですよっつ)、楽しむのは結構だけど、せめて場所柄をわきまえて欲しいなぁ・・・と思いつつ、宍道湖を横目にコーヒーをすすったのでありました。時計をふと見ると6時過ぎ。気になってた「真夜中の弥次さん喜多さん」のレイトに間に合うかな?と高速を140Kmで駆け抜けて・・・ナビの「到着予定時刻」とにらめっこしながら、映画館のレイトに10分ほど遅れる事が判った時点で脱力。諦めました(苦笑)でもでも、久しぶりにドキドキしながら全力で走った感じは、それほど悪くは無かったかも。高速を突っ走った後、岡山市内からは普通に国道を走って帰る。帰宅したのは10時半。丁度「オールイン」に間に合う時間だったので、お風呂に入ってお肌のお手入れをしながら「オールイン」を視聴。あらすじを知ってるんだけど、結局DVDに撮って、暇があれば見られるようにしてるという状態。(実は・・・ビョン様ファンなのです;)そして、その後。お土産に購入したミュージアムグッズを見て余韻に浸るのでした。「ギュスターヴ・モロー展」会期:2005年3月19日~5月22日(日)場所:島根県立美術館(※3時間まで無料の専用駐車場あり)今後のギャラリートーク日程:5月15日(日)5月22日(日)(※担当学芸員による作品解説。両日とも14時~)開館時間:10時~日没後30分後(※展示室への入場は日没時間まで)
2005.05.07
-
「王は踊る」+「ダロウェイ夫人」+オマケ
先日、薦めて頂いた「王は踊る('00、ベルギー・仏・独)」と個人的に鑑賞予定だった「ダロウェイ夫人('97、英・蘭)」を観ました。「オルランド」→作者:ヴァージニア・ウルフ→「ダロウェイ夫人」と繋がって、今回「ダロウェイ夫人」を観たわけですが・・・。「オルランド」ほど、劇的・波乱万丈ではなく、淡々と描かれています。平凡な下院議員の婦人となった女性が、ふと自分の青春時代を振り返りながら「自分の人生はコレで良かったの?」と自分自身へ問い掛ける。人間が、生きる時間を重ねれば自然発生的に現れる疑問。その問いに対しての答えは、決して明快ではない。けれど、自分の辿ってきたものを承認する作業を重ねて、認めなければ人は生きていけないのかもしれない。まー、そんな感じです。それから「王は踊る」。コレ、「カストラート」と同じ監督さんだったんですよね!なので、時代考証もしっかりしてて安心して観ていられました(衣装も豪華!)実は・・・この作品を観る数週間前、実際にルイ14世が踊ったというバレエの演目をTV(NHK)で観たんですね(すっごい、偶然!!)。彼は歴史上でも「ロア・ソレイユ(=太陽王)」と称えられ、若さと太陽を象徴するアポロンを特に好んでいたとか。その為、アポロンに捧げるバレエを作らせて自ら上演していたと言うのです。なので、TVで再現されてたバレエの衣装も、アチコチに太陽が描かれていて・・・しかも金ピカ(一歩間違えると、悪趣味そのもの)!でも、そんな悪趣味(苦笑)なルイも、バレエの発展には貢献したそうです。バレエの基本ポジションや、基礎的なテクニックはこの時代に確立されたのだとか。実際、バレエ音楽のスコア(楽譜)だけでなく、脚の位置や動かし方を「動線」で描いた、バレエの足取りの楽譜(他に言葉が思いつかないの;苦)が、キチンと残されてるため、当時の踊りを再現する事が可能なのだと、再現した舞踏手の方が言われていました。劇中で、ルイが踊るシーンでは「上半身裸で金粉」らしきものが塗られていて・・・ちょっと引きました(汗)が、踊りのシーンは最近バレエにハマってるおかげで、かなり楽しめました。ルイ14世に、片思いな宮廷音楽家リュリ。「ソドミー(男色家)は嫌いだ!」と公衆の面前で罵倒されながらも、一途に思いつづける姿が、ちょっと痛い感じでした(リュリは男色家という設定)。バレエお好きな方、または「カストラート」を御覧になって、何かしらの感銘を受けた方にオススメ。◎オマケ◎丁度「王は踊る」を観終わった後、TVつけっぱなしにしてると、偶然古典バレエをやってたので、演目は何かな~?と思って観てたら、踊っているプリマの背中に小さな羽根が見えて・・・かねてから観たいと思ってた「ラ・シルフィード」だとわかりました!途中からとはいえ、なんという偶然・・ラッキー☆でした。パリ・オペラ座バレエ団の公演でしたが、流石に素晴らしかったです・・・。ソロ、コールド(群舞)、コーダ。どれ1つとっても、「非の打ち所が無い」とはこの事かもね。いつか生で観たいです♪
2005.03.06
-
Yoshitomo NARA ~From the Depth of My Drawer~
ということで、奈良美智展(@米子市美術館)に行って参りました!今回は、奈良氏が自ら作品を選び構成する展覧会ということで、小さな美術館ながら、2階の空気がもう既に「奈良ワールド」。奈良といえば・・・カワイイっ!っていうのには少し違うテイストのある、「ひねた目の子供の絵」というイメージが先行しますが、今回の展示はそういう「いかにも」なものだけでなく、もっと静かなインパクトを持った作品も多かったように思います。会場も壁は白一色。壁は所々に節穴(ワザと開けてあるのか?)のある板を使い、空間を仕切ったり、小部屋を作ってみたり。空間構成にも遊びが満載。ドールハウスを歩いているみたいな感じ、とでもいうか。そして、小部屋に入るとまた部屋の中や、部屋の壁の中に作品が展示してあって。また、壁の隙間の行き止まりのところに写真作品が展示されていたり(注意してみてないと、見落とす可能性大!)更には小部屋の窓の、その又向こう側の窓に他の作品が見えるよう配置してあったりと、遊びゴコロも有り。そんなわけで、目につく節穴を覗きまくった私(←勿論こんな「見るからに怪しい客」は私だけです)。展示作品は、オブジェ、アクリル画、水彩、デッサン数十点(テクストがドイツ語のものもあり。当然読めませんが;「アムロ(歌手の)」と書かれたスケッチもあったり)。ですが、やはり一番良かったのは「Fountain of Life」。会場の中に作られた小さな家の中に配置された、私の身長よりも少し高いオブジェ。ソーサーに乗ったカップの中には、瞳を閉じた子供の頭部。その閉じた瞳からは、細い筋を描きながら水が流れていきます。かすかな水音を立てて、カップに流れ落ちた水はモーターでくみ上げられ、再び子供の中へ帰っていきます。オブジェの中を流れる水は、永遠の循環さえ感じさせます。観ていて、時間を忘れる。そういう作品でした。(ずっと観ていたい、という「(目の)快楽的作品」とは又違った趣があります。こういう作品に会うのって、久しぶりかも・・・)。米子市美術館での会期は3月21日(月・祝)まで。この展示は、吉井酒造煉瓦倉庫・弘前(青森)に巡回します(会期:4月16日~5月22日)。お近くの方は是非!それから、極秘(苦笑)に進めていた50000hitプレですが、今回は奈良さんグッズ(展示のお土産)+αを予定しております。なお、基本的にBBSに申告宜しくです。こちらも詳細は後日。
2005.03.05
-
レニングラード国立バレエ、観てきました♪
そんなわけで、1階席10列目左端の席をGETして、事前に予習(教材は、山岸漫画「アラベスク」笑)までして。今日の演目は「白鳥の湖」。今回の日本公演は主に「白鳥の湖」だったみたいですが、「ドン・キホーテ」「海賊」「ジゼル」「眠りの森の美女」「くるみ割り人形」なども上演されたみたいです。とにかく凄かったです。ゲスト・ソリストとして、草刈民代(「Shall We Dance?」でダンサ-役を演じ、後に周防監督と結婚しちゃった、世界的プリマ)や、あのルジマトフ(この世界屈指のプリンシパル)が舞ったステージもあったらしいです。ビックネームのソリストの舞にお目にかかることはなかったですが、やっぱり凄い。滅多に涙腺が緩まない私が、「半泣き」してましたから(恥)。判りやすいあらすじ(ネタバレありです)。1幕ジークフリート王子の誕生日。村の若い娘や青年たちも歌い踊り、王子のお祝いをしている。祝宴の終わった夜。王子は白鳥狩りに誘われて森へ。悪魔ロットバルトに追い掛け回される白鳥達は、夜の帳の中で次々に乙女の姿に変わっていく。何事かと見ている王子の前にひときわ美しい乙女が現れ、一目で王子は心を奪われる。その乙女、王女オデットは、魔法で姿を変えられた哀しい身の上話を語って聞かせる。献身的な深い愛がこそが、ロットバルトの邪悪な力を退ける事ができることも。そして、王子はオデットに変わらぬ愛の誓いを立てて、別れる。2幕王子の花嫁を選ぶために舞踏会が催される。王妃は花嫁候補を連れてくるが、王子は首を縦に振らない。其処に何故かロットバルト登場。しかも傍らにはオデットそっくりの乙女を伴って。しかし、その乙女オディールをオデットと取り違え、王妃に歩み寄り「彼女を花嫁に」と申し出る。あまりの事態に王妃は卒倒。企みが巧く運び、満足げな表情のロットバルト。そして、王子はその時初めて欺かれた事を知る。3幕白鳥の乙女たちはオデットの帰りを待ちわびているが、オデットから、誓いが裏切られた事を聞き、共に嘆き悲しむ。王子も駆けつけるが、誓いが破られた以上はオデットを救う事は出来ない。再びロットバルトが現れて高らかに勝どきを上げる。湖は朝を迎え・・・王子と王女の愛と自己犠牲により、乙女たちの呪いが解ける。みどころ(独断)・1幕の1場、小椅子やメイポールまがいのものを使った若い男女の郡舞。この小道具を使った演出は珍しい。バレエ団によっては、この演出をカットしてるところもあるそうな。・1幕2場。此処は見所満載。トロックスで必ず演じられる「4羽の白鳥の踊り」も2場の見所の1つ。乙女たちの2人ないし3人での踊り(パ・ド・トロワって言うんですかね?)もいいし、主役2人のパ・ド・ドゥ(で、あってます?マダム?)に、ハープと弦の混じった哀しげな旋律には、否が応でも胸が締め付けられます。(哀しげに寄り添う所なんて半泣きでした)・2幕花嫁候補の踊りもさることながら、他の外国の踊りも良いです。お国によって衣装がカラフルで、曲調も違うので面白い。最大の見せ場は、オディールの32回転(グラン・フェッテ・アン・トールナンというらしい)。3幕王子と王女のパ・ド・ドゥ。これに尽きますね。今回も生オケで、音響も良かったです。ただ、楽器にハープが入るために「打楽器サマご一行」がオケ・ボックスから追い出される羽目に(これってワザとなんですかね?)。1階席のオケ・ボックスの傍らで職人の如くシンバルを鳴らしたり、タンバリンを鳴らしたり・・・お疲れ様でした;これはパンフからのウケウリなのだけれど、レニングラードの「白鳥の湖」は原典に忠実な演出がなされてるとか。例えば、1幕の小道具を使った群舞や、2幕の各国の踊りの舞踏手たちは、ヒールのある靴を履いて躍っている、とか。初演から現在にいたるに、演出も色々といじくられた経緯があるらしく、最後のオチも原典とは異なる「ハッピーエンド版」が存在するらしい。これはこれで観てみたい気もするけれど。。。それにしても、皆様やはり身体そのものが芸術品。舞踏してる方というのは皆姿勢がよく、ぱりっとしてますが、バレエはラインの美しさ(止めの動作、踊りの動作全てが美しく見えるように)にごまかしが効かない分だけ、厳しく節制されてるとのこと。そのうえ、爪先だけで数10秒も静止したり、跳躍・回転(男性の場合これに女性を持ち上げる「リフト」が加わる)など、かなり筋肉がシッカリしていないと出来ないのです。例えば、トゥ・シューズで跳躍しますよね。ソリストクラスになると、着地の時に「音がしない」んです。(群舞で固めてた方の中で、ちょっと靴音がしましたが。ちょうどスリッパかミュールで歩いてるようなパタパタした音がする)着地のその瞬間まで脚の力を抜いていないからこそできるのだそうです。これだけでも、すごいと思いません?あと個人的感想。悪魔ロットバルト役の方が妙にカッコ良かったです(かなり萌えました)。「カストラート」のファリネッリみたいな感じの方。最初の1幕1場の登場シーンも、舞台中央から舞台左端に向って大きめの跳躍で、「しゅたっつ!」とポーズ決めて着地ですから。もう、この時点で王子役の方は目に入りませんでした(ゴメンナサイ;でも、王子は、2場にならないと本格的なソロを躍らないのであんまり目立ちません)。プロフィールを見ると「マラト・シェミウノフ:身長195cm、かかとからウエストまでが124cmという。」面立ちも好みだったけれど、その「長さ」にはビックリ・・・。124cmって、一体どうよ?ジーンズは特注なんだろうか?とか余計な妄想を膨らませてました(苦笑)しかもサーヴィス精神もあり、幕が閉じた後も幕間から例のジュッテで愛想を振り撒き、主役2人を引っ張り出して拍手に応えてくれました(しかも3回も!)彼は「白鳥の湖」ではロットバルトをやってますが「ドン・キホーテ」ではタイトルロールもこなす実力派。いつか、彼の演じるドン・キホーテも観てみたいものです。あ、ルジマトフの「海賊」と「ボレロ」もね♪←DVD出てますがやっぱ、生で観たい!!しかも射程距離で(・・・何の?)。最後に今回のメイン3人のキャストをご紹介。オデット/オディール:オリガ・ステパノワ(98年、入団したばかりでオデット/オディールに抜擢された期待のプリマ)ジークフリート王子:アルチョム・プハチョフ(80年生まれ。18歳で入団したばかりでジークフリートに抜擢された。テクニックが確かな期待の若手)ロットバルト:マラト・シェミウノフ(長身、手足長ーい!化粧も映える☆)夏にはトロックスの公演が決まったので(これまたラッキーな事にウィークエンドの夕方☆)、観に行こうか考え中。トロックスで一人だけ、日本人で頑張ってるユリカ(勿論芸名)は元気かなぁ。。。
2005.02.05
-
古いといわれようとも・・・「カストラート」+「オルランド」
昨日紹介した新作DVDに続き、今度は旧作のご紹介です。先ずは「カストラート」('94、伊・仏)コレはDVDで、特典映像が見られなかったのがちょっと残念でしたが(普通は、メイキングとかつきますよね?)、お話は楽しめました。18世紀。去勢された男性歌手、カストラート(でも去勢されてるので、声変わりしない。高い声のまんま歌える)となった、ファリネッリ。その声の美しさのため、時代の寵児となった、彼の苦悩と愛がお話の核となっています。物語の終盤で、ヘンデルの「涙あふるる」が歌われますが、コレがまた本当に美しい・・・。このシーンだけでも見る価値はあります(自称:クラシック・ヲタは見るべし!)。それから、「オルランド」('92、英・仏・露・伊・蘭)。ヴァージニア・ウルフ原作の壮大な物語をサリー・ポッター(ハリポタ、ではない。)が映画化した作品です。お話はエリザベス1世の統治する英国。青年貴族オルランドは女王の寵愛を受け、「決して老いてはならない」という条件のもと、女王から莫大な財産を受け取ります。・・・まぁ、ここまではよくある話。しかし、彼は女性遍歴を重ね、詩に耽り、大使として外国へ派遣されたりと・・・実に100年の時を重ねるが全く年を取らない。しかも、6日の昏睡から目覚めた後に、彼は「彼女」になっていたという「ありえない状態」。今度は女性として男性遍歴を重ねる。しかし、月日は流れ、「女性になった」ため、女性は財産の相続権がない為、女王から賜った屋敷も手放さなければならなくなるが・・・。原作はまだ読んでないですが、バージニア・ウルフと親密な関係にあった男爵夫人(同性愛の相手とも言われる)が「女性であるがゆえに、財産を相続できなかった」と言うエピソードは、映画にも登場しますが、実話だそうで。この時代、女性に相続権がなかったのです。。。映画は原作と少し違う、という指摘もありますが、壮大なファンタジーとして「400年も老いることなく生きるってどんな感じかな?」「途中で性別が変わったら、自分ならどうするだろう?」「社会が作った『ジェンダー』も生物学的な『セックス』も、もっと境目の曖昧なものなのかも・・・」と、不思議な気分にいざなってくれる作品です。400年という長い月日を彩る賢覧豪華な衣装も素晴らしい。メイキングでも語られてますが、「衣装さん、ご苦労様でした」の一言。そして監督のサリー・ポッター。彼女は非常に多才な方で、監督業のほかに作曲・作詞、それに歌手としても活躍しています。私が彼女を知ったのは、ヨーヨー・マのアルバムで、歌手としての彼女。これだけだと「?」なので、ちょっと説明すると、オルランドを撮った後、映画「タンゴ・レッスン」で自ら監督・出演し、ピアソラ(「リベルタンゴ」の作曲者。「リベルタンゴ」は、サントリーローヤル12年のCMで一躍有名に)の曲に彼女が歌詞をつけて歌ってる「I AM YOU」が、ヨーヨー・マのベストアルバムに収められてて、ヨーヨーのアルバムを聞くうち、彼女の不思議な歌詞と歌声に虜になって、彼女って何者?と思ったのがキッカケ。これがサリー・ポッター作品との出会い。「オルランド」という作品自体、気になっていたものの1つでは有ったのですが、サリーポッター繋がり、でしたね。「オルランド」をキッカケに是非「タンゴ・レッスン」「耳に残るは君の声」もチェックしたいところです。(特に「タンゴ・レッスン」は、1930年代からの歴史的な音源もあるとのことで興味深いですね)そんな今日。久しぶりに女性4人でランチに行きました。いつものエステの会社が主催する、ダイエット講座(隣の会場では結婚式やってました;)に行って、サンプルのサプリを飲んだ後、食べ放題・・・。講座行った意味無いじゃん(爆笑)。あ、サプリの「お土産」があったから、油断したというのもあり(核爆)
2005.01.30
-
最近見たタイトル。
ちょっとブログをお休みしてましたが、その間も毎日のように何かのDVDなり、ビデオなり見てる日々でしたな。因みに先日の日記で「字幕が出なかった・・・」と書いていたのは、「カストラート」のDVD。お店の人に「字幕でないんですー、ついでにメニュー画面も。他の作品はこんな事無かったのにー」と言ってみたら、ビデオ版を無料で1週間貸してもらえた。らっきー☆そんなわけでここ2週間で見たモノ「シルミド」「華氏911」「真珠の耳飾りの少女」「カストラート」「オルランド」「攻殻機動隊S.A.C.(全26話)」上から3つは新作棚のところにあるので、チェックしやすいでしょう。3つとも「当たり!」でしたね。「華氏911」は大統領就任式の後だったので、それなりに感慨もありましたね、うん(今回アポ入れてたのはブリトニーくらいか?少なくとも他の皆様については、例によってアポ無し。多分)。BBSへのお返事にも書きましたが「ボウリング・フォー・コロンバイン」を見てからの方が、ブッシュ氏についてより理解が深まります(笑)「ラズベリー賞」の行方も気になりますね。ブッシュ氏とライズ女史の受賞は確定ですかね。余談ですが、久しぶりに「吹き替え」で観ました;(目に飛び込んでくる情報が多すぎるんで;)「シルミド」は「ブラザー・フッド」にちょっとおされ気味ですが、イイ仕上がりでしたね。ちゃんと泣き所を押えてありました。内容は、金正日暗殺部隊にまつわる、ノンフィクション。他にレビュー書いてた方が「『男塾』みたい」とコメントしてましたが、訓練の場面はまさに「男塾」でしたね。熱き漢(おとこ)達のドラマを観たい方は是非。「オールイン」でイ・ビョンホンと共演してた俳優さんが、ここでもイイ上官役を演じてます。「真珠の耳飾りの少女」は、去年ミニシアターで細々と上映されてましたが、これもいい作品でした。これは、劇場で観たかったなーと感じましたね。フェルメールの一枚の絵にまつわるフィクション。フェルメール自身謎の多い画家なので、まぁ、こういうのも有りだな、と。因みに本物の「真珠の耳飾りの少女」についても、諸説あります。(なぜ、当時の流行でもないのにターバンを巻いているのか?とか。絵画の中の人物の服装は、当時の流行が反映されている場合が多い為。)ヒロイン、グリート役の女優さんの美しさに、うっとり。ピアスの穴を開けるシーンに、エロティシズムを感じてしまったのは私だけじゃない筈。
2005.01.28
-
Sopranista~Tomotaka Okamoto~
数年前、映画「もののけ姫」で、米良氏の「カウンターテナー(通常のテノールを越える高音域)」が話題になりました。その後、その「カウンターテナー」を越える高音域である「ソプラニスタ」として注目されている、岡本知高氏のデビューアルバムを聞きました。彼の声は、幼少期の高い声を残したまま「声変わり」をしないで成人した男の声。世界にも数人しか存在しないといわれる、稀有な存在なのです。その昔・・・例えば映画「カストラート」の舞台となる時代、「天使の歌声を保つために去勢した男性歌手」が活躍していました(映画の中の歌声はソプラノ歌手の歌声を吹き替えしているとのことですが)。確かに昔は「人工的に」高い声を保ち、歌いつづける男性も存在しました。でも、それも昔の事。歌うためだけの身体を作るという事は、歌えなくなればそこでオシマイ。普通に家庭を持つ事も出来ないし、勿論去勢してるから自分の子供を持つ事も不可能。。。例え栄光を手に入れたとしても、それまでの人生って、一体・・・と、ついつい考え込んでしまうのです。話が、カストラート寄りになったので、ちょっと軌道修正。「ソプラニスタ」は女性が歌う「ソプラノ」と違い、男性ならではの肺活量により、・声量が豊かである事・振り幅が利く事という、利点があります。岡本氏もまさにそんな感じ。少し前にもTVで、北野たけし氏と話しているのを観ました。とても気さくな感じの普通の男性。話してる声はそんなに違和感はなく、ただ低い声でないことは確か、という感じです。もともと、楽器(確かサックスか何か金管楽器だったハズ;失念;;)をやっていたため、音楽との関わりは深く・長かった。しかしある日、彼を指導していた方がたまたま彼の「声」に気付き、声で勝負してみるように勧めたのが、ソプラニスタとして開眼するキッカケだったとか。今日聞いた、彼のデビューアルバム「Sopranista」(2枚組 ビクターより販売)は、「ブラヴォー!」の一言につきます。先日、マリア・カラス(ソプラノ)のベストアルバム(ベスト、といいつつも声が出ていない、絶頂期を過ぎたような録音も含む)を聞いたばかりなんですが、同じ曲が入っているので聞き比べてみると、明らかに違う。先ずやはり単純に声が美しい、ということ。全く無理が無く、聞く側にストレスを感じさせない、透明さに加えて温かさがある。特に、「トスカ」の「歌に生き、恋に生き」(歌劇「トスカ」から)の「神よ、何故です?」という歌詞の部分に本当に泣きそうになりました。(主人公の歌姫が、反逆罪にされた恋人を救うために悪辣な警視総監と対峙するシーンで、恋人を助けたければ貞操をよこせと冷笑されたあと、絶望と苦しみを歌うアリア。サビの部分は某ジュエリーのCMに使用されました~)逆に、「トゥーランドット」(同名のオペラより)の「誰も寝てはならぬ」(錦織健氏が某ネスカフェのCMで歌ってたアレ、です)は、もともとテノール用、つまり男性用に書かれたアリアなのですが・・・まるっきりソプラノの声で歌ってるんです。なんだか「すわ!宝塚?!」という感じで、なんだかとても新鮮でした(そもそもソプラノ歌手が歌う事事体「有りえない」ので)。先日のブログにも書いたけれど、マリア・カラスの声は「努力で勝ち取った高音域」なので、どこかしら無理がある。が、それを独特の迫力でカバーしているがゆえに、ドラマティック。彼女も彼女でやはり絶頂期の歌声は素晴らしいのですが、声の美しさでは断然「彼」の方がイイ!と感じられます(聞き比べたから特にそう感じてしまうのかも)。アルバムは、TV出演した時に歌っていた「アレルヤ(モーツァルト、K165から)もちゃんと入っていて、他にアリアの名曲を収めており、聞き所は多いです。因みに1枚目がクラシックのパートになっています。2枚目は「さくら」(直太郎君の方ね)や「少年時代」(陽水氏の)など、日本でもおなじみのナンバーを集めた、日本の歌のパートになっています。昔の歌もあり、「懐かしい~」と思う方もいらっしゃるかもしれません。「オペラは苦手・・・言葉わかんないし;」という方にもオススメ。(←実は私。字幕や歌詞カードが頼りです 爆)とにかく、世界に誇る貴重な「ソプラニスタ」の歌声を是非!お友達や聞かせてみて「これ、男のヒトの声だよ~」とバラして、ビックリさせるも良し。とにかく美声に酔うも良し。
2005.01.19
-
「パッション」VS「スティグマータ」の巻。
年末に観た「パッション」に続き、「スティグマータ」をようやく観る事が出来ました。(探してたんですよ・・・フフ)↓↓以下、一部(?)ネタバレ有りですので、ご注意。。。↓↓「パッション」については昨年日本で公開され、コレ観ておすぎは泣いたとか、製作はメル・ギブソンが私費でやっちゃったとか、色々と話題性の多い作品だったので、記憶にも新しいかと。人物の描写や言葉(イエス達はアラム語、ローマ人はラテン語)にこだわって書かれるなど、凝ったつくりであったなぁという感じです。神の子ではなく、人間としてのイエスの苦しみ(例えば、ゲッセマネでの苦悩する姿など)であったり、人間持っている残酷さや悪意(囚われたイエスを鞭打ってる刑吏の人間が段々残酷さを増していくシーン等に象徴される)などなど、見所はそこそこあります。この映画の中に「パッション」があるとすれば、それはイエス本人の中(信念にたいする情熱)ともう1つ。母マリアの中にもあると思うのです。普通、絵画の中の磔刑のシーンでは、マリアは失神して女弟子達に支えられていたり、目を背けています(しかも妙に若い。イエスは30の半ばは過ぎてるはずなのに)。が、この映画の中でのマリアは、息子の最期を決して目を背けることなく見届けようとします。涙ながらにも、最期まで見届けるその胸中には、「自分の息子は間違っていない」とか「息子は罪に死ぬのではない」とかそういう強い「信念」があったのではないか?と。そんなわけで、私は、どちらかといえばマリアの姿に「パッション」を感じたのでありました。かなり時代考証も頑張ったはずのこの作品、惜しい!と思える点が1点。それは「磔刑のやり方」なんですね。「スティグマータ」はその点いいところまで行ってましたが、釘を打ち付ける位置は掌ではなく、手首の骨の隙間(橈骨と尺骨の間)に打ち付けていました。でなければ、上半身の重さに耐え兼ねて掌が裂けてしまう(・・・)為だったのだそうです。そして、足は足の甲から足の裏に向って・・・でなく、丁度十字架の柱になる部分に、踵の骨を横方向から打ち付けて、釘の先は体と十字架が離れないように曲げていたとか。そうして、不自然な格好でぶら下げられてるうちに、その姿勢のため、肋骨が折れて呼吸困難に陥り・・・ある程度のところで、受刑者の苦しみを早く和らげるために脛の骨を折って衰弱が早く進むように工夫(?)していたといわれています。これらは実際、近代になって磔刑になったローマ人の骨を解剖学的に研究して得られた事実(実は私も数年前に知ったトピック;)であるので、まぁ、そこまで詳しく突っ込む必要があるのかどうか。(私、突っ込みすぎ?)しかし、史実とは違っていても、昔からの絵画や彫刻のビジュアルの方が、やっぱり視聴する側としては安心するのでしょうかね・・・。んで、対するは「スティグマータ('99 米)」。引き合いに持ってくるのはどうかと思いつつ、これも扱ってる素材はキリスト教だからいーや♪というノリで書いてます。気になるあらすじは・・・ブラジルの小さな町の教会のマリア像が、その教会の神父の死後、血涙を流しているという噂を聞いたヴァチカンは、奇跡を専門に調査する部門からアンドリュー神父を派遣する。しかし、調査は像を持ち帰らない事には出来ないという規定と住民の猛反対のため、調査は断念せざるをえなかった。その少し後、ピッツバーグで若い女性、フランキーが「聖痕」らしき傷を受けているという噂が再びヴァチカンにもたらされる。再び派遣されたアンドリュー神父は、彼女の傷が本当に「聖痕」であるかどうかを調査するうちに、彼女がトランス状態で話し、壁に書きなぐった「ある言葉」がやがて、「謎の福音書」の存在を指し示していることを知るが・・・。かなり、「痛い映像オンパレード」です。フランキーの手首に「釘を打たれたような傷」から始まり、「鞭打たれた傷」「茨の冠の傷」「足の甲の傷」と次々と傷が現れて、そのタイミングは所構わずで、入浴中・電車の中・街角のカフェetc.という感じで、本人も痛いんだけど、周りの人もパニクりそうなイキオイが有ります。が、後半で明らかになる「謎の言葉」と「謎の福音書」、そしてその解釈をめぐって破門された一人の神父の存在が浮かび上がってきます。このあたりがちょっとサスペンスみたいで面白いかも。少し前に流行った「死海文書の謎」とかそういうのがお好きな方には、結構楽しめます。それからアレ。「エクソシスト・シリーズ」お好きな方にもオススメ(爆)DVDを借りていただくと判るのですが、この映画にはエンディングが2つあります。私は未公開バージョンの方が「聖痕が彼女を聖女に至らしめた」ようで個人的に気に入っています。でも・・・ちょっとつっこんじゃうと、細部が粗いというところが難点。ヴァチカンの人間達がなんで英語で読み書きしてるのかという突っ込みは、まぁ、「製作サイドのお約束」として突っ込みはナシ(苦笑)ただし、劇中では「謎の言葉」として登場する「アラム語」。これが実は古いヘブライ語だったり、聖フランチェスコ(フランキーの名前は彼の名前をもじっているのかも?)が改心したキッカケが、「聖痕現象」だとアンドリュー神父が語るシーンがあるんだけれど、これも嘘。(改心は熱病を患った時に「声を聞いた」というのがキッカケといわれる。聖痕現象は死の2年程前という説が有力)。ついでにもって、「トマスによる福音書」は外典扱い(=正式な福音書として認められていない)だけれど、別に「トップシークレット」とかそういうのではなく、普通に出版されています(爆)たしか、日本じゃ岩波書店から出てたはず。しかも、問題の「アラム語」で書かれていたわけでもなく、古いヘブライ語でもなく、「コプト語」で書かれていた文章だとか。グノーシス派(ヴァチカンから見れば異端派)の流れを汲む文章に、歴史的な価値(聖書として云々ではなく)を当てる学者もいるとかなんとか。コレを観た後で色々調べてみると、「福音書」をめぐる解釈の仕方も様々で、なかなかに興味深かったですね。知識が増えたという感じです(でも、トリビアレヴェル 笑)そんなこんなで、色々突っ込みまくった「スティグマータ」ですが、信仰と教会(=総本山であるヴァチカン)の権威の関連など、歴史的なものを踏まえて観るとそれなりに深いのかもしれない。「教会の権威」「威光」が沢山の人間の血を流しつづけたことも、また真実であるわけだから。・・・で。まぁ、「VS」にしちゃったわけだからどっちかに軍配を上げなければいけない訳ですから。私としては、私費を投じたメル・ギブソンの「情熱」に軍配を☆さぁ、明日はどの作品のレビュー(つか、単なるネタばらし?)、いきましょうかね・・・?
2005.01.16
-
~神よ、もう一度声を下さい~「永遠のマリア・カラス」
昨日の予告どおり、年末年始に見まくったDVD映画レヴュー第一弾は「永遠のマリア・カラス」('02)です。(日本公開は2003年。)オペラや声楽に興味のある方については説明は不要なくらいの、伝説の歌姫、それがマリア・カラス。「ディーヴァ」という言葉は、彼女の為に存在する言葉と言われる・・・。本名、マリア・カロゲロポウロス。ギリシャ移民の子供として1923年12月に生まれる。父親は娘を愛したが、母親は娘に対し冷淡であった。しかし、ある日マリアに音楽の才能を感じた時から、愛情を注ぐようになり、また音楽教育に力を注ぐ。その後両親は離婚し、マリアは母と共にギリシャに渡る。その後、ギリシャで往年の名ソプラノ歌手の指導を受けて見事に才能を開花させ、14歳で歌手としてデビュー。後の終戦後のイタリア公演での成功が、当時のイタリア最高の指揮者セラフィンに見出されるきっかけとなる。もともと太めの体型だった彼女は、ヴィスコンティ監督の精神的な支援を受け、11ヶ月間で30kgの減量に成功し、容姿ともに「ディーヴァ」の名に相応しいものとなった。また、20世紀最高の指揮者カラヤンにも、その才能を見出されている。しかし、彼女の歌声はもともと「メゾ・ソプラノ(高めのアルト)」であり、努力で高音域を征服していた特殊な声であったために、声の破綻が他の歌手よりも早く訪れていた。その為全盛期と呼べる期間は短く、40歳頃には声の衰えが見え始め、1965年のロンドン公演(因みに演目は「トスカ」)が最後の舞台となった。ギリシャの船舶王オナシスとのロマンスも、マリアを語る上で重要なエピソードだが、その出会いはオナシスのクルージングに招待された事がきっかけだったという。彼女はオナシスの豪腕ぶりに魅了され、オナシスも彼女に沢山のジュエリーを贈り・・・実際に彼女はそれを身につけて歌っていたという。この頃からシャネルやディオールの服を愛用するようになる。が、名声や権力に対して貪欲であったオナシスは、故ケネディ夫人、ジャクリーンと関係を持ち、遂にはマリアを捨ててジャクリーンと結婚。このことに精神的なダメージを受け、ダメージを引きづりながら、パリで隠遁生活を送るようになる。かなーり、長い前フリですが、このお話を語る上では外せない部分を網羅しておきました;物語は、声とオナシスを失い、失意の中で隠遁生活を送るマリアのもとに、かつての友人が、マリアを起用してマリアの伝記映画を撮ろうと話を持ちかけるところから始まります。始めは、声の出ない惨めな自分の姿を曝す事に抵抗を感じていた彼女も、映画の中で「カルメン」を演じるうちに往時の輝きを取り戻していきます。しかし、彼女は、演技しながらかつての輝きと現状(実際には声が出ない)との間で揺れながら、苦しむのです。見所は、やはり実際のカラス演じるファニー・アルダンの美貌と、この映画を製作するに当たり全面協力したというシャネルのスーツ。(実際、マリア・カラスは「上得意様」だったので)オペラや声楽の知識がなくても、これだけで見たくなるような魅力があります。それから、オペラシーンの迫力。コレはひとえに監督が良かったというのもあるでしょう。というのは、監督フランコ・ゼフィレッリ氏はヴィスコンティ監督(イタリアの名門貴族にして有名な映画監督)のアシストを務め、自らもオペラ・演劇・映画の演出を手がけている方。実際、ゼフィレッリはカラスとも面識があり、先にも書いたとおりオペラへの造詣も深い。極端な話、この監督でなければ、この物語は撮れなかったのではないかと思うのです。劇中の「カルメン」のシーンもスゴイし、端々に有名なオペラアリアの名曲が使われていて、オペラや声楽が好きな方も満足していただける仕上がりだと思います(シーンごとの、アリア選曲も秀逸)。マリア・カラスという1つの「伝説」をフィクションでありながら見事に描いた作品で、かなりツボでした。この作品、以前ミニシアターでの上映を見そびれたので、コレがスクリーンで見たらもっと凄かっただろうなぁ、と思うのです。追記:監督のフランコ氏、代表作は「ロミオとジュリエット('68)」「ブラザー・サン シスター・ムーン('72)」「ジェイン・エア('96)」「ムッソリーニとお茶を('98)」なんだそうな・・・。観終わった後で、あの「オリビア・ハッセー版のロミオとジュリエット」を撮った監督!と知り、かなり興奮しました(興奮するタイミングが遅いっちゅーの)!作品群を見ると、伝記的な映画がお得意な感じです。「ブラザー・サン~」はアッシジの聖フランチェスコの伝記映画だし(これ、見たいんだけど、近くのレンタル屋さんにないの;)あとの2作は、ビデオと飛行機の中で見たけど、そこそこ面白かったです。
2005.01.13
-
個人的な、今年のニュース。
個人的に、今年の個人的ニュースなど(順不同)。1、ブログを始めて1日のアクセスが300を越えた事。韓国ネタだった所為もあってか。アクセス記録見て、ビックリ。2、久しぶりに俳優さんにラヴィ!な感じになったこと。ヨンジュン氏とビョンホン氏の御両名についてです。そんわけで、追っかけまではしてませんが、目がハートな時があったり(笑)3、自分の描いたイラストが此処以外で掲載された事。この話は少し前の日記にも書きましたが、マジで嬉しかったです。しかも優秀賞まで頂きました。ゆうきゆう先生、多謝!!4、イラスト絡みでもう1つ。生まれて初めて、外部からイラストの依頼がきました。同人とか個人HPへのプレゼントとかそういうのじゃなく、仕事として。(しかもすんごく真面目なお話)緊張しましたが、いい仕事を与えてもらえたこと、そのチャンスを下さったYさんに、心から感謝です。5、6年ぶりに恩師に再会したこと。しかも待ち合わせてた訳じゃなく、オペラの会場で偶然に。どうしてるかな?と思ってただけに嬉しい偶然でした。6、ランプベルジェに開眼する。なんか、此処のブログで紹介したらCOCOさん、架名さん、木蓮さんが購入されて。彼女達はもともとアロマ好きな方なので、愛用してくださってるという話を聞くと、ブログに書いてみて良かったかな?と。7、買い物依存ギリギリのラインまで、買い捲る(爆)。勿論楽天でレビューを書いて・・・。「買う」という行為もさることながら、商品を選び、手に取り、試してみて・・・いいことも悪い事も体当たりで、自分の言葉で書くことが正直楽しく思えた。反響もそこそこあったので、レビューは続けていこうかなと。8、フリマを始めた事。当初から一撃も出て、嬉しいスタートを切れた。今は出品がほとんどナシだけれど、正月の間にでも少しUPできれば、と考え中。9、カラコンや巻き髪とか、今までタッチしなかったものにチャレンジしてみる。30前でオシャレに目覚めたとでもいうか(苦笑)10、ケアマネ資格試験を受験した。結果は「サクラチル」(苦笑)合格率は27%だったという。まぁ、勉強不足だったから仕方ないかな、と。いつもと違ってメチャ落ち込むという事も無く、そのことに自分で驚く。昔なら絶対落ち込んでるな。逆に、自分が今携わってる仕事に対してもっと知るチャンスが得られたんだ、と前向きに考えてる。実際、試験勉強で得た知識は自分の中で生きてるし。順不同の羅列ですが、まぁ、こんなもんでしょう。は?恋愛事情??まぁ、これだけは相手のあることなので、暫くは自分一人で自由にする事にしました。もう、鳴るかどうか判らない電話を待つ苦痛は無いし(そこからくる「二次的な苦悩」もないし)、週末に自由に予定を入れても全然OK。自分の恋愛観も確認できたし(やっぱ、愛=自己愛って考えは捨てません 笑)。私が今、何かを愛してるとすれば・・・それは美術品や宝飾品(手持ちの)。この感情は、「愛でる」という感覚に近い。多分、来年も美しいモノを「愛でる」楽しみを、魂の糧として生きてるような気がする。それも、また「愛」なのかな・・・?
2004.12.30
-
久々のゴスペル!
久々に、生のゴスペルを聴きました。先日ちょこっとだけ書いたかもしれないけれど、北海道在住の女性シンガーKiKiさんのライブのチケットが手に入ったので、行ってきました。例によって遅刻するかな~~?とギリギリの時間で会場入りしたけれど、比較的前の、ピアノに近い席に座れた。らっきー☆彼女を見てて、ちょっと綾戸千絵に似てるかな?と思ったけれど、KiKiさんの人生は更にハード。経済的な事情により両親と離れて過ごし、やがて不登校から暴走族に入り、薬物にも手を染める。そして、17歳でお水の世界に入り、21で自分のお店を持ったけれど、7年でそのお店もCLOSE。原因はお金も適当に溜まったし、疲れたから、という。お金が溜まったら叶えたかった事、それがNYの教会で本物のゴスペルを聴く事だった。初めて聴いたとき、涙がただ流れたと言う。それから、日本とUSを往復するうちに彼女自身も歌うようになり、その後も母の癌宣告、そして自身の妊娠・出産・結婚、そして癌宣告を受けながらも、歌いつづける。それはありきたりの「賛美」ではなく、自分の人生の中のサレンダーであったり、行き場のない悔しさや怒りであったり。しかし、その中にも「神の愛」を見出す、彼女自身の「魂のうた」なのだと感じた。少なくとも私にはそう思えた。ゴスペルのいいところは、他のコンサートと違って「座りっぱなし・聞きっぱなしのお客さん」にしてくれないことだ。何処からともなく、誰かがクラップし、それが会場全体に広がり、みんなマトモに座ってなんかいられなくなる。そのうち、会場全体がどんどんヒートUPして、気がついたら皆が歌ってる。巧いとか下手とかそういうのナシで。とにかく、声を出す事が楽しく、嬉しい。本当に、快感。歌詞のとおりに、本当に「Thank you,God!」な気分になってしまう。改めて思ったけれど、歌の力は凄い。私はクリスチャンではないけれど、こうして教会に来て賛美歌を大声で歌ってる。勿論、まっとうな信徒さん(結構高齢の紳士やご婦人もいらっしゃる)も一緒に。宗教や個人的なイズムとか、そういう壁を取っ払って、人の心を結びつける力がある。コンサートの終わった後の、皆の高揚した顔を見ればそれが判る。あ、因みにKiKiさんについて補足情報。只今「ロイズファクトリー」(チョコレート好きな方には説明の必要なしですが;北海道で有名なチョコレートメーカーです)のCMに起用されたり、道内ではドキュメンタリーも放送されたりしたとか。また、関東・関西でもライブ活動(教会でのライブも含む)を行ってますので、興味のある方は是非、早めのチェックを☆(少し先の関西のライブもチケットが既にSOLDOUTなので)(この日はサインがいただけると言うので、早速1stマキシシングル「God bless you」を購入してちゃっかりサインを頂きました。握手までしていただき、可淡感激!!)普通のゴスペルもイケルのですが、クラブ系・R&Bアレンジもカッコ良くて素敵でした!さ、来週はバレエのチケット買いに行くぞ、っと。
2004.12.19
-
チケット買いました☆
冬のボーナスが出て、最初に買ったのは「チケット」だった。某タウン誌で週末にゴスペルのライブがあることを知り、なんだかそわそわ。5年前、NYのゴスペルシンガー(確か、ジュビリー・シンガーズだったかな)のライブを聞いて以来、機会があれば生でゴスペルを聞きたいと思っていた。場所がアドベント派のチャペルで、日曜の礼拝の後ということに少し抵抗があったが、電話で空席状況を聞いてみると、随分感じがいいので、とにかく会場に行ってみて考える事にした。もともと、「アパレルの空き店舗」を改装して作ったチャペルは、とても現代的でオシャレな感じ。しかも、今晩は水曜なので「聖書研究会」があり、8時には伝導師である牧師夫人がいるという。つまり・・・コレは天啓?「聞きに行け」とばかりの展開。実はこの日、仕事の後に一寸した会議があったこともあり、これに加えて偶然とはいえ、牧師夫人と会えたことといい。前売りのチケットはまだ残っていた。シンガーは北海道の女性。名前はKiKiという。27歳でゴスペルを学ぶために渡米し、CDも製作している、プロの方。赤いコスチュームが良く似合う女性で、頭のてっぺんから足の先までゴスペル!と言う感じの方なのだそうだ(牧師夫人曰く)。日曜は、時間が許せば2月のレニングラードバレエのチケットを買いに行きたいなーと思ってるので、日曜もかなりの強行軍となりそうです。。。でもでも、凄く楽しみ。うしし。ま、いっか。クリスマスも近いし、盛り上がっちゃえ、自分。PS.ドローイング用のペンの調子が不調です。。。どうしよう・・・入稿日なのに(爆死)
2004.12.15
-
もう買っちゃいましたから~。なんだかなぁ。
「明日はボーナスじゃないかぁ!、澁澤さん、君の札束を僕が数えてやるよ!」とのたもうたのは、私の直属ではないけれど、偉いさん(ポストはナイショ)。「なんですか・・・私よりも沢山貰ってらっしゃるクセに(いじいじ)。なんなら、私が数えて差し上げてもいいですが・・・枚数が足りなくなってる可能性有りますよ(苦笑)でも、私のは正直『嫁入り先』が決まってるんです。もう、1月には跡形もないかも・・・」「ほう、というと?」「DVDレコーダーに、ローマンガラス(1世紀頃の古代ガラス)に、店のツケ(爆)」←飲み屋のツケ、ではない呆れられました(当たり前)といっても、最近そこそこ忙しくて、浪費以外に時間のかからない趣味に打ち込めないというのも理由だったり(韓国ドラマも撮りっぱなしで、観る暇が案外無かったり)70時間近く撮れるのでいーや、とタカをくくってますが)週末、ゴスペル@某礼拝堂のコンサート行けるといいなぁ。金曜日は「しゃぶしゃぶ忘年会」土曜は「和懐石忘年会」(勿論、気功治療の後で)と、なかなかにハード。後は、年明けの2月。レニングラードバレエのチケットが取れたら最高なんだけどな!
2004.12.14
-
ヒートUPの理由。
さてさて、続き。何故、私がこの食玩に執着するかと言うと、理由は2つ。1つはミュシャの立体造型であるということ。もともと、ミュシャはほとんどの作品を立体にする事を意図せずに製作しているので、彼の描線は好き放題に画面の中を駆け回っている。まぁ、その奔放かつ優美なラインが、現在も人の心を捉えて話さない理由なのだが。もう1つの理由はというと・・・10種類あるフィギュアの中で「花(花と果物)」のフィギュアに、1000個限定で本物のダイヤ(確か0.05ctくらい)が埋め込まれているという・・・まるで某洗剤の「金・銀・パール、プレゼント!」なノリである。まぁ、ダイヤについては、あわよくば・・・くらいの感じで、とにかく商品を探して、捜し歩く事コンビニ6件、大手スーパー2件。無い・・・・(ショボーン;;)しかも、コンプリート(=全種揃い)した暁には、次に集めようと思っていた「仏像フィギュア(密教曼荼羅系)」なんぞは、大箱ごと商品棚から消滅していた・・・。ぐおおぉぉぉぉーーーー!!!!「孔雀明王」カムバーック!!(号泣)←彩色とデザインがかっちょ良かったので、狙っていた結局、食玩を扱ってるお店に頼る事となりました。。。サスガに大手のコンビニ7件回って、「ガンダムシリーズ」や「黒沢明」フィギュアはあるのに、コレだけがないなんて(あ、仏像も品切れだったっけ)。。マニア、恐るべし。←オマエモナー
2004.12.08
-
アルフォンス・ミュシャ フィギュアミュージアム☆
に、ハマってます。いちお、発売はTAKARAさん、原型製作は天下の「海洋堂」!しかも、ミュシャ財団お墨付きと来れば、コレは買い!!でしょう☆あの、ミュシャだけに原型師さんは随分ご苦労されただろうなぁ・・・と手にとるとシミジミ判ります。デザインは「花」の連作シリーズから「アイリス」「百合」「薔薇」「花」「カーネーション(酒の広告から転用)」の5種類の「フルカラー彩色」と「象牙彩色」の2パターンの計10種類。一番初めにセブンで発見したのは11月の初旬。丁度オペラのチケットを買いに行った時だったっけ。この時には「百合」の象牙彩色バージョンだったんだよねぇ。あー、この時「大人買い」しておけば良かったぁ・・・。(風邪気味なので、続きは明日)
2004.12.07
-
セクシーな演出(改訂版)。
そんなわけで、6年ぶりにオペラ公演会場で、偶然にも再会してしまった私と師匠。上演後、一緒に食事に行く事と相成りました。本当は、年明けの同窓会で再会かな?と思いきや、師匠は年末から休暇を取って、オペラ三昧(タイトル覚えてるだけでも6本+バレエ1本)の日々を過ごすんだそうだ。全く、羨ましい話である。師匠の最近の近況はというと・・・確か「市民音楽祭」関係で色々と立ち回ったり、今年の「第九コンサート」の歌唱指導・指揮(数年前までは、テナーのソリストとして歌ってた)にあたってる事は知ってたけれど、趣味と実益を兼ねた音楽趣味(フェチ+マニア)っぷりには、予想以上に拍車がかかっていた。連絡を取っていなかった数年間は、少なくとも毎年2回はヨーロッパに出かけ、オペラ・バレエ・美術館三昧、となんとも羨ましい生活をしてたらしい(県職員なので、給料はしれてるのだが・・・一体何処から捻出するんだろう?妻子もあるのに)。私からすれば本当に溜息モノの生活・・・。(大体、海外に行くほどの休暇が取れないし、語学力も貧弱としてるし、出かけられたとしても、「女一人」なので何かと物騒だったり。)出かけた都市は、オーストリア、ドイツ、イタリア、イギリス等など。休暇と演目にあわせて出かけるとかなんとか。勿論、毎晩がオペラかバレエ。昼間は美術館だそうな。そんな生活をしてる中で、色々・着々とコネも広げてたみたいで、某L航空会社からオペラハウスの支配人に引き抜かれた方とも、ちゃっかり「お友達」してて、師匠がどうしても見たいオペラが取れなくて困ってる時のこと。その「お友達」が、傍らにあったダンボール箱を切って、ダンボールの端きれに「自らのサイン」を入れて、師匠に渡し、「指揮者がオケボックスに入った時をねらって、何処でもいいから前の方の空いてる席に潜り込んで、知らん顔して座ってろ!」と、いったのだと。そんで、師匠も言われたとおりに実行し、まんまと潜り込む事に成功したのだという。。。。やっぱ、コネ社会だな。アチラって。私もいいコネを作らなきゃ・・・そう思いながら、ペスカトーレ・ビアンコを口に運ぶ私。現地逗留中は、夜は音楽、昼間は美術館に行くので、西洋絵画の話もしつつ、今日の公演に関するコメントも頂いた。師「エルヴィーラがさぁ、のっけからトチってたでしょ?」私「あ、そうなんですか?歌詞までは覚えきってないからなぁ。でも、印象的だったのはレポレロかな。主人よりも目立ってたし。声が通ってて、役作りもイイ感じだったような。あとはアンナ役かな。結構若くて美人だったし。」師「そうだね。レポレロの声って、ジョヴァンニよりも本当は低く設定されてるんだけど、今日の人は声が若干高めだったからね。それに、アンナ役の人は上背もあるから見栄えがしたね。あと、残念なのは、ゼリーナ(=ツェルリーナ)役の子かな。体格はいいのに、声が出きっていない。」私「でもまだ若いから、これから伸びてくる可能性はあるんじゃないですか?体格もいいし(笑)」師「そうかもね。でも、ドン・ジョヴァンニってなかなかあっちじゃやってないんだよ。何故か判らないけれど、今日も含めて数回しか見たことないなぁ。他の演目は結構色々やってるのに。」私「海外じゃ、やってないんですか?意外だなぁ。。。」師「そうそう、今日の演出は「おとなしめ」の演出だったけど、もっと凄いのがあるの。」私「凄いのって、どんな?」師「そう・・・もともと面白い演出をする人で有名な人が手がけたモノなんかはね、例えば、劇中でゼリーナを誘惑するシーンがあるでしょ?そこで本当にドレスをガバッツと脱がせちゃったり。」私「ガバッツ・・・ですか・・・。」師「それから、最後の騎士長の亡霊を招いて晩餐を取ってるシーンで、料理を裸の女性の身体の上に盛ってるの!で、ジョヴァンニは何食わぬ顔でフツーに食事をしてる。」私「それって・・・『女体盛り』じゃないですか・・・(汗)」師「んでもって、地獄の亡霊に連れて行かれた後で、残された人たちが歌うでしょ?『コレが悪党の最後だ』って。で、その後ろで、死んだはずのジョヴァンニが「あの世で女を口説いてる」シーンが繰り広げられるわけ。」私「凄い演出ですね。なんだか、そういうのを見ちゃうと今日のって何?って感じしますねー(苦笑)」師「でも、オケは良かったでしょ?(タクト)振ってる姿も見えたんじゃない?」私「そうですねー。あと、幕間にチェンバロの調律も見たりして。それも、ちょっぴり感激しちゃいましたよ。本物見るのは初めてだったから。」師「復刻版でしょ?」私「うん。東京からワザワザ持ってきたみたい。1980年代のものだったし。でもチェンバロって、個人的に好きな楽器だし。復刻だろうがなんだろうがいいですよ、この際。そういや、バンドネオン(アコーディオンと同じ要領で音を出す楽器。形もアコーディオンに似ている。元は教会のミサでオルガン代わりに使われた)も骨董品並の楽器ですね。ピアソラ(リベル・タンゴとかが有名。CMでも多用されてる)繋がりで知った楽器なんですけど。リベル・タンゴの影響でピアソラに嵌った時期があって・・・」(それからピアソラについて、実に長ーい話が続いたので、ちょっとその部分は割愛。)その後は、トドメに「モーツァルト談義」。大体、モーツァルトのオペラは、ほとんどが色恋沙汰をテーマに描かれている。師匠に言わせれば、彼は同時代の作曲家よりもより人間的な部分を持っていて、人間の愛や欲望をそのままに描きたかったんじゃないかと言う(私もこの点については、激しく同意)。良く言えば、人間味のあふれる物語と、情感を刺激する音楽性。こき下ろすならば、俗っぽく下品(「げぼん」と読むべし)。人が人でありつづける限り、色恋沙汰は避けては通れないし、所詮世の中には男と女だけ・・・そんな話から、アルコール抜きでお互いの人生観を語り、今度は絵画の話へ。なんだか、久しぶりに「知的な会話をした気分」になった(あくまで、師匠の話を聞いては、茶々入れてただけなんだけどさ)。気分だけでなく、ちょっと知識も増えたような気もしないでもないが。私「それにしても、どこかに先生が来てるだろうなぁ・・・と思ってたらあそこでバッタリ、だもの。ビックリ!ほんと偶然ですよね。」師「入り口を入る時、後姿を見て『なんだかキレイな人がいるな』と思って振り返ったら、君がそこで手を振っててくれたから。」私「またまたー(苦笑)相変わらず、口が巧いなぁ。」師「そういえば君は・・・昔から、独特の内的な世界を持ってたよね。できれば僕が関わった皆に、そうであって欲しいと思ってるんだ。」私「確かに、独特。個性的な方でしたよね、当時から(苦笑)」師「18年経ったんだな、あれから。それにしても、今日はオペラや音楽、美術に人生の事・・・色々な部分で合致しててとても楽しい夜だったよ。今日は、実にいい日だった。また、音楽や美術系の催しも一緒に行きたいね。勿論、それだけじゃなく、お酒でも飲みながら色々と語ってみたい事もあるし。」私「そうですね。最近、催事に出かけるときはいつも一人なんで。誘ってくださると嬉しいです。お互い感じた事を共有して、語り合うのも楽しいし。」そして、すっかり食事をご馳走になった後、私が車を停めてるパーキングまで送ってくれて、「又何かあったら、事務所に電話してね。今日は本当に楽しかったよ、有難う!長話の分だけ駐車場代が高くなったかもしれないけど、ゴメンね!」そういって、笑って右手を差し出す。「いえいえ。お食事、ご馳走様でした。もうそれだけで充分なんで。とにかく、会えてお話できて良かったです。また、近いうちに・・・それから、レマン湖のほとりのオペラハウスの写真、送ってくださいねー☆」そういって、握手して別れた。師匠は、今日もレストランのところでエスコートしてくれたり、椅子を引いてくれたり、なにかとやることがスマートでカッコいいのだ(やっぱ、場数を踏んでるだけはある)。自分が男だったら・・・できるだろうか。つか、これだけこなせたらカッコいいだろうなぁ(笑)それにしても気になったのは、西洋にも「女体盛り」という概念があったということ。そんな「面白い演出」があるなら、1度といわず、同じ演目でも何度か脚を運んでみるもんだなぁ、と思った一日でありました。(あとは、「ヨーロッパのコネ社会」に思いを馳せながら、黒い野望も抱きつつ(爆)PS.そんな師匠も、私がかつて1度だけ手にした「プラチナチケット(因みに3大テナーの一人、ホセ・カレーラスの独唱)」は羨ましがってました。まだまだ日本では敷居が高い感じのするオペラですが、ヨーロッパのオペラハウスでは、「天井桟敷席」があり、そこならわずか数百円(!!)で見られるとの事。やっぱ、本場は違うなぁ。。。憧れるっす(その前に台詞とお話はある程度押えなきゃいけないんだけど;)。
2004.11.24
-
「ドン・ジョヴァンニ」と、意外な再会。
というわけで、行って参りました。「ドン・ジョヴァンニ」を観に。「前から2列目・ど真ん中」という、奇跡的な席をgetできたわけですが・・・前の席に座るとやはり、オケの音も近いし、演じてる歌い手さんたちの、微妙な表情や演技もバッチリ見えてしまうし、時々、指揮者の振ってる手やタクトが見えたりして、かなり大感激でした。歌い手さん達もそこそこ。役に見合うだけの容姿でした。(若い娘役や姫役が妙に老けてたり、ぷくぷく・ぴちぴちだったりというのはよくある話。主役級になると「それなりの歌唱力」が要求されるため、どうも避けられないことらしい;)色男のドン・ジョヴァンニも容姿としては「うきゃー!」というレヴェルではないですが、OKレヴェル。黒髪(実は澁澤は金髪が苦手)に、黒一色の衣装がまたセクシー。黒の上着からヒラヒラと揺れるレースの飾り袖も素敵でした。当時、お洒落としてカツラをかぶる風習があったので、ジョヴァンニも当然衣装を着け、カツラをつけ・・・唖然。ジョバンニ役・・・薄かったよ、頭(ひゅ~~るりぃ~ひゅ~るりぃ~ららぁ~)。裾から登場してきたとき、カツラがないと同一人物だと判りませんでした(爆)。対して、従者レポレロは赤一色の衣装で、主従は「黒と赤」という対照的な色合い。この対照的な色合いの衣装が2つ揃って舞台をウロウロしてると、何事かが起こりそうな予感がして、ドキドキ。(衣装さん、心理的効果狙ってる?)声質は非常に良く・通る声で、主役のジョヴァンニよりも目立ってました。キャラが立ってた、とでもいう感じ。後は、ドンナ・アンナ。最初夜這いを掛けられて白の寝衣姿で登場するのですが、これまたセクシー!頭はボサボサですが(寝てたわけだから)、コルセットにテロテロのスカート、レースのついたゴージャスな袖。コルセットの間から見える谷間まで・・・。上背のあって、細身で華奢な(でも、谷間は立派!)「いかにも貴族の娘」っぽい気品のある方だったので、見てて結構うっとり、でした。「ドン・ジョバンニ」もそうですが、オペラを生で観るのが初めてだったので、興奮も感激もあったのですが。感想をまとめると・・・舞台装置と演出がもうひとつ物足りない感覚でした。あとは歌い手さん。主役よりも目立つ、レポレロってどうよ?というのもあったり、ジョバンニとレポレロ以外の衣装デザインが、ちょっとなー;と言う感じ(コレは趣味の問題もあるけれど)もあったり。でも、オケのクオリティは、かなり高かったです(フォローじゃなく)。少し脱線しますが。ジョヴァンニが何かを囁いたり、話したりするシーンにはチェンバロ(ハープシコードとも。ピアノの前身的楽器)が使われるのですが、ちゃんとこの日のために、東京からチェンバロ(といっても、復刻版ですが)を用意してあって、一幕と二幕の間に専門の方が調律されてました。実は私、チェンバロとリュートの音色については「完全にフェチ」なので、この調律の様子をジックリ眺めては、ドキドキしてました。ピアノの前身といわれる楽器で、姿も良く似ていますが、黒鍵と白鍵がピアノとは逆の色使いであることに加え、何よりも音の出し方が違います。ピアノを弾かれる方はご存知でしょうが、ピアノは張った弦を叩いて音を出すように出来ています。が、対してチェンバロは爪のようなモノ(しかも、この爪様のモノは鳥の羽根で作る)で弦を弾いて音を出すようになっています。なので、ピアノの音が「ポーン」とか「バーン」であるのに対して、「びよよよよん」「ぼよよよよよん」と、どちらかと言うと弦楽器に近いニュアンス。私はその「びよよよよよん」を偏愛してる訳でして。しかし、これらの古楽器は一時はすっかり廃れてしまい、チェンバロなどは復刻されていますが(このオペラのときに来てたのは、1980年代、日本製のもの)リュートなどは絵画の中に残るだけで、実は「正確な製法」が未だ謎だったりします。そんなミステリアスな部分も、古楽器の魅力であったりします。大分、話がそれました(汗)。やはりジョヴァンニが、ツェルリーナ(マゼットという新郎がいる)を「貴女には私のほうが似合ってる。さぁ、手に手をとって、行こう。私の別荘で、2人っきりで結婚式を挙げるんだ(意訳)」と誘惑するシーンのアリア「手に手をとって」は良かったです(このアリア、個人的に好きだし)。それと、エルヴィーラの召使を口説く時、レポレロに化けて「ああ、窓辺においで、私の愛しい人よ・・・」とセレナーデ(リュート伴奏付)を歌うシーンも好き。あと、歌い手さん(の声質・声量)がイマイチだったけど(爆)ツェルリーナのアリア「薬屋の歌」は歌詞が良かったので、聞けましたね。ジョヴァンニを闇討ちしようとして返り討ちに合ったマゼットを見たツェルリーナが「ヤキモチを焼かないなら、お薬をあげる。それはどんなお医者でも調合できない薬よ・・・(意訳)」と、ヤキモチさえ焼かなければ、私の愛で癒してあげる♪と優しく歌うのです。うーん、やっぱ、「愛」だよなぁ(ごーいん)。。。愛といえば、エルヴィーラの愛の形も凄い。ジョヴァンニに3日で捨てられて憎んでるはずなのに、復讐の刃を向けるアンナとオッターヴィオに「あの人を許して。お願い」と庇ったり、放蕩暮らしを諌めたりと、ジョヴァンニへのエルヴィーラの愛は、憎しみよりももっと深いところにある。自分の愛で更生させようとする感もあるような。本当は今すぐにでもアンナと結婚して幸せになりたいのに、「哀しみが癒えるまで、結婚は待って」というアンナの言葉を、アンナの気持ちを大切に思うがゆえ、いともアッサリと受け入れる、オッターヴィオの愛。いろんな愛の形のあるドラマ、と観るのがいいのかもしれません。そんなこんなで「オペラな夕べ」は幕を閉じるはずだったのですが・・・実は上演前に、一階席専用入り口を通っていると、どっかで見たような人が。「あれ?」小さく呟いたつもりなのに、聞こえちゃったのか、その男性が振り返ってこっちを見た。手を振ると私だと判ったらしく、ビックリした顔で「元気?今日は一人?」と。実は彼は、私がクラシックを聞くキッカケを作った、まさにその人であり私の「音楽の師」だったのです。私「お久しぶりです。数年前の、ゴスペルのコンサート以来ですね!」師「いやぁ、そうだね。今日は本当に一人?」私「ええ。今日はお休みだし、観に来たんです。先生も、お一人ですか?」師「そう、僕一人。どう、後で食事でも?」私「今日、携帯持ってないんですけど・・・」師「じゃー終わったら、カフェテリアの所で待ってるから」てなわけで上演後、2人でオペラの余韻に浸り、感想を述べながら、イタリアンと洒落込むことに。師「飲めないのが残念だよねー。」私「そうそう。久しぶりだから飲みたいんですけどね、私も。そういえば、同窓会にはいらっしゃるんですか?」師「そういや、何時だっけ?」私「元日の6時でしたけど?あれって、既婚者には厳しいですよー。特に嫁に行った人にはねぇ。」師「ああ、でもその日は欠席だな。丁度その日はルツェルンだよ。オペラ見てる頃だ」私「はぁ?!」(そんな感じで、続く)
2004.11.23
-
「ドン・ジョヴァンニ」を観てきます♪♪(改訂版)
先日、オペラのチケットを買いました。オペラだって、立派な演劇なので、いちお、このテーマに書いてみました。演目は「ドン・ジョヴァンニ」。『稀代の女たらし』のお話は、モーツァルトの曲により、見事なエンタティメントに仕上がっていて、モーツァルトの傑作オペラのひとつに数えられる。しかも、今回はS席でも1階席、オケボックス(オペラの場合、オーケストラの生演奏が入るため、前列5列分はオーケストラのためのスペースになる)の2列後ろの「ど真ん中」。この席が取れた事そのものが奇跡に等しいのに。(チケットの売り出しは9月。買ったのは11月初旬 爆)大興奮です。ああ、何を着ていこうか。ドレスならスネの脱毛もしなきゃいけないし(このあたりが妙に所帯じみ)。ストッキングはどれにするか・・・?バッグはどれにするか、コートはやっぱり毛皮にするかと、もう衣装からして悩みまくり。とりあえず、ベッツィー・ジョンソンのホログラムチックなドレスにシープスキンのエナメルパンプス、レッキスのコート(レビュー参照)に、バッグはモノグラムマルチカラーあたりで妥協。。明日は「肌の手入れ」(デコルテ丸出しなんだよ、このドレス。。)と「手足のエナメル塗り」の作業が忙しくなりそうです。後は、コートの毛並みを整えとかなきゃ。。<あらすじ>世界中を巡り、女を口説き落とし、征服した女の数は既に2065人。道楽者の放蕩児、ドン・ジョヴァンニ(=ドン・ファン)は従者レポレロ(主人の「征服した女のリスト」を作るのが趣味 爆)を引き連れて、今日も女に手を掛けようとする。ある晩、騎士長の娘ドンナ・アンナに夜這いをかけて、騎士長の怒りを買い、その場で決闘する事となる。が、ジョヴァンニは不覚にも騎士長を殺してしまう。父の死を目前にし、悲嘆に暮れながらも、父を殺した者への復讐を誓う、ドンナ・アンナとその婚約者ドン・オッターヴィオ。一方、「騎士長殺しの一件」から逃れようとしていると、結婚して3日で捨てた女、ドンナ・エルヴィーラに出くわす。彼女に不実をなじられ・追いかけられつつも、たまたま出会った純朴な村娘ツェルリーナに言いより、新郎マゼットのもとから奪おうとしたり、彼の放蕩は留まるところを知らない・・・。そんな中、アンナはジョヴァンニに偶然再会し、父の仇が彼であることを知り、婚約者オッターヴィオに、父の殺された晩に何が起きたのかを話すのだった。オッターヴィオは、アンナの身に起きた事を知り、復讐への決意を固める。追っ手から逃げるために(更には女を口説くために)、ジョヴァンニはレポレロと(強引に)服を交換し、さらにレポレロの姿でエルヴィーラの召使を口説くジョヴァンニ。一方、レポレロは「その姿」のために、追っ手(アンナ、オッターヴィオ、マゼット)に囲まれ殺されそうになりつつ、自分の所為ではないと言い放ち、逃げる。こうして、放蕩の限りをつくしたジョヴァンニのもとに、騎士長が墓地から蘇り、彼の前に姿を現す・・・「悔い改めよ」と。。。今回、私が観に行くのは、「ポーランド国立ワルシャワ室内歌劇場」の引越し公演。モーツァルトのオペラ21作品全てを世界各地で上演してる、というのがウリのようです。舞台セットは日本公演用にコンパクトに作られてはいるものの、まさに目の前で生でやってくれるのだから、大期待なのです。あー、どきどき。最近は、オペラ上演の際は「字幕」が付くので、お話を知らなくても、言葉がわからなくても(実際私もほとんど判んないっす。爆) 確かこの演目はイタリー語のはず;)楽しめます。敷居が高いと思わず、チケットセンターに行ってみると、結構イイ席が残ってるかもしれませんよ(特に、モーツァルトくらいになると、「あ、コレCMで聞いた事ある!」ってメロディーに沢山出くわすはず。そういう意外な「メロディーとの再会」もオツなもんですよ)
2004.11.22
-
ハウル、観てきました!
というわけで、観に行ってきました!公開日に観に行くなんて、「マトリクス・レボリューションズ」以来ですねー。ほぼ1年ぶりかな?ヒロインは90歳の老女、恋人は弱虫の魔法使い、2人が暮らすのはあたかも動物のように動く城・・・。大まかなあらすじは公式サイトを御覧になっていただくといいと思います。さてさて、以下はネタバレ有りの感想をば。(※ネタバレNGって方はスルーしましょう 笑)「動く城」のビジュアルは協賛のハ○スのCMや日テレで何度も放映されてましたが、実際に動いてる様子が凄い!私、戦車のキャタピラとか、ごっつい機械が「ガタピシ・ガタピシ」とか「プシュー」とか、音を立てて動いてる様子に異様に興奮してしまう性分なので、のっけからかなり惹きつけられましたが(爆死)、まぁさておき。まず、魔法使いハウル。宮さんが「宮崎アニメの男性の中で一番のハンサム」といってるとおり、確かにビジュアル系。ハンサムです。(個人的には、人間のポルコ・ロッソ(@紅の豚)もイイと思うのだが)「弱虫」と書かれていて、自身も「弱虫なんだ」と言っているけれど、彼は基本的に「自由人」。本当に弱虫であるなら、街に爆撃を加える戦闘機に夜な夜な向っていったりなんざしませんし、ソフィー達を連れて逃げるしかしなかったでしょう。なのに、立ち向かっていく。そして、何度も王宮からやってくる召集令状も無視しつつも、王宮に居る宰相サリマンのもとへ、使者として送ったソフィーを救いに赴いたり。「相応の能力・強さ」を認められながらも、自由人であることを貫く所は、「紅の豚」のポルコと同じ性質なのかな?と思いました。そしてソフィー。倍賞さんの声は最初から最後まで、全く違和感ナシでした。亡き父の帽子屋を「長女だから」と言う理由で切り盛りする彼女は、ハウルに出会ったその晩に、荒地の魔女の呪いによって、突然90歳の老婆になります。が、90歳になった彼女は、姿が90になっただけでなく、精神的な成長を遂げるているようです。その変化は姿が変わってから僅かな時間でで現れ始めます。まずはその姿で大丈夫なところを探しに、という理由で家を飛び出し、その結果ハウルの城へ潜り込み、火の悪魔カルシファーと出会い、彼が城の動力を担っていることと、ハウルとの契約(これはよーく見てると最初のシーンに「伏線」と思しきものが映ってます;)により使役されている事を知ります。が、彼女は火の悪魔を見ても、全く動揺しない。むしろ現状にに対しての受け入れがとてもよくなって、少女でいたときよりもポジティブに、アグレッシヴに活躍してくれます。主人公の少女の(精神的)成長というテーマは「魔女の宅急便」「千と千尋の神隠し」で顕著ですが、「ラピュタ」のシータや「紅の豚」のフィオなど、他の作品でも大なり小なり描きつづけられてる、共通項のようです。この作品もその点であてはまってたように思われます。そして2人の関係。「街で出会うシーン」(これまた宮崎アニメお約束の、「空中浮遊」!)のもなかなか素敵なのですが、お話の中盤でプレゼントを贈ったり、自分だけの秘密の場所に案内したり・・・ラブストーリーの王道をちゃんと押えた展開になってるあたりは流石。ソフィーを爆撃の炎から守るために飛び出していくハウルと、それを「行かないで!」と止めるソフィー。もう、このあたりで涙腺緩みます。(「守りたいものは、君だ」っていう台詞もクサいけど、やっぱグッときますねー。)声はキムタクでなくてもこの際、誰でもOKな気がしましたが(笑)多分、宮さん渾身の「ラブストーリー」であることは間違いないです。私の横のカップルの女性、最後までハンカチが手放せなかったみたいで。私も途中から、かなりキましたので。女性は必見。お子様にも推奨。男性の反応は・・・どうだろう?(他にブログで感想書いてる方も沢山いるようですが、「戦争の原因は何?」とか「なんで、荒地の魔女も一緒に居るわけ?」とか細かい事気にしないで楽しんじゃったほうがお得ですよ、と私は言いたい。現実世界が、全て納得できるものでないのと同じように、「あの世界」でも不条理や、説明の付けにくいことが存在していて当たり前なのだから。いや、むしろ「虚構」の中だからこそ、制約も多いんであって。・・・文章力が貧弱なので、巧く説明できないけれど;)書きたいことは色々とあるのですが、あとは劇場で、是非。あっと驚くエンディングに「やられた!」と思うことは必至ですね(笑)追記:お話の前半で、ソフィーの所為でハウルの髪の色が変わってしまい、ハウルは「美しくない僕はもうオシマイだ・・・」と呟き猛烈に凹むのですが・・・まさか、この台詞を言わせたくてキムタクにハウルのCVやらせたのか?と思ってしまう、私。いーんだ、ヒネクレ者ですから(笑)
2004.11.20
-
やっぱ、宮さん凄いわ。。。
ハイ、というわけで只今「もののけ姫」を観ながら書いております。海外でも公開された作品ではありますが、「千と千尋の神隠し」と同様、自然の中に存在する「八百万の神」とか、そういう日本独特のモノの見方(アチラは基本的に一神教だし)がないと、作品世界を理解するのは難しいと思うのですが。如何なもんでしょ?さておき。この作品のコピー、「生きろ」でしたな。生と死、破壊と再生。善と悪だけの二元論だけでは語れない人間像。こういう部分が、映画版の「ナウシカ」で表現できなかった部分が、ここではうまく昇華されたのではないか思っています。(映画版ではキャラの善悪が前に出すぎてて・・コミック版のクシャナの人間性とか、ナウシカ自身の人間としての苦悩とかそういうドロドロしたものがない、「お子様に理解できるレヴェルの描き方」でしかなかったのが残念なんですね)台詞の中にも注目。瀕死のアシタカがサンに「生きろ、そなたは美しい」という台詞も非常に印象的ですが、石火矢(コレであってるのかな?)を作る職人達の長の台詞もなかなか沁みます。おそらく、彼らの様子を見る限り、彼らはかつて忌み嫌われたハンセン氏病の患者(あくまで推測ですが)。長は言います。自分も呪われた身(=病気で身体が不自由)だから、貴方の気持ちはよく判るのだが、自分たちを人間扱いしてくれた大切な存在だから、エボシを責めないで欲しいと懇願し、「生きるということは苦しい事。だが、生きなければいけない」という意味合いの事をアシタカに語ります。見過ごされがちなシーンでは有りますが、描くのが難しいシーンだったと思います。病に冒され包帯だらけでムシロを被って動く事もままならない・・・いわゆる「悲惨な姿」をとったキャラクターだから効く台詞だと、そう思います。まぁ、このシーンに限らず、他の宮崎作品と比べて、「生き死に」(人だけでなく、森やその神であったり)をめぐる台詞がずば抜けて多い気がします。「生き死に」は、昔から自分にとってはとてもコアな部分なので、それゆえに、この作品は重く感じられます。来月同じ時間枠で放映の「千と千尋の神隠し」も「生きる力を取り戻せ」とかいうコピーだったような気が。こちらはこっちで、エンタティメント性が高くそれなりに好きだったりします(多分、観ちゃうんだろうなぁ・・・)。そういや、明日から「ハウルの動く城」いよいよ公開!!市内の映画館でも明日から上映してくれるので、早ければ日曜あたりに観に行ってるかも(あくまで予定)。ハウルasキムタクよりも、魔女as美輪様の方が気になっちゃうのは何故なんでしょうか(笑)。主題歌の歌詞が谷川氏で、歌詞読んだだけで泣けてきました・・・(コレで弓さんの声がプラスされたの聴いたら、マジで泣くかも)
2004.11.19
-
一目惚れ☆
あああ、BBSにまた返事付けられてません、ごめんなさい(反省中)で、本日の言い訳↓今日はPIECE MONTEEの店長の紹介で、店の近所のジュエリーショップの「上得意様特別案内」なんぞ頂いてしまって・・・フラフラと行ってしまったわけなんです。もともと、薬指用(10.5号)しか持ってなかったので、人差し指か中指につけられるエタニティか、カジュアルなデザインのピンキーが欲しかったのですが。エタニティの「レール止め」と「爪止め」の両方を見せてもらったんだけれど、イマイチ。「キレイだけど、ちょっと寂しい感じ・・・」と呟いたら、「細めのエタニティ」を3本組み合わせたような、緩やかなカーブを描くフェミニンな感じのものを出してくれて。勿論地金はプラチナ。ダイヤのクラス・カラーはちょっと置いといて(苦笑)0.5カラット相当。結局一目ボレで、買いました(爆死)無金利の限界回数=10回払いで。「冬ボーナス」で払っちゃうと、夏まで暮らせそうにないので(切腹モノ)PIECEの店長からの紹介だから、ということでスエードタッチな「ジュエリーケース」まで頂いてしまった。最近、こんな感じで色々とオマケを頂く事が多い。(因みに。他の「上得意様」は菓子箱だけだったみたい)お店の奥で支払いのことについて話してると、ケースには「すんごいモノ」がもう、ザクザクと。パパラチアサファイア(オレンジかかったピンク色)やら、ブラックオパール(マラカイト・グリーンの遊色がメチャ美しかった!!)、稀少なパライバトルマリン(ネオンブルーが美しい!)など。普段はなかなか生で見たり嵌めたりすることのないものを次々と嵌めて遊ばせて頂きました☆信販会社からの電話を受けてる時などは、左手に5カラットのダイヤ(ただし、インクルージョンが多い;肉眼でも確認できたくらい。色はそこそこ良かったのだけど)がキラリーン☆な状態でお話してました。脇についてるメレダイヤを含めれば6カラット相当にはなると思われ。でも5カラット以上にもなると重たかった・・・。色々な意味で。当分ジュエリーショップには近寄っちゃ駄目だな、うん(反省)。さて、明日は日帰り旅行だな・・・。早速デビューですかね?(丁度大安だったし。使い始めにはいいかも?←こういうところが「年寄り臭い」)
2004.11.12
-
アロマのある日々。
昔から、いい香りのあるモノが好きだった。それは花の香りであったり、人工的なアルデハイドの香りであったり。そんな私の「香り」に関するエポックメーキングはHERMESの「AMZON」の小瓶。しかし、今回は「香水」について語るトピックではないので、その後の「香水遍歴」は後の機会に譲る事にする。アロマテラピーと名の付くものを始めたのは、高校生くらいだったか。ティーンエージャーの女子の為の雑貨屋に並んでいた、ニールズヤード社のラベンダーの精油がキッカケだった。ニールズヤード社の瓶は濃いコバルトブルーの瓶で、飾ってるだけでも美しい(実は「キレイな色の瓶フェチ」だったりする)。他の精油はマッサージなどに用いる際、必ずキャリアオイル(ホホバオイルなど)で薄めて用いなければならないが、ラベンダーの精油だけは別格でそのまま肌に塗って用いる事が可能だ。しかもラベンダーにはリラクゼーション作用もあり、美肌作用もあるので、ラベンダーばかりを偏愛して使っていた。数年後。私は「アロマランプ」と「専用ラベンダーオイル」を贈られた。精神的に参っていて、休業していたある日の事だった。始めはそのランプの使い方が判らないため、セラミック芯ではなく、綿芯に着火したりと無茶な使い方をしていて、効果が感じられなかった。そして、2年ばかり、部屋の中でオブジェ化していた。ところが、最近ネットサーフしていて吃驚。昔貰った「例のランプ」が「ランプベルジェ」ということがようやく判ったのである。因みに「ランプベルジェ」とはランプベルジェ社謹製のアロマランプのこと。概略は以下を参照されたし。「Lampe Berger社は、パリの薬剤師であったマルセル・ベルジェが創設した芳香アロマ製品の研究・開発をしているフランスのメーカー。エッセンシャルオイル(植物精油)に天然オゾンアルコールを溶け込ませる技術や独自のバーナー芯(触媒芯)を用いてアロマオイルの燃焼温度を常に60℃に維持する技術(共に国際特許取得)を開発し、その独自の技術と安全性(国際安全認証・ISO-11014を取得)でフランス国内における芳香アロマ消費量の70%を占めている。また、ランプベルジェ社のアロマランプは芸術性豊かなデザイナー達の手により、室内インテリアやコレクターズアイテムとしても高い評価を得ている。※すべてのアロマランプはフランスのデザイナーによりデザインされている。また、陶器製のアロマランプはフランスの文化国宝といわれるリモージュ磁器。」 しかも、愛好者にはピカソ、シャネル、コクトーなど凄い顔ぶれが並ぶ。ランプそのものの美術価値もあるため(リモージュ・バージョンは有名だが、ルネ・ラリック《アールヌーヴォー期の工芸作家》やバカラ《クリスタルのブランド》もランプをデザインしてるとか!)・・・機会があれば、これらのランプも是非観てみたいものである。そんなわけで。正しい使い方が判ったこともあり、何種類かオイルを取り寄せて、受験までの間、ずっと焚いていた。それこそ一日中といっても過言ではない(勿体無い使い方!!因みに500ml:3900円)このランプの凄い所は、部屋及び部屋に干していたもの、部屋の隅に置いていたバックまで消臭?するというパワーにある。実際、職場でバックの中身をゴソゴソやってると「マルキーズ(=梔子)」の香りやら、「エロイーズの海(ハマナス+バラ)」の香りがふんわりと。部屋の中に吊っていたジャケットも、人と食事に行った時についた「食べ物の香り」が消えていた!それに、アロマテラピー効果も抜群。例えば、今焚いている「マルキーズ」には食欲抑制作用があるとのこと。また「ブーケ・プロヴァンス」には肌の引き締め効果・頭痛止め・風邪の予防効果がある。コレにはタイムとローズマリーに含まれる殺菌作用が関連しているのだろう。(古代ギリシャかローマでは、殺菌作用を利用して、墓地にローズマリーを植える習慣があった。当時は「土葬が一般的」だったので、死体から発生する瘴気を防ぐためと思われる)そして「エロイーズの海」。“波の無い静かな海”という意味だが、ハマナスとバラの香りには嫌味の無い穏やかさがあり、心を穏やかにし、ホルモンバランスを整える作用があるとのこと。あと、効能はハッキリしないが「スミレの愛」。コレがまた素晴らしい香り!「マルキーズ」よりも主張しない、その「愛らしい甘さ」は、正に地に咲くスミレそのもの♪♪(相互リンクしてるCOCOさんも随分気に入ってくださってる様子で私も嬉しい♪)スミレ・エロイーズ・プロヴァンスは、次回リピート決定!ついでに、試してみたいのは「フィヨルドの霧(ユーカリ)」ユーカリには強い殺菌作用があるため、精油成分が化粧品や入浴剤に使われることも多い。入浴剤で有名な「クナイプ」にもユーカリが有るけれど。多分、居室でガンガン焚いたら、風邪のウイルス(アデノウィルスやロタウィルスとか)もどっかにお隠れになるかもしれない・・・。多分、明日の私は、「全身マルキーズの香り」と化してるでしょうね(笑)☆これからランプにトライしてみよう!と思っていらっしゃる方へ。※1.低血圧のある方でラヴェンダーを使おうと思ってらっしゃる方へ。ラヴェンダーの鎮静作用のため、血圧が下がりすぎて気分悪くなる事が有りますので要注意です。※2.普段香水やルームフレグランスの類を使われない方には、ヌートレ(無臭)を購入し、半分程度に希釈して焚くことをお勧めいたします。香りがキツク、却って不快に感じられるようなら、「リラックス」なんて出来ませんものね・・・。※3.サブページにも何箇所か「取り扱い店」をリンクしてますので、良かったら御覧になってみてください。また、「価格リサーチ」を怠り無いように。
2004.10.28
-
アンティークと「プレイ」。
今日は「お蔵入り」していたお話を。まだ暑かった7月末のある日。夏休みを貰った私は、久しぶりに一人で出かけた。映画でも見ようかと思っていたけれど、お気に入りのミニシアターの上演内容が「アンパンマン」だったりしたので、映画は止め。オーバーホールに出していた時計を引き取りに、某デパートに出かけた。たまたまデパートの5階の催事場で「ベルナール・ビュッフェ展」と「オールド・マイセン展」をやっていたので、思いがけない催事内容に小躍りしながら、5階へ。隣の区画はバーゲンをやってるらしく、ごったがえしてるけれど、隣の催事場は静かで、ガラン・・・としている。私的には、ガランとしているほうがユックリ観られるので、これまたラッキー☆と悦んでみる。たかだか数百円や数千円のものをつかむためとはいえ、ゴクロウな事だなー、と尻目に見ながら会場へ。ビュッフェそのものは「ストライクゾーン、ど真ん中」と言うわけではないけれど、見ていると何点か「いいな」と思うものもある。因みに「いいな」と思ったリトグラフ。一枚17万円。(この会場の中では格安なんです、これでも)ビュッフェを堪能した後は、オールドマイセン展(会場がお隣さんになる)へ。TV東京系の「某お宝鑑定番組」でも、よく取上げられてるマイセンだけれど、オールド・マイセンを実際に見るのは初めてなので、かなりドキドキ。作品の隣にはちゃんと「お値段」が明記されていた。因みに、会場で一番高価なモノは18世紀のマイセンの壷(確か5・600万くらい)。とにかくいたるところに細かな細工が施されていて、個々のパーツの造形も美しいし、彩色も見事。その繊細な美しさには感動。。。薔薇の花なんか、「本当に粘土で出来てるの??」と思うくらい。この展示。マイセンの他にも、「リモージュ(深いブルーが特徴)」や「ロイヤルコペンハーゲン(イヤープレートで有名)」の年代物が展示されていた。ミニアチュール(細密画)を思わせる繊細な絵付けに溜息を洩らしながら脚を進めていたけれど、「これは・・・?」と思ったものがあった。それは額装された、リモージュの陶板。陶板そのものは20×10cmくらいのもので、それほど大きなものではない。2枚で一対になった、その陶板に現されていたのは・・・「樹に吊るした天使を、鞭で引っぱたく女神」&「後ろ手に縛った女神を、鞭で引っぱたく天使」・・・・・・・・・・・・・・・・コレは「プレイ」なのか・・・?(爆)笑いをこらえるような仕草をしていたのを、図らずも催事係りの若い男性に目撃され、後ろから声を掛けられた。「それ、面白いデザインでしょう?リモージュの中でも少し変わってるんですよ。イタズラされた女神が逆襲して『お仕置き』してるって感じですね。」なるほど、貴方の中ではそういう順番なんだな(←心の声)。声を掛けてきた彼は、よほど暇だったのだろう。その後も熱心に説明をしてくれた。「リモージュといえばブルーが一般的ですが、こちらはグリーンで・・・しかも釉薬を掛けた上に薄い陶土を塗り重ねるようにして人物を描いてあるんです。」そう言ったあと、彼は額を取り、私に手にとって観るようにと促した。「手袋、しなくてもいいんですか?」と聞くと、心配ないことを告げてくれた。(よく考えたら、万一汚れてもふき取れるし、手袋してる方が、手が滑って危ないのかもしれない)確かに、モスグリーンの背景は釉薬の色で、その上に白い陶土が塗り重ねてある。手にとって観ると、女神の乳房や腹直筋などは厚めに塗り重ねてあり、触れると凹凸がある。髪の毛などの部分は極薄く、背景に溶け込むように薄く塗られていた。それは、大きな「カメオ」のようでもあった。因みに18世紀の作品で、お値段は1対で240万。「素晴らしい手仕事ですね!此処でこんな良い物を観られるとは思いませんでしたよ。」と興奮気味に話すと、彼は気を良くして、最後まで作品群を丁寧に説明してくれた。薔薇を描き金彩で囲んだ「リモージュのプレート」(1枚:平均200万↑)や、ロイヤル・コペンハーゲンの「トンボモチーフのコンポート」や「アヤメのフラワーベース」など、エミール・ガレやラリックを髣髴とさせるデザインも目を楽しませてくれた。他にも、コペンハーゲンの「動物フィギュア」(ほとんど出回っていないので稀少なのだそうだ)があった。ペンギン、カバ、カエル、魚など・・・これがまた愛嬌があり、可愛らしいものが多く、それぞれを手にとって目と手の両方で楽しんだ。(1体で平均14・5万くらい)作品の作られた年代とともに値段も記されていたことから、ツイツイ値段の話になってしまうあたり、やはり私は俗物なのだな、と認識を新たにした;作品個々の値段も印象的だったが、あの「プレイ」とも解釈できる「リモージュの陶板」の方がもっと印象的だった。いや、本当に(苦笑)さ、今度は「菊川コレクション」でも観に行くかな・・・。
2004.09.22
-
パリから、「アテネ総括」とな。
先日、2年ぶり(!)にメールをよこしてきた記者のS氏。そんな彼から「アテネ総括」というタイトルでメールが届いた。ネタが切れかかってる時に、こういうメールは有り難い。パリコレやオークション、バレエの取材もあるらしいけれど、やはり得意分野のスポーツの事となると、気合の入り方が違う(笑)話の最後には、選手村に配られた20万個のコンドーム(・・・)の消費の具合まで気にかけていた(核爆)。まぁ、アレもある意味「スポーツ」みたいなもんだし。つか、使ってる暇+体力あるのか??彼のメールで、ちょっとスポーツ(情報)音痴が解消されたような。そんな感じです。後日談:S氏、パリにのアパルトマンに帰って、素麺を食べてたとのこと。パリ暮らしが長いから、時々は日本食が恋しくなるらしい。後日談その2:20万個のうち、実際にハケたのは3万個とのこと。私の妄想回路は「餅撒きの如く、余ったコンドームのパウチが物見櫓からばら撒かれる様子」を想像していた。「餅撒き(地方によっては「餅投げ」とも)」「物見櫓」というあたりが、私らしい。。。
2004.09.03
-
蜷川「オイディプス」
オリンピックも最終日。そんな中・・・やってるじゃありませんか!オリンピックの前にアテネで上演された、蜷川「オイディプス」を!!まさかTVで見れるとは思ってなかったので、「超」が付くほど嬉しい!!「エディプス・コンプレックス」の語源にもなったオイディプスの話を、蜷川がどう演出するか、どう見せてくれるか、楽しみ☆
2004.08.29
-
ギリシャから。
先日、私のメールボックスに妙なタイトルのメールが着ていた。何となーく、見覚えのあるような名前プラス「はてな?アテナ」などというタイトルだったので、中身の見当はついていたけれど。記者S氏、でした。S氏からメール貰ったのは2年ぶり。もともとスポーツ系記事がお得意だったので、今回もギリシャへ取材に行ってるんだとか。S氏のことはさておき。この人からメールが来る時って、何か転機になる事が多い。このS氏がキッカケとか、そういうのではなく。メールの関知しないところで、何かが起こるという感じ。何か、「いいこと」あるといいなぁ・・・。
2004.08.20
-
ユウ先生、ありがとー!!
いきなり何?といわれそうですが。先日、とあるイラスト募集に応募した・・・という話の続きなんですが。載っちゃいました。しかもコメント付きで(うきーっつ☆)。因みにココです。掲載+コメントに、かなり・かな~~り舞い上がりました、ハイ♪でも、先生・・・リンク張ってくれてないのよねー。しくしく;あんましデータ公開とかやらないんだけど、今回は調子に乗って「大公開」(エイヤッ)使用画材:漫画原稿用紙(A6サイズ DELETER)、ピグマ 0.1(サクラカラー)スキャナ:Canoscan D1250 U2F(CANON)ソフト:PhotoshopElements(for Win)所要時間:下絵含め3時間弱(故にアラが・・・)
2004.08.19
-
Gerdenia
梅雨の中休みの晴天。庭の梔子が花を付けてました。まだ2輪程度しか咲いてないけれど、近くに寄ると上品な甘い香り。甘い芳香を放つ花は数あれど、梔子の香りは私にとって「別格の香り」。私にとって、憂鬱な梅雨の季節の、たった一つの慰めであるからだ。天の蒼に、白い花がよく似合う。<香りの記憶>「香り」の記憶は、いつまでも頭の中に留まる。多分、香りを感じる神経が、直接脳から伸びている所為だろう。一番古い香りの記憶は、「クレゾール」その他の消毒薬の香りだ。それは外科に勤めていた母の香り。その為、「石鹸の香り=母親の香り」という、ありがちな公式が私の中には無い。今でも没薬(ミルラ)などの「薬臭い香り」に懐かしさを感じる。 <生花の香り>高校あたりから、HERMESの「AMAZON」を皮切りに、「香り」をコツコツと集めている。おそらく私の収集癖のなかで、一番長続きしてるのは「香りの蒐集」だろうと思う。切手の収集も小学生の時までだったし、便箋やシールの収集は、もっと早くに止めてしまっていた。確かにどの香りにも愛着がある。そして、それにまつわる思い出も。けれど、梔子の香りには「全くその通り」といえるだけの、完成度の高い香りに出逢っていない。先日たまたま見つけたネットショップで「生の花に近い香り」を扱っていると聞き、ワイルドローズ(芙蓉)と、マグノリア(木蓮)、ホワイトローズ(白薔薇)を購入した。確かに、生の花に近く、これまでの香水と違い、香り立ちが優しい。これは是非梔子も手に入れなければ、と思っていたら「品切れ」になってしまった。残念。入荷は少なく見積もって、あと1月以上と言ったところか。。。運良くその香りを手に入れられれば、いつでも「梔子の香り」に再会出来る。憂鬱さを幸福な気持ちに変える、香りに。 おまけレンズの洗浄液が残り少なくなったので、TSUTAYAの会員更新がてら買いに出かけた。とりあえず更新を済ませて・・・ついでに「バリスティック(02、米)」と「ある貴婦人の肖像(96)」の2本をレンタル。更新特典で1本はタダ。その後、郵便局に引き出しに行くと・・・先週に引き続きナンパされる。しかも今度は外国人(ラテン系)。。。オイラにどういう隙があるのか?と問い詰める相手が居ないので、仕方なく自分に問い詰めて凹む(苦)。ついでに持病の頭痛まで発生し(以下略)しかも凹んだ挙句に洗浄液買うのを忘れてた。あーあ。。。
2004.06.13
-
なんちゃって鑑定士、な一日。
というわけで、昨日の続き。昨日、「ネタ拾い」がてら聴きに行った講演会では、簡単な「筆跡鑑定」についても触れられていた。「筆跡鑑定」については、あまり説明の必要は無いかもしれないけれど、イロイロな人の筆跡と人物像を照らし合わせ、筆跡から人物像を鑑定するもの。講師の鈴木氏によると1.筆跡には各人ごとに固有の傾向が表れる。2.筆跡は人間の行動の一つであり、その行動結果の痕跡である。3.性格とか人格というものは行動を離れて独立した実態があるわけでなく、実は各人ごとの行動のあり方、すなわち各人ごとの固有の行動傾向といってよい。4.各人ごとの固有の行動傾向は日常生活上の各種の行動にほぼ同質的に表れる。書くという行動に関しても同じである。5.したがって書かれた痕跡すなわち筆跡に表れる特徴を見れば他の日常行動も推定できる。(講演会資料より、原文ママ)こういわれると、かなり説得力がある。因みに私の筆跡の場合、几帳面お金が入ってくるけれど貯まらない(ザル)アイデア・ユーモアに恵まれる自分の欲求を追及する華やかさが好き平凡さが嫌いスペシャリスト(=専門職)である料理が上手、叉は刃物の扱いが巧い、鋭さがある(刃物運)集団のトップではなく、トップを補佐するNO.2の器自分じゃ当たってるな、と思うんだけど。「鋭さ」を現す筆跡は、かなりの頻度で出てくるし、実際「おクチの鋭さ(『超絶技巧』じゃなく、毒舌っぷり)」は磨きがかかる一方で・・・。ことあるごとに書いてるとおり、金遣いは荒いし。ファッションは「華やかさ」を通り越して、最早「歩く人食い薔薇」か「食虫植物」(あ、こっちの方が近いな)っぽくなってるし・・・。←ヒカリモノ&フレグランス好きに拍車+院長には「チーママ」呼ばわり。。でも、ちょっと発見。昔書いてた「字のクセ」では、「責任感皆無」に近かったのに、社会人になってからの、特に最近身に付いたクセで、「責任感」を示す相が出てた事。もっとも、社会人になってから「責任感皆無」じゃ困りモノだけれど。今日、事務所で訪問記録のチェックをしてて、ふと昨日の講演の中身を思い出しつつ各人の記録を見てみると、これが面白いほど当たってる。私のほかに「刃物運」(剣の達人にも見られる。宮本武蔵、沖田総司など)が出てる人がいたけれど、この人は本当に料理が巧い。短い時間で凝ったモノを作れる人なのだ。他にも「几帳面さ」「物事を引きずりやすい」特徴が出てる人は本当にその通りの性格で、いつも通りの記録にも関わらず、読んでいてニヤニヤ笑いが止まらなかった。因みに。ウチの事務所には「天下取り」の器は居ないみたい。もしかしてウチの事務所って、烏合の集団??・・・とは思いたくないなぁ(^_^;)まぁ企業じゃないから、天下取る必要もないですが(ていうか取っちゃダメ)。さぁ、明日は「美肌ドック」の日。肌年齢が幾つと診断されるか、かなりドキドキ。。。あと、お腹の調子がイマイチなので、以前入院した「コスプレ外科医」のところへ行って来ます。ヨシ、これで明日のネタはOKさぁ!!(本当かよ・・・汗)おまけ2週間ぶりにペインに行く。ペインの医師に「どう?元気にしてた?安定剤は止めてるんだよね?」と言われ、「なんとか気力で乗り切ってますよ。『病は気から』ですから」なんか、皆絶句してました。 私、悪い事言った???
2004.06.11
-
「スキャンダル」見ちゃったよ。
ダメダメモード炸裂中だけど、週末を無為に過ごすとあとで余計に凹むので(悪循環スパイラル状態。。)、「スキャンダル」を見てきました。ついでに2週間前から止まりっぱなしのGUCCIの時計もオーバーホールに出して。これまたついでにナンパされた・・・。あの~、ナンパされて凹むのって私だけ?なんかね、自分はそんなにスキだらけの格好してるのか?って。でもって、冴えないナンパだったんで余計に凹みました。(でも、オペラとか声楽とか聞きにいってる時なら悪い気しないんだよね 謎)気を取り直して「スキャンダル」。お話が「時代劇」なだけに、ヨン様も両班(かつての支配階級。因みに字幕では「貴族」と訳されてた)姿。コレはコレで良しとして(個人的には髭が;)。劇中のプレイボーイっぷりもなかなか楽しいです(昔の漫画みたいで)。あ、それから。劇中でヨン様の描く春画が、かなり凄いです。完全に枕絵状態ですね(というかそのまんま)。江戸時代の枕絵だと男性自身が大根並に描かれてて、漫画っぽくて笑えますが、ヨン様の春画はそのあたりリアルです。って、何書いてるんでしょう・・・。(しかも予備知識まで動員してるしさ)途中である程度展開は読めちゃいますが、映像はキレイでそこそこ楽しめました。それから、誰が「一番オイシイ目」をするか、予測しながら観るのも面白いかもしれません。それにしても、館内は女性ばかりでした。しかも30~40代くらいの女性がほとんど。中には奥さんの付き添いの男性も若干(苦笑)次は「真実のマレーネ・デートリッヒ」あたりにしようかな・・・。今、ふと思い出したんだけれど、「スキャンダル」のモトネタになってる「危険な関係」って本国あたりで映画化されてなかったかな?と思い、調べてみると・・・。ありました、「危険な関係(88年、米)」。タイトルは原作と同じ。コレです、私がいつか、深夜放送で観たものは。断片的には覚えてるんですけれど、若き日のキアヌとかも出てるらしいので、レンタルして見比べてみようっと。(実は作品名のところにリンク貼ってたけれど、楽天以外のリンクだとはじかれちゃうのです;キャストなど詳しい内容はamazon、gooなどで御覧になれます。因みにgooのは「ネタバレ有り」なので要注意です)
2004.06.06
-
KILL BILL観ちゃったよ。
という訳で、なんとか新作棚に並んでるうちに借りてきました、「KILL BILL」。「借りてまで観るほどか?」という辛辣なコメントも目にしてたので、ドキドキしながら観ましたが・・・面白い。。ツボですよ、ツボ!(以下、ネタバレ有り?なので要注意)日本の描写が変なのはまぁ仕方が無い・・・というか故意にやってると思われ。(先日TVでやってた「WASABI」の冒頭の弁護士事務所の描写も妙だったが、日本らしさを出す為に故意にやってる事は後のシーンを見ると明らか)千葉真一、ちょっとしか出ないのに、カッコいいし(くぅ)。ユマ・サーマンの100人斬りのシーンが、昔のチャンバラ映画みたいで笑えるわ(他にも殺陣のシーンは同じようなノリ「バッサリ」→「ぷしゅ~ッ」って感じ)、あと栗山千明の「ゴーゴー夕張(この名前だけはどうにかして;)」の「においたつ妖しさ」にメロメロ。鉄球振り回しアクションに「萌え」だし(基本的に日本刀萌え、な私だけど)。それから、ルーシー・リューの着物姿も素敵☆だし。基本的に昔の時代映画とかが好きなのか?それに対するオマージュをこめて作ったのか?と思って見てたので、変ではあるけど楽しめました。が、基本的に流血描写が嫌いな方にはオススメしません♪さぁ、VOL.2がどう展開するのか楽しみ!後で気が付いたので追加:イロイロと「元ネタ」があるようです。詳細はこちら。↓http://www.eiga.com/special/killbill/02.shtmlBGMなんかはどっかで聞いた事があるような、と思ってたら納得。千葉真一の役名は「影の軍団」からパクったのねぃ。更に納得。。。
2004.04.26
-
「イタメシ」の謎。
きっかけは数日前。此処のBBSに寄せられた情報、それは「イタリアにはイタニシキ、ミラノ小町などのブランド米が存在する」という噂。イタリアの有名な米料理といえばリゾット。リゾットに使われてる米にそういう銘柄があるのか?と思い調べてみる(職場で昼休み中にやってる事なので、詳しくはないが)。サーチする際の単語の選択に問題があったのか・・・とりあえず、わかった事だけ↓◎米の品種遺伝的な流れと形から、ジャポニカ米(短粒種)、粘り気が少なく細長いインディカ米(長粒種)とジャワ原産のジャワニカ米(短粒種。中粒種と記載の場合も有り)の3種類があり、現地であるイタリア本土で栽培されてるのは、主に「短粒種」との事。しかし「短粒種」とだけあっても、ジャポニカなのか、ジャワニカなのか。書いてある事がマチマチの為、不明。(栽培してる方のページにはジャポニカ種とあるんだけどね、別の料理のサイトを見ると、「ジャポニカ米では、リゾット作った時に柔かくなりすぎる」などの記載があったのさ)銘柄を調べてみたけれど、それっぽいのは見つからなかった。。というわけで、情報求む。追記:パスタでおなじみ、茹で加減の「アルデンテ」。「(歯で)噛む感触が判る程度の硬さ」という意味合いだが、リゾットの場合も同様。煮えた米粒を噛むと、芯が残ってるくらいの硬さにするのが望ましいとのこと。以前、ヴェネツィアで食べた「イカ墨」と「バローロ風味」はいずれも硬く、気合を入れて噛まないとダメという、正に「スローフード」そのものだった。。。(その後のリサーチで「リゾット用に改良された米がある」という事が判明;)
2004.04.13
-
お隣の国の思い出など。
今更ながら「冬ソナ」にハマッた私。N○Kの公式サイトや、冬ソナ関連のページを閲覧しては悦にいる日々。。。ふと、ソウルに行った時のことを思い出したので、思いつくまま書いてみる。<冬のソウル>1月の半ばに行く方もどうかしてるのかもしれないけれど・・・金浦空港に降りた時も寒かった。滞在中一番温かくてマイナス15度。震える私と対照的に、現地ガイドのチェさん(妙齢の女性)はセーターとコートだけという薄着。慣れらしいです、ハイ。<街>ソウル市街の印象は・・・東京よりも建物が広々と建ってる印象。冬らしく空気もピンと張り詰めた感じ(マイナス15度だから当たり前か)。そんな中を、タクシーやバスを使いながらチョロチョロと歩き回る。南大門市場の辺りは活気がある印象。沢山の屋台が建ち並び、様々な種類の食べ物の匂いが漂ってくる。甘いにおいにつられて煎餅を買って食べながら歩く。蚕の屋台もあったけれど、サスガに手が出なかった。南大門近くのメガネ屋「カナメガネ店」で、メガネを作る。ちゃんと視力も測ってくれたので度はピッタリ。帰国してからコンタクトの度を、この時作ったメガネに合わせた。その後、東大門近くの「ミリオレ」に買い物に行く。日本のデパートの印象よりも何処か気さくで、所狭しと服・靴・下着・バックなどが並ぶ。売り子さんも気さくに声を掛けてくる。しかし試着する場合、試着室が無い為、商品をトイレに持ち込んで試着しなければならなかった(今はどうなんだろ?)。東大門付近にはスポーツ用品店が並ぶ。NIKEなんかもあり、好きなヒトにはたまらないんだろう(私は見てただけ)。<夜遊び>泊まったホテルがウォーカーヒルだった事も有り、ホテルの中のカジノで遊んでみる。バカラやルーレットなどなどイロイロあったけれど、詳しい遊び方が判らなかったので、とりあえずルーレットに。かけ方のバリエーションが何通りかあるけれど、一番かけやすいのは「赤」か「黒」、「奇数」か「偶数」、「0」。色と数字がピタリと一致すると掛け金が30倍に跳ね上がるので、やはり「ピタリ賞」を狙いたくなる。狙ったけれど、当然ハズレ。でも、連れのIさんが「ピタリ賞」を見事に当てたのにはビックリした。私は最高で3倍まで。欲を出すとダメみたい。<健康的>名物のサウナに入ってみる。こちらのサウナは汗蒸幕といって、乾式のサウナなので、蒸気ムンムンのサウナがダメなヒトでも苦しくはない。チマを着た「おっかさん」っぽい女性がコースを尋ねてくれるので、コースの希望と垢すりの希望を伝える。汗蒸幕にやってきた時間が9時頃とあって、中はそれほど熱くは無い。中で火を燃やした後などは、麻布を被って横にならないと熱くてたまらないらしい(天井に向うほど温度が高い為、姿勢を低くする方が熱くない)。中に座って10分ほど身体を温めて、頃合を見計らって外で水を飲んで休む。それを何度か繰り返し、地下の風呂場に下りる。地下の風呂場には人参風呂があり、そこで身体をふやかしてから垢すりに行く。垢すりは、腕っ節のいいお姉さまが下着(汗だくなので、スケスケ)もしくは水着姿で迎えてくれる。垢すり後はヨモギ蒸しやマッサージ、顔の産毛取りなどをお好みで行う。私は軽めに垢すりした後、マッサージを受ける。様子を伺いながら施術してくれるので、痛くもなかった。夜ということもあり、外はマイナスの寒さだったけれど身体の心からポカポカ。冷え性にはお勧めと思われる。因みに男性もOKの所もあるそうだ。が、その後私は「湯中り」してしまった。。。(のちダウン)<参鶏湯>で、湯中りの為かダウンした翌日。参鶏湯を食べに行く事になった。チェさんイチオシの「高麗参鶏湯」というお店に行く。専用の雛鳥のおなかにもち米・棗・人参を入れて、ぐつぐつと煮込むもので、現地では暑い時に精をつける為に食べるとか。アツアツの「本体」に付属の塩・コショウで適度に味をつけながら頂く。ただし、人参については食べない方がいいという。というのは、人参が鶏肉や米などに含まれる「陰」の気を吸っているので、人参を食べたら陰の気を取り入れてしまう為元も子もなくなってしまうとのこと。「陰」の気が抜けたためかどうか、スープも雛鳥の肉も非常に美味だった(ダウンした為、全部食べられなかったのが悔やまれる)。チェさんのイチオシのお店はどれも素晴らしい味で、滞在中は食事に不満を覚える事が無かった。追記:「イタメシ」ならぬ「イタ米」ネタはリサーチ中。しばし待たれよ。。(つーことで、待っててね。COCOさん)
2004.04.12
-
なんだか、カミーユに縁があるな。
先週の「美の巨人たち」に続き、今週は「永遠の恋物語」でカミーユ・クローデルがテーマに。個人的にロダンとカミーユの作品好きなので、今日も要チェックですな。ロダンの「接吻」と「ダナイード」とかが、なまめかしくて好き。 やっぱ、シモネタ大好きのエロ人間(爆)なので、ちょいエロ入ってるのが好きですね。絵画でも風景画や静物画より、人物画に惹かれるのはそのためかもしれない。 先週末に借りてきた「まぼろし」(01年、仏)は何時見よう・・・明日は返却日なのに(苦)しかも明日は朝から研修なんだけどな。。 「永遠の恋物語」は番組としては、ちょっとつくりが甘いような感がある。「美の巨人たち」の方が、取り上げた作品や作者の生き様を壊さないように構成できてると思う。(あくまでもテーマとなる作品と、その作者がメインであり、番組内で展開する物語は狂言回しが演じているようなものだが、毎回違う物語が展開するのでそこそこ楽しめる)そこそこ知名度のある俳優をもってくればOKなんて思ってない?ひょっとして。。なんて、邪推をしてしまった。
2004.02.20
-
買っちゃったよ。。。
日曜にボード初体験で、その味をしめた私。とうとう買っちゃいましたよ。。。ブーツとビンディングと板。これでウェア買ったら、10万は軽く越えてしまうな(-_-;)ブーツはBURTON(ボーダーには言わずと知れた老舗)のRULERで今期モデル。店員のお兄さんが付きっきりでブーツ選びに付き合ってもらい、違うブランドのものも含めて、5足くらい履き比べてみる。スキーの老舗SALOMONのもあったけど、踝が当たるので断念。ボード用のブーツは、通常靴と同じようにレースアップして履くようになっているので、イチイチ紐を解いて・絞めて履かなきゃいけない。普通は試着する時も自分でやるんだけど、このお兄さんがすんごく親切で、「ひざまずいてブーツを持ち脚を入れて履かせてくれる」わけ。。。多分「ひざまづかれる」という状態に酔ってたな、自分(爆)板とビンディングはKISS MARKのANGELKISSを購入。板の表と裏に天使の顔がプリントされてる(私に似合わんような少女趣味な感じのデザイン;)板そのものはロシニョール(スペル忘れ)の「ブルーの金魚」の板にするか迷ったけど、予算の関係もありこちらに。KISS MARKのステップイン(脚を乗せるだけで板とブーツが固定できるタイプのビンディング)も気にはなってたけど、実際に専用ブーツ履いて、ステップインに乗ってみたけれど、安定感にやや不安が。。。ミカがステップインを勧めなかったのが何となく判った。また週末に雪が降ったらいいな~(ただし仕事に差し支えない程度)そんでもって、ミカと休みの都合が合えばいいんだけどな。(欲を言えば、Kさんとの約束にかぶんないといいんだけど 苦笑)
2004.01.20
-
生存確認。
とりあえず管理人、生きてます☆前回の日記(8日付けだよ、嗚呼)が思わせぶりな文章で終わってるだけに、続きを期待してくださってる皆様には「お待たせしました」なのか、はたまた「ご心配かけました」なのか。とりあえず、彼には逢ってきました。多分(これまた)数日後にこっそりUPしてることでしょう(笑)クリスマスプレゼントのお返しまで頂いてしまい、結構嬉しがってたりして。しかし、ちょっぴり脱力もしつつ、2日ばかり彼の部屋で過ごしました。その後は、あれだけ鬱ってたのが嘘のように、アクティブにばたばたと過ごしていました。土曜はH医師の診察らしくない診察(苦笑)を受け、日曜には「ボード初体験」したし。この冬はボードにハマリそう(今更ながら)。。。今日も仕事帰りにイロイロ物色して、結局まだまだ検討中。どうしよう・・・この調子で行くと、彼よりもボードにハマリそうだ(やばっ;) PS.BBSに温かいメッセージありがとうございました。ぼちぼちお返事書きますので、気長にお待ち下さい(はぁと)
2004.01.19
-
ボードにGO!
と言うわけで、旧友ミカとアキちゃんに誘ってもらってボードに行ってきました!社会人になってから元彼の影響でスキーを始めて、雪焼けと戦いながらほぼ毎年彼と雪山に繰り出していた。一昨年は私の体調不良の為、大事をとってスキーはお休み。去年はその彼と別れた後、休職しててとても雪山どころではなく。2シーズンもブランクがあると、少々不安なところもある。それでもボードに関しては、何せ「初体験☆」だったりするから、ワクワクする。ミカは今シーズンでボード歴5年。やはり5年やってるだけあって、器用にターンしながら軽やかに斜面を降りていく。立ち方と転び方、体重の乗せ方をレクチュアしてもらい、5本程度滑った。途中休憩しながら滑ってたはずなのに、4本目辺りから膝に力が入らなくなってきた。5本目はコントロールが効かなくて散々転びながらロッジまで行く羽目に。。。やっぱり、初めてということもあり、余計な力が入りすぎてたんだなと思った。(スキーなら10本は行けるのに;ちょっと悔し)4本目の様子を見ていたミカが、ロッジに帰ってきた私を見るなり「疲れたんじゃない?今日はコレで上がろうか?」と言ってくれて、素直にこの日は上がることにした。ミカもとアキちゃんが滑り足りないんじゃないかなと思って「私はロッジで休んでるから、2人で行っておいでよ」と言ったけど、「時間も早いし、一旦帰ってカラオケでも行こうか?」というお返事が。。。ミカよ、カラオケに行きたかったんだな(脱力)←ミカはカラオケ好きスキー場からの帰り、自分では気づかなかったけれど相当疲れて痛みたいで、移動時間の半分くらいは眠ってた。その後、折りしもフリータイム実施中のお店で3人で2時間半歌いまくった。アレだけ眠かったのに歌うと眠気が飛ぶ。それしても、ミカとアキちゃん元気過ぎ。というか、私が体力(スタミナ)無さ過ぎなんだな、きっと(涙)ミカからの次回の課題:次はターン~ジャンプをやろう。チワワには負けるなよ♪←無謀
2004.01.18
-
いつも通りのダラダラ正月。
元日から稼動したので、今日はいつも通りの「ふやけた正月モード」で過ごす事に決定(苦笑)特に観たい番組もなく、ちょいと気になる番組も深夜に集中(まぁ、主に洋画ですが)してるので、昼間はビデオ鑑賞。「世界の涯てに」(96年、香港)と「The Rose」(79年、米)を続けて観る。最近、韓国映画がアツイらしいけれど(「冬のソナタ」とか)、マイベストアジアンムービーな一本が「世界の涯てに」なのです。哀しいけれど、希望に繋がるラストは必見。「つまり、命こそは魔術であり、人は皆、魔術師なのです・・・」主人公のモノローグが沁みます。。ジャニス・ジョプリンをモデルになってるという、「The Rose」。ベット・ミドラーのパワフルさ(歌いっぷりとか)を感じつつ、ラストで脱力。。。ラストの「ローズのテーマ」は昨年末に平井堅がカヴァーしてましたね。ストレートに響く歌詞がイイですね。残りの休みはあと1日。どう過ごすか考えながら、YO-KINGを聞き、一日終わってしまった。
2004.01.02
-
HOLY SMOKE
たまたまTSUTAYAに立ち寄ると、新作の棚に「ホーリー・スモーク」が並んでいた。「ピアノ・レッスン」以来、ジェーン・カンピオン作品に嵌ってる私は、当然、即座に中身を掴んでレジへダッシュ。映画そのものは99年のヴェネツィア映画祭に出品されたものなので、単にヴィデオ化が遅れただけ。新潮社からノベライズされたものも出てるので、私は先にこちらを読んだのだが。<あらすじ>インドでの旅で、カルト教団の洗脳を受けたルース(ケイト・ウィンスレット)。父の危篤を偽ってようやく彼女を連れ戻した家族は、プロの脱会カウンセラーPJ(ハーヴェイ・カイテル)に彼女を託す。砂漠の中の一軒家にこもり、PJはルースに洗脳をとくためのプログラムを開始する。ハーヴェイ・カイテル、今回もいい味出してます(役者として、ということで)。彼の変容っぷりはまさに「逆転移」とでもいうか。。。そう言及していいのかどうかは、少し迷う所だけれど。そんな粗筋の所為もあって、ちょっと気になる作品(-_-;)(どうも楽天の調子が良くない・・・実はこの日記、もう一度書き直し&UPなのです)
2003.12.28
-
御法度。
日曜にTVでやってたから、見ましたよー。大島監督+坂本龍一+ビートたけしの組み合わせは「戦場のメリークリスマス」以来でしょう。お話自体は司馬遼太郎の原作を読んでたから知ってたけど、松田龍平がねー、アヤシー感じでグゥ。それから、衣装のワダエミ。新撰組の「浅黄色のダンダラ模様の隊服」っていう概念を見事にぶち壊してくれた。今回デザインされた、黒一色の隊服はモダンであり、「戦う男の装束」としてのリアリティを感じさせる作り。大島監督、まだまだやれそうな感じがしたので、次回(あるのか?)にも期待。(と言いつつも、鈴木清順とどっちがポックリいくのだろう?とロクでもないことを考えてしまう私;)新撰組の中の局中法度には「隊を勝手に抜けてはダメ」「勝手に金策するな」「私闘はやっちゃダメ」「武士道に背くような事はNG」という具合に規則があったのだけど、不思議な事に女性に関する事が全くない。男ばかりの隊の中で、女性をめぐって私闘でも起きないのか?という疑問は未だに私の中にある。そういや、来年のNHKのドラマ、新撰組らしい。果たして誰が、土方を演じるかがすんごく気になる。。。
2003.09.22
-
サティはお好き?
そーんなワケで、今日はサティの話。小学生の時からナニゲに、私の音楽の趣味の中に食い込んでるのが、サティの楽曲。キッカケはファミコンのゲーム。迷路の端っこに離れ離れになったペンギンのカップルを迷路の真中で引き合わせるというパズルっぽいゲームなんだが。案外コレが嵌った。このゲームのBGMが「あなたが欲しい」だったのだ。もっとも当時は曲名はおろか、サティがどういう作曲家かなんてなことは知る由も無く。この曲のことも気にしながら、ピアニカでポール・モーリアの「恋は水色」、S&Gの「サウンド・オブ・サイレンス」やシュトラウスのポルカなどを弾きまくっていた(勿論、ピアニカ用に編曲済みのヤツです)時は流れて。中学の時。日曜の朝、TV東京系のチャンネルで美術系の番組をやってた。その中で、聞き覚えのある音楽を耳にする。そう、「あなたが欲しい」の歌詞つきバージョンだった。現在、サティの曲を集めたアルバムが3枚手元にある。パスカル・ロジェ、フィリップ・アントルモン、ランベルト・デ・レーヴ・・・収録曲が微妙に違うので結局3枚揃う事となったが、同じ曲で聞き比べるも楽しい。演奏する人間の解釈によって曲調も変わる、とは聞いていたが、サティの曲には他の作曲家と違い、スコアに「怪しげな演奏指示」がかかれている為、曲調の違いがもっと明確に出るようだ。最近、ケータイの着信音のバリエーションに「あなたが欲しい」「ピカデリー」と「ジムノペディ」を加えた。「ジムノペディ」は誰かさんとオソロイ、を狙ってやってるんだけれど・・・曲がユックリ過ぎて「私的着信音」には向かない、と判断。その後、イロイロDLしてみて・・・結局「ワルキューレの騎行」に今のところ落ち着いてます(爆)
2003.09.10
-
ビデオ三昧。
先週、近所のTSUTAYAが1本100円レンタル(ただし旧作のみ)を久々にやってたので、3本借りた。んがっつ、帰宅してから「さて、見るか」という気持ちにもならず、金曜日まで3本とも放置プレイ。。。返却の迫った金曜の23時ごろからやっとこさ、見始める始末。パトリス・ルコント監督の「フェリックスとローラ」を見終わった所で、一旦就寝。9時起床。次はゴダール監督の「気狂いピエロ」。ラストの台詞が・・・ランボォでしたな。しかもTOPに飾ってる「地獄の季節」からの引用(はぁと)ゴダール監督の作品は初めてだったけど、台詞回しとカメラワークが中々に気に入りました♪今度は「決別」くらいでも借りてみよう(公開当時は結構話題になったらしいです。とある理由で;)続いて、「スィート・ノベンバー」。主演がキアヌ・リーブスだったんだ;テーマになってる「ONLY TIME」をENYAが歌ってることが興味のキッカケだったんだけど。もう見たヒトも多いと思うけど、ルコントの「髪結いの亭主」を思い出したな。なーんか、美しい自分を覚えてて欲しいとかいう台詞が、ね。切ない1本でした。。。昼から返却に行って、今度は再び「時計仕掛けのオレンジ」か「O嬢の物語」か・・・あと「DOLLS」もまだ見てないな、と物色してたら、デュラスの「愛人」の続編(というかメイキングに近い?)に当たる「愛人ー最終章ー」があったので、思わず手に取りました。ジェーン・マーチ演じる少女時代のデュラスと、レオン・カーフェイの華僑の青年との話には、正直泣けた。あと、ジャン・ジャック・アノー監督。巧いっス。ジャン・ジャック・アノー監督モノではウンベルト・エーコ原作「薔薇の名前」もヨカッタ!「セブン」とテイストが少々似てるお話だけど、中世の僧院が舞台だけに現代劇とは違うオモシロさがある。分厚くて活字の小さい(笑)原作を読んでから、ある程度予備知識があるとスゴク楽しめる1本です。(ショーン・コネリーは「頭が薄いので剃らなくても坊さん役ができる」と言うネタは全て却下(爆)話は戻って。ゴダール監督の「決別」を見つけたけれど、その前にやっと「DOLLS」を見つけたので、今回は見送り。あ"-、ソレニシテモ。何で「時計仕掛けのオレンジ」が見つからないんだろう!?ひょっとしてDVD版だけしか置いてないのかな??
2003.09.06
-
ウチの王子。
「幸福の王子」を見ていた。最初は、主人公がモックン(この言い方で世代がバレる;)ってことと、劇中の彼の職業が医者という事で、何気なく見始めたのだけど。。。次々と不幸になる周平と海の話に毎週クギ付け。更に、トドメはミスチルの飾るエンディング。泣けるぜ。。。TVを見てたら、PCの横で充電中のケータイが鳴る。しかも着信音が「Ring」。昔は22時には寝るとか言ってたクセに。1日に電話したばかりだし、この日は電話してないのに。何だろ?「もしもし?起きてた?」寝てたら出られません(@心の声)。まだ23時を半分回ったばかりだし。「うん、起きてたよ。いつも通りね」「いつもこの時間は起きてるの?」「そう。それに今日は『幸福の王子』やってるし」「あー、今日なんだ?じゃ、TV見てるから切った方がいい?」「なんでそんな事言うの?いいじゃん、別に。ドラマくらいどうでもいいよ。それよりも先生の話が優先でしょ?」ドラマ見てることを話すと、少し拗ねた言い方してた。いいよ、別に。ドラマ見れば?って感じで。あ"-、可愛いなぁ、チキショウ!(爆)←実はこういう風に拗ねられると弱い;「今、部屋からかけてる?お家に帰ってるの?」「うん、今日は帰ってきてる。今日はね、沢山飲んでた」「どしたの?誰かと飲んでたとか?ひょっとして、仕事先のヒトとかと?」「ううん、一人でね。明日からハードな当直続きの日が続くからね・・・」そりゃ、当直室で飲めないからね。。飲み溜めといったところか?続けて「当直予定のお知らせ」を頂く。聞いてないのに、イチイチ報告してくる所が可愛いなぁ(微笑)!ああ、可愛いついでに。かぼちゃパンツ(笑)に白のタイツで「王子コスプレ」させて写真とってみたいなぁ。。。←妄想。その後、王子殿は眠気を訴え、サッサと眠ったみたい。私はというと。疲れてるくせに大脳の緊張が取れないようで、1時頃まで布団の中で眠気を待ちつづけることとなりましたとさ。とほ。
2003.09.04
-
ようやく見ました。。。
やっとこさ、マトリクス見ました(苦笑)中々見に行くヒマもチャンスも無かったので、本日午後から映画館へGO!この際なので、どっぷり一人を楽しむ事に決めましたわよ、ええ!明るい色の服の方が、気分も明るくなるかなー?とは思ってたけれど、どうせ「マトリクス」なんだから、と全身黒で固めました(笑)ピタ系の黒のジャケットとパンツで。メイクはベージュ系。因みにバックは最近購入したばかりのLVマルチカラー(これまたブラック)←やっぱ、この格好チーママかぁ(爆)!?トリニティ、美人だったなー(溜息)ああいう、エナメルのツナギが似合う女になりたいものよのう。。。←かなり厳しい;「マトリクス」のトリニティーや、「トゥーム・レイダー」のララとか、美人でとにかく強い女には憧れます。昔から王子様を待つだけの「か弱いお姫様」には、あまり魅力を感じなかったのです。幼少期の度重なる「置き去り体験」のため「誰かに助けてもらう事を当てにはしていちゃダメ」っていうのが焼きついてるんだろう、きっと。帰りにTSUTAYAへ。土日限定でビデオ・DVD・CDが1本100円(ただし旧作のみ。いづれもお一人様4本まで)最初は、大好きなパトリス・ルコント監督作品の1つ「髪結いの亭主」とキューブリック監督の「時計仕掛けのオレンジ」を借りるつもりだったのに、結局ルコント監督の「フェリックスとローラ」、ゴダール監督「気狂いピエロ」「スイート・ノベンバー」(監督名失念)を借りる。多分明日以降、ボチボチ見ることになるでしょう。その脚でジャスコのMAXFACTORブースで秋の新色をチェック。でも、丁度今使ってる色と同じ色調なので「私ってナニゲに先取りしてる??」とちょっと優越感←勘違いその後ingのパンプスと靴のケアグッズを購入。たまたま、欲しかったデザインで、24.5だったので足を入れてみると・・・ワイズ(足囲)もピッタリできつくなく、シックリと足に馴染む。かかとも高すぎないから背が高くなりすぎず、世の男性諸氏の脅威になることも無い(オオゲサ)。と、いう訳で即買い(爆)しかも財布の中身があと僅かなのでカード使っちゃいました。あはは。
2003.08.30
-
クリムト~1900年ウィーンの美神展~
と言うわけで、行ってきましたクリムト展!!クリムトと言えば、有名な「接吻」などで知られる画家。「一番好きな画家は?」と聞かれれば、少しためらって私は彼の名前を挙げるだろう。私の中では「誰が一番なのか」ということはどうでもいいこと。クリムトにはダ・ヴィンチやラフェエロには表現出来ないスタイルがあるから(あえて比較の対象にするのもナンセンスなのだが)。彼の絵にはしっかりとした描写力と観察力、そして其れを彼なりの様式へと昇華させる力があった。其れが私の心を16年以上も捉えている理由だ。エロスとタナトスの画家。彼はしばしばこう呼ばれる。彼の絵の中には、肌も露な美女が恍惚の表情を浮かべている。あるものは男の接吻を受けて。あるものは敵将の生首を携えて。性の恍惚の向こう側には、暗い淵がある。其れは高みから一気に突き落とされ、地底に打ち付けられ、苦痛のうちに現実感覚を呼び覚まされる感覚であろうか。人は其処に一種の虚無を見る。「接吻」を思い出して欲しい。恋人の抱擁と接吻を受けて恍惚の表情を浮かべる女の足元を。足元の地面を覆う花は、彼女の足元で消えている。つまり、彼女達が居るのは崖。今ある抱擁と恍惚は、彼女が目を開けた途端に崩れてしまいそうにも思える。古来から永遠を象徴する金色の輝きに包まれて、永遠に続くと思える愛の愉悦も、また儚いのだろうか・・・。(ネタバレあり?これから鑑賞に行かれる方は要注意)図録で確認する限り120点程で、点数としてはとても多いというわけではないけれど、彼の作品の中でもかなり有名なものが多い事がマニアにはたまらない。「黄金様式」の傑作の1つともいえる「ユディットⅠ」や同じく金彩を施され、彼の方向性を決定づけた「ヌーダ・ヴェリタス(裸の真実)」「パラス・アテナ」。そして彼が生涯親密な関係を持ちつづけたという女性を描いた「エミーリエ・フレーゲの肖像」。そして彼の製作過程を垣間見せるデッサンの数々。彼が生涯に描いた素描は2000とも4000とも言われていて、それだけの枚数があるのは、彼のアトリエに「裸になってポーズをとるモデル達が数人常駐していた」ことにもよる。そんなモデルをゴロゴロさせていた所為か、彼が亡くなった時には彼の子を自称する者が14人も現れたというのだから、作品の製作がてら別の「セイサク」(自由に漢字を当てはめてクダサイ。。)も手は抜かなかったのであろう。そして圧巻は延べ35mの壁面に実物大に再現された「ベートーベン・フリーズ」。ベートーベンの「第9交響曲」へのオマージュとして描かれた壁画である。オリジナルは1902年の「第14回分離派展」の為に製作され、会場に据えられたベートーベンの肖像を中心に据え、クリムトの他に20名程の芸術家が出展した。出展した作品は全てがベートーベンへのオマージュであり、展示の為だけに製作されたもの故に、取り壊される運命にあった。が、この作品は様々な経緯を経て現代に生き続け、「苦悩を突き抜け歓喜に至れ」というベートーベンの生涯のテーマを、シラーの詩の世界を歌いつづけている。復元とはいえ、決してバカに出来ない作り(クリムトが製作したときと同じ材料と技法)がなされてることに加えて、マーラー編曲版(実際にオリジナルが公開された時に会場に花を添えたという。。)の「第9」がBGMとして流れてるという、ニクイ演出!私がこの壁面に通りかかった時、丁度第4楽章が流れて・・・結局第4楽章が終わるまで「フリーズ」から離れられなかった;あとは、クリムトとエミーリエの写真や遺品。エミーリエはブティックの経営者だった。彼女はデザイナーであり、経営者であり、そして店の商品を紹介するモデルだった。そして、クリムトの一番親密な女性。結婚する事は無かったが、生涯関係をもち、クリムトを看取ることになる。そんな彼女の衣類を見ていると、現代でも充分イケそうなものもあった。今回出品された「エミーリエ・フレーゲの肖像」は「描かれた服装がイケてない(本当にそう言ったかは謎だが」という理由で、受け取りを拒否されたというエピソードを持つ。デザイナー兼モデルの彼女には絵の中であっても、自分の美意識に反する服装を拒絶したのだろう。今回、この作品に逢えるとは思ってなかったので、かなり興奮。「ヌーダ・ヴェリタス」も会場の終盤を美しく飾ってくれたので印象的だった。(どちらも壁一枚占拠という贅沢なセッティング!特に「ヌーダ・ヴェリタス」に至っては、背景が真紅で金彩がとても映える)他に分離派の画家やクリムトが影響されたと言う画家の作品も何点か展示。ココシュカの真筆を始めて拝めた(南無~)。2年前に島根に分離派展が来たとき以上のスケール。同じ作品に再会できる喜びもさることながら、図録でしか見たことの無い作品に出会えるのは、やはり感動。道に迷いつつ、他の美術館の駐車場係のオジサンに地図を頂いて行った甲斐はありました(実は美術館の建物が新しすぎて、ナビが探せなかった)。私が帰途につく頃には、駐車場の空きを待つ車が建物の周りを取り巻いててビックリ(私が来たときはスムーズに入れたのに;)。なーんか、私がレポやると、説明口調に偏って、展示や作品の「良さ」そのものが伝わりにくいのが残念。。(つか、文章力に問題ありかぁ??)
2003.08.18
-
母からの書置き。
朝、キッチンに書き置きがあった。「3時に出発して、釣りに出かけます by 母」準夜明けでしょーが?ヲイ。つまり前日夕方から勤務に入り、午前1時ごろ深夜の勤務のヒトに申し送りして、2時間近くかけて帰宅。そのまま釣りに出かけたらしい・・・これってほとんどオール@柄にも無くギャル調 状態だな・・・確か若い頃は槍と穂高に登るわ、冬場はスキーでブイブイいわせてたらしいし(娘の私はアンチ体育会系なのに)。。。
2003.08.11
-
sofa
彼は何度か目を覚ました。寝返りを打つときも慎重に、ユックリやったはずなのに。照明を落とした寝室の中で、彼は決して不愉快な顔をする事はなく、むしろその顔はとても穏やかだ。眠りを妨げられた人間のものとは、とても思えないような。9時過ぎに彼は部屋を出て行った。「水分はちゃんと取ったの?寝起きで軽く脱水してるはずだから、キチンと飲むようにね。2時間ほどで戻るから、なるべく早く帰るから。」「うん、いい子にしてるから心配しないで」「お昼を買って帰ってくるから、待っててね」ドアのところまで見送る。そういえば、こういうのって久しぶりだな・・・2時間どうやってヒマを潰そうかと考え、まずは持参した本を開いてみる。「ベロニカは死ぬことにした」と「須賀敦子のヴェネツィア」をガラステーブルの上に置く。ふと見るとガラスが随分曇っている。ガラスの曇りを拭きとって、ついでにシンク周りの掃除をし、調子に乗って水周りの掃除を始める。しかし、完璧にはできないし(洗剤とか道具が不足してるので)、それにあまりガシガシと磨きまくるのも、彼の縄張りを好き勝手に弄ってるみたいで嫌なので程ほどに留める。程ほどに動いた後、ソファに身を預ける。赤いカーペットの上に白いソファ。このソファは中々に座り心地が良く、1人で横になるには丁度いい大きさ。調子にのって身体を横たえて、ソファを独占してみる。いつだったか、ル・クプルの歌にうたた寝していたんだ 気持ちいいsofaのような 貴方の中で・・・なんてな歌詞があったけれど、本当にうたた寝してしまった。彼はそれなりに眠ってたのだと思うけど、私は寝返り一つに神経質になってしまうため、少し眠りが浅くなる。そして自分の部屋に帰ってきたときに、どっと疲れが噴出してしまう。彼の前では疲れは吹っ飛んでるくせにね・・・彼が帰って来たときのドアの音で目が覚めた。彼はガラステーブルの曇りが取れてることに気が付いて、少し機嫌がいいようだった。仕事もつつがなく終わった事もあるのだろう。先程まで私が眠っていたソファに、今度は彼と並んで座る。そこで食事を済ませて、それから少し仕事の話をしてくれた。病院そのものの規模は大きくしなくていいから、患者さんの社会復帰の為のデイケアとか作業所とかを作りたい。それが彼の夢なのだ。今日の講演も彼の患者さん達で結成した自主グループ(患者会)に向けた、一般向けの内容だったのだという。因みにお題は「ノーマライゼーション」。患者自身は病気を上手にコントロールし、社会の一員としてやっていこうとする。それに対し、周辺も病気に対しての理解ができ、地域の中で受け入れようとする。(私の理解と表現がコレで正しいのかについて、少々自信がないが)精神疾患というとまだまだ、偏見も多い。他の診療科の所には行けても、精神科を標榜する所には行きにくいという話は、とても判りやすい例だ。事実私もそうだったから。難しい事だからこそやりがいもある、こうなってくれるといいんだけれど、等と話して聞かせてくれるのを、頷きながら聞いた。忙しくて日々の業務に追われていても、叶えたいものがあることは彼の原動力に繋がるわけで・・・疲れを感じさせず熱っぽく語る彼の姿を見て、私は心底羨ましいと思った。とりたてて、叶えたいものなどなく、日々をただダラダラ送るだけの自分とを重ね合わせ、恥ずかしく思った。帰り際、「ねぇ、今度はいつにする?」思いがけず聞かれたのでビックリした。今まで帰り際に、次回の予定なんか話した事がなかったからだ。「いつがいい?先生は14日は何処か行くわけ?」「墓参りに行こうと思ってたくらい。」「14日に仕事終わってからこっちに向ってもいいし、次の15日でもいいし。先生の都合のいい方でいいよ」「仕事終わった後でも大丈夫?疲れない?」「心配しないで。片道2時間くらいだから大丈夫」「じゃ、途中まで送ってくよ」「ありがと」駐車場まで2人で歩く。「今度は海を見に行こう。海が見たいんだ。別に泳ぎたいとかじゃなくてね」「じゃ、水着持参でなくていいね(笑)」また、彼の方から約束を取り付けてくる。束縛されるのは一度酷い目にあってるので嫌いなんだけれど・・・なーんか悪くないな、こういうの。
2003.08.10
-
ハルシオン。
夜が明けないうちに、台風による警報は解除になった。嵐の去ったあとは、嘘のようにクリアな青空と夏らしい積乱雲。そういえば、ようやく夏らしい青空を見たような気がしたけれど、暦は秋へと移っている。今日のイデタチは一寸サイケな柄の白のTシャツ(MISS SIXTYの)に黒のローライズパンツと赤いミュール。「前回待ち合わせた場所で、7時に」その待ち合わせ場所に差し掛かったところで、何故か記憶が蘇る。「あ、あそこ彼のマンションじゃないかな?」そういえば、さっき彼から電話があった。「待ち合わせの場所についたら、電話してね。部屋で待ってるから」部屋で待ってるんだったらいいや、と記憶を辿って運転すると、またまた見覚えのあるマンションの駐車場に到着。「もしもし?私だけど。なんだかマンションの駐車場まで着ちゃった。」「え?自力で着ちゃったの?凄いな。。。じゃ、そっちまで迎えに行くから待ってて」待ってろと言われて素直に待ってる私じゃあない(苦笑)此処まで来ればこっちのもの。彼のマンションまで歩いて2分。エントランスで待ってると・・・人影がこっちに近づいてくる。なーんか、Kさんビックリしてた(感嘆符つき)。そりゃそーだ、私がたった一人でここまでたどり着けるなんて思っていなかったから。私も此処まで来れると思っていなかったからさ、私もビックリ。一旦私の荷物を置きに行った後、食事に出かける。今日は中華。大皿に乗った料理をシェアして食べる。彼は食事の間も、終始機嫌良くしていた。酢豚の中のパインが苦手だとか、そういう他愛もない話をしていた。電話で話した重い話が嘘みたいだった。食事から帰って、リビングのガラステーブルの上にブルーのカケラを見つけた。赤いカーペットの上にはもう少し小さなカケラが落ちている。「これ、ハルシオンだよね?銀のシートのヤツ?それとも金の?」「0.25の方だよ。持続時間が短くてキレがいいからね・・・」彼の名前の書かれた薬の薬局の紙袋からは、ビタミン剤と一緒に銀色のシートが覗いている。シフト上、不規則な生活を送るうちに睡眠障害を起こす医療従事者も少なくない。彼もおそらくその一人だ。その隣には資料。明日の講演の為の、医学雑誌からの論文のコピーだ。「ねぇ、今日は飲まないの?それとも私のマイスリー飲む?」「ん、いいんだ。薬で眠っちゃうのは勿体無いからね・・・」「中途覚醒しちゃうかもよ」「いいの。途中で目が覚めたとしてもそれはそれで。・・・一人じゃないって感じられるから」
2003.08.09
全124件 (124件中 1-50件目)
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- ◆老後になってから、どんな老後を過…
- (2025-02-18 16:42:39)
-
-
-

- ニュース関連 (Journal)
- 指定席を譲る必要はない。
- (2025-01-06 10:17:03)
-
-
-

- たわごと
- 多くの外国人も日本語は出来ても日本…
- (2025-02-18 10:26:26)
-