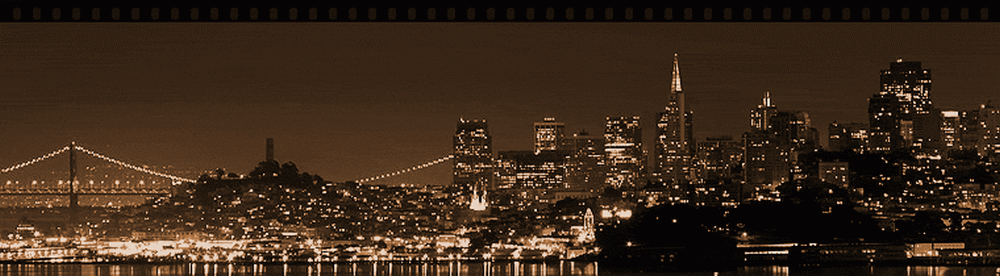2025年07月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
阿字観と胎蔵界曼荼羅
阿字観という行法は、大日経(大日如来=光)との密接な関係があるとわかるので胎蔵界曼荼羅との結びつきを強く感じます。また曼荼羅には立体曼荼羅というものがあります。曼荼羅はその立体を上から見ている姿とありました。つまり、その中心には塔が立っているのです。これが、法華曼荼羅の中央にある塔、それは法華経の第11番「見宝塔品」で、釈迦の説法中に大地から七宝の塔が現れ、その中にいた多宝如来が釈迦の説法を証し、並んで座るという場面を描いています。つまり法華経と曼荼羅は、おなじことを表しているとみています。
2025.07.28
コメント(0)
-
胎蔵界曼荼羅と金剛界曼荼羅
この二つの曼荼羅は日本の真言密教に弘法大師の手によって日本に伝わりました。その起源について胎蔵界曼荼羅が描かれた根本経典は大日経(大毘盧遮那成仏神変加持経、または大毘盧遮那経と呼ばれる)から作られた物です。その成立は7世紀頃と推定され、西インドで成立した物のようです。この経典は唐の開元13年(725)にインド僧の善無畏三蔵が80歳の高齢の身でありながら中国にもたらし、中国人の弟子一行の協力を得て漢訳されました。シルクロード経由で中国に伝わった物と言えます。また金剛界曼荼羅が描かれた根本経典は、金剛頂経であり、その成立は7世紀中頃で南インドで成立した物のようです。この経典は不空(不空金剛、不空三蔵とも呼ばれる)人物によって741年(8世紀中頃)から5年を掛けて、南の海のシルクロードを伝って、完全なものが中国に伝えられました。あの理趣経なども、この金剛頂経系です。この事から、密教の系統は二系統あり、西インドと南インドという二つの流れがあり成立は大日経がざっと半世紀早いことから、積み重なるように発展してきたものと思えます。また密教の成立についてはこの発生状況から、二種類の核があり、それが金剛界、胎蔵界を生んだのでは無いかと思えます。この時期以降インドの北西部などは、イスラム等の侵入から戦争による混乱がはじまります。そしてこの南インドの系列から、後期密教がうまれてきたのだろうと思います。
2025.07.28
コメント(0)
-
消したい記憶
消したい記憶という文章があり、色々な話が載っていました。自分にも様々な消したい記憶、失敗や挫折などがありました。そしてそれは、消したいと思っても、それは突然頭に現れて、自分を何度もいじめてくるのです。追い払っても、追い払っても、別の事をもっと面白い事をしていても、その隙間に出てくるのです。それは、自分を痛めつけ、どんどん落ち込んでしまうのです。しかし、それはあるとき、消えてしまい、どこに行ったかと言うのですがまた出てくるのです。これは、消えて無くなるのです。というか一気に減ってしまうのです。また出てきても、それは事実として、平然と、優しく見ているのです。瞑想とはそういう事ができるのです。(それが出来て驚きました。)
2025.07.26
コメント(0)
-
シンギングボウル4
これを鳴らすと、すぐに心は統一された状態になることが出来ます。音に集中していくその音を聞く、その音の中に入っていくようなリラックスして、全てが静まってきます。その音に入る、音と一体となるこれは入我我入という状態なのですが非常に簡単に統一性が取れます。これは、サマタ瞑想(止瞑想)そのものです。座って呼吸を観ろといっても、その形だけでもできません。そして、あの統一観、動かない心の状態というものは、容易に出来る物では無いとおもいます。すぐに別の考え(思考、悪魔、猿)が沸き起こるのですがそれが少ない様におもいます。集中して棒を廻して、音に入り込んでいくことで容易にその状態を知ることができます。瞑想してみたらといっても、嫌だとか、体が痛いとか色々言っていましたがこれは、とっかかりが良いので、なぜかいつもそれを気が向いたら廻して音をだしています。この統一された状態は、とても心地よいのです。(悪魔が猿が出てこないからです。)時間は短いとはおもいますが、その状態を知ってもらいたいと思っています。
2025.07.18
コメント(0)
-
シンギングボウルと阿息観
シンギングボウルの振動音と、真言宗の阿字観で行なわれている阿息観とは密接な関連があると考えます。阿息観とは、阿字観瞑想において、アー----という声を出して行なう行法は人の体を楽器のように、シンギングボウルの倍音のように発声するのでは無いかと言うことです。阿息観は多人数で行なうのですが、10人くらいでしょうか人の頭は倍音を発生する共鳴板という機能がありますから、アー-という発声を響かせるようにかつ、流れる他の発声と同調させるように、してみました。まだ始めたところですが、阿字観が終わった後の感想ではなにか調子がよいとか、入り込めるたとか、ある人は光輪があらわれたとかいう今までに無い感想が多かったように思えます。それがこれが理由かどうかはわからないのですが、色々試してみたいと想っています。これは声明学と瞑想の深いつながりだと考えています。声明学については752年(天平勝宝4年)に東大寺大仏開眼法要のときに声明(四箇法要)を営んだ記録があり、奈良時代には声明が盛んにおこなわれていたと考えられる。平安時代初期に最澄・空海がそれぞれ声明を伝えて、天台声明・真言声明の基となった。天台宗・真言宗以外の仏教宗派にも、各宗独自の声明があり、現在も継承されている。源氏物語の中に度々出てくる法要の場でも、比叡山の僧たちによって天台声明が演奏されていた。平安時代に中国から入ってきた実践的な仏教声楽は梵唄と呼ばれていた。また、インドの声明にあたる悉曇学という梵字の文法や音韻を研究する学問が盛んとなった。やがて、悉曇学と経典の読謡を合わせたものを声明と呼ぶようになり、中世以後には経典の読謡の部分のみを指して声明と称するようになった
2025.07.17
コメント(0)
-
その2
これは不空の著作から描き出された法華曼荼羅、法華経の塔の記述(法師品)この曼荼羅は、胎蔵界曼荼羅と同じものを表していると見ていますので中心には大日如来=光であることから、そう見えてしまうのです。
2025.07.12
コメント(0)
-
大般涅槃経から
この経典は涅槃教から発展し、龍樹(二世紀)には記載がないことから、四世紀頃に成立したと予想されています。その記述の中にお釈迦様は入滅を前に、死別を悲しむアーナンダ(阿難)に話しています。アーナンダよ、この塔を見て「ああ、これがかの世尊、如来、尊敬されるべき人、正しいさとりを得た人の塔なのだ」と、多くの人が感慨も新たに、清らかな心になることができ、この功徳によって五体が壊れて死んだ後、よき所・天の世界に生まれることが出来るからなのだ。岩松淺夫訳「大いなる死(大般涅槃経)」からこれを見てひっかかる点がこの塔なのです。この塔については、引用した人は釈尊の遺骨が祭られた記念の塔とあるのですが、この時点では釈尊は亡くなってはいないのです。釈尊の死後それこそ無数の仏舎利の塔(サンチーなど)が作られるのですけどわたしには、この塔が瞑想にあらわれる光りの塔(月輪)に見えるのです。同じ事が南天鉄塔(大日如来の所説の法門をその上首たる金剛薩埵が結集して、機を見て授けんとしてこの塔に蔵(おさ)め置いたところ、龍樹(龍猛)菩薩がついにこれを開いてその経典 金剛頂経あるいは大日経を伝授したといわれている。)にも言えるのでは無いかと思えるのです。
2025.07.12
コメント(0)
-
深呼吸 その3
静かな心、大きな海の様なとでも、悠然とある大山の様なとでも、どこまでもある青空のようなものみたいなものが、一瞬でもあるという時点が来るとおもうのです。かく即という邪魔な思考に気がついていく作業をすすめるとそうなるとある時点で、前にもかきましたが、この自動思考とでもいう悪魔が出てこれなくなるのです。完全にでは無いのですが、激減する時点がやって来ます。張り詰めると言うわけでもなく、ダランと放逸しているわけでも無く適度な これも弦の喩え通りです。それを観ているのは、優しい視点になっているんです。世界をその様にみえています。その視点があらわれると、観るものはハッキリとし、きれいに、やさしく投げかけてきます。消しゴムが微笑む んですから思考が現れてくると消えて行くのです。が、なにかしらのものがあるとわかるのです。
2025.07.10
コメント(0)
-
深呼吸 その2
不安になるという事は、その時その様な身体の(特に上半身)にその様な身体変動が現れているはずです。その身体変動があっても、それを掴まないなら、そういう不安は起こらないというかもっと小さいものなのです。人の心は、常に何かをつかむ様に出来ているので、それをつかんで落ち込んでしまうのはしょうが無いといえます。掴むなら、離せばよいのですが、案外とそれは難しいのです。だから深呼吸という上半身の動作をすると、その不安の身体動作をある程度緩和してくれます。また、深呼吸をするという動作に意識というか心を集中すると、その掴む作用を不安という掴んでいる動作から、少し離してくれるからです。また不安という動作は、もうひとつ法則があり、それを掴み続ける事は出来ないのです。これは常に変わっていくという(諸行無常)事をあらわしています。心は常に別のモノを掴もうとするからです。ですから、呼吸という動作に心が掴むモノを代えてしまう。という事でもあります。その内不安も、そこに居続ける事は出来ないことから、全てが無くなって行きます。新聞紙を丸めて、下から熱を掛けていくと、紙が炭化して、新聞紙の丸まった炭になりそして、その炭は形を崩し、崩れ落ちる、そこに一陣の風によって、炭の粉は飛び去っていくそこには何も無く、空っぽの、平安なモノ、平安な心だけが残っていくそれを観察していきます。(観瞑想)それを繰り返すことで、そこで起こるモノは、私が起こしているものでない、勝手におこってくるものその勝手におこっているものを、自分であると思い込まされて来た事(一切行苦)に気がつくと思います。どこにも私はいない(諸法無我)という理解(知恵)に到ると思います。そこには、静かな心だけがある ことに気がつくと思います。
2025.07.07
コメント(0)
-
深呼吸
よく不安になったときなど、深呼吸、深い呼吸をすることを指示されるのですがあまりうまくいった記憶はありませんでした。今は瞑想の事から、ある程度うまくいくようにはなったとは思いますが深呼吸をすることと、なぜそうすれば良いのかと言う説明がなかったからです。またその行為はある程度うまくいくのですが、理解がないと(智慧がないと)また同じ事をやってしまうのです。またそれを指示している人も、なぜそうかと問われると、そうなんだからそうだとしか言えない状態ですので、なんとなくそう伝えられて来たのだと思うのです。実際ある程度はうまくいきますから
2025.07.06
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- 今日のこと★☆
- 小田原のみかん園に、東京からみかん…
- (2025-11-26 21:48:57)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 届いたscope便と楽天ブラックフライ…
- (2025-11-26 22:13:16)
-