2007年01月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

Tom's of Maine
今日は、Tom's of Maine(http://www.tomsofmaine.com/)という会社のプレゼンテーションにいってきた。こんなデザインの品々を見たことがありませんか?1970年にTom ChappellとKate Chappellという夫婦が作った天然素材のパーソナルケア用品(シャンプーや歯磨き粉など)を作っている会社です。Body Shopみたいなノリのブランドで、アメリカの天然素材パーソナルケア市場では圧倒的なシェアを誇っているはずです。原料はすべて植物性で、環境にやさしく人体に害を与えない商品を、リサイクル素材で作った容器に入れて販売するという徹底したポリシーを保っている会社です。COOがハーバード出身の人で、彼が会社の理念やビジョンなんかを熱く語ってくれました。基本は、「これからはLOHAS(注1)がアメリカを制覇するぜ!」、というメッセージで、日本じゃとっくにはやってるよ、というつっこみを入れたくなったものの、すごいなあと思った点もいくつかあった。そのひとつが、会社は税引前利益の10%を必ず、環境問題や貧困削減に携わるNGOに寄付をしていること。体に優しい商品を提供して消費者を幸せにする、ということ以外に、社会全体をよりよいものにしていくこともmissionのひとつとして考えたいとのこと。でも、税引前利益の10%ってかなり大きくないか?Tom's of Maine社は、ずっと未上場で、昨年コールゲート(アメリカの巨大歯磨き粉会社)に買収された。でも、仮に上場していたら、どういう反応になっていたんだろうなあ。いくら社会のためといっても、10%もマージンを犠牲にしていたら、投資家にぶったたかれるんだろうなあ。。。で、僕がこの会社の経営者だったら、どうやって投資家を説得するか?かなり屁理屈だが、ファイナンスの授業でやっているMM理論(注2)と負債のTax Shieldの考え方を用いて考えてみた。もっていきたい結論は、「会社のステークホルダーが世の中全体とすると、NGOへの寄付は企業価値を増大させる」。(うさんくさ。。。)今、A社とB社という二つの会社があったとします。二社とも、営業利益が100ドル、金利費用が10ドルで、A社は毎年10ドルをNPOに寄付しており、B社は寄付はしていない。実効税率は40%。そうすると、二社のPLは次のようになる。 A社B社損益計算営業利益100100金利1010NPOへの寄付100税引前利益8090法人税等3236当期利益4854で、二社のステークホルダーの取り分は次のとおり。ここでは、ステークホルダーに債権者と株主に加えて、「社会」というのを加えるのがミソ。 A社B社ステークホルダーの取り分債権者(=金利)1010社会全体(=寄付)100株主(=当期利益)4854合計6864 おおーー、なんと、NPOに寄付しているA社のほうがステークホルダー全体の取り分が大きいではありませんか!(単にTax shieldが効いてるだけですが。。。)でも、債権者も株主もお金を会社に入れてるのに、これに加えて社会がステークホルダーというからには、何らかのCapitalを会社に入れてるんですか?という問いには、「寄付によって保たれる環境のベネフィット(生態系が保たれることで、A社がよりよい天然材料を入手できるかもしれない)や、社会貢献することによるブランド価値の向上こそが、Social Capitalだぜ!」なんてことは言えないかしら?一応こういう健康志向なパーソナルケアの会社にはプラスでしょ。とはいえ、結局Tax shieldによる価値の増大分が、株主に流れないと、こんな施策は株主に認められないだろうなあ。(負債を増やしてTax shieldを増やそうというのは、負債のアップサイドが限られていることと、負債調達による手取金で自社株買いをするから、合わせ技で一株当たり利益が上がるから受け入れられるんだよね)じゃあ、「社会全体 = 株主」ということで、なるべく多くの人に株主になってもらえばいいのか?でも、それは無理がある。加えて、A社が社会に寄付することで良くなった世の中のベネフィットを、B社も享受できてしまったら(Free Ride)、意味ないか。。。うーーん、だめだ(合掌)。所詮は屁理屈です。。。* * *なんか、世の中のためになっている会社が最終的には企業価値が高いんだ、というのを誰か理論的に説明してくれないかなあ。そういうのが証明できたら、かっこいいと思いませんか?てなことをつらつら考えるうちに、眠くなったので、予習は早朝に回してとりあえず寝ます。あ、ちなみにCOOの人が、学生一人につき、見本の歯磨き粉とシャンプーをダンボール一個分くれました!(なぜって気もするけど)しばらく歯磨き粉とシャンプーは買わずにすみそうです。 注1) Life Styles of Health and Sustainability注2) モジリアーニ=ミラーの理論ね。舌かみそう。。。
January 30, 2007
-
お役立ち(!?)英会話講座(その1)
ちょっと内輪ネタ気味ですが、ひとつ。僕が働いていた証券会社では、理不尽な理由で上司の怒りをくらうことを、「焼かれる」といいます。このニュアンスを、日本オフィスに来る外人バンカーたちに伝えたいなあと思っていたのですが、ついぞいい表現を見つけることができませんでした。ところが、今日ついに、「焼かれる」の英語訳と出会うことができました。それは、「Grilled」。いいと思いません?ケースで、「うその証言をした主人公が、法廷で検察官にGrillされた。」というような文脈で出てきました。G社の人たちはぜひ使ってみてください。くだらなくて、失礼しました。。。
January 30, 2007
-

極寒
今日は一段と冷え込みが厳しいっす。最高気温マイナス11度、最低気温マイナス16度。いい天気で晴れているのに、一歩外に出ると、冷たい風があたって顔がちくちくと痛い。そしてチャールズ川も凍ってます。。。(合掌)極寒にも関わらず、毎朝7時45分からのStudy Groupのミーティングは相変わらず続いており、メンバーのメリッサが渋いファッションで登場したので一枚。昔なんかの雑誌で見たけど、アフガニスタンの山中で越冬するタリバーンの兵士が確かこんな格好をしていた。* * *ところで、授業開始2週間の通算打率(発言した授業の数 / 全ての授業の数)は、7割5分に上昇!しかし、ここにきて、みんな頭が冬休みモードから回復したのか、クラスメートの手の上がり具合が激しくなってきた。多分、これからは打率はどんどん下がっていきそうです。。。でも、この先こんな高打率の達成はまず無理なので、とりあえず、記録しておきました。* * *授業終了後にIndian Business Conferenceというカンファレンスがあったので、インド人の友人に半分拉致られるようにして出席してきた。感想は、いまいち、なり。。。やはり、パネルディスカッションは、時間がない上に、スピーカー同士のハーモニーをとるのが難しいから、今ひとつ纏まった学びが得られない感じだ。でも、これから陽がのぼっていくぜ!みたいな国の人たちの勢いはなんとなく感じることができた。ひとつ僕のミーハー心をくすぐったのは、グラミン財団(http://www.grameenfoundation.org/)のCEOと会えたこと。グラミン財団は、グラミン銀行のユヌス氏の活動に感銘を受けたアメリカ人によって1997年に設立された財団で、世界最大のマイクロファイナンス団体への資金提供者のひとつだ。彼が言っていたのは、「今のsocial enterprise業界は、まだまだ発展途上で、今僕らがやっていることの3/4は、きっと後世から見ると間違っていたとされるのだろう。でも、そういう混沌とした成長状態の中で仕事をしてみるのも面白いと思わないかい?」なるほど、でした。* * *今夜は、待ちに待った金曜の夜ということで、飲み会ラッシュ!いろいろ迷った結果、国際開発クラブ(International Business and Development Club)の飲みにいってきます。熱い話でも盛り上がれそうで、楽しみです。
January 27, 2007
-
開幕ダッシュ!
二学期がはじまって、ぼちぼち一週間が経とうとしている。今学期から、自分がどの授業で発言したか記録をとることにした。すごくみみっちい(※)感じがしてほんとは嫌なのだが、いろんな先輩方もやっていたようで、確かに自分を律する上ではいい方法ではあると思う。で、いまのところ、なんと、なかなか好調な開幕ダッシュです。11回授業があって、8回発言しているから、打率7割3分。先学期の打率はシーズン通算3割くらいだったから、あたりまくりということになる。科目的には、BGIE(マクロ経済)、FIN2(ファイナンス2)、LCA(Leadership and Corporate Accountability - 「企業倫理と法」みたいな感じ)の三つがはじまっている。そのうちLCAは、先学期のリーダーシップみたいな感じで、クラスメートが早口の英語で自分の思ったことをランダムに言いまくって、英語下手な僕は沈黙・合掌・成仏、という展開になるのかと密かに恐れ慄いていたが、はじまってみると、これがかなり快調。この授業は、法律にのっとったきちんとした考え方のフレームワークがあるので、勝手な議論展開にもっていくことは許されない。先生も、ガンジー似のインド人のご老体で、クラスをきっちり締め上げるので、学生たちも慎重になってあまり手を挙げないのだ。誰も手を挙げないから、手を挙げるとたいていちゃんと当たる。こうなってくると、インターナショナルとアメリカ人の差がそれほどなくなるので、戦いやすくなります。がんばって予習すれば、その努力は報われやすいです。残りのBGIE、FIN2も似たような感じで、クラスは比較的静かで、きちんとした意見を持っている人がきちんと発言する、というイメージです。今学期は、こういった静かめなダイナミクスで進んでくれるといいのですが。。。とはいえ、就職活動が本格化すると、忙しくなって早速爆死するリスクもあるので、気は抜けませんが。。。* * *明日から、就職活動でNYにいってきます(といっても一泊のみですが)。前の会社でとてもとても尊敬していたバンカーの方にお会いできる予定で、面接よりもどっちかというとそっちのほうが楽しみかもしれません。(※)みみっちいって福井弁じゃないよね?
January 23, 2007
-
ボストン空手家同盟
ちょっと前の話になりますが、年明けにボストン在住空手家のYukiちゃんとお会いすることができました。学生時代は日本体育大学のエースとして大活躍。(ちょうど学連の試合に出ていた時期が同じ。僕は弱小校でしたが。。。)今はボストンで教育関係の仕事をしつつ、パートタイムの大学院にも通っているそうだ。中華を食いながら、空手の話や学校の話、仕事の話を聞く。やっぱ、空手やってる人は考え方がシンプルで、話していてすっきりするなあと思った。ブルックラインにいい道場があるという話も聞いた。「アメリカでは自信過剰な空手人を作り上げる道場もあるけど、そこは謙虚な空手人を育てる道場」だそうな。「謙虚たるべし!」っていう空手観、かなり共感でした。一時期ハーバード大学の空手部にも顔を出していたが、最近はやはり勉強が忙しくまったく行けていない。空手再開は二年生になってからの楽しみにとっておく、ということになりそうです。
January 21, 2007
-
グロービス堀社長講演会
昨日、グロービスの堀代表がいらっしゃって、HBSとMITの日本人学生向けに講演会をして下さった。堀さんは1989年のHBS卒業生で、いわば大先輩。楽天の三木谷社長、DeNAの南場社長などが起業される更に前にグロービスを立ち上げた、いわばHBS卒起業家の先駆けの方。テーマはMBAを出たあとに起業することについて。僕も人生のどっかでNPOを起業(社会起業)できたらいいなあ。。。とささやかながら思っているので、顔を出してみた。すげー熱いプレゼンテーションで、とても元気が出ました。以下備忘録的に印象に残ったポイントを:1) 起業は気合だ!(起業家精神)堀さんはHBSにいたとき、色々な起業家の講演会を聞きにいって、「彼らと自分と何が違うんだろう?実は何も違わないんじゃないか?」と感じたそうだ。また、日々のケーススタディの中で主人公の問題を解いていくうちに、どうも自分にもビジネスが立ち上げられそうだぞ、と思うにいたったそうだ。(本人いわく「大いなる勘違い」)でも、この「大いなる勘違い」のおかげで、強い志を持つことができた。結局起業家で成功するというのは、まずは気持ちの問題なのではないか?(Sustainableなビジネスをつくっていくという観点では、能力も大事だとおっしゃっていたが)2) 自分の頭を信じろ何かアイディアを考えても、必ず人は反対する。でも、そこでへこまずに、「ほんとにこりゃ無理だな。。。」と思うところまで、ロジカルに自分の頭で徹底的に考えてみる。で、考え抜いた挙句、ほんとにうまくできそうなら、ほんとに成功するのではないか?ケーススタディは、ビジネスの問題について自分の頭で徹底的に考える訓練になるし、ケースを考える中で起業アイディアがわいてくることもあるのではないか?<筆者感想:これはなるほどと思いました。僕は自分の脳みそはあまり信じられませんが、まあ徹底的に考える訓練はがんばろうと思います>3) 日本の社会は失敗者に厳しいといわれているけど、実はそうじゃないのでは?起業するとき、やはり失敗が怖かった。アメリカではビジネスに失敗しても個人資産まで持っていかれることはないけど、日本ではまず自己破産。でも、よく考えてみると、日本社会は失敗者に厳しいのではなく、失敗していく過程の「ふるまいの悪さ」(粉飾決算とか、うそをつくとか、逃げるとか)に対して厳しいのでないか、と思うようになった。つまり仮に失敗しても、その過程で卑怯なことをしなければ、日本の社会はまたチャンスをくれるのではないか?だから、堀さんは起業するとき、絶対にうそはつかないし、逃げない、と心に誓ったそうだ。4) 起業のプロセス無理な規模を狙わない。自前のキャッシュフローでなんとかなる範囲で小さくはじめて、徐々に成長させていく。だから、今も内部留保で成長できているし、上場もしていない。<筆者感想:超共感!僕も万が一会社を作ることがあれば絶対に上場させたくないと思ってるので (とても元証券マンとは思えないけど)>あと、ビジネスを育てる過程で、失敗リスクを減らす一番の方法は、自分がコントロールできない要素をできるだけ取り除くこと。5) 数あるアイディアの中で、どのビジネスを選ぶか?ソフトバンクの孫さんに聞いたところ次の三つの基準が出てきたそうだ:(i) 10年で日本一になれる事業、(ii) 持続的に成長できる分野、(iii) 自分が一生ほれ続けられる事業。とくに最後の要素は超大事。以上です。がんばろうと思います。講演会のあとはハーバードスクエアのレストランで、大量のお酒と料理をごちそうになりました。ごちそうさまでした(*^-^*)
January 21, 2007
-
就職活動アップデート
二日間降り続いた雨がやんで、気温がぐっと下がってきた。天気予報によると、明日はマイナス10度を切るらしい。ついに、今年はじめての寒波がやってくる。授業が始まる前に、ある程度就職活動準備を片付けておこうと作業中です。投資銀行やコンサルなどの民間企業のエントリーは12月に終わったのですが、僕がターゲットにしている非営利系の組織は1月・2月がエントリーの山場。カバーレターというエントリー・シートの英語版みたいなのをせっせと書いております。今日までに10社ほど送りつけました。結構がんばりました!備忘録及び、もし今後非営利系の就職活動をする方々がいましたら参考にして頂くべく、団体名を書いておきます。世界銀行http://www.worldbank.org/大御所International Finance Corporationhttp://www.ifc.org/開発金融ならここでしょ!Ashoka http://www.ashoka.org/fec途上国の社会起業家への資金サポート、コンサルティングを行う(非営利団体)。社会起業支援の先駆け的存在Acumen Fundhttp://www.acumenfund.org途上国の社会起業家向けにファイナンスを行う非営利団体Endeavorwww.endeavor.org/embaラテンアメリカ中心に社会起業家へのファンディング、コンサルティングを行う(非営利団体)TechnoServehttp://www.technoserve.org/途上国の農業セクター向けのコンサルティング・ファーム(非営利団体)Good Moring Africaアフリカの民間企業向けのコンサルティング・ファーム(非営利団体)OTF Grouphttp://smtp.otfgroup.com/eng/careers.aspxマイケル・ポーターのコンサル会社モニターからスピン・オフした途上国企業向けのコンサルティング・ファーム(非営利団体)EcoLogic Financehttp://www.ecologicfinance.orgラテンアメリカの農業・環境セクター向けに中規模の貸出しを行う団体(非営利団体)Wellspring Consultinghttp://www.wellspringconsulting.netボストン・コンサルティング・グループの元パートナーが作ったアメリカ国内非営利団体向けのコンサルティング・ファーム(非営利団体)Domini Social Investmentshttp://www.dominiadvisor.com/advisor/About-Domini/Job-Opport/index.htm#investmentinternSocially Responsible Investment Fund(社会に貢献する事業を行う企業に投資をするファンド。金融市場においても、社会貢献をする企業こそが長期的にリターンを生む!ということを証明しようとしている)あと、締め切りはまだ先だけど、ACCTION International(http://www.accion.org)という途上国向けベンチャー・キャピタル/マイクロ・ファイナンスの超有力団体もある(かのMichael Chu教授が代表を務めていた組織で、「ハーバード留学記」を書かれた岩瀬さんが役員をされていたそうな)。どれかひっかかってくれー、と願う今日この頃です。* * *ところで、カバーレター作成の過程で、面白い話を見つけました。Acumen Fundという途上国の社会事業向けに資金提供を行う非営利団体があります。2004年に、ドナーから約1.2億円のお金が入って、パキスタン向けに投資をすることにした。ドナーからは「これは寄付だからリターンもなくていいし、元本も帰ってこなくていいよん」といわれている。どこに投資するかだが、パキスタンでは貧しくて家が買えないという人々が多いそうで、Acumen Fundはパキスタンの低所得者向けに住宅ローンを広めるプロジェクトに投資をすることにした。で、この1.2億円を、「プロジェクトで生じたリスクは真っ先に私が取ります!」ということで、住宅ローンプロジェクトに拠出した。そうしたら、Overseas Private Investment Corporationというアメリカの政府機関が、「その心意気やよし!」ということで、3.8億円の債務保証を付けてくれたそうな。これであわせて5億円のリスクマネー。この5億円がついたところで、パキスタンの有力銀行であるNational Bank of Pakistanが、「5億円リスクマネーがあるのなら、自分たちはその上に45億円出すよん」と申し出てきたそうだ。これで最初1.2億円のプロジェクトだったものが、なんと50億円のプロジェクトになった。リスクはAcumenとOverseas Private Investment Corporationの5億円が最初にカバーしてくれるから、パキスタンの銀行としても、安心して低金利で住宅ローンが出せるわけだ。(貸倒率が10%を超えない限り、通常レートで貸し出せることになる)リスクのあるプロジェクトに資金を付ける場合、相対的に高いリスクを取るお金、相対的にリスクを嫌うお金など、いろんなリスク感覚を持ったお金が入ってくる。たとえば、会社が資金調達をするとき、株式(高いリスクを取るが、高いリターンを求めるお金)、メザニン(中程度のリスク、中程度のリターンを求める)、借入(リスクはなるべく取らないお金)を混ぜて調達するわけだ。で、高いリスクを取ってくれるお金が少し入ると、低いリスクなら取ってもいいよ、というお金が割とたくさん入ってくるという現象が一般的に起こる。(万が一プロジェクトが失敗したとき、元本が帰ってくる順位が自分たちよりも低い人たちがいると安心だからね)Acumen Fundのプロジェクトは、このメカニズムをたくみに利用し、ドナーからの少ないリスク資金を「呼び水」にして、プロジェクトの規模を大幅に広げたなかなか革新的な手法なわけだ。すげー、と思った。どうせサマーインターンをやるにしても、こういう面白いことが発想できるような仕事ができるといいですよね。
January 16, 2007
-
速報! - 成績
一学期の成績が出ました。印象は、「9回裏のポテンヒットで、なんとか引き分け」という感じで、きわめて平均的なHBSの学生の成績に仕上がりました。LEADは予想通り即死(合掌)、ファイナンスは元ジャパニーズ証券マンの根性を発揮し外人をなぎ倒しました(大人気ない。。。)予想外にうれしかったのは、マーケティングの試験で驚異的にいい点数が取れたこと。ゼロスタートの学科の試験でぶちかませるとやっぱりうれしいです。まあ、勝因は、凄腕マーケッターJ氏による手取り足取りのアドバイスに尽きますが(ありがとう!)夏のPre-MBAでぼろくそのフィードバックを受け(http://plaza.rakuten.co.jp/kocchan0826/diary/200608010000/)HBSでの衝撃デビューを飾った僕にしては、まあ上出来かなと。ということで、なんとか放校にならず生き残れそうな気配も出てきたのでご報告でした。* * *夜は、成績が出たということで、ボストンに残っている日本人面子で、厄払いと新学期の健闘を期すべく、我が家でど派手に飲み会。二年生の斬込隊長Y氏(http://blog.livedoor.jp/acejoker/)にも来て頂いて、生き残りのためのリアルなアドバイスを頂いたり、大変盛り上がりました。結局朝6時まで飲んでました。相変わらず、バカですな。。。まあ、そんなこんなで今年もがんばります。
January 13, 2007
-
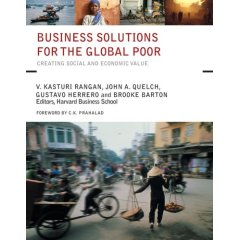
Business Solutions for the Global Poor
HBSから、なかなか熱い本が出ましたので、ご紹介をば。「Business Solutions for the Global Poor: Creating Social and Economic Value 」Kasturi Ranganというマーケティングの教授を中心に纏められた本で、ビジネス的なやり方で世界の貧困層のニーズに応えている企業やNGOのケースが書かれています。読んでみて面白かったら、ブログに感想をアップしようと思います。
January 11, 2007
-

日本酒をひろめよう!
ボストンに帰ってきました。昨晩は、気温マイナス10度とかいう表示が出ていて半泣きでしたが、今日は結構暖かいです。今回の帰国の最大の課題は、日本酒の搬送。親戚が福井で酒蔵(常山酒造というところです)をやっているのですが、クラスメートたちから是非飲んでみたい!という声が強く、運び屋よろしく720ml瓶を6本ほど密輸した次第です(注1)。重かった。。。液体持込規制で手荷物にもできないし瓶が割れないか心配だったのですが、なんとか無事(箱に大きな穴があいていてあせりましたが。。。)。税関なんかもさらりとかわせたし、まずはよかったです。お酒は、「常山(じょうざん)」というブランド。手前味噌ながら、柔らかくまとまりのある純米酒でお勧めです。ご興味のある人は常山酒造のウェブサイトものぞいてみてくださいね。http://www.jozan.co.jp/で、授業がはじまったら、早速外人をターゲットにテイスティング会をやる予定です。テイスティングのあとは、日本酒がどのくらいうけそうか、簡単なマーケティング調査もやろうとおもっています。(味についてのフィードバック、どのくらいの値段なら飲みたい?とか)日本酒というものに対する認知度は高いものの、こちらの小売店やレストランにははっきり言ってろくな酒がおいてありません。(純米酒はほとんどなく、あるのは「鬼殺し」系の醸造アルコールががんがん入った安酒のみ)しかも、アメリカ人たちは日本酒をとんでもない飲み方で飲みます。ご承知の方も多いと思いますが、「Sake-Bomb」というゲーム。一言で言うと、ビールの中に日本酒を混ぜて一気飲みするゲームです(罰ゲームに近い)。こんな失礼な飲み方は許せませんが、「日本というエキゾチックな国からきた酒なんだけど、味がまずくて飲みにくいし、いい感じで悪酔いする!」という、アメリカ人学生の日本酒に対する評価を表しているんだと思います。。。なので、こういう誤解を解くべく、おいしい日本酒を、まずはハーバードの中ではやらせたい、というのが僕のささやかな野望です。純米酒だから悪酔いなんて絶対しないし、さっぱりした飲み口だから、日本料理のみならず、いろんな料理にも合うと思ってもらえるはず。年末SK-II(P&Gが出している化粧水ね)のマーケティングのケースが出てきて、SK-IIの美肌成分は、日本酒の醸造過程で使う酵母から発見されたのだ!というストーリーにクラス一同感動していたので、日本酒に対するモメンタムも今が最高潮だと思います。飲ませてみて、まずはどんな反応になるか、学期開始が少しだけ楽しみです。注1)最初はヤマト運輸とかに頼もうと考えたのですが、酒類の送付は規制が厳しく、当局の特殊な許可が必要とのことで断念しました。皆さんもお酒の送付の際はご注意を。
January 11, 2007
-
日本にかえってきました
ひさびさの日本。* * *正月は地元の福井でゆっくりしておりました。冬の福井には珍しく晴天の日々が続いていて快適でした。ほんとはスキーをしまくりたかったのですが、帰ってみるとなんだかんだいって怠け癖が出て、テレビ見るか温泉いくかというだらけまくった生活を送ってしまいました。それでも収穫だったのは福井のうまいものを満喫できたこと。うちの爺さんはなかなかのグルメで、ストーカーなみにつきまとって、うまいものをいろいろご馳走してもらいました。そのなかでも特においしかったのは、はら田寿司(福井市照手一丁目16-21、0776-26-4630)というところで食ったかに寿司。セイコガニの中身がどっさりのったチラシ寿司です。あと、寒ブリの握り寿司もいい感じで脂がのっていておいしかったです。ボストンでひたすらマグロとサーモンばっかり食っていたので、こういう味のある魚には毎度感動します。もし福井にいくことがあれば食べてみてください。その後、爺さんが家まで歩いて帰るというので、3キロくらいの壮大な散歩につきあわされました。福井の町のど真ん中に城跡があるのですが、その石垣に登ると、延々と広がる田んぼの向こうに白山連峰がくっきりと見えて、それはそれは美しい景色でした。こうやって改めて帰ってみると、福井もいいところです。うわさで聞いたのだが、東京の小学校児童へのアンケートの結果、福井県がめでたく「日本一知名度の低い県」に輝いたらしく、県側は開き直って、「なにもないんだけど、正統派の田舎があります!」というポジショニングで観光誘致に励むらしい。悪くない戦略だ。福井県の観光マーケティング戦略について考えてみるのも面白いかもしれませんね。* * *で、昨日から東京に戻ってきて、いろんな友達に会いまくっている。前職の関係上、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ、投資銀行などの金融系の友達が多く、みんな相変わらずシャープにがんばっている感じです。みんな色んな夢を追っかけていて、すごいエネルギーあります。そういう中に入ってみると、自分は随分とおっとりした人間に戻ったなあと思います。もともとぼけーっとしているのが好きな人間で、投資銀行に入って無理やり性格改造した面もあるので、本来の自分の性格に戻ったという気もしますが。。。もちろんHBSはHBSで勉強の世界の中で必死の競争があるのですが、やはり実戦で斬ったり、斬られたりしている人たちのシャープさにはかないません。正直ちょっとうらやましく感じる面もあります。たとえると、空手の監督から「お前は体力が弱いからしばらく基礎トレーニングをきっちりやって体作りしろ」といわれて、試合から遠ざかって基礎トレをやってるんだけど、たまに試合に出てる選手を見ると、ちょっとうらやましく思える、みたいな。。。とはいえ、大学院という「基礎トレ」をやってる中で見えてきたものはたくさんあったし、そういう自分の中に起きている地道な変化は大事にしたいと思っています。で、そういう基礎トレの環境の中で見えてきた今年の目標は、「考えるチカラ」を鍛えぬくこと。投資銀行にいたときももちろん頭は使いまくっていたと思いますが、どっちかというと実戦の中で次々と出てくる問題を反射神経的に斬っていたという感じです。投資銀行の仕事も慣れてくると、大学入試の数学の問題みたいに、公式をいくつか組み合わせればスピードでばんばん解けちゃうようになりますから(もちろん新手の複雑な問題もありますけど)。今年はせっかく大学院というアカデミックな環境にいるわけなので、今までの公式はいったん置いといて、自分にとっての課題を時間をかけて、根っこのレベルまで深くえぐって考えぬいてみたいと思います。たとえば、途上国がなぜ「貧困の罠」から抜け出せないか?貧困という問題に対してビジネスが何をできるのか?表面的な理論なんかはわかっているつもりですが、もっともっと自分の頭でしっかり考えて、自分なりの問題への関わり方を、できるだけ簡単な言葉とロジックで詰めていきたいと思います。そして、そうやってひたすら考え抜くことが、「実戦」の世界で戦っている友人たちと同じレベルで、この一年を有意義な一年間にするひとつの方法だと思うのです。
January 6, 2007
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…
- ついでの2泊3日・6県ぐるっと旅 …
- (2025-11-19 12:00:07)
-
-
-

- タイ
- 2025タイ紀行 ①置かれた場所でかが…
- (2025-09-13 10:00:11)
-
-
-

- 温泉旅館
- 錦秋の東北へ 米沢・白布温泉 湯滝の…
- (2025-11-13 06:46:38)
-






