2025年11月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
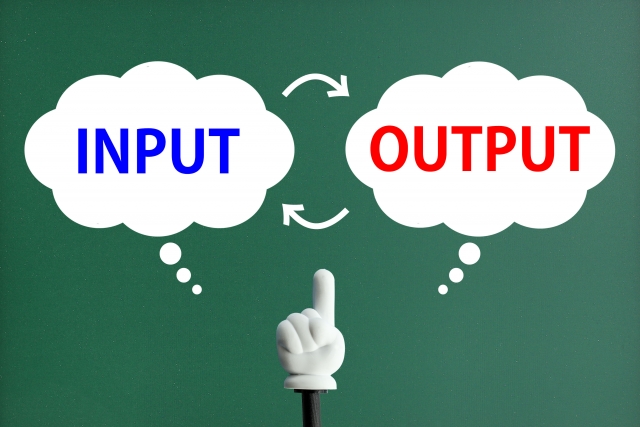
中学受験期、親の愛情と信頼が我が子の才能を育む
中学受験期、親の愛情と信頼が我が子の才能を育む理由は主に3つあると考えます。1.安心感が集中力を生む 2.自己肯定感が挑戦力につながる 3.感情の安定が継続力を支える 見守る力が、未来への土台になります。頑張れ!受験生!
2025.11.19
コメント(0)
-

解答欄が埋まらない…
これはやる気がないのではなく、「どう書けばいいかわからない不安」 が多いです。書けない子は、頭の中で▶情報の整理▶言葉にする変換▶文字にする作業これらが一気に来てパンクしてしまいます。だからこそ、家での声かけが安心の土台になります。それは…書けない子へのNG声かけはこれです。「なんで書かないの?」「ほら早く!」本人の頭の中はすでに渋滞しているので、急かされるほど動けなくなります。代わりに使いたいのはこの2つ👇①「まずは思いついた言葉だけでOK」②「書く順番は後で一緒に考えよう」とりあえず書き始めてもいいんだと思えた瞬間、子どもの手は動き出します。書けない子が一歩踏み出せる魔法のひと言。それは…「書く前に、口で言ってみようか」国語の記述は、いきなり書くより▶口で説明する▶短くまとめる▶言葉を拾って書くこの順番が圧倒的にラクです。家はトレーニングの場ではなく、「失敗していい場所」。親のひと言が、子どもの書ける自信を育てます。少しでも楽しい要素を取り入れることです。↓詳しくはコチラ↓IN国語教育研究室のブログ頑張れ!受験生!
2025.11.18
コメント(0)
-
設問を読み飛ばす子の共通点と、家でできる読む姿勢づくりの話。
設問を読み飛ばす子の共通点と、家でできる読む姿勢づくりの話。まずは振り返ってみてください。▢指で行を追いながら読む習慣をつけている▢急がせる声かけを控えている▢短い文章でも音読で理解を確認している▢設問の条件を一緒に確認している▢本人が落ち着いて読むための環境を整えている① 設問を読み飛ばす子には共通のクセが多いです。ポイントは、読めていないのではなく、読む姿勢が整っていないだけということ。だから、家庭でのちょっとした声かけで変わります。② 家でできる「読む姿勢」づくりの3つのコツ読解力の土台は、文章と設問を丁寧に読む姿勢です。これは家庭で作れます。「まず質問からね。何を聞かれてる?」→ 設問先読みの習慣が、読み飛ばし予防の決定打。「同じ言葉、問題文にある?」→ 指示語・キーワードを探す習慣が、読解の精度を上げる。「区切って読んでみよう」→ 一気読みは読み飛ばしの原因。小分けに読むことで理解が深まる。読む姿勢は、勉強の前に育てる生活習慣みたいなもの。少しずつの積み重ねが大切です。③ 読み飛ばしが減ると、点数だけでなく「自信」が戻る??設問を読む姿勢が整うと、正答率が上がるだけではありません。✔ 落ち着いて問題に向かうようになる✔ 焦りが減る✔ 「あ、読めた!」という成功体験が増えるすると、子どもは国語ができるという実感を持ち始めます。読み飛ばしはミスではなく姿勢の問題。だからこそ、家庭のひと言で必ず改善します。頑張れ!受験生!
2025.11.17
コメント(0)
-
イライラする前に深呼吸!
親の心が整うと、子どもの目も変わる。朝の支度、宿題、受験勉強。「早くして!」が口から出る前に、息をふーっと吐くだけで、子どもはあなたの気配を感じ取ります。親が落ち着いていると、子どもの視線は不思議とまっすぐになります。それは安心が伝わるからです。なぜ親の心が、子どもの集中に直結するのか?子どもは、「言われた言葉」よりも「親の雰囲気」を先に感じ取ります。親がイライラしていると、子どもの脳は“危険信号”を受け取ったようにそわそわと落ち着かなくなります。逆に、ゆっくり息を吐いて表情が緩むだけで、子どもの緊張もスッと抜けます。だからこそ、 深呼吸は家庭学習の即効性あるスイッチなんです。今日からできる「イライラする前の一呼吸」習慣✔ 朝、最初の声かけの前に深呼吸✔ 子どもが宿題に入るタイミングで深呼吸✔ 怒りが登ってくる“途中”で深呼吸✔ 夜、寝る前に3回だけでも深呼吸深呼吸は、子どもを変える魔法ではありませんが、 「親の余裕」を作り出す手軽で最短の方法です。そしてその余裕は、子どもの目つき、「やるぞ!」という前向きな表情に確実につながっていきます。今日もゆっくり、ふーっとひと息つきたいですね。頑張れ!受験生!
2025.11.14
コメント(0)
-
点数よりも気持ちを見よう。子どもの「自己否定」を防ぐ声かけ3選
「どうしてできないの?」よりも、「ここまでよくがんばったね」。受験期の子どもは、結果も、自分を責める気持ちもと戦っています。親の声かけ一つで、自己否定を防ぎ、自信を取り戻すきっかけになります。ちょっと振り返ってみませんか。✅チェックリスト▢ 結果よりも、過程を見て声をかけている▢ できなかった理由を一緒に考えている▢ 失敗を次のチャンスとして話している▢ 他の子と比べる言葉を控えている▢ 「大丈夫」と信じる言葉を伝えている詳しくは概要覧のホームページからブログ「点数よりも気持ちを見よう。子どもの「自己否定」を防ぐ声かけ3選」をご覧ください。頑張れ!受験生!
2025.11.13
コメント(0)
-
がんばり屋の子ほど、限界までがんばってしまう時の声掛け
がんばり屋の子ほど、限界までがんばってしまう。「もう無理…」とつぶやく夜もありますね。 そんな時の「大丈夫」はプレッシャーになることも。「よくがんばったね」+「今日は休もう」子どもの目線と同じ高さで心をこめていつもよりもゆっくりと伝えてあげてください。 努力を見てもらえた実感が、子どもを回復させます。頑張れ!受験生!
2025.11.12
コメント(0)
-
試験前に涙が止まらなくなる子、います。
試験前に涙が止まらなくなる子、います。「忘れた」「もう無理かも」など、その言葉や表情の裏には、子どもなりの「ちゃんとやってきた」という証があります。不安は、努力した証拠です。このとき、親がかける言葉で子どもの心は変わります。「大丈夫、やってきたことはなくならないよ」この一言で、子どもは見てくれていると感じ、緊張の中にも安心を取り戻します。「泣かないで」「頑張って」など、気持ちを抑えつける言葉は気をつけましょう。不安を否定せず、「そう思うほど頑張ってきたね」と受けとめることが、何よりのエールになります。頑張れ!受験生!
2025.11.11
コメント(0)
-
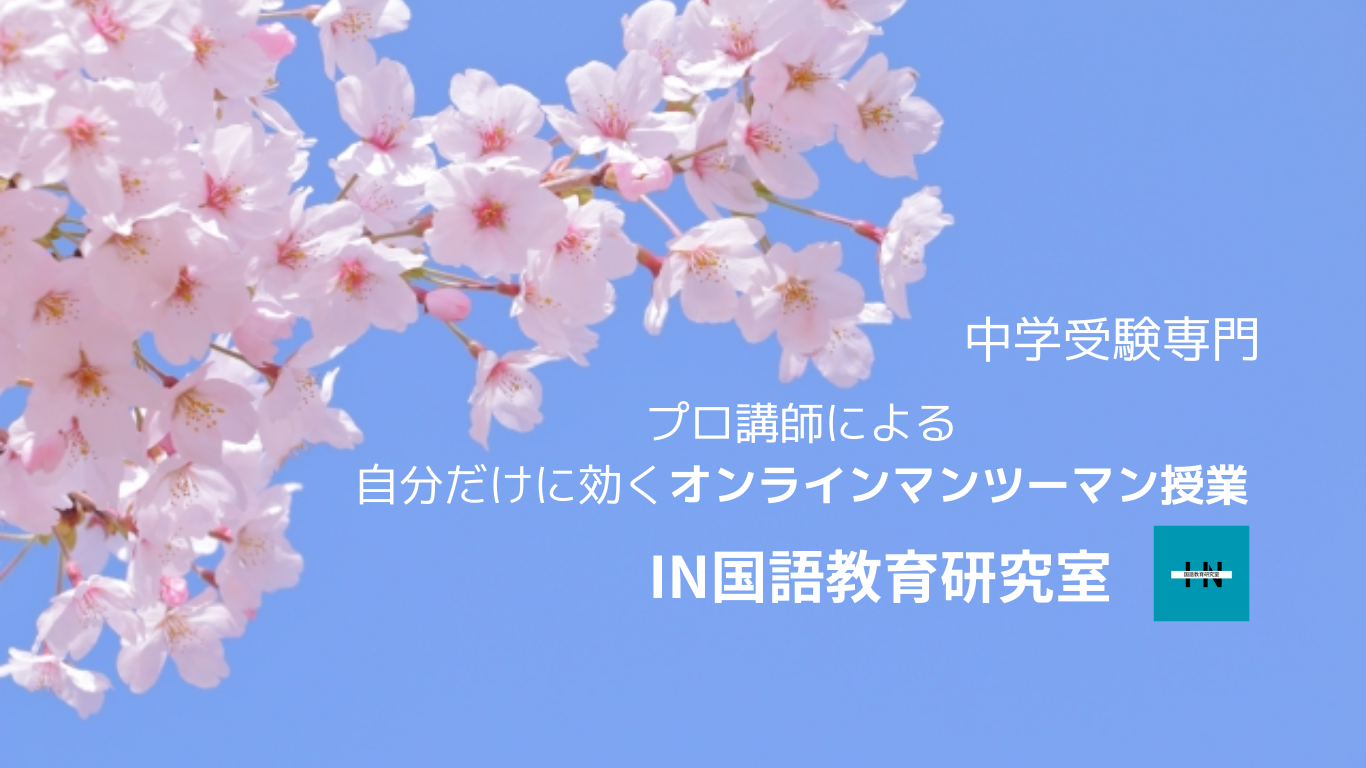
新年度オンライン家庭教師の国語指導のご案内
2026年2月より新年度募集を受け付けております。お問い合わせいただいた順番に現在、ご案内しております。学習相談時に詳細をお知らせいたします。1:1オンライン授業(Zoom)平日は17:00~ 18:30~ 20:00~土曜は13:00以降新小456年生の中学受験生が対象です。新小4.5年生は70分、新小6生は80分です。曜日と時間を固定し、月4回実施します。教材の予習復習、テスト直し等の授業の進め方は個人差がありますので学習相談と体験授業でイメージができます。保護者はオンライン授業ですので授業を見ていただいても、席を外していただいても構いません。学習相談⇒体験授業⇒正式決定(入会)⇒受講開始の流れです。学習相談(Zoom)新小456年生の中学受験生の保護者が対象です。平日13:00~17:00の間で30分/60分の選択1回ごと、もしくは月1回、週1回の選択ができます。相談内容は中学受験全般、大学入試、子育てなど多岐に対応いたします。※会員の方は授業の最後の10分は保護者とのお話か授業が選べるので基本は必要ありません。指導者向けコーチング(Zoom)指導方法、ペースメイク、併願組みのアドバイスなどを適時行います。平日13:00~17:00の間で30分/60分の選択1回ごと、もしくは月1回、週1回の選択ができます。お問い合わせホームページはコチラ⇒お問い合わせ※ご紹介の方はお問い合わせに紹介者名を書いてください。
2025.11.08
コメント(0)
-
【ブログ更新】連休中の連続模試受験は実践のシミュレーション
3連休を振り返りましょう。①移動時間は「集中力の土台」になる②食事は「脳と心のエネルギー補給」③休息は「次へのエネルギーを育てる時間」④復習は「思考力を育てる宝の時間」国語の場合は試験中と解き直しがポイントです。【試験中】は時間配分と「保留」の勇気【解き直し】は「思考の迷子」を見つけ、解消する詳しくは概要覧のホームページ「IN国語教育研究室」のブログをご覧ください。
2025.11.07
コメント(0)
-
【ブログ更新】「やぶさかでない」ってどういう意味?
論説文や小説でもよく出る大人の言葉。 知ってるようで実は理解しにくい言葉です。 即答できれば素晴らしいです。 難しければ、問題は👇からクイズで出しています。 Q:「やぶさかでない」はどんな時に使う? A)いやいや受け入れるとき B)喜んで協力したいとき C)しぶしぶ断るとき答えはB)「喜んで協力したいとき」に使う言葉です。たとえば、 「お手伝いを頼まれたら、やぶさかでない」=「よろこんで手伝うよ!」 ちょっとかたい表現ですが、大人の文章では好まれます。 語彙力を増やすコツは、📚「知る」だけでなく「使う」こと。 子どもが日常で耳にした言葉を、「これ、どんなときに使うんだろう?」と 親子で話すだけでも記憶に残ります。 ひとつずつ「使える言葉」に変えていきましょう✨ 詳しくは概要覧のホームページ「IN国語教育研究室」のブログ「やぶさかでない」をご覧ください。頑張れ!受験生!
2025.11.06
コメント(0)
-
国語が苦手な子どもの読解力向上
📖「うちの子、国語の文章問題が苦手で…」そう感じている保護者の方、多いのではないでしょうか。実は「苦手」にはタイプがあり、原因を見極めると学び方が変わります。①言葉の理解が浅いタイプ👉語彙があいまいで筆者の意図を読み取れない低学年:音読+辞書引き中学年前後:言いかえ練習高学年:語彙ノート+文脈で理解②想像がふくらまないタイプ👉場面や心情のイメージができない低学年:読み聞かせ後に感情を言葉に中学年前後:セリフ・行動・気持ちの三段整理高学年:心情変化を図解して整理③読む目的があいまいタイプ👉設問を意識せず読み流してしまう低学年:「だれが」「なにをしたか」を意識中学年前後:「なぜそうしたの?」と問いかける高学年:設問→本文→設問の順で“戦略的読解”💡文章問題が苦手な子どもには、「語彙」「イメージ」「目的意識」どこにつまずきがあるかを見極めることがカギです。日々の読書や会話の中で「読める力」を育てていきましょう。詳しくは概要覧のホームページ「IN国語教育研究室」のブログをご覧ください。
2025.11.05
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1









