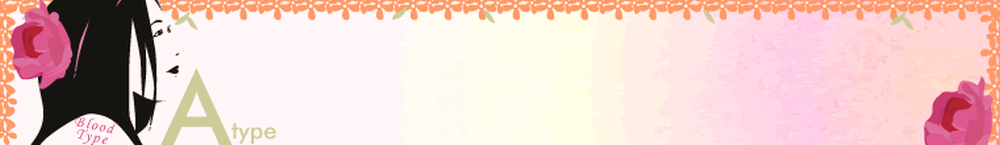PR
Free Space
どうして
大人に
なるんだろう
嗚呼
僕は
いつごろ
大人になるんだろう
Comments
Calendar
Keyword Search
A .第一次世界大戦は、ヨーロッパ列強ばかりでなく、その支配下にあった諸地域をも巻き込んでいった。
中東では、イギリスが フサイン・マクマホン協定 でアラブ人に戦後の独立を約束する一方でフランス・ロシアとの間では サイクス・ピコ協定 を結んで密かにアラブ地域を分割する約束をするという無責任な外交を展開し、さらには バルフォア宣言 を発してパレスチナにユダヤ人の独立国家を建設する約束をした。
中国では、列強がヨーロッパでの戦争に忙殺されている間隙をぬって、1915年1月、日本が 対華二十一カ条要求 を袁世凱政府に突きつけ、同年5月これを受諾させた。この要求には当時日本が占領していた 山東省 の青島など旧ドイツ権益の継承、満州、モンゴルでの日本の優越なる地位の承認などが含まれていた。
1917年4月、それまで中立を保っていたアメリカ合衆国が連合国側について参戦した。その背景にはドイツの 無制限潜水艦作戦 に対してアメリカの世論が参戦に傾いたことや、英仏に多額の借款を与えていたため連合国側尚勝利が不可欠であったことなどがある。アメリカの参戦は、霊力面以上に経済力の面で連合国側に有利に作用した。
1917年11月、ロシアに誕生したソヴィエト政権は、直ちに 「平和に関する布告」 を発し、 無併合・無賠償 の原則による掃除講和を提唱、全交戦国にこれを呼びかけた。交戦諸国は何の目的のために戦っているのかを問われることになった。アメリカ合衆国 ウィルソン が 「14ヶ条」 を発表したのもこうした背景があったからであった。しかし連合国側は講和には応じず、ソヴィエト政権はドイツと プレスト・リトフスク講和条約 を結び、戦線を離脱した。劣勢にたたされていたドイツは、この機に大攻勢を仕掛けたが成果は上がらず、1918年の夏には敗北が決定的となった。しかし講和の条件がまとまらず、戦争は続行され、ドイツ国内の経済状況は悪化した。1918年11月、キール軍港の水兵の反乱をきっかけに ドイツ革命 が勃発、各地で労働者や兵士が レーテ(老兵評議会) と呼ばれる評議会を組織した。革命の急進化を恐れるドイツ支配層はついに皇帝を退位させることを決意し、11月11日、休戦協定が成立した。
B .第一次世界大戦の最中の1917年3月、ロシアの首都ペトログラードの労働者によるストライキをきっかけに、革命が勃発した。これを2月革命という(3月におきたけどロシアの暦では2月だから)この革命の結果、帝政は倒れ、ブルジョワを中心とする臨時政府が成立したが、労働者と兵士の代表はソヴィエトと呼ばれる評議会を組織し、いわゆる2重権力状態が出現した。しかし臨時政府は 戦争を継続 したため民衆の指示は臨時政府から離れていった。一方、亡命先のスイスから帰国した レーニン は 「四月テーゼ」 を発表し、 戦争を継続 することを反対するとともに全ての権力を ソヴィエト に委譲するよう主張した。そのためレーニンの率いる 社会民主労働党 が次第に ソヴィエト 内での勢力を強めていった。1917年11月7日、ソヴィエトは武装蜂起によって政権を掌握、 ソヴィエト政権樹立 を宣言した。また翌8日には 「土地に関する布告」 を発して、地主制を廃止し、全ての農民に土地使用権を認めた。
1918年、日米英仏軍はソヴィエト政権打倒のため、 対ソ干渉戦争 を開始した。この干渉の背景には、共産主義の影響を恐れたこととともに、ソヴィエト政権がドイツと単独講和を結んで戦線離脱をしたことや、 外債の破棄 を宣言したこともあった。国内の反革命勢力のみならず、外国軍とも戦うことになったソヴィエト絵試験は、 義務兵役製の導入 によって軍備を強化し世界革命を進めることによって体制維持を図ろうとした。そのために創設されたのが コミンテルン である。このような努力によって1919年の末には連合国はロシアからの撤退を決定し、革命の防衛には成功したが、1921年に ポーランド との戦争に敗れたことにより、 世界革命 の可能性もなくなった。
対ソ干渉戦争後、ソヴィエト政権は、戦争によって疲弊した経済立て直しのため、それまでの 戦時共産主義 にかえて、 ネップ を採用した。この。資本主義の原理を一部復活させる政策によって、経済は急速に回復し、それとともに、それまでの 世界革命論 にかわって 一国社会主義論 が浮上してきた。1924人、レーニンが亡くなり、その後継者の地位をめぐって 世界革命論 を主張する トロツキー と 一国社会主義 を主張する スターリン とが対立するようになった。この争いに勝利を収めたスターリンは1928年から5カ年計画を開始し、急速な工業化を推し進めた。その結果、1937年にソ連は世界第二位の工業生産を誇るまでになった。
しかし、その影で、農村では農業集団化が強行され、これに協力しないものはクラークのレッテルを貼られて強制収容所に送られるなどして、多くの農民が犠牲となった。また都市の食糧確保のため濃くも問うなどの強制挑発を強行したため、1933年には秀百万の農民が餓死したといわれる。
C .第一次世界大戦後の国際体制を ヴェルサイユ体制 という。その大枠は1919年の パリ講和会議 で決められたが、この会議では、アメリカ大統領 ウィルソン が発表した 「14ヶ条」 を基本原則とすることになっていた。しかし、実際にはフランス代表 クレマンソー やイギリス代表 ロイド・ジョージ の現実主義的以降によってこの原則はゆがめられ、 民族自決 などの理想はあまり実現しなかった。この会議の結果、1919年6月28日に ヴェルサイユ条約 が結ばれ、ドイツは全ての植民地を失ったばかりでなく、 アルザス・ロレーヌ やシュレジェンなどの資源産出地も割譲されられ、軍備も大幅に制限された。また、同条約の第231条で戦争責任を負わされたドイツは多額の 賠償金 をかせられることとなり、その金額は後に1320億金マルクととけって胃された。さらに、これらの戸きり決まり効されるかどうかを監視するために、 ラインラント の一部(ライン左岸)は連合軍が15年間占領することになった。このた。 ヴェルサイユ条約 によって中央~東ヨーロッパに7つの独立国(ポーランド、チェコスロバキア、リトアニアなど)が誕生したがこれには明らかにドイツと ソ連 を封じ込める狙いがあった。また、 ウィルソン の 「14ヶ条」 による提案を受けて 国際連盟 が発足したが、アメリカが上院の反対にあって加盟せず、ソ連やドイツも当初は参加が認められなかった。
D .ドイツに課せられた多額の 賠償金 支払いは同一経済を破綻させ、1922年、ついにドイツはその支払いを停止した。これに対し、フランスはベルギーを誘ってドイツ最大の工業地帯である ルール 地方を軍事占領した。フランスがこのような強硬な措置を取ったのは、第一次大戦中のアメリカからの 外債の償還 にドイツからの 賠償金 が不可欠だったからである。これに対しドイツが行った、いわゆる「消極的抵抗」は破局的な インフレーション を引き起こし、ナチスや共産党といった極右、極左勢力を台頭させた。これに対し機器を感じたアメリカは ドーズ案 を提示して賠償金の支払いの円滑化を図ると同時に、ドイツに多額の借款を与えて経済復興を助けた。この結果、フランスは ルール から撤退し、ドイツも 履行政策 を推進するようになったため、ヨーロッパ諸国は協調に向かうこととなった。1925年にはヨーロッパ7カ国により ロカルノ条約 が結ばれ、ドイツ西部国境の現状維持と相互不可侵が取り決められた。また、1928年にはアメリカ国務長官 フランク・ケロッグ とフランス外相 アリスティード・ブリアン の提唱により不戦条約(ケロッグ=ブリアン条約)が結ばれた。さらに、1930年には ロンドン海軍軍縮条約 が結ばれ、補助艦の制限が行われた。
E .1920年代のアメリカ合衆国では、空前の経済的繁栄の中で 孤立主義 の傾向が強まっていた。上院議会が ヴェルサイユ条約の批准を拒否 したのはその現れである。しかし、そうした石とは裏腹に、アメリカは世界一の債権国としてヨーロッパ諸国の復興などに力を注がねばならなかった。また国内では 保守主義・排外主義 の傾向が強まり、イタリア系移民を無実の罪で処刑した サッコ・ヴァンゼッティ事件 や黒人へのテロを行う K.K.K(クー・クラックス・クラン) の台頭に見られるように海外からの移民や黒人などのマイノリティー、あるいは共産主義者・社会主義者への追害が頻繁に行われた。
F .第一次大戦に妻子、イギリスはインドに対して出兵と引き換えに戦後の自治を約束していた。ところが、戦後のイギリスは自治を認めず。ローラット法を制定して民族運動の弾圧を図った。これに対し、インド国民議会派の指導者ガンディーは独自の非暴力・不服従運動を指導して抵抗した。1920年代後半からは国民会議派の急進派の指導者ネルーと協力して完全自治=プールナ・スワラージーを目指す運動を展開、1930年には塩税法に講義するため塩の行進を行った。これらの運動にはヒンドゥー教徒だけでなく多くの 知識人 も参加し、イギリスに脅威を与えた。
G .第一次大戦中、列強の勢力が後退する中で、超動くでは民族資本が成長し、西欧の近代思想を学んだ新知識人も台頭してきた。こうした背景から新しい文化運動が起こってくる。
1915年、 陳独秀 は雑誌『新青年』を発刊、 儒教道徳 を痛烈に批判し、大きな反響を呼んだ。さらに、この雑誌の中で 胡適 が「文学改良芻議(ぶんがくかいりょうすうぎ)」という論文を発表、 自話文学(口語文学) を提唱し、新しい文学運動を生み出した。 魯迅 の傑作『阿Q正伝』『狂人日記』などはこうした中で書かれたものである。これらの運動は、帝国主義的侵略と封建支配に苦しんでいた中国の人々の意識を変革し、新しい時代の精神を生み出す力となった。
大戦後の1919年4月、パリ講和会議で、中国が要求していた 「二十一ヵ条要求」 の地理けしが拒否されると、北京大学の学生たちを中心とする抗議運動が行われた。この運動を五・四運動という。彼らは、 二十一ヵ条要求 の取り消し、 二十一ヵ条要求 を受諾した 親日派の政治家の罷免 、 ヴェルサイユ条約の調印拒否 を北京政府に要求し、全国的な運動の高まりの中で、ついに北京政府は ヴェルサイユ条約調印拒否 などの要求を呑んだのだった。
五・四運動は1920年代の中国の革命運動の出発点となった。1921年、 五・四運動 のリーダー達を中心として 中国共産党 が結成され、コミンテルンの指導の中で 孫文 を指導者とする 中国国民党 との合作を呼びかけた。これを受けて、1924年1月、 中国国民党 は 「連ソ・容共・扶助工農」 を綱領として、 中国共産党 が党籍はそのままで 中国国民党 に加入することをみとめた。これを 第一次国共合作 という。
ここで一万字を突破しちゃったので
ちょっと休憩。
あとでまた更新します。