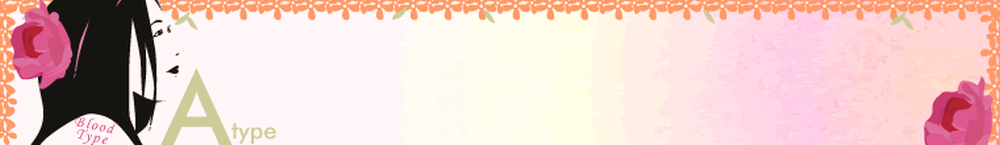PR
Free Space
どうして
大人に
なるんだろう
嗚呼
僕は
いつごろ
大人になるんだろう
Comments
Calendar
Keyword Search
1925年に公衆で起きた5・30事件は、中国全土に革命運動が広がるきっかけとなった。翌1930年、国民革命軍は北方軍閥の征討運動、すなわち 北伐 を開始した。軍は順調に勝利を重ねていったが次第に 中国共産党 と 中国国民党 の対立が表面化してきた。1927年34月、中国国民党右派の指導者・ 蒋介石 は財閥や列強の支持のもとに上海でクーデターを決行し、 中国共産党 の弾圧に転じた。国民革命と袂を分かった 中国共産党 はその後農村で 解放区(ソヴィエト) を組織する中国独自の革命路線に転換していった。一方、この頃から日本の中国への干渉が強化された。1927~28年にかけての3次にわたる 山東出兵 や、1928年6月の 張作霖羽爆殺事件 などがその例である。しかし、1928年6月には国民革命軍は北京に入場し、父 張作霖 の後をついで満州の支配者となった 張学良 も国民政府への参加を表明したため、ここに中国は 中国国民党 の下に一応の統一を見たのである。
H .日本の植民地となっていた朝鮮では、1919年3月1日、知識人33人により記草された 「独立宣言文」 が発表され、これを機に大規模な民衆運動が全土で展開された。これを 三・一独立運動 という。日本はこれを武力で徹底弾圧したが、以後、支配政策を従来の 武断政治 から 文化政治 へと転換した。
1937年以降、日本の中国侵略が本格化すると、日本人としての意識を植え付けることで戦争への全面協力を強いる政策が行われた。「私共ハ大日本帝国ノ臣民デアリマス・・・」という 「皇国臣民の詞書」 を制定(1937年)したり、名前を日本風に改めさせる 創氏改名 を断行(1940)したりしたのはその礼である。これらを総称して皇民化政策という。
I
.1929年10月のニューヨーク市場での株価大暴落をきっかけに、世界は未曾有の大恐慌に巻き込まれた。その中で、資本主義諸国はそれぞれに強硬の打開策を模索していった。
大恐慌勃発時の合衆国大統領 フーヴァー
は、ヨーロッパ諸国に対して賠償金や債務の返済を一年間猶予する、いわゆる 保護貿易政策
を行ったが、国内の政策は中途半端でまったく効果を上げず、1933年の大統領選挙で民主党の フランクリン・ローズヴェルト
に大敗した。この新大統領 フランクリン・ローズヴェルト
が行ったのが有名な ニューディール
である。 ニューディール
の主な政策としては労働者保護と価格引き上げのための生産制限とを行わせる 全国産業復興法・・・(NIRA)、
作付面積を縮小した農民に保証金を与える、 農業調整法
、失業対策や総合的地域開発を目的とする TVA(テネシー川流域開発公社・・・Tennessee Valley Authority)などの政府企業の設立
などが有る。しかし NIRA
と 農業調整法
はそれぞれ1935年、1936年に違憲判決を受けたため失効した。そこで フランクリン・ローズヴェルト
は ワグナー法
を制定し、あらためて労働者の権利保護を図った。これ以後AFLと並ぶ新しい労働組合・ CIO(産業別組織会議)
が発展し、非熟練労働者の組織化が進んだ。
J
.イギリスは、 マクドナルド首相
率いる挙国一致内閣の下、1931年の 金本位制
の停止、翌年オタワ(カナダの首都)で開かれた英連邦会議における 特恵関税制度
の確立により、いわゆる ブロック経済政策
を進めていくことになった。これをきっかけにほかの資本主義諸国も同様の政策をとるようになる。アメリカ合衆国のラテンアメリカ諸国に対する 善隣外交
とよばれる新しい外交もその現われと見ることができる。また日独伊などのようないわゆる「持たざる国」の場合は、侵略によって自国の経済範囲を獲得していくことになる。
1933年1月、政権の座に着いたヒトラーは同年3月の 全権委任法
の制定によって独裁の権力を確立すると、 ヴェルサイユ体制
の打破に着手した。すなわち国際連盟を脱退、1935年には 再軍備宣言
を行って ヴェルサイユ条約破棄
を公然と宣言し、翌36年3月には ラインラント
に進駐して世界を驚かせた。そして同年9月から 4ヵ年計画
に着手し、東欧にドイツ人の 「生存圏」
を獲得するための戦争準備を開始したのである。このように、いとも簡単にドイツの再軍備を許した背景にはイギリスがソ連をけん制するために勧めたいわゆる 宥和政策
があったといわれる。
K
.1931年9月18日、奉天郊外の 柳条湖付近
で満鉄線が爆破される事件が起きた。日本の 関東軍
はこれを 張学良軍
の仕業であるとして満州全域を制圧、大陸侵略の大きな一歩を踏み出した。この出来事を 満州事変
という。さらに翌32年1月上海で日本人僧侶が襲撃され、ここでも日本軍が軍事行動を開始した。これを 上海事変
という。これらの事件は、いずれも 関東軍
が仕組んだ謀略であり、いわば軍部の暴走だったのだが、時の若槻礼次郎内閣は結局軍部の行動をとめることはできず、むしろその行動を追認していった。
中国側は事件を日本の謀略であるとして国際連盟に提訴、これを受けて リットン調査団
が現地に派遣されることになった。これに対し日本は1932年3月、 満州国
を建国し、民族自決の名の下に侵略の事実を覆い隠そうとした。しかし、国際連盟は事件の責任は日本にあるとしたため、終に翌33年3月、日本は 国際連盟を脱退
、孤立化の道を歩み始めた。
こうした日本の侵略に対する中国民衆の反感が強まる中、国民政府を率いる 蒋介石
は相変わらず 中国共産党
を敵視する政策を続けていた。これに対し、 中国共産党
は 八・一宣言
を発し、内戦の停止と抗日統一戦線の結成を呼びかけた。これに動かされた 張学良
は 中国共産党
と休戦協定を結び、督戦に来た 蒋介石
を逆に幽閉、終に 中国共産党
との統一戦線に合意させた。この事件を 西安事件
という。
1937年7月、北京郊外で 盧溝橋事件 が起こり日中両国は全面戦争へと突入した。同年12月には 首都・南京 に日本軍が入城、以後2ヶ月間に渡って市民を大量虐殺する事件も起こった。日本の侵略は中国全土へと広がっていったが、37年9月には 第二次国共合作 が成立し、また中国人民の抵抗も激しく、日本軍は戦争の泥沼へとはまり込んでいった。
L.
ヨーロッパではイタリアのファシスト政権が1935年10月、 エチオピア
に侵入、翌年3月にはその征服に成功し、ファシズムの脅威はさらに強まった。またこの エチオピア問題
をきっかけに、独伊は ベルリン・ローマ枢軸
と呼ばれる提携関係を結び、さらに同年11月には 日独防共協定
が、翌37年にはそこにイタリアを加えて 三国防共協定
が成立、ファシズム陣営の結束が強まっていった。
こうした動きに対し、反ファシズム陣営では、1935年8月に コミンテルン
の第7回大会でいわゆる 人民戦線戦術
が採択され、翌36年には フランス・スペイン
の両国で 人民戦線内閣
が成立した。
1936年2月、 スペインに人民戦線内閣が成立 すると、国内各地で右翼勢力が反乱を開始、モロッコでは フランコ将軍 がクーデターを宣言し挙兵した。スペイン内乱の勃発である。この戦いでは反乱軍側にドイツ・イタリアが、また政府軍側には ソ連 が援軍を送り、また政府軍側にはさらに世界各国から 国際義勇軍(白井さんとか) が援軍に駆けつけ、ファシズム対反ファシズムの国際戦争の様相を強めた。しかし、 反ファシズム側 の内部不統一もあって、戦いは反乱軍の勝利に終わり、ファシズムの脅威はさらに増すこととなった。
M.
1938年ドイツと ポーランド
の合邦を成し遂げたヒトラーは次にチェコスロバキアに対して ズデーテン地方
の割譲を要求した、イギリス首相 ネヴィル・チェンバレン
はこの問題を解決するため仲介に入り、ここに1939年9月末に英独仏伊4カ国の首脳による会談が行われた。これを ミュンヘン会談
という。しかし、ここでもまたドイツへの譲歩、すなわち、 ズデーテン
のドイツへの割譲が承認され、ヒトラーは難なく東方侵略を進めることができたのである。このミュンヘン会談はイギリスの 対独宥和政策
の典型例とされる。この宥和政策の背景には、イギリスなどの ソ連
に対する警戒心があり、ナチス=ドイツの侵略の矛先をソ連に向けようという意図があったといわれる。
しかし、その早くも半年後、(1939年3月の半年後)ヒトラーはスロヴァキアの保護国以下とベーメン・メーレン(ボヘミア・モラヴィア)の併合を行った。これをチェコ併合という。ここに、 宥和政策
は破綻を見たのである。
一方同じ頃、ソ連・「満州国」国境近くの ノモンハン
で日ソ両軍が衝突する事件が起こった。スターリンは西方の安全を確保するため、英仏との提携交渉の一方で、ドイツとの提携も模索し始めた。これに対しドイツも ダンツィヒとポーランド回廊
の割譲などの要求をポーランドに拒否されていたためにソ連に接近、こうして1939年8月23日、 独ソ不可侵条約
が成立、世界を驚かせたのであった。なお、この条約には付属の 秘密協定
が存在し、ポーランドおよびバルト三国の分割が協定されていた。こうしてソ連による攻撃という危険の芽を摘んだドイツ軍は、1939年9月1日 ポーランド
に侵入、これに対し9月3日、英仏がドイツに宣戦、ここに第二次世界大戦が勃発したのである。
ふたつ分からないところがあります。
わかったらひっそり更新します。
追記:わかったんで更新しました☆
参考書を買っていたのをすっかり忘れていました。
あ~!
おわったぁ~・・・(達成感