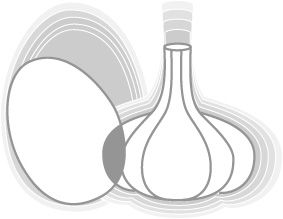PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 食べ物あれこれ(51663)
カテゴリ: 食事
植物が用意したスクロースを中心とした蜜を転化酵素でブドウ糖、果糖などに変化させ、水分を抜いて糖度80%までに濃縮されたハチミツは、濃厚な食品の代表の一つともなっています。
液体の粘度はcP(センチポアズ)という単位を使って表される事があり、ハチミツの粘度は5000~6000cPに達すると言われます。cPは摂氏20度の水の粘度を1cPとして基準にしているので、水の6000倍近い粘度を持つ事となります。
身近なところでは、とろっとした食感のマヨネーズの粘度が2000cP、トマトピューレを煮詰めたケチャップが2000~3000cPとされているので、身の回りにあるとろみのある食品の倍近い粘度を誇っている事になります。
それだけの粘度を持つだけあって、ハチミツは糖の溶解度のほぼ限界点に近い状態にあり、低温になると溶解度の限界点を超えて結晶化が始まってしまいます。冬場などにハチミツが固まってしまい、使いにくくなってしまうのは、糖の溶解度の高さによるもので、主に結晶化するのはブドウ糖が中心となっています。
結晶化したブドウ糖は容器の下の方に沈み、上澄みには液状のままの果糖を中心としたハチミツが残されます。ブドウ糖に限らず物質は凝結核があると結晶化しやすい事から、花粉などの不純物が多く含まれているとハチミツが固まりやすい傾向を持つ事になり、ろ過して不純物を取り除いてやると固まりにくいハチミツにする事ができます。
よく低温で固まると純粋なハチミツで、固まらないと糖分を加えた合成のハチミツといった言い方をされる事がありますが、単純に結晶化するかどうかだけではハチミツの純粋さを見分ける事は困難となっています。
固まってしまったハチミツは湯煎するなどで温めてやれば元にように液状化してくれますが、一度結晶化してしまうと湯煎しても後々固まりやすくなるという傾向があります。結晶化したハチミツを高温にする事で糖の溶解度を上げて液状化しますが、結晶質が完全に溶けていないと新たな凝結核となるので結晶化が促進されてしまい、湯煎が不充分であるほど再結晶化しやすくなります。
湯煎で完全に溶かす事が面倒で、上澄みだけを先に使ってしまう事もありますが、結晶化するブドウ糖と液状のまま残る果糖とでは甘さが倍ほど違い、より甘味が強い果糖を先に使ってしまうと甘味が弱くなってしまうので注意が必要です。多少手がかかるように思えますが、ミツバチの手間を考えると最後まで上手に使いたいと思ってしまいます。
液体の粘度はcP(センチポアズ)という単位を使って表される事があり、ハチミツの粘度は5000~6000cPに達すると言われます。cPは摂氏20度の水の粘度を1cPとして基準にしているので、水の6000倍近い粘度を持つ事となります。
身近なところでは、とろっとした食感のマヨネーズの粘度が2000cP、トマトピューレを煮詰めたケチャップが2000~3000cPとされているので、身の回りにあるとろみのある食品の倍近い粘度を誇っている事になります。
それだけの粘度を持つだけあって、ハチミツは糖の溶解度のほぼ限界点に近い状態にあり、低温になると溶解度の限界点を超えて結晶化が始まってしまいます。冬場などにハチミツが固まってしまい、使いにくくなってしまうのは、糖の溶解度の高さによるもので、主に結晶化するのはブドウ糖が中心となっています。
結晶化したブドウ糖は容器の下の方に沈み、上澄みには液状のままの果糖を中心としたハチミツが残されます。ブドウ糖に限らず物質は凝結核があると結晶化しやすい事から、花粉などの不純物が多く含まれているとハチミツが固まりやすい傾向を持つ事になり、ろ過して不純物を取り除いてやると固まりにくいハチミツにする事ができます。
よく低温で固まると純粋なハチミツで、固まらないと糖分を加えた合成のハチミツといった言い方をされる事がありますが、単純に結晶化するかどうかだけではハチミツの純粋さを見分ける事は困難となっています。
固まってしまったハチミツは湯煎するなどで温めてやれば元にように液状化してくれますが、一度結晶化してしまうと湯煎しても後々固まりやすくなるという傾向があります。結晶化したハチミツを高温にする事で糖の溶解度を上げて液状化しますが、結晶質が完全に溶けていないと新たな凝結核となるので結晶化が促進されてしまい、湯煎が不充分であるほど再結晶化しやすくなります。
湯煎で完全に溶かす事が面倒で、上澄みだけを先に使ってしまう事もありますが、結晶化するブドウ糖と液状のまま残る果糖とでは甘さが倍ほど違い、より甘味が強い果糖を先に使ってしまうと甘味が弱くなってしまうので注意が必要です。多少手がかかるように思えますが、ミツバチの手間を考えると最後まで上手に使いたいと思ってしまいます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.