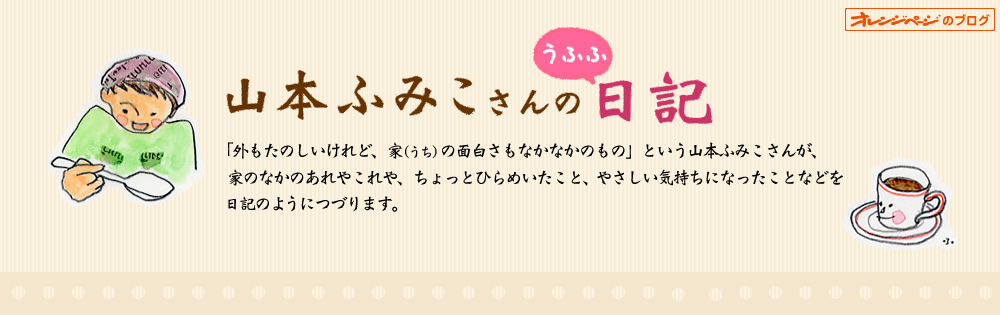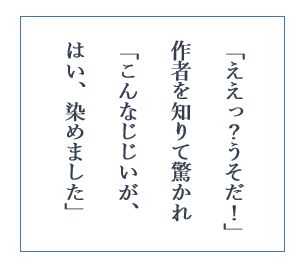2014年02月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

変態
ごはんを食べにやってきた若い友だちが浮かない顔をしている。 いろいろと不調で……、と話しはじめるその様子が気にかかり、後片づけの手をとめて、友だちの前に坐りなおす。わたしとしたら、自分のなかのひきだしをあけ、友だちの前に過去の不調の記録を全部ならべて見せようというほどの心持ちである。 そうだ。わがひきだしには「不」のつく記録がごっそり入っている。 どこかのひきだしの隅っこに成功例らしきものをみつけたとしても、用心しなければいけない。得意になってひっぱり出しても、裏面にはきっと不行き届き、不徳といった「不」の連中が貼りついている。そのことはとりもなおさず、わたしの数少ない成功が、さまざまの「不」にもめげずたくさんのひとの助けによってやっとのことでひきだしに納まったことを意味している。 さて、友だちは云う。 「変わりなく日日の仕事をこなし、変わりなくひとと接しているのに、いつものようにゆかない」 それをことばどおりに受けとり(ひとのはなしを聞くとき、ともかくことばどおりに受けとることが大事、と心得ている)、聞いたことばを反芻(はんすう)する。 「変わりなく……、日日の仕事をこなし……、変わりなく……、ひとと接しているのに……、いつものように……ゆかない」というふうに。 反芻の効能だろうか、不意に「変態」ということばが胸に置かれた。へんたい。変態じゃなくて、変態。……何云ってるんだろう、ええと、昆虫やカエル、植物が、成長のなかで異なる形態をとることをさす変態である。ほら、オタマジャクシがカエルになるような、あれだ。 「変態なんじゃないの?」 友だちに直球を投げてみた。 案の定「ぼくのどこが変態なんですか?」という顔をしたから、オタマジャクシに登場ねがって、説明す。 「あなたが変化してるんじゃないかってこと。敏感なひとは、それを感じとって怪しむだろうし、わけがわからなくて苛立つこともあるんじゃないかな。変態の時期をどう過ごし、どこにつなげるかは自分で決めるしかない。ひとつだけはっきりしてるのは、カエルは、二度とオタマジャクシにはもどれないってことだよ」 変態、変態と云いながら、家じゅうのみんなで友だちを囲み、日本酒を飲む(高校生は、お茶)。変態おめでとうの意味の酒盛りだったが、そのことは伝わったろうか。伝わらなくてもかまわない。ただただ、わたしは友だちの変態を見守ろう。 翌日、ソチ冬季オリンピックの閉幕を迎えた。 やけに熱心に競技を追いかけている自分に驚きつづけた2週間だった。いろんなことを気づかせてもらった。 誰もメダルが好きだけれど……、メダル獲得はうれしいものにちがいないけれど……、メダルに納まりきれない事ごとに刮目(かつもく)する、その連続だったようでもある。 閉会式を前に放送の「ソチ冬季オリンピック・ハイライトシーン」なる番組をテレビで観ながら、わたしはまた変態を考えている。友だちを「変態だ」と決めつけたことから、同じことばを自分自身に当て嵌(は)めているのである。 かつてわたしも幾度かみずからの変態に気づいたことがある。ひとつひとつ数えたら、10本の指では足りないような気がする。ところが最近はどうだろう。この歳になったから、もう変態などはないと、高を括っているのではないか、わたしは。 頭のなかがこんがらかってきた。こんなときは、手仕事にかぎる。 夫の実家で穫れたもののほか、ほうぼうからいただいてたまった里芋をならべたて、ひとつひとつ皮をむいてゆく。 ソチ冬季オリンピック。里芋。変態。 何の関係もないように見える3つのものが手を組んで、わたしに何かを促す存在となっている。里芋はピンポン玉大のコロッケになった。テレビには、フィギュアスケート・フリープログラムで最高の演技を終え天を仰ぐ浅田真央選手の姿が映っている。 ———この春、わたしも変態しなくちゃ。 しきりにそう思わされている。 〈つづく〉雪のなかのブロッコリ。埼玉県熊谷市の夫の実家の畑の様子です。「お互いがんばろうね」としみじみしました。東京にまで降り積もった雪が、ソチ冬季オリンピックに気持ちを近づかせてくれたようでもあります。ね。
2014/02/25
コメント(26)
-

雪の遠足
東京・新宿のカルチャーセンターではじまった「エッセイを書いてみよう」の講座も、気がつけばじきに2年めを迎える。 お話をいただきはじめてみようと決心したとき、先のことはまるで予測できなかった。自分にできることは4つ。皆さんの作品を読むこと、ちょっと添削すること、時時(ときどき)にふさわしい文章を紹介すること、わたしの知る限りの書くときのちょっとした約束事を伝えることだけだった。できることは一所けん命したいと思って、そうしてきたつもりだが、そのこととは別のところで講座は育ち、つづいてきた。 12人からスタートし、現在は20代から80代まで20人のお仲間がある。20の世界がやさしくやわらかく咲いており、わたしはそのあいだを、唸りながら飛んでいる。そうだ、まさにそんな感じ。 1年半が過ぎたころ、講座の皆さんと遠足をしてみたいと考えるようになった。いつか、そんな機会がめぐってくるといいなあと思いながら、遠足に行くなら……、と、行き先を考えるともなく考えていた。 2月に1回、わたしの都合で休講しなければならない日ができたとき、あ、遠足!とひらめいたのは、自然なことだった。講座1回のかわりに遠足を計画したのである。そのときには2月の寒さを考えず、雪の予想もしなかった。ただただ、あたまのなかに「えんそく」のひらがら4文字がひらひらひらひら飛んでいた。 大人としての配慮には欠けているが、配慮ばかりじゃおもしろいことの生まれる余地はない、とこっそりわたしは考える。 遠足当日は雪の予想だった。 東京へのことし2度めの大雪がくるという。 予想は見事に的中し、その日の朝、起きたときにはあたりはもう白かった。 ……雪の遠足。笑おうとしたが、笑えなかった。思いきりうろたえた。 よほど情けない顔をしていたのだろう、夫が「バスでの移動もあるから、ぼくも行くよ」と云ってくれた。当然のことながら、欠席の連絡が3人から入る。 結局総勢14人の遠足となった。 集まったひとりひとりの顔を見るなり、笑いがこみ上げてきた。たのしい遠足になりそうだった。 テーマは、東京都武蔵野市めぐり(わたしの暮らす街である)。 ひと・まち・情報創造館「武蔵野プレイス」、やさい食堂 七福(武蔵野福祉作業所)、武蔵野市立吉祥寺美術館である。 やけにたのしくて、それぞれが何かをみつける不思議の遠足となった。このはなしは、いつかどこかでゆっくり聞いていただくとしよう。 翌日は土曜日で、びっくりするほど雪が積もっていた。 家のなかの感覚だと、綿のようなものにくるまれているようでもあった。静かな朝だった。 静けさを破って、電話が鳴る。1月の半ばに家を出て、ひとり暮らしをはじめた長女からだった。 「おはよう。雪、だいじょうぶ?」 と挨拶。 前夜、帰宅が遅くなった上、電車が動かず難儀したそうだった。最寄り駅から、暗くて長い道をひとりざくざく、ざくざく歩いて帰るところを、偶然友人のクルマに拾われて、帰宅したというはなしを聞く。 奇跡のようなはなしだが、こちらも負けじと雪のなかの奇跡の遠足のはなしを聞いてもらう。電話を通して、笑い声が耳に響いた。 「あのさ、ちょっともホームシックにならないの?」 と尋ねる。 「忙しかったから、かかる間がない」 という答え。それは、こちらも同じだった。仕事や用事に救われて、さびしがる暇(いとま)がなかった。 「一度遊びにいらっしゃいよ」 と友だちに向かって云うような調子で云いながら、そんな自分の有り様(よう)だって、ひとつの奇跡だと心づく。 「行く行く。あのね、お母さん、とっても暮らしがたのしいよ」 ことしは、冬期もぬか漬けを休まず(これまでは冷凍していました)、やってきました。食卓を支えてもらいましたし、胃腸も守ってもらっているような気がします。友人が、ぬか漬けめあてにやってきて、ビールを飲んだりして、それも愉快です。写真はブロッコリ(さっと茹でて漬けています)、セロリ、かぶ、大根、にんじん。ほかにこの季節は、ピーマン、きゃべつ、いろいろの青菜、長芋を漬けます。ぬか漬けを休まずつづけられたことも、この冬の奇跡でした。
2014/02/18
コメント(39)
-

雪の伝言
東京都心に27センチもの雪が積もった。 わたしのところは都心のはずれだから、もう少し積もった。 これほどの積雪は、45年ぶりのことだと云う。 週末でもあったから、いつになくおおっぴらに雪をよろこぶ。 寒さのきびしい土地の、ことに山間部を考えたら、本筋からずれるようだけれども、都心の場合、雪でもっとも困るのは、交通機関の乱れである。雪は降るたび、ひとの足を妨(さまた)げる。雪に不馴れな分、都心のひとの困り方には、目を覆いたくなるものがある。それで、とてもではないが、雪、雪、ばんざーい!などとは叫んだりできない。東北出身の友だちにそっと、雪うれしさのメールをするにとどめてきた。 土曜日の朝早くから、あたりは銀世界に変わっていた。めずらしく粉のように細かい雪が、これまためずらしく吹雪(ふぶ)いている。窓越しに眺めていると、あっという間に雪かさが増してゆく。 友人が、「息子がかまくらをつくりたがってね」と云っていたのを思いだした。このまま降り積もれば、かまくらづくりも夢ではないかもしれない。 その昔、わたしが十(とお)くらいであった昔、東京に大雪が降った。 父は生まれも育ちも北海道であったから、朝の早よから装備を整え(父は毛皮の耳当てのついた帽子をかぶっていた)雪かきにかかり、弟とわたしが起きだしたときには、当時空き地だった家の前まで、雪の道ができていた。少しの雪が積もっても、わたしたち姉弟(きょうだい)は、雪だるまをつくり、雪に遊んだものだが、それも両親、ことに父の雪うかれの後押しがあったおかげだ。 東京の雪だるまは、どうかすると土混じりになったり、そうでなくとも、すぐと溶けていなくなってしまう。わたしが好んでこしらえたのは、雪だるまのきょうだいだったが、ならべてつくった雪だるまのきょうだいたちが、学校からもどるころにはふたり半くらいになっていた。長男から8男までの大家族なのだが、末に向かうほど小振りにつくるため、このような悲劇に見舞われるのだった。そうだ。雪だるまとのあっけない別れは、幼いわたしには悲劇としか云いようがなかった。 さて、わたしが十だとすると、弟は九(ここの)つということになるが、その年、ふたりは、東京校外の実家前に、かまくらをつくったのである。後(あと)にも先にもかまくらは、つくるのも入るのも、そのとき一回きりだった。雪まみれになりながら、ふたりとも汗だくになった。掘る雪はどこまでも白く、どこまでも豊富だった。でき上がったかまくらは、ふたりがまるまってならんで坐るといっぱいのこじんまりとしたものだったが、それでもかまくらにはちがいなかった。母は、「おめでとう」と云って、湯を注いだ懐中汁粉を運んでくれた。 そのかまくらが次ぐ日、どんなことになったかは、記せない。記憶から消えてしまっているからだ。かまくらのなかで、窮屈に弟と肩寄せあって食べた汁粉のところまでおぼえていれば、それでよかった。 週末ニュースでくり返し伝えられた東京の、45年ぶりの大雪というのは、あのかまくらのときだったのだろう。そのときから45年の歳を重ねたわたしは、雪だからと云って外に飛び出したりはしない。窓辺でじっと雪の降るのを眺めている。出かける予定もなしにして、ひたすらぼんやりしていた。雪は等しくひとや小鳥、動物の目に映り、雪はどんな地面も、どんな草木も覆う。そうした目的を持って降るのではないにせよ、雪はこの世を浄めてゆく。 日曜の朝カーテンをあけると、おもては前日とは打って変わって、雪に輝いている。雪はやみ、日が燦燦(さんさん)と照っている。かつても悲劇を思いださないこともなかったけれど、雪は分厚く、まだ、子どもたちのつくった雪だるまたちは無事だろうと思い直す。 昼過ぎ、旅仕事からもどった夫が、玄関に荷物を置くなり雪かきをはじめた。前日からのぼんやりをまだつづけていたわたしが、ふと我に返ると、2時間以上が過ぎていた。夫はまだ雪と格闘しているらしい。2軒先のあたりに姿をみつけたので、声をかけると、「雪遊びだな」と笑った。 「ご苦労さま」 45年ぶりに降った雪は、わたしにぼんやりする時間をくれ、夫には近隣を思う機会を与えたのかもしれなかった。雪から2日たった月曜日の午前中、近所で雪だるまの無事を確認。葉っぱの目、小枝の口。壊れたカチューシャと葉っぱの蝶ネクタイも、洒落ているでしょう?
2014/02/10
コメント(27)
-

節分
目覚めたとき、あたまのなかは節分でいっぱいだった。 豆の準備よし、恵方巻きの準備よし、と確かめて布団をはね除けた。 豆まきの豆と恵方巻き(うちのは、ひとり1本ずつの細巻き)があれば、じゅうぶんに節分を迎えることができそうにも思える一方で、わたしは何かをさがしている。いったい何を……? もぞもぞと動きそうな何かに向かって、目を凝らそうとしている……。 湯を沸かしたり、弁当をこしらえたり、ぬか漬けの大根に塩をまぶしたり、洗濯物を干したりしながら、もぞもぞの主をさがす、さがす、さがす。 ゼロ時限講習(1時限前の授業/数学)のため、早出の娘を高校へと送りだしたあとも、もぞもぞの尾はつかめそうでつかめず、洗濯ものを干すときスニーカーソックスのつま先にみつけた穴を繕うことにした。穴に気づかなかったことにして干すと、わたしは穴を忘れる。すると、穴あきの靴下が幾足もたまることになって、結局それらの繕いに半日かかったりするのだ。ごく最近、干すときに気がついた穴は、干す前の湿った状態で繕うようにしてみたら、これがなかなかいい具合だ。時に溜めこんだりしていたとはいえ、繕いものだけはやめるわけにはいかない。これほど、後世に伝えたいこともないというくらい、大事なしごとだ。 繕いものは、わたしを、さがしていたもぞもぞに近づけたようだ。 近づいた、近づいたと思って、胸のなかが晴れてゆく。 そのこころが思いださせたのが、窓の敷居だった。 家の窓の敷居に埃がたまっていたのを思いだしたのである。湯を張ったバケツと雑巾と、乾拭き用のボロ布と古歯ブラシを持って、ひとつひとつ、窓と対面す。古歯ブラシで埃をたたき出すうち、どうやら、このしごとは節分にふさわしい、と思えてきた。 夜、皆がそろったら、「鬼は外」と、「福はうち」と云いながら豆をまくことになるだろう。子どものころから欠かさずつづけてきた立春前日の節分の豆まきだが、その日を迎えるたび、鬼とは何だろうか、福とは何だろうか、と考えてしまう。それこそが、この日、わたしがさがしていたもぞもぞの主だったか。 鬼という存在のなかに福が宿るのを見ることも少なくはないし、福と呼ばれるものが鬼の一面を持っていることは、もっと少なくはない、というのがわたしの実感なのだ。歳を重ねるにつれて、鬼と福とを分けて考えられなくなってゆく。子どものころから、鬼を疎(うと)めない体質だった。これには、「泣いた赤鬼」(浜田廣介作)のものがたりの影響もあったかもしれない。 家じゅうの窓の敷居の掃除を終えたわたしは、この敷居をまたいで、鬼がくるもよし(きたければ)、福が去ってゆくもよし(去りたければ)、と考えている。鬼も福も好きにしたらいいけれど、問題はわがこころだ。胸の「ここ」は、すがすがしくあらねばならない。何をするにも、何を捉えるにも、澄んでいなければしきれないことばかり、捉えられないものばかりだという思いが募っている。澄んでいなければ、と云っても、いきなり澄むわけではないから、正確に云うなら、澄みたいと希うことなのじゃなかろうか。 夜になったら、「澄みたい、澄みたい」と思いながら豆をまこう。節分の朝、家のなかをうろうろしているときに、飾り棚や書架で、昔、絵を描いた石と目が合いました。ひとところに集めてみました。長いこと離ればなれになっていた石を合わせるというのなんか、じつに節分らしいではありませんか。これは、食器棚のなかでうたた寝していました。カップラーメンを食べるときの、ふたの重石(おもし)です。
2014/02/04
コメント(24)
全4件 (4件中 1-4件目)
1