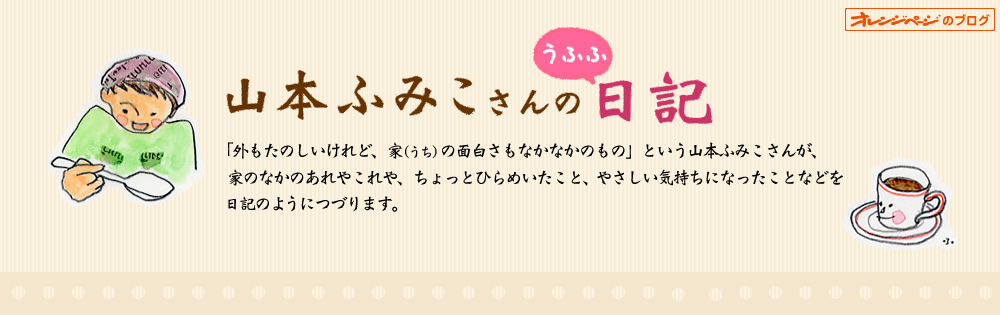2014年01月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

原点
到来物の白味噌の羊羹(ようかん)と、渋めのお茶を、と思った。 休みの日の朝、このような甘味とお茶をたのしむことがある。文字通り「朝飯前」のひとときだ。食卓には、朝ごはんの仕度がほぼできているので、ちゃぶ台を出して……。 そうだった、ちゃぶ台はなかった。 ひとり暮らしをはじめた長女に持たせてやったのだった。 ひとり暮らしの準備に際し、娘に伝えたいことがあった。 「間に合わせのモノは持たない」 というのがそれだ。 が、なんとなく口に出して伝えるのは憚(はばか)られた。娘には娘の考えがあるのだから、との思いから、口にしかけて黙った。それに、「間に合わせのモノは持たない」ということなら、すでにじゅうぶんに伝わっているはず、と思いたくもある。 わたしが娘ふたりと3人の暮らしをはじめたとき、テーブルは持たず、暮らしのまんなかに古いちゃぶ台を置いた。ちゃぶ台は、わたしの暮らしの原点であり、「間に合わせのモノは持たない」という、暮らしの象徴的存在だった。 現在、娘の家にはないモノがたくさん。 たとえば机。たとえばフライパン。包丁もない。包丁はただし、わたしが使ってきたペティナイフだけは持たせた。三徳(文化包丁)は、いずれ贈れたら……と考えているけれど。 娘の引っ越しを手伝ったとき、荷造りの箱のなかに、おろし金をみつけた。 「取材先でもとめたんだ。一点豪華というヤツです」 うつくしくて頑丈な、純銅製だった。 それを見て、ああ、これがこのひとの原点だな、と得心した。云うことは何もない、と思った。 若いひとに伝えたいのは、調度の類いは間に合わせで持っても、吟味して持っても、長持ちするということ。気がつくと、軽く20年くらい過ぎてしまう。20年が過ぎたとき、間に合わせの道具の多くはそこで終わりを迎えるが、吟味して選んだモノの多くは、まだゆける。修理も利く。この実感だけは、若いひとにはつかみきれぬだろうと思うものだから、こそっと云っておきたいのである。 老婆心のついでに書いておくのだが、家に食器棚が入り用、食卓が入り用、ソファが……、というのはどこかで誰かがつくり上げたイメージだ。このイメージに囚われて、暮らしをスタートさせるのはいかにも窮屈。 自分がどんな暮らし方をしたいと考えるか、どんな好みを持っているかを尋ねつつ、計りつつ、ゆっくりゆくのに限る。ほんとうに欲していたわけではないのに、のせられてもとめてしまった調度に苦しめられる(空間を奪われる)のだけは、よろしからず。……である。 ところで、朝飯前の甘味とお茶を、わたしたちは盆の上でたのしんだ。ちゃぶ台もよかったけれど、盆もいい。わたしが好きで、使いつづけてきたべこべこのフライ返しです(右)。娘にも同じモノを、とさがしさがして、もとめました(左)。押しつけがましいとは思ったものの、「べこべこ」を愛するあまり……。
2014/01/28
コメント(35)
-

暮らしの子ども
長女の家に荷物を運びこんだ日から3日間は連休で、皆で通ってカーテンを取りつけたり、棚を吊ったりした。注文した灯油ストーブの到着を待って、長女は本格的に転居することになっていた。 その日は、4日めの朝にやってきた。 いつものように起きてきて、いつものように朝ごはんを食べ、いつものように玄関で靴を履き、「じゃ、行ってきます」と長女は云った。けれど、もう、このひとはここへは帰らない。 「ときどき、遊びにきてくだ……」 と妙ちきりんな挨拶をしかけたら、娘に遮(さえぎ)られた。 「いつもどおりにたのみます」 「い、行ってらっしゃい」 その日から1週間が過ぎようとしている。 仕事と雑用に追われて、感傷に浸る時間がなかったのは幸いだったかもしれない。すでに胸は何かが破れるような音をたてたし、そこから立ち直ろうともがきもしたし、それでじゅうぶんな気がした。じゅうぶん、という思いが湧いたのは、そこを通ったおかげで、あたらしい生活をはじめるつもりになれたからだ。 これでいい。 ひとり暮らしの経験のないわたしは、娘のおかげで、ひとり暮らしとはどんなことであるかを学ばせてもらっている。わたしが実家から独立したときは「結婚」で、相方がいた。約7年後「離婚」したときにも上ふたりの娘たちが一緒だったから、ひとり暮らしにはならなかった。最初の夫との生活は、通勤時間が長かった苦労と、空き巣に入られたことのほか、記憶がない。おぼえていなくてもかまわないかな、と考えた時点で記憶が薄らいでいったような。 一方、それにつづく3人暮らしの記憶は鮮明である。あのころのわたしはたくましくもあったが、そのじつ、幼い長女と二女にたよってもいたことが、いまよくわかる。たよるというより、しがみつくと云ったほうがいいかもしれないほどに。 とくに長女は、わたしの選んだ生き方を体現するかのような、そんな存在であった。子というよりも、相棒だった。 その相棒に対する長年の思いが、いま、わたしのなかで渦巻いている。これまで口にしなかった分の「ありがとう」の渦のなか、溺れてしまいそうだ。これからあたらしい生活がはじまると感じているのは、わたし自身が親元から離れたこの30余年が、相棒の独立によって、ここでざっくり締めくくられたからだ。思えばめまぐるしい歳月だったが、相棒が「(自分の住む)家がみつかったの!」と云った瞬間、この30年一括りの「1章」(もっと細かい分け方があるだろうとしても)が終わった。 現在、長女のいなくなったこの家のなかに、小さなふたつの引っ越しが行われている。 長女と三女が使っていた2階の15畳あまりの部屋と、わたしたち夫婦の6畳の部屋を取り替えるのがひとつ。15畳の部屋に、夫の仕事場を移すのがひとつ。 まさに、あたらしい生活がかたちとなってはじまっているのがおもしろくもある。長女の引っ越しのさなか、暮らしが暮らしを生んだなあと考えたが、長女の暮らしがこちらにも暮らしを生まれさせたのだった。暮らしの子どもがあちらにも、こちらにも。 三女は自分ひとりの部屋を気に入って、これまたあたらしいページを生きはじめている。わたしはと云えば、生まれたばかりの暮らしの子どもたちが、排出したモノを片づけながら日を送っている。不要なモノを持たずに暮らしていたつもりだったが、どうしてどうして。こちらの油断につけ込んで、なくていいようなモノたちが列をなし、わたしを見上げて笑うのだ。 イヒヒヒヒと、笑うのだ。長女の家の台所です。掲載許可を得ることができました。食器棚のうしろ側が、古い下駄箱です。裏側が破けていたので、板で補強しました。わたしの、ひとり暮らしの学習記録として、見ていただけたら、と思います。
2014/01/21
コメント(39)
-

ひとり暮らし
「家がみつかったの!」 と長女が云った。 そのとき、ごくりと苦いものを飲みこんだような気がしたが、気のせいだったかもしれない。 家から自転車で30分ほどの場所に、古い文化住宅をみつけたのだ、と長女は胸を張ってみせた。古いものが好き、オンボロのものを直したり磨いたりして使うのが好き、土好きのこのひとにぴったりの家だったらしい。 昨秋「ひとり暮らし宣言」をし、長女は古い家をさがしつづけていたのだった。それが2013年もそうとうに押し詰まってから、実現した。 「年の瀬の家の契約は、夜逃げと相場が決まっているのよ。あなたのような若いひとだとわかって、びっくりしたりほっとしたりしています」 と家主の老婦人は云ったそうな。 無事契約がすみ、引っ越しは年が明けて10日あまりあとに決まった。 正月、自転車に乗り、みんなで長女の家を見に行く。なるほど古い家だったが、やさしい老人がきものを着て静かに坐っているような印象を受けた。 妹たち(二女三女)が「梓らしい家だねー」、「ほんとにねー」と云って笑った。 年明けから、引っ越しの準備にとりかかった。 昨年、訪れた雑誌Kの記者に「山本さん、ほかの食器はどこにしまっているのですか?」と訊かれ、「見えているこれが全部です」と答えて驚かれた食器棚の扉を開く。ここから食器を分けてやろう、と思う。この機会に、この家の風通しもよくしよう。 そう考えようとしていた時点では、わたしは自分にうそをついていた。 しかし、器や道具類を新聞紙でくるみ、段ボールにおさめながら、胸のなかに、ごまかしようのない気持ちがひろがってゆく。 胸がちりちりする。さびしくて、胸が……。 なんとだらしのない母親だろうか、わたしは。こんなはずではなかった、娘の独立をさっぱりとよろこび、勢いよく背中を押してやるような、そんな存在であるはずだった、わたしは。ところが、胸はちりちりと震えたあと、びりっびりっと、音をたてている。胸の「このあたり」がところどころ破れるようなのである。質(たち)のよくない破け方だ。こんなことでは、身がもたない。長女が引っ越してゆくころには、ずたずたになってしまう。 けれども、胸が破けそうなことに気づいて、それをみずから認めてしまったら、そこから少しずつ、気持ちを変えてゆくことができた。 娘に向かって、「引っ越しの準備に口は出さないけど、手を貸させてね。そうすることで、背中を押せるような気がするから」と宣言す。 それから、必要なものを買いに走ったり、夫の実家の土蔵にしまってある古い器や踏み台なんかをもらいに行ったりした。夫の祖母の嫁入り道具だった下駄箱までもらってきてしまった。 自分の家のことを自分で整えようとする娘に遠慮して、隠れていそいそ準備をすすめた夜半のこと。冬休みの宿題をしていた三女に向かって、わたしは思わずこう告げていた。 「お母さんさあ、いま、いちばんやりたくないことに精出してる感じなんだよね」 正直な気持ちをこんなふうに吐露することで、だんだん、子の独立を敬うことのできるわたしになってゆけそうな。 〈つづく〉 赤ん坊だった長女のために、29年前、わたしがもとめたうさぎのちっちゃなぬいぐるみです。こんなのを眺めながら、「このうさぎさんの耳をちゅうちゅう吸っていたあなたが、大きくなったもんだね!」と云って笑えるまでになりました。1週間ほど前、思いがけないほどさびしがっていた自分をつついてやりたかったけれど、つついたら、泣けてきそうで、それもできなかった……のでした。あはは。
2014/01/14
コメント(64)
-

晴れ晴れと。
あれは、暮れの29日のことだった。 午前中、友人夫妻が年賀状を届けてくれた。古い友人であるふたりは乗松印刷という小さな印刷会社を経営しており、相手の意図を汲みとることにかけて、抜群の感覚を持っている。 「カヲリちゃん、年賀状頼むの忘れてた」 と電話をしたのが26日で、文字要素(原稿)と馬のイラストを届けたのが27日。するとたちまち校正が送られてきて、見ると、云うことなしの出来映えだった。その時点でもう、年賀状のことが頭から消えてしまった。めでたしめでたし……というように。 だからこの日、刷りたてほやほやの年賀状を渡されたとき、ああ、そうだった、とめんどうなことを思いだすかたちだった。これに宛名を書きこんだり、ひとことコトバを入れたりして、投函しなければならない……。忘れていたわけではないが、忘れたふりをしていた。 「フンコ(カヲリちゃんは、わたしをこう呼ぶ)の描いた馬の絵、禿げてるよ。馬には前髪があるんだからね」 カヲリちゃんに、わたしが描いた馬の絵のことを指摘される。そう云われたら、馬の頭のてっぺんが寂しく思えてきた。ひとだったら何でもないのに、馬の禿げ頭は思わしくないのは、なぜだろう。仕方がない、頭の毛だけ色鉛筆で描き足すとしよう。 印刷を急がせた上に、家まで届けてもらったお礼に、近所のファミリーレストランでささやかに昼ごはんをごちそうする。カヲリちゃんと夫はビールを注文し、乾杯している。乗松氏とわたしは、ドリンクバーのブドウジュースと韃靼(だったん)そば茶で。注文したもののなかのいちばん人気は、酸辣湯麺(スーラータンメン)。わたしが注文した。 帰るなり、やおら自転車にまたがり、北へ向かう。 あたらしい道路の脇に、自転車専用レーンができているのをみつけて、うかれて走る。ことし10年ぶりに自転車を買ったよろこびに浸りながら、ペダルを漕ぐ。ときどきめぐってくる坂道はきついが、わたしの心臓も足も、まだ錆びついてはいないようだ。 驚いたことに自転車レーンは、わたしの「目的地」のごく近所までのびていた。自転車レーンをはずれて小学校の裏手を走り、豆腐屋(ここのがんもどきは、滅法おいしい)の前を抜け、ビートルズのレコードをかける床屋をうれしく眺めたどり着いた「目的地」はわたしの実家である。時間にして約30分。 実家の門には、千両の実もあざやかな松飾りが2つとりつけてある。これまでの据え置き型の門松をよして、簡便なものにしたということだろうけれど、なかなか洒落た飾りである。柵状の門にとりつける縄の結び方に、見惚れる。 「やあ、ふみこか」 父が出てきたところを見ると、母は留守らしい。いまのいま、買いものに出たとのこと。 「いいの、おとうちゃまに用事だからね。90歳のお誕生日おめでとう」 「90歳だなあ」 この日は父の誕生日で、わたしはおめでとうを云うために、前にしたガラス拭きのつづきをするために、来たのだった。ガラス拭きを1時間ほどで終え、わたしは母を待たずに、また自転車にまたがった。 年末もおもしろかったが、年始もおもしろかった。 5人そろって歩いて深大寺に初詣したり、わたしの実家に(自転車部隊で)出かけたり、夫の実家に電車(湘南新宿ライン)で出かけたり、書いてみれば何ということもない日日だった。 が、その何でもない積み重ねの、かけがえのなさとおもしろみを知るこころこそは、晴れ晴れとしたこころと云えるのではないか。 ところで。 結局年賀状は、年が明けてから、書きはじめた。 そのため、1月1日は夜なべ仕事になった。同じことになっているらしい長女と向かいあい、「年の初めはさだまさし」をテレビで観ながら笑って、ときどき涙ぐんだりした。ここ数年、書家の山田麻子さんの「手書き暦」をかけています。力強くうつくしいだけでなく、おもしろい。そこが、好きです。ことしの表紙は、「陽に向かって走る馬」。そして、1月が、これ。「『志向』こころがある方向に向くこと。向かうという字には「口」が入っています。口に出すとそちらの方へ行くと私は思っています」とは、山田麻子さんのことばです。「志向」の文字は名刺サイズの作品で、両面テープをはがして、暦の「好きなとこと」に「貼る」ことになっています。わたしは……、ここへ、貼りました。
2014/01/07
コメント(38)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- ★「片付け・お掃除・捨てる」の成果★
- なかなか進まない片付け
- (2025-11-18 15:19:03)
-
-
-

- *雑貨*本*おやつ*暮らし*あんな…
- 編み物CAL2025 編み図1
- (2025-11-18 16:43:14)
-
-
-

- DIY
- 社殿の修理〈増森新田神社(埼玉県越…
- (2025-11-17 21:59:55)
-