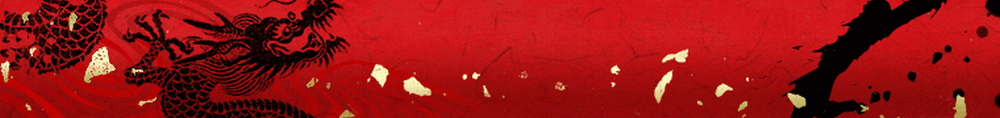2008年01月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
ローケツの着物見た事ありますか
手描き友禅の一つの技法としてローケツが位置付けられています。確かにロー彩友禅とか称して友禅の一種の様に思われてきました。しかしローケツは友禅よりも遥かな昔より染めの技法として使われてきた全く別のものと言って過言ではありません。正倉院の御物にある染技法を三纈(さんけち)と呼んでいます。纐纈(絞纈)こうけち、夾纈きょうけち、臈纈ろうけちの三つ。纐纈は絞りの事、夾纈は板締め、臈纈はろーけつの事です。当時のローケツに使われていた蝋は蜜蝋で今でも高価ですが昔は貴重品だったのでしょう。日本のローケツでは現在、蜜蝋は殆ど使われませんがインドネシアのバティックでは蜜蝋が今でも使われています。融点が高いのでぬるま湯に浸ける染に向いているのが主な理由だと思われます。正倉院の御物にある臈纈は木版彫の板を蝋鍋に浸して生地に押しつけたものや、筆で描いたもの二種類だと言われています。つまり奈良時代からローケツ染が存在していたのです。ところが中世時代にはあまりローケツの作品を見る事は少なくなり、その姿を見られる様になったのは近世になってからです。戦後、着物バブルによって彩色友禅には無い手描きの味がもてはやされ、綺麗なだけの友禅よりも深みや独特の味が着物通の人に喜ばれました。そのお蔭で、ローケツの工房は乱立、芸大出身からパートの奥さんまで沢山の職人さんが従事する事に。その工房は一階が引き染め場(長さ十五メーターは必要です)で二階はロー描きする作業場が一般的な様子です。二階でロー描きして彩色、大きい場所や地色は階下へ持ってきて染めます。ローケツの彩色に加熱して乾燥させる事は出来ませんから。それで、ざっと十人足らずのローケツ工房が沢山あったわけです。それがどうです。そんな工房殆ど無くなりました。仕事が減り、職人さんが減ると固定資産税が重い負担となって廃業に。長い染工場を持たない我が工房の様なところはローケツ染には不利で、地染めには引き染め屋さんに依頼せねばなりません。しかし、京都にはそんな工房しか残っていないのです。正絹の小紋着尺の小売上代価格がほぼ十万円の時代に入ったと言います。言わば安物の型物の全盛時代ですが、室町問屋の悪弊で皆右に倣えでそんな小紋が室町中溢れ返ってしまいました。数が売れる時代は過ぎ去ったと言うのに、その不良在庫が室町問屋を苦しめています。今日は工房の休日、大丸、高島屋の呉服売場を見てきましたが、その十万円小紋が沢山ありました。情けないですね。天下の大丸高島屋があんな安っぽい商品を売っていて恥ずかしくないのかと思う程の低級品。一般の皆さんの前にはそんな小紋しか現れなくなったのかも知れません。十万円小紋にはローケツなどの手描きの物は参入不可能です。我が工房ではローケツの小紋を染めていますが、残念ですが皆さんの前にローケツの小紋が届く事は無いかも。(臈の字は月へんでなく、草かんむりが正しいのですが表現不可になっています)
2008年01月29日
コメント(4)
-
乗っ取りと風邪にご注意
家内は鹿児島出身。テレビに出ている篤姫と自分を相対化して「鹿児島の女性は言いたい事を素直に言う」とほくそ笑んでいます。ところが無い物ねだり。それは「雪」です。子供をソリ遊びに連れて行っている内に、スキーにはまり始めました。それから滋賀県、福井県、そして新潟県まで足を伸ばしてスキー場通いが始まったのです。子供も大きくなってきたので、いく機会は少なくなってきたのですが。ところが、一月の終りは京都でも雪山を見る事が多くなります。さすればスキーの虫がムズムズと動き出した様で、毎晩ネットで宿探しを始めたのです。家内のパソコン『アイマック』は痛んだ自分の物と交換に息子に取られてしまっています。しばらくパソコンから離れていたから、たっぷりと私のパソコンと相撲取りに。で、自宅のパソコンは家内の独占状態になりやした。やっと予約がムツカシイのが分かったのか、こっちにも使える時間が出来たのですが、ちょっと体調が。工房での昼食に簡単に済まそうと、コンビニでおでんとおにぎりを食べて二時間程すると、急に胸焼けが始まりました。それから戻しはなかったのですが、下の方も悪化。他の人間はケロッとしているので、どうも風邪からの胃腸炎らしい。夜の食事はお茶一杯だけ、軽い睡眠薬を飲んで九時には床へ。お蔭で朝までぐっすり、何となく少しはマシになったみたいでした。一日消化の良いものを食べましたが、それでも胸のむかつきは残っています。皆さんどうぞお体にお気をつけ下さい。慢心はいけませんよ。
2008年01月27日
コメント(2)
-

今朝の京都は雪化粧、山に雪が
昨日、お昼からの天気予報は雪、しかし降ったのは小雨でした。朝日新聞に掲載されたので、ご存知の方も居られるかも知れませんが「職人を囲む会」というのが月に一回催されています。所は京都市下京区東洞院通花屋町下ル「大行寺関西道場」和尚さんが京都の伝統工芸の異業種交流を通じて勉強会を主催されています。昨日、次々会の講師を依頼されたので下見に行ってきました。当日の様子は詳しくはこちらに載せているので御覧下さい。ただ小雨の中、帰り道は職人の一人として作務衣姿だったものですから、寒くてたまりませんでした。今朝も続いて雨だろうと起きてみたら、京都の四方の山は雪化粧。てっぺんから三分の二程雪山に。こちらは比叡山。昨年廃業したスキー場に雪は積もったのでしょうか。左へ回って北山。奥の方もしっかり雪を被っています。こちらは愛宕山。物心ついた時にはもうありませんでしたが、スキー場とケーブルカーがありました。愛宕神社は火事除けの神様。七月三十一日の夜にお参りすると千日詣でしたと同じご利益があると言います。こちらは西山のポンポン山。狸の多い山だったのでしょうか、変わった名前のお山です。
2008年01月21日
コメント(4)
-

ぼかしの道行コート
十二月の十五日のブログには家内と義姉のきもの姿の写真を公開しました。家内はベタゴム友禅に刺繍の訪問着、義姉は友禅の留袖でした。その日のブログには掲載しませんでしたが、結婚式への道中、ぼかしの道行を着ていました。これです。今、なぜこれをお見せするかと言うのは、この道行コートと全く同じ配色のぼかしの訪問着を着た呉服問屋の女将さんがテレビに出ていたからです。実はこの道行、女優の浅丘ルリ子さんが着ていた着物の配色に惚れ込んだ家内の注文でつくったものなんです。金茶から錆びた紫にそして鉄グリーンにグラデーションした配色は道行として最高の取り合わせに感じたと言います。テレビに出ていた着物はこの呉服問屋から浅丘さんに貸与されていた物かも。このぼかしはもちろん「例」のぼかし屋さんの作品。先日のお約束の「壷垂れぼかし」の道行コート、新色の写真が撮れましたのでお見せ致します。これです。薄地ですが、高級感溢れる配色に染め上がりました。生地は伊と幸の駒無地。余談ですが得意先の社長は伊と幸の社員に「伊と幸のマークを外したら半分で買えるやないか、外してしまえ!」と言います。でも伊と幸さんは外しません。本当か嘘か、冗談として聞き流して下さい。
2008年01月19日
コメント(4)
-

ぼかしの名人
我が工房が地色を染めてもらう工房は「ぼかし」の名人でもあります。でも知る人ぞ知るだけで有名ではありません。名人と言っても「名」を上げる事には無頓着。「伝統工芸士」って何?職人さんや作家名を大々的に宣伝した着物はそのルートによって宣伝され、それなりには良い物ではあるのですが消費者の購買意欲を刺激するだけで中身に疑問があります。私の得意先の製造卸問屋さんでは作家名や工房の名前が分かる事を極端に嫌います。白生地でも生地の出に付ける機屋(はたや)さん名を付けない様に生地屋さんに依頼します。それは名前の一人歩きで価格が勝手に決まったり勝手に付加価値が付いたり消えたりする事を嫌うからです。着物はは一点一点がそれぞれ生きています。名前の相場変動で勝手に上げ下げされてはその着物に対して失礼だと。我が「ぼかしの名人」は頑固で体は小さいくせにでかい態度の得意先を平気でしかりとばします。私も何回かやり合いました。こちらも筋を通してやりますから、お互いに引けをとらなくてドローとなります。そんな名人のぼかしだけで表現した道行コート、明日新色が上がります。ぼかしとしては可成り「重い」。 これは旧作。可成り高価なので追加が沢山あるというものではありませんが、新色を作り続けている人気シリーズです。「壷垂れ」文様、ぼかし絵羽道行コート。明日上がる新色も即納なので写真に撮れるかどうか分かりませんが、撮れたら何時かお見せします。
2008年01月17日
コメント(4)
-
室町の情勢は変わらず
昨夜、得意先の染着物の製造卸問屋の新年会に参加してきました。社長曰く「室町の問屋はもう必要無いね」と。着物の流通工程は次の通りです。ただ染屋は製造卸問屋さんから生地を預かって染め加工をしています。職人→悉皆屋(染屋)→製造卸問屋→前売問屋(室町)→(地方問屋)→小売屋→消費者前売問屋でも自前で染屋に注文している所も結構あるのですが、今はかなり少なくなっています。前売問屋は製造卸問屋から商品を買ったり借りたりして商っているのですが、借りることが大半になってきています。小売屋さんへの口利きだけ。小売屋さんも消費者への口利きだけ。借りて商売しているのですから。借りる以上価格は付け放題、ほっておいても高くなる道理です。つまりこんなものが商売と言えるのでしょうか?こんな人達はもういらんと云うのがその社長の言なんです。正しいでしょう。製造者から消費者になるたけ距離を縮めるべきだという訳は。その点我が工房は職人→消費者となってしまいます。昨夜の新年会には社員さんと染屋さん、白生地屋さんが参加していたのですが、暗い話ばっかり。数年前までは、一人位「おかげさまで」と言う人が居たものですが全く無し。不安ばかり。こちらも不安だらけですが、昼間に聞いた話がもっと悲惨でした。昔修行に勤めていた同僚の女の子は山口の呉服屋の一人娘。その呉服屋が昨年夜逃げしたと聞いてしまったのです。ショック!息子が跡を継ぐと言って、山科の工房に見学に来た事もあったお友達なんです。年賀状も来なかったけど、出した年賀状も帰って来なかったのに。小紋の低価格化は可成り進んでいる様で、市場の九割が安物だそうです。我が工房ではせっかく安く出来るんだから手間暇かけた高級品を作ろうとしているのですが。一月近く彩色にかかるものまで作っています。京都の老舗「ゑり善」さんでも小売価格十万円以上の小紋は置かないと言って居られるとか。十万円の小売価格だとすると工賃は一万円代前半が限度。とても手描きのものは無理。得意先の社長は「ゑり善」さんがそんな事したら「ゑり善」さんは客が付いて来ないから潰れると断言。さて今年の行く末は、如何に。
2008年01月12日
コメント(4)
-
物作りのよろこび
私の工房はきものの染工房です。極一般的な彩色友禅はもちろんローケツ、素描、木版摺など手描きと言われる加工方法は殆ど可能な程、手がける種類は多いのです。別に自慢でもなく、昔は結構色んな種類の技術を持った職人さんがいました。今は少なくなっただけ。そんな染工房ですが、店頭には色んな和小物を展示販売しています。今日も福岡から来られたお客様が「京都らしいものを探していたのです」と仰って入って来られそれなりにお買い物をして頂きました。店頭には、手描き友禅のタペストリー、姫几帳タペストリー、和手ぬぐい、絞りの風呂敷、絞りや型染めのハンカチ、ランチョンマット、ティーマット、爆弾絞りのスカーフ、東海道五十三次の文庫カバー、大小の巾着袋、コースター、信玄袋、半襟が置いてあります。全て自家製。もちろん縫製や仕立は外注に頼っています。先日もアイスランドからの観光客が来られました。外国人は金を使いません。これ京都の観光業界の常識。それなりに外国人としては珍しく買物をされたのですが、次の日もやって来られました。なぜなら、あっちこっちで日本の土産を買おうとしたのだけれど殆どメイドインチャイナだったと言います。日本らしいもので日本製が少ないと言うのです。土産用の低価格品は京都でもチャイナ製が多いんですね。我が工房の競争相手は中国だったのです。それが分かっているから我が工房で売っている和小物は見事な低価格に。実際、お金を付けて売っている様な物も結構あります。しかし、何故そんな事をしているかと言えば、作る事が楽しいからと言えるでしょう。世間に格安の和小物があって価格では遜色なくても中身は凄いとお客様に言ってもらえるのが嬉しいからです。小さな店頭に置ける量は知れていますから、これ以上の品数は無理だと思えますが。先日も和手ぬぐいの別注で五十枚もの注文を頂きました。お客さまの描かれたイラストをモチーフに。喜んで下さったし、楽しかった。創作の喜びと、お客様の喜びがある以上、着物の染めの合間を作って作り続けます。
2008年01月09日
コメント(4)
-

室町問屋の系譜
タイトルが学術的な文句で、大層な事を書いてあると思われる方には期待はずれで申し訳ありません。昨年の年末当たりから、室町業界の通の方はご存知だと思いますが。呉服の問屋としては東証一部上場の大手商社である「市田」さんが「ツカモト」さんに吸収、子会社化されるという大きな事件が起きています。市田さんは名門、扱商品には森口華弘さん、田島比呂子さん、福田喜重さんなど仙台から沖縄までの人間国宝がずらっと。そのブランドには「夢工房」「こむさでもーど」から「花井幸子」「池田重子」の名前を冠するものまで、着物好きな人は良くご存知です。市田さんが一部上場の大会社でありながら、その実態が極めて前時代な商慣習を行なってきた事は室町に籍を置く人なら殆どの方がご存知。支払いの悪さは徹底していました。山科に住んでいた時、同じ町内に居られた方がこの市田さん専属の作家さんの弟。工賃をまともに払ってくれないと何時もこぼしていました。取引のある仕入れ先への支払いはもっと悪辣。経理は残高全部を支払っていると仰いますが、仕入れ担当が伝票を経理へ回さないから経理は知らん顔。大体支払いは、手形で残高の一割位との評判でした。公正取引委員会が何もしない事が分かります。私の工房が納めている製造問屋は数年前に取引を停止しています。創業は明治の初め東京日本橋ですが、四年後に京都店を開設、業績の大半を京都店が請負っています。京都の室町問屋の系譜は家康の時代から始まると言われています。明智光秀の「本能寺の乱」の際、数人の家来しか連れていなかった家康を逃がす手だてをした「茶屋四郎次郎」に特別の優遇許可を与えたのが始まりだとか。茶屋四郎次郎は幕府の呉服を一手に引き受け財をなしたのです。その後、幕末に消滅するまで代々続きました。同じ様に室町の呉服屋は武士出身も多く、呉服以外に両替商も兼ねている店舗も多く莫大な財を成しました。今でも烏丸通りと室町通りの間には両替町通りがあります。当時、御池通りの北側の通りである押小路通りと両替町通りの交差する界隈は両替商がひしめき合っていたとか。室町問屋と言っても室町通りだけでなく、烏丸通り、両替町通り、室町通り、釜座通り、新町通りに散らばっています。伊勢出身の三井家は宮家の出入りを許されるなど特権を持ち、呉服だけでなく同じ様に両替商にも進出、大坂や江戸にも店を開き江戸時代末期には日本一の豪商になっていました。京、大坂、江戸の豪商の中でも、京室町の豪商は利ざやの大きい「大名貸し」をやり荒稼ぎをしたのですが、踏み倒しで壊滅されてしまう店も多く出ました。江戸や大坂の商人は危険な「大名貸し」はしませんでしたが、それには江戸の「明暦の大火」に起因していると言われています。江戸城にまで及んだ大火は江戸の両替商も被害を受け大坂は規模が小さく、京都の室町の呉服商の経営する両替商しか貸す金がなかったからです。一時は京都の両替商すなわち呉服商達は飛ぶ鳥を落とす勢いで勢力を伸ばしました。その大儲けを狙う博打の様な商売のやり方は最近までの室町や西陣に受け継がれていた様に思います。特に西陣では「一夜でビルが、一夜で夜逃げ」と言われてきました。つまり当たれば大儲け、はずれば倒産という博打商い。今は規模の縮小で、返ってそんな当たり外れの大きな商売は無くなりました。これから室町や西陣はどのように変身を遂げるのでしょうか。こんな夜明けを見る事が出来るのでしょうか。
2008年01月06日
コメント(6)
-

着物の染、基本編 草稿
明けまして、お目出度う御座居ます。今年もよろしくお願い致します。染工房 遊を起ち上げて二年近くなります。小さな工房に移ったので、多くの使っていた着物の草稿を処分せねばなりませんでした。もったいない事でした。振袖なら一柄で五、六万円しますから。一番重くて嵩のある振袖の草稿は半分位処分しました。二度と描けないものだけを残して処分したのですが、出来るものはスキャンしてパソコンで描き直しして保存する事に。幸い長尺の草稿をプリントする事も出来たので、草稿のデータベース化を進める事にしました。今では新しい柄の大半はパソコンで描き、データベース化も少しずつ進展してきました。パソコンで図案を保存しておけば配置や大きさは自在に工夫出来るのです。そこで最近仕上げにかかっている草稿を一枚。几帳の柄。振袖に使われています。振袖一柄にはこの様な几帳を十以上使います。
2008年01月01日
コメント(6)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-
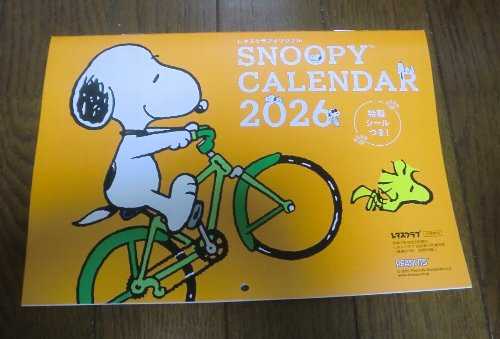
- 雑誌・本の豪華付録
- レタスクラブ SNOOPYカレンダー2026
- (2025-11-26 03:48:49)
-
-
-

- アメカジ全般
- 名盤 ECWCS パーカーをナイロン素材…
- (2025-01-29 23:55:24)
-
-
-

- レディースファッション新着情報
- 【SALE中!! 冬の細見えワンピ】選べ…
- (2025-11-22 16:46:18)
-