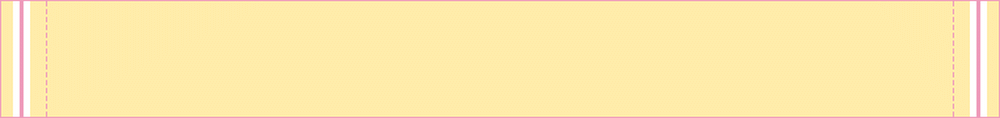2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年10月の記事
全38件 (38件中 1-38件目)
1
-
演奏会に行って・・・♪(^^)/☆
昨夜は(10月31日)演奏会に行ってきました。場所はサントリーホール(大ホール)でした。以前にも何度も足を運んでいる、私の好きなピアニストのうちの一人です。るんるん♪ るんるん♪(^^) 曲目はオール・ベートーヴェンでした。席は背中側でしたので、”ちょっと微妙~”と思いましたが、私がみたかった角度で弾く手なども見えて、また得たことがたくさんありました。るんるん♪♪ 本当は先月にもう一つ演奏会に行く予定だったのですが、仕事の都合で行けなくなり知り合いの方にお譲りしました。また日本に来るでしょう・・と思って、その人の演奏会は見送りました。テレビでも放送しそうな予感もするし・・・。 でも、今日のピアニストの演奏会は予定通りに行くことができました。やっぱり行くといいな~☆ちがうな~♪♪と思います。昨年度は全然演奏会に行けなかったので、その分今年は行きたい放題行っています。でも、本当はもっと2倍くらい行きたいところなのですが・・・(^^; 演奏会に行くというのには、とても意味があります。たしかにCDもたくさん売られています。それらを聴くのも大変良いことです。でも、演奏会にはそこでの空気や会場の雰囲気、演奏者の細かい様子なども見ることもできるっという良さがあります。もちろん、生の音の演奏を聴いて吸収できる部分もたくさんあり、それのために(=それを求めて)演奏会に行くのですが・・。 私の個人的には今年はもう演奏会に行く予定はありません。っというか、この先に行く演奏会はまだ一つも決まっていません。でも、今日得たことを自分のなかに入れたまま、明日からの自分の練習や生徒さんたちのために生かしたいと思います。 とにかく、演奏会に行ってよかった~☆☆☆(^^) Merci!!
2005.10.31
コメント(0)
-
ピアノをつかって表現すること。のおはなし。
「あなたの演奏はあなたしか演奏できない。だからみなさん一人ひとりが演奏をする意味がある」ーーーと以前のブログに書いたと思います。 音楽で何を表現するか。ピアノで何を表現するか。---これについては、人それぞれの色々なこたえがあると思います。”自分がここにいる!!”ってことを表現したいとか、”自分は今こんなふうに思っているんだよ~”ということを聴衆に伝えたいという方もいらっしゃると思います。 どのこたえもみんないいこたえだと思います。 私が以前書いた”みんなたいせつな演奏”という回に書き残したことがあったので、それをここに書こうと思います。 私たちはピアノで何を表現するか。何のために演奏するか。ーーーそれは、上記の「みなさんのどの演奏も、その人にしかできない演奏。だからみんなどれも大切だし、全員の人が演奏する意味がある」ということのほかに、「言葉で表現できないことを表現する」ということも挙げられると思います。 赤ちゃんや子どものときは、感情のままに行動します。うれしければニコニコとし、嫌なことや不満など上手くいかないことがあれば声をあげて泣いたりします。 自分のおもったことを素直にその場で表す。これは年齢とともに狭められていってしまいます。嬉しいや楽しいという感情は表に出しても大抵は大丈夫ですが、怒りや不満、悲しみなど・・・といったマイナスといわれる感情は大人になると、それを素直にその場でおもてに表してはいけなくなります。それをもし全員の大人が日常で表に100%出してしまっていたら、収拾がつかなくなり、仕事にもならなくなってしまいます。暮らしていけなくなります。また、怒りとか悲しみっというふうに、はっきりと分類できない”言葉にできない(orならない。)感情”というものもたくさんあると思います。 でも音楽や美術、スポーツなかではそれらを表現して良いのです。そこにぶつけても良いのです。岡本太郎さんのように(^^;☆☆ 音楽や美術の中でなら、喜ぼうが怒ろうが悲しもうが泣こうが、誰も文句を言う人はいません。人間の色々な感情、自分がこれまでに体験した&経験したいろいろな”感情”を、芸術やスポーツのなかで表現できる。 これが醍醐味といえるのではないでしょうか。 そう考えると子ども時代に「感覚的」なことを身につけるのはとても大切です。俳優さんとも似ていると思います。あまりにもなんにも経験していないと、いくら台本を読んでも、どういう意味なのかイメージがわかず、表現することがとても難しくなってしまいます。 楽しいとか嬉しいとかどきどきするっという経験はもちろんですが、辛いとか痛いとか悲しいとか・・そういう感情はとても必要です。人間だれしも、たおれちゃうほどの辛さや苦しみは、なるべく避けたいところですが、少しの辛い経験とか悲しみといった経験はしないよりはしてあったほうが良いです。 長く生きていくと、さまざまな事に直面し、いろいろな感情を経験します。それらが、音楽を美術などをする上ではとても活きてくるのです。なので、同じ曲を演奏したとしても、子どもとはまたちがったよさがそこには表れるのです。だから、大人になって音楽や美術を習うことはとっても良いのです。 子どもには子どもの良さがあり、大人には大人の良さがあります。だれにとっても、ご自分が表現したいと思ういろいろな感情をぜひ曲や絵などの中に存分に出していただきたいものです。ピカソは長生きした画家ですが、”おじいさん”と言われる年齢になっても、目は輝き、生き生きとしていました。音楽家も年がいっていても生き生きと若々しい方がたくさんいらっしゃいます。小澤征爾さんも、今年70歳ですが、全然そんなお年には見えないと私は思います。年齢を感じさせない。いくつになっても”バリバリの現役!!!!!”っというかんじで、エネルギッシュに活動していらっしゃいます。とても素敵ですね。 来年4月からのNHK朝のドラマは、主人公がピアニストになる!!という役だそうで、「ピアノ」がもろに登場しそうです。今ヒロイン役の方は、ピアノを猛練習なさっているそうです。朝ドラマを通して、みなさんに今までとはまた一味もふた味もちがった”あたらしい”ピアノの良さや素晴らしさなどなどが伝わるといいな~と私は思っています。 かく言う私も、ドラマを見たわけでないので、どんな内容なのかお話の細かな部分は知らないのですが・・・。(^^;) 珍しく朝ドラでピアノが題材なので、みなさんどうぞご覧になってみてくださいね。 P.S. なぜか私は番組の宣伝をしてしまったような記事になってしまいました。朝ドラは来年の4月。まだまだ先ですが、みなさんお忘れにならないように、時期が近づいたらチェックしてみてくださいね。
2005.10.30
コメント(0)
-
+α のおすすめ練習法☆のおはなし。
私が近頃実践しているピアノの練習方法があり、みなさまにも是非オススメなので、今回はその内容について書きたいと思います。 私がおすすめなやり方は、「鏡を使う」というものです。鏡の大きさは自分の上半身または全身が映るくらいの、ある程度大きなものです。 なぜ鏡を使用するのかというと、歌を勉強している方は鏡を見ながら練習すると、いい顔で歌えるようになり上手にもなるという話を聞いたことがあるからです。たしかに一流のプロの方たちも、みなそれなりの”いい顔”で歌っていらっしゃるように思います。 ピアノにおいても同じことだと思います。 一流のピアニストも、見かけもとても美しい姿で演奏しています。余計な無駄な動きは一切なく、必要最小限の動きだけで演奏しています。なれば、”私も鏡でチェック!!”っとばかりに、私も鏡を使用するようになりました。 鏡を使うと、たとえばレッスンで自分が”そんなふうには手を動かさなくていい”といわれたとき、自分ではそういうふうにしているつもりはないっという場合があります。でも、それを鏡で見てみると、”あぁ、ほんとだぁ~~そうなってた・・・”と気がつけるのです。客観的に見る目を鏡の中にももつというのは、とても練習において重要な気がします。 俳優さんなど舞台上で演技することを仕事にしている人たちも、舞台上で演技しているときに、同時にもう一人の自分でもって”演技する自分を客観的にみる”っということが必要だそうです。演技し役に入りきっている自分だけでは、成り立たないのです。 これもまたピアノと同じです。 何を弾いているときでも、何を練習しているときでも、自分の中に”自分を客観的にいつも見ている目”というものが必要です。そのために、自分のやっていることをより正確に理解するために、この「鏡使用大作戦☆」もとても有効だと思います。 これによって、弾いているときの手の形だけでなく、姿勢や手首や腕や首などなどの使い方にも目をむけ、より良い演奏の助けになると良いと思います。 みなさんも是非、実践なさってみてください。♪♪(^^) ぺこり。
2005.10.30
コメント(1)
-
いまの子どもたちに思うこと。
いまの日本は実に物が豊富で、便利になりました。¥100ショップの出現もそうですし、昔は沸かすのに苦労していたお風呂も今はスイッチ一つで入れます。 これらの便利さは、とてもありがたいことですが、こどもたちにとってはあまり良くないのかな~と思うこともあります。 私たちの今の便利さは、すでに今までの不便さをしっている方々にはとても良いと思います。でも、同じことをするにもそれまでどんなふうにして苦労して行ってきたかを知らない今の子どもたちにとっては、今のこの便利さが「普通」になってしまっています。 お風呂を薪でたこう!とは言いませんが、たとえばせめてお湯だけがでる蛇口と水だけがでる蛇口とで、お風呂のお湯の温度を調節できる。とか、電子レンジにしても「おまかせボタン」をポンと押すのではなく、温める物とその量をみて、これはどのくらいの時間レンジにかければ良いかを自分自身で考えるなどなど。 自分の頭を使って覚える、身につけるという習慣がもっとあると良いのではないかと思います。便利な機能は、これらのことがある程度自分できるようになってわかってからのほうが、そのありがたみもわかり、きちんと「便利な機能」として、子どもたちにも浸透していくのではないかと思います。 また同時に、今の子どもたちには”自分の体を使う”ということが不足しているように思います。たしかに学校のお勉強もとても大切ですが、自分の体で色々なことを体験して、自分で感じるっという経験の方がよほど大切なのではないかと思います。 よく見かけるのは、ぼそぼそとしゃべる子どもです。はっきりとしゃべれないのです。ぼそぼそ言っているから、聞き取れないし、もっと大きな声で話すよう促しても、一向に声が大きくならないのです。自分の体の使い方がわからないのかもしれません。 みなさん、ちょっと実験してみてください。なんでもいいので、何かをぼそぼそと、なるべく相手が聞き取れないようにしてしゃべってみてください。そして次に同じことを、今度ははっきりと話してみてください。すると、どうでしたか? はっきりしゃべってみると、脳に何か刺激がいきませんか?なにか”ピーン”と張っているというか指令がいっているような感じがしませんか?それに対して、ぼそぼそしゃべると何も脳には感じないと思いませんか? この違いがわかることが大切なのです。 はっきりしゃべらないと、頭に入りませんし、脳も動きません。いつもぼそぼそしゃべっている子は、今からでも遅くないので、ぜひ直していただきたいと思います。家だけでなく、外でも学校でも、よい話し方でしゃべるようにしていただきたいものです。 それから、子どもたちを見ていると、物をきちんとみられないという子が多いような気がします。自分も子どものころは同じような感じだったのかなぁ~???とも思いますが、とにかくテストを解くにも、きちんと問題文を読んでいないのです。雰囲気で解いています。私たちがいくら”終わったら必ず見直しをするのだよ”と言っても、本人たちの頭がそうなってしまっていますから、見直しはするものの結局は雰囲気で解いたままで提出することになってしまっています。 子どもも子どもなりに、自分で色々なことを考えていますので、頭が自分の世界でポ~っとなっているような感じで動いてしまうのも仕方ないのかもしれませんが、少しでも早くこのことに気がつけると、とても良いのではないかと思っています。成長とともに解決していくことかもしれませんが、なるべく早くこのことに気がつけることでなにかを聞きのがすことも少なくなるでしょうし、きちんと指示にしたがって動くことができ、一番本人のためになるのではないかと思っています。子どもたち、がんばれ~!!(^^)♪
2005.10.29
コメント(0)
-
「先生」についてのおはなし。
日本ではどんな世界でも「先生」というと、弟子や周りの人たちは逆らえず、あまり言いたいことも言えず、納得いこうがいくまいが、とにかく従う・・・・・。というところがあるように思います。でも、これって考えてみたら、ちょっと変だと思いませんか? 外国では、相手が目上の人であっても、違うと思えば”ちがうと思う”と言いますし、また言われた相手もそれを嫌とは思いません。相手の年齢などとは関係なく、良いことは良いし、違うことはちがうと言うという習慣があるようです。 親であれ兄弟であれ友人であれ上司や部下であれ、どんな関係においても”こういうことは人間として言ってはいけない”ということさえ守れば、あとは自由にお話し合って良いと思います。また、日本では”「先生」の言うことは、嫌でも従わなければならない!”っというようなおかしな風潮がありますので、”先生”という立場になった方も、そのへんを考えて行動してみると良いような気がします。 私が今も大変お世話になっている大学のときからの師匠は、そのへんのことをとてもよく理解なさっていますので、とても接しやすいですし、良い意味で生徒一同、先生には言いたいことを言っています。とてもこのやり取りが楽しいですし、レッスンに行っても本当に色々なお話が先生とできて、とても幸せな時間を毎回過ごしております。とにかく大笑いしながらレッスンをしていただいています。 世の”先生”といわれる方のなかには、生徒さんに(=弟子)対してご自分(=先生)の失敗談などをお話しすることは、生徒さんからの尊敬が失われるとお思いの方もあるようですが、そのへんも私はちょっとちがうと思います。 私の師匠もこのお話には「・・???」とお思いですし、私もまた同じです。私の師匠は、ご自身の色々な失敗談をお話になります。内容はピアノに関してだけでなく、音楽とはまったく関係のないことも話してくださいます。でも、だからといって私たちは師匠に対して、尊敬がさがるなどとは誰一人思っていません。それどころか、先生の人間らしさをより多く感じ、より一層色々なお話ができるのです。 「先生」とは、スーパーマンではありません。”先生”だって、人間なのです。最低限度の節度さえ守れば、お話になりたいことはぜひぜひお話になると良いと思います。ご自身のお困りごとも、あまり隠さずにおっしゃってみたほうが早い解決になると思います。 でもとにかく、色々なタイプの”先生”がいますから、よりご自分に合った先生が見つかると良いですね。私自身は、素直にお話になれる先生がのぞましいのではないかなぁ~(^^)と思っているところです。♪♪
2005.10.29
コメント(0)
-
楽譜をよみ始めるときのポイント
楽譜をみて最初に弾いていく、”はじめまして”の演奏を、「初見」と言います。事前の練習一切なしで、初めて見て、読んで弾いていく。これが「初見をする」ということです。 楽譜を読むとき、どんどん読んで弾くことができる人と、逆にそれが遅い人ーーーつまり、苦手っという方がいらっしゃいます。 色々な方がいらっしゃると思いますが、まず「初見」が強い人はとても有利というか得です。なぜなら曲であれ何であれ、楽譜を”はやく”読んで演奏できることが演奏への第一歩だからです。ただし、間違いだらけで読んでいるのではいけません。人間ですから、誰にでもまちがいはあるものですが、あっても1つまでっというくらいに心がけたいものです。楽譜を読むのに苦手意識がある方は、苦手っということのおかげで、ゆっくりであってもかえって丁寧に読むことができて良いかもしれません。とはいっても、やはり誰でも少しでもはやくきちんと読んで、練習につなげたいものですね。 やはり楽譜を読むときにはポイントがあります。それは、常に”先へさきへ”と楽譜を読んでいくということです。今弾いているところを今みているのでは、次に音がたくさんあるときやリズムが少し難しいときなどに、すぐに対応ができません。いつでも弾いているときの次の小節を読むくらいを心がけると良いと思います。音の並び方もあるので、ここでどのくらい先かを読むべきかを定義することはできませんが、文章を読むときと同じだと思います。 私たちも日本語の文章を読むとき、先へ先へと読んでいると思いませんか?楽譜のときほどには先をは読めないかもしれませんが、たとえばページが次に移るときにはやめにページをめくりませんか?これと同じだと思います。 楽譜が次に移るときはもちろん、ページ内でも”次、次・・!!”という具合に、後ろ後ろをよむと良いと思います。 ものによっては、あまりにも細かいなどの理由で先先へとは読めないものもあるかとは思いますが、これをいつも心がけると良いと思います。 それからもうひとつ。楽譜を読むときに大切なことは、「目でキャッチする」ということです。要はいつでも大事なのは、”頭の中”なのです。いつでも頭も目も連動させて、目でどんどんキャッチしていく!!ということをなさるととてもよいと思います。 ぜひ実践なさってみてください。 あともう一つの注意点は、「足で拍子をとらない」ことです。足で拍子をとる方もたくさんいらっしゃると思いますが、それはあまり良い方法とはいえません。足でとると、体全体が必要以上に動いてしまいますし、頭の中できちんと数えていれさえすれば、なにも足までも使ってからだのあちこちで拍子をとる必要はどこにもないのです。足を動かすくらいなら、声に出してなさっていただきたいと思います。もちろん練習のときだけですが。。 曲を読み取るとき、カデンツになっている部分があります。カデンツとは、ものすごく簡単にくずして言うならは、おじぎのときの和音というのでしょうか。チャーン、チャーン、チャーンという”ドーシードー”というような流れです。 *全然伝わっていないかもしれません。文面では限界がありますので、お許しください。(^^; このお辞儀のときの和音の流れは、文章やお話の一区切りにあたります。曲の途中でもこの流れが出てきたときに、何事もないかのように弾いてはいけないのです。”ここでいったんまとまりが終わっているな~”っというような具合に、そこで一区切りであるように思って弾いていただきたいと思います。 いつもですが、説明がわかりにくいところが多々あったと思います。いつでもご質問等々はたくさんお待ちしておりますので、どなたも気軽にお書きくださいませ。♪♪
2005.10.28
コメント(0)
-
ピアノを通して学べること。のおはなし。
習い事ーーー私の場合、「ピアノ」ですが、ピアノをやっていると、実にいろいろなたくさんのことを学ぶことができます。音楽のことのほかにっという意味です。私は何も習い事をなさっていない方を見ると、ちょっとぞっとすることもあるくらいです。 ですが、もちろんただ”習えば良い”のではなく、どんなふうに習ってきたかにもよりますが、とにかくピアノを通じて”人生”をも学べているのでは・・・と思うことがあります。 でもまだまだ未熟者ですが・・・・・・・・。 今回は私がこれまで学んだことの中の一つを、お話したいと思います。 私がピアノを通して学んだことのひとつ。それは、「物事は見かけ通りではない」ということです。”見かけは簡単そうでも、実際はみるのとやるのでは大違い!!!!!!”っということが、世の中には実にたくさんあります。たとえばこの例としては、「曲選び」が挙げられると思います。 みなさんの中には、自分がやりたい曲を選ぶときにプロの演奏家、とくに一流のプロの演奏家の演奏をCD等々で聴いて、それで”あぁ、この曲をやりたい!!”と思い、決めようとしてしまう方がいらっしゃいます。もちろん、それがわるいと言っているのではありません。自分のそのときのレベルや色々な状況に合っていればもちろんそれで良いのです。しかし、そういうものは一切無視して、”やりたい!”という気持ちだけで、お選びになる方がいらっしゃいます。 以前もわがブログの中で、曲選びについてを書かせていただいた回がありましたが、何度も申し上げるようですが、本当に曲選びは自分の気持ちひとつで選ぶことはとても危険です。 「やりたいもの」と「やれるもの」は必ずしも一致しませんし、そのためにきちんと少しずつ勉強していくのだと思います。これで良いのです!!(^^)♪♪♪♪♪ 私たちが演奏するとき、難しいものをいかにも”ムズカシそう”に演奏してはいけません。目指すは、どんな簡単なものでも難しいものでも、どちらも易々と演奏している!!という形です。まぁ、口で言うのは簡単なのですが・・・・(^^; 私はフィギュアスケートを観ることが好き(TVでですが・・・)なのですが、滑る選手を見ていると、”クルクルクルッ”とか”シュッッ”とか、”スイ~~ッ”等々。とても”簡単そう”に滑っていらっしゃいます。私も”クルクルクルッ”とか、今やってもできちゃうのではないか!??っという錯覚というのか幻想というのか・・・(^^;)そういうものに陥ることがあります。 しかし、実際今すぐに私がここで”クルクルクルッ”なんて出来るはずがありません。そんなことは現実に戻れば、いやいや戻らなくてもわかることです。でも、観ている私たちにそう思わせる。これが大切なのです!!!!!! 実際にやるのはとても難しいことだったとしても、易々となんでもないようにやれる。これが本当に上手な人なのです。難しいものを難しそうに弾くのは、だれにでもできます。それでは芸がありません。難易度の高いものでも、易しいものをやるのと同じように&なんら変わらないように披露できるのが、最も良いのです。 実際、何の世界でも一流の人はぜったいにどんなことも易々とやっているように見えるでしょう。 あぁ~勉強、勉強っですね♪♪(^^;)やることはたくさんある!!!!! それから、もうひとつ。 たとえば、ピアノを習うとき。基礎はどっかにとばしてしまって、やりたいものだけをピックアップしてやっているという方が少なからずいらっしゃると思います。それに対し、きちんと順を追って最初からをなさっているという方もいらっしゃると思います。どちらにもそれぞれ望むものが違うのかもしれませんので、一方を激的に非難することはできませんが、ちょっと私の個人的な意見を書かせてもらいます。 先日、私の上司が通うある先生の門下生の書道展へ行かせていただきました。(日本語&説明がおかしくてすみません。。) 私は書道にはまったくの素人ですが、そこに飾られたひとつの門下の生徒さんの数々の作品を拝見し、とても音楽とつながりがあるように感じました。また、作品のひとつ一つにはそれをお作りになった生徒さんのコメント等が書かれていて、とても興味深く拝見いたしました。 小学生の作品もいくつもありましたが、大人の方の作品がとても多く、シニアと言われる年代の方の作品も大変多くありました。どの方もみなさん大変苦労され、本当に心のこもった&丁寧に作られた作品であることが、コメントを読まなくてもわかるほどどれも素晴らしい作品でした。コメントの内容は、制作期間の長さについてはもちろん、この展覧会にはもしかしたら出品できない、つまり仕上げることができないのではないかと一時は諦めかけたけれど、色々な方に支えられて&力を振り絞って仕上げられたという方や、ご家族の不幸があったりして、とてもめげそうになったけれど、頑張ったという方や、”こういうことを表現しようとして努力したけれど、なかなか難しくうまくいかなかった”等々。 生徒さん一人一人のそれぞれのドラマがあり、どの方もとても苦労されて仕上げられたのだな~ということが、とても良くわかりました。中でも”満足のいく作品ができあがるまで、何度も何度も何十回もやりなおした”というコメントが書かれているものも大変多く、ピアノと同じだな~と強く思いました。みなさん、書道も決して一筋縄ではいかないけれど、そのことも心の底で楽しみながら一生懸命に取り組んでいらっしゃるのだな~ということが、とてもよくわかりました。また、作品を書くときの集中力や気持ち(=精神)との関係等々においても、まったくピアノと同じなのだな~と思いました。 後日、上司にうかがったところ、みなさんきちんと基礎から学び、一人も”やりたいものだけピックアップ!”という方法でなさっている方はいないとのことでした。そのことは作品を通してもよくわかりましたし、同門の生徒さんの作品でもみな一つひとつちがっていて、しっかりと個性のある作品になっていらっしゃいました。 私の上司によれば、”やりたいものだけをピックアップ!!”というやり方で習ってしまうと、出来上がる作品はいつまでたっても薄っぺらなものとなり、門下生の作品にはあまり違いがなく、どれも同じように見えるのだそうです。 私は書道にはまったくの素人ですが、なんだかとてもよくわかる気がしました。ピアノにおいても同じことだと思います。 家を建てるときと同じで、やはり土台がしっかりとしていなければきちんとした良いお家はできません。基礎をきちんとするっということはもちろんですが、やはり手順もきちんと、0から1へと順に進むべきだと私は思います。家だって、順番を通りでなければ作れないでしょう。それと同じことだと思います。 ベートーヴェンの弟子でもあったツェルニーは次のように言っています。 『やさしい曲からだんだんに難しい曲へと進むことがとても大切です。なぜなら、どの作曲家も、どの演奏家も、仕事をする時、彼らは自分たちより前の人が築いたものを土台にして、その上に新しい創造を加えて芸術なり、科学なりを打ち立てて行きます。したがって、ピアニストたちがひいている曲は、そのような自然の過程により、あらゆる面においてひと昔前の曲よりずっと難しくなっているといえましょう。また、必要な準備段階の練習をはぶいて学習をいそぎ過ぎる生徒は、いつも曲をいい加減に弾くことをおぼえ、時間を無駄にし、ついには難しい曲ばかりか易しい曲さえも満足に弾けなくなってしまいます。』 私もまったくその通りだと思います。 どんなときにもより自分に合った”ただしい”選択をするには、「自分を知る」ということが大切だと私は思います。自分はどんなことが得意で、どんなことは不得意なのか。自分はどんなことが好きで、どんなことは嫌いなのか。どんなことは向いているのか。どこまでやれるのか、そのキャパシティはどのくらいなのか等々。 このことが自分でわからないと、とても大変なことになると私は思っています。 だれにでも得意なことと不得意なことはあるものです。また、すべてを得意になる必要もないと思います。それぞれの”畑”があるように、人にはそれぞれの人にしかできないことというのが必ずあると思っています。また、仕事以外の趣味を持つことも大変素晴らしいことですし、自分の世界を広げることができ、より素晴らしい人生になると思います。年齢は関係なく、趣味があるというのはとても良いことです。ちょっと話は外れているかもしれませんが、老人ホームなどに入る方でも、趣味を持っているのともっていないのとでは、周囲の方たちとの関わり方とか、寄って来かた等もずいぶんと違うと聞きました。これは結局は、ご本人に返ってきているのだと思います。 色々な経験を通して自分を知り、仕事でも趣味でもそれ以外のことでも、思い切り&自分らしく過ごせるととても良いですね。私もいつまでも自分らしさを失わないように努力したいと思っています。♪♪♪ P.S. 話まとまらず、すみません。読んでくださった皆様、いつもどうもありがとうございます。今後ともどうぞお付き合いくださいませ。m(__)m
2005.10.27
コメント(0)
-
”ちょっとしたことなのだけど” ~弾くときの準備のおはなし~
ちょっとしたことなのに、それによってその出来が大きく左右されることがあります。ちょっとしたことだけど、これは大切だな~と思うことを今回は書かせていただきたいと思います。 レッスンや発表会や演奏会、また家で練習するときなどで、ちょっとしたことなのにとても大きな影響を与えることがあります。たとえば、衣装(服装)やアクセサリーの有無や、お手洗いに行きたいかなどなど。日常ではそれほど大したことではないと思われる事でも、演奏するときにはこれらがとても大きな影響を及ぼすものです。 たとえば、あなたがレッスンの順番を待っている時、急にお手洗いに行きたくなったとします。このとき、みなさんはどうしますか?もちろん一番良いのは、お手洗いに行くことですが、少し行きたいくらいならそのまま我慢しても大丈夫なのではないか?と思う方もいらっしゃると思います。 私の経験上、フシギなことに普段の日常の生活のなかではそれほど影響力のないことでも、演奏するときにはとてもとても大きな影響を与えます。 演奏には、そのときの心の状態などが120%表れます。驚くほど、”そのまんま”表れます。たとえば、何か時間を気にしているとか、実はお手洗いに行きたいとか、なんだかそわそわして落ち着かないとか、またはリラックスしているとか・・・・。 理由は何であれ、少しでも心に”そわそわ”があると、良い演奏=自分らしいいつもの演奏は、出来ません。 また女性の場合、演奏会に出演するときにイヤリングやネックレスをつけるかどうか、どんなものをつけるかを考えることになります。ちなみに、私自身はネックレスはしますがイヤリングは絶対にしません。普段、ピアスやネックレスをなさる方はまったく問題ないのだと思いますが、私は耳に何かをつけるとそれが気になってしまって落ち着かなくなってしまうので、ぜったいにつけません。マニキュアも同じです。 何もしらない方は、見かけだけを考えてあれもこれも付けたら?とおっしゃる方もあると思いますが、いつでも演奏するご本人が一番心置きなく、一点のくもりもない状態で演奏できる状態を作ることがとてもとてもとても大切です。 それから、服装やアクセサリーと同様に椅子の高さも大変大変重要です。以前にもこのブログにてお話しましたが、椅子の高さ一つで、その演奏が良くも悪くもなってしまいます。椅子の高さが違うということは、鍵盤に対しての腕の高さや角度が違ってしまうということです。そうすると、演奏においてのすべての動きまでも違ってしまいます。 あまり椅子の高さは気にしていないという方も意外にたくさんいらっしゃると思いますが、一度再確認なさってみると何かの解決になるかもしれません。 (*詳しくは過去のブログをご覧いただければと思います。) それから私が最近重要だと再認識しているのはやはり「姿勢」です。”どうもうまくいかないなぁ・・・?”というとき、自分の姿勢に目を向けてみると、背中が丸まっているとか左足が前に出てしまっているとか。お恥ずかしいことに、そういう基本的なことが油断し抜けてしまっているということがあります。 演奏するとき、おなかや腰がしっかりとしていないと絶対に良い演奏はできないとつくづく思います。おなかと腰は体の中心と言えると思います。どんなに姿勢を良くしようとしても、腰が曲がっているのでは一向に良い姿勢にはなりません。また、声を出すときによく”おなかから出す”といわれますが、大きな声を出すとき自然と息をたくさん吸いますし、おなかに”ンッ!!”という感じで力を込めると思いませんか?またそのときの姿勢も絶対に曲がってはいないと思いませんか? ピアノを弾くときにも同様で、とくにfやffなどを出すときにはそれと同じことをします。良い姿勢で、良い呼吸、良い椅子の高さ。これがそろえば、上達への道の入り口に立ったといえるのではないかと私は思っています。
2005.10.26
コメント(0)
-
☆”レッスンではいつもキンチョーしてしまって・・・”というみなさまへ。
わがブログでのみなさんからのたくさんのコメントや、他のかたのブログ内のみなさんのコメント等々をみていると、”自分は家では弾けているのに、レッスンに行くとキンチョーしてしまって、弾けなくなってしまうのデス・・・”という方を、大変多くみかけます。このことがみなさんの大きなお困りごとの一つでもあるようなので、今回はそれが少しでも楽になるようなことを書きたいと思います。 さて、レッスンで自分はいつもやたらとキンチョーしてしまって、家では弾けているものも弾けなくなてしまう・・・。そして、ミスがミスを呼び・・・というふうにボロボロになってしまうの・・・・。っというみなさま。 そうなってしまう原因の一つは、私が思うには、みなさんは自身の先生に対して、”うまく弾こう”とか”先生にいいところをみせよう”とか、なさろうとしていらっしゃいませんか? わが過去のブログの☆”みんなたいせつな演奏”のおはなし☆という回にも詳しく書かせていただきましたが、レッスンでも人前でも発表会でも、どんなときでもみなさんは”うまく弾こう”となさらないことが良い演奏をする第一歩です。 人間だれしも、人に悪いよりは良くみられたいものですが、普段以上のことはまずできません。”いつもより上手く弾いてやろう”とか”いつもと何かちがうことをしてやろう”などと思う方もいらっしゃると思いますが、それは逆効果というものです。 大切なのは、”ありのままで弾こう”ということです。家での練習だって、ありのままで弾いていらっしゃるでしょう。それをレッスンでも発表会などでもすれば良いのです。 こうなると、ますます普段のみなさんの家での練習が重要になってくることがわかると思います。 では、みなさんはいったいどんなふうに家での練習をなさっているでしょうか。つまり、どのくらいきちんと練習なさっていますか? たとえば、いつも通してばかりで弾いていて、まったく「部分練習」なんてしていない!という方。それは大変危険です。苦手な箇所やいつもきまってミスをする箇所などは、必ずそこだけを取り出して重点的に練習しなければなりません。”部分練習”を必ずすることです。 野球を例にしてお話したいと思います。みなさんがいっつもやっているであろう「通して弾く練習」とは、野球で言えばみんなで”練習試合”をするにあたります。一方みなさんがあまりなさらないであろう「部分練習」は、野球で言えばバッティング練習等々、野球で必要な技の練習といえると思います。(また「教本(ハノン等々)」の練習は、”準備体操”や”ジョギング”等々、基礎体力をつけるようなものといえると思います。) さて、こうして考えてみたとき、野球選手は”練習試合”と”ひとつ一つの技の練習”と、どちらを多く練習していると思いますか?ーーーそれは、言うまでもなく”技の練習”ですね。いくら練習試合をしたところで、一つ一つの大切な動き(バッティング等々)がきちんとできなければ、試合で勝つことにはつながっていきません。 ピアノにおいても同じです。 部分練習がきちんとできていなければ、いくら通しでも良い演奏にはなりません。たとえば、部屋をお掃除をするとき。ほこりを端によけて、部屋の真ん中だけを掃除してある部屋があったとします。みなさん、その部屋はきれいですか?たしかに、中央部分はきれいかもしれませんが、それは「きれいになった」とはいえません。お部屋の掃除も、真ん中部分はもちろん、部屋の端も隅っこも、全部がきれいに掃除されたお部屋が、だれにとっても居心地の良いお部屋となるのです。 ピアノにおいても、すべての部分、箇所がおなじようにきちんと弾けていなければなりません。 また、自信のなさは、ミスに大きくつながります。少しでも自信をつけるには、”きちんとした”練習をするほかにありません。 普段の練習で、なんとなく弾いていないかとか、だらだらと通してばっかりで弾いていないかとか、苦手なところはいつも放っていないかなどなど。 色々と見直してみると良いと思います。 それから、それができていてもすごくキンチョーしてしまうっという方は、家で練習するときに、録音をするとか、ぬいぐるみを自分の見えるところに(ピアノの上など)に置くとか、何か普段を違う環境をつくってみるのも良いと思います。 あとは、”どうしても・・・”という場合は、ご自身の先生にお話してみても良いと思いますよ。結局は、おそらくみなさんは先生の反応などを気になさってしまっているのではないかと思うので、お話になると、すっきりするということもあるかもしれません。 いずれにしても、演奏するときに絶対に必要なのは、弾いている最中はいつも頭の中でそのメロディを歌ってるということです。これがないと、絶対に絶対に絶対にいけません!!音楽の基本は「歌」です。頭の中ではきちんとその曲のメロディを歌っているということが、まず良い演奏をする条件の一つでもあります。きちんと頭の中で”歌って”いれば、暗譜も忘れずらくなります。 そして、同時に、”余計なこと”を考えないことです。なにか色々と頭の中で考えてしまう方、いませんか?そういうことも、しない方がずっと良い演奏ができますよ。♪♪♪ 私も音大を卒業し3年目である現在も、大学時代からお世話になっている先生のところへレッスンに通っています。私もそれなりには、レッスンで一発目を弾くときは、緊張はしますが、そのせいで家では弾けていたものもレッスンで弾けなくなるっということはありません。”まったく緊張しない”っというもの良くないので、程よい緊張は必要だと思います。緊張感というものでしょうか。 わがブログの過去の記事にも、緊張にそなえた内容のものもありますので、そちらをご覧いただくこともおすすめします。 ☆そして最後にもうひとつ。 みなさんは、自分と同じ先生の生徒さんの演奏を聴いたことがあるでしょうか。発表会でもそうですし、とくに普段のレッスンを聞くという機会はあるでしょうか。 世の中には実にいろいろなタイプの先生がいらっしゃいます。レッスン中、”どなたもどうぞお入りになってきてください”という方もいれば、”終わるまでぜったいに入ってこないでください!”という方もいます。 私は前者のタイプです。どうしてかというと、”自分が受ける”ばかりがレッスンではないからです。人のレッスンをみることもまた、とてもとてもよい勉強になります。 たとえばレッスンをみたとき、”あ~、自分と同じことを言われているな・・。私ひとりじゃないいんだな~(^^)”と思うこともあるでしょうし、”すごくよく練習していらっしゃるのだな~、宇私もがんばらななくちゃ”とか、”私にもあてはまることだな~直すようにしよう・・・”などなど。 色々なことを感じとることができます。 私が今年の夏にピアノの勉強でオーストリアへ行ったときも、今回は私はレッスンを受けるのではなく、「聴講(ちょうこう)」というのをしました。「聴講」とは、レッスンをしている様子をみて、学ぶということです。聴講しながら、生徒さんの演奏についてはもちろん、ピアノの先生となった私ですので、同時に先生の指導法などもみせていただきました。レッスンを受けるのとはまたちがった、たくさんの得ることがあったと思って、とても行ってよかったと思います。とにかくとても勉強になります。 みなさんには、ぜひとも”上手”を最初から目指すというよりは、「自分らしい」演奏をしていただきたいと思います。そして、結果的に”上手な演奏”になってもらいたいと思います。あなたの演奏は、あなたにしかできません。このことをどうか大切になさっていただきたいと思っています。
2005.10.25
コメント(0)
-
☆ピアノのただしい弾き方 ~脱”日本流”~☆のおはなし。
さて、今回はピアノを弾く上での正しい指というか手というか・・の動かし方についてご説明したいと思います。 ちょっと一つその前に。わがブログ内では事あるごとに申し上げていることですが、まずここ日本では、間違ったピアノの弾き方が横行しております。はっきり申し上げますと、日本の98%以上のお教室(個人、大手問わず)で、正しくない弾き方である「日本式」を信じてやみません。*きちんとした正しいやりかたをなさっているところも、少数ですがもちろんございます。 ”ここは日本なのだから、それで良いじゃないか~!!”と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ピアノの弾き方が国によって違うということは、まず「普通」のことではありません。サッカーのやり方も野球のやり方も、「やり方」は世界中どこの国へ行っても同じでしょう。国によって走る方向が違うなんてことはないと思います。ピアノもこれと同じなのです。 ずっと長い間日本がやっているピアノの弾き方は、世界中どこへいってもそんなふうに弾いている方は、プロ&アマ問わず、まずいません。”日本”だけが信じてやっているやり方だからです。 私も最初はこの間違った”日本式”の教育を受けてきましたが、大学に入ってからの先生は”正しい”ほうのやり方でずっと勉強されてきた方でしたので、私は”正しい本来のやり方”を大学に入ってからたたきなおされ、今はこちらのやり方が「普通」のなっています。 っというわけなので、いわゆる”日本式”のやり方を習ってきた方が98%もいらっしゃるこの日本ですので、今回のこの記事をお読みになった方のなかで、「え~~~~!!!自分が習ってきたのとちが~う!!」という方がおそらくかなり多いと思いますが、私はここで勇気をもって、「正しい」弾き方を書かせていただきたいと思います。 では、先ほどからお話している”間違った「日本式」”とは、具体的にはどういうことなのか?それはまず一つ目に、「鍵盤を底までしっかり弾こう!!」という弾き方です。”えっ!!これは正しくないの!????”と思った方、かなりいらっしゃると思います。が、残念ながらこれもまさしく「日本式」なのです。 「鍵盤を底まで押してしっかりと弾く」---この発想は、日本だけが行っていることですが、なぜそうなってしまったかというと、まずみなさん歌舞伎などの日本の踊りを思い浮かべてください。歌舞伎などでは足をトンッと床に打ったりすることがあると思います。そのときの力の方向は床へ床へーーーつまり「下へ下へ」といっています。 一方、西洋の踊りーーーー「バレエ」を思い浮かべてみてください。バレエでは、美しいバレリーナさんはつま先で立って、歩いたりクルクルと回ったりします。バレリーナはお人形さんのようにスッと軽々と立っているようにみえます。雲の上を歩くようにふわふわと優雅にみえますが、見かけとは反対に、つま先立ちをしているバレリーナは床ではなく天井に向かって伸びています。床方向ーーーつまり「下」方向でなく「上(天井)」方向に力が向かっているのです。足、特につま先はピーン!!となって、かなりしっかりとした足になっています。 日本では力を「下方向」に、西洋の踊りでは「上方向」に向かわせているのです。 このことがピアノにも影響を与えているように思います。 ここでみなさんに実験をしていただきたいと思います。まずまっすぐに立って、片方の手を天井の方向にピーンと伸ばしてみてください。そして、”もっともっと・・・”という具合に、高い天井を触るつもりになってみてください。すると、どうなりましたか?上へ上へ!!と伸びれば伸びるほど、足も床へ向かってしっかりとするでしょう。ピアノを弾くときも、これと同じです。「上へ」という方向にいくほど、下半身はしっかりとしていなければなりません。指がふにゃふにゃではいけないし、そうならないためには、下半身がしっかりとしていなければなりません。 すべてが、「下方向」へと行ってしまっては、いけません。 また、ピアノを弾くときに大切なことは、あまり指を動かさないことです。たしかに一つも動かさないのでは鍵盤は動きませんので、弾けないわけですが、それでも弾くときにできるだけガチャガチャとは動かさないということです。 かの有名な大大大作曲家であるショパンも、『鍵盤はなでるように弾く』と言っています。 「指をよく動かして、しっかりと鍵盤を底まで押して弾く」というやりかたを止めることが、上達への一歩となるのです!!!!!!!! ☆☆具体的な「正しい」ピアノの弾き方☆のおはなし。 まず指は第2関節ではなく、指と手のひらの付け根から動かします。決して、指先のみで弾くのではありません。そして指は、鍵盤を”弾く時”ではなく、”弾いてから”上げる(=upさせる)”ことです!!!!! これを行わないと、指を必要以上にガチャガチャと動かすことになり、良い演奏にはなりません。シールをだんだんにはがしていくように、”弾いてから”指を放していくことが大切です。また、弾くときには置いたままの手で弾いていきます♪♪ あくまでも、指をあげるのは、「弾いてから」です。 また、手の甲がつぶれないようにしていただきたいと思います。ピアノを弾くときは、手は”タマゴを持った形”ではありません!!!!!!!!! 手は、「生えているままの形」で置き、弾くことが大切です。あなたが力を抜いて、だらんと腕を下げたとき、そのままを鍵盤にのせると正しいフォームが出来上がります。指が、橋のようになっていると良いと思います。そして、スケールでもオクターブでもアルペジオを弾くにも、この「生えているままの手の形」で演奏することを心がけると大変良いと思います。 そして先ほどバレエのお話のように、腕や肩などは力を抜いていて、指はバレリーナの足のようにしっかりとしていなければなりません。「脱力」するからといって、すべての力を抜いて良いわけではありません。ここでも実験です。まず力を抜いて、まっすぐに立ってみてください。立ちましたか?そうしたら次に、もっと力を抜いてみてください。---すると、どうなりましたか?本当にすべての力を抜いてしまうと、あなたは床へ、へにゃっとしゃがんでしまうでしょう。っということは、あなたが先ほど力を抜いて立っていたときにも、必要最小限のいくらかの力は入っていたわけです。 ピアノを弾くときもこれと同じです。”力をぬいて、まっすぐに立てるだけの必要最小限の力”これが、必要なのです。あとは力むことも力を抜きすぎて、指がふにゃふにゃになることもありません。 そして手の甲は、天井を作るようにして、へこまないようにしっかりと支えることです。 こうしてお話してくると、やはり弾くときの「姿勢」が大変重要になってくることがわかると思います。背中をまるめて弾いているとか、首を曲げながら弾いているとか・・・。それでは、体をしっかりと支えるなんてことは、できません。ピアノを弾くときは、「背中で支える」というふうにも言えると思います。ときによっては、背中を少し後ろにしたほうが、弾きやすくなることもたくさんあります。スケールとかfやffとか、和音を弾くなどなどなど。 ピアノを弾くときには、正しい椅子の高さで、きちんとした姿勢で、良い指の形で、指はしっかり&腕や肩等は力が抜けていて、指をバタバタと動かさずに、鍵盤をかならず”弾いてから”指をupさせることです。弾くとき(=弾く前というか、直前というか・・)に指を上げるのではありません。 これらを守れば、かなり弾きやすくなると思いますし、美しい演奏になると思います。”え~、そうかなぁ・・”と思っていらっしゃる方、いまNHK教育テレビジャンマルク・ルイサダというフランス人ピアニストが、日本人等にピアノのレッスンをしているというのを放送しています(いました?)。それをみると、みな日本人の方は、「そんなに一生懸命に弾かなくてよい」とか「指をそんなに鍵盤の底まで弾かなくてよい」とか、「演奏中に首を動かさないで」等々といわれています。あの番組に出演されているかたも、それなりの経験を積んだ方たちなわけですが、日本式で弾いていらっしゃる方が大半ということだと思います。 私がこのブログでお話させていただいていることは、ルイサダさんのおっしゃることと同じことだと思うのですが・・・。日本で”ふつう”とされているやり方も、外国に行けばだれもやっていないことなのです。日本人だけがやっていることです。だから、外国に行くとなんだか日本人だけ変。ということもあります。もちろん正しいやり方で勉強なさっている方も、多くいらっしゃいますが、日本全体の2%ほどだと思います・・・。。 「日本だけやり方が間違っている」というのは、とても悲しいことですし、残念なことでもあります。私は少しでも多くの方に、”正しい”弾き方、を勉強してもらいたいと思っています。絶対に、日本式よりも本来の正しい弾き方のほうが、弾きやすいですし、理にかなっているのですから。これは私の経験上からも言えることです。このブログでもそうですし、わがピアノ教室でもみなさんに少しずつでもお教えしていこうと思っております。 興味のある方は、ぜひわがお教室へどうぞ♪♪♪
2005.10.23
コメント(3)
-
初心者と経験者のそれぞれの良さのおはなし。
私はピアノを4歳になってすぐから始めましたので、もう20年もやっていることにもなります。その中で、やめようかと思ったことも一時的にはありましたが、私にとってはピアノを”本当に”やめることはできないな・・・っとも思い、辛いときもやめずに、ずっと今日まできました。 また、今年4月にはヴァイオリンを始めました。24歳になってからのスタートです。始めた理由は、もともとのヴァイオリンへの興味に加え、ピアノに何か役立てばなどの想いと、大人になって習いはじめる方の気持ちを少しでも分かることができればということです。 実際に習ってみると、本当に色々なことを感じます。ヴァイオリンは難しいな~と感じることもあれば、できるようになってきたときの喜びなどなど。。やってみて本当によかったと思っています。得るものはとても多いです。 私がピアノとヴァイオリンの経験を踏まえて思うことは、まず年齢に関係なく「初心者」で習うことの利点は、先入観がないので先生のおっしゃることを”そうかぁ”と聞き入れられることです。”未知”であるために、先生のご指導に耳をかたむけられると思います。一方で注意点は、特にお子さんの場合に、先生から言われる内容の重要さ、大切さがあまりわからないという場合もあると思います。指導者のやり方にもよると思いますが、子どもはとくに発展途上ですので、”面倒くさい”とか”すぐにはできそうにない”などなど。忍耐力が大人ほどにはないかもしれません。それを鍛える意味もあるといえばあるのですが、子どもの場合は自分の気持ちの方が先行してしまうこともあると思います。 ですが、要はやり方だと思いますし、習うお子さんに大切なことは、「素直さ」をもっていることだと思います。以前にも書きましたが、先生から何かを言われても、我を通してしまって自分の勝手に練習等をしてしまうと、その人はある程度まではいったとしても、結果的には伸びません。 良い指導者とめぐり合い、心を素直にして、言われたことを「そうか!」と思って、実行することが上達への近道だと私は思っています。これには年齢問わず、共通のことだとも思います。 そして、もうひとつ。昔ならっていたけど大人になって再開したっという方の利点は、子どものときの経験がありますので、昔よりも色々なことをきちんと冷静に理解でき、そのことの大切さもわかるので、素直に実行し上達すると思います。また、大人になってから再開する方は、大抵はご自身の意思で始められると思いますので、相乗効果になると思います。また、子どものころよりもさまざま経験をしてきていますので、より味わいのある演奏になるとも思います。 大人になると子どもよりも理解できる幅がかなり広がりますし、子どものころの経験を踏まえてきていますので、練習への心の入り方も違うと思います。”やらされている”のではなく、”やりたい!”と思って始められることが、なによりの上達への道の第一歩です。 初心者でも経験者でも、どちらの場合でも共通することは、自分に合った良い指導者と巡りあい、自分に合ったペースで素直な心で習うことが、上達への道だと思います。始められる年齢は、関係ないと思います。たしかに大人よりも子どものほうが、指などはよく動くかもしれませんが、子どもには子どもの、大人には大人の良さがありますから、より味わい深い演奏ができると思います。年齢を理由に、やめてしまう必要はないと思いますし、いくつになっても”始めよう!”とか”やってみよう!”という心を持ち続けていたいものですね。それが若さにもつながると思います。♪♪♪
2005.10.22
コメント(1)
-
★なぐっちピアノ教室のやりかた ~レッスン システム等~★★
ここのところ、巷の色々なピアノ教室でのお困り話や良いお話など、色々なお話を耳にするので、みんさんのほんの少しでも参考になればとの想いで、今回はここでわがピアノ教室でのシステム等をお話させていただきたいと思います。 まず最初にお話したいのは、私のお教室では、なぐっちピアノ教室ならではの”特徴”、あるいは”個性”を出したい、持ちたい!!と考えました。これは、私自身にとってもそうですが、習いにいらっしゃる方々へのメッセージ、選ぶ指針になればとの想いもあってのことです。 わたしのお教室は、子どもさんにも大人の方にも安心して来ていただけるお教室を目指しています。大人になってから習う方の多くは、”自分は大人になってから始めた”ということをたいへんに気になさったりします。私も大人になってから(今年の4月から)ヴァイオリンを始めた人間です。私がヴァイオリンを始めたのは、ピアノに少しでも役立てばっという想いのほかに、そういう方のお気持ちが少しでもわかればと思い、始めました。なので、私もある意味では同志です♪♪(^^) 私自身は、大人になってから始められることは、とてもすばらしいことだと思いますし、むしろ子どものときからではわからなかったことなどに気がつけるという利点も大変多くあるので、大人になってから始められたことを誇りに思っていただきたいと思っているくらいです。 それから、私のお教室では”ちょろっと弾ければよい”という「イイトコ取り」希望の方はお断りさせていただいております。”イイトコ取りをしたい!!”という方の気持ちはわからなくはありませんが、それではピアノの本当の楽しさや歓びをしるには到達できないと思うからです。楽しくやるけれども、「まともに&きちんと弾けるように!!」という志を持つ方に向けてのお教室なのです。 また私はあまり時間をキツキツに、時計を見ながらのレッスンをしたくないと思っています。”ゆったり”のレッスンをしたいと思っています。なので、基本的な一回あたりの時間はありますが、広めの「時間枠」を取っています。 具体的に言えば、たとえば一回あたりのレッスンは30分や40分と決められているけれども、枠は60分とってあって、残った時間もそのままレッスンをしたり、あるいは親御さんと次のレッスンやご相談などのお話をする時間にあてられるというシステムです。もちろん時によっては、基本の時間終わることもあると思います。その辺は臨機応変というところです♪ 小さいお子さんの場合は、時間枠が1時間あっても集中力は30分くらいしかもたないと思いますので、のこりの30分は親御さんと次のレッスンのお話や、ご相談等をお話するための時間となります。また中級や上級等の方の場合は、基本の時間が30分でも、よく練習してあって曲などをたくさんやっている場合や、色々なお話をしながらゆったりとしたレッスンをする場合に1時間を自由に使えるということです。なので、レッスン代は一般のお教室よりはちょっぴり高めだと思いますが、時間枠を自由にゆったり使えるのです。 なお、私の教室は「大人コース」と「年長組~高校生コース」にわかれています。 *このほかに、「音楽専門コース」「保育系・小学校教諭受験コース」もございます。 「大人コース」の場合は、初級・中級・上級という3つのコース。 「年長組~高校生コース」の場合は、年長組~小学校3年生/小学校4~6年生/中学生&高校生という年齢別の3つのコースになっております。 また、〔年長組~小学校6年生〕までは月謝制のみですが、中学生&高校生と大人コースの場合は1回ごとから可能です。月に一回ごとでも2回ごとでも3回ごとでも4回ごとでも可能です。それから、都合のわるくなった回は、可能な限り振り替えレッスンを致します。 ★コースの詳細は次のようです。★ 「年長組~高校生コース」 年長組~小学校3年生:一回30分 〔時間枠 60分〕 ¥10000/月 小学校4年生~6年生:一回40分 〔時間枠 60分〕 ¥11000/月 中学生&高校生 :一回60分 〔時間枠 90分〕 ¥12000/月 「大人コース」 初級:一回30分 〔時間枠 60分〕 ¥3500/回 中級:一回40分 〔時間枠 60分〕 ¥4000/回 上級:一回60分 〔時間枠 90分〕 ¥5000/回 です。尚、このほかのコースについても詳細がお知りになりたい方は、おっしゃってくださいませ♪ お教室の場所についてですが、場所は群馬県伊勢崎市韮塚町です。(合併する前からの”伊勢崎市”です) 近くには目印となる大きなお店等がたくさんありますので、かなりわかりやすいと思います。 ”ぜひ習いたい!!”という方、いらっしゃいましたらどうぞご連絡くださいませ。このブログ内でかまいませんよ(^^) P.S. 宣伝ばかりで、もうしわけありません。今後もまたいつも通りの記事を書いてまいります。ぺこり。よろしくお願いいたします。
2005.10.21
コメント(0)
-
子どもたちに必要なこと&大人のレスナーの方に大切なことのおはなし。
私は音大を卒業後、最初の2年間は県内の高校にて音楽の先生をしておりました。そしてその次の年である2005年は、市内の小学校にて非常勤講師をしております。 ”今”の高校生や小学生をみているなかで、”子どもたちには、こういうことが大切&必要なのかな~”と私なりに思ったことがあるので、今回はそのことを私の考えですがお話させてもらいたいと思います。 私が感じることは、小学生も高校生も基本的には同じだということです。小学校では人間がいろいろな人たちと生きていく、暮らしていく上での基本ーーー「規律」を教えられます。さんざん教わったはずなのに、高校生になっても同じような基本的なことを注意されたり、同じような事がらが起きたりすることがあります。 もちろん、高校生ということは小中学校での経験を経てきていますので、それなりに「大人」の部分もありますし、しっかりしている部分もたくさんあります。 また、高校ではもちろん小学校のようには一つ一つ手取り足取りはしませんし、勉強等々においても大きく異なります。また高校生には高校生なりの悩み等もあり、日々の疲れやその日のテンションがもろに出ます。それに比べて小学生の場合は、それでも本人なりのそれぞれの悩みはあるのだろうと思いますが、高校生ほどには重く深刻に悩んだり、抱え込んだりはしないような気がします。 高校生や大人の方たちをみたりしていると、いかに小学校時代の教育が大切かがわかります。ハンカチ&ティッシュは必ず毎日持っていくとか、人に対して嫌な想いをさせるようなことはしないとか、忘れ物はなくすとか、決められたことは守るとか・・・。 こういう基礎ができていないと、成長するなかでーーー生きていくなかで、とても大変で苦労します。修正されたりすることがあれば良いのですが、これはかなり人それぞれです。小学校で習ったことが、ずっと大人になっても続いていくことが本当にたくさんあります。 私が感じることは、まず子どもたちは基本的に動物とか虫や自然がとても好きだということです。私はずっと地元群馬県に住んでいますので、子どものころに川や山に行ったりして、色々な体験をさせてもらいました。その経験が今も生きています。生き物や自然が大好きな子どもたちにとって、コンクリートジャングルに暮らすとか、いつもTVゲームばかりしているとか・・・。やはり子どもの感性を育てるには、大きな影響を及ぼすような気がします。たしかにお家の都合ですとか、色々な事情があることもわかっています。でも、”子どもたちにとって”ということを考えると、せめて夏休み等のまとまって休めるときなどに体験させてあげられると良いのではないかと思います。 また、子どもたちは体を動かすことがとても好きです。自分の体を使って、その子なりの”何か”を表現したいのかな~と私は思います。 私が子どもたちにとって大切だと思うことは、まず「何でも自分で体験する」ということです。本人以外の人たちーーーたとえば、大人等がその子に代わって”やってあげてしまう”ことは、あまり良いことでないように思います。 大人でもそうですが、考えてみると基本的にだれでも、”自分で体験”してみないと覚えないと思いませんか? あれこれ口で説明されたり、人がやっているのをみるだけよりも、自分自身で”やってみる”ことで私は一番理解できると私は思います。同時に、自分で経験することによって、喜びや感激等々のさまざまな感情を味わうことができます。このことは、「音楽」をする上でも大変重要です。 また、ここで大切なのは、「失敗」はしても良いということです。失敗をおそれて、こわくて何もできないのでは、何も成長できないと思います。”必要な失敗”は、ぜったいに必要です。 それから私個人的には、指導者は失敗も受け入れる心を持っていてほしいと思っています。”少しでも失敗したり間違えたりしたら、怒られる!(><)”という状況では、良い意味で”心おきなく間違えられない”ので、生徒さんは精神的に大変だと思います。たしかに、「厳しい」先生というのも、必要だと思いますが、教わる側にも色々なタイプの方がいますので、その人に合った指導者が見つかると良いですよね。♪(^^) それからもう一つ、私が重要だと思うことは、「自分自身で考える」習慣をつけることです。「学校」では、どうしても色々な場面で受け身になりがちです。どちらかというと一方的に指示をされ、それに従ったり、いろいろなことを教わりますので、まずそれができるようになる!ということに重点が置かれるように思います。 私自身がピアノをやってきた中で重要だと感じることは、「自分自身で考える」ことができるということです。たしかにレッスンでは、先生にさまざまなことを教わりますが、それはレッスンに行く前の下準備ーーーつまり、「ご本人の練習」があってのことです。 馬が水を飲みたいとき、飼い主が馬を水飲み場につれていくことはできても、実際に”飲む”という行為は馬自身がしなければできないのです。 レッスンも、これと同じだと思います。 私が申し上げたいことは、まずは下手でもなんでもいいから、習う側が自分なりに少しでも練習をしていかなければ、レッスンに行っても得られるものは少ないということです。まず自分なりの練習ができていないと、先生に何か質問をしたくても、自分がいったい何はできていて、何をできないか。そして、どんなふうに自分は困っているか等・・を、まず自分でわからなければ質問をすることはできないのです。 まずは、自分なりの”練習ありき”なのです。 大人の方の場合は、お仕事をしながらのレッスンという場合が多いと思いますので、正直に”練習のようす”をお話なさったほうが良いと私は思います。具体的には、週のなかでどのくらい練習時間を取れるか等です。もしある週にまったく練習できなかったとしても、それを隠したり取り繕ったりせず、正直にお話なさったほうが良いと思います。無理に取り繕うことはないと思います。 誤解ならないでいただきたいのは、私は決して”練習をしていかなくても良い”と言っているのではありません。練習はもちろん絶対に必要です。ただ大人の方の場合は、その時々のお仕事の状況やお家の事情もあると思いますので、そのあたりのことは大変なときには先生にぜひご相談なさると良いと思いますよ♪ きちんとした先生であれば、その辺もきちんと考慮して、宿題の量など調整してくださると思います。 子どもさんも大人の方も、それぞれのタイプに合った先生が見つかると良いですね。私のお教室でも、いつでもお待ちしております。♪♪♪(^^) ぺこり。
2005.10.21
コメント(0)
-
☆繰り返し記号の解釈のしかた。のおはなし☆
みなさんは、繰り返し記号ーーー1カッコや2カッコやコーダやリピート等々を、どのように解釈していらっしゃいますか? 今回は「リピート記号」について、お話したいと思います。 まず最初に、「リピート記号」というのはわかりやすく言うと、”同じ部分を2回繰り返して(=2回やって)次へいく”というものです。とくにピアノで言えば、「ソナタ」などの場合に大変多く使われます。 楽譜上では”同じところを二回やる”ので、時間短縮(?)というので省略して一回だけにして次へいくっという演奏をされることもあります。 人前で演奏する正式のときには、普通きちんと楽譜通りに演奏しますが、大学などの実技試験や普段のレッスンの時などに、しばしば”すっとばした”演奏をされてしまうこともあります。「同じことを2回やる」という意識なのだと思います。 さて、ここで「リピート記号」についての正しい解釈の仕方をお話します。 「リピート記号」は、決して”同じことを2回やる”のではありません。たしかに楽譜上では、”さっき通ったところをもう一回通る”というふうに見えると思いますが、それは違います。正しくありません。 もし「リピート記号」を用いないで楽譜を書いたとき、当たり前ですが、ページはその分先に進みます。決して”戻る”わけではありません。弾くものは楽譜上では同じ音でも、そのニュアンス等は変わっていなければなりません。時間は経過していくのです。時間が戻って、巻き戻しの演奏をするのではありません。 *またまた説明が上手くなく、すみません。。ご質問等ありましたら、ぜひどうぞ♪ 「繰り返し」は、音楽形式の一部なのです。決して”やってもやらなくてもどっちでも良い”というものではないのです。繰り返しを行うとき、時間はその分進んでいるのですから、ぜったいに”最初とおなじこと”をしないことです。ニュアンスであるとか”なにか”を変えるべきなのです。 繰り返しをするとき、繰り返しをする喜びをもつことです!!ただ単に”あ~、またおんなじことをするんだな~・・・”などと思ってはいけません。作曲家がそこにリピートを書いたということは、それをする意味があるのです。音楽の内容からいって、”繰り返しをしないではその次にはいけない!!”ということなのです。 たしかに音大等の試験などでは、受験する人数がある程度いますので時間等のことも考え、”繰り返しをしないこと。”っという指示がある場合がとても多いです。確かにそれはやむを得ないと思います。 でも、だからといってみなさんが普段からその曲を繰り返しをしないで演奏して良いのではありません。 ここで大切なことは、まず本来の「繰り返しをする」形で勉強し、ある程度まできたら、繰り返し無しの練習をするべきだと思います。最初からずっと繰り返し無しだけをすることは、望ましくありません。 楽譜に書かれていることで、必要のないこと”、”やってもやらなくてもどちらでも良いこと”っというのは、ありません。すべて”やってほしい”から書かれているのです。とくにベートーヴェンは、やってほしいことは全部楽譜に書いたといわれています。モーツァルトにおいてもほかのどの作曲家においても例外なく「楽譜を読む」ことが基本であり最重要なことですが、中にはその時代には暗黙の了解で”ふつうこういうときはこうする”という「システム」が存在した時代もあります。でもそれは主にバッハやモーツァルトの時代のことです。ベートーヴェン以降からはかなり楽譜を忠実に読むということが重要になってきます。 どんなことでも、解釈ひとつでステキにも台無しにもなってしまいます。どの部分においても、正しい解釈をもって演奏したいものですね!!♪♪♪
2005.10.20
コメント(0)
-
☆強弱記号の解釈のしかた☆
みなさんは楽譜に書かれている強弱記号ーーーpやf、ffやpp、mfやmp、fpやsfzやcrescendoやdecrescendo等々を、いったいどのように解釈なさっているでしょうか? 今回は少しそのことについて、書かせて頂きたいと思います。 まず、楽譜にはpやfが書かれていることが大変多いです。このとき、みなさんはどのように演奏していらっしゃるでしょうか? pが書かれているからといって、いつも急に小さくなさっている方。あるいは、fと書かれていると、そこから先をずっとただ大きいだけで弾いていらっしゃる方、いませんか? ここで正しい解釈についてお話します。 pやfが書いてあったとき、その記号から次の記号までの「区間」が”p”、あるいは”f”であるという意味です。pなりfなりが書かれているすぐ上の音が、いきなり大きいとか一番大きいのではありません。もし楽譜を強弱別に色塗りをするとしたら、pが書いてあったら、そこから次までが”pの区間ですよ”というわけなので、同じ色で塗られます。(fにおいても同様) 決してpの書いてある音が”一番小さい”というわけではありません。pの区間ならpの区間なりの盛り上がりというかフレーズの流れ方があるわけなのです。pの範囲で考えて、一番大きくするところ、小さくするところを作るのです。 また、クレッシェンドをするときにそれが書かれているところからすぐにクレッシェンドをし始めてはいけません。少しあとから始めます。そのときの”あとから”具合は、時と場合によりますので、ここではっきりと申し上げることはできませんが、すこし待ってから始めると良いと思います。デクレッシェンドについても、同様です。 クレッシェンドというのは、教科書通りの意味を言えば「だんだん大きく」という意味です。デクレッシェンドは、「だんだん小さく」という意味です。 っということは、クレッシェンドは”これから大きくしよう”としているのですから、クレッシェンドが印刷されている最初の所は、pであるはずです。 デクレッシェンドも、”これから小さくしよう”としているのですから、デクレッシェンドが印刷されている最初は、fであるのです。 このことを大変大変大変多くの方が、誤解なさっているのです。考えてみれば当たり前といえば当たり前のことなのですが、意外にこのことはあまり理解されていないように思います。 かの有名な作曲家、メンデルスゾーンも『cresc.の最初はp。dim.やdecresc.の始まりはfである!』と言っています!!!♪♪♪ またここでもう一つ大切なことは、sfz(スフォルツァンド:特に強く)の解釈の仕方です。 大変多くの方が、楽譜にsfzが書かれているとき、”強くしよう、強くしよう”となさっていると思いますが、それは間違っていると私は思います。 sfzの正しい意味とは、espressivo(エスプレッシーヴォ:表情豊かに)なのです。 みなさんここでちょっと考えてみてください。みなさんが子どものときでも大人の現在でもどんな方でも、”想い”が強いと自然に大きな声になっていると思いませんか?子どもに言うことを聞いてほしいとか、わかってほしいとか、呼んでいる相手がなかなか振り向かないときなどなどなど。その気持ちーーー”想い”が強ければ、強くしようと思わなくても自然に声も大きくなっているものです。ここを多くの方が理解なさっていないところだとわたしは思います。 すぐに”ここは強くするんだ、とにかく強くだ!!”と思って、曲のその部分のあり方や状況を考えずにただひたすらに「強く」している方が大変多くいらっしゃいます。でも、それは正しくはありません。 きちんと弾けていれば、強弱は楽譜をみなくても、自然に”そうしたくなる”ものです。楽譜に書かれているどんなことも、みな必要事項です。”ここはこういうふうに書いてあるけど、やらなくて良い”というものは存在しません。「自然な演奏」をするのには、楽譜に書かれていることを大切に扱わなければなりません。”どうもうまくいかないなぁ~・・・・”という方、ぜひ基礎であるメトロノーム使用&拍子を守る、リズムも正しくっということを見直してみてください。「まっすぐに歩けているか?」ーーここをもう一度立ち返って、考えてやってみることをお薦めいたします。それができていれば、”ここをこんなふうにしたい”ということが、自然に内から湧き上がってくるものです。そうすると、結果的にそんなにおかしな(=不自然な)表現はしていないことになると思いますよ。♪♪♪
2005.10.19
コメント(0)
-
ピアノを習い始める時期のおはなし。
みなさんはおいくつからピアノを始められましたか? 3~4歳の幼稚園からという方もいらっしゃるでしょうし、小学生のときからという方も中学や高校に入ってからという方、また大人になって新たに始められたり再開なさってという方もたくさんいらっしゃることと思います♪♪ いくつになっても”何かを始める”っということは、ちょっぴり勇気が要るかもしれません。でもそれはとても素晴らしいことだと私は思っています。 ”自分はもうこんな年齢だから・・・・・”などと理由を作って”始める”ことをやめてしまうのは、大変もったいないことだと思いますし、そんなふうに年齢を気になさる必要はまったくないと私は常々思っています。 ”何事もあきらめてしまって何も始めることもなくただボーっと過ごしている”という人より、いくつになっても年齢を関係なく、勇気をもって何かを”始めたよ!(^^)”っという人の方が、何倍もすばらしいと思いますし、”先を行っている””進んでいる””意欲をもって生きている”という気がします。 さてさて、いくつになっても何かをスタートさせたり、再開させたりするのは大変良いことですが、私はピアノに関して、ちょっぴり気になることがあります。 私自身のピアノの始まりは、大手音楽教室に通ったことです。たしか4歳になってすぐのことだったと思います。私は習い始めたときの事を断片的には思い出せても、はっきりと具体的にどんなふうにやっていたかを思い出すことはできません。そこでその頃の楽譜をいま見てみると、3歳や4歳の頃はピアノを弾くというよりも何かを歌ったりタンバリンや鈴などを鳴らしてみたり、そういうことに重点を置いていたように思います。確かにそういったことは、何かしらの役には立っていると思いますが、私はそのほかに家でいつも聴いていたクラシックのテープのおかげをとても感じます。幼い頃にクラシックや童謡のテープを聴いていたことは、かなり良かったと思います。 私は、ピアノでも歌でも他の楽器をするにも、「音楽性」を持っていることはとても重要だと思います。特に音楽を専門にやっていこうとする方には、これがあるのとないのとでは雲泥の差です。 音楽は「想像」、「創造」する力が必要です。どんなにすばらしい技術を持っていても、技術だけではやっていけません。想像する心や力がないとある程度まではいくと思いますが、それ以上は難しいような気がします。 たしかにピアノを習い始めるには小さい年齢からの方が良いとは思います。歌や管楽器等の場合はもろに体を使いますので、ある程度体が成長してからでないとできませんが、ピアノの場合は遅いよりは早いほうが良いと思います。 ただ、私は”早いけりゃ良い!!”とは思いません。私自身の考えでは、ピアノを始める年齢は「年長組や小学校1年生」からで十分だと思います。「学校」が今の年齢からスタートすることになっている点からも、その年齢からが最も物事を覚えるのに適しているのかな~・・と思ったりします。 では、その年齢までは何をしたら良いかというと、とにかくその”土壌”を作っておくことが大切だと、私は思います。クラシックを日常的に聴かせ、そういうものがその子にとって”普通”になるといいと思います。そうすればその後、その子がそういうものを好きだと思えば、3、4歳から始めなくても、技術はあとからついてくると思います。 「日本」のやり方では、しばしば”頭でっかち”のピアノになりがちだと思います。音符や休符の種類や音の高さ等々は十分に知っているけれど、自分が弾いている曲の題名も知らないし(=関心がない)、拍子も守っていないし、ただメロディだけを追っているだけっというピアノ。音楽の中身なんか、どこかにいってしまってめちゃくちゃなピアノを弾いているっという子。大変大変多いと思います。必要なやるべきことができていないのです。そして、そのことを習っている本人はもちろん、その先生もそれをまったくわかっていないという場合もたくさんあると思います・・・。”The 日本”流だと思います。 *もちろん、きちんとやっていらっしゃる先生もいらっしゃいますが・・・。 リトミックも、私個人的には必要ないと思います。曲を学べば、自然にというか必然的に「歌う」とか「リズム」をきちんとすることもその中に入ってくるからです。 歌うことやリズムを取ること、また聴音や音楽理論や語学は、すべて「音楽」をする上でつながっています。別々な、関係ないことなのではありません。ひとつの円をつくっているともいえると思います。演奏する上では、すべて関わっています。 人それぞれ色々な考えをお持ちでいらっしゃると思いますが、いずれにしてもピアノに関して、音楽に関して言えば、私はあまり早いころから始めることばかりを追わずに、その土壌を作ることもとても大切だと思います。今若いお母様たちが、お子さんに早くから英語や英会話を習わせよう!!としていらっしゃいますが、それは幼いうちからその子にとって英語が「自然」、「普通」の存在になって、成長していくなかで英語と抵抗なく関われるようになってほしいからではないかと思います。 「音楽」でも同じことです。音楽教室に通わなくても、お家で日常的にクラシックのCDを流したりして、親しみを持たせる。それからお母様となにかちょっとした童謡で良いので、歌ってみる等々。お子さんにとって一番うれしいのは、お母様と一緒になにかをするっということではないでしょうか。そういったやり取りを通して、親子のコミュニケーションをしてみることは大変良いことだと思いますし、また必要なことだとも思います。ピアノの先生はたくさんいらっしゃいますが、その子にとっての「お母さん」は一人しかいないのです。 本人の様子もみながら、親子のコミュニケーションとより良いお教室選びをしていただきたいと思っております。私も年長組のお子さんから130歳まで、お待ちしております。♪
2005.10.18
コメント(0)
-
☆指使いのいい所のおはなし。☆
みなさんの中で”指使い”と聞くと、とても耳の痛い方がいらっさしゃると思います。私も昔昔昔はそうでした。私も最初から何でも言うとおりにきちんとやってきたわけではなく、数々の反抗(?)があったものです。 さてこのごろでは何か物事を行うときに、必ずきまって「これは何のためにやるのか?」とか「これをやっていったい何になるのか?」という〔理由〕や〔意味〕を問う人が多くいらっしゃいます。役に立つとか立たないとか、そういうことを物事の指針にしているのだと思います。ですが、それはあまり良いことではないと思います。 たとえば百人一首や論語等々。昔からある素晴らしいものを意味がまったくわからなくても、子ども時代に「暗記」をすることは大変大変良いことです。なぜこれが良いことなのかというと、こういうことを通じて幼いときから「物を隅から隅まできちんと見る」という習慣がつきます。この力を備えているのといないのでは、雲泥の差があります。また、これらのものを暗記することは、中学生や高校生になったときにも、”コレって、あの昔に覚えたアレだ~!!”というふうに頭の中でつながりますし、勉強するときにも親しみを持つことができます。また、様々な言葉を知ることもできます。 漢字を書くとき、私たちの中でいったいどれくらいの人が書き順通りに書いていらっしゃるでしょうか。私は現在小学校に勤務しておりますが、子どもたちをみていると漢字がよくできる子は共通してみんな、正しい書き順で書いています。漢字ができないという子は、書き順なんてどこへやら・・という具合で、自分の好き勝手に書いてることがとても多いです。 なぜ書き順を守る必要があるのでしょうか?それは単に学校などでそういうふうに教えられているからということ以上に、何より書き順通りに書くことが最もきちんとした美しい字が書けるのです。書き順通りに書くと、最も字の形がよく取れるのです。 指使いもこれと同じです。普段から指使いの通りに弾くことが、いちばん美しく弾けるものです。また、クラシックの曲には大抵指使いは書かれていますが、学校などで歌う曲や一般のポピュラーの曲等々の楽譜には、指使いが書かれていません。いつもテキトーに自分の好き勝手に弾いていると、そういう楽譜を演奏するときに、いったいどの指を使って弾いて良いのか方法がわからず、大変困ってしまいます。しかしいつも守って弾いていれば、どんな楽譜に直面しても、特別に何か考えなくとも自然にすんなりと適した指使いで演奏することができ、とてもラクです。 このような理由から、漢字の書き順もピアノの指使いも、すべこべ言わずにその方法で”やってみる”ことが、いちばん本人のためになります。わざわざ遠回りして結果的にそのことをわかることももちろん良いですが、おとなしくその正しい方法をご自身でやってみることが、いちばんの近道だと私は思います!!♪♪♪
2005.10.17
コメント(0)
-
☆絶対に忘れない暗譜のしかた☆
みなさんはどのようにして暗譜をなさっていますか?暗譜は指ではなく、頭でするべし!!ということは前回お話したと思います。 さて、今回は具体的なそのやり方などについてご説明したいと思います。 「音楽」は、”言葉”でもあります。なので、暗譜をするということは、外国語を覚えるにも似ています。暗譜をより上手くきちんとできるようになるには、やはりそれなりのコツが要ります。しかしそれは、数をこなさなければ本当にはわかっていきません。ですが、ここで何か少しでもみなさんの助けになれることがあればと思い、具体的なある程度の方法を書かせていただきます。 たとえば、みなさんが外国語の文章を暗記するとしましょう。そのとき、どんなお話なのかや文章の流れ等。ある程度の中身がわからないと、覚えるのはとても大変です。闇雲に内容もわからないのに暗記するのは、良い方法ではありません。 それと同じで、暗譜をするにもまず、だいたいの”お話”の流れがわかっていないのでは、ますます大変になってしまいます。 私が暗譜するときに最初に行うことは、CDを聴いて曲のおおまかな流れをインプットします。そのとき音などをなるべく”記憶しない”ことが大切です。なんとなくの”ながれ”だけがわかれば良いのです。 次に今度もピアノは一切使わず、楽譜をよく読んで分析していきます。曲には、同じ箇所と新しい箇所や、音はちがうけどやっていることはまったく同じなどなどなど。様々な特徴があります。これは、曲の構成をしることにもつながりますし、とても大切なことです。どうやって分析をするかというと、横の音の流れや、ここはこれとつながっているとか。素人の方には少し難しいかもしれませんが、できる範囲の簡単なことから始められると良いと思います。 そしてその次に、その分析を元に”ここはこっちと同じ”とか”似ているけどここが違う”とか”ここはまったく新しい場面”など、楽譜にしるしをつけます。そしてそれを元に少しずつ頭で覚えていきます。 問題の覚え方ですが、私の場合は楽譜をみながら、目をつぶって頭の中に鍵盤を思い浮かべ、頭の中でその鍵盤を弾いていきます。しっかりと音を頭のなかで追っていくのです。そのときに途中で空白がでてくると思います。わからなくなるということです。それができるだけ初期段階にある方が良いのです。”あれ??次はなんだっけ???”と思ったら、そのときに覚え直せば良いのです。ここで大切なことは、欲張らないことです。決してその日にやったことは次の日にまた同じところを覚えなおさなければならないなんてことがないように、確実にして進むことです。欲張るのはやめてください。少し余裕をもったくらいがちょうどよいと思います。確実に覚えなければ、せっかくやる意味がありません。 これを両手ともにできれば、OKです。望ましいのは、やはり左手から先に取り掛かることでしょう。「左手→右手→両手」という順にできると良いよ思います。右手から先に覚えてしまうと、そのときはまだエネルギーがたくさんありますし、頭の中が新鮮な状態で覚えられます。でも、そのやり方をしてしまうと、ただでさえ苦手な左手をやるのが、とても辛くなってしまいます。エネルギーが最初よりは少し減っていますし、気持ちが疲れてきちんとやろうという気が少なくなってしまいます。 最初にいつもは苦手な左手を先にやってしまえば、あとはみなさんの大好きな右手をやるのみです。右手がメロディ担当を多くする曲はとても多いので、やりやすいと思います。もしかしたら、左手をやっているときに、早く右手をやりたくてウズウズしてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、そこはぐっと我慢です。そこで右手のことをやりだしてしまうと、せっかくおぼえた左手にもわるい影響を及ぼしてしまいます。 初めはおそらくかなり大変だと思いますが、これをやれば人前で弾くときにとてもラクになります。うる覚えではないので、直前にあせって楽譜の上で指を動かすなんてこともする必要がありません。最初にちょっとがんばっておけば、あとがずっとらくになります。 とにかく先に頭にいれてから、実際に弾いてみることです。また、前日覚えたことを次の日に実際に弾いてみることも良いと思います。でも、絶対にその日に覚えることは弾かないことです。あくまで、それまでに覚えたことを確かめるだけです。 それからもう一つ、みなさんに申し上げたいことは、世の中に「譜読み」というものは存在しないということです。ここで100%近くの方が、”えっ!!!????”と思われたのではないかと思います。 「譜読み」がどうのこうのといっているのも、これもまた「日本」のやり方です。”「譜読み」というものは存在しない”とは、どういうことかというと、「音楽」とは、”言葉”なのです。”モーツァルト語”とか”ベートーヴェン語”とか”シューベルト語”などといった具合に、それぞれの作曲家のカラーというか世界があり、その作曲家らしさをあらわしているわけでもあります。 みなさんはおそらく「譜読み」という言葉を”普通”の言葉として使っていることと思います。ですが、音楽は言葉なのです。みなさんは、新聞を読むとき、どのようにして読んでいらっしゃるでしょうか?すぐに内容を読み取っていると思いませんか?字を最初から最後まで読めるようになってから、中身を読んでいくという方は、いらっしゃらないと思います。音楽でも、それと同じなのです。 みなさんが曲でも教本でも勉強なさるとき。もう始めたときから中身を読んでいっている。これが、正しいやり方なのです。そう聞いて、”なんだか難しそうかな・・・”と思ったかたもいらっしゃるかもしれません。”そうかなぁ~・・・・”と納得できない方もいらっしゃるかもしれません。日本では、”日本式”のやり方を、98%のお教室でなさっていると思いますので、本当に「正しいやり方」でやっているところはそう多くはありません。そういう中で暮らしている以上、”こっちが本当の正しいやり方です”とお話しても、理解するのはもしかしたら難しいと思います。 私も自分は今でこそ、その残りの”正しい”2%の側になりましたが、もともとは”まちがった”日本式で育ってきました。なので、この”正しい”方を教えてくださった大学からお世話になっている現在のピアノの先生に習い始めた当初は、先生のおっしゃる意味がよくわかりませんでした。でも、その先生に色々なことを教えていただくにつれて、その本来の”正しい”やり方がどんなに「正しい」か、どんなに”日本式”がおかしいかを理解できるようになりました。日本では少数派の部類に入りますが、外国に行けば、この”日本式”が滅多にいない少数派なのです。日本にいると、そのことがわからないと思いますが、本当の正しいやり方、音楽の方向を教えていただくことができた私は、少しでも多くの方に「本物」を提供できたらと思っております。
2005.10.16
コメント(5)
-
☆演奏するのに欠かせない大切なことのおはなし☆
みなさんは、レッスンに行くとそこで先生からさまざまなご助言をいただくことと思います。私も今日レッスンに行ってきましたが、そこでもまたたくさんのことを得ることができました。本当にレッスンに行くと、元気になって帰ってきます!!(^^)♪♪♪ さて、みなさんはレッスンで”その音はもっとながく!”とか”もっと短く!”とか、”この音をもう少しだして、こっちの音をひっこめて!!・・・”とか”もっと速く!!”とか”もっと遅く!”などと言われる方がとても多いと思います。そして、実に98%のお教室で、このやり方をしていると思います。個人、大手は関係なくです。またまたこれも、「日本」ならではなのです。 しかし、そういうやり方というのは、実は「正しい良いやり方」とは言えないのです!!!!! 私たちが教本であれ曲であれ何であれ、演奏するときに最も大切なことは、いつでも今やろうとしているものを、”どんなふうに演奏したいか”という実際の音楽的な表現の「完成形(=完成目標図)」を頭の中できちんと先につくっておくのです!!!それは頭の中や実際に声に出して歌えなければ、弾くことはできないのです。その目指す完成形を、今度は実際に体の動きと”一致させる”ーーーつまり、頭と体が一致してそのことができるようにするのです。それが「演奏する」ということですし、それを「練習」によって、可能にするのです。 たしかに場合によっては、”もう少しながく”などと言うこともあるかもしれませんが、それは完成形を本人にわからせるためでなければなりませんし、あまり良い方法とはいえません。教わる側は、ただ単に”もっと長く”とか”短く”などと言われたのでは、いつも先生の顔色をうかがうことになってしまうし、ご本人には”いったいどういう形をやろうとしているのか”、”どういう形が良い形なのか”がわからないままです。そうなると、弾く側は演奏の流れのことはどこかに飛んでいってしまって、”長く”とか”短く”という判断で演奏してしまいます。つまり、自分の弾いている音を「聞いていない」ということです。これでは、「音楽」のことを”考えていない”ということになってしまいます。こうなると、何のためにやっているのか、何を目指せば良いのか、音楽の方向さえもまったくわかりません。 それからもう一つ。 楽譜には強弱記号や発想記号など、さまざまな表記がされています。みなさんは、それらをどのように扱っていらっしゃるでしょうか? 「音楽」とは、”自然”なものです。何においても「自然」でなければなりません。不自然な演奏を弾いていることは、大変です。 演奏するにあたって、いちばん最初にやらなければならないのは、「まっすぐ歩ける」ようになることです。つまり、拍子を守って、テンポもリズムもきちんとその通りに弾くことができなければ、それ以上の深いところにまで入っていくことはできません。また、それができないうちにテンポを揺らすとか、強弱を好き勝手にやるなどは、絶対にあってはいけません。言語道断です!!!!! rit.やcresc.、dim.などなど。楽譜に書かれていることを挙げればキリがありませんが、とにもかくにも”まっすぐ歩ける”ようになれば、自然に”ここはこういうふうにしたい”とか”このrit.は、このくらいの度合いでやりたい”などなど。内から生まれてくるものなのです。それは、楽譜を意識しなくても、下地がきちんとできていたら、自然と内から生まれてくるそれは、楽譜と一致しているものです。 たとえば、みなさんが何かを朗読するとしましょう。当たり前ですが、朗読というくらいですから、もちろん声に出して読むのです。そのときに、もし読みをつっかえていたら、読み間違いをしていたら、話の内容を理解するのにたいへん邪魔になってしまいます。朗読でいう、”句読点をもちろん守り、スムーズに滞りなく読める”ーーーこれが、私が先ほどから言っている「まっすぐに歩ける」ということです。 そして、スムーズにきちんと読むことができてくると、自然に”ここはもっとこんなふうに読もう”という案が、自分なりにでてくるものです。それが、音楽でいう、rit.やcresc.、フォルテやピアノ、ピアニッシモなどなどのさまざまな表記、そしてそのほかのニュアンス的な部分のことです。 ”まっすぐに歩ける”ことができないのに、ダンスをすることはできません。つっかえずにきちんと最後まで、守るべき”約束事”を守って読むことができなければ、細かい表現の仕方を考えるには及ばないのです。 それから、なぜ私たちは”音を間違える”ーーーつまり”ミスタッチ”をしてはいけないと思いますか?楽譜に書いてある通りに演奏しなければならないからですか? たしかにそうだと思います。でも、もう一つの言い方をするならば、またここで朗読のことを考えてみるとわかります。 朗読をするとき、言葉を間違えてしまうと、聴いている方はもちろん、読んでいるご本人の気持ちも、”ガクッ”とずっこけてしまうからです。せっかく気持ちよく読んでいるのに、弾いているのに、間違った音がそこに入ってしまったら、音楽ならばハーモニー(=響き)がそこでちがってしまうのです。聞こえてほしくない響きが、そこで生じてしまいます。本人の気持ちが揺らいでしまうだけでなく、聴いている方にとっても同じことです。もちろん、間違えても”ガクッ”とならなければ間違えてもよいというわけではありませんよ。わかっていらっしゃることと思いますが・・。あえて書かせてもらいました。(^^;) こうして考えると、いかに「楽譜の通り」に演奏しなければならないかがお分かりになると思います。わがブログのお話にしばしば出てくる”98%のお教室が・・・”というときの、その残りの2%という少数派に属する私としては、少しでも多くの方に、大間違いの”日本式”ではなく、本来の正しい”音楽”の方向をお話できたらと思うと同時に、自分のお教室にいらしてくださる生徒のみなさんにも、伝えていかなければと思っております。”日本式”よりも、本来の正しいやり方の方が、ずいぶんとやりやすく、わかりやすく、また理にかなっていると思います。 ぜひ色々な方々、お待ちしております。♪♪♪
2005.10.15
コメント(0)
-
上手く弾けるようになるためのポイント&普段の練習の仕方 のおはなし。
今回は、みなさんが少しでもピアノが弾きやすくなるように、ポイントとなるようなことをお話したいと思います。 今までのお話のなかでも少しずつ触れてきたことですが、すべては「頭の中次第」ということです。これは、頭の良し悪しを言っているのではありません。私が言う意味は、暗譜をするのも、指を上手く動かすのも、すべて頭の中とつながっているということです。頭が停止状態なのに、指が勝手に動いてくれるということはあり得ません。”きちんと身についているから、意識しなくてもできる”ということがあるだけで、それも身につけるにはそれなりの努力があってのことです。 暗譜をするのも、慣れないパッセージを弾けるようになるのも、音楽的表現をするのも、すべて「頭の中の整理+からだに覚えさせる」という作業だと思います。私は最近このことを、”自分の中にまだない引き出しをつくる”っということかな~♪と思うようになりました。”まだない”引き出しを作るのですから、容易なことではありません。 みなさんは、「練習」というといつでもピアノを弾いているのを想像すると思いますが、練習のやり方はそれだけではないのです。 すぐにピアノに向かっているだけでは、ピアノを上達させることはできません。結局、どんなにたくさんの練習をしても、頭の中がそれを受け入れるだけの準備ーーーつまり、「整理」ができていなければ、何もあたまには入っていきません。そして、頭に入れる内容もきちんと「整理」されていなければならないのです。 だから、やみくもにただピアノに向かうのではなく、とにかく”やろうとしていることを頭に入れる。”&”段取りを考える。”&”やり方を考える。” ことが大切です。ピアノに向かうまえに、いったん頭の中を整理して、楽譜をながめ、暗譜をするのならば、机上で覚えるほうが良いと思います。ある程度流れは頭にいれたら、弾くよりも先に目でみて頭で覚えるのです。「暗譜」は、決して”指で覚える”ものではありません!!!!!!この辺は、実に大変多くの方が誤解なさっているのではないでしょうか。指で覚えると、暗譜がとても怖くなりますし、もし演奏中にハッとしてしまうことがあっても、もうどうにもなりません。とにかく、指ではなく「頭」で覚えるのです!!!絶対に!!♪♪♪ すべては「頭の中次第」ということは、細かいパッセージがでてきたとき。よく、”途中でつっかえてしまう”とか”指がもつれてしまう”という方がいらっしゃると思います。そういうときには、指よりも先に、音程はともかく、口に出してそのメロディの”ドレミ~”を言ってみてください。すらすらつっかえないで、流れるようにスムーズに言えるようになるまでです。そうなってから弾くと、何もその間に指の練習はしていないのに、たちまち弾けるようになるのです。本当ですよ。とにかく頭の中がしっかりとしたら、弾けるようになっているのです。指より、頭です。 口で言えないものは、弾けないのです。っということは、口で言えれば、弾けるのです。♪♪ また、もうひとつ。 みなさんの中で「教本&小さい曲&メインの曲」というセットで、勉強なさっている方がいらっしゃると思います。そういう方は、おそらく家での練習は、教本を一番最初にやり、次に小さい曲。一番最後にメインの「曲」という順でなさっていることと思います。 もちろんそのやり方は良いのですが、でもいつもその順でしかやっていないのなら、ここで提案したいと思います。 みなさんが人前で演奏するとき、まさか舞台上で教本から順に追って弾くことはできません。たとえ、リハーサルから本番での自分の出番まで、どんなに時間があいても、本番ではその曲しか弾くことはできないのです。 もしみなさんが普段の練習で、教本からスタートという順番でやっているとしたら、メインの曲を練習するころには、教本→小さい曲とやってきていますので、それなりに指は動くと思います。でも、本番では、時間がどんなにあいていても、その曲をいきなり弾くのです。”まだ何もその日弾いていない”ような状態でも、普通にいつも通りに弾けなければならないのです。 そこで私が提案したいのは、普段の練習の一番始めには、”まだ何も弾いていない”状態でそのメインの曲を弾いてみてほしいのです。そのときに、たとえどんなにボロボロでもかまいません。そういう経験を自分にさせることが重要なのです。このやり方を始めると、おそらく最初はあまり上手くは弾けないと思いますが、回を重ねることで、それも上手になってくると思いますし、本番でのこわさも減ります。 それから、練習の基本はスケールや教本などをスタートにしていただきたいのですが、もうきちんとそういう基礎が”普通に”弾けるようになって、落ち着いたら、それをキープできるようにしていただきたいのです。言い方を変えれば、”指をつくっておく”ということだと思います。いつもスケール等の”準備運動”から始めていると、もし何日か練習ができなかったとき、一気に弾けなくなってしまいます。弾いていなくても、それなりに”動く”ようになっていると望ましいと思います。でも、そこへたどり着くには、かなりの年数がかかるかもしれませんが・・・。 いずれにしても、まずは「きちんと基礎ができる」ということが第一だと思います。私も最初からきちんと基礎をやれていたわけではありません。色々経験する中で、たくさんたくさん反省してその穴を埋める努力をしてきたのです。今すでに、”自分はぜんぜんダメです・・・(;;)”という方。今からでも遅くはありません。気がついたら、正すことです。あきらめて直そうとしないことが、いちばん良くないとわたしは思います。私もまだまだ発展途上です。がんばらなければ!!! みなさんも一緒にがんばっていきましょう!!♪♪♪
2005.10.14
コメント(0)
-
左手と”のばしの音符”と「休符」のおはなし。
みなさんは、教本や曲を演奏するとき、どのくらいのことを配慮できていますか?気を配れていますか? よくあるのが、”左手無視”です。私も昔昔昔はこういう時代もありました・・・反省・・(^^;。左手無視とは、左手はあくまでも右手のおまけであり、右手が主導権をにぎっているっというような演奏のことです。これはピアノを習い始めの初期段階で、左手の重要性を教わらなかったのではないかと思います。”教わらなかった”とは、少し乱暴な言い方ですが、要は教え方の問題です。私も自分が習った記憶では、あまり左手!左手!!とは言われなかったと思います。初期段階の教本は、どちらかというと右手に主のメロディがあるものがとても多いです。もちろん左手がメロディで右手が伴奏っというものも入っていますが、大半の人は左手よりも右手の方がすぐに動かしやすいと思いますので、”早くピアノをすらすらと弾けるようになりたい!!”という気持ち+右手の動かしやすさが加わって、「右手主導」の演奏が多くなってしまうのだと思います。 あまりにも右手ばかりに気がいくようになると、左手が同時にどんなことを弾いているかは、その人の頭からはどこかに飛んでいってしまいます。要するに、”聞いていない”のです。ここで誤解しないでいただきたいことは、”聞こえている”のと”聞いている”のはまったく違うということです。”聞いている”というのは、きちんと内容に耳を傾け、頭で理解しながら聞いていることです。”聞こえている”のと”聞いている”のは、大きな違いがあるのです。 これらを防ぐには、一番良い方法は、何でも「左手」から練習するということです。初めてやるときから左手を先に取り掛かれば、まだ頭は新鮮ですし、先入観なく自然に頭に入ってくると思います。そのあとに右手に取り掛かれば、右手のことは放っておいても抵抗なく頭に入ってくると思いますので、もう右手さえやればそれは”完成”ということになります。もちろん「下地」の部分ですが・・。 やり始める同じ日に、左手も右手も両方やるのではなくて、最初の何日かは左手に徹底するのです。左手がきちんと弾けるようになったら、右手に取り掛かり始めるのです。左手をやっている間は、もしかしたらウズウズしてしまうかもしれませんが、先にみなさんがやりやすくて大好きな右手をやってしまうと、左手をやるころにはもうエネルギーは残っていません。そうなると余計に左手がおろそかになってしまうものです。ここはひとつ、ちょっぴり我慢して、先に左手を終えることが懸命だと私は思います。より良い演奏をするには、左手がしっかりしていなければならないのです。左手こそ大切なのですよ♪♪♪ 左手を大切に扱えないと、ある程度段階が進み、バッハをはじめとした様々な作曲家の曲を演奏する時にとても苦労します。たとえば、左手がメロディで右手が伴奏になっているものを演奏するとき、”左手を聞く”ことになれていないと、どうしても伴奏である右手の音ばかりが目立ってきこえてしまい、肝心の左手のメロディが隠れてしまいます。右手も左手も同等に、”聞こえている”のではなく、”聞くことができている”演奏にしたいものですね。 それからもうひとつ。 みなさんは、”のばしの音”をどのように扱っているでしょうか。まさか、伸ばすの音の鍵盤を弾いたとたんにもう次のことを考えてしまっていて、自分が何かの音を”伸ばしている”ことは頭からどこかに行ってしまっている方、いませんか?これも実はとても多くみかけるのです。 たとえば息を使って吹く管楽器は、演奏する本人が息を吸い、吐き続けなければ、音を何拍であれ伸ばすことはできません。弓を使う弦楽器も、自身が弓を動かさないことには、音を伸ばすことはできません。しかし、ピアノはどうでしょうか。本人がちゃんとその音を”想って”いなくても、指さえ鍵盤にのせたままにすれば、音は伸びています。(もちろんある程度の時間がたてば、聞こえなくなりますが・・) これがかえって、厄介でもあるのです。 みなさんに忘れないでいただきたいのは、音楽の基本は「歌」なのです。だから、和音であれ単音であれ音を伸ばすときには、それを考えた演奏をしなければなりません。具体的に言えば、きちんと音を伸ばすなら伸ばすなりに、その通り(=その旋律の通り)に心の中で、「歌って」いなければなりません。もし”歌って”弾いていないと、それはそのまま演奏にすべて表れてしまうのです。 そしてもう一つ。最も大切なのは、「休符」の扱いかたです。最も多いのが、休符のときはすべて”無しの時間”としていることです。休符があるときは、空白のように音楽のカウントさえしていないのです。音のあるところしか見ていない。これは、本当に多いです。 みなさん!!「休符」は、”休み”をあらわす立派な「音符」なのです。ただの穴埋めでテキトーに書かれているのではありません。休符は、数字の「ゼロ」と同じだと私は思っています。もし「1005」と書きたいとき、ゼロのところを空欄にして、「1 5」と書いたらどうでしょうか?これでは、いったい何なのかまったくわからなくなってしまいます。ゼロは、ほかの1や2や3などの数字と同じようにとっても大事な”数字”なのです。 だから、休符も音符を弾くときと同じように、またはそれ以上に大切に扱わなければなりません。休符を”すっ飛ばして”楽譜を読むことが、絶対にあってはいけません。それは、癖になってしまいますし、音楽の流れをとめてしまうことにもなります。 これらをすべて解決することができるのは、やはり教本でも曲でもそれと”はじめまして”の時からの「メトロノーム使用」に尽きると思います。具体的なより良い使用の仕方は、以前のブログ本編に書かせていただいておりますので、お知りになりたい方はぜひそちらをご覧くださいませ。 何はともあれ、より良い素敵な演奏ができると良いですね。私もがんばらなければ~・・!!!!
2005.10.13
コメント(0)
-
もし習い事を”やめたい”と言われた(または”思った”)時には・・・のおはなし。
みなさんのなかでピアノに限らず、人によってさまざまな習い事をしている方がたくさんいらっしゃること思います。 さて、いわゆる「習い事」といわれるものは数多くありますが、いったいそれらとどのように付き合っていったら良いでしょうか? もしお子さんが、習い事を”やめたい”と言ったら、どうしたら良いでしょうか。 私の考えでは、やはりこれはケースによると思います。やめたほうが良い場合もあるし、続けたほうが良い場合もあるのです。 まず「続けたほうが良い場合」についてですが、それはやめたい理由が”今やっている曲を好きでない”とか単に今やっていること(テクニック等々)が”できない”からっという場合です。私なら、おそらく「やめても良いけど、今やっていることができてからにして!」っと言うと思います。 ”習い事”とは言え、だれにとっても趣味でも専門でもそれなりの苦労や困難、乗り越えなければならないことがあるものです。”ただの習い事”とおっしゃる方もあるかもしれませんが、物事をそれなりにきちんと習得しようとすることはいつでもだれにとっても、”一筋縄ではいかない”ものなのです。 ちょっとここで原点にかえって考えてみましょう。みなさん自身が習う、またはみなさんがお子さんに「習い事」をさせる理由は何でしょうか? 一つの経験や教養になればっとの想いが圧倒的に多いのではないかと思います。習った本人がその道のプロを目指すかどうかは、二の次、三の次。まずはその子にとって、一つの経験となり、それを通して集中力や忍耐力、乗り越える力を養わせてあげたいのではないでしょうか。”やめたい”と本人が言っても、今やっていることをできるようにしてからやめても遅くはないと思いますし、乗り越えた結果、本人に気持ちがあればそのまま続けることでしょう。 ”できない”からといって、やめてしまうことは私としては大変もったいないことだと思います。私が昨年度に高校の音楽の先生をしていたときにも、自分がピアノをやめてしまったことにとても後悔をしている子が多かったです。習っていたときは、”いやになってやめた”というのが大半の人の原因だったようですが、大きくなってみたときにはそのことを後悔している子がとても多かったのです。自分は嫌になってやめてしまったけれど、友達がすらすらとピアノを弾いているのを見て、それを重ね合わせるのだと思います。自分もやめずに続けていたら、あの子のようになっていたかも・・・。というふうに。 その経験は、本人にとっては大げさな言い方かもしれませんが、”敗北感”や”劣等感”として心に残るようです。ちょっと肩身の狭い様子をしていました。 とはいえ、人には「向き不向き」もあるのです。ピアノより歌が向いている人、楽器を演奏するよりバレエが向いている人、音楽よりもスポーツが向いている人など、実にさまざまです。色々な人がそれぞれ得意なジャンルに取り組むことは、大変良いことだと思います。 おそらく”向いていない”場合は、先生にもわかるのではないでしょうか。また本人の様子からもわかる部分もたくさんあると思います。本人の意見もききながら、一番はそういうことがあったらまず先生にお話してみることでしょう。先生に遠慮して何も言わないことは、良いことではありません。習いごとは親子だけでやっていくものではありません。お母さん一人で悩まずに、是非そういうときには先生に遠慮なくお話になってみることをオススメします。そうすれば、より良い道が見つかると思いますよ。 いずれにしても、本人の様子をよく観察して、知ることです。好きなのかどうか。無理して”行かされている”のかどうか。本人にとってちょっと大変な時期なのか。乗り越えなければならない壁があるのか。それとも実は習い事とまったく関係のないところに問題があるのか・・・等々。 その判断は容易ではないかもしれませんが、本人のためになる選択をしてあげたいですね。お家とレッスンでは、また雰囲気が違うと思いますので、先生にレッスンの様子をうかがってみたり、家での様子をお話してみるなど、先生と色々なコミュニケーションをとってみると良いと思いますよ。
2005.10.12
コメント(0)
-
☆ピアノの上達のコツ!!!☆
ここではみなさん(&自分にも?)に向けて、ピアノを上達させるコツを書かせていただきたいと思います。 まずみなさん、ご自身の弾くときの姿勢を見直してみてください。何気なく練習していらっしゃる方いませんか?椅子の高さはもちろん、前のめりな姿勢や背中が曲がった姿勢で弾いているとか、片手練習のとき、弾いていない方の手を足の腿や椅子など、どこかについてしまっている方などなど、いらっしゃいませんか?おかしな姿勢で弾いている方いませんか? 特に弾いていると肩がこるとか、どこか痛くなったりする方!!!「普通に」やっていれば、どんなに長時間弾いても、肩が凝ったり、どこかが痛くなるということはありませんよ。一度、ご自身のピアノを弾く時の姿勢などを見直してみてくださいね。ポイントは、「おなかと腰+背中」で支えることです!♪ 次に、ピアノを弾くときの左足の位置です。弱音ペダル(一番左のペダル)を踏む場合はやむを得ませんが、そうでないときの左足はどこに置いていらっしゃいますか?まさか両足を前に投げ出すようにして伸ばしてしまっているなんてこと、ありませんよね。 (昔昔昔、私はこんなときがありました・・反省・・・・・・・) 右足は一番右のペダルに、踏む時の状態でかけておきます。そして、左足はどうしたら良いかというと、ペダルに用事がないときには、足をおしりの下あたりーーー椅子の下の真ん中あたりに引いておきます。引く深さの感じは、人それぞれの体に合わせてなさってください。 目安は、自分で”これで正しい”という位置に足が置いたら、そのまま足を一切動かさずに立ち上がってみてください。 もし両足が前に伸びていたら、立ち上がれませんので、演奏のときにフォルティッシモなどの場合に”ふんばる”必要があるときに、それができないっということがわかります。 (*説明がうまくなくてすみません。わからない方は、遠慮なくおっしゃってください。) 左足の位置は、椅子の高さと同じくらいとてもとてもとても重要です。左足が正しい位置に置かれていれば、それだけでテクニックの習得や演奏の向上に役立つのです。 次に大切なことは、ピアノを弾くに、手や指をなるべく”動かさない”ことです。 そう聞いて、”弾くのに指や手を動かすななんて、コレじゃ音がでないじゃないか~!!”っと思った方もいらっしゃると思います。確かに、なんらかの手や指を動かさなければ音は出ません。そうなのですが、ここで私がみなさんに申し上げたいのは、”必要以上に手や指を動かさない!!!”っということです。 あの大大作曲家のフレデリック・ショパンも、自分の弟子たちに『鍵盤はなでるように』っと言っています。 日本では、指をガチャガチャと”よく動かす”ことが良いという認識があります。そして、”鍵盤はいつでも一番下まで押さなければいけない”っという認識もあります。日本では98%くらいのお教室で、個人や大手に限らずこういう認識がされています。かく言う私も、昔はその認識での教育をされました。私が今もお世話になっている大学からの先生に習うまでは・・・・・です。 これらの認識は、まさしく「日本式」であり、実は「間違ったやり方」なのです。日本だけがやっているやり方、考え方です。クラシック音楽が生まれた西洋では、だれもそんなふうに弾いている人はいません。プロの方はもちろん、素人の方でもです。世界の演奏家(ピアニスト)、とくに一流の方をみても同様です。 私は今の先生に習ってから、本当にありがたいことに、”正しい方向へ”とたたきなおされました。このことは、自分にとって大変ではありましたが、とても良かったことだと思います。おかげで私にもこの正しい「本来あるべき弾き方&やり方」が定着しましたが、これは日本では一部でしか見られないと思います。それほどこの「日本式」が定着してしまっているのです。 私はこのブログのなかで、この指と手のお話は、実は書かないことにしようと思っていました。それは、”日本式”を日本式と思わずに育った方々が大半であるこの日本では、あまり理解していただけないと思ったからです。反論もあるかもしれません。でも、このブログで出会う方はみなさんピアノがお好きで、熱心な方が多くいらっしゃいます。日本ではこのまちがった”日本式”が「普通」のやり方として認識されていますので、もしかしたらほんの一部の方にしか理解していただけないかもしれません。でも、少数の方でも良いので、少しでも多くの方に”そうなのか~”と、この誤解にはまらないでいただければと思い、書かせていただきました。 ぺこり。 さてさて、本題に戻りましょう。 続いての大切なことは、ペダルの踏み方です。バタバタと音をさせながら踏んでいらっしゃる方、少なくないと思います。しかも、大抵はご本人さまは気づいていません。ペダルを踏むときに、バタバタと音を立ててしまうと、見かけはもちろん、その音も演奏に交ざってしまって、観客のみなさんに聞こえてしまいます。ペダルをふむときは、何もそんなに足を上げなくても十分にその機能を果たしてくれます。みなさんも、ペダルは置いた足のままで踏むようにしましょう。わざわざ足を上げてから踏む必要はありませんよ。 さあ、ここからは「レッスン」に直接関わってくるお話です。 まず練習の際に、次のレッスンまでの日々の予定を立ててみてください。具体的に言うと、次のレッスンの”前々日”にその予定が完了することをめがけて立てるのです。次のレッスンに行くときには、「こんなふうになっていたい」という完成予想図をつくります(←頭にえがきます)。そうすると、レッスンを終えたつぎの日からレッスン前々日までにやるべきことが見えてきます。ここでもし、”前日”を目標にして予定を立ててしまうと、大抵の場合やはり実際は”前日”までかかってしまいます。なので、ちょっときつめに&でもその分の余裕をつくっておくのです。 毎日の練習で、その日いったいなにを練習するか、どんな練習をしたら良いのか。これがわからないと結局行き当たりばったりのレッスンになってしまいます。どうか成り行きで進んでしまうのではなく、ある程度はきっちりと予定をたてて進めていくと、上達が早いと思いますよ!! それからもう一つレッスンで重要なことは、一度言われたことは次のレッスンでも言われないことを心がけることです。これを念頭に置くのと置かないのとでは、雲泥の差がでます。みなさんの先生だって、生徒さん一人一人のために一生懸命レッスンをしてくださっているのです。せめて、一度言われたことは次のレッスンでも同じことを言われないように、それぞれの人が気をつけるべきだと思います。 しかし、私たちも「人間」です。一度言われて早くに解決できることもあれば、そうでないこともあります。レッスンのときには、”なるほど、そうか!”と思っても、家でやっているうちにわからなくなってしまうこともあります。難しい技術の場合はとくにそうだと思います。そういうときには、”2週連続”まではOKっというふうにすると良いと思います。ただそれはもちろん、自分なりの試行錯誤をした上でのことです。まったく手をつけずに次のレッスンに行くのは、良いことではありません。言語道断です!!! レッスンで、質問や自分の困ったことなどを先生にお話することはとても良いことです。でも、それを言うためには、自分はどこができていて、どういうものができないのか、どういうふうになっちゃうのか、どこはわかっていて、どこはわかっていないのか・・・。これらを自分でわからないと、質問もなにもできません。どんなレッスンを受けるのでも、受ける側がその人なりに努力をしなければ、前に進むことはできないのです。これは、ピアノだけでなく勉強にも、ほかのすべてのことにも共通することだと思います。 また、ここで特に申し上げたいことは、ご自身が練習するなかで、いつも間違えてしまう箇所や苦手なパッセージや音楽的な表現などがあると思います。そういうときに重要なのは、それがたった1回や2回できたからと言って、すぐ次のことに移らないことです。2回や3回できただけで、”あ、もうできた”と思い、次にいってしまう方、大変大変多くいらっしゃると思います。でも、それでは絶対に上達しません!! ここで大切なのは、2回や3回などではなく”眠っていても”できるくらいまでーーーつまり、「安定」するまでやり続けることです。2、3回は、「できた」うちには入りません。あくまで”できるための一歩進んだ”に過ぎないのです。 また、このときにたとえば”100回やろう!”などと回数を設けることはオススメできません。回数を設定して目標にしまうと、回数をこなすことだけに目がいってしまって、結果的にはきちんと「音」を聞けていないということになってしまいます。 私がおすすめする方法は、”1分”とか”2分”というふうに時間を設定するほうが効果的だと思います。もちろん、設定したその時間内は、ずっと”止まらずに”やり続けるのです!! または、携帯の時計をみながら、”○分になるまでやる”というふうにしても良いと思います。 いずれの方法をとるにしても、最初に設定した時間数では達成できなかったら、かならず延長して行うことです。安定してきちんとできるようになるまで連続して続け、途中で止まってしまったり、指がもつれたりしないように続けてさらうこと(=練習する)が大切です。 このやり方をすると、ある程度までいくともうずっとこれを自分は一生やっていられるんじゃないかっと思うくらい、ラクに普通にできるようになります。マラソンで言う”ランナーズ・ハイ”のようなものだと思います。そこまでやれたら、もう「安定」したと言って良いと思います。そうなったら、もうその練習を一生しなくてもいつでもどんなときでも”できる”ーーーつまり「習得できた!!」ということになります。 そして、今回のブログの最後の一つです。 みなさんが家で練習するときには、間違った音のまま先に進んではいけないし、リズムがおかしくても指がもつれそうになっても、そのまま素通りで弾くことはいけません。 ですが、本番ーーーつまり人前で演奏するときは、別です。演奏会や発表会など、人前で弾くときには絶対に弾きなおしてはいけないし、”しまった”や”間違えた!!”という顔もしてはいけません。ポーカーフェイスを保つことです。なぜなら、観客のなかであなたがミスをしたその一瞬に、頭がどこかにいっていて聴いていなかったかもしれません。それなのに、あなたが”やってしまった~”という顔をしたら、その観客はあなたの顔をみて、「なにかやってしまったのかな」と思ってしまいます。 なかには、”私が今さっきまちがったことは、自分でもきちんとわかっていますよ。ちゃんと知っていますよ!”という意味で、そういう顔をする人もいます。でも、それをする必要はまったくないのです。そういう顔こそやってはいけないのです。観ているお客さんにとっても、それは”美しい”ことではありません。 今回もまた色々と書かせていただきましたが、少しでもみなさんの参考になるところがあれば嬉しいです。みなさんも、いっしょにがんばりましょう~!!!♪♪♪
2005.10.11
コメント(0)
-
今までのピアノを通して ~私のおはなし~
ここではちょっと私の小話を書かせていただきたいと思います。すみません。 これまで私がピアノをやってきて感じることは、習い事は指導者によって教わる側の”その後”が大きく左右されるということです。 私のピアノの始まりは、テレビをみて自分もやってみたいと思い、それを親に話したことから始まりました。(*私が見たテレビは堀ちえみさんが主演していたドラマで、たぶん「スチュワーデス物語」の一つ前くらいのドラマだったと思うのですが、自分が3歳くらいだったので今となってはそのドラマの正しい題を知りたいと思っています。どなたかしっている方、教えてください~!ドラマの内容は、本当は悪者なんかではないのに、ひたすら堀ちえみさんが周囲の人たちから”悪者”にされてしまって、牢屋に入ったりするのです。あー、少ししかわからなくですみません。) さて、話を元に戻しましょう。 私は某大手音楽教室へ入りました。そのことは、良かったところもたくさんありますが、そうでないところもあったと、その後感じることとなりました。 そのお教室では、グループレッスンや個人レッスンなどさまざな授業を受け、お友達もできたり本当に色々な経験ができたと思います。プラスになった部分がたくさんあったと思います。ですが、その後音大へと進む道を選んだ私にとって重要な「技術」の面で、大変苦労することとなりました。これは、私がそんなに練習熱心ではなかったことが原因かもしれませんし、一般的にみてどうなのかはわかりません。。。 私は、グループレッスンで音楽の色々な面での楽しさに触れることができた一方で、技術面では幼いときにそれほど”厳しく”育てられなかったと強く思います。 私は大学に入り今現在でもお世話になっている先生に師事し始めたとき、今まで自分が受けてきた”ピアノ”が、いかに「日本的」であり「まちがっているか」を思い知らされました。その先生から私は、本当に多くのことを根本から教え直していただき、本当にとても感謝しています。 私はその先生には大学からお世話になっていますが、当然ながら、ピアノの習い始めからその先生についているという人もいるわけです。そういう人たちは、”日本的でない&本来あるべき音楽の姿”のままとても自然に演奏をしていて、とてもうらやましく思いました。その方たちは、当然私なんぞと比べれば、幼い頃に私以上に”良い意味”で「叩き込まれ」たおかげで、きちんとした”正しい”基礎が身についています。 音楽専門に進んだ私にとって、きちっとした”正しい”音楽の仕方を教えてもらわなかったことは、とても大きな代償でもあったと思います。特に大学のときには、そのことを痛感しまくったという感じで、苦労しました。幼いとき、自分ももし今の大学での先生に教えていただいていたら、きっとそのときは大変だっただろうけど、それでも良いから自分もそういうふうにきちんとしたものを最初から身につけたかったと強く思いました。 今では、自分が実際に進んできた道があったからこそ、色々な意味で「今の私」があると思いますので、私はわたしなりに少しでもその穴を埋められるようにと勉強を続けているところです。 今の世の中には、習いごとでも”苦しいことはしたくない”、”ちょこちょこっとやって、イイトコ取りができれば良い”っという考えの人もとてもたくさんいます。私は、そうおっしゃる方の心の中もわかります。習いごとには、求めるものが人それぞれだと思いますので、そういう方はそういうふうにやってくださるお教室へ行かれれば良いと思います。そういう需要よ供給があるのですから。。 しかし、私自身は、そのやり方ではその事の「本当の楽しさ&すばらしさ」を知るには到底及ばないと思います。はっきり言って、中途半端だと思います。もちろん、そういう”イイトコ取り”のやり方をのぞむ人は、それで良いのです。色々な考え方をお持ちな方が集まって、この世界が形成されているのですから。 でも私は、”イイトコ取り”のやり方には反対なのです。これはあくまでも、私の意見です。あしからず。 お教室の中には、曲は”耳で覚えさせて、ご本人は楽譜を読めるようにはなっていない”というやり方でレッスンを行っているところが少なからずあります。そういうやり方の方が導入や初級のうちは、もしかしたら手っ取り早いのかもしれません。生徒さんも”耳コピー”をやっているだけですので、生徒さんがすでに知っている曲をやれば、確かにラクかもしれません。 でも、このやり方で通してしまうと結果、すでにしっている聞いたことのある曲しか演奏できないということになってしまいます。その生徒さんは、楽譜が読めないのですから・・・・。 ”イイトコ取り”は、やっているそのときはラクで良いかもしれません。でもそれは、本当の意味ではラクではないのです。 以前、私がこのブログを始めたばかりのときにもこのあたりのお話を書かせていただきましたが、何年ピアノを習っていても、楽譜が読めないままであるということは、本人にとってこれほど気の毒なことはありません。 音符やリズムを読めるようになることは、決して難しいことではありません。”楽譜恐怖症”のみなさん、楽譜をおそれすぎです。私が専門でやっているから簡単だと言っているのではなく、本当にむずかしくはないのです。どんな方でも、必ず覚えられます。音譜の読み方やリズムの読み方ーーー要するに「楽譜の読み方」は、一度覚えたならばあとは一生使えます。覚えさえすれば、どんな難しい曲もご自身が読んで演奏することができます。”耳コピー”で行うより、よっぽど簡単でラクだと思います。”耳コピー”の方が、かえって難しくなってしまうような気がします。 なにを習うにも、どんな先生と一緒に勉強するかはとても大切です。私にはそのことが痛いほどよくわかります。苦労するのは、自分です。どうかみなさんも、より良いお教室選びをなさってくださいね。もちろん、私のお教室でもいつでも募集しております。参考までに。。
2005.10.09
コメント(0)
-
”習い事”へのたいせつな心構えのおはなし。
私が今までの様々な経験を通して感じたこと、これはとても大事だなっと思ったことを書きます。 私がこれまで”生徒”として&教える立場になった者として感じることですが、「習い事」に限らず人にものを習うときに大切なのは、〔素直さ〕です。 これがないとどんな素晴らしい力を持った指導者がいても、受ける側がそういう心を持っていないと良い結果は生まれません。 〔素直さ〕とは、具体的にどういうことかと言うと、たとえば”今度はこんなふうに練習するといいよ”とか、”こういうやり方はよくないよ”など。先生が生徒さんに言ったとします。そのとき、生徒さんが自分の我を通してしまい、”そんなこと言われたって、そんなふうになんかやりたくないよ”とか”そんなこと言われたって、このやり方がいいに決まってるんだ!”などと思ってしまって、聞き入れないーー受け入れないと、その生徒さんはもうそれ以上上手くなりません。ある程度までは上手くなるでしょうが、もうそれ以上にはなりません。 良い「指導者」は、それなりに経験を積んでいますので、生徒さん一人ひとりの現在&将来を見据えて指導してくださっているものです。その”先輩”の言うことを聞かずに進んでしまうと、その生徒さんにどんなにすばらしい才能があっても、その才能を開花させることはできません。 上手になる人は、レッスンの受け上手なのです。先生に言われたことを、”そうなのか!!”と素直に聞き入れ、実行する。これはマラソンの高橋尚子さんを育てた小出監督もおっしゃっていることです。私も本当にその通りだと思っています。 そしてもうひとつ。習いごとをするのに必要なことは〔謙虚さ〕です。上記のほか、この心もないと良いものはできません。 〔謙虚さ〕とはつまり、たとえば何か曲をやるのでも、”こんなのこういうふうにやればいいんでしょ!”とか”こんなのへっちゃらだ。簡単だぁー”などと軽視してのぞんでしまうということです。そういう心は、とくに演奏に現れてしまい、とても見苦しいものです。また、作曲家に対して大変失礼なことでもあります。 どんなに自分が上手くなろうとも、〔素直さ〕と〔謙虚さ〕を忘れずにいたいものですね。芸事は奥が深いですから、長い時間かかります。「これで完成!!」というものはないのです。自分の人生を豊かにするためにも、すきなことは長く続けたいものですね。
2005.10.09
コメント(0)
-
私が考える”ピアノレッスンにおいての親御さんの望ましいお子さんへの対応”のおはなし。
今回は、ピアノレッスン全体においての私が望ましいと思う親御さんのお子さんへの対応について書かせていただきたいと思います。 たとえばここでお話したいのは、主にお子さんが家で練習しているときのお母様のお子さんへの対応の仕方についてです。 お母様自身が音楽に素人の方でも、また音楽をなさっていた方でも、どちらの場合にも起こることだと思いますが、たとえばお子さんがお家で練習しているときに、お子さんが明らかに間違っている音を弾いているとかリズムがまちがっているとか、お母様が気づいた場合に、お子さんに向かって、”音が違うでしょう!”とか”リズムが違ってるよ!”とか”メトロノームを使うんじゃないの?”などなど。色々と「先生」に代わって言ってくださっている方が大勢います。 ですが、私は実はこれは必要ないと思っています。 お子さんは自分の親とピアノの先生では、お子さん自身の中でやはり”ポジション”が違うものです。よく、同じことでも親に言われると反発して、他の大人(先生や親の友人など・・)に言われると素直に聞けるっということがあるでしょう。 年齢の発達に応じて、子どもが”よく反発する”時期というものがあるのです。それはあって当然のことなのです。 たしかにお子さんが間違った音で弾いているのを無言で聴いているお母様には、かなりの忍耐が要ることは私にも十分に想像できます。しかし、ここでお子さんに”チェック”の言葉を言うことは逆効果なのではないかと思います。 先ほどお話した”反発”のこともありますし、またお子さんの中ではピアノの先生以外からも”言われて”しまうと、お子さんにとってはおそらくどちらもそれぞれ大切な存在だと思いますので、「自分はいったいどちらの言うことをきいたら良いのだろう・・・」と二者択一を迫られることになってしまうと思います。たとえ「ピアノの先生」と「お母様」のおっしゃる内容が同じだったとしてもです。 それに、家でもあれこれ”注意”されていたら、いつもお母様の反応を必要以上に気にしてしまうかもしれませんし、また自分は何も考えなくてもお母様が注意を言ってくれますので、本人は自分は考えなくでもいいんだ!っと思ってまうこともあると思います。 何も言われなければ素直に言うとおりにできていたことも、おうちで”言われる”ことで反発もてつだって意地になって「やらない」ということになってしまったら、本末転倒です。 それに、ちょっと考えてみてください。 もしあなたが一生懸命やっていることに対して、自分より経験のない誰かに”知ったよう”にダメだしされたら、ムッとしませんか?反発したい気持ちになりませんか?しかも、その内容があなたにとって”図星”なことだったら、なお更その人の前ではやりたくないっと思ったりしませんか? 自分がやっていることに対して、それを教えていただいているその道の「専門」の方に言われるのと、まったくの素人に言われるのと、感じがちがうと思いませんか? たとえば、ご自身のお仕事のことを、ど素人の方に何か知ったようなことを言われたら、とても嫌な気持ちになるでしょう。それと同じだと思います。 子どもだって、同じ人間。どうかお互いのために良い方法を取りたいものですね。望ましいのは、大変でも、お子さんが家で練習しているときに、お母様(またはご家族のみなさま)はお子さんがどんなに音を間違って弾いていても、リズムがおかしくても、なにもおっしゃらないで頂きたいのです。あくまでも、”先生”と”お子さん”の間のやり取りであって欲しいのです。そして、お子さんが前よりも上手になったなっと思ったら、”上手になったね~”と褒めてあげる。これで十分だと思います。 またもう一つ重要なことは、もしおうちでお母様がお子さんの手助けをしてしまうと、お子さん自身の本当の力が「先生」にはうまく伝わらなくなってしまいます。お母様が家で手助けした結果でレッスンに行っていると、その力をその子本来の力なんだなっと思われてしまいます。こうなってしまうと、とても危険です。その後の方向性や選曲など、さまざまな点で歯車がくるってしまうことにもなります。 たとえどんなに下手でも、音が間違っていても、親御さんは恥ずかしがらずに”そのままの姿”でレッスンに通わせてあげることが、私は一番その子のためになると思います。音が間違っている練習を聴き続けるのは、おそらくかなりの忍耐が要ると思いますが、このほうが本人のためになると思います。 以前私は、ピアノ教室を”病院”にたとえるなら、「先生」は”お医者さん”で、「お母様」は”患者さんのお母さん”、「習う本人」は”患者さん”である。この3人の連携がうまくいけば、その生徒さんは上手になる。”患者”さんには「治ろう!!」とする強い意志ーーーピアノで言えば「上手になろう!!」という強い気持ち。お母様には、”患者さん”---つまりはお子さんの心のケアをしてあげる。そのことがとても大切であるっと書きました。 このことを考えたとき、”お医者さん”ではない素人が、”患者さん”に向かって横から何かを「言う」ことは、とても危険であることがお分かりいただけるのではないかと思います。 ”すこしでも何か手助けしてあげたい”、”少しでもその子のためになることをしたい”っと思う親御さんのお気持ちはよくわかります。ですが、”してあげる”ことだけが、その子のためになるのではないと私は思っています。一歩ひいて見守ることも、十分お子さんには伝わるのではないかと思います。 私はどの子にも、「自分で考えることができる」人になってほしいと思っています。日本は物にあふれていて豊かで、あまりにも暮らしが便利になったおかげで、あまり自分で考えなくてもなんとなくやっていける様になってきてしまったように思うのです。”自分で考えなくても、だれかが考えてくれる。”、”自分では考えなくても良いようになっている”---これでは、その人にとって決して良い環境とはいえません。子どものときから”自分で考える”ことが自然になっていれば、その後の人生にもきっと大きく役に立つのではないかと思っています。 それに近づくためにも、まずは見守ってほしいなっと私自身は思います。
2005.10.09
コメント(0)
-
”緊張”とのつき合い方のおはなし。
みなさま、いつもわがブログにご訪問いただき、大変ありがとうございます。みなさまのコメント等を読ませていただくと、とても励みになりますし、毎日何か少しでもみなさんのためになることを書こう!!と意欲が湧いてきます。今後もどうぞよろしくおねがいいたします。ぺこり。 さて、みなさんのさまざまなコメントの多くに、「レッスンに行くと緊張してしまって、なかなか思うように弾けない」という意見が書かれています。 私もそのお気持ちはよくわかりますし、レッスンに通い続けている現在でも、やはりレッスンでは緊張はします。 緊張は、まったくしないよりは少しはした方が良いものです。まったく緊張感がないというのは、良い演奏につながりません。しかし、体がコチコチに硬くなって、どうかなってしまいそうなくらいに緊張するのは良いことではありません。もしそうなってしまっても、ご本人さまはそうなろうと思ってなってしまっているわけではないので、どうすることもできないっという感じでしょう。私も緊張しずぎて、失敗した経験があるので、お気持ちはよくわかります。 人前で演奏する以上、”緊張”とは離れられないと思います。一流のプロの演奏家でも緊張はする!!ということからも、よくわかるのではないでしょうか。 私たちのしている”呼吸”と精神は、とてもつながっています。私たちは眠っているなどリラックスしているときには、ゆったりとした呼吸をしています。また、50メートルなど走ったときは神経が興奮していますので、速い呼吸になります。 私が大学生のときに、こうすれば緊張しても”自分らしい”良い演奏ができるなと発見した方法があります。 ”呼吸”が精神と直結していることは、先ほど書きましたが、要するにそのへんをうまくすれば良いのです。 私があまりに緊張しすぎて”大失敗”したとき、私は上手く呼吸ができていませんでした。具体的には、息を胸のところでばかり吸ってしまって、全然おなかまで息がいかなかったのです。これば、体の中に十分な酸素が行き渡るのを妨げてしまいます。この経験から、本番の数日前、または前日でも良いので、夜寝る前に「腹式呼吸」を何度もするのです。腹式呼吸とは、寝ているときにしている呼吸で、息を吸うとおなかがふくらんで、吐くとおなかがへっこむという呼吸です。赤ちゃんが寝ているのを見ると、その様子がよくわかると思います。 さてやり方ですが、まず鼻から”もうこれ以上息を吸えない!!”というくらいまで5秒間かけて十分に息を吸います。上手く吸えない場合は、あごをひくと良いと思います。次に今度は、口から”もうこれ以上息を吐けない”というくらいまで十分に息を10秒間かけて吐きます。 これを10回または5分くらい続けるとよい睡眠をとることができます。 そして、問題の当日ですが、朝からいつでも気がついたときには息をきちんとおなかにいれるようにして、ひたすら出番のときまで”腹式呼吸”をすることです。私の経験上、息を変わらずすっと直前まで十分におなかに息をいれての呼吸ができているときは、演奏も上手くいきます。逆に、息がおなかに入っていかず、胸のところでしか呼吸できないというときは、まず上手くいきません。 本番で、またはレッスンでも自分の思うように”自分らしい”演奏をできるようにするためには、1にも2にも「練習」です。練習が十分にできていれば、自信もつきますし、落ちついて演奏するのに一歩一歩近づくことができます。 ですが、わたしたちも”人間”です。どんなに練習しても、まったく緊張しないっということは、普通はあまりないと思いますし(まれにあるかもしれませんが・・・)、「ほど良い緊張」のなかで演奏したいものです。 どんな素晴らしい練習をしたとしても、最後は「心(=気持ち=精神面)」です。いろいろな経験を踏まえて、私はより強くそう思います。どんなにすばらしいテクニックを持っていても、”心”のない演奏は人を感動させません。またテクニックはそこそこでも、”心”のこもっている演奏は人を感動させるのです。”心”がこもっているかどうかーーーこれは観客にかならず伝わるものです。”テクニック”が先行してしまいがちな日本人の演奏は、「機械的である」といわれたりもします。テクニックがあるだけでは、良い演奏にはなりません。 みなさんも、”ほどよい”緊張感をもって「自分らしい」演奏ができると良いですね。レッスンでも発表会など、人それぞれの経験ができてくると思います。たとえ上手くいかないことがあっても、そこで「今までしらなかった自分の新しい一面」をしることができ、それに出会うことで成長していけるとも思います。”失敗”は、わるいことではありません。”失敗”なくして「成功」はありません。色々な自分を知ることで、本番のことやそれまでの取り組みのことなど、”今度はこうしてみよう”と思えるのです。こうして”まちがった解決法”が一つ一つ減っていくのです。上手くいったときには、自分を褒めてあげるとともに自分のやり方への再認識&再確認をし、上手くいかなかったときには、どうか逃げずに、反省することろは反省して、”こういうところが良くなかったな”とか”ここはよかったな”などと自分のしてきたことを冷静にみて、かならず次に生かすようにすると良いと思います。 成長するには、「段階」があります。1からいっぺんに100になることはありません。かならず、「経験」が必要なのです。色々な面で試行錯誤しながら、より良い”自分らしい”演奏ができるようになれるとよいですね。失敗したときに、冷静に落ち着いて、自分の良かったところ&もっとこうすれば良くなる点を見つけ、「失敗した」と自分を責めないことが大切です。どうかプラスに考え、前向きに取り組むことが大事だと思います。必要以上に自分を責めたりしてしまうと、かえって逆効果になってしまうと私は思います。あまり深刻にならないことですね。 みなさんも、めげずに思い切ってがんばっていきましょう~!!!
2005.10.08
コメント(0)
-
レッスンで行き詰ったとき・・・ のおはなし ~”先生”と”生徒さん”の関係~
みなさんはピアノ(または、他の楽器でも。)をやっていくなかで、なかなか思うように教本なり曲ができず、”次のレッスンは気が重いな・・・・”と思ったことがありませんか? だれにでも人間ですから、上手くいっているときばかりでなく、なかなか上手くいかないときがあるものですが、みなさんはこういった場合、どのようにしてきたでしょうか? 私も今まで20年くらいピアノをやってきて、決して順風満帆ではありませんでした。私にとって相性がよくない先生に5年間(中学1年~高校2年生)も習っていたこともありましたし、レッスンの中でもなかなか”できない”こともありましたし、与えられた課題が”できなすぎて&よくわからない”ために、次のレッスンに行きたくないな~・・・・・・と思うこともたくさんありました。 なので私は、現在はピアノの先生をしておりますが、生徒さんがそういう状態で来ても私自身はまったく迷惑ではありません。怠けていて”できない”のではなく、自分なりに一生懸命やっているけど”出来ない”という場合はです。 *怠けが原因は、困りますが・・・。 とは言っても、”できない”ことが原因でレッスンをお休みするのはいけないことだと思います。はっきり言ってそれは「逃げ」です。そしてそれは何も言わなくても先生にもわかります。(”きちんとした”先生ならば・・・です。) 私はどんなに”できない”せいで行きたくなくても、実際に”行かなかった”ことはありません。もしそこで休んでしまったら、次のレッスンが行きづらくなりますし、何よりその”解決方法”を教えてもらっていないわけですから、ひとり悶々をした日々を送らなければなりません。 生徒さんは、「もしかしたら、できていなければ”怒られる”かもしれない。」---というふうに思いますよね。たしかにそうかもしれません。でも、よく考えてみてください。怒られるときって、どんなときなのでしょう。 怒られる原因は、”怠けた”ことが原因でそのことが”できていない”ときだと私は思います。ただ”できていない”ことだけで怒っているわけではないと思います。 あなたが”できていない”とき、それが怠けではなく、自分なりに一生懸命練習したけど、なんだか自分ひとりで練習している間に、よくわからなくなってきてしまったっというのなら、そのことをぜひご自身の先生にお話してみてほしいと私は思います。 ”いやぁ、なんだか先生にそんなこと言うのは、気が退けるよ・・・”っという方。私はそう思う必要はないと思いますよ!!! たしかに先生とは”お友達”ではありませんが、私はそれでも節度を守りながらも、本当に思っていらっしゃることをお話になれる関係が望ましいと思います。でもそれって、その先生との「相性」&その先生がどんな人であるか(=お人柄や思考等)に大きく関わってくると思います。 今みなさんの「先生」でいらっしゃる方々も、昔はだれかの”生徒”さんであったはず。先生も過去の色々な経験をお持ちですから、相談してわかっていただけることも多いのではないでしょうか。 私が”合わない”先生と過ごした5年間は、本当に毎週ではなく毎日が辛かったです。私の年齢が中学1年~高校2年生にかけてっという、多感な時期であったこともあるかもしれません。 その”合わない”先生とのレッスンでは、私は「(レッスンが始まる前の)おねがいします」と「(レッスンの最中の)はい」と「(レッスンが終わったときの)ありがとうございました」ーーこの3つしか話せませんでした。とにかく怖くてなにも自分が思っていることなんて言えませんでした。その先生と私は”良い関係”とは、ほど遠かったと思います。 その後私は、高3になる直前に先生を変えることができ、おかげさまで次の先生とは本当に相性がよく、節度を守りながらも言いたいこと(=聞いてほしいこと)を言えるとても仲良しの関係になりました。今でもとてもお世話になっていますし、とても感謝しています。 私がこれらの経験をして感じたことは、やはり基本は「人間同士」であるということ。だから、自分が相手に本当に伝えたい、知ってほしいことは、たとえはずかしくても言いづらくても、きちんと伝えることです。理解ある先生ならば、それを話した生徒さんの心情も理解し、むやみに怒るなんてことはしないはずです。私も上記の”相性の良い”先生に師事するようになってからは、”こんなこと聞いたら(または、”言ったら”)バカだと思われるかな・・・”と思いながらも、質問したり気持ちを言ったりしましたが、一度もバカとは言われませんでしたし、(^^;)そういったことを相手との間で乗り越えることで、「良い関係」が形成されていくのだと思います。 たしかに、なんだか気が退けて”言いづらい”っというお気持ちはとてもよくわかります。でも、”言わない”ことには何も始まりません!! もしそれが原因で、レッスンが生徒さんの気持ちと全然違う方向に進んでしまうことがあったら、一番困るのは生徒さん自身ですし、それでピアノに行くのが苦痛になってしまっては本末転倒だと思います。それは、とても悲しいことですよね。 私は現在では上記の”仲良しの”先生には「ピアノ」は習っておらず、音大からのお付き合いである東京の先生にピアノを引き続き習っています。その先生とも、良い関係で、自分なりにがんばって練習したけど、どうしてもここがよくわからない、またはうまくいかないなどなど。そういうことがあったときには、私も言うようにしていますし、私が自分の考えや気持ちを伝えることで、先生のわたしに対する理解も深まりますし、いつも”言ってみてよかったな~~!”という気持ちになってレッスンを終えます。 生徒さんが質問等をすることは、お互いのために私は、絶対に必要だと思います。最低限、「人」としての節度さえ守れば、あとは先生と良い意味で”仲良く”なって、良い関係を築けるととてもよいと思います。 先生も人間ですので、色々なタイプの方がいらっしゃいます。みなさんも良い先生をめぐり合えると良いですね。
2005.10.08
コメント(2)
-
”曲順”のおはなし。
みなさんはお好きな曲がたくさんあると思いますが、そのなかでどんな順に選んで勉強をなさっていますか? わたしたちが「曲」を選ぶとき、まずご自分の”気持ち”だけで選んではいけません。「曲」には難易度もさまざまであり、その時々に適した(=レベルに合った)選曲があるはずなのです。 クラシック音楽をやるなら、まずバイエルのような基礎的な「教則本」を勉強します。そしてそのレベルにあった無理のない「曲集」をやることをおすすめします。 それがある程度進んできて、少し曲らしい曲をやれるようになったとき、ここからが特に大切です。 クラシック音楽において、「バロック」時代の音楽が”基本”です。バロック時代に代表されるのは、J.S.Bach(バッハ)やヘンデル、ヴィヴァルディなどの作曲家です。とくに絶対にはずせないのが、J.S.Bach(バッハ)です。バッハなくしては、クラシック音楽は語れません。なぜなら、バッハに続く作曲家たちは、みなバッハの曲を勉強していて、その上でそれぞれの作曲家の世界を創っているからです。 バッハは、自分の子どもたちを含めた弟子たちのために勉強用の「曲集」等を書いています。その代表と言えるものが、『インヴェンション』『シンフォニア』『平均率クラヴィア曲集』が挙げられます。もちろんそのほかの組曲や協奏曲やオルガン曲など、勉強しようと思ったらきりがないくらい素晴らしい作品がたくさんあります。ですが、いずれにしても”ピアノ”を勉強する者にとって、『インヴェンション』『シンフォニア』『平均率クラヴィア曲集』は、欠かせない教材です。また、名曲もたくさんあります。これらの曲を勉強すると、バッハのさまざまな”工夫”や”ひっかけ”、”わな”があり、それらを発見するのはとても楽しい作業です。とにかくバッハを勉強ることは、大変勉強になるのです!!!!! お弾きになりたい曲の時代は、色々だと思いますが、バッハを筆頭にバロック→古典派→ロマン派→近・現代へとお進みいただきたいと思います。 近頃は、楽典(=音楽理論)などもきちんと勉強したいとおっしゃる方が増えてきました。そのことは、大変素晴らしい、良いことだと思います。 音楽を勉強する上で、理論や時代のことなどを知ることは大変役に立ちます。また本来は、趣味でも専門でも関係なくこれらの音楽の基本(=理論&時代のこと)は、”知って”いる上で「曲」を勉強することが正しいとも思います。ですが、実際のお教室ではそこまでしないところが大半だと思います。 たしかにそれらを知らなくても「曲」を弾けないわけではありませんが、でもやはりそれだと”限界”がくるとも思います。なんというか演奏が、空虚のようになってしまうのです。 私自身は、やはりより多くの方に「音楽」に関する色々なことーーーつまり、音楽理論や時代等のことなどを知っていていただきたいと思っています。なので、わたしのお教室では、それらにも触れていき、バランスのとれた演奏になっていただきたいと思っています。理論等は、様子をみながら進めていき、時代等については折に触れて生徒さんには説明などさせていただきたいと思っているところです。 なにはともあれ、音楽は「楽しい」ことがいちばんですね。それを何より忘れずに、より良い演奏につなげられると良いですね。
2005.10.07
コメント(0)
-
”第1楽章”のおはなし。
みなさんのなかで「ソナタ」や「ソナチネ」を演奏したことがある方は少なからずいらっしゃると思います。 よく「ソナタ」などを勉強する際、どこかひとつの楽章だけを勉強なさる方がいらっしゃいます。ですが、ちょっと待ってください!!! 「ソナタ」とは、”楽章”というのを用いて書かれていて、4つの楽章でできていれば、第1~4楽章のセットで「一曲」なのです。”楽章”とは、曲のなかのまとまりであって、楽章をばらばらにして良いわけではありません。 「ソナタ」を含め、”楽章”を使って書かれている曲は、かならずすべての楽章を勉強する必要があります。なぜなら、曲のなかで”楽章”は相互に関係しあっていて、つながっているのです。 そしてみなさんに強く申し上げたいことは、楽章を用いて書かれているどんな曲でも”第1楽章”がその曲の「顔」です。その曲を聴くとき、一番最初に耳に入ってくるのは第2楽章でも第3楽章でもなく”第1楽章”なのです。 いつでも”第1楽章”には、とてもたくさんの要素が詰まっていて演奏するのも一番難しいのです。なので特によくじっくりと勉強しなければなりません。 第1楽章は、曲全体のなかで一番たくさんの内容が詰まっていますが、それだけにやりがいもありますし、またたいへんでもとてもおもしろいです。 「ソナタ」や「ソナチネ」などのように”楽章”を使って書かれている曲を勉強するときは、かならず全楽章をなさっていただきたいものです!!!そうすることで、それぞれの楽章の曲全体での”位置”やそれぞれの楽章の特徴や楽章同士の共通点も見つかり、演奏することがより楽しいものになると思います。 みなさんも、がんばってくださいね。
2005.10.06
コメント(0)
-
スラーとフレーズ&スタッカートのおはなし。
みなさんは、曲のなかについているスラーやスタッカートをどのように演奏していらっしゃいますか?また、音だけでなくスラーなどのアーティキュレーションにも目を向けられていますか? まず、以前にもお話しましたが、「音楽」とは、”言語”でもあります。モーツァルトの作品ならば”モーツァルト語”。シューベルトの作品なら”シューベルト語”。ベートーヴェンの作品なら”ベートーヴェン語”というふうになります。 どの作曲家でも、かならず”その作曲家らしさ”を持ち、そのように&”それらしく”聴こえる演奏をしなければなりません。それぞれの作曲家によって、その作曲家自身の個性や特徴などなどが、たくさん詰まっているからです。 「曲」(または練習曲=エチュードでも)を練習するとき、音をたどることのほかにわたしたちは、スラーやスタッカート、アクセントや強弱記号など、楽譜に書かれているとても多くの大切な情報にも目を向けなければなりません。 ではまず、スラーとどのように付き合っていけば良いのでしょうか。 「曲」は一つの”物語”とも解釈できますが、スラーは文章のなかでいう「句読点」に置き換えられます。つまり言葉の切れ目であったり、一つの文のまとまりであったり、実にさまざまです。 曲を勉強する上でスラーは特に重要です。スラーがきれるからといって、フレーズがかならずしもそこで切れるわけではありませんし、いくつかのスラーをまたいで一つのフレーズを作っているという場合もたくさんあります。 いずれにしても、スラーがでてきたら、「どこからどこまでがつながれているか&フレーズはどこまでなのか&どこでスラーが切れているか」 をいつも考えることが大切です。 しかし、曲をやっていくうちにそれらがだんだん”景色”になってしまって、見過ごしがちです。私もよくあります・・・(;;)反省・・。 みなさんも、気をつけてくださいね。 それからスタッカートについてです。 みなさんは、スタッカートというとどんな意味だとお思いでしょうか?学校や音楽教室などでは、スタッカートというと”音を短く切る”という意味で認識なさっている方がふつうであると思います。ですが、それは”本当の”正しい意味ではないのです。 スタッカートは、正しくは、決して”音を短く切る”という意味なのではありません。正しくは、スタッカートは”アクセント”の意味として扱うことがとても多いです。そして、スタッカートを日本語のなかで表すと「行っちゃった」と声に出して言ってみたときの”小さい「ッ」”にあたります。みなさんは、”行っちゃった”と言うとき、意識して小さい「ッ」を”短く切って言おう”と思っていらっしゃいますか?ーーーだれもそんなことを意識して「ッ」を言っている方は一人もいらっしゃらないと思います。スタッカートとは、そういう意味なのです。 多くのみなさまが、スタッカートが出てくると”短く切ろう!”と思って実行なさっていると思いますが、それは日本語に置き換えれば”行っちゃった”と言うときに、小さい「ッ」を”意識的に”切ってはねて言っているということになってしまうのです。それでは、やはり不自然ですね。 スラーもスタッカートもまた他の表記も、その曲&その時々によって解釈の仕方を考えなければなりません。いつどんなときもこうすればよいっということは、ないのです。その判断はなかなか難しいですが、そのあたりはそれぞれの先生に教わりながら、理解&判断できるようになると良いですね。 今日のお話は、なかなか説明がうまくできずに申し訳ありません。なんとなくでもわたしがお話したかったことは、みなさんに伝わっていれば幸いです。またご質問等ありましたら、いつでもおっしゃってくださいね。
2005.10.06
コメント(0)
-
ツェルニーさん&”練習曲”のことのおはなし。
ピアノをやっていらっしゃるみなさんの中で、エチュード(=練習曲)を勉強している方はたいへん多いと思いますが、中でもツェルニーさん(またはチェルニーさん・・*おなじ人です。)が作曲した「ツェルニー30番」や「ツェルニー40番」または「ツェルニー100番」といった、”ツェルニーシリーズにくるしめられている!!”という方、とても多いのではないかと思います。 (*あっ、みなさんご存知のことと思いますが、”ツェルニー”とは、人の名前ですよ!一応念のため確認で書かせていただきました。ご了承くださいませ。) 私もツェルニーさんにはずいぶん”くるしめられた”、いや、「勉強させていただいた」うちの一人でもあります。(^^;) ですが、ずっと勉強してくるとツェルニーさんの教本がいかに大変役に立つか&どれほどこれらを”きちんと”勉強しなければならないか。その必要性をとても強く感じ、理解できるようになります。 なぜツェルニーの作った練習曲がこんなに重要なのか?単なる偶然でしょうか。ーーーこたえは、きちんとあります。単なる偶然などではないのです。 さてここで、このあたりの歴史を振り返ってみましょう。まず最初に、ハイドンさんがいます。この人は交響曲を生涯に100曲以上も作曲したことから『交響曲の父』といわれています。有名な曲は、『驚愕』や『時計』といった名前のついた交響曲があります。聴けばすぐにわかると思います。この人は音楽史上「古典派」に属します。この人はとても長生きし&当時でも大大活躍した人です。また多くの作曲家が”ピアニスト”であったのに対し、ハイドンはどちらかと言うと”作曲家”であったので、ピアニストの場合は自分でピアノを弾きながら作曲しますが、作曲家なのであまりピアノを弾いて自分でたしかめずに作曲したらしく、演奏者の側からすると”少々弾きにくい”パッセージやメロディも含まれているといわれています。でも良い曲もたくさんありますよ。悪しからず。。 そしてこのハイドンさんに作曲を教えてもらおうとハイドンに作曲を師事したのがあのベートーヴェンです。ですがベートーヴェンがハイドンに”作曲を教えてください!!”と言った頃、ハイドンはとてもとても忙しく、ベートーヴェンが望むようにはあまり教えてもらえなかったようです。それを不満に思っていたベートーヴェンは、ハイドンとは別の人にも作曲を師事していたと言われています。 そしてこのベートーヴェンの弟子であったのが、みなさんの敵?、いや、”師匠”であるあのツェルニーです。冒頭からお話している、その人ーーーツェルニーさんです。ツェルニーはベートーヴェンからとても信頼されていて、頼りにもされていました。ツェルニーは当時のすぐれた教育者としても活躍しました。ツェルニーは後世にも残る「教育」に関するすばらしい著書も残しており、『若き娘への手紙(全音楽譜出版社)』というピアノの勉強仕方、奏法に関するとても興味深い本もあり、これはとてもオススメです。現代でももちろん十分使えます。興味のある方は、ぜひ購入なさってみてください。ちなみにこの本の目次を紹介させていただくと以下のようです。 手紙一 ・・・レッスンの基本条件について 手紙二 ・・・タッチ(打鍵法)、音質、スケール(音階)について 手紙三 ・・・拍子、音符の分け方、指使いについて 手紙四 ・・・音楽の表現と装飾記号のひき方について 手紙五 ・・・調性の勉強、曲の練習法、そして、人前での演奏について 手紙六 ・・・自分に適した曲を選らぶことについて 手紙七 ・・・通奏低音に関する基礎事項について 手紙八 ・・・和音の構成について 手紙九 ・・・通奏低音(続き) 手紙十 ・・・即興演奏(インプロヴィゼーション)についてというふうになっています。ちなみにお値段は私が購入したときは800円+税でした。参考までに。 さて、話を元に戻しましょう。先ほどのツェルニーにも弟子となった人がいたのです。あの”ピアノの名手”であったリストさんです。あのヴァイオリンでいう「パガニーニ」にあたるピアノ界のパガニーニ、フランツ・リストさんです。リストといえば、大変なピアノの名手でしられ、『超絶技巧練習曲集』などという名前の曲集も作曲してしまっているくらい、とてもとてもとてもピアノがスペシャル級に上手かった人です。当時リストは女性に大変人気があり、風刺漫画でもリストさんの演奏会(リサイタル)で、客席の一番前の人が失神している様子が描かれているほどです。またリストはとてもピアノがよく弾けた人なので、自身の曲にもその要素はふんだんに入っており、高い演奏技術の要る曲が多いのも特徴です。当時は作曲家とピアニスト(=演奏家)がイコールであった時代なので、聴衆に”自分はこんなにも弾けるんだ!!!!!”ということをアピールしたような曲であるという部分もあります。またツェルニーはまだ幼い(たしかまだ8歳くらいのとき。)リストさんを、自分の師匠であるベートーヴェンの所に連れて行きその才能を見せたそうですが、そのときベートーヴェンはリストのその才能を認め、将来も大変有望であると言って褒めたとも言われています。 また、リストさんが音楽史上最初の「リサイタル」を開いたといわれています!!!今日では当たり前の”リサイタル”という演奏会の形式も、昔はそうでなかったのですね。 さてさて、こんなふうにハイドンからリストまでみんなつながっていて、ハイドンの弟子はベートーヴェン。ベートーヴェンの弟子はツェルニー。ツェルニーの弟子はリストという具合になっていることがわかります。また、どんな天才であれみな「人間」です。人間がすることですから、師弟関係にあればそれなりに影響を与えるものです。たとえばツェルニーの練習曲の中にも、リストと関係のあった「ショパン」に似た曲、または”一部分”があるものもあります。ツェルニーとショパンは直接の師弟関係ではありませんが、ツェルニーの弟子であったリストとのつながりで影響を受けたのかもしれません。 なぜ私たちはツェルニーを勉強するかというと、それはたくさんの色々な作曲家の作品を勉強するときにすべてその共通点があるからです。また、ツェルニーに出てくる「テクニック」は、あらゆる曲に登場します。言ってしまえば、ツェルニーを本当の意味できちんと勉強しひとつ一つを”身につける”ことができたとき、私たちは曲のなかでそこの部分をわざわざ取り出して、練習をすることも少なくなるのです。 ツェルニーを好きでないという人は、決して少なくないと思います。でも避けて通ることはできないと思います。たとえツェルニーの教本を使わなくても、「曲」をやっていくなかで行う練習はツェルニーのそれと変わりないものと思います。ピアノを上手くなりたい!!!っと本気で思う方は、是非ツェルニーをご自身に合ったものを、徹底的に勉強してください。具体的には何をするかというと、やはり拍子を守って、リズムを守って、そしてテンポも表示に近いテンポで弾けるようになるようにしてください。あせらず欲張らず、落ち着いてきちんと着実にゆっくりなテンポから行うことは、必須です。あとはそれぞれで習得するべき「テクニック」があると思いますから、そこが達成されることが目標です。 私もツェルニーで苦労した経験は、山のようにあります。でもとても苦労して、でも徹底的にやって”マスターした”エチュードは、その後ほかの曲で同じパッセージが出てきても改めて練習しなくてもすぐにできるようになりました。 テクニックを身につけるのは決して楽なことではない、むしろ苦しいことでもありますが、一度身につけられたものは一生そのまま使えるのです。どうかみなさん、エチュードは徹底的に&辛くてもとにかく”身につける”までやる!! これを頭において勉強なさることをおすすめいたします。 私も、まだまだいろいろがんばらなくては~~~~!!!!!!!
2005.10.05
コメント(0)
-
CDの聴き方&”らしさ”のおはなし。
みなさんは、ご自分が弾くことになった「曲」のCDを聴いていらっしゃいますか?そして聴いていらっしゃる方々は、いったいいつどんな風に聴いていらっしゃいますでしょうか? よく、”自分が演奏する曲のCDくらい聴かなければだめ。”っと言われます。私も”聴く”ことは、とても大切だと思いますが、私はその”聴き方”にしばしばモンダイがあると思うのです。 みなさんはご自分が演奏なさる曲のCDを、いつ聴いていらっしゃいますか?ここでの「いつ?」とは、”ご飯食べているとき”とか”なんとなくBGMで。”っというような意味ではなく、”曲を勉強し始める前”とか”曲がある程度できあがってから。”などという意味の”いつ?”です。 おそらく多くの方が、その曲と”はじめまして”のとき。つまり、「これから楽譜を読んでやり始めるよ」っという”初期”の段階で、CDをたくさん聴いていらっしゃるのではないでしょうか。 私の考えでは、一番CDを聴くべきなのはある程度その「曲」を理解し、自分なりの具体的な”こんなふうに弾きたい”という案が固まってからです。もし何もしていない”始めっから”CDをたくさん聴いてしまうと、”そのCDの演奏”のままあなたにインプットされてします。そうするとそのCD以外の”演奏(=表現)の仕方”をなかなか考えられなくなりますし、”なんとなく”記憶されたCDの音を頼りに楽譜を読んでいってしまいます。そうすると、記憶を頼りに音を読んでいますので読み間違いが生じる原因にもなります。 CD屋さんに行くと同じ「曲」でもさまざまな演奏家のものが売られています。そしてその一つ一つはすべて違っていて、”同じ演奏”というものはまず存在しません。 あれだけ多くのものが売られているのに、なぜ同じものがないかというとそれは、演奏している”人間”が違うからです。以前にもお話しましたが、「あなたの演奏はあなたにしかできない」のです。だからプロであろうと素人であろうと、”その人自身”の演奏をしなければ”その人が弾く”意味がありません。 たしかに「曲」を勉強していく中で、行き詰ることもあります。”ここはどんなふうに演奏したら良いのだろう・・?”/”自分はこんな風に演奏したいと思っているけど、演奏家の人たちはどんなふうに演奏しているのかな?(=他にどんな案があるか。)”など。そういうことを知るために、CDを聴くのです。CDのままをなぞって演奏するのではなく、あくまで自分の演奏の”参考”にするのです。 ただ、どんな曲か何も知らないで取り掛かるのには気が退けるという方は、もちろん初めにCDを聴くことも大変良いと思います。ですがそのときに気をつけなければならないことは、できるだけ”記憶しない”ことです。なんとなくその曲の雰囲気や大まかな流れを知るっというだけに留めておくのが、私は望ましいと思います。 曲を勉強するとき、なんだか宝物をさがすように”どんなふうになっているかな~。あ、ここにこんな仕掛けがあった!”とか、”ここにワナがあるな”っとか、なぞ解きのように「ご自分」で曲を”読んでいく”ことが大切です。 「音楽」とは、”言葉(=言語)”なのです。ベートーヴェン語、モーツァルト語、バッハ語、シューベルト語っといった具合にです。そして「曲」は、”物語(=”お話”)”なのです。その証拠に曲の始まりはいつも、私たちが作文を書き始めるときに最初を一マスあけるのと同じように空いているでしょう。 ”どんなお話なのか?”ーーーそれを読み解き、その人なりに表現する。これが曲を勉強し、”演奏する”ということです。そしてそれぞれが”ベートーヴェン語”や”モーツァルト語”、”バッハ語”、”シューベルト語”というふうに一つ一つ違っていて、そのことを私たちは聞き手にわかるように演奏しなければならないのです。 どんな作曲家の曲を演奏するにも、かならず”その作曲家らしく”聞こえる演奏でなくてはならず、その曲をしらない人にも、”この曲はきっと○○が作曲した曲だな”とわかる演奏でないと、その作曲家のその「曲」を演奏したことにはならないのです。 では、どうすればそれぞれの作曲家の作品らしく聞こえる演奏にできるかっというと、みなさんが「曲」を勉強するとき、とにかくその作曲家のさまざまなジャンルの作品を聴くことです。”聴きまくる”のです。オーケストラの曲でも弦楽四重奏などのような室内楽、また協奏曲でも歌曲でも良いのです。とにかく偏らずにたくさん聴いて、”その作曲家まみれ”になることです。そうするとだんだんご自身の中にその作曲家の「引き出し」が出来てきます。そうするとだんだんと”その作曲家らしさ”がわかってきます。そうすればご自身が演奏するにも反映されるのです。 私は、ご自身が勉強なさっている真っ最中の曲のCDをお聴きになるよりも、同じ作曲家のすべてのジャンルの曲を演奏することの方が大切だと思います。特に、ご自身が勉強なさっている曲と同じような時期に作曲された曲を聴いてみることの大変良いと思います。作曲家も一人の人間ですので、共通の点もみつかることも多いのです。 ご自身が勉強なさっている曲のCDは、ご自分のその曲に対する”案”がある程度まとまってからが望ましいと思います。 また、CDを選ぶときは1枚だけでなくて、少なくとも2人以上の別の演奏家のCDを購入なさると良いと思います。そうすると、自分が求めてそのCD聴くときに2つの違った”案”をしることができます。一つのCDしか聴いていないと、その案しか知らないことになってしまって表現の幅が偏ってしまう恐れもありません。 一つの曲でも何枚かのCDをお聴きになると、だんだんピアニストにも目がいくようになって、”お気に入り”のピアニストまたは演奏家も出てくるでしょう。そうして今度はその演奏家の演奏会にも足を運ぶようにもなるかもしれませんね。そうすると「音楽通」になっていくとともに、趣味や興味の幅も広がって、より楽しい人生になるかもしれませんね!! Good Luck!!
2005.10.04
コメント(0)
-
”ハ長調はいちばんかんたん???”のおはなし ~調と指&曲のかんけい~
みなさんは、練習またはレッスンで「スケール」をなさっていますか?スケールとは、”ドレミファソラシドドシラソファミレド”っみたいなもので、それぞれの「調性(ハ長調やト長調、ホ短調など)」の音階ののぼり&くだりをやるものです。 さて、一般的には何もシャープやフラットがつかない「ハ長調」が最も簡単であると認識されていると思いますが、果たしてこれは本当でしょうか? たしかに、とくに初心者の方の場合、勉強するものにシャープやフラットがついていない方が、すべて白鍵を弾けば良いため混乱が少なく、”かんたん”であると思います。 ですがみなさん、「スケール」を弾くときはまったく逆なのです!!!!!! 理由ですが、まずピアノの鍵盤をみると白と黒という2つの色の鍵盤があります。そして、黒い鍵盤のほうが白い鍵盤よりも”上”というか、”奥”に入っています。(=黒鍵のほうが長さが短い。) そして、私たちの指はすべて長さが違います。親指は5本の中で一番短いですし、中指は一番長いですね。っということは、長い指が黒鍵をたくさん弾く「調」が、一番弾きやすいのです。もっと言えば、最も簡単なのは、「調号(ト音記号やヘ音記号の隣りに書かれている”シャープ”や”フラット”)」が多い調から、スケールを弾くことなのです!!!!! 何を弾くにも、いつでも「生えているままの手の形」で演奏することが自然です。調号が多い調の方がよりそれに近づくのです。 ハ長調は、シャープやフラットが1つもないので、すべての指が白鍵を弾くーーーつまり長い指にとっては指を意識して”縮めて”弾かなければなりません。逆に、最もシャープまたはフラットが多いのは、ロ長調です。ロ長調には、シャープが5つ付きます(ファ・ド・ソ・レ・ラ)。もっと簡単に言えば、ミとシ以外はすべてシャープです。「ロ」というのは、ただの「シ」のことです。”シ”から始まって”シ”でおわる「明るい」調。それが、「ロ長調」です。*詳しい指使い等は「ハノン」等をご覧ください。 みなさんの多くは、なにかを演奏するとき、シャープやフラットの数をとても気になさっているのではないかと思います。そのお気持ちは私も理解できますが、ちょっとした考え方でやりやすくなるのです。 調号は一番多くて7個つきます。ですが、7個付く調は少ないと思います。みなさんがどきどきし始めるのは、3個や4個からではないでしょうか? たとえば3個付いたとき、シャープなら「ファ・ド・ソ」の3つに必ず付き、フラットなら「シ・ミ・ラ」の3つに付くと決まっています。 おそらく3つくらいまでならなんとか、”これとこれとこれに付くのだなっ”と覚えられると思いますが、4つ付くともうやる気をなくしてしまう方、ちょっと待ってください!! 調号は、一番多くて7個付くっということは、シャープであれフラットであれ4個付いているということは3つはついていないわけですから、そちらを覚えれば良いわけです。 シャープが4つ付いた調であれは、「ラ・ミ・シ」以外はすべてシャープ。フラットが4つの調なら、「ソ・ド・ファ」以外がすべてフラットという具合になります。そして5個や6個の調の場合は、付いていない方の音を考える方が断然簡単です。4個くらいならば、それでもまだ”これとこれとこれとこれ”という具合に、付いている方の音を覚える方がラクという方も多いと思います(私はそうです)が、4個よりも、5個や6個のほうがある意味ではラクだと思います。 私が最近楽器店や本屋さんの音楽コーナーに行って思うことは、実にここ最近でずいぶん色々なタイプ楽譜が増えたなっということです。とくに大人の方のための楽譜が豊富になりました。以前はこんなには売られていなかったと思います。また、音楽をより楽しく学んでもらおうと工夫を凝らした楽譜もたいへん増えました。とても恵まれた環境になりつつあるのではないかと思います。 ですが、同時にあまりに”たのしく無理なく”という傾向に行き過ぎているように感じることがあります。私が疑問に思うのは、どんな曲でも「ハ長調」に直してしまっている楽譜です。たしかにハ長調にしたことによって、楽譜を読む初心者の方はずいぶん楽でしょうが、それでは「曲」の味わいが激減してしまうと思います。 どんな曲でも良いですが、みなさんがお好きな曲を思い出してみてください。その曲は何の音から始まるでしょうか。もしそれが「ソ」から始まる曲だとしましょう。でも、なぜ「ソ」から始まるように作曲家は書いたのでしょう?別に「ミ」でも「ド」からでも良かったと思いませんか? 作曲家が「ソ」から始まるように作ったのは、単なる偶然でしょうか。ただ書いたらそうなっただけで、とくに深い意味はないのでしょうか? 答えは違います。「ソ」から始まるには、「ソ」からでないといけない理由があったのです。始まりの音、つまりその曲の「調性」は、曲にとってとても重要です。”ドレミファミレド/ミファソラソファミ/・・・”でおなじみの「かえるの歌」ですが、もしこれが”ソラシドシラソ/シドレミレドシ/・・・”だったらどうでしょう?可能な方は弾いてみてください。明らかに曲の雰囲気がガラっと違うことがわかると思います。 「調性」には、それぞれの”カラー”があります。たとえば、ハ長調なら平和的。ト長調なら華やか。ハ短調はベートーヴェンの「運命」や「第九」、ピアノソナタの「悲愴」などさまざまな名曲を残したこともなにかその調の特性や意味があることがわかるのではないかと思います。 「調」には、それぞれの意味があります。始まりの音ひとつ、調号ひとつで、曲の雰囲気はガラリと変わってしまいます。引き立たせることも台無しにさせてしまうこともできるのです。 何を演奏するにも、原曲のままを弾くことが一番良いと私は思います。みなさんもどうか、シャープやフラットをおそれずに”なかよく”付き合っていきましょう~!!!
2005.10.03
コメント(0)
-
私が思う”お教室えらび”のおはなし。
私は4歳~小学校6年生まで、某大手音楽教室に通っていました。そこでは初めはグループレッスンをし、小学校の途中からは週2回、グループレッスン&個人レッスンを行っていました。 そのころの私は毎週のために練習は大してしておらず、特に個人レッスンのときなどは先生とおじゃべりすることが楽しかったように思います。ピアノの先生に学校での出来事やグチなど・・・。色々なお話をきいてもらっていました。あまりにもたくさんしゃべるのでその当時の個人レッスンは30分間でしたが、あっと言う間に経ってしまってピアノをひとつも弾かない日もありました。先生はお困りで、”先生はお金もらっているし、ピアノに来ているのだから今日は弾かないとね”っと、後半の15分ほど弾いたこともありました。(^^; その後中学、高校、大学へと進む中で色々なレッスンを受けてきて私が思うことは、まず教える上で大切なことは、相手の年齢問わず、その人とまずたくさんのコミュニケーションを取りながらその方についての情報ーーーつまり趣味やそれまでのことなど何でも良いので、知ることです。 コミュニケーションを取れなければ、ピアノ(=習いごと)の上でもキャッチボールはできません。 たしかにピアノを習いにきているのだから、”ピアノを弾いてもらわなくちゃ!”っとお思いになる先生の気持ちは理解はできますが、それだけでは成り立ちません。 教える側は、たとえおなじことをお教えするにも相手が変わればこちらの言い方も変えなければ相手には上手く伝わりません。それぞれの相手に合った”言い方(=言い表し方)”をしなければなりません。だれ一人として”同じ人間”は存在しないからです。 私はそれぞれの方への言い表し方の決定とは、相手の方の思考や趣味などをしることでされると思います。なので本題以上にそういう一見”ピアノとは全然関係ないのではないか・・?”と思われるようなことが実はとても重要だと思います。 私のピアノのスタートは大手音楽教室にでしたので、そこではきっちり一人あたりの(個人)レッスン時間が決まっており、自分の前の人のレッスンがのびても自分のレッスン時間の終わりは変わりません。なので、そういった色々なことを先生とお話する時間はありません。本当に”ピアノを弾く”ための時間しかないのです。 それは大手教室では仕方のないことかもしれませんが、教える側となったいまの私には習う側の方のお気持ちを考えるととても残念な気がします。親御さんも、その日自分の子どもがレッスンでどうであったかや今後の方向など、きっと知りたいはずです。でも30分ずつ交代で先生に空く時間がないとそれもなかなか聞けませんよね。こういうことが、だんだん両者に溝ができていく原因にもなると思います。 私自身、自分のお教室では、”ゆったり”とレッスンをしたいと思っています。いつも時計を気にしながら進めるレッスンではなく、たとえば基本は30分だけど枠は60分とってあげる。そうしてもし時間通り30分でレッスンの本題は終わったとしても残りの時間で親御さんとお子さんのお話などができる。または、30以上60分以内という枠でいろいろなお話をしながらゆったりとレッスンを行うというスタイルです。それから、30分の枠でも30分では終わらなかった場合はそのまま延長し、もちろん料金の加算はありません。私のお教室は基本的に、”きちんと”やりたい方のためのお教室ですので、お値段の世間の相場よりは少々高めだと思いますが、その分時間は過ぎても十分なレッスンをしてあげたいと思うのです。 個人教室の場合はある程度の融通も利きますので、そういうところが利点だと思います。個人教室でも”時間きっちり多少のえ延長もナシ”では、個人教室にいらっしゃる意味がありませんよね。 私が通う大学からの先生のレッスンは、まず時間はのびます。それはどなたのレッスンも大抵伸びますので、自分の番になってもまず時間通りに始まることがないことと、なぜのびるかというと色々な音楽のお話やそのほかのお話などなど。先生と順番を待っている生徒さんと今レッスンを受けている生徒さんとでいつもいろいろなお話をしています。時間がどれだけ延びても、意味のある時間を過ごしていますので、それについて文句を言う生徒さんはいません。私も含め、みなさんこれでとて良いと思っています。なので大学を卒業しても、そのままいらっしゃる門下生がたくさんいます。私はとても素晴らしいことだと思います。 お教室は”生徒さんのため”になることをするべきだと思います。大手教室では時間で動かなければならないという点があると思いますが、個人教室ではそういう縛りは先生が設けなければありませんので、わたしは”ゆったり”としたお教室をめざしています。あまりせかせか動くのは性に合いませんし・・(^^;) みなさんもぜひ、ご自身に合ったお教室をえらんでくださいね!!!
2005.10.03
コメント(1)
-
作曲家と演奏のつながり☆のおはなし。
よく演奏するからには、その作曲家がどんな人生を送ったかなどを知っていなければならないと言われます。 私は演奏するのに作曲家のことをしらなくたって、どうってことないじゃん!と昔々思っていた時代がありました。きっとしらないよりは知っているほうがいいだろうけど、調べていったい何になるのか、知るとどんないいことがあるのかまっうたくわかりませんでしたし、何より面倒くさかったのです。 その後、さまざまな勉強や経験を経て、だんだんになぜそれらが必要といわれてきたのかをわかるようになってきました。 結果、やはり作曲家の中身を知ることはとても大事です。すっからかんで何も知らないまま演奏してはいけません。なぜなら、どんなに偉大な大大作曲家!と言われる人たちもみな、私たちとおなじように「人間」であるからです。 作曲家がどんな人生を送ったか?---これは、バッハやモーツァルト、ベートーヴェン、ショパン、リスト、ドビュッシー等々のいわゆる「クラシック音楽」の代表といわれる人たちの作品を演奏する場合に、とくに必要です。 作曲家の人生を知って、いったいどんなふうにその知識が役に立つか?---別になにも、演奏の最中に”この作曲家は○○で生まれたなぁ~”とか”○○で暮らしたなぁ~”とか”○○さんていう人と恋仲だったなぁ~”などと思い返したりはしません。演奏の真っ最中にそんなことをしてしまったら、かえってよくないと思います。(演奏中は、「その曲」を演奏することに集中する必要があるからです) では、いったいいつその得た知識を活躍させるか?ということになりますが、それは「いつ」ということではないのです。 「字」や「絵」をかいたときのように、音楽も”演奏”には演奏者「その人」の心の中が100%というくらいに表れます。それは好むと好まざるとに関わらず、かならず自然と何も意識しなくても現れるものです。そしてまたこのほかに、”その人がどれだけその曲の作曲者のことを知っていて演奏しているか”ということも同時に表れます。 ある程度その”作曲家”のバック・ボーンを知った上で演奏していないと、どこか空虚というか中がスカスカのように感じます。その理由は、演奏している本人がただ音符を追いかけているだけで、色々な意味での「中身」を理解できていないことが原因だと思います。 たしかに演奏者が作曲家の中身を知った上で演奏をしているかどうかは、誰もがはっきりとこの人は”知っている”とか”知らないままだ”というふうにはわからないかもしれません。しかし、どんな素人の方でもそのことは「言葉にならない”何か”」として受け取られることと思います。 私たちも自分がしらない分野でも、演技や競技をみたときになんとなくその良し悪しというか上手い、下手というか・・・そういったことを感じると思いませんか?そしてそれは専門家の意見と一致していたり・・・。 よく”聴衆なり観客は素人だから、やる側の上手い、下手なんかわからないからテキトーにやったってわかりゃしないよ・・・”と言う方が時々いらっしゃいますが、私はそれは間違っていると思います。 相手が素人であれ専門家であれ、どこかおかしいところがあればかならずそれはどんな相手にも伝わると思います。専門用語等を使って、具体的におかしい部分を言葉で説明できるかどうかっという違いがあるだけで、相手が素人の方であれプロの方であれ、どんなことをやっても相手は”わかる”には変わりないと思います。 私たち演奏する側も、素人の方を前にしようが専門の方を前しようが、行うことはいつも同じでなければならないと思います。”素人の方にはテキトーに、プロを相手なら本気に。”っという気持ちでは、おそらく何一つきちんとしたことはできないと思います。また、いつも”テキトー”にやっていれば、プロの方を前にしたからといっていきなりその時だけ”本気”を出せることはありません。自分の”普段”がそのまま出てしまうからです。 それぞれの作曲家がどんな人だったか、どんな人生を送ったかを調べるなんて、なんて面倒くさいのだろう・・・と思った方もきっと少なくないと思います。私もむかしはその中の一人でした。でも自然と”知ってみたい!!(←変な日本語ですが・・。)”思うようになり、今はすっからかんでは演奏しなくなったと思います。昔は面倒くさいなどと思っていましたが、調べていくとその作曲家の”人間らしい”部分を見つけられることもあり、以前より近い存在に感じられたりもします。今はとてもわかりやすく読みやすく書かれているものもありますので、そういうものを見てみることもぜひお勧めします。「曲」のためっということ抜きに、面白いと思いますよ。 J.S.Bach(バッハ)は、子どもが16人くらいいたとか、モーツァルトは曲に似合わず結構”下品”なことを言ったりしていたとか(←私はこれは結構ショックでした・・・)、ベートーヴェンはコーヒーがとても好きだった&お風呂もとても好きだった&引越し魔だったなどなど。逸話として、とても楽しめるところもあります。 私自身もまだまだ色々と勉強しなければ・・と思うことがたくさんたくさんあります。落ち着いて、がんばらなければ~!!と思う、今日この頃です。みなさんも、がんばりましょう!!!
2005.10.02
コメント(0)
-
”たくさんのいろいろな演奏”にまつわるおはなし。
ピアノに限らず、なにか音楽を趣味でも専門でもなさっている方々。みなさんは何のために演奏をなさっていますか? みなさんの中には人前で演奏することがあまり好きでないという方も多くいらっしゃることと思います。私もすごくそう思っていた頃があるので、そのお気持ちはとてもよくわかります。 ですが、何のためにわたしたちは演奏するのでしょうか?自分ひとりだけで”ひっそり”と演奏するのでしょうか。それもたしかに良いとは思いますが、それだけではただの”自己満足”であって、私は自己満足がわるいとは言いませんが、それは本来の演奏する意味とは違っていると思います。 演奏を通して何を表現するか? それは、”その人自身”以外の何者でもないと思います。昔に”演奏家”が誕生したときには、宮廷などで依頼があって演奏したのです。あるときはお食事会で。またあるときは大きな催し物でなどなど。かならず「聴く」人たちがあっての”演奏”だったのです。 CD売り場に行くと、同じ曲でも実にさまざまな演奏家のものが売られています。そしてそれらはみなひとつ一つその”演奏”はちがいます。 私たちが「文字」を書くとき、同じ文字を書いてみてもみなそれぞれ、”その人の字”というものがあります。絵を描いてもかならず”その人”がでます。 どんなに似せてみても、あくまでもそれは”似せてかいたもの”のままで、”モトのもの”にはなりません。 みなさんが”あなた”にはなれないのと同じように、あなたの演奏は、あなたにしかできないのです。たとえどんなに”似せて(=真似て)”演奏してみても、必ずそこには”その人(=本人)らしさ”が存在し、100%同じ演奏にはなりません。ひとり一人みんなちがうからこそ、みなさん一人ひとりそれぞれが”演奏をする”意味があるのです。何度も申し上げますが、あなたの演奏は、あなたにしか演奏できないのです。 演奏によって”自分”を表現する。そしてそれは、自分自身のためだけでなく聴いてくださる方々に対しても同じです。あなたにしかできない”演奏”だからこそ、周りの方々にお聴かせする。演奏は、自分を表現するため&人に聴かせるために行うのです。 人前で”演奏”するにはどんなプロの方でもそれなりの緊張を伴いますが、でも演奏した後のみなさんからの”拍手”を浴びると、緊張もふくめそれまでの苦労もぜんぶ吹っ飛んでいくというものです。 そしてもうひとつここで大切なことがあります。人前で演奏するとき、よく普段以上に”良い演奏”をしようと思ってしまう方も大勢いらっしゃると思います。が、そう思う必要はまったくありません。 まず学校のテストでも同じですが、人前で演奏するときには”普段以上のことができる”ということはまずありません。もし練習ではなかなかきまらなかったところが本番でうまくいったということがあったとしたら、それは本番で”本気”になったからでしょう。練習でも同じ気持ちいなってやっていたら、できていたかもしれません。 普段やっていることを、そのまま弾く。本番で普段以上のことを何かやってやろうとか思うと、余計なことに気をとられてしまって、本来の”自分らしい演奏”ができなくなります。 普段のことを本番でだせるようにするのが練習です。それだけに”普段”の練習の内容、どんな気持ちで練習しているかがとても大切となり、いい加減なことはできません。本番だけうまくいかせようということはできません。 本番では”いつも通りの自分”で、「自分らしい演奏」をすることが一番大切だと思います。いつも以上に上手にみせようとか、本番だけこうしてみようとかそういう”小細工”は一切必要ありません。かえって邪魔になるので、しないことが一番です。 なにより”あなたの演奏は、あなたにしかできない。”のですから、みなさんどうか自信をもってがんばりましょう~!!!
2005.10.02
コメント(0)
-
拍子の感覚の身につけ方&メトロノーム選びのおはなし。
ブログにてご質問がありましたので、そのことに今日は触れたいと思います。 内容は、「拍子の感覚をつかむおはなし&メトロノーム選びのおはなし」です。 まず、拍子の感覚をつかむにはどうしたら良いか。それは、もちろんメトロノームをしようすることから始まるのですが、このときにひとつ気をつけなければならないことがあります。 メトロノームを使うとき、ただ”カチ、カチ、カチ・・・”とかけるだけではいけません。このときの頭の使い方がとても大切です。 前回のブログで、私はメロディを拍子の数字カウントに合わせておこなうことをお話しましたが、基本的にはそれに尽きるのでが、具体的には次のようです。 メトロノームの”カチ、カチ、カチ、・・・”を聞いたとき、頭ではどのように変換されたら良いでしょうか。数字に直したとき、”1、1、1、1、1、・・・”と思ってしまってはいけません。たとえば4拍子の場合なら、”1、2、3、4、・・・”とカウントしなければならないのです。1拍目ならば、”1”。2拍目ならば”2”。3拍目ならば”3”っと、数字を拍目にあわせてかならず変えなければ意味がありません。もし”1、1、1、1、・・・・”とカウントしてしまったら、拍子はあってないようなもの。すべて”1拍子”となってしまいます。 もちろんメトロノームをかけることは、大変良いことですし必要なのですが、拍子も十分に意識して行うことをオススメします。 また、メトロノーム選びについてですが、私は左右に棒が揺れる”カチ、カチ型”と、デジタルの”ピッ、ピッ、型”の両方を持っています。 基本的にはどれでも良いと思いますが、私自身は自分でねじをまく”カチ、カチ、型”ですと、ながく一つのリズム(またはパッセージ)を練習することが少なくないので、そういうときにねじが終わってしまうとそこで弾くのを中断して自分でねじをまき、またそこから始めなければならないため、それをjなるべく避けたかったので、今は見かけは”カチ、カチ型”なのだけど、音は”ピッ、ピッ、型”で音量の調節もでき、なおかつ電池式を購入しました。 デジタル派か、”カチ、カチ派”かは、個人の趣味によるところも多いと思いますので、基本的にはどれでも問題ないと思いますよ。ただ、さまざまな機能がついているものもありますので、探せばたくさんのタイプがあります。また、用途にもよりますがあまり小さすぎると(万歩計のような。。)、かえって使いづらいのではないかと思います。でも、そのくらい小さいものが欲しいという方はそれで良いと思います。ただ、その場合はあまりプラスαの機能は少ないです。ではまた・・。
2005.10.01
コメント(0)
全38件 (38件中 1-38件目)
1
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…
- (2025-11-12 00:00:13)
-
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-