2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010年08月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
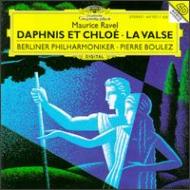
ダフニスとクロエ
「名曲100選」 ラヴェル作曲 バレエ音楽「ダフニスとクロエ」モーリス・ラヴェル(1875-1937)は、ピアノ曲などの器楽曲、ヴァイオリンソナタなどの室内楽曲、ピアノ協奏曲などの協奏曲、それに精緻な響きの管弦楽曲などを書き残しています。 それらの音楽の中でも「オーケストラの魔術師」とか「スイス時計のような精緻な音楽職人」とかで呼ばれるほど、彼のオーケストラ音楽は精緻を極め、フランスの洗練された瑞々しい気品に溢れた曲が数多くあります。原曲がピアノ音楽で、それを彼自身がオーケストラ版として編曲している物が多いのですが、いずれにしろ陽を射されてキラキラ光るような、クリスタルガラスの光沢・輝きのような感触の音楽を感じます。ムソルグスキーのピアノ曲「展覧会の絵」を見事にオーケストラ版に仕立て上げた才能は、まさに「オーケストラの魔術師」と呼ばれるにふさわしい音楽として完成されています。ラヴェルのオーケストラ曲としてもうひとつ有名なのが「ボレロ」です。 「ボレロ」については、以前この日記で書いていますので省略致しますが、もうひとつラヴェルの最高傑作と呼ばれているバレエ音楽「ダフニスとクロエ」があります。ロシア・バレエ団の旗揚げ公演に選ばれたこのバレエは、古代ギリシャの「田園詩」に基づいており、バレエ団の主宰者ディアギレフが当時親交を深めていたラヴェルに音楽の作曲を依頼して、そのラヴェルが足かけ4年かけて完成しているそうです。古代ギリシャのレスボス島が舞台で、牧人に育てられた、お互いに捨て子の身のダフニスとクロエの恋愛が中心となり、二人が幸せな平安の時を得るまでに、ダフニスを誘惑する人妻や、羊飼いや海賊に言い寄られるクロエの話が絡み、最後にはパンの神に救われるという幻想的な物語で、ラヴェルの書いた音楽はその話の内容を髣髴とさせるもので、念入りに構想を練って設計されたような、緊密さと洗練さを極めた音楽です。ラヴェルは後に演奏会用として全曲から3曲ずつ選んで第1組曲、第2組曲として発表もしており、現在もオーケストラコンサートでしばしば演奏されています。しかし、私はこのバレエ音楽を聴いて感動するには10年以上も費やしていました。LP盤でピエール・モントー/ロンドン響の演奏を聴いても音楽そのものを理解できずにいたのですが、何度も繰り返し聴いているうちに音楽の素晴らしさがわかるようになってきました。 「ボレロ」を聴くようなわけにはいかなかった思い出が残っている曲です。愛聴盤(1) ピエール・ブーレーズ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(グラモフォン・レーベル 447057 1993年録音 海外盤)(2) ピエール・モントー指揮 ロンドン交響楽団(DECCAレーベル 4757525 1959年録音 海外盤)
2010年08月31日
コメント(0)
-
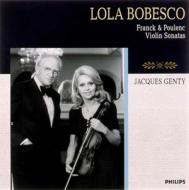
フランク
「名曲100選」 フランク作曲 ヴァイオリン・ソナタ イ長調ベルギー出身ながら、近代のフランス音楽に一つの針路を残した作曲家がいます。 セザール・フランク(1822-1890)がその人です。彼の作品で今日も名作と呼ばれている曲はいずれも晩年に書かれた曲ばかりで、ブルックナーと同じように「大器晩成型」と言われる作曲家です。 例えば「ピアノ五重奏曲」は58歳の1879年、フランクの代名詞でもある「交響曲 ニ短調」は66歳、「弦楽四重奏曲」は亡くなる1年前の1889年にそれぞれ書かれています。モーツアルト、シューベルト、メンデルスゾーンなど30代で後世に残る珠玉の名曲を書き残して、在世時代から評判高い作曲たちとは、ブルックナーやフランクは大きく違っています。フランクは、ブルックナー同様に信仰深いクリスチャンであり、オルガンの名手でもあったそうですが、名声を確立したのは高齢になってからで、まさに「大器晩成型」典型的な作曲家でした。そして今日の話題曲「ヴァイオリン・ソナタ イ長調」は、彼が64歳の1886年に書かれています。彼はその生涯にヴァイオリンソナタはこの1曲しか書いていないのですが、それが現代でもヴァイオリンの名曲として世界中で愛されている名品です。 ベートーベン以降のヴァイオリン・ソナタの中でも、ブラームスの第3番のソナタと共に、最も優れた作品と呼ぶ人もあるほどです。曲には、彼の「交響曲ニ短調」で用いられたのと同じような「循環形式(一つの主題がそれぞれの楽章に現れて、有機的に結びつける手法)」がこのソナタでも用いられており、それによって新鮮さに溢れ、聴く人に親しみを覚えさせる音楽の「調和」と「詩的な」雰囲気の漂う曲です。第1楽章の開始から「憧れ」とか「祈り」のような情緒が感じられる、神秘的な雰囲気に包まれていて、ヴァイオリンの弾く旋律に思わず惹きこまれていきます。第2楽章は、第1楽章の神秘的な雰囲気から一転して情熱的な旋律の主題と、抒情的な旋律の第2主題の対比が見事で、非常に魅力のある音楽が展開します。第3楽章はこのソナタの核となるような楽章で、「朗誦~幻想的に」と指定されており、ラプソディのような情緒の音楽です。 この楽章では「詩的」な瞑想のような雰囲気に包まれていて、私は、第1楽章と共に、この曲のなかで最も好きな楽章です。第4楽章は、澄んだ青空のような明るさに満ちており、これまでに現れた各楽章の旋律が、フラッシュバックのように回想される様は見事で、循環形式を用いた効果が最も現れています。ところで、この曲は作曲家としても有名なベルギー出身のヴァイオリニストのウジェーヌ・イザイの結婚祝いとして贈られたそうです。 献呈を受けたイザイのヴァイオリンによって初演されたのですが、当時(1886年の冬)は夕方になって楽譜が見えないほど暗くなってくると、演奏が中止されて次の機会までお預けと言う時代だったそうです。 この曲の初演時も楽譜が見えないほど暗くなったのですが、ウジェーヌ・イザイもピアノ伴奏者も禁止されていたローソクの火を灯さずに、暗譜で最後まで演奏したそうです。 それだけこの曲が美しさに溢れていて二人の演奏者が初演までに暗譜していたことを物語るエピソードです。愛聴盤(1) ローラ・ボベスコ(Vn) ジャック・ジャンティ(ピアノ)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP3497 1981年録音)フランク、ドビッシー、フォーレのフランス3大ソナタが収録された1200円廉価盤。ボベスコの美音が静謐な表情と詩的な祈りに近い情緒を巧みに表現した名演。(2) オーギュスタン・デュメイ(Vn) マリア・ジョアン=ピリス(ピアノ)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG70097 1993年録音)艶やかなデュメイの美音が理性・知的な雰囲気と燃え上がるような情熱を、ひつに巧みに表現している美しい演奏
2010年08月30日
コメント(0)
-
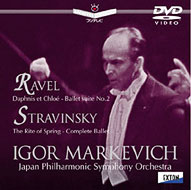
春の祭典
「名曲100選」 ストラビンスキー作曲 バレエ音楽「春の祭典」この曲の初演(1913年5月29日 パリ・シャンゼリゼ劇場)からほぼ100年が過ぎた2010年の現代では、「現代音楽の古典」扱いをされるくらいに私たちの耳・心に馴染んでいますが、初演当時のパリの聴衆には聴くに堪えない大胆で、原始的な変拍子・リズム・響き・不協和音の羅列・連続の音楽だったのでしょう。クラリネットがこの楽器の音にしては異常に高い音で曲が始まると、聴衆はもう騒ぎ出して猫の声の真似で野次りだし、オーケストラの音楽が聞こえないほどに喧騒が大きくなり、上と下の席で怒鳴りあったり、座席に立ち上がって拳をする上げる者がいたりと、それはもう混乱の極みだったそうです作曲者イゴール・ストラヴィンスキー(1882-1971)は「自叙伝」の中でこの曲の初演の模様を書き記しています。「序奏の最初の数小節が始まっただけで嘲笑が湧き、不愉快極まる罵声が飛び交った。」と。またこの初演の指揮者ピエール・モントーは「回想録」の中で、この初演をこんな風に書き残しています。「知ってのように、聴衆は混乱の極みに達していた。新しいシャンゼリゼ劇場満席の聴衆はこ。のバレエへの不満を激しく表明した。 特別席やボックス席の上等席に座る上品な客たちも、階上席へ罵声を浴びせたり、激しく罵り合いを始めた」この初演に対する聴衆の拒否反応は凄まじいものであったようです。しかし、今でこそこの音楽を聴いてもそれほど斬新な手法とは思えませんが、不協和音と強烈なリズムが渦巻いていて原始的な響きの音楽が初演当時の聴衆にはそれほど聴くに耐えない、大胆でとんでもない音楽だったのでしょう。音楽は原始時代民族が大地と太陽を讃えて行う「いけにえの儀式」を表現しており、第1部「大地礼賛」(8曲)、第2部「いけにえの儀式」(6曲)から成り、不協和音と鮮烈、強烈なリズムと管弦楽の咆哮といった原始的色彩の濃いバレエ音楽です。1962年イゴール・マルケビッチが来日して日本フィルハーモニー交響楽団を指揮して、東京での定期演奏会で振ってこの曲を披露したのをフジテレビの放送で聴いたのが、最初の体験でした。 すっかりこの曲の虜になりマルケビッチ帰国後にEMIから25cmLPで新録音としてリリースされたのを買ってから、長い間このLPを聴いていました。 日本ではこの時の演奏会を「春の祭典 元年」と言われるくらいに、復刻されたCDを現在聴いてもその意味がよくわかる、マルケビッチ畢生の名演奏だと思います。愛聴盤 (1) イゴール・マルケビッチ指揮 日本フィルハーモニー交響楽団(Extonレーベル OVBC00009 1968年 フジテレビ音源)マルケビッチ再来日時のテレビ映像をDVD化された盤です。42年経った現在でも名演として聴ける、リズム感覚と激しい原始の儀式を彩る管弦楽表現が素晴らしい貴重な演奏記録です。(2) イゴール・マルケビッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団かなりの演奏を聴いてからこの盤を聴き直すと、かなり知性的な演奏というか理性的というか、原始的な表現をかなり抑え込んだ演奏に聴こえます。録音はさすがに劣化していますが、トップクラスの名演としてこの盤を挙げました。(3) ロリン・マゼール指揮 クリーヴランド管弦楽団(テラーク・レーベル CD82001 1980年録音 海外盤)演奏も凄いのですが録音に驚く盤です。 これほどクリアーに強烈に炸裂する録音盤を知りません。聴いていて怖くなるほどの迫力です。特にティンパニーの炸裂するような打音に圧倒されます。
2010年08月29日
コメント(2)
-
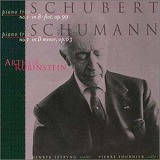
ピアノ三重奏曲
「名曲100選」 シューベルト作曲 ピアノ三重奏曲 第1番変ロ長調 D898あれはもう50年前くらいの話になるのでしょうか、高校生になってから定期購読していた雑誌「レコード芸術」の室内楽月評で紹介されていた、シューベルトのピアノ三重奏曲第1番に目がとまりました。 その当時室内楽の新譜レコード評を担当されていたのが故大木正興さんでした。 淡々とした語り口の中に、その音楽の魅力を十全に伝える文章を書いておられる、私の好きな音楽評論家の一人でした。 NHKクラシック番組にもよく出演されていて、バリトンの渋い語り口にも非常に魅力のある人でした。その大木氏がシューベルトの「ピアノ三重奏曲 第1番」についてどれほど魅力のある音楽であるかを書いておられて、そのあとに演奏の批評を述べておられたように記憶しています。 演奏家の名前はもう忘れてしまいましたが、この曲を聴いてみたいという願望がそれからも続いていて、念願のLP盤で聴いたのがこの曲との最初の触れ合いでした。 ユージン・イストミン(P)、アイザック・スターン(Vn)、レナード・ローズ(チェロ)のトリオでした。 以来、私が好きな室内楽作品の筆頭に挙げる曲となっています。フランツ・シューベルト(1797-1828)は、2曲のピアノ三重奏曲を書き残しています。 2つの曲はとても対照的な性格を持っていて、第1番は愉悦感さえ感じられる明るい作品ですが、第2番は少し劇的で緊張感のある音楽です。今日はそのうちの第1番を採り上げました。シューベルトの作品はどれもロマンティックな美しい旋律に満ち溢れています。歌謡性と抒情性豊かな情感たっぷりの音楽ですが、特にこの第1番のトリオは、第1楽章に象徴されているように、ピアノのリズミカルな音と叙情性の味わいのある旋律で、冒頭から室内楽を聴く魅力へと誘ってくれます。 そして最終楽章までこの気分は失われることなく、至福の境地へと運んでくれる音楽です。 シューベルトは600以上の歌曲を書いていますが、彼の器楽・管弦楽作品の美しい歌謡性と叙情的な旋律はこうした歌曲の作曲から生まれているのでしょう。この曲が作曲された年は定かではないのですが、1827年という説が多いのだそうです。 そうだとすればシューベルトにはすでに死の影が忍び寄って来ている頃で、しかもベートーベンの棺を泣きながら運んだのも1827年でした。 そんな出来事があった時期、或いは自身を苛む病気に負けずに書いたこの曲は、実に楽天的な気分に溢れた音楽なのです。 そこにシューベルトの胸に秘めた「悲しみ」を私は強く感じます。いつまでもこういう気分で生きていたいという願望のようなものが、曲全体に横溢しているような気がしてなりません。まさに室内楽の魅力ここに極めリ、と言った感のあるロマンの香りと旋律の美しさ、絶妙の和音の響きの美しさなどが味わえる音楽です。愛聴盤(1)アルトゥール・ルービンシュタイン(P)、ヘンリク・シェリング(Vn)、ピエール・フルニエ(チェロ)(RCA原盤 1974年9月録音 BVC35072 (旧R25C-1070) カップリングはシューマンのピアノ三重奏曲です。(2)ジョス・ファン・インマーゼル(P)、アンナー・ビルスマ(チェロ)、ヴェラ・ベス(Vn)(VIVARTE原盤 ソニーレコード SK62695 1996年4月録音)カップリングはシューベルトのピアノ三重奏曲第2番です。
2010年08月28日
コメント(0)
-
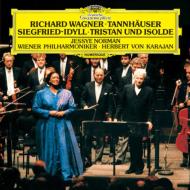
ジークフリート牧歌
「名曲100選」 ワーグナー作曲 「ジークフリート牧歌」リヒャルト・ワーグナー(1813-1883)と言えば「楽劇」というオペラのジャンルに新しいスタイルを確立した作曲家で、楽劇「ニーベルングの指環」や「トリスタンとイゾルデ」、「ニュールンベルグの名歌手」や、楽劇を確立する前の歌劇「さまよえるオランダ人」や「ローエングリン」などの名作オペラを書いて、ワーグナー音楽を好きで愛する人たちを「ワグネリアン」と呼ぶほどの人気のある作曲家であり音楽です。現在もスイスのルッツェルン郊外にワーグナーの住んでいた家が記念館として保存されています。風光明媚なルッツェルン湖を眺めおろす素晴らしい風景を楽しめる小高い丘に建っています。 私は在職中にスイスへ行った時にこの「ワーグナー記念館」を訪れたことがあります。その記念館はワーグナーがコジマト過ごした館で、玄関を入ると素晴らしい螺旋階段があります。それを見た時に思い出したのが17人のオーケストラ奏者と指揮するワーグナーが、その螺旋階段に立って「ジーグフリート牧歌」を演奏したことでした。ワーグナーは56歳で妻コジマとの間に3番目の子供として初めて長男を授かり、「ジークフリート」と命名してその喜びを表す為に彼はコジマに一曲の音楽を贈ったのです。 その曲が「ジークフリート牧歌」で、贈られた日がコジマの誕生日でした。ワーグナーの妻コジマは、あの有名な作曲家フランツ・リストと当時の名ピアニストと言われたマリー・ダグーとの同棲中に生れた娘で、伝説的名指揮者ハンス・フォン・ビューローの妻でしたが、ワーグナーに惚れて彼の許に走ったのです。 ビューローはワーグナーの弟子で、コジマとビューローとの間に二児がいました。 ワーグナーはそれまでの借金生活が嘘のようにバイエルン国王の寵愛で年金を授けられて不自由のない生活をしていた頃の話です。ワーグナーにはバイエルン国王からミュンヘン近くに別荘を提供されるほどの寵愛を受けていました。 その別荘に落ち着いた時に、ワーグナーはビューローの家族を別荘に招きました。ワーグナーの成功を喜んだ弟子ビューローは、別荘でのワーグナーの身の回りの世話をさせるために、妻コジマと子供二人を先に別荘に行かせたのでした。 それが間違いのもとで、ワーグナーとコジマはビューローが別荘に来るまでにただならぬ関係になってしまっていました。 ワーグナーが51歳の1864年のことでした。その翌年(1865年)にワーグナーは楽劇「トリスタンとイゾルデ」の初演に大成功を収めます。 初演の指揮は勿論ハンス・フォン・ビューローでした。 そしてビューローがこの初演に情熱を傾けていた頃に、コジマはビューローの子として3人目の女の子を産んでおり、その子に「イゾルデ」と命名しています。 しかし、実の父親はビューローでなく、ワーグナーだったそうです。 何とも皮肉な話です。楽劇「トリスタンとイゾルデ」は1859年(46歳)に完成されていますが、この時もワーグナーは不倫騒ぎを起こしています。 不遇の時代を支えた豪商ヴェーゼンドンクの妻マティルデと不倫の恋に落ちていたのです。この歪んだ恋が「トリスタンとイゾルデ」を書かせる原動力になったのではないかと穿った見方をしてみたくもなるエピソードです。いずれワーグナーとコジマの正式結婚に至る経緯は他の機会に書くことにしますが、長男「ジークフリート」が生まれた時にはワーグナーとコジマの生活は正式な夫婦として成立していなかったのです。話は「ジークフリート牧歌」に戻ります。1870年12月25日の朝、目覚めたコジマは部屋の外の物音に気づいて寝室を出ました。 すると寝室に通じる階段には17名の楽団員が並んでいて、ワーグナーの指揮でこの曲の演奏を始められ、これが夫ワーグナーの自分への誕生日(12月25日)の贈り物と知ったのでした。楽劇「ジークフリート」が作曲されている頃の音楽で、「愛と平和の動機」、「ワルキューレの眠りの動機」、「ブリュンヒルデの叫びの動機」、「活躍するジークフリートの動機」、「鳥の声の動機」など、実にのどかな、時には静謐な音楽空間が広がり、幸せな気分に包まれた極上のサウンドが聴く者を酔わせます。愛聴盤 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル ミュージック UCCG4504 1987年ザルツブルグライブ)歌劇「タンホイザー」序曲ジークフリート牧歌楽劇「トリスタンとイゾルデ」から 第1幕前奏曲 イゾルデの愛の死が収録されており1987年のザルツブルグ音楽祭での公演ライブ盤。ジェシー・ノーマンの「イゾルデの愛の死」は、オペラ舞台で彼女のイゾルデを聴けないだけに貴重な演奏会記録です。 ジークフリートではウイーンフィルのビロードの肌触りのようなサウンドを楽しめ、「トリスタンとイゾルデ」ではこれほどの官能をこの年で、と思うほどのむせ返るような法悦を聴かせてくれるカラヤン最晩年の演奏記録を味わえます。上記商品番号は最新(2009年再発売)のものです。
2010年08月27日
コメント(2)
-
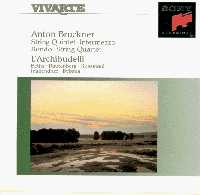
弦楽五重奏曲
「名曲100選」ブルックナー作曲 弦楽五重奏曲 ホ長調アントン・ブルックナー(1824-1896)が書き残しましたこの弦楽五重奏曲は、交響曲第5番、第6番の時代の1879年7月に完成されており、ハイドンやモーツアルトの古典派室内楽作品はもとより、ベートーベンのような古典派からロマン派への移行も窺える作品でもなし、シューベルトのようなロマンの薫りが零れ落ちそうな音楽でもない、ブルックナーの交響曲に表現されている音楽がそのまま弦楽5本の楽器で奏でられているような音楽です。つまり普段聴いています弦楽による室内楽でも、室内楽作品という概念を超えた交響楽的な響きのある音楽が特色となっている作品です。 ブルックナーの交響曲と言えば、長大で、重厚で、ものすごく渋い、オルガン的な響きが特徴なんですが、そういう彼の音楽を敬遠される方には、そんな交響曲的な響きのある室内楽なんてまっぴらです、という声が聞こえてきそうですが、室内楽を愛好される方であればきっとこのシンフォニックな、一風変わった音楽に共鳴されるはずです。交響楽的と言っても、音楽はあくまでも室内楽作品で弦楽器5本による和声の響きがとても美しく、第3楽章の「アダージョ」は筆舌に尽くしがたい、この世の音楽とも思えないほどの美しさと気品に溢れた音楽を聴くことができます。現代ではブルックナー音楽の演奏・録音は、ほとんど交響曲に限られています。それはブルックナーが作曲した室内楽は、極めて少ないからです。弦楽五重奏曲はこの紹介曲だけですが、他には弦楽四重奏曲やピアノ作品なども数少ないのですが書かれています。五重奏曲の曲として「インテルメッツォ」が一つありますが、五重奏曲の第2楽章「スケルツォ」が当時としては演奏が非常に難しいと言われて、ブルックナー自身が、それではとばかりにこの「インテルメッツォ」を替わりの音楽として書いたそうです。CDへの録音にはこの「インテルメッツォ」が含まれていることが多いですね。 尚、この代替音楽はブルックナーの生前には演奏されなかったそうです。愛聴盤 ラリッキブデッリ(ヴェラ・ベスーVn、アンナー・ビルスマーチェロ、他)(SONY CLASSICAL SK 66251 1994年5月録音 輸入盤)「インテルメッツォ」、弦楽四重奏曲 ハ短調も収録されています。
2010年08月26日
コメント(0)
-
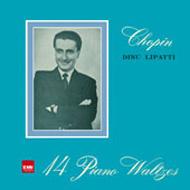
ショパン 「ワルツ集」
「名曲100選」 ショパン作曲 「ワルツ集」フレデリック・ショパン(1810-1849)が亡くなったあとに、彼の机の抽斗から一通の封筒が出てきたそうです。 その封筒には「わが悲しみ」という言葉がポーランド語でショパンの自筆で書かれていたそうです。 リボンで結ばれていて、彼の生前には誰も目にしないように、大切に保存しておいたのでしょう。 封筒の内には手紙が入っていて、それはマリア・ヴォジンスカという女性と彼女の母親からの手紙でした。ショパンは生涯に3人の女性を真剣に愛したと言われています。 そのうちの一人がこのマリアでした。 二人は幼馴染みで、彼女の家は伯爵家でしたが、ショパンの母がこの伯爵と遠縁にあたる筋という縁から、二人は子供の頃からよく遊んだという仲だったそうです。有名なショパンのポーランド脱出が20歳の時で、パリに住んだ彼はそれ以後一度も祖国に戻っていません。 それで伯爵家との縁も無くなり、マリアとも会うことなく月日が流れて行きました。ショパン25歳の時に、彼の両親が湯治旅行に出かけ、その時ばかりはショパンも出かけて行き、その帰りにドレスデンで伯爵家族と思いもかけない劇的な再会を果たします。伯爵家は、ショパンを歓迎して昔と同じ交際を続けてくれたのですが、彼はそれよりもマリアが美しい娘に成長しているのを見て、恋心が芽生えてきました。翌年も二人は再会して熱い恋心を育んでいったのでしょう、ショパンは彼女にプロポーズをしたのですが、結局伯爵家との家柄の違いとショパン自身の病弱を理由に、この婚約話は暗礁に乗り上げます。その2年後にショパンは病に倒れてしまいます。 その頃にマリアとその母親から冒頭に書きました手紙が届いていたのでした。ショパンは「ワルツ第9番変イ長調」をマリアに捧げ、その楽譜を自分の机の奥深くにしまいこんでおり、この曲はショパンの生前には演奏されることも出版されることもなかったそうです。これが「ワルツ第9番」が「別れのワルツ」と呼ばれている所以です。ショパンはその生涯にワルツを20曲以上作曲したと言われています。 「ワルツ」はもともと踊る為の音楽ですが、ショパンのそれはダンス用に書かれた音楽ではなくて、ワルツの形式とリズムを使って書かれたもので、あくまでも詩的に心象を表現した曲集です。愛聴盤 (1)ディヌ・リパッティ(ピアノ)(EMI原盤 東芝EMI TOCE14026 1950年録音)軽やかさとエレガント、詩情豊かに紡いでいくピアノ音楽の白眉とも呼べる世界がここにあります。 60年前の古い録音でモノラルですが、訴えてくる音楽に圧倒されます。(2)アルトゥール・ルービンシュタイン(ピアノ)(RCA原盤 BMGジャパン BVCC37669 1963年録音)ステレオ録音ならこの盤でしょうか。 軽やかに、華麗にピアノ音楽の魅力を聴かせてくれる演奏。
2010年08月25日
コメント(0)
-
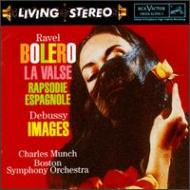
ボレロ
「名曲100選」 ラヴェル作曲 「ボレロ」このモーリス・ラヴェル作曲の「ボレロ」は、もともとフランスのバレエ団の舞台上演用として書かれた音楽ですが、 初演は管弦楽コンサートで行われれたそうです。とにかくこの曲は、音楽常識からしますと完全に常軌を逸脱した音楽なのです。 曲の始まりは小太鼓。 CDで聴いていても思わず音量つまみを上げてしまうほど小さな小太鼓の音が「タン・タタタタン、タン・タタタタン・・・・」と単調なリズムを刻んで始まります。 そうしているうちにフルートがどこかエキゾチックなメロデイーを吹き始めます。 続くクラリネットが後半の旋律を引き継いで吹き始め、2つの旋律を別の楽器が延々と引き継いでいくのです。その間小太鼓で、相変わらずあの始まりの単調なリズムが間断なく刻まれており、しかも執拗に繰り返される2つの同じ旋律が延々と楽器を変えて演奏され続け、やがて音量を増していき、フルオーケストラでリズム、同一メロデイー、響きが一体となって音楽はそのままクライマックスを迎えて、まるで爆発するかのように転調した瞬間に音楽が終るという曲なのです。 音楽の終焉はまるで階段から人が転げ落ちたかのような終り方です。演奏時間 約15分の曲です。二つの旋律、主題とリズムだけが楽器を替えることだけで始まりから最後まで繰り返される音楽はこの1曲だけではないでしょうか。ラヴェルは旧ロシアの作曲家ムソルグスキーが書きましたピアノ曲「展覧会の絵」を華麗な管弦楽作品に編曲して、現代でもオーケストラ作品としては最もポピュラーな曲に仕立てあげているように、「オーケストレーションの魔術師」と呼ばれた人でした。 この「ボレロ」でも旋律を演奏させる楽器の音色、彩りなど計算し尽して書かれているように思えます。 ストラビンスキー(作曲家)がラヴェルを評して「スイスの時計師」と呼んだそうですが、オーケストラを知り尽くした正確無比な音楽設計を評してのことでしょう。 この「ボレロ」はそれほど人を喰ったような音楽であり、興奮させる音楽、そして最後には感動させる音楽です。ラヴェルはその後交通事故に遭い、脳が少しずつ縮小していく残酷な脳障害に冒されました。 彼の頭の中では新しい音楽が鳴り響いていても、それを楽譜にして音楽にすることができなくなっていったのです。 亡くなる直前まで脳は理性を保ち、音楽を鳴らせているかのような残酷な運命を与えられたそうです。そして、あたかもこの「ボレロ」の終結が突然転調して爆発的に曲を閉じたのと同じように、彼自身も頭の中で音楽を響かせながら悲劇的にその生涯を閉じたのです。この曲を聴くたびに、私は彼の生涯の終焉でのわずかな期間の、階段から転げ落ちたような、悲劇的な人生に思いを馳せるのです。愛聴盤シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団(RCAレーベル 61956 1956年録音 海外盤)この曲は15分程の曲だからフランス音楽集だとか、ラヴェル音楽集とかのタイトルCDならほとんどと言ってもいいくらいに収録されている曲。 どうしても複数枚所有することになってしまう。 そうした中で、エルネスト・アンセルメ(スイス・ロマンド管弦楽団)盤と並んで好きな演奏・録音盤。 ステレオ初期の54年前の録音ですが音質は美しく古さも感じません。ボストン交響楽団の各プレイヤーの美演に酔える演奏です。
2010年08月24日
コメント(0)
-
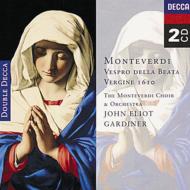
聖母マリアの夕べの祈り
「名曲100選」 モンテヴェルディ作曲 「聖母マリアの夕べの祈り」12歳の時からクラシック音楽を聴き続けていますが、49年間の間に数え切れないほどの曲を聴いて、そのほぼ大多数の曲に感銘を覚えてきて、それらをこの日記で紹介していますが、それらの感動を覚えて中でも忘れられない曲というのがいくつかあります。 ベートーベンの第9交響曲であったり、マーラーの「大地の歌」であったり、ショパンのピアノ曲であったり、チャイコフスキーやドヴォルザーク、ブラームスの作品だったり。そういう魂を揺さぶられるほど感動した曲から一つ選んでみました。イタリアの作曲家モンテヴェルディ(1567-1643)が書き残した「聖母マリアの夕べの祈り」です。 独唱、合唱、通奏低音、を伴った管弦楽で演奏される一種の合唱曲のような曲ですが、イタリア初期バロック音楽の時代から400年を経ても今尚輝きを失わない不滅の音楽として、聖母マリアの肖像のように燦然と輝いている美しい音楽です。このCDを購入したのが1994年11月。今から16年前に2枚組廉価盤として再発売されたのをほとんど衝動買いで求めた盤でした。自宅に持って帰ってもすぐには聴かずに2~3日はプレーヤーに置いたままでした。それまでにこの曲の名前も知らず、音楽も聴いたことはなく、まあ秋の夜に聴くのにいいかなと何気なく買ったものでした。聴き始めて驚きました。たかだか教会音楽だろうと思っていたのが、これほど深い味と滋味に溢れた音楽にただただ茫然自失の状態で聴いていました。まるで天使の声とはこのことか、天上の音楽とはこのことか、心を癒す音楽とはこのことか、色々な想いをめぐらせながら100分間ほどの至福の時空を過ごしていました。音楽は純粋な祈りに満ちており、純粋無垢な美しいカトリックの教会音楽のような旋律に全編に紡ぎ出されていて、聴いている間は無上の愉悦、喜びがひしひしと伝わってくる音楽で、初めて聴いた時から3ヶ月もの間、来る日も来る日もこの音楽を聴いていました。白眉は「マニフィカート」で、古雅な趣きを伴いながらグレゴリオ聖歌を男性コーラスが歌う様は、聖母マリアの肖像画のような気高い佇まいを見せている音楽です。 文字通り「マニフィカート」(崇める)を覚える音楽です。愛聴盤 ジョン・エリオット・ガーディナー指揮 モンテヴェルディ管弦楽団・合唱団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・クラシックス UCCD3088 1974年録音)
2010年08月23日
コメント(0)
-
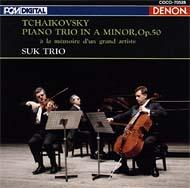
偉大な芸術家の思い出
「名曲100選」 チャイコフスキー作曲 ピアノ三重奏曲イ短調 「偉大な芸術家の思い出」作曲家にとても親しい友人や先輩、師匠がいて、その人たちが亡くなると懇意にしていた作曲家がその人の思い出をこめて音楽を書くということがよくあります。 そういう曲の中でも有名な1曲があります。チャイコフスキーが作曲しましたピアノ三重奏曲イ短調 作品50「偉大な芸術家の思い出」です。チャイコフスキーにとって「偉大な芸術家」とは、モスクワ音楽院の設立者であり、ピアノの名手だったニコライ・ルビンシテインのことです。 チャイコフスキーが音楽院の教授として迎えられてからその親交が始まったのですが、彼の曲の初演や音楽への助言などもおこなっていたそうです。ところが、チャイコフスキーが書いた「ピアノ協奏曲第1番」については、ルビンシュタインに助言を求めなかったことで、この親友はへそを曲げてしまい、完成後に楽譜を親友に見せに来たチャイコフスキーに散々な酷評を述べたために、さすがのチャイコフスキーも怒ってしまい不仲となりました。実は、このピアノ協奏曲はルビンシテインに捧げるつもりで書かれていて、楽譜にもそう書くつもりだったそうです。その後この協奏曲はまったく手を加えることなく出版されて、曲は名指揮者ハンス・フォン・ビューローに捧げられてニューヨークで初演されました。しかしその後二人は元の仲に戻り、再び親交を深めるようになりました。再び戻った友情でしたが、そのルビンシュテインが46歳の若さでフランス・パリで亡くなり、チャイコフスキーはその死を嘆き悲しみ、親友の死を悼んで書いたのがこの曲です。曲の冒頭、ピアノの分散和音に乗ってチェロが奏でる深い悲しみに溢れた旋律が流れると、そこはもうチャイコフスキーの世界で、ルビンシュタインを思う気持ちが切々とあふれ出ています。 曲は2楽章構成で、第1楽章はこのチェロで流れる旋律がヴァイオリン、ピアノに引き継がれて連綿と悲しみを歌い上げています。この曲の白眉が第2楽章で、民謡調の旋律がピアノ独奏で流れ出し、ヴァイオリン、チェロを交えた11の変奏が繰り広げられます。 最も活躍するのはピアノで、ここにもピアノの名手ルビンシュタインへの想いが溢れているのでしょう。2部構成の第2楽章で、変奏の終曲と終結部が第2部で、ここでは親友の死を悼みながら悲しみながらも静かに思い出に耽っていたチャイコフスキーが、なりふり構わず泣きじゃくっているかのようで、第1楽章の主題がヴァイオリンで奏されてクライマックスを迎えるところなどは、泣きに泣くヴァイオリンの旋律が胸をしめつけてきます。 やがて静かに、静かに、ピアノとチェロが消え入るように音を刻みながら曲を閉じます。 愛聴盤 (1)スークトリオ(DENON レーベル COCO70528 1976年録音)スケールの大きさではモノラルの名盤 ロストロポービチ、コーガン、ギレリスの演奏に匹敵する録音で、第1楽章の迫力には圧倒されます。 深い哀切を刻んだ第2楽章がとりわけ共感を呼ぶ名演だと思います。 (2) バレンボイム(P) デュ・プレ(チェロ) ズーカーマン(Vn)(EMI原盤 EMIジャパン TOCE14315 1972年ライブ録音)デュ・プレの貴重な演奏記録。モノラル録音ながら切々と迫りくるチェロの旋律が、後になって知る彼女の死への病と重なって涙した演奏。独りよがりなお薦め盤ですが、この曲の演奏となると外せない録音盤。
2010年08月22日
コメント(0)
-
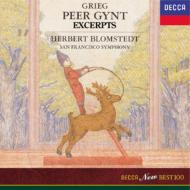
ペール・ギュント
「名曲100選」 グリーク作曲 劇音楽「ペール・ギュント」北欧のノルウェーは、国土の1/3が北極圏に入っている国で、土地の大部分が山地です。 私がオスロを訪れたのがいつも冬のために、この海岸線のクルージングが出来なかったので、実際には見ていないのですが、ここの海岸線は「フィヨルド」と呼ばれる入り組んだ地形で、まるで切り刻まれたような形をしています。 そういう地形が国民性を育てていったのでしょうか、こういう地形によって海への航海術に優れていたのでしょう、「ヴァイキング」と呼ばれるヨーロッパの海岸線を巡って、強奪、略奪を繰り返す「海賊」の発祥地でもありました。現地の人に聞いた話ですが、コロンブスのアメリカ新大陸以前にこのヴァイキングがすでに新大陸に足を降ろしていたそうです。 富と冒険を求めて航海可能なところには勇敢に乗り出して行ったのでしょう。こういうノルウェーには有名な文豪イプセンがいます。 この人は「人形の家」や「野鴨」などの現代でも上演されています戯曲で有名な人です。 特に「人形の家」は、ヒロインのノラが夫に向かって叫ぶ言葉ー何よりも第一に、私は一人の人間です。 あなたと同じように」-は女性解放の高らかな宣言として有名です。 こういう社会問題とまったくかけ離れた戯曲も、イプセンは書いています。 ノルウェーに伝えられる「ペール・ギュント伝説」を戯曲にして冒険好きな国民性を描いてみせたのです。この戯曲の舞台上演に際して、イプセンは劇的効果を高めるために付随音楽を使いたいと願って、自国の作曲家グリーグ(1843-1907)にその音楽の作曲を依頼しました。 それが今日、優れたオーケストラ作品として親しまれています劇付随音楽「ペール・ギュント」です。主人公は冒険好きなペール・ギュントで、婚約者の女性ソルベイクがいるにもかかわらず、村を飛び出して結婚式最中の花嫁を奪ったり、魔王の娘をたぶらかして殺されそうになったりした挙句に、アメリカ新大陸に渡って巨万の富を手に入れて祖国に帰る航海中に嵐に遭い、一命を取り留めたものの無一文となって村に帰ってくると、白髪となったあのソルベイグが彼の帰りを待っていてくれたのです。 「私を救ってくれたのは君だ」と泣き崩れるペール・ギュントは彼女の膝を枕に、静かに安からに死を迎えるのでした。初演後、グリーグは全23曲から4曲ずつを選び、演奏会用組曲としました。 それが第1組曲、第2組曲です。愛聴盤 ブロムシュテット指揮 サンフランシスコ交響楽団(Decca原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCD5039 1988年録音)20曲を選び、物語順に演奏され、台詞も入っておりほぼ舞台上演に近い形の演奏・録音です。
2010年08月21日
コメント(0)
-
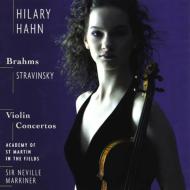
ブラームス ヴァイオリン協奏曲
「名曲100選」 ブラームス作曲 ヴィオリン協奏曲ニ長調ヨハネス・ブラームス(1833-1987)はヴァイオリン協奏曲を1曲だけ書き残しています。1878年、ブラームス45歳の作品です。作曲家が協奏曲の名曲を生み出すきっかけは独奏楽器の名手との出会いがあります。 モーツアルトとクラリネット奏者シュタットラーの出会いによる名曲「クラリネット協奏曲」や、チャイコフスキーとピアノのニコライ・ルービンシュタィンの出会い、ブラームスとクラリネット奏者ミュールフェルトの出会いで生まれた名曲「クラリネット五重奏曲」などが挙げられます。このヴァイオリン協奏曲も、当時名ヴァイオリニストであったと言われているヨアヒムとの出会いで生まれています。 ヨアヒムは自らも3曲のヴァイオリン協奏曲を書いたと言われているほど、ヴァイオリンについての当時第一人者であったようです。そのヨアヒムに作曲家と早くから認められていたようで、友情さえも生まれているようです。この作曲に関してヨアヒムに意見を求めるなど、ブラームスはまるで共同作業のように書かれたと言われています。ブラームスはユーゴスラヴィアの近くのペルハッチャという所の美しい自然を愛していたようで、音楽全体が「田園」を想像するような交響曲第2番もこのベルハッチャで書かれているのですが、ヴァイオリン協奏曲もここで書かれているためでしょうか、牧歌的な情緒が第2楽章に色濃く陰を落としています。ピアノ協奏曲などと同じように、この曲もブラームス特有のオーケストラ部は分厚いハーモニーと交響楽的な響きを持っています。まるで交響曲のようなオーケストラパートは、独奏ヴァイオリンを圧倒しているので、ソロ・ヴァイオリンはその音に負けずに弾くことは、大変だろうと思います。しかし、こうした響きの管弦楽にも負けぬ独奏ヴァイオリンは、詩的な情緒を醸し出していて、しかもオーケストラに一歩も引かない迫力を備えていて、しかも情熱的で熱情さえ感じられる力強さを感じます。ベートーベンやメンデルスゾーンの協奏曲のような旋律性に富んだ曲とは違って、親しみにくいところもありますが(約50年前にはこの曲や同じブラームスのピアノ協奏曲などは、音楽評論家たちから交響楽的響きで聴きづらい音楽などと書かれていたのを思い出します)、やはりブラームスらしい渋い趣きの、しかし美しい曲です。愛聴盤 (1) ヒラリー・ハーン(Vn)ネヴィル・マリナー指揮 イギリス室内管弦楽団 (SONY SK89649 2001年6月録音 輸入盤)この録音当時はまだ20歳くらいだったと思いますが、ハーンの弾くヴァイオリンの音色は第1楽章の主題からして惹き付けられる冴えた技巧で、輝くような音色を楽しめる1枚です。(2) ムター(Vn) カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー(ドイツ・グラモフォン 445515 1981年録音 海外盤)まさに豊穣と言える天才少女ヴァイオリニストがカラヤンに見出されて、秘蔵っ子として以降カラヤンに帯同して世界をめぐるコンサートツアーに旅立った記念碑的な演奏。 カラヤンをあまり好まない(オペラ以外)私もこのブラームスには脱帽する、カラヤン美学が曲の隅々まで琢磨された演奏で、誰もが納得の素晴らしいディスク。 ベルリンフィルの見事なアンサンブルには言葉もありません。(3) ムター(Vn) クルト・マズア指揮 ニューヨークフィル (ドイツ・グラモフォン 457075 1997年録音 海外盤)81年のカラヤンとの共演から16年。 このディスクにはムターの成長が鮮やかに刻み込まれています。 ものすごく官能的な音色、表情付け、テンポが遅くフレージングにムターの息遣いが聴き取れるような、むせ返るほどの熱演。 81年盤との比較試聴も面白いディスクです。(4) ムローヴァ(Vn) アバド指揮 ベルリンフィルハーモニー(Philips 4757454 1992年1月 東京ライブ)アバド、ベルリンとの夢の競演を行った東京の演奏会ライブ録音。 ムローヴァの美しい音色、伸びのいい高域での美音、表情豊かな音楽性がアバドの指揮によるベルリンフィルとの美しいアンサンブルに溶け合った、コンサートでの記録。
2010年08月20日
コメント(2)
-
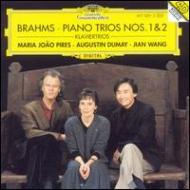
ブラームス ピアノ三重奏曲
「名曲100選」 ブラームス作曲 ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 作品8今日は叙情性豊かな室内楽の名作です。 ヨハネス・ブラームス(1833-1897)を好きな私には100選には落とせない名品。 ブラームスの初期の名品「ピアノ三重奏曲第1番」です。実はこの曲との触れ合いはまだ新しく、下に紹介しましたCDを買って聴いたのが初めてですので、まだ10年くらいの付き合いの曲です。ブラームスは4曲のピアノ三重奏曲を書き残していますが、普通は作品番号の付された第1番~第3番までが彼の三重奏曲と呼んでいます。これらの3曲は初期、円熟期、晩年の3期にわたって1曲ずつ書かれています。今日の話題曲の第1番はブラームス22歳の1855年に完成している、青年ブラームスの覇気の伝わってくる曲で、いかにも北ドイツの生まれと連想させるほどに雲の垂れ込んだような、渋く、くすんだような北ドイツの空の色彩と厚い和声に包まれたほの暗い情緒が特徴の音楽です。 曲は4楽章で構成されています。ピアノソロが抒情的で豊かな響きで奏でる旋律のあとのチェロ、そしてヴァイオリンが加わって進んでいく、明るく、若々しさに溢れた豊かな抒情性の第1楽章は、まるで一日の終わりの夕暮れの、のどかさを感じさせるロマンティックな音楽です。親しみやすい旋律と魅力ある楽想のスケルツォの第2楽章。宗教的とさえ形容できそうな神秘的なアダージョの第3楽章。ピアノが華麗に、輝くように音楽を盛り上げる第4楽章。好きな珈琲を味わいながら聴くこのブラームスも、これからやってくる涼しい秋の夜長の静けさを演出してくれる、味わい深い演奏時間約38分の室内楽作品です。 初演は1854年3月26日に、クララ・シューマンのピアノで非公開で行われ、1855年11月27日にニューヨークで公開の初演が行われています。愛聴盤 ピリス(P)、デュメイ(Vn)、ワン(チェロ)(ドイツ・グラモフォン 447055 1995年4月録音 輸入盤)
2010年08月19日
コメント(0)
-
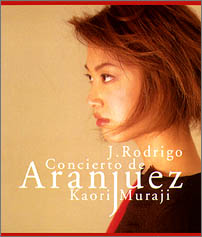
アランフェス協奏曲
「名曲100選」 ロドリーゴ作曲 「アランフェス協奏曲」アメリカの作家アーネスト・ヘミングウエーは、1930年代の「スペイン革命」に参加して、スペインに長く滞在しており、パエリアに代表されるスペイン料理やビーノ(地酒ワイン)、それに美しいセニョリータの笑顔、人の心に情熱をかきたたせるフラメンコダンスとスパニッシュギターの音色や、生と死の境に立つ闘牛をこよなく愛した作家で、長編小説「誰がために鐘は鳴る」「日はまた昇る」、ノンフィクション「午後に死す」などを書き残してとても熱くスペインの情緒を語っています。そのヘミングウエーと同じ時代に、盲目のスペイン生まれのホアキン・ロドリーゴ(1901-1999)がいました。 3歳で目の障害を患って以後盲目に近い状態が、亡くなるまで続きました。「アランフェス」は首都マドリードから南へ50kmほど離れたところにあり、スペイン黄金時代に200年かけて建てられた壮麗な離宮やスペイン随一と言われる美しい庭園があります。 私は若い頃に欧州出張の際にこのアランフェスを訪れたことがありますが、乾燥地帯の多いスペインには珍しく、豊かな水と深い緑の森に囲まれた小さい、しかし、美しい町を見て感動した思い出があります。その「アランフェス」にトルコ人で生涯ロドリーゴを支えていた妻と共に彼は訪れています。 そして頬を撫でる風、木々を吹きそよぐ微風、鳥たちのさえずりや鳴き声、川のせせらぎの音などを、目にすることが出来なくてもその空気に触れた感じをまるで目にしたかのように音楽で表現したのです。 そこに立った時にこの「アランフェス協奏曲」の構想を練っていたと語っていたそうです。曲は3つの楽章から成り、第1楽章冒頭のギターがかき鳴らす舞曲風の陽気で明るい序奏からもう私たちはスペイン情緒に包まれています。明るく、明快なテンポのいい旋律が聴く者をスペインへと運んでくれるかのようです。第2楽章は、オーボエのソロと哀切の旋律を奏でるギター、それをバックアップするオーケストラの豊穣で寂しげな音楽は、後に「恋のアランフェス」と呼ばれるほど有名な、筆舌に尽くし難い美しい旋律が私たちを魅了してやみません。クラシック音楽を聴いてなくても、この曲の名前を知らなくても、一度この第2楽章の旋律を聴くと忘れ難い音楽となり、心に沁み込んでくること請け合いの曲です。愛聴盤 1. 村治香織(ギター) 山下一史指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団 (ビクター レーベル VICC-60154 1999年12月 東京録音)若い村治香織の演奏を採り上げました。 超優秀録音の美しい仕上がりの録音です。2. ナルシソ・イエペス(G) アンドレ・ナヴァロ指揮 フィルハーモニア管(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCG5034 1979年録音)3.ぺぺ・ロメロ(G) ネヴィル・マリナー指揮 イギリス室内管弦楽団(Philps原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7045 1978年録音)イエペス、ロメロの演奏を聴きますとさすがにスペインの土の香りが匂ってきそうな、土着の音楽性と現代的な野生の味のするオーケストラ演奏など、私にはどうしてもこの2点で挙げざるを得ない不朽の名演盤で、価格もどちらも1000円盤としての再発売ですから、初めてお聴きになる方にはこれら2点を薦めています。
2010年08月18日
コメント(0)
-
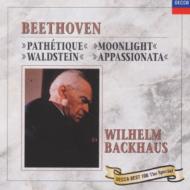
「熱情」ソナタ
「名曲100選」 ベートーベン作曲 ピアノソナタ 第23番「熱情」 作品57J.S.バッハの「平均律クラヴァイーア曲集」がピアノ音楽の「旧約聖書」と呼ばれ、ベートーベンの書いた32曲のピアノソナタが「新約聖書」と呼ばれていますが、音楽史上に燦然と輝くピアノ音楽の金字塔のようなベートーベンのソナタの中でも、最高傑作に数えられているのが第23番「熱情」です。どの音楽でも副題が付けられている曲には親しみが持てるものです。 音楽には「絶対音楽」と「標題音楽」という大きな分け方がありますが、副題とか標題のない曲よりもあった方が親しみを感じます。 交響曲でもベートーベンの「田園」とかチャイコフスキーの「悲愴」、ドボルザークの「新世界より」などがあります。 聴く前から何となくイメージしやすいのでしょうか。ベートーベンのピアノソナタにも副題のついている曲が多くあります。 「悲愴」「月光」「ワルトシュタイン」「告別」「テンペスト」そしてこの「熱情」です。しかし、この「熱情」は彼自身が付けたものでなくて、曲のイメージから出版社によって付けられたそうですが、じつに楽想を言いえて妙なる名前です。私とこの曲との出会いは48年前でした。 カール・シューリヒト指揮 パリ音楽院管弦楽団の7枚組のベートーベン交響曲全集を、美容院を経営していた母親のポケットマネーから買ってもらった時に、自分の小遣いで1000円のモノラル録音25cmLPで、バックハウスの録音盤を衝動買いで購入したのがこの「熱情」ソナタでした。 以来社会人になるまでこのLPで聴いていましたが、とうとう聴くに堪えないほど盤にキズがついて処分したのが懐かしい思い出です。この「熱情」ソナタには有名なエピソードがあります。 ベートーベンにはフェルディナンド・リースという弟子がいました。 夏のある日、避暑地で過ごしていた二人は林や森を散策していました。 その時にベートーベンは歩きながら何やら口の中で唸っていました。曲想のインスピレーションが湧いてくると、旋律の断片を口ずさむのが、ベートーベンの習慣だったそうです。一休みしていると遠くから笛の音が聞えてきました。 その音色がとても牧歌的でリースはとても感動して隣のベートーベンにそれを話すと、まるで笛の音が聞えていないような素振りでした。 その時にリースは自分の師が耳の病に冒されていると確信した最初の出来事だったようです。散歩から帰ったベートーベンがすぐにピアノの前に座り、リースに新しい曲だと言って弾き始めました。それが「熱情」ソナタの終楽章だったそうです。この曲は、有名な交響曲第5番「運命」を構想中に完成された曲で、「運命の動機」と呼ばれている有名な三連音符の「ダ・ダ・ダ~ン」が各楽章に散りばめられていて、このソナタの激しい楽想を雄弁に表現しています。ピアノで紡ぎ出される音楽は、雄渾で力強く、激しく燃焼するかのような、まるで炎の塊のようなベートーベンの情熱が迸る曲となっています。リースが伝え遺している森の中での、ベートーベンの難聴への想いとそれと対峙していく激しく、厳しい決意の表われかなと、このソナタを聴くとそういう風に思えてきます。第1楽章、終楽章(第3楽章)は「熱情」そのものの楽想ですが、私はむしろ第2楽章のアンダンテ・コン・モートの主題が八分音符、十六分音符、三十二分音符に変奏されていくさまの美しさが一番好きなところです。愛聴盤ウイルヘルム・バックハウス(ピアノ)(デッカ原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7002 1959年録音)上の日記に書いたモノラルLP盤と同じ録音です。LP時代も含めて限りなく再発売されている演奏で、私が最も気に入っている演奏です。この紹介CDは1000円の廉価盤で、「月光」「悲愴」「ワルトシュタイン」を収録したお買い得ディスクです。
2010年08月17日
コメント(2)
-

子供の情景
「名曲100選」 シューマン作曲 ピアノ曲集「子供の情景」ロベルト・シューマン(1810-1856)の最も有名なピアノ曲集「子供の情景」を今日は採り上げてみました。 子供が空想する、夢を見る、あるいは胸をときめかす空間を描いたのでしょうか。このピアノ曲集は「見知らぬ国より」「珍しいお話」「鬼ごっこ」「おねだり」「満足」「大事件」「トロイメライ(夢)」「炉辺で」「木馬の騎士」「むきになって」「びっくり」「子供は眠る」「詩人は語る」の13曲から成るピアノ曲集です。他にも子供への贈り物の音楽があります。 同じくシューマンのピアノ曲集「子供のためのアルバム」、ベラ・バルトークのピアノ曲集「子供のために」、それにドビッシーのピアノ組曲「子供の領分」、フォーレのピアノ組曲「ドリー」などが挙げられます。 おもしろいのはフォーレとドビッシーです。フォーレは、後にドビッシー夫人となったエンマ・ダルダックの娘エレーヌ(愛称ドリー)に6曲から成るピアノ組曲「ドリー」を贈っており、ドビッシーはすったもんだの大恋愛の末にエンマ・ダルダックと結婚して生まれた一人娘クロード・エンマに「子供の領分」を贈っています。さて「子供の情景」の音楽は、平明で簡潔で想像を誘うような旋律ばかりでどの曲も甘く美しく、優しさにあふれた傑作揃いで、聴いていてしばし子供の世界に遊ぶような気分でいられる曲ばかりです。 最も有名で美しい旋律の「トロイメライ(夢)」は後世で他の楽器などにも編曲されている人気曲です。 旋律を聴くと「あ、あの曲!」と、クラシック音楽に親しんでいない人でもいつか、どこかで聴いた曲の一つでしょう。全13曲のうち、私の好きな曲は第1曲の「見知らぬ国より」と「トロイメライ」です。 「見知らぬ国より」はいきなり子供の世界に連れ去られたような感じを受けています。この曲を聴いていますと、他の技巧を要する音楽と違って弾きやすいだろうなあと思うのですが、実際にピアノを弾いている人に訊きますと、簡潔で想像たくましくして、歌うような音と詩人になったような心で弾くことが要求されるそうです。 「音の向こうに描かれている世界を表現するのがとても難しいのですよ」と言われたことがあります。今日は子供の世界で遊んでみようと思っています。愛聴盤 1.「ホロヴィッツ・イン・ロンドン」 ウラディミール・ホロヴィッツ(ピアノ) (RCAレーベル 09026.61414 1982年5月22日 ロンドン・ライブ録音 海外盤)2.マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)(ドイツ・グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG7076 1983年録音)
2010年08月16日
コメント(0)
-

交響組曲「シェラザード」
「名曲100選」 リムスキー=コルサコフ 交響組曲「シェラザード」リムスキー=コルサコフ(1844-1908)は「ロシア5人組」という作曲家の一人で、この「5人組」とは当時のロシア音楽界の若手たちが集まって、ロシアの国民の生活・感情・精神などを民族的色彩の濃い音楽で描こうと結成されたグループでした。その5人とはバラキレフ、キュイ、ムソルグスキー、ボロディン、リムスキー=コルサコフでした。しかし、お互いに人間的に成長していくにつれ芸術がそれぞれに確立していったのでしょうか、意見の異なることが多くなり、1881年にムソルグスキーの死と共にこの「5人組」は解散しました。この5人組の中でも、一番若く華やかだったリムスキー=コルサコフは、その後富裕家の支援を借りて、ロシア国民主義音楽をさらに進めて行き、彼の「傑作の時期」と言われた1887~1888年に、「シェラザード」「スペイン奇想曲」序曲「ロシアの復活祭」などが書かれています。交響組曲「シェラザード」は、アラビア語の説話文学で、世界の国の言葉に翻訳された親しみ深い物語ですが、リムスキー=コルサコフはその中の序章にあたる部分を音楽で描いたのです。アラビア王シャリアールは名君の誉れ高い王様でした、ある日彼の愛妃が奴隷とベッドを共にしているのを見つけて即座に二人の首をはねてしまい、以降毎夜にわたり生娘を呼んで愛欲に耽り、朝になればその娘を殺してしまうという日を繰り返す暴君に変貌します。ある日、大臣の娘シェラザードが夜伽に呼ばれます。彼女は一計を案じて床に臨み、諸国の冒険談、好色談などをおもしろおかしく王に話して聞かせると、王は話の続きを聴きたくなって朝には彼女を殺さず、また次の夜に語らせるという日が続き、それが千夜一夜も続いてとうとう王はシェラザードを王妃に迎えたという有名な「千夜一夜物語」または「アラビアン・ナイト」です。「海ととシンドバッドの船」「カランダール王子の物語」「若い王子と王女」「バクダッドの祭りー海ー青銅の騎士の立つ岩での難破ー終曲」という4楽章形式の組曲です。シャリアール王の登場を表す荒々しい冒頭の音楽に続いて、「むかし、むかし・・・」と語り始めるシェラザードの旋律は独奏ヴァイオリンで、エキゾチックな東洋風の艶麗な旋律で始まります。 このシェラザードの主題が全ての楽章で表され、彼女の物語が始まることを表しています。 ヴェールを顔にかけ、シースルーの薄物をまとったシェラザードが目の前に表れるかのような実に美しい魅惑的なメロデイーです。曲全体に東洋風のメロデイーが色濃く溢れており、色彩豊かに繰り広げられ、あなたをアラビアン・ナイトの世界に導いてくれます。今日はとても個性的な表現でファンの多い「爆演型指揮者」という異名を付けられた、ロシアのエフゲニー・スヴェトラーノフの演奏をご紹介しましょう。ロシア指揮者とイギリスは交流が深いのか、ロジェストヴェンスキーというロシア指揮者も60年代からしきりにロンドンへ呼ばれてコンサートの指揮を行っていました。スヴェトラーノフは、今回はロンドン交響楽団に客演してこの「シェラザード」を振っていますが、実に個性的な演奏です。 私はカラヤンとベルリン・フィル、ストコフスキーとロンドン交響楽団の演奏したCDを最もよく聴いていますが、このスヴェトラーノフの演奏も個性的でおもしろいディスクの一つです。 徹底的にロシア色に染め上げた、極彩色の大伽藍絵巻のような、スペクタクルな表現を聴く者を圧倒してきます。 私はスヴェトラーノフの演奏を一言で表現するときは「重戦車」という例えをよく使いますが、まさにこの演奏もその例えにぴったりです。エフゲニー・スヴェトラーノフ指揮 ロンドン交響楽団 (BBCレーベル BBCL4121 1978年ロンドン・ライブ録音 輸入盤)
2010年08月15日
コメント(0)
-
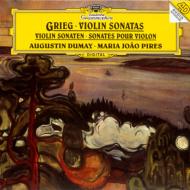
グリーグ ヴァイオリン・ソナタ
「名曲100選」 グリーグ作曲 ヴァイオリン・ソナタ第3番ノルウエーの作曲家エドヴァルト・グリーグ(1843-1907)は劇音楽「ペール・ギュント」やピアノ協奏曲イ短調、抒情組曲集などで有名な人ですが、室内楽でもいい作品を書き残しています。 チェロ・ソナタもあればヴァイオリン・ソナタも書いています。グリーグのヴァイオリン・ソナタが全部で3曲残されており、その中で最も親しみを感じるのが今日の話題曲第3番ハ短調 作品45です。 3楽章形式で全曲で25分弱の演奏時間の曲です。グリーグの音楽はノルウエーの民族色豊かな彩りを添えた物が数多くありますが、この第3番のソナタはドイツ・後期ロマン派を彷彿させる旋律と和声、リズムで彩られており、彼の3つのソナタの中でも演奏会や録音に採り上げられる機会の多い作品です。3つの楽章はすべて速いテンポの楽章で(アレグローアレグレットーアレグロ)、沈み込むような緩い楽章の調べはありません。しかし、第1楽章や第3楽章の音楽に見られるように、かなり激しい情熱が織り込まれています。第1楽章などはアレグロ・モルト・アパッショナータという指定のごとく、かなり情熱的な旋律が支配しており、緊張感漂う音楽が展開しています。特に第1主題の旋律は情熱的で聴き始めから引き込まれる大きな旋律が魅力的です。第2楽章もアレグレットでありながら「ロマンツェ」と指定されており、ロマン情緒あふれる旋律が支配しており、室内楽の醍醐味を味わうかのような魅力をたたえています。第3楽章は、これもアレグロでかなり速いテンポでヴァイオリンとピアノの駆け巡るような旋律が印象的で、力強さ前面に押し出した魅力に圧倒される音楽です。愛聴盤 オーギュスタン・デュメイ(Vn) マリア=ジョアン・ピリス(P)(グラモフォン・レーベル 4375252 1993年録音 海外盤)グリーグのヴィオリン・ソナタ全3曲を収録しています。日本プレス盤としてユニヴァーサル・ミュージックから同じ演奏・録音で1,800円盤としてリリースされています(UCCG4227)。現在ではこの日本盤の方が600円ほど安くなっていますので、日本プレス盤がお勧めです。
2010年08月14日
コメント(0)
-
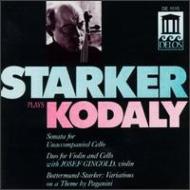
コダーイ 無伴奏チェロ・ソナタ
「名曲100選」 コダーイ作曲 無伴奏チェロ・ソナタゾルタン・コダーイ(1882~1967)は、ベラ・バルトーク(1881-1845)と並ぶハンガリーの代表的な作曲家で、最も有名な作品で演奏される機会の多いのは管弦楽のための組曲「ハーリ・ヤーノシュ」ですが、コダーイはバルトークと親友で、二人はハンガリーの民謡や民俗音楽を集めるための旅行などもおこなっています。バルトークとコダーイの違う点は、バルトークは生涯にわたって創作活動を貫いた孤独な作曲家であり、ナチス・ドイツがハンガリーに侵攻した時にはアメリカに亡命して、故郷に戻ることなく白血病で寂しく生涯を閉じました。コダーイは大戦中もハンガリーを離れることなく国民の心の支えとなり、親しみやすい音楽や、わらべ歌や民謡に基づく音楽教育を提唱した「コダーイ・システム」と呼ばれる教育メソッドで人々の尊敬を受け、戦後はハンガリー楽壇の最高指導者として数々の国際的栄誉を得た作曲家でした。コダーイは上述のようにマジャール(ハンガリー)の民族音楽に多大な興味を持ち、その音楽生活を民族音楽に捧げたと言われています。 バルトークと共にハンガリーの農村を歩いて、マジャールの伝統的な民族音楽を多数収集して研究を重ねたと言われています。さて今日の話題曲ですが、チェロ1本で演奏される無伴奏の音楽です。無伴奏の音楽といえば、大バッハの無伴奏ヴァイオリンソナタやパルティータや無伴奏チェロ組曲、パガニーニの「24の奇想曲」などがありますが、この曲はバッハ以来の無伴奏チェロソナタの名曲として音楽史上に燦然と輝く作品です。1915年(33歳)に作曲されて、チェロ1本の音楽の中にマジャール情緒溢れる民俗音楽の旋律や、トランシルヴァニア地方(現在のルーマニア)の民族楽器の響きなどが随所に表現されている作品です。 激しく、力強さと哀愁を覚える第1楽章、静かなハンガリーの田園風景を思わせる音楽と、情熱的な音楽の見事なコントラストの第2楽章。 激しく、情熱的なマジャールの祭のような第3楽章など、民俗音楽的な調べが見事な作品です。演奏上は非常に高度な技巧が要求されていて、トレモロ、トリル、ピッチカートなど独特の技巧が凝らされている曲で、初演時には演奏不能とさえ言われた難曲ですが、ハンガリー出身の名チェリストである、ヤーノシュ・シュタルケルが戦後1950年代にLPにこの曲を録音して、一大センセーションを巻き起こして以来、有名・高名なチェロ奏者が演奏会や録音でも採り上げられて、今では大バッハの作品と並び賞される曲となっています。私がこの曲を聴いたのが1970年代の前半で、フランスのアンドレ・ナヴァラの新録音LP盤を買って初めて聴いて以来、この曲の魅力の虜になりました。1974年だったか同じフランスのポール・トゥルトリエが来日したステージで、初めて生演奏を聴いたのですが、この曲が技巧的に難曲だということがよくわかった演奏会でした。1923年の今日(8月7日)、コダーイの無伴奏チェロ・ソナタが初演されています。愛聴盤 1. ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ)(USA DELOSレーベル DEL1015 1970年日本録音)この曲を日本に普及させたシュタルケルの新しい録音。 チェリストとしてシュタルケルの名を世界に知らしめたこの曲は、彼の代名詞とも言われています。強靭な弦の響きと荒削りで激情的な表現で、シュタルケルは思う存分この難曲を奏でています。 2. 長谷川陽子(チェロ)(日本ビクター VICC161 1994年録音)無伴奏チェロ・ソナタ Op.8(コダーイ)ザッヒャーの名による3つの詩(デュティーユ)無伴奏チェロ・ソナタ嬰ヘ短調 Op.133(プロコフィエフ)の3曲が収録されており、これらの曲を300年前の銘器 ヴィヨーム(コダーイ)、ゴフリラー(デュティーユ)、ロジェリー(プロコフィエフ)で弾きわけているのが特徴です。演奏はシュタルケルの男性的・激情的な表現に比べると「美しさ」を前面に押し出した、しっとりとしたチェロの響きが聴きものです。録音は生々しいチェロの音色が眼前に迫ってきて、恐ろしさえ覚えるほどの超優秀録音盤です。
2010年08月13日
コメント(0)
-
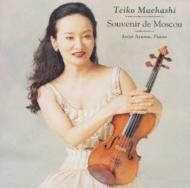
名曲100選
「名曲100選」 マスネー作曲 「タイスの瞑想曲」オペラ「タイス」「マノン」「ウエルテル」などで知られるフランスのロマンティク・オペラ作曲家のジュール・マスネー(1842-1912)は、彼のオペラを観ていない人、全曲盤オペラを聴いていない人、またはオペラに関心がない人でも、この曲はどこかで聴いていたり、ヴァイオリンの小品集などのレコード・CDなどで、あるいはコンサートなどで聴いていると思います。「タイスの瞑想曲」はオペラとは別にクラシック音楽では超有名曲で、私などがここでくどくどと書き連ねる必要のない曲だろうと思います。この曲はオペラ「タイス」の第2幕第1場と第2場の間で演奏される間奏曲で、神と人間の間を漂う娼婦タイスが信仰に目覚めていくのですが、その葛藤を表したのがこの間奏曲で、オペラとは独立してヴァイオリン作品の名曲として、頻繁に演奏される抒情的な美しさに満ちた音楽で、アンダンテ・レリジオーソの清澄な響きの分散和音にのってあの名旋律が歌いだされます。 修道士によって神への信仰の大切さを教えられ、オペラ終幕で三ヶ月の改悛の行を不眠で行うタイスが、その罪を浄められて天に召される場面で、尼僧の祈りののなかで天国を夢見て歌いながら息絶える幕切れは、この「瞑想曲」の旋律がタイスの歌と共に流れますが、実に感動的な旋律であることを改めて感じました。この「瞑想曲」の旋律はその他の場面でも随所に現れて、オペラを抒情的に歌い上げています。最後はG線でしだいに消え入るように余韻を残しながらおわるヴァイオリンの絶品といえる官能的な趣きのある名曲です。オペラも抒情的で非常に魅力ある作品です。一度は全曲盤を聴かれることをお薦めします。愛聴盤(1) 前橋汀子(ヴァイオリン)(ソニー・レーベル SICC-3 2000年録音)ヴァイオリン小品の名曲100曲の録音を目指した前橋の小品集の一つで、「モスクワの思い出」などが収められた「ヴァイオリン小品集」。 情感たっぷりに歌い上げたヴァイオリンの美しい音色に時を忘れてしまいます。(2) 映像ならエヴァ・メイ(S) ミケーレ・ヴィルトゥージ(Br) ヴィオッティ指揮 フェニーチェ歌劇場管弦楽団(ダイナミックス社原盤 TDKコア TBDA3020 2002年11月フェニーチ歌劇場ライブ)「タイス」の映像はあまりリリースされていなかったのですが、2002年11月のイタリア・フェニーチェ歌劇場での公演をDVDに収めたもので、納得のいく演出(少々官能的過ぎるとの批判もありますが)だと思います。 エヴァ・メイのタイスは官能的でありながら清楚な美しさも表現されていてとても満足出来る公演です。紹介しています商品番号では価格が高く、今年6月にはコロンビアが廉価盤を発売しています。2840円盤で日本語字幕もついています。この映像は万人に楽しめる舞台だと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2010年08月12日
コメント(0)
-
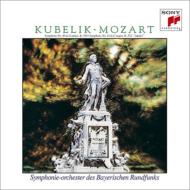
指揮者クーベリック
「指揮者 ラファエル・クーベリック」1996年に亡くなったチェコ出身のラファエル・クーベリック(1914-1996)は、地味な存在でした。 この人はおそらく音楽藝術に非常に純粋な人であったのかも知れません。チェコ政府からの干渉を嫌って亡命したこと(戦後チェコが共産化したことへの反発)、1961年からバイエルン放送響の音楽監督の地位にあって、1970年代に契約更新の際に放送法という政治の動きがあると更新を拒否したり、1972年にニューヨークメトロポリタン歌劇場の音楽監督に就任しても、やはり政治という力学的なことのために突然辞任をしています。 純粋に音楽をやりたい再現芸術家の一人であったのだと思います。 彼の死後さまざまな作曲家、曲の録音が埋もれていたのを復刻されて脚光を浴びていますが、70年代からマーラーやベートーベンの交響曲全集をリリースしていました。 マーラーブームの起こる前です。しかし、カラヤンやベーム、バーンスタインなどの指揮者と比べてレコード会社からすれば商業戦線に乗らない指揮者だったのかも知れません。 クーベリックの純粋な芸術性が選曲などでレコード会社と反りがあわなかったのかも知れません。ブームとかレコードの売れ行きとはあまり縁のない人でした。 地味な存在は、彼があまりに純粋過ぎたのかも知れません。しかし、現在ではまるで「神の領域」の人のように尊敬されている指揮者です。私は1965年の大阪国際フェスティバル、ドイツ・ミュンヘンでのバイエルン放送響のコンサート、それとニューヨークでニューヨークフィルを振った演奏会を客席で聴きましたが、「しなやかさ」「柔らかさ」のある温かい響きを引き出す表現にいつも魅せられていました。カラヤンのような磨き上げた美麗な表現でもなく、ベームのようのな骨太の確固たる表現でもなく、フルトヴェングラーのようなカリスマ的な麻薬のような情念のような趣きでもなく、バーンスタインのような活気と生命力と情熱溢れるような表現でもなく、クーベリック独自「しなやかさ」「柔和な」表現に酔わされていました。彼の死後見直された膨大なディスクがリリースされていますが、ワーグナーの「パルジファル」やウエーバーの「魔弾の射手」、ハイドンの「天地創造」などのオペラやオラトリオの演奏にも魅かれています。交響曲や管弦楽曲にも勿論名演と呼ぶにふさわしい録音がたくさん残されています。彼が9つの管弦楽団を振り分けたベートーベンの交響曲全集も話題になりました。いっとき聴いていましたが、私が聴きたいベートーベン象とは距離があったので、先年私のCDを無料放出した時のリストに載せてどなたかかにお譲りしました。 1965年や1990年の来日公演ライブ録音もCDでリリースされています。私がもっともクーベリックらしい演奏と好んで聴いていますのが、1980年に手兵バイエルン放送響と録音しましたモーツアルトの後期の6つの交響曲です。実にいいテンポで音楽が進み、ヴァイオリンを左右の両翼に置くことによって、高弦での壁のようなものができて、そこへ管楽器が明瞭に浮かび上がり溶け合う様は、モーツアルトの美しさを現代オーケストラができる可能性をいっぱいに表現しているかのようです。 レガートやスラーの処理が実に巧く、管楽器との絶妙のバランスを保ちながらの表現に脱帽です。艶やかで、しなやかで、軽やかに鳴るのは、彼のテンポの設定の良さだろうと思います。 そして何よりも柔らかい響きが音楽全体を支配しており、モーツアルトの美しさがいっそう引き出されている演奏です。 特に弦のしなやかさはこの人独特の表現のように思えます。前述のニューヨークフィルとの演奏でも、あの大音量の凄まじい音を美しく響かせるオーケストラから、柔らかい、しなやかな響きを引き出していたのは、さすがクーベリックという思いを強くしたものでした。最も感銘を受けたのがこのモーツアルトの演奏のテンポでした。速くもなく遅くもない絶妙のテンポを守りながら、聴く者を納得させていく、しかも柔軟でしなかやかさに溢れた表現は絶品とも言える演奏でした。父ヤン・クーベリックは稀代の名ヴァイオリニストであったそうで、そのことがひょっとしてクーベリックの指揮、音楽表現に影響を与えているのかも知れません。最後の来日でチェコフィルと演奏したスメタナの「わが祖国」も、彼の最後の輝きとして残されており、「私はやはりチェコの人間で故郷をこのように愛しているのです」というメッセージが込められているかのようで、終演後もチェコフィルのメンバーが舞台上で涙ぐんでいた光景は終世忘れることのできないコンサートでした。 NHKで全曲を放映した際のビデオを今でも飽くことなく観ています。 最近この時のNHK音源がCDやDVDでリリースされたようです。1996年の今日(8月11日)指揮者ラファエル・クーベリックは82歳の生涯を閉じています。愛聴盤 (1) モーツアルト 後記6大交響曲集(ソニークラシカル SICC258 1980年録音)40番と41番が収録されており、あと2枚には「プラハ」「39番」と「リンツ」「ハフナー」が収録されており、1枚が現在では1250円でリリースされています。(2) ブラームス交響曲全集 バイエルン放送交響楽団(ORFEOレーベル ORFEO70833 1981年録音 海外盤)あの重厚なブラームスの音楽がこんなにもしなやかなサウンドに変身するなんて、と驚きの演奏でクーベリックの資質が如実に表現された名演。(3) ドヴォルザーク 交響曲第9番 「新世界より」(ORFEOレーベル ORFEOR596031 1981年録音)ここでも柔軟でしなやかなにボヘミア色濃厚な音楽が情熱豊かに表現されており、ライブ特有の熱気が伝わってくる物凄く熱い名演奏。
2010年08月11日
コメント(2)
-

名曲100選
「名曲100選」 W.A.モーツアルト作曲 「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」この曲の旋律は、クラシック音楽に精通した人でなくても「あ!知っている!」と声を上げるのではないかなと思うほどに、超有名曲なんですね。私も初めてこの曲を聴いた中学生の頃に同じように思いました。TVやラジオから流れるCMでも使われていました。「どこかで聴いたクラシック音楽」のベスト3に入るのではと思う曲ですね。ウォルフガング・A.モーツアルト(1756-1791)は「セレナード」と名の付く曲を13曲書いています。有名な「ハフナー・セレナード」「グラン・パルティータ」「ポスト・ホルン」「ナハトムジーク」「セレナータ・ノットルナ」などがこの13曲のうちの曲で、この「アイネ・クライネ・・・・・」が最後のセレナードとなっています。タイトルはドイツ語で直訳すると「小夜曲」。 私はこの曲が流れるTVドラマか映画かを高校生時代に観たのですが、明治時代が背景で「鹿鳴館」の大広間でダンスに興じる紳士・淑女の姿のBGMがこの曲でしたので、今でもこの音楽を聴きますと、鹿鳴館時代にタイムスリップするような錯覚を覚えます。モーツアルトらしい明快な、優美な美しさに溢れている音楽で、誰もがこの曲を聴くと幸せな気分にさせてくれるように感じる音楽です。特に、第2楽章の「ロマンス」は、モーツアルトが書いた音楽で最も美しいものだと思います。まるで夢見るような気分に誘ってくれる美しい音楽です。愛聴盤ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団(Colombia原盤 SONYクラシカル SICC1067 1958年録音)数枚の同曲異演盤がありますが、一番歌心に溢れたこの演奏を最近は好んで聴いています。
2010年08月10日
コメント(0)
-
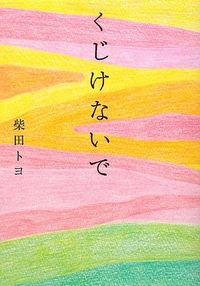
くじけないで
「くじけないで」産経新聞朝刊で連載されている「朝の詩」。わずか15行程度の短い読者からの投稿詩。 毎朝配達されてくるこの投稿詩を読むのが楽しみ。そんな詩を投稿し続けて選者を毎回唸らせて、とうとうその投稿された詩をまとめて1冊の本として出版された。 「くじけないで」 その詩を書いた人が今年白寿(99歳)の女性。 この年まで生きていることだけでも驚きなのに、90歳から始めた詩作りが、本としてまとめられるほどの詩を書いている稀有の女性。 それらの詩の中で、私が一番好きな詩がある。「神様」昔お国のために と死にいそいだ若者たちがいた今いじめを苦にして自殺していく子供たちがいる神様生きる勇気をどうして与えてあげなかったの戦争の仕掛け人いじめる人たちを貴方の力で跪かせて作者は柴田トヨ。 99歳の女性彼女が「私の軌跡」に書いている。九十歳を過ぎて出会った試作で、気付いたことがあります。どんなに辛いこと、悲しいことがあっても、私は両親や夫、倅、嫁、親戚、知人、そして多くの縁ある方々の愛情に支えられて、今の自分があるんだちうことです。だからどんなにひとりぼっちでもさびしくても考えるようにしています。「人生、いつだってこれから。 だれにも朝はかならずやってくる」って。一人暮らし二十年。 私しっかり生きてます。何と単純で、しかも重い言葉だろう。 ただただ、この人の、詩を通しての、生きる姿に頭が下がります。これからもどんどん投稿して私たちに生きる素晴らしさを教えて下さい。
2010年08月07日
コメント(2)
-

赤目四十八滝
昨年2009年のストックからです。連日のあまりの猛暑に涼を求めて。赤目四十八滝からカメラ Pentax K-10Dれんず Tamron 28-300mm XR Di
2010年08月06日
コメント(4)
-

西洋朝顔
何故100歳以上の人27名(産経新聞8/04付け)も生死も判らずに所在不明なのか? その間に選挙もあって投票のための入場切符のようなものが、選管から送られてくるのでそこに生活していなければその時点で異変がわからないのかな?大阪府和泉市にてカメラ Pentax K-10Dレンズ Pentax 100mm マクロレンズ
2010年08月04日
コメント(2)
-

名曲100選/茄子の花
「名曲100選」 ベートーベン作曲 交響曲第5番ハ短調「ベートーベンの一生は嵐の一日に似ている」と作家ロマン・ロランが言ったと伝えられているが、言いえて妙であると思います。 過酷な運命に一度は負けそうになって自殺まで思い詰めて遺書(ハイリゲンシュタットの遺書)まで書き残したベートーベン。 その彼が不屈の如く立ち直り、尚も神から与えられた運命(難聴の進行)に負けずに、この5番の交響曲(作品67)以降同じ数の作品を書き残している。この5番の交響曲は30分ほどの時間の音楽だが、凝縮性は彼の作品、他の作曲家にも見られないほど密度の濃いもので、冒頭の「ダ・ダ・ダーン」という3連音符の主題が終楽章まで形・リズムを変えて各楽章のテーマとなって現れており、第3楽章と終楽章は切れ目なく怒涛の勝利のファンファーレのように鳴り響く様は、何度聴いても心が躍り興奮させられる曲です。第2楽章の変奏もいいですね。ベートーベンは変奏曲を書くのを得意にしていたと言われていますが(ピアノ曲や室内楽にも名変奏曲が書き残されています)、私はこの第5番で最も好んで聴いているのが、この第2楽章の変奏曲です。 この第5番の主題は、ヘ短調の作品57のピアノ・ソナタ第23番「熱情」全体を支配する主題に非常によく似ていますが、このソナタの第2楽章の変奏曲もこの第5番の交響曲のそれと似ています。運命に戦いを挑むベートーベンと、その運命に負けない不屈の闘争心の現れと人間の精神の不滅を高らかに謳った名曲です。中学1年生の時に初めて聴いたときの感動は今もって忘れ得ないものです。あれほどの感動をもう一度味わいたいとかねてから思っているのですが、やはり最初に感動したことはもう二度と起こらないのでしょうか? 聴き終わって部屋の中をぐるぐる歩き回っており、家族から気がふれたのかと思われたくらいに興奮したことを覚えています。愛聴盤ウイルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(EMI ジャパン TOCE14034 1954年録音)私が初めて聴いた当時はまだLP盤だったこの演奏。これを中学の友達から借りて聴き入った懐かしく、この曲の最初の感動をもたらせてくれた演奏・録音盤です。このジャケット、この商品番号のCDを所有はしていませんが、発売以来何度も再発売を繰り返してきた不滅の名演奏盤です。ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団(SONYクラシカル SICC1068 1958年録音)フルトヴェングラーの演奏がデーモニッシュと呼べる劇的な主観的解釈による名演奏なら、このワルターの演奏は対極にある、「歌心」にあふれたベートーベンの音楽を心おきなく楽しめる盤。その他まだまだここに紹介したい盤は数多くあるのですが、今日はこれら2枚のディスクに絞っておきます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 茄子の花大阪府和泉市にてカメラ Pentax K-10Dレンズ Pentax 100mm マクロレンズ
2010年08月03日
コメント(0)
-

鬼百合
また起こった大阪市内での幼児虐待・遺棄事件。23歳の母親にアパートの室内に置き去りにされた3歳と1歳の幼児。ひと思いに殺したのか詳細はまだ不明。しかし母親が逮捕される前に「あのままだと死んでしまう」という言葉があったというから、殺してはいなかったのか?さればもっとひどい。飢えて亡くなったのか?澤田ふじこや司馬遼太郎が書いた室町時代を背景の歴史小説を先月読んだ。そこに書かれている室町末世の市井の様相。飢饉に苦しみ、やがて餓鬼のように飢えて亡くなった市民の遺体が、三条河原におびただしく重なって死臭が京都市内を包んだという。亡くなったこの2人の幼児はミイラ状態で発見されたという。 思わず読んだ小説を連想して、無念であり、どれだけ苦しかっただろうと想像すると泪が溢れてきた。成仏してください。合掌大阪府和泉市にて
2010年08月02日
コメント(0)
-

名曲100選/カラス麦
「名曲100選 悲しき口笛」丘のホテルの 赤い灯も胸のあかりも 消えるころみなと小雨が 降るようにふしも悲しい 口笛が恋の街角 露路の細道ながれ行くいつかまた逢う 指切りで笑いながらに 別れたが白い小指の いとしさが忘れられない さびしさを歌に歌って 祈るこころのいじらしさ夜のグラスの 酒よりももゆる紅色 色さえた恋の花ゆえ 口づけて君に捧げた 薔薇の花ドラの響きに ゆれて悲しや夢と散る美空ひばりの代表作。藤浦 洸の詩に万条目 正が曲を付けた1949年(昭和24年)の曲。 私が5歳の時のことだ。日常生活のことや世の中の出来事が明確に記憶に残っているのは小学校に入学したころからだろう。1952年に流行した「リンゴ追分」と共に耳にこびりつくほど聴かされた曲。映画にもなった(美空ひばりの主演第一作となった)。 子供ながらシルクハットにタキシードという姿は、後々までひばりを回顧する場面で使われている。8歳で舞台デビューした天才歌手。永遠の歌姫などと呼ばれる美空ひばり。57歳で逝くまで現役を続けた歌手。 七色と言われた声。その代表作がこの「悲しき口笛」。 49年言えばひばりは12歳の子供。それがまるで人生の悲哀を知っているかのように歌うことに驚異を覚える。詩を読んでみてもわかる通り情感を歌い込むのは非常に難しい言葉。 それを12歳の子供がいとも易々と歌っている。低音から鼻へ抜けるような高音まで「七色」と呼ばれる声で歌っている。 この歌が美空ひばりでなくて他の歌手が歌っていたなら、はたして100選に選んだかどうか? 永遠に歌い継がれていきたい名作でしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 カラス麦大阪府和泉市にてカメラ機種 Pentax K-10Dレンズ Pentax 100mm マクロレンズ
2010年08月01日
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
-

- いま嵐を語ろう♪
- 嵐ライブ2026生配信を見逃さないため…
- (2025-11-23 20:15:02)
-
-
-

- ☆モー娘。あれこれ☆
- 【野中美希・牧野真莉愛・羽賀朱音(…
- (2025-11-25 22:17:17)
-
-
-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 【輸入盤】ミニ・アルバム:ラッシュ…
- (2025-11-25 00:00:11)
-







