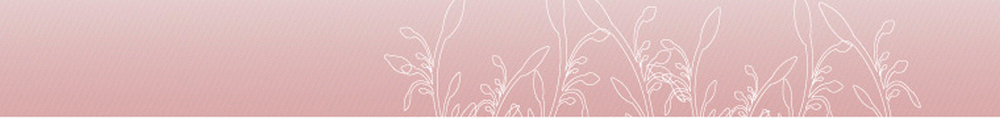-
1

古地図を持って中世の大坂を訪ねる?
豊臣秀吉は上町台地の北端に大坂城を中心とした巨大な近世城下町を築きましたが、それ以前の大坂には寺院や神社を核とした中世の集落点在していました。現在は巨大ビル群に覆われた大阪ですが、弥生三月が真近となり、地下に眠る中世都市大坂を古地図を参考にしながら、中世大坂の景観を体感したくなって歩いてきました。☆旅人が行き当たりばったりに歩いたコース☆大坂本願寺と渡辺津を結ぶ島町通り→上町台地北端の崖→坐摩神社お旅所→府立労働センター〔大坂城遺跡〕→高麗橋〔大坂城惣構堀・高麗橋里程元標跡〕→北浜界隈→少彦名神社〔道修町・薬の資料館〕上町台地に行けば、古代・縄文時代に遡る台地が実感できるし、道修町に行けば、古地図〔商人町図〕と現代の町割りの変わることのない同時性〔奥行き20間〕や秀吉の城下町作りの精緻性や狙いが良く分かり絶対感動しますよ。♪帰り道、薬問屋の多かった道修町の(日本の薬祖神を祀る)少彦名神社で「お守り」を買って帰りました。訪れたコースの紹介はこれから少しずつ紹介します。♪
2006.02.26
閲覧総数 423
-
2

平野(環濠都市)に行ってきましたよ。♪
大坂歴史ぶらり散歩シリーズnumber3平野(環濠都市)に行ってきましたよ。♪もともと平野は平野川の水運を利用して、河内・摂津をまたぐ交通の要衝の地であったが、南北朝から戦国時代にかけて戦乱に巻き込まれたことから、自衛のため濠を巡らした自治都市として発展しました。その繁栄ぶりはイエズス会宣教師ルイス・フロイスの書翰〔天正11年12月〕にも書きとどめられています。「堺の彼方―レグワ半または二レグワの所に城の如く竹を以って囲いたる美しき村あり、名を平野という。・・・・・・」現在の町割りは大坂夏の陣による焼亡後、1616(元和2)年に末吉家によって行われたといわれています。自治のシンボルである濠は、現在、杭全(くまた)神社〔下の写真〕と平野公園に一部をとどめるばかりですが、近年の発掘によって少しずつ豊かな都市の生活ぶりが明らかになりつつあります。杭全神社の本殿は三つもあるのです。写真では、左端の一番の本殿が隠れています。平野に行く最寄り駅は地下鉄谷町線の平野駅、又はJR大和路線の平野駅〔各駅停車駅〕ですよ。
2006.03.11
閲覧総数 24
-
-

- 京都。
- 👂️ 上賀茂神社 馬のおみくじ
- (2025-11-20 06:05:32)
-
-
-

- 日本全国の宿のご紹介
- 【静岡*浜松・浜名湖・天竜】スーパ…
- (2025-11-22 13:42:17)
-
-
-

- あなたの旅行記はどんな感じ??
- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい
- (2025-11-16 22:43:16)
-