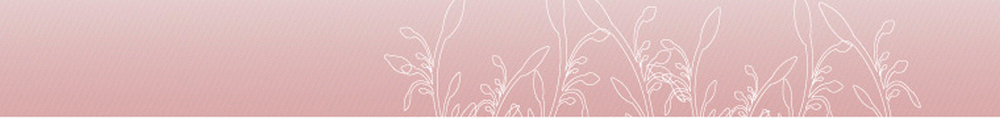全149件 (149件中 1-50件目)
-
最近、夢中になっている事(2題)♪
〔1〕郡山藩最後の藩主って知っていますか?柳沢保申は廃藩で禄を失った旧藩士たちの生活再建のために様々な事業授産策を講じたほか、郡山尋常中学校(現在の県立郡山高校)創立のために土地や多額の資金を提供。現在の大和郡山市の基礎を築いた開明的な政治家ですよ。柳沢保申は廃藩置県を冷静に受け止めるよう注意を促す一方、自らを世間知らずの「不肖」と称しへりくだって忠勤を呼び掛けるなど、所謂“お殿様”の言葉とは思えない言葉使いをしています。 柳沢家は、5代将軍・徳川綱吉の側用人、老中として権勢を揮った柳沢吉保の子孫にあたる有力大名ですが、保申は、自分は門閥家に生まれ、世間の苦労を知らないとし、「不肖之身」の自分に悪い点があれば忠告し、「せいぜい尽力のほどひとえに頼み入る」と常々、家臣に訴えています。 廃藩置県後、職を失った地方士族が各地で反乱を起こしたが、保申は旧藩士のために、授産所や郡山の特産である金魚の研究所を設立もしています。 〔2〕奈良・大和郡山の中世戦国史は面白いよ!夏以降、僕は奈良・大和郡山を中心とした中世戦国史関係の資料収集や分析にどっぷりとはまり込んでしまいました。今は幻となった筒井順慶の筒井城から豊臣秀長の郡山城へどのように変遷したんやろか?秋の夜長、関係する文献資料を読みふけってます。そんな訳で、ブログの更新がぜんぜんできませんでした。でも、これから、少しずつブログで紹介していきますよ。♪ご期待をしてくださいね。・・・・・♪
2006.10.10
コメント(61)
-
この花知ってますか?
この花はインド浜木綿の花なのです。一般的には幾何学的な花弁の浜木綿が有名なのですが、インド浜木綿は百合の花に似た一風変わった浜木綿なのです。 関西大学の網干先生が7月29日亡くなられました。網干先生は関大助教授時代で奈良県立橿原考古学研究所研究員を兼務した1972年、高松塚古墳発掘の現場責任者となり、「飛鳥美人」と評された人物群像や四神図など極彩色壁画を発見されました。 網干先生の高松塚壁画古墳の発見により、現代の古代史ブームが巻き起こったのだと思います。網干先生は高松塚壁画の劣化が発覚してからは文化庁の姿勢を厳しく追及し、文化庁が計画する古墳の解体に強く反対しておられました。今年、1月28日、橿原考古学研究所付属博物館の友史会創立50周年記念講演会がかしはら万葉ホールで実施されました。当日、先生は「高松塚・キトラ古墳の保存をめぐる諸問題」というテーマで記念講演をされました。当日の先生の体調は悪く、気力だけで高松塚古墳壁画の保存に係る問題点を明快に指摘しておられました。僕は網干先生を通して、高松塚から考えられること、すなわち、自分の現在の生活と高松塚古墳がどのように結びつくのかということを学びました。具体的に言うと、星辰のこと、四神のこと、陰陽のこと、青春のこと、甲子園のこと等々。〔一例として、六甲山の甲山の麓の野球場「甲子園」は1924年に開設された。この年の年回りが十干・十二支によれば「甲子」になることに由来する。〕先生のおかげで、考古学のあるべき姿・本質が良く分かりました。でも、一つだけ心残りです。それは、1月28日の記念講演会の日、先生の著作集を買って、サインをして頂こうと思って行列していたのに、サインして頂けなかったことです。今はもう、先生のざっくばらんな人柄だけが目に浮かびます。網干先生、ありがとうございました。では、優しかった網干先生へ、先生も大好きだった手向け花をご覧ください。♪
2006.08.02
コメント(4)
-
ジャーン! 新年度のスクーリングが始まりました。♪
梅雨末期の大雨の中、7月15日から17日の3日間、久しぶりに大学に行ってきました。懐かしい友達との再会は良いものですね。元気にしてた。?勉強はかどってますか?今年、卒業できるやろか?等々、話は尽きず・・・・今回のスクーリングは保存科学の研究と実験です。X線回折、蛍光X線分析、走査型電子顕微鏡電子線マイクロスコープによる分析法、イオンクロマトグラフイー、X線透過撮影等々。文科系の頭構造の僕には非常に難解・超難しかったですね。でも、少し理解できたみたい。実習はこんな感じですよ。
2006.07.20
コメント(3)
-
笹百合の花を見たいですね。♪
奉げられた百合の花々は元気なくて可哀想ですね。何時か、三輪山に行って、自生している笹百合の群生を見たいものです。♪
2006.07.07
コメント(1)
-
百合まつりってこんな雰囲気ですよ。♪
率川神社の百合まつりを紹介していて、美しく撮れた笹百合の写真を紹介して、本題の率川神社の写真をUPしていませんでしたね。御祭はこんな感じなのですよ。
2006.07.02
コメント(5)
-
率川神社 三枝祭 6月17日 ササユリをかざし舞う巫女達♪
卒川神社に出掛けませんか? 率川神社は、別名子守明神とも呼ばれ、古来より安産・育児の神として信仰をあつめている神社である。また、奈良で一番古いとされる恵比須様も祀られる古社で、祭神は、五十鈴姫命、狭井大神、玉櫛姫命です。この神社の特徴は、主祭神の五十鈴姫命を中央に、向かって左に父神の狭井大神、右に母神玉櫛姫命と、三殿並んでお祀りされていることです。その様子は、子を守る父母の姿を彷彿させるため、子守明神と呼ばれ、安産、育児、息災延命の神として崇敬されることとなった。ちなみに、神社のある町の名は「本子守町」ですよ。五十鈴姫命は、神武天皇の皇后様として内助の功が高かったという。皇后を主祭神としてお祀りした神社は、全国でも珍しい。左殿の狭井大神は、大神神社の大物主大神、出雲大社の大国主神と同じ神である。右殿には、母である玉櫛姫命がお祀りされていいます。別名「ゆりまつり」。ササユリ香るたおやかな初夏の祭りですよ。♪1年中で1番、率川神社に人が溢れる日、それが6月17日の三枝祭(さいくさまつり)である。神楽が奉納される舞台の周囲はもちろん、あまり広くない境内は毎年超満員の混雑ぶりですよ。三枝祭は、「ゆりまつり」としてその名を広く知られる典雅な祭りである。4人の御巫が三輪山で摘んできたというササユリが、あらゆる場面で用いられます。最初に黒酒、白酒を酒器に入れて、その酒器をササユリで飾り供える。そして、神前では、厄除け祈願の祝詞が奏上と、巫女達による神楽の奉納がはじめる。手には、やはりササユリを持ち、ゆったりと、かざしながら踊る。笛の音が雅楽ならではの荘厳な雰囲気で、巫女の透ける朱に白の薄ものを重ねた衣装は、ゆるゆるさらさらと風に動き、木々に囲まれた小さな境内で光り輝きまぶしいですよ。神社での祭典の後は、七媛女、ゆり姫、稚児などによる巡行が、奈良の繁華街を練り歩くことになります。お供えされた約2000本のササユリの花は、疫病除けになるといわれ、参拝者が自由に持ち帰れたのだが、昨今、自生のササユリが激減し、祭りにおいても広く配るほどのササユリを手配するのはかなり難しい状況になっています。近年では、県農業試験場の指導で大神神社(奈良県桜井市)が「バイオササユリ」を栽培しています。最後に百合の花を歌った万葉歌を紹介しましょう。 1257: 道の辺の草深百合の花笑みに笑みしがからに妻と言ふべしや 1500: 夏の野の茂みに咲ける姫百合の知らえぬ恋は苦しきものぞ 1503: 我妹子が家の垣内のさ百合花ゆりと言へるはいなと言ふに似る 2467: 道の辺の草深百合の後もと言ふ妹が命を我れ知らめやも 4086: 油火の光りに見ゆる吾がかづらさ百合の花の笑まはしきかも 4087: 灯火の光りに見ゆるさ百合花ゆりも逢はむと思ひそめてき 4088: さ百合花ゆりも逢はむと思へこそ今のまさかもうるはしみすれ 4113: 大君の遠の朝廷と任きたまふ官のまに.......(長歌) 4115: さ百合花ゆりも逢はむと下延ふる心しなくは今日も経めやも 4116: 大君の任きのまにまに取り持ちて.......(長歌) 4369: 筑波嶺のさ百合の花の夜床にも愛しけ妹ぞ昼も愛しけ
2006.07.01
コメント(0)
-
六月の花は紫陽花が一番ですね。♪
近畿地方も入梅ですね。雨上がりにカメラ片手に愛犬〔チャッピー〕の散歩に行きました。我が家で額紫陽花を撮り、それからお城跡〔郡山城〕に行きました。ところで、紫陽花は雨の花で、梅雨をいろどる一番の花ですね。雨の降りそそぐ時、色彩が鮮やかになり、花の光沢が一段と美しくなって風情があり、雨上がりが一番美しく見えますね。手まりのような形、澄んだ色は、梅雨でうっとうしく悩み大きい私達の心に安らぎを与え、詩情をかきたてます。何時、紫陽花の花を観賞したらよいのか、以前、矢田寺・大門坊の前川空識和尚にお聞きしたことがあります。「晴天の時は、陽射の強い日中は避けて、午前10時ごろまでか、午後5時過ぎが美しいですよ。」「また、晴天つづきの場合は、球状のガク片が乱れて、花は美しくなし、また、満開を過ぎると、花色が次第に変わって鑑賞には適さないようですよ。」そんなことをお聞きしました。今年も、我が家の近く、60種類を越す立派な紫陽花園の矢田寺に行こうと思います。以下はおまけです。(紫陽花に寄せた歌・俳句です)Like the eightfold ajisai full in bloom may you be flourishing for years to come.(20-4448)いまもかも きませわがせこ みせもせん 植えしあじさい 花咲きにけり (藤原知家)すれすれに 夕紫陽花に 来て触れる 揚羽の蝶の 髭大ひなる (北原白秋)紫陽花や 藪を 小庭の 別座敷 (松尾芭蕉)
2006.06.28
コメント(2)
-
紀伊風土記の丘を紹介しましょう。♪
紀伊風土記の丘って?紀伊風土記の丘は、国指定特別史跡「岩橋千塚古墳群」の保全と公開を目的として1971(昭和46)年8月に開館、考古・民俗資料を中心とした和歌山県立の博物館施設です。1972(昭和47)年6月には登録博物館となっています。和歌山市の郊外に位置する博物館施設は、標高約150mの丘陵からその北斜面・麓まで約65haの広さがあります。丘陵の上からの眺めはすばらしく和歌山市街地・紀ノ川や和泉山脈を一望できますよ。岩橋千塚古墳群の特色って何だろうか? この古墳群は、5世紀から7世紀前半かけて築造された前方後円墳、円墳、方墳など約700基が集まり、その古墳の数の多さは全国でも最大クラスといわれています。 それぞれの古墳の埋葬施設は、結晶片岩の板石を積んで長方形の空間を造った竪穴式石室、横穴式石室などがあります。石室を設けず板石を立ててつくる箱式石棺、また木棺をぶあつく粘土で包んだ粘土槨なども見られます。 なかでも横穴式石室に見られる石棚と石梁は、岩橋千塚古墳群の最も大きな特徴です。とくに石梁は、割り石を積み上げただけの石室の壁面を崩れにくくするために支える「構造材」の機能があると考えられているそうです。そのため将軍塚などは天井の高さ約4.3メートルの大きな「玄室」を確保することができたと考えられます。また、床の下には排水施設があり、水が外に抜けるような構造になっていますよ。百聞は一見に如かずとか言いますよね。出掛ける機会があれば是非見てきてください。
2006.06.10
コメント(2)
-
和歌山県立博物館の特別展は面白いぞー!
6月4日まで和歌山県立博物館では「和歌祭」の特別展示を開催していましたよ。和歌祭は、江戸幕府を開いた徳川家康をまつる紀州東照宮の祭礼だそうです。元和2年(1616)駿河城で亡くなった家康は、久能山に埋葬され、翌年日光山に改葬されました。元和5年(1619)駿府から和歌山に入国し、紀伊藩初代藩主となった家康の子・頼宣は入国直後の元和7年(1621)和歌浦に東照社を造営しました。その翌年の4月17日(家康の命日)には春祭が行われ、初めての神輿渡御が行われました。この春祭が和歌祭と呼ばれるようになり、和歌山で行われる祭礼のなかでも最も規模の大きいものとなったそうです。当初の和歌祭は、頼宣が好む風流な練り物が多く出され全国的にみても類をみない風流尽くしの祭礼であったようです。しかし、家康の50回忌にあたる寛文5年(1665)に練り物が縮小され、その様相は大きく様変わりしたそうです。この和歌祭には、城下町に住む武士や町人のほか、和歌浦周辺の人々やさまざまな身分の人々も参加し彼らによって祭が支えられています。県立博物館の特別展の展示では、その成立から変容を遂げる和歌祭の姿を現在残されている祭礼絵巻などから確認できました。また、他地域で行われていた東照宮の祭礼と比較することで和歌山の和歌祭が持つ固有の性格を把握することができましたね。来年の事を今ごろ言うのは、「鬼が笑う」とか言いますが、でもね、来年は和歌山に行って、本物の和歌祭りを見て楽しもうと考えています。♪
2006.06.09
コメント(0)
-
久しぶりに近場の博物館に行って来ましたよ。♪
この旅人のブログタイトルが「近場の博物館巡り」なのに、かなりの長期間にわたり博物館紹介をサボっていました。4日〔日〕に阪神高速・阪和道をとばして和歌山市に行ってきました。訪れたのは、「和歌山県立博物館」「和歌山市立博物館」そして「紀伊風土記の丘博物館」です。当日は和歌山県立博物館では「和歌祭」の最終日でした。50年以上近畿に住んでいて、初めて、徳川家康を偲ぶこんな大規模な祭事が江戸時代から、平成の今日まで続いていることに感動しました。通常、関西のお祭りといえば、京都の「祇園祭」「葵祭り」「時代祭り」、大阪の「天神祭り」「岸和田・だんじり祭り」奈良の「薪御能」「春日若宮御祭り」「二月堂・お水取り」等がメジャーですね。和歌山には無いのやろか?こんな事書いていて、和歌山県〔市〕は宣伝ベタやなあ!と思いました。後世に、若い世代に、日本を代表する伝統行事が器でなくその歴史的思いが引き継がれていくことが一番大切やなあ!と思います。今日から和歌山で撮ってきた写真を少しずつ紹介します。♪
2006.06.08
コメント(0)
-
内堀の美しき花シリーズ(その2)
黄菖蒲に続き、第2段として、咲き始めた蓮を紹介しましょう。♪ ひさかたの 雨も降らぬか 蓮葉に 溜れる水の 玉に似たる見む〔巻16-3837〕
2006.05.28
コメント(1)
-
青空に映える、古城の黄菖蒲の鮮やかさは抜群ですね。♪
うっそうとした内堀の野草に混ざりながらも、美しき黄菖蒲の気品ある黄色が良いですね。♪
2006.05.24
コメント(2)
-
お城の堀に黄菖蒲が咲いてますよ。♪
郡山城跡の堀では、今時、黄菖蒲が美しさを競っています。黄菖蒲はヨーロッパ原産で明治の中頃に渡来し、栽培が始まったそうです。最近では、水田の溝や池の畔,湿地などに繁殖しているのを良く目にしますね。根葉は 60 ~ 100 cm。幅 2~3 cmの長い剣状で中脈が隆起して目立ちますよ。では、水面に映え美しく気品のある黄菖蒲をご覧あれ。♪
2006.05.23
コメント(0)
-
5月の城跡風景って?
大和郡山城跡の5月初めの景色はこんな感じですよ。つつじが咲き始め、シベリヤに帰りたくなーい!と叫んでいる冬鳥が遊んでいますよ。♪静かなたたずまいで、騒がしかった桜祭りと同じ場所〔舞台〕であることを疑ってしまいますよ。
2006.05.05
コメント(2)
-
皐月の初物と言えば、?
5月に入り、早朝のお城の散歩道では、青空を泳ぐ鯉のぼりと吹流しが目立ってきました。郡山城のお堀では、鯉のぼりと競うように若い錦鯉が活きよい良く泳いでいますよ。では、その美しき泳ぎっぷりを特とご覧あれ。♪
2006.05.03
コメント(6)
-
今年最後のチューリップが咲きましたよ。♪
毎年、我が家では100個~150個のチューリップを植えています。何時も、球根の値段が一番下がったとき〔12月初め〕に大量に買い込んでいます。今の時期、チューリップの開花も終盤に入り、すかし百合達にバトンタッチももう直ぐといったところですよ。♪
2006.04.30
コメント(0)
-
蒲生野の万葉歌の花々〔その2〕
前回、「紫の花」と「あかね」の写真を併せてupする予定でしたが、サイズが大きすぎてup出来ませんでした。そんな訳で、その2として残りの写真を掲載しまーす。♪
2006.04.26
コメント(1)
-
壬申の乱の地「蒲生野・不破の関」に出かけませんか?
桜の花も終わりましたね。桜の次は「紫の花」と「あかね」を紹介しましょう。次のコース〔壬申の乱と万葉の花が楽しめる〕は旅人のお勧めコースですよ。♪京都駅→→→瀬田川の唐橋→→→八日市市・船岡山ー太郎坊宮→→→不破の関資料館・・・不破の関跡・・・藤古川ほとり・・・大友皇子・自害ケ峰〔黒血川〕・・・若宮八幡宮〔JR関が原駅へ徒歩→→→JRで大阪・京都へ〕ー近鉄京都駅次の歌も是非、覚えてほしいですね。額田王が大海人皇子に詠んだ歌あかねさす 紫野行き 標野行き 野守は見ずや 君が袖ふるこれに対する大海人皇子の返歌紫草の にほへる妹を 憎くあらば 人妻ゆゑに 吾恋ひめやもこの二つの愛の歌に出てくる「あかね」と「紫の花」、船岡山で見つけることができますよ。〔下の写真にありますよ。〕天智天皇が定めた大津の都は、わずか6年たらずで滅び、都は再び大和の飛鳥に還ってしまいました。大海人皇子は即位して天武天皇〔在来の豪族との妥協によらないで大王となった〕となり、新たな古代国家〔神権的な天皇制〕の建設に向かいました。日本列島の中央部のほとんどを戦乱に巻き込んだ、古代史上最大の動乱は、その後の歴史に何を残したんでしょうか?人麻呂の歌に「大君は神にしませば・・・・・」とあるけれど、完全な官僚政治である律令体制の中で、天武天皇が生きながら神であるということ〔現人神〕をどのように関連・位置づけたらよいのでしょうか?等々いろんな思い、また、疑問が湧いてきますよ。疑問を解決するためには、じっくりと犬養先生・清原先生・和田先生・山内先生著の「壬申の乱を行く」を読み込まれることをお勧めします。〔矢田旅人の独り言〕♪
2006.04.25
コメント(0)
-
我が家のベスト写真って?
旅人の大好きな我が家のベストワン写真?はこれですよ。〔15年ぐらい前かな?〕場所は運河の都市であるベネチュアと金剛山をバックにした葛城山とマイホームの大和郡山です。笑顔〔ワンも含めて〕をキーワードにして、これからも頑張りたいですね。♪
2006.04.22
コメント(0)
-
桜花吹雪く城跡は絶好の遊び場所ですよ。♪
我が家の愛犬〔チャッピー〕は何時も散歩で通る郡山城跡でこんな雰囲気で戯れているのですよ。面白いですよ。ワンのような天真爛漫でありたいものですね。♪
2006.04.20
コメント(0)
-

こんなにも美しき桜の絨毯見たことありますか?♪
昨日今日の豪雨を受けて、とうとう桜花も終わりを告げましたね。桜シリーズの最終として、旅人が知っている中で一番美しい桜の絨毯をお見せします。さて、場所は何処かお分かりでしょうか?JR宮原駅から徒歩、湯浅へ7キロ栖原へ6キロ。栖原施無畏寺からの湯浅湾の眺望は素晴らしいよ。♪足代過ぎて 糸鹿の山の 桜花 散らずあらなむ 還り来るまで 作者未詳〔巻7-1212〕
2006.04.12
コメント(1)
-

早朝散歩のベストパートナーとは?
旅人の早朝散歩のパートナーは写真のビーグル犬ですよ。名前はチャッピーと言います。♪とっても可愛いでしょう。でも、本当は見かけによらず、なかなかの曲者and腕白坊主ですよ。彼の本当の正体を次回に紹介します。お楽しみに。
2006.04.10
コメント(0)
-

お城祭りの裏舞台とは?
桜咲き、金魚の品評会があり、夜桜が賑わい、屋台の店が多い光景は良いのですが、でもね・・・・・お城祭りに来る人々は殆どマナーありません。最近の夜桜等では、バーベキュー、焼肉が多くなりましたが、何故か後片付けはほとんどなし。早朝のAM5:30頃、市商工会の奥さん方や自治会の役員さんが散らばったゴミの回収・後片付けのおおわらわです。郡山城跡が一年で一番汚くなるのがお城祭りの開催期間なのです。うるさい、汚い、ゴミだらけ、お城の近隣住民と商工会・自治会関係者が苦労するだけなのです。日本の品格とは言いませんが、少なくとも、自分のゴミは持ち帰ってほしいものです。そんな訳で、旅人はお城祭りの前〔郭公の声が聞こえる〕と後〔新緑の候〕の静けさが一番好きですよ。♪ 毎日、毎日こんな状況なのですよ。
2006.04.08
コメント(1)
-
郡山城跡の桜、開花率90%以上ですよ。♪
郡山城跡の桜、満開に近く、少し冷たい風に花枝がはらはらと揺れて美しいですよ。
2006.04.08
コメント(0)
-
郡山城の金魚宣伝パ‐ト3
郡山城の南方向一帯のエリアで、数は激減してしまつたけれども、今直、金魚養殖は細々と続けられていますよ。 でも、最近は高級な金魚の養殖は激減し、縁日の屋台や夜店の「金魚すくい」用の「小赤」と呼ばれている「和金」が養殖の主流を占めているようです。 日本有数の金魚の産地であった郡山で生まれ育つた僕としては、非常に心寂しいですね。
2006.04.03
コメント(0)
-
江戸時代から伝統の金魚達で‐す!(NO-2)
金魚の即売もやってますよ。当然ですが、「産直」やから「本物」and「手頃な値段」ですよ。
2006.04.03
コメント(0)
-
今年のお城祭に出品のきらびやかな金魚達です♪
江戸時代から金魚の名産地として名高い郡山の金魚達を紹介します。♪
2006.04.03
コメント(0)
-
大学入学式でビックリ〔ショック〕しました。♪
家内と二人で長男の大学入学式にいってきました。近鉄京都線の興戸駅下車、徒歩15分で大学正門前、正門前から歩くこと10分で入学式場に到着です。入学式も様変わりですね。僕らの時代、入学式には一人で勝手に参加していました。〔旅人の母は僕の入学した大学に一度も行きませんでした。〕昨日の入学式、ほとんどの両親が参加してしました。新入生の子供の服装も大幅に様変わりです。黒のストライプのスーツ、黒の靴、どの子の髪型も良く似ている、個性はほとんどない、学生服が黒のストライプのスーツに変わっただけです。個性のない、無機質で透明色の子供たちかな?。同志社大学では、もう、学生自治会は消滅し、いろんなサークルの部室も空部屋ばかりとのこと。総長のお話にしても、その他の方々のお話にしても、くらえもん事件や偽装建築問題等を象徴とした「市場原理至上主義」に陥ってはいけないという事を繰り返し言っておられました。最近の学生は大学から指示や指導がないかぎり何も自発的に行動しないそうです。従って、大学当局から学生にいろんなアクション指示を根気強く事細かに出さざるを得ないそうです。〔大学生になっても、殆ど高校4年生のレベルかも?〕同志社には父母会があり、同志社大学では、毎年、5月と10月に子女の成績表を父母宛に送付しているそうです。でも、4回生になって学生の20数%が卒業できないということも聞きました。大学当局からいろんなことを聞けば聞くほど、情けなくなりました。〔悲しいね。〕きっと、同志社創設者の新島先生も天国で嘆いておられることでしょう。新島先生の建学の本旨は何処に行ってしまったんでしょうか?泥中の蓮ではありませんが、わが子には頑張って美しい花をさかせてほしいと祈っています。
2006.04.02
コメント(0)
-
桜花の似合う大学入学式でした♪
桜の花のちらほら咲き始めた今日、息子の大学入学式に行ってきました。息子は新調のスーツに靴にネクタイにドレスシャツでバシッと決めた姿です。新品の靴で踵が痛そうでしたね。誰もが大学正面が列をなして記念撮影しています。我が家も息子と家内の記念撮影をしてきました。当日の詳細は後日に報告しますよ。♪
2006.04.01
コメント(0)
-
郡山城跡の桜は美しいですよ。♪
下の写真は昨年4月10日過ぎに撮ったものです。今年も4月中旬にはこんな感じかな!と想像しています。ここ数日はメチャメチャ寒いのですが、着実に桜の蕾は膨らんでいますよ。今日現在はチラホラ咲きといったところですよ。
2006.03.29
コメント(0)
-
美しき金魚達♪
郡山城のお城祭に欠かせない金魚達を早朝の愛犬の散歩途中で見てきました。♪ 見た目、とっても可愛いでしょう。 桜は来週末ぐらいが見ごたえがあると思います。桜と金魚を見に是非、郡山城に行きませんか!♪
2006.03.29
コメント(0)
-
花の気品とは?
毎年、桜の花の咲く頃に我が家では、シンビジュ‐ムが数多く開花しますよ。 22年前、結婚のお祝いとして叔父から頂いたシンビジュ‐ムなのです。 20数年間順調に育つて、開花、株分けを重ね、親戚や友人にさしあげたりしてきました。 現在、10数鉢ですが可憐でほのかな香の花を咲かせています。 温かくなつたので、週末には温室から庭に引越しの予定ですよ?
2006.03.28
コメント(0)
-
用意万端ですよ♪
大和郡山城のお城祭の用意がほぼ完了したようです。 桜の蕾もかなり膨らんできましたよ。 金魚の品評会も楽しみです。 それと植木市もね。♪
2006.03.19
コメント(2)
-
大好きな家持の春の歌を紹介しまーす。♪
矢田旅人の大好きな家持の春の歌〔巻19〕紹介しまーす。♪二十三日、興に依けてよめる歌二首春の野に霞たなびきうら悲しこの夕影に鴬鳴くも〔4290〕我が屋戸の五十笹群竹吹く風の音のかそけきこの夕へかも〔4291〕二十五日、よめる歌一首うらうらに照れる春日に雲雀あがり心悲しも独りし思へば〔4292〕春ノ日遅々トシテ、ヒバリ*正ニ啼ク。悽惆ノ意、歌ニアラザレバ撥ヒ難シ。仍此ノ歌ヲ作ミ、式テ締緒ヲ展ク。但此ノ巻中、作者ノ名字ヲ称ハズ、徒年月所処縁
2006.03.18
コメント(0)
-
平野(環濠都市)に行ってきましたよ。♪
大坂歴史ぶらり散歩シリーズnumber3平野(環濠都市)に行ってきましたよ。♪もともと平野は平野川の水運を利用して、河内・摂津をまたぐ交通の要衝の地であったが、南北朝から戦国時代にかけて戦乱に巻き込まれたことから、自衛のため濠を巡らした自治都市として発展しました。その繁栄ぶりはイエズス会宣教師ルイス・フロイスの書翰〔天正11年12月〕にも書きとどめられています。「堺の彼方―レグワ半または二レグワの所に城の如く竹を以って囲いたる美しき村あり、名を平野という。・・・・・・」現在の町割りは大坂夏の陣による焼亡後、1616(元和2)年に末吉家によって行われたといわれています。自治のシンボルである濠は、現在、杭全(くまた)神社〔下の写真〕と平野公園に一部をとどめるばかりですが、近年の発掘によって少しずつ豊かな都市の生活ぶりが明らかになりつつあります。杭全神社の本殿は三つもあるのです。写真では、左端の一番の本殿が隠れています。平野に行く最寄り駅は地下鉄谷町線の平野駅、又はJR大和路線の平野駅〔各駅停車駅〕ですよ。
2006.03.11
コメント(2)
-
天王寺七坂の地図ですよー!♪
自分で地図を書こうと思いましたが、上手く描けませんでした。グッドタイミングで、大阪夕陽丘ライオンズクラブさんの「歴史の散歩道にある藤原家隆塚」のパンフレットに分かりやすい地図があることに気がつき、掲載させていただくこととなりました。では、この地図で天王寺界隈の七坂をイメージしてみてくださいね。♪
2006.03.08
コメント(0)
-
勝鬘院(愛染堂)とはどんなとこかな?
勝鬘院(愛染堂)ってどんなとこか知ってますか?593年(推古天皇元年)聖徳太子は、敬田院、施薬院、寮病院、悲田院からなる四天王寺を建立しました。 四院の中の施薬院が勝鬘院と呼ばれるようになったのは、この寺で聖徳太子が勝鬘経を人々に講ぜられたため、後にこう呼ばれるようになりました。 当時の面積は現在より一層広大であり、また、建立の意味あいからいうと、我が国の社会福祉事業発祥の地とも言われている。 主な堂塔として、金堂と多宝塔がありますよ。下の写真は多宝塔の前で撮った梅と椿ですよ。♪本寺の正式名称は勝鬘院ですが、金堂に愛染明王が奉安されており、それによって金堂は「愛染堂」と称され、また愛染明王信仰の普及とともに、勝鬘院全体が愛染堂と通称されるようになったそうです。金堂に奉られる愛染明王は縁結びの本尊としても有名で、境内にある「愛染めの霊水」は飲むと愛が叶うといわれ、女性参詣客が毎年たくさん訪れています。関西では、人々は親しみを込めて「愛染さん」と呼びます。お寺に入ってすぐ右に「愛染桂の木」〔二代目〕がありますよ。一度、見られたし。!♪
2006.03.07
コメント(0)
-
夕陽丘という名前の本当の由来とは?
前回、四天王寺界隈で夕陽丘という名の由来について、宗教的には浄土信仰の影響が強いと言いましたが、別にもっと有力なものがあります。それは、藤原定家と並ぶ鎌倉時代初期の歌人藤原家隆〔1158-1239〕の歌なのです。藤原家隆は新古今和歌集の選者でした。晩年、官職を辞してこの地に庵を造り、余生を送ったそうです。彼は西の海に落ちる夕日を見て七首の秀歌を作っています。契りあれば なにわの里に宿り来て 波の入日を拝みつるかな藤原家隆のこの秀歌から、この地一帯の夕陽丘の地名が生じたのです。「一見は百聞にしかず」と言います。上町台地にある歴史の散歩道に出かけられたし。!♪最寄の駅は地下鉄谷町線「四天王寺夕陽丘駅」ですよ。
2006.03.05
コメント(0)
-
四天王寺前夕陽丘駅って知ってますか?
この前、上町台地の最北端辺り〔北浜~天満橋〕をぶらりぶらりと歩いてきましたが、今日は上町台地の最南端辺りに行ってきました。上町台地の最南端の中核は四天王寺さんですよ。明治21年の地図と昭和6年の地図と現代の地図の3点セットを持って四天王寺界隈をぶらぶら歩いてきました。発見その1上町台地の西端は急激に落ち込んでいて、その昔、此処から遠く大坂湾に沈む太陽の落日を臨むことが出来たらしい。このことから「夕陽丘」と風情豊かな名前が付いたらしい。11世紀以降、庶民層に広がっていった浄土信仰の影響が強かったと思いますね。発見その2上町台地の端に位置するゆえに、天王寺には「天王寺七坂」がある。その七つとは次の通りです。愛染坂、清水坂、口縄坂、逢坂、天神坂、真言坂、源聖寺坂ですよ。四天王寺界隈ぶらり散歩の詳細報告は後日とします。お楽しみに待っていてください。写真は愛染坂〔大江神社の南側〕です。
2006.03.04
コメント(3)
-
くすりの町「道修町」を訪ねてpart2ですよ。!♪
少彦名神社の入り口の注連柱って何んだ? 少彦名神社の入り口には『定給療病方咸蒙其恩頼』(やまひをおさむるのりをさだめたまひ、みなそのみたまのふゆを、かがふれり)と記された注連柱(しめばしら)が立っています。これは日本書記で「大国主命が少彦名命とともに、国を治め、人々や家畜の病気の治療法を定めて、獣や昆虫の害をはらうまじないを教え、万民にいたるまでその恩恵をこうむっていた」という意味ですよ。注連柱の著者は(伯爵)東久世通禧です。彼は幕末の公卿で、長州へ七卿落ちした内の一人だったそうです。「なんのこっちゃろな?」と思われた方も、そうでない方も、ちょっと覚えておいていただけたら幸いですね。くすりの町「道修町」のはじまりとは? 『くすりの町 道修町』はいつからあったのでしょうか? 歴史書を繰ってみると、大坂が豊臣秀吉の城下町であった天正16年1588)に「“道修町”で火事があって町家が20軒焼けた」という記録が残っています。この頃には既に“道修町”があったことはまちがいないようです。また道修町古文書には一番古い事例として、明暦4年(1658)の似せ薬取締りに関する文書が残っており、そこからは、道修町に33軒の薬種屋が住んでいたことがわかります。薬種というのは、草根木皮など、和漢薬の原料になるもの。 でも、道修町が本当のくすりの町となるのは、徳川吉宗による“享保の改革”の時期以降のことです。享保7年(1722)、道修町の薬種屋仲間124軒が幕府から“株仲間”として公認されました。株仲間とは独占的に商品を扱える同業者団体のこと。幕府は江戸・駿河・京都・大坂・堺に「和薬改会所」という役所をつくり、国産の薬種(和薬)について、これは正しいとかまちがっている、これは使っていいとか使ってはいけないなど、薬の見分けを行わせます。大坂では道修町の薬種屋仲間が、幕府による講習を受けてこの仕事を担当することになりました。和薬改会所はまもなく廃止されましたが、道修町の薬種屋仲間は、和薬種だけでなく中国から輸入される唐薬種についてもプロフェッショナルでしたから、和薬・唐薬の両方の管理・取り扱いについて、「(和薬改会所はなくても)自分達の“仲間”はお役に立ちますよ」ということを幕府にアピールし、その後も「道修町薬種中買仲間」として存続していきます。また、当時から長崎貿易は幕府の重要な財源でもありましたので、唐薬種も道修町の薬種屋に管理させることは、幕府にとって都合がよかったのです。 これが「道修町薬種中買仲間」の起源であり、“くすりの町「道修町」”の始まりとされています。 道修町は地下鉄御堂筋線の淀屋橋、京阪電車〔おけいはん〕 の北浜駅はら歩いて直ぐのところです。皆さん、暖かくなった頃、出かけて見ませんか?♪
2006.03.02
コメント(2)
-
隼と鳩の戦いと玄宮園の美しさの関係は?
(彦根城の続編)彦根城にある美しき玄宮園の紹介でーす。!♪玄宮園は彦根城の北東にある大池泉回遊式の旧大名庭園なのです。彦根城天守閣や茂った木々を背景にして大きな池に突き出すように臨池閣が立ち、築山には鳳翔台があります。この鳳翔台は、彦根藩の賓客をもてなすための客殿なのです。ひなびた趣のある建物。樹木・岩石・池を巧みに配し、池の周りに、湖南省洞庭湖の瀟湘八景にちなんで選ばれた近江八景、竹生島や沖の白石などを模して造られていて情趣のある庭になっています。また、鳳翔台では、抹茶を楽しむことができます。隼と鳩の戦いを忘れて、庭園を鑑賞しながらの抹茶の味わいは格別かな?池に浮かぶ蓮や菖蒲の花が咲く初夏の季節には、花の香りが園内を包みます。楽々園とともに国指定の名勝ですよ。ぜひ、一度行かれたし。!♪
2006.03.01
コメント(0)
-
彦根城と玄宮園を訪れて♪
気分転換を兼ねて、琵琶湖東岸の彦根城に出かけてきました。彦根城は元和8年〔1622〕に20年の歳月をかけて完成したそうです。唐破風、千鳥破風、火灯窓をつけた華やかな天守閣は国宝に指定され、彦根の象徴ともなっています。また、天守閣をめぐる石垣と内濠、中濠を持ち、城郭が往時のまま現存し、全国でも数少ない名城として名高いですね。いい事ばかりですが、天守閣の中の階段は、超急角度+幅の狭すぎ+つるつるピカピカ状態→メチャ滑りやすいので要注意!です。玄宮園は楽々園の東隣に造られた井伊家の旧下屋敷の大名庭園です。その名の起こりは、唐〔中国〕の玄宗皇帝の離宮にならったもので、その造りは近江八景を取り入れたということから八景亭とも言われています。池泉回遊式の優雅な庭園で、四季折々風情があります。池越しに眺める彦根城は一幅の絵を見ているようですね。今の時期、沢山の冬鳥が飛来しています。堀や池に冬鳥のための可愛い小屋が浮んでいます。〔入りやすいようにアプローチ階段もあるのですよ。〕でも、今日、内堀の池でまだ若い隼が鳩を襲う瞬間を目撃しました。でも、若鳥ゆえのキャリア不足で隼は鳩の捕獲に失敗しちゃいましたよ。良かったのかな?彦根城内外の松の木々は素晴らしい。江戸時代から平成の今日まで風雪に耐えて尚且つ生き生きとしています。〔のきしのぶが沢山群生してますよ。〕今度は桜咲く四月にもう一度出かけようと思っています。♪
2006.02.28
コメント(0)
-
古地図を持って中世の大坂を訪ねる?
豊臣秀吉は上町台地の北端に大坂城を中心とした巨大な近世城下町を築きましたが、それ以前の大坂には寺院や神社を核とした中世の集落点在していました。現在は巨大ビル群に覆われた大阪ですが、弥生三月が真近となり、地下に眠る中世都市大坂を古地図を参考にしながら、中世大坂の景観を体感したくなって歩いてきました。☆旅人が行き当たりばったりに歩いたコース☆大坂本願寺と渡辺津を結ぶ島町通り→上町台地北端の崖→坐摩神社お旅所→府立労働センター〔大坂城遺跡〕→高麗橋〔大坂城惣構堀・高麗橋里程元標跡〕→北浜界隈→少彦名神社〔道修町・薬の資料館〕上町台地に行けば、古代・縄文時代に遡る台地が実感できるし、道修町に行けば、古地図〔商人町図〕と現代の町割りの変わることのない同時性〔奥行き20間〕や秀吉の城下町作りの精緻性や狙いが良く分かり絶対感動しますよ。♪帰り道、薬問屋の多かった道修町の(日本の薬祖神を祀る)少彦名神社で「お守り」を買って帰りました。訪れたコースの紹介はこれから少しずつ紹介します。♪
2006.02.26
コメント(0)
-
スクーリングの延長線上ですよー!♪
2月17日~19日のスクーリングでは、江戸時代の大和郡山城の領域の歴史地理をかなり詳しく教えていただきました。僕の生まれ育った郡山、我が家の愛犬の毎日の散歩コースである郡山城と城下町の勉強でした。身近であり、改めて、江戸時代の城と城下町と街道がどのように変貌して明治時代の姿になったのか、良く理解できました。そんな訳で、今日はスクーリングで学んだ事の延長線上で、城内にある柳沢文庫の「郡山町名尽」を紹介します。この史料の作成時期については、はっきりしたことはわからないのです。明治時代の作品と想定されています。たわむれに詠まれた戯歌の類ですが、柳町を初め郡山の町名が全部で23も詠み込まれています。さらに、「大橋」を奈良口の秋篠川にかかる大橋と考え、これを奈良口町の代わりとすると合計24になります。それでは、その歌詞を紹介してみましょうか。♪ ♪♪ 郡山町名尽 ♪♪実おもしろや、君が代は、よむとも尽し言の葉の、其名も高き郡山、町の数々詠れハ、人のこころもやわゝゝと風にも忍ぶ柳町、緑とともにさく咲く花に、君をとめてゝ岡町や、おもひ入たり一念は、石にも立や矢田町の、つつ姿は(〃も)あらわれて、うき名やよそに高町田(田町)、恋の重荷を積載て、君にひかるゝ車町、かくと丸との人こころ、材木町ハ色とかや、唯世の中のまかりをも、すくに直すや大工町、ふかき心と満入て替らぬ色ハ紺屋町、都女郎は色白く、きめのよひのハ豆腐町、華のさかりは過ぬとも色の盛ハ今井町、いつれこころハ片はらぬ、すいとやほどの堺町、心のたけきものゝふも、恋にやわらく綿町や、おもふ心ハ神かけて偽りならぬ本町や、親子夫婦の中よきハ誠に水と魚屋町、ころりと人をころすのか、君かめもとの塩屋町、たれとの(〃〃に)引れてうかうかと今宵ハ爰に藺町や、せうねのわるい女郎衆雑魚寝の雑穀まつ恋そつもりて渕となる、身のすへ何と奈良町や、人の姿ハ黒くとも、こゝは白き鍛冶町や、二人の中ハいつ迄も薄きはいやよ濃茶町、観音寺町祈りなはいつかは君に大橋や、爰も名に逢ふ名所とて咲やこの花難波(何和)町、只何事も平らかに治る御代や平野町、野辺山々も蒼々と賑ふ春こそめでたけれ(以下は省略します) 歌詞の調子だけみてもたいへん滑稽な、そしてたいへん味わいのある歌です。出だしが「実おもしろや、君が代は、よむとも尽し言の葉の、其名も高き郡山、町の数々詠れハ」と始まりますが、「其名も高き郡山」とあるあたり、詠み人の郡山に対する思い入れのほどがよくうかがえます。その歌詞も軽妙ななかにうまく町名が詠み込まれています。 掲載の写真は大工町を詠み込んだくだりで、1行目の2文字目から3行目にかけて「唯世の中のまかりをも、すくに直すや大工町」とみえます。郡山城下町を造った豊臣秀長によって当初大工が集住させられたといわれる大工町ですが、家などの修繕をする大工の仕事をもじった歌詞となっていますよ。この続きはまた後日のお楽しみに!♪
2006.02.21
コメント(0)
-
二つのハードルを越えて?
ばんざーい! ばんざーい! 嬉しいなあ!♪四面楚歌・火の車状態になっていた我が家ですが、今日、ハッピーand平安な出来事が報告できる事になりました。一つは家内が退院しました。病院にずーつと居ると退屈で退屈でしょうがなかったようです。僕も慣れない主婦?とおさらばできるようになりました。もう一つは、昨年、全滅・全敗で浪人生活中だった息子がやっと浪人脱出できる事になりました。息子は希望する大学に入学できることとなり、気持ち先行で、今から入学式はスーツを着ていくとか、入学前に車の免許が取りたいとか、パソコンが欲しいとか等々はしゃいでいます。やれやれです。これで僕も休止していた文化財歴史学の学習に本格的に取りかかる気分になれそうです。
2006.02.19
コメント(4)
-
四季折々の楽しみとは?
誰もが時代を離れて生きられないように、風土からも離れる事はできません。日本の風土は四季折々にその素晴らしさを持ち合わせています。「春も淑し、夏も良し、秋も好し、そして冬も吉し」ですね。また、「晴れた日、雪の降る日、雨の降る日」と時に応じて趣をことにした姿がありますね。旅人の今日この頃は、家内の病と息子の大学受験が重なり、ダブルパンチ・火の車状態です。我が家の息子が小さかった頃は、冬といえばスキーand温泉が家族のメーンイベントでした。一番よく出かけたのは、新潟県の赤倉スキー場でした。冬は盆地ということでかなり寒い奈良なのですが、殆ど、雪は積もりません。雪の殆ど降らない奈良県人にとって、天武天皇の大原の雪の歌〔巻2-103〕の僅かな雪降りでも、ものすごーく嬉しいという気持ちは良く分かりますね。♪わが里に 大雪降れり 大原の 古りにし里に 降らまくは後そんな訳で、冬は雪遊び・温泉という固定観念がぬぐえず、毎年のように雪に出会うために、奈良を脱出していました。きっと、鬼に笑われると思いますが、今から、来年こそ"冬を満喫するためにスキーand温泉に行くぞー!"と心に決めています。♪
2006.02.13
コメント(0)
-
飛鳥美人は泣いているぞー!!!
2月9日の早朝、愛犬の散歩から帰宅し、郵便受けから朝刊「毎日新聞」を何気なく取り出し開いて、”ホンマなんやろか?”と我が目を疑いました。以下、関係箇所を新聞記事より一部抜粋します。「文化庁は9日、高松塚古墳の石室西壁の女子像の右目尻と右肩に、黒いしみを見つけた」文化庁の説明「女子群像の中央に立つ像で、しみは目尻が直径約1ミリ。右肩は衣服を中心に、縦約2センチ、横約3センチの範囲に広がっていた」「今月2日の点検で撮影し、画像を精査した。過去の写真との比較では、9月には既に兆候が出ていた。目尻のしみは、漆喰内部から染み出しているようにも見え、肩の部分は9月と比較すると少し濃く大きくなっていた」写真をよく見れば、悲しいかな、しみは泣きぼくろに見えますね。誰が泣かしたんやー!!! 恒久保存対策検討会では、今後、壁画を保護する養生期間を経て、来年2007年2月半ばから約1カ月半かけて石室を解体し、約10年の長きにわたり石材、壁画を保存する日程を決定してしまいました。こんな悠長なことをしていて良いのでしょうか?飛鳥美人が泣いてます。一刻も早く救出すべきですよね。♪
2006.02.12
コメント(1)
-
親父のおにぎりの味はどんなんやろか?
今日は息子の大学受験日です。早起きして、生まれて初めて、子供のお弁当を作ったのです。梅干・昆布・雑魚入り・韓国海苔巻きのおにぎりを2つ。出来上がりは、かなりの不ぞろいでしたね。お茶を用意してあげて、「お母さんは大丈夫やで!、頑張っといでー!」と声かけして送り出しました。今日合格なら、僕の後輩になるのですが・・・・・・???普段は殆ど話しをしない親父と息子ですが、我が家の四番バッターである家内が不在中は、ぎこちないですが夫々協力しあって精一杯頑張っていますよ。そんな訳ありで、当分の間、ブログのテーマからかなり外れちゃいますがよろしく。
2006.02.11
コメント(0)
-
本当の幸せとは?
今、帰宅しました。朝、AM8:00からPM11:00までたった15時間しか経過していないのに、あっと言うまに2日以上過ぎ去ったような気がします。妻の手術は少し転移があったものの、結果は成功でした。よかったー!♪家内も良く頑張りました。麻酔が覚めて時間が経って家内の笑顔を確認して安心しましたよ。今日は昼食抜きでした。真っ暗な夜道を家内の洗濯物を引っさげて帰宅すれば、息つく暇もなく夕食の用意・夕食・愛犬の散歩・洗濯等々すっかり主婦に早替わりです。これから先、家内の退院するまでの一週間あまり、試行錯誤を繰り返す事となりますが、精一杯頑張ろう!?と思っています。
2006.02.10
コメント(2)
-
妻よ、頑張れ!
めったに神仏に縋らない僕も今日は何度も何度も祈っています。 家内は今、手術室で頑張っています。 家内は気丈なのですが、手術が無事終わるまで気掛かりです。 時間の長さをこんなに感じたのは生まれて初めて経験です。 今さらながら家内がいないと何も出来ない自分自身が情けない。 改めて、家族の健康と心の平安の大切さを実感しています。 わが家は息子の大学受験とも重なって、今、緊急事態なのです。 今、全てハッピ-エンドで完了することを祈っています。
2006.02.10
コメント(0)
全149件 (149件中 1-50件目)