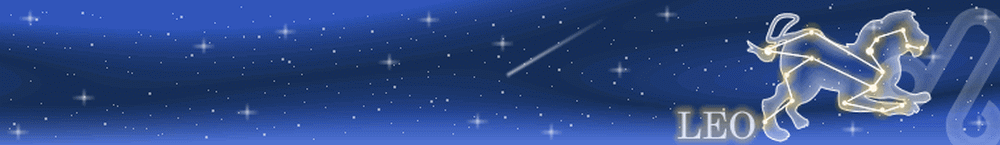2010年06月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-

ホタルブクロ
百人一首 春の夜の夢ばかりなる手枕に かひなく立たむ名こそ惜しけれ 周防尚侍 (短い春の夜の夢のような儚いたわむれに、手枕を借りたばかりに、立ってしまった浮名が残念です) 周防尚侍(すおうないしのかみ)は、平仲。後冷泉天皇、後三条天皇、白河上皇、堀河天皇に仕え、多くの歌会に参加した。
2010.06.05
コメント(1)
-

アブチロン
法務省赤レンガ棟明治19年、政府は西洋建築による官庁街集中計画に着手した。当初の案では、主要官庁すべてを一ヶ所に集めて、巨大な官庁街にする筈だったが、諸般の事情により縮小された。最終的に、現在は残っていない最高裁判所と、この司法省の庁舎の完成のみにとどまった。 赤レンガ棟は、明治28年に竣工し、計画の壮大さを今に残す唯一の遺構である。堂々たる建物は、ドイツのネオバロック様式で、ドイツ本国の建築にも優るとも劣らない。屋根中央に小さな尖塔を乗せ、左右両翼に張り出したゴシック風の外観は、気品さえ感じさせる。レンガ造りの西洋館には珍しく、なんとなく懐かしさもある。
2010.06.05
コメント(0)
-

徒然草 5
「人は、おのれをつづなやかにし、おごりを退けて、財をもたず世をむさぼらざらんぞ、いみじかるべき。昔より、賢き人の富めるは、まれなり」 訳「人間は生活を簡素に整え、贅沢に走ろうとする気持ちを戒め、必要以上に財産など蓄えず、世間の名声や名誉を求めて奔走せず、あるいは他人に見せびらかすことを慎むことが、見上げた生き方である。昔から、賢い人と尊敬されるような人が、財産家であったためしはない」 むさぼらんぞとは、得られる限りの利益や快楽を掻き取ろうとする浅ましい行いはするな。とはいえ、この日本に暮らしている人々は、そんなことを言い聞かせたところで、聞く耳は持たないだろう。そうした行いがいかに醜く、やがて悪い結果に繋がるとしても、それは自業自得だから、放っておけば良い。贅沢や快楽が身体を損ねるよと言っても、人間はそうなってからでないと気がつかない。言っても理解できない人間には、いくら言っても無駄だ。 「富貴爵禄は、みな人事の無くんばあるべからざる所の者。只当に礼儀を弁ずべし。あに徒に以て外物と為して之を厭うべけんや」富や地位、名誉を欲しないのなら求めなければよろしい。それを罵るのは、世を拗ねた負け惜しみである。人の世には身分があり、(魂の人格もある)隔ても存在し、富貴があり、それによって社会は成立している。富貴爵禄を蔑んだり、罵ったりする人間は、所詮人間社会から遊離し、寂寞の拗ね者になるのが落ちだ。この説は、江戸時代の儒学者、伊藤仁齋の言葉である。
2010.06.05
コメント(0)
-

百人一首
タチアオイ 百人一首 もろともにあはれと思へ山桜 花よりほかに知る人もなし 前大僧正行尊 (私があなたを懐かしく思うように、あなたも私を懐かしく思っておくれ山桜よ、山奥では花以外に私の心を知ってくれる人がいないのだから) 前大僧正行尊(さきのだいそうじょうぎょうそん)は、十二歳で出家し、修験者として名高い。
2010.06.04
コメント(0)
-

猫の母子
2010.06.04
コメント(0)
-

古事記 3
宇宙の初めにあらわれた三柱の天神は、男神のイザナギと、女神のイザナミに言葉を与えた。「地上の有様を見ると、ただ脂のようなものが漂っているだけだ、お前たちはあの地を、人間が住めるように造り上げなさい」こう命令すると、美しい玉飾りを施した天沼矛をイザナギ・イザナミに授けた。国造りという重い責任を負った二神は、天と地の間に架けられた天浮橋に立ち、天沼矛を漂う脂のようなものの中へ突き刺し、ぐるぐると掻き混ぜた。すると、次第に固まっていった。天沼矛を引き上げると、潮が滴り落ちて、積もり積もって島になった。その島をオノゴロ島という。イザナギ・イザナミは天浮橋からオノゴロ島に天降り、立派な柱を立て、巨大な邸を建てた。新婚生活を始めた夫のイザナギが、妻のイザナミに言った。「そなたの身体はどのようにできているのか?」「私の身体は美しく完璧にできていますが、ただ一箇所だけ欠けているところがあります」「私の身体も美しく完璧だが、一箇所だけ余分なところがある、そなたの欠けているところへ、私の余分なところを合わせ、塞いで国を生もうと思う」と話し合った。「そなたは柱の右側から回りなさい、私は左側から回りましょう」と、左右に分かれて回り始めた。出合ったところで、イザナミが、「なんと、見目麗しい男神でしょう」と感嘆し、イザナギも、「なんと、見目麗しい乙女だろう」と感激した。しかし、イザナギは、「女神が先にものを言ったのは、良くない徴だ」と言った。やがて生まれてきた子は骨のない子だったので、葦の舟に入れて流してしまった。次に淡島を生んだが、これも同様だったので、子の数には入らない。
2010.06.04
コメント(0)
-

赤いバラ
百人一首 恨みわびほさぬ袖だにあるものを 恋に朽ちなむ名こそ惜しけれ 相模 (あの人のつれなさを嘆き悲しんで、袖が朽ち落ちてしまうのも口惜しいが、浮名を流して我が名が朽ちることが惜しくてならない) 相模は、相模守大江公資の妻なので相模と呼ばれたが、離婚して一条天皇の娘脩子内親王に仕えた。
2010.06.03
コメント(0)
-

万葉集
モチツツジ 大伴旅人山上憶良とともに「筑紫歌壇」を形成していた。大伴氏は大和朝廷の軍事を担当する有力氏族で、旅人の父安麻呂は壬申の乱で大海人皇子側で戦い、功績をあげた。しかし持統・文武時代の大伴氏には風雅な人が多く、旅人も和歌や漢文学に優れていた。旅人の弟の田主も風流士と呼ばれた人物であり、また妹の坂上郎女にいたっては、女流歌人の第一人者として名を残した。旅人は政治の面でも順調に昇進し、720年には征隼人持節大将軍(せいはやとじせつだいしょうぐん)となり、728年、太宰帥(だざいのそち)として筑紫へ赴任した。その前に、聖武天皇が吉野へ行幸した際の歌。 み吉野の 吉野の宮は山からし 貴くあらし水からし さやけくあらし 天地と長く久しく 万代に 改らずあらむ 幸しの宮(天皇が行く美しい吉野の宮は、山が良く貴い、川が良く清らか、天地は長く久しく万代変わらずこうあってほしいものだ) 昔見し ささの小川を今見れば いよいよさやけく なりにけるかも(昔見た象の小川を再び見ると、ますます冴え冴えと美しくなった) 奈良の都を愛していた旅人にとって、大宰府への赴任は本意ではなかった。太宰帥は名誉ある役職ではあったが、その時旅人は60歳を過ぎていた。その上、大宰府に到着するとすぐ、同行していた妻が亡くなった。故郷から遠く離れた土地での不幸は、老齢の旅人にとって辛過ぎた。 世の中は 空しきものと 知る時し いよよますます 悲しかりけり(この世は空しいものだと知るにつけても、新しい悲しみがこみあげる)
2010.06.03
コメント(0)
-

古事記 2
ザクロ 古事記の著された目的は、第一に、日本の初代天皇が神武天皇で、彼によってこの国の統治権が発動されたこと。第二に、この国の国土は、イザナギ・イザナミの神によって造られ、この神の正統な血を引く者が国土の所有権を持ち、統治権を発動できる、ゆえに天皇が日本を治めるのは正しいことであるという見方が正統とされている。しかしそれは表向きで、その細工された文体、含みを持った叙述、旧約聖書との類似点などから、古事記はそれ以外にもっと重要な意図を持って著されたのではないかと思える。古来より、古事記の謎を解明することは死を意味するなどと言われてきたが、その理由は一体何だろう。古事記は、人類が滅亡する時期を予言しているのではないのか?あるいは、古事記には滅亡を食い止める方法が隠されているのではないか。古事記こそ、人類の未来への手引書なのかもしれない。旧約聖書の天地創造には、「初めに神は天と地を造った。地は形なくむなしく、闇が淵のおもてにあり、神の霊が水のおもてを覆っていた。神が『光あれ』と言うと光があった。その光を見て、神はよしとする。神は光と闇とを分け、光を昼、闇を夜と名付けた。夕となりまた朝になった。第一日目である」と書かれている。一方古事記の国造りには、「宇宙のはじめ、天も地も混沌としていた時、天のいと高いタカマガハラに三柱の神がいた。世界の中心となるアメノミナカヌシ神は宇宙を統一する役目を持った神である。つづくタカミムスビ神とカミムスビ神は宇宙の生成を司る神である。これらの神は配偶者をもたぬ単独神で、姿を見せることはなかった」とある。続いて旧約聖書は、「神は二日目に天と地を分け、三日目には海を、四日目には天体を造った。五日目に空を舞う生物と、水に棲む生物を造り、六日目に地上の動物と最初の人間を造った」と続く。古事記は、「天と地のけじめがなく、形らしい形もない地上は水に脂を浮かべたように漂うばかりで、あたかも海月が水中に流れるような頼りなさであった。しかしそこに水辺の葦が春にいっせいに芽吹くがごとく萌え上がるものがあった。その中から二柱の神があらわれた。うるわしい葦の芽の、天を指し登る勢いを示すウマシアシカビヒコヂ神、ついで永遠無窮の天そのものを神格化した神であるアメノトコタチ神である。この二柱の神も配偶者を持たない単独神で、姿を見せることはなかった」となっている。
2010.06.03
コメント(0)
-

台風
日本は台風の通り道ですが、フィリピンも同じように台風の通り道であるため、昔から大変な目に遭ってきました。フィリピンに台風が襲来するのは、年間20回から30回で、そのうち上陸するのは約9回にもなります。日本の場合は、台風が上陸するのは年間3回前後ですから、多いように感じてもフィリピンに比べれば少ないですね。被害も深刻で、2004年には死者が千人以上、家屋の損壊は13万棟に及びました。フィリピンの気象庁では、台風シーズンには4段階の警報を出し、注意を呼びかけています。警報の第一段階は、小さな木の枝が折れる程度の暴風。第二段階は、ココナツの木が倒れたり、傾いたりする暴風で、一部の学校や会社が休みになる。第三段階は、全てのバナナの木が倒れるほどの暴風で、全ての学校や会社が休みになる。第四段階は、大木が根倒しになるほどの暴風で、この段階になると非難するのも遅すぎるらしい。
2010.06.02
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 朝ぼらけ宇治の川霧たえだえに あらはれわたる瀬瀬の網代木 権中納言定頼 (夜がほのぼの明ける頃、宇治の川面に立ち込める霧がとぎれて、その絶え間から川瀬に仕掛けられた網代木が、あちらこちらに見えるようになる) 権中納言定頼(ごんちゅうなごんさだより)は、藤原定頼。和泉式部の娘の小式部をからかって、やりこめられたという逸話がある。
2010.06.02
コメント(0)
-

徒然草 4
徒然草 4或人、法然上人に、「念仏の時、睡にをかされて行をおこたり侍る事、いかがして、この障をやめ侍らん」と申しければ、「目のさめたらんほど、念仏し給へ」と答へられたける、いとたふとかりけり。また「疑ふながらも念仏すれば往生す」とも言われけり。これもまたたふとし。ある人が法然上人に、「念仏を唱えている時、眠くなってしまいますが、どうしたら、仏に対するこのような不始末を解消できるでしょうか?」と訊ねた。すると上人は、「目が覚めたら、その時から続きを唱えれば良いんですよ」と答えた。また、念仏を唱えることにどんな意味があるのかと疑いながらも、念仏さえしていれば、極楽往生できる運命になるのだとも言ったと聞いた。まことに尊いお言葉だ。法然以前の仏教は、戒律重視の宗教だった。法然が登場した平安時代末期から鎌倉時代初期にかけては、貴族文化が衰退し、疫病が流行し、さらに釈迦の教えが形骸化していくという末法思想が広まった。人々は厭世観に捉われていた。そこへ法然が登場し、ただ念仏を唱えなさい、阿弥陀如来は、全ての人間を極楽往生させたいと願っていらっしゃる、如来に帰依しなさい、それだけで良いのだと説いた。これが、法然が始めた浄土宗の教えである。浄土宗のように、念仏を唱えることによって極楽往生できるという宗派を、念仏宗と言います。念仏は「極楽往生させてください」という請願かと思われているが、実はそうではなく、阿弥陀如来の慈悲深さに感謝するお礼の言葉なのである。人々が慈悲深い心を持ちさえすれば、それ以上は何も要求しない。この教えを後に親鸞が、浄土真宗という形に発展させた。吉田兼好が、この法然を取り上げたということは、念仏宗の教えの根本を、兼好は押さえていたのである。
2010.06.02
コメント(0)
-

ブラシノキ
ビン洗いブラシにそっくりな花。英名もビン洗い。日本には明治中期に渡来した。ブラシの毛のように見えるのはオシベで、花びらは極小さくて、開花後すぐに散ってしまう。白花もあるが、まだ見たことがない。
2010.06.01
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 今はただ思ひ絶えなむとばかりを 人づてならでいふよしもがな 左京大夫道雅 (今となっては、ひたすらあなたを忘れてしまおうと、それだけを人伝でなく、直接あなたに言える方法があれば良いのに) 左京大夫道雅(さきょうにだいふみちまさ)は、藤原道雅。藤原道長の権勢に押されて、父伊周に死後は没落し、不遇の人生を送った。
2010.06.01
コメント(0)
-

徒然草 3
ニワゼキショオウ 徒然草には、名前を出さず「なにがし」などで表す人の言葉がよく引用されています。これは吉田兼好が、自分の考えをいかにも他人が言ったかのように記したのであろうと、内海月杖(明治の歌人・国文学者)は推測しています。徒然草の内容は、思想、人間観、有職故実、恋愛観、政治批判など多岐にわたり、細やかな感性と観察眼、豊かな知識を持った作者の幅広さをあらわしています。その人間観察の鋭さは、井原西鶴などに多大な影響を与えました。西鶴の作品の多くは、徒然草なくては生まれなかったと言われています。 仏教思想が人々の間に浸透していた中世は、貴族を中心とした華やかな平安時代も末期になると、天然痘などの疫病、日照りによる飢饉、武士の台頭など、混乱期を迎えた。仏教は比叡山の僧兵による三井寺の焼打ちなど、内部抗争が絶えなかった。釈迦入滅後2千年を経ると、教えだけは残るが悟りを得る者はいなくなるという末法思想が流行した。人々は無常観に沈潜し、神仏の助けを懇願した。貴族も庶民も諸魚無情を感じた。兼好も例外ではなかった。それに呼応して現れたのが、鎌倉新仏教で、阿弥陀仏に救いを求める浄土信仰、法然の浄土宗、親鸞の浄土真宗、一遍の時宗が民間に広まった。武士は座禅によって悟りに至る禅宗、栄西の臨済宗、道元の曹洞宗などが受け入れられ、法華経が中心の日蓮宗も発生した。お盆や先祖供養の習慣も、収穫祭と合わさって農民の間にも広まった。仏教が持つ無常観の雰囲気は、文芸にも多大な影響を与え、平家物語などの軍事小説や、出家した世捨て人による隠遁文学が盛んになった。徒然草のほかに、鴨長明の方丈記、西行の山家集などが後世に残った。貴族社会で出世した兼好は、慕っていた貴人が亡くなったのをきっかけに、宮仕えを辞め、世を捨てて出家したと考えられる。兼好のような世捨て人は、出家しても寺には所属せず、僧侶とは区別して、一般には沙味、沙味尼と呼ばれていた。兼好も貴族社会から遠去って、小野の山里、延暦寺の別院修学院の辺りの庵に住んで、一人ひっそり暮らしていたが、歌人としては貴族達との交流を断たなかった。仏教思想の浸透と同時に、兼好のような暮らしを求める人は多く、社会もそれを受け入れていた。そうした立場の人々によって、和歌や文芸、学問の世界で偉大な業績が残った。
2010.06.01
コメント(0)
全15件 (15件中 1-15件目)
1