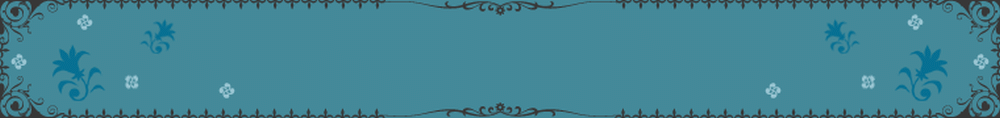全153件 (153件中 1-50件目)
-
演奏のお知らせ
2月9日18時ハイデルベルク大学旧講堂大学関係者招待貴志康一 竹取物語 かごかきHaendel 9つのドイツアリアより「Flannmende Rose」Mozart 「牧人の王」より「彼女を愛そう」J.Strauss 春の声Sop.Emmy AboViolin 長谷川明美ピアノ N.N.4月22日 Karfreitag 受難の金曜日 15時Weinheim Markus教会オルガン曲とPergolesi Stabat MaterよりアリアSop.Emmy Aboオルガン Pr.Leo Kraemer
2011.01.15
コメント(0)
-
villa musica 堺 第一回 声楽講習会
11月に堺市民会館でヴィラムジカ堺 第一回声楽講習会を開催します。詳細はこちらです。http://www.villa-musica.de/13.htmlドイツに留学してみたい、でも事情がよくわからない、という方。ドイツ語の歌詞に苦労している方。テクニック上の疑問がある方。コロラトゥーラの練習法を知りたい方。時々ネット上で、声楽を習っている方の疑問に答えてきましたが、言葉で説明するのはとても大変だけど、目の前で歌ってみればすぐ理解できることがあります。そういう問題を解決する機会になれば、と思います。
2010.09.23
コメント(0)
-
ブブゼラ@クラシック
3時間後に対アルゼンチン戦、土曜の4時、きっと外を歩いている男は一人もいないでしょう。点が入ると、ドイツでは大晦日以外禁止されている花火を備蓄していた家庭が打ち上げるので、その音でTVを見ていなくても試合の運びが判ることになっています。我が家ではゴールをすると、息子が習っているトロンボーン、私が付き合いで吹いているトランペットでナチュラルトーンをぶっ放しております。ファンファーレなんて無理ですから・・・・。アフリカ大会で急に流行したプラ管ブブゼラ、集団でぶんぶん羽音のような音を立ててますね。このラッパでB以外の音も出せるそうです。ベルリン某オケ金管セクションの三人組による世界初演ビデオをどうぞ。英語字幕付き。http://www.youtube.com/watch?v=wf2P8SnOwLo&feature=player_embeddedDie Zeitという真面目な新聞のサイトに載った冗談ヴィデオ。この新聞社、真面目なCDブックも出していて、三代目は最近フランクフルトの某書店で定価9,95を特価2,95で買い込んだばかり。バーンスタイン、デュプレなど天国の巨匠に混じって刈上げ君ナイジェル ケネディもという人選。友人Kちゃんによると日本では東京新聞が東スポに次いで冗談がわかるそうなので、(東スポの次って相当柔軟なような)ぜひ東フィル(都響が冗談に参加するんだろうか・・・)金管セクションで日本初ブブゼラバンドを披露していただきたい。法螺貝とのコラボもよいかも。ではサッカーに備えてラッパの練習を。
2010.07.03
コメント(0)
-

ヒットラーとバイロイト音楽祭
三代目が姐御と仰ぐベルリン時代の友人が、長年掛けて翻訳した大作が遂に出ました。ワグネリアンのみならず歴史好きにも推薦の良書、「ウィニフレッド ワーグナーの生涯ヒトラーとバイロイト音楽祭」ブリギッテ ハーマン女史の原著は大変分厚い本で、この日本語版は上下巻に分かれています。原著同様、翻訳も読み易い文体です。バイロイト音楽祭を現役のドイツ首相が訪問するのは戦後長らくタブーでした。それを破るのに貢献したのは、オペラ好きな日本の首相(当時)。招待したのはシュレーダー首相(当時)。切符を手に入れるのが至難の業となっているバイロイト音楽祭。1990年代、バイオリンのトーマスの御厚意でゲネプロを見学した三代目、雨女の呪いは緑の丘にも及び、上演中に降った雹が屋根を打ってうるさかった・・・。リハーサルなのに満席で、切符を求める人がSuche Karteと紙に書いて立っていました。もちろん転売防止にゲネプロの切符には名前が書き込んであって確認のためにパスポート持参のことと裏に書いてありました。(実際にチェックはされませんでしたけどね。)(その後勢いづいてレーゲン詣でにも行きました。もちろんヴァルハラは雨で、船着場からの登り階段には巨大なナメクジが這っていました。)それほどレアな切符となった現在と違ってバイロイト音楽祭には切符をさばくのに苦労した時代もありました。ワグナーの音楽を愛した独裁者ヒトラーとバイロイトのつながりについて、この本を読めば理解できることがあります。性懲りもないナチばあちゃんと思われていた、先ごろ亡くなった音楽祭の総監督ヴォルフガングとその前をつとめたヴィーラントの母、ヴィニフレートの別な姿が見えてきます。ワグナーの息子の嫁ヴィニーの「細腕繁盛記」ともいえる上巻。高価な本ですが、購入者が古本に出さない本と思われます。懐が寂しい方は図書館に購入希望を出しましょう。最近下巻も発売されました。
2010.05.11
コメント(0)
-
清しこの夜Stille Nacht 秘話
ORFの番組で清しこの夜秘話というのを見ました。作詞者のヨーゼフ フランツ モーア は1792年ザルツブルク近郊で生まれ、貧乏だったけど才能を見込まれ援助を受けて神学を勉強しました。1816年にStille Nachtの詩を書いたというので、24歳の時ですか、若いですね。村人と一緒にビールを飲んだり、人々との付き合い方が神父らしからぬ、というので田舎に飛ばされました。Oberndorf村の聖ニコラウス。そこでトラのオルガニストをしていた作曲者のフランツ クザーバー グルーバーと出会います。1787年だから5年年長。モーアの詩に付けた曲の初演はギター伴奏でした。そういえば、ギター伴奏だとオーストリー民謡っぽいですね。ぶんちゃっちゃ・・・。教会のオルガンはネズミに風袋をかじられて音が出なかったからだそうです。Youtubeの無かった時代、口コミ?でStille Nachtは近郊の村へ、ザルツブルクへ、ウィーンへと、歌われ広がっていきました。この有名になった歌はミヒャエル ハイドン(ヨーゼフの弟)の作曲ではないかという噂も立ったそうで、問い合わせに答えてグルーバーが書いた手紙のお陰で作詞者作曲者の名前が正確に後世に伝わりました。教会音楽家、教育者として成功したグルーバーは1863年没、76だったら当時としては長生きですね。肖像も残っています。一方1848年に亡くなったモーアは僅かな遺品しか残さず、葬儀費用にも足りなかったそうです。肖像も残ってないので、銅像を作るときにお墓から掘り出した頭蓋骨で顔を推定したそうです。Frohe Weihnachten!素敵なクリスマスを。
2009.12.24
コメント(0)
-
日本で買ったチューナー
日本に帰った時に絶対買おうと思っていたものがコレ。チェンバロの調律用に、昔買ったドイツ製は反応が遅く使いにくかったので、調律師さんお勧めのKorgが欲しかったのです。でもドイツで買うと、143Euroから。日本で買うと半額じゃありませんか。使いやすいです。二段マニュアルの調律に今まで1時間以上掛かってましたが40分に短縮。プロは20分でやるので、まだまだ下手なんですが、チューナーを替えただけで、ずいぶん早くできるようになりました。配送も比較的早かったし、ここが一番安かったです。それにしても電器関係は物価安いわ、日本。食べ物は食材が結構高いわりに外食はドイツより安い。なんでや!?
2009.11.09
コメント(0)
-
巨匠とコンサート
遂に念願が叶い、巨匠レオ クレーマーを迎え、わがマルクス教会で第一回のチャリティコンサートが実現します。今年1月から毎週奏楽を担当させていただいているワインハイム、マルクス教会。戦後に開発された住宅街にありがちな、コンクリートのモダン建築。60年代の建物ですが、既に文化財保護物件です。その理由は美しいガラス。中世のステンドグラスとは一味違う、活気のあるデザインと色。で、早々と保護されてしまったのですが、問題は隣接する鐘楼も一緒に保護がかかってしまったこと。中世のレンガだったらよかったのにコンクリートなので、劣化してきました。いっそ壊して立て直すほうが安いくらい、現状を維持しながらの修復には費用がかかるそうです。スポンサーマラソンなどイベントを開催したり、月一回手作りケーキ販売したり、コツコツと募金活動をしているゲマインデ。教会の塔と鐘は地域のシンボルでもあります。アウトバーンを南下してくると、Weinheim出口付近で目に入るマルクス教会の塔。これは地域住民にももっと知ってもらおう、というわけで、かねて希望していた演奏会の収益を修復費用に寄付することにしました。なにしろ当教会のオルガニストは歌手の副業(すみません私です)、コンサートにはゲスト オルガニストが必須です。楽器は60年代、歴史的価値があるものではありませんが、機械式トラッカーでバッハを演奏するのに決して悪くないものです。小さなオルガンを弾いていた頃、熱望していたPosauneだって電子コンビネーションも付いてます。どうせなら当たってくだけろ、ビッグネームが第一回なら今後も続けやすかろうと、歌人けふちゃんに紹介していただいたSpeyerの巨匠レオ様にアタック。ワシは何弾いたらいいんだね、ととっても気さくにOKしていただきました。レオ様、今年の誕生日に大聖堂を定年引退されましたが、ぜんぜん枯れてません。演奏は快活、指揮はエネルギッシュ、食欲旺盛。こないだの演奏会の後の打ち上げで、パスタ、サラダ、ワインで皆が終わった頃、肉料理とワイン1本追加注文して完食してました。ヘアスタイルは御茶ノ水博士で、キャラはエロ抜きのミルヒーのだめって感じでしょうか。最近メキシコでカルミナ ブラーナを指揮してきたそうです。キューバのダンス付き上演で、1万5千人収容、なのに好評につき追加公演するそうです。来たいんだったら席をいくらでも用意するぞ、って、メキシコまで追っかけする財力ありません・・・・。指揮は、ブルックナーのTe Deumで大暴れって感じでした。一回振ると3Kg減るって、そりゃそうだろう。巨匠近影はこちら。http://www.palatiaclassic.de/wPalatiaC_d/aktuelles/meldungen/2009_06_12_53715664_meldung.shtmlそして日本からのゲストは、以前にベルリンの花輪クンことフローリアン ヴィルケス博士と共演した山田久美子さん。花輪クンが元ベルリンフィル首席のグロート教授に電話して、キミは絶対この子の演奏を聴くべきだ、とむりやりベルリン行きのICEに乗せた、若手トランペット奏者です。おっとりした可愛い人ですが、演奏になると人が変わります。少しお手伝いしたコンクールの入賞者演奏会で耳にとまり、ひょんなことからドイツの演奏会に招いたのですが、空港で始めて素の久美子さんに会って、あれっ、舞台での印象と全然違うぞ、と思いました。キリっとした曲を演奏したので、その世界に入り込んで別の人みたいになっていたようです。ベテラン音楽家と有望な若手を迎えて、ニコラウスの日にふさわしい楽しい演奏会にしたいと思います。
2009.11.02
コメント(1)
-
昭和時代の千秋先輩-貴志康一
1.家は超お金持ち2.美形3.ヴァイオリンが上手4.ストラディバリウスを買ってもらったら日本に里帰りした時に大騒ぎになった。5.作曲も指揮もやる6.巨匠に気に入られ、普通の人は女性秘書のガードを突破するのも大変なのに自宅に電話もリハーサル見学もOKだった。7.ベルリンフィルを指揮、BPOと録音もした。8.東京では第九を暗譜で指揮し、合唱の女学生の目をハートにした。千秋真一くん@のだめ じゃありません。昭和時代の千秋先輩?は、貴志康一。今年が生誕100年です。では検証いってみよう。1.実家は大阪の貿易商、地主(職業・大家と書類に残る)。 生家も母親の実家も保存されているくらいのお屋敷。育ったのは芦屋。2.美形が災いしてキザだとか音楽とは関係ない悪口満載の批評を書かれてしまった。3.上手@当時としては。 習い始めたのは大正時代なので仕方ないですね。 亡命ロシア人に習ったりしてました。なんせ芦屋ですから外人が近所にいた。 で、留学してカールフレッシュ門下のおちこぼれ、壁にぶつかってしまった。4.シベリア鉄道で帰国。膨大な関税を払ったそうです。5.ヒンデミットのクラスを聴講。6.秘書はエリーゼではありません。ベルタというユダヤ女性。ヴィニフレート ワーグナー(バイロイト音楽祭を仕切った英国人の嫁)も巨匠フルトヴェングラーをガードするベルタには手を焼いたそうです。エリーゼとイメージが重なりますね。康一くんは真一くんと違って巨匠のお守りはしませんでした。7.自作を指揮してベルリンフィルの日曜演奏会に出演しました。ただし、これは定期演奏会ではないので、マエストロ小澤がBPOを振るようなステイタスはありません。それにしても昭和9年に日本人が世界最高のオケを振ったということが事件。後日同じオケで録音したものが復刻されていてCDで聴けます。8.当時日本には他に暗譜で指揮する人はいなかった。華麗かつ情熱的な指揮スタイルであったらしい。使わないならどけりゃいいのに、譜面台を置いて、丸めた楽譜を置く演出をしたので、モテない批評家男子の嫉妬を煽った。批評には派手、キザ、が付いて回った。ちなみにベルリンではドイツ人の彼女がいたらしいです。まるで漫画の主人公のような康一くん、残念ながら28歳の若さで亡くなりました。亡くなった理由・・・・・盲腸の痛みを過労のせいと思って我慢しすぎて腹膜炎、KO病院での手術の経過が思わしくなく、大阪に戻って再手術するも一年後心臓麻痺。 その後忘れられていましたが、K松K彦氏が康一くんの伝道師を自認して復活演奏に力を入れ、少しずつ知名度が上がってきました。その康一くんの生涯を三代目が語り、デンハーグのRオケ・ヴァイオリン奏者の由紀さんが貴志康一の作品と彼のレパートリーを弾き、KA在住の桂さんがピアノ伴奏、歌曲は三代目が歌う、という演奏会をします。オランダとドイツから3人が集結、果たして大阪の猛暑に耐えられるか!?2009年8月22日 土曜日14時高槻現代劇場レセプションルーム終演後懇親会つき。関西の皆様、お待ちしております。
2009.07.03
コメント(0)
-
古楽メッセ@Stockstadt 南西ドイツ
行ってきました古楽メッセ!とっても良い天気の今日、仕事に行ったら『本日はルカと合同です。マルクス』という張り紙。がび~~~ん。代理の牧師(もとドレスデン少年合唱団員しゅらいやーの後輩)だから賛美歌の連絡が来ないと思っていたら、私の仕事がなかったからだったのね。はるばるBaselからやってきた学生さんに歌ってもらおうと思っていたのに、申し訳ない。気を取り直して別の曲をレッスンして、お弁当作って、いざ古楽メッセへ。三代目と3人の素敵な独身女性チーム、畑や草原や森やイチゴ畑やアスパラ畑を突っ切って、のどかな村Stockstadtへ。会場の体育館付近は車がいっぱい。駐車しようともがいていたら、弟子2号が友人わじさんを発見。ちょうどコンサートの調律が終わって出てこられたところに出会えてラッキー。楽譜、リコーダー、チェンバロその他の展示即売会場は蒸し暑い体育館のなか。楽器だいじょうぶ・・・・?まずは涼しい木陰に避難してお弁当。楽器を見たりCD、楽譜を漁り。巨大リコーダー、鼻笛、ポルタティフオルガン、チェンバロ・・・。個人的に受けたのは、こどもチェンバロ。かわいい値段はかわいくないけど。鼻笛は白人仕様だったらしく、弟子二号では音が出ず。リコーダーの展示が多く、試し吹きしている人たち、みな上手です。裾野が広い楽器なんですね、ドイツでは。巨大リコーダーなどは、ファゴットよりでかいです。香港人の女の子に日本語で話しかけられました。古楽を勉強していて、わざわざオランダから来たそうです。わじさんのN社、7台のチェンバロを持ってきて、現地で一台売れたという。へぇ~メッセの即売で高額商品を買いにくる人っているんですね。(札束とお持ち帰り用毛布持参かと思いきや、N社社長は梱包のプチプチをあげたって・・・・・)初めて弾かせていただきましたが、いい音しますね~。マニアっぽいお兄ちゃんが、これいいぜ、と弟子二号にコメントを残していきました。しかし蒸し暑い、体育館。隣の建物でコンサートもありましたが、もはや室内で座る気力がありません。わじさんにアイスをご馳走になって、撤退準備の梱包を手伝う美女軍団←突っ込まないように。ビールが飲みたい熱気でしたので、家に帰ってからぶっどわいざーぱうらーなーを飲みました。今年のクリスマス用にCarissimi Sop+リコーダー2本+BC楽譜とスカルラッティ宗教音楽集CDウステフーデ Menbra Jesu Nostri CDを購入。クリスマスに歌ってくれる弟子が何人いるんだろう、と思って手を引っ込めた二重唱も・・・。
2009.05.26
コメント(0)
-
ドナドナ@アイルランド 市場からの逃走
市場に行く途中の雄牛がスーパーマーケットを混乱の渦に!http://www.spiegel.de/video/video-62737.html混乱して裏まで突進した牛、どうも通路がわかりにくかったらしく何もお買い上げせず。持ち主のオジサンが誘導して無事に出て行きました。店のオーナーのコメントうちには毎日新鮮な牛肉があるって、顧客の皆さんによくわかっていただきましたね。アイルランド流ジョーク?
2009.04.28
コメント(0)
-
広い欧州・狭い音楽界
音楽家と知り合うと必ず共通の知人が見つかります。ぜんぜん音楽と関係ない話題がきっかけで出会った新友・Yさん。オランダの某オケでヴァイオリンを弾いておられます。なんと三代目が日本で先生をやっていた時代初期の生徒にお友達が多数!Yさんに御紹介いただいた同じ州にお住まいのピアニストKさん。ベルリンで学生やってたころの宴会仲間T大トリオ@ピアノともお友達。この三人で夏休み、大阪で演奏会をすることになりました。生誕100年の貴志康一の生涯をたどるコンサート、語りつき。高槻市現代劇場レセプションルーム2009年 8月22日 土曜日午後2時から詳細が決まり次第、また御案内いたします。
2009.04.05
コメント(0)
-
フランクフルト演奏会の御案内
メンデルスゾーン 生誕200年コンサート 2009年3月7日(土)午後5時フランクフルト ハウゼン地区 プロテスタント教会Ev.Kirche Alt Hausen1, Frankfurt am MainJ.S. バッハ『マタイ受難曲』よりメンデルスゾーン『詩篇95』『アタリア』交響曲第2番『賛歌』より二重唱『エリア』より二重唱とアリアAve Maris StellaSalve Reginaオルガンソナタ第1番へ短調オルガンJee -myong KIMソプラノ安保恵美 犬塚千草 湯浅千秋入場無料修復されたオルガンのために御寄付をお願いいたします。地図は教会HPで御覧下さい。http://www.ffm-hausen-evangelisch.de/
2009.02.09
コメント(0)
-
就任の御挨拶
Frohes neues Jahr!新年おめでとうございます。この1月1日より、葡萄酒村 Markus 教会(Evangerisch)のオルガニストに就任いたしました。時々練習させていただいていたのですが、前任者が40年のDienstの後、引退することになり、なぜか私に声が掛かりました。今までヘッセン州で仕事をすることが多かったので、ついHessenのハレルヤを弾いてしまいそうになりますが、ここはBaden。当分ドキドキしながら弾くことになりそうです。私より上手に弾ける人は山ほどいらっしゃるんですが、歌いながら弾ける人は他にあまりいないようで、しいて言えば、それで目に留まったとしか思えないというか、他にとりえがないというか。独奏曲のレパートリー不足は生徒を歌わせることで解消しようという目論見。大晦日にはVivaldi、本日の正式な初仕事では、Vincent Luebeckのクリスマスカンタータ、でした。オルガンは1960年Weigle28 Register コンビネーション2Mechanischer Spieltraktur 塔の修復費用募金中なので、まずはチャリティーコンサートを企画しています。皆様、よろしくお願いします。牧師に、ここで弾かないかと声を掛けられたとき、常連代理をしていたHP村の教会を思って、3秒考えました。まあ即答みたいなものですが、ずぶの素人として代理を始めて暖かく失敗の数々を見守ってもらった精霊教会とお別れするのは寂しいものがありました。たまには弾きにいきたいからと鍵はまだ持たせてもらってます。(ここは15 Register Trompeteなし。でも木の鍵盤で手が冷えにくい!!)日曜の9時半から、夫と子供が寝てる間に(!!)仕事って、なんだか主婦の新聞配達みたいです。ギャラも主婦パート並だったりしますが、初めてLohnsteuerkarte 納税者カードなるものを手にしました。今までフリーの音楽家という、きわめて失業者に近い立場でありましたから、納税者カードとは縁が無かったのです。さぁ次はチェンバロ界に忍び込むために先生探しかなっ!?(A=440Hzでないと弾けないのに、どうする・・・・)
2009.01.01
コメント(2)
-
音楽ライターデビュー
10月20日発売、クラシックジャーナル034号『ミレッラ フレーニ単独インタビューイタリアオペラの名花、カラヤン、亡夫ギャウフロフパヴァロッティの思い出を語る』と題して、8月にオーストリーでインタビューした内容を書きました。本誌は録音ファンを主な対象にした、ディープな音楽雑誌です。ぶっちゃけていえば、オタクによるオタクのためのクラシック、でも明るいよ、という感じでしょうか。コンサートでよく会う仲間と雑談しているような楽しさです。とはいえ、この楽しさをわかってもらえるのは全人類の3%以下かもしれません。われこそ、その3%と思われる方は手にとってくださいませ。インタビューは英語にイタリア語を交えて行いました。全部イタリア語でできたら良かったんですけどね・・・・発行はアルファベータhttp://www.alphabeta-cj.co.jp/cla_j/クラおたには面白い本を刊行しています。仕事もらったからではなく、自分の興味にハマッタので買ってしまいました。
2008.09.29
コメント(0)
-
オペラの扉を開こう Tactus第2号発刊
トスカニーニ オペラ アソシエーションから発行されている情報誌 Tactus 第2号が出ました。 不肖三代目、フルネームのHNと本名で記事を書かせていただいております。 三代目名義では『フィガロの結婚』の伯爵夫人について『不幸な結婚生活が快活な娘を憂いの伯爵夫人に変えた』という『婦人公論』っぽいノリの仮想インタビューでお届けいたしております。 興味がおありの方は 東京銀座の山野楽器楽譜売場 カワイ表参道店 または直接こちらでお申し込みくださいませ。 http://www.toscanini-opera-association.com/
2008.07.19
コメント(0)
-
特殊作業車の祭典!?とカート体験
モータースポーツファンの皆様こんばんは。 かのミヒャエルシューマッハーも子供の頃から乗っていたというカート。 一度体験したいな~と相方と話しつつ気になる視線を向けていた、 隣村のインドアカートバーンはアウトバーンA5から見えるところにあります。 日曜にダブルヘッダーの礼拝でオルガンを弾いた帰り道、 へっぺんはいむの広場にTHW Techinisches Hilfswerkの特殊車両大展示会が開催されているのに気づき、 子供たちを連れて出直しました。 ガス爆発、洪水、あらゆる災害に対応した作業車と消防車各種という、子供の好きそうなものが満載です。 消防車は赤ですが、THWの車両は濃いブルー。 もちろん無料。 お腹がすいたらドイツのこの手の催しのお約束、ソーセージ、イモ、ビール、ケーキ、カフェが許せる値段で買えます。 その後、気になっていたカートバーンに寄ってみることになりました。 6歳120cm以上、年齢上限なし。 うちのもうすぐ6歳の双子は身長が5cmほど足りません。 子供向きの電気自動車だと器用に抜きまくる運動神経のいい方の子(女)にやらせてみたい相方タヌキ。 けっこう親ばか入っています。 じゃあ一度キミが試してみろ、というタヌキの一声で三代目がトライ。 約10分で10Euro(16歳以下は8)、 ヘルメットは貸してくれます。 公道じゃないから免許はなくてもいいし、ギアチェンジはないし、 お子様でも乗れるとはいえ、見ていると結構スピード出ています。 こういう展開になるとは思っていなかったのでサンダル履いてるし・・・。 乗っているのは10代の少年が中心。 子供にさせる前に自分で試してみる母親っていうのは、 あまりないパターンではないだろうか。 コースがどう曲がるかわからない一周目はビビります。 一度は壁に突っ込みました。 後退はできないので手を上げて救助を待つ。 でも突っ込んだのは最初だけ。 だんだん慣れてくるとアクセルを踏み込みますが、 オートマチックに慣れていないので 時々ガスとブレーキを同時に踏み込んでます。 (これが怖いから三代目はマニュアル派) 結論 当分うちの子たちには無理。 理由 けっこう力がいる。 Servo=パワーステアリングが付いていないのでハンドルが重いです。 公道でも気の強い運転をするけれど自分より速い人には さっさと道を譲る方針でおりますので、 直線コースの前で先に行ってもらいました。 タヌキによりますと、ベストの周ではトップから8秒遅れだったそうな。 何回も同じコースを回っていると集中力が切れるとミスをします。 F1で50周も回るとそりゃミスもするわ、と納得しました。 これはそんなに何回も走れるものじゃありません。 その後タヌキも挑戦。 KYなタヌキは後ろにぴたっと付いた速い人が いらいらしているのも平気で簡単には抜かせません。 三代目同様、10代の少年に負けてます。 負け惜しみ 「僕は彼らより体重が40Kgくらい重いからハンディがある。」 そう、レーサーはデブじゃだめなのよね・・・・・。 筋力がいるのもわかりました。 もう少しお子様向きなのを探します。本格的な子供用をシューミのカートセンターで見つけました。 http://www.ms-kartcenter.de/de/indoor/karts.php#KK でも140cmから。 うちのおサルちゃんは20cm以上足りません。 アイスの点数を集めたら入場料おまけ。 http://www.langnese.de/site/alias__de/lang__de/1127/default.aspx
2008.07.01
コメント(2)
-
お昼つき お城の遠足 びゅーでぃんげん 市長も公爵も太っ腹
フランクフルト郊外の小さな街 びゅーでぃんげんhttp://www.buedingen.net/inhalt/i_historie.cfm人口は葡萄酒村の半分程度の3万ちょい。観光的には日本人の間では無名にひとしい B?dingen、独日協会などとタイアップして観光キャンペーンの一環として日本人家族200名を御招待してくれました。現地集合お昼つきケーキ・カフェつき参加費無料。お知らせのメールに『決して怪しい話ではありません。』と強調してあったぐらいイイ話。子供むきプログラムもあるので一家全員と弟子一号、むすたあちゃん、ちぃちゃん、まとめて申し込みました。しばら~~く何の音沙汰も無かったので参加者リストに入っているのかキャンセル待ちなのかわからなかったのですが、無事に案内メールが届いて一安心。タヌキは3年間ガレージで眠っているバイクに乗るぞと息巻いておりましたが、雨女が遠足に行くときは当然雨が降ります。ホッとした三代目と後ろに乗せられそうになった、この中で一番軽そうな大人(さて誰でしょう)。A君とTwingoに分乗して出発。Twingoはアウトバーンの流れに乗るスピードに上がるまで(140km/h)時間がかかるので、1時間半を覚悟していましたが、渋滞も無く160km/hまで出せたので1時間で到着してしまいました。メールで指示してあった駐車場、ほとんど街を出たくらいの外れにあって不安になります。車もあまり止まっていない。でも中世の扮装をした人と名札を付けたオバちゃんという、いかにも観光局っぽい人がいます。どうやらほとんどの人は街の中の駐車場から城に向かった様子。(引き返そうと三代目も思った。)それにプール前の駐車場に止めたら城に案内しますというのは、ドイツ語の案内には書いてあったが日本語版には書いてなかったような。本格的な改修工事中の野外プールの横を通り、城への近道は素敵な散歩道です。城の中庭に入る門にはPrivatと書いた札があります。ここはイーゼンブルク公爵の居城なので、普段は観光客がふらふら入ってはいけないようです。一人くらい知っている人に会うだろうな~と思って誰に会うか楽しみにしていましたら、子供たちのクラスメートの他に、なんと私のカルマン君(1886年製グランドピアノ)の次の持ち主御一家に出会いました。小雨降る中庭で公爵のご挨拶。長いフルネームだという通訳さんからの御紹介だったのに、名乗ってくれなくて残念。『750年間先祖代々住み続けているお城にようこそ、私の曾祖父は最初の日本駐在ドイツ大使でした。』おお~っ、それで日本人観光客誘致に動いたのか!市参事(市長さんみたいなもの)、独日協会、FRA総領事・・・と続く連続ご挨拶攻撃。子供は2、大人は4つのグループに分かれて見学開始。これは素晴らしいアイディアです。子供は子供だけで行動できるのを楽しんでいましたし、大人は落ち着いて話が聞けます。お城の中世部分、礼拝堂、狩猟の部屋などを見せてもらいます。15世紀の当主ルートヴィッヒ2世(バイエルンにあらず)は趣味が建築、設計しただけでなく現場監督にも立って、足場から落ちて怪我して亡くなったといいますが、その時の年齢が90歳、当時としてだけでなく現代でも立派な御長寿です。礼拝堂は結婚式に借りられます。600Euroプラス花代と神父の謝礼。安くありませんが日本の結婚式場を思えば高くないかも。ただしオルガンはポジティフのみ、ペダルのない一段鍵盤です。もっとも豪華なオルガンを入れるには狭すぎるので、ちょうどいいのかもしれません。広い居間は公爵家が使うこともあるプライベート部分、熊の毛皮がしいてあったり、中国のでっかい花瓶がおいてあったりして、テーブルには妙な花瓶が置いてあります。ろうそく立てにも見える青磁風の花瓶、昔は高価だったチューリップの花が長持ちするように花びらを固定する仕組み。ケチとチューリップ栽培で有名なオランダ人ならではのアイディア商品。ちなみに公爵氏はドイツ自動車クラブの会長でもあるらしい。この季節にはひんやりして気持ちいいけれど、お城は石造りで寒い。こういう場所に冬住むのは冷え性の人には拷問に等しいかもしれない。外の暖かさは伝わらないし、暖房してもエネルギー効率最悪。我が家の石とガラス張りの階段だけですら冬は冷えひえ、恐ろしいガス代になるのに、これが建物全部なんて暖房不可能です。ベルリン時代に歌を教えた生徒(当時学生)に『夫の実家のケラーにピアノがあるからコンサートを。』と言われて訪ねて行き、そしたら彼女は実はお城の次男の若奥様で、大層びっくりした経験があります。ここは元修道院だったので中世のお城よりマシとはいえ、すごく寒かった。庶民のアパートのほうが城に住むより暖かくてイイよ、夏以外は・・・・・。お城見学の後は旧市街散策。壁に派手なカエルの人形が張り付いています。かのベルリーナーベーアのカエル版。カラフルに色が塗られていて、各国国旗に塗られたカエルも。街のシンボルは蛙。なぜかというと、昔外国からお嫁に来たお姫様、新婚の夜に変なゲロゲロ声が聞こえてきて、『変なカエルの声が聞こえるなんて嫌。明日もカエルが鳴いたら実家に帰ります。』と駄々をこねた。王子様は領民に頼んでカエルを袋に詰めて遠いところに捨てさせた。ところが『カエル』というだけあってカエルには帰巣本能がある。翌日には帰ってきて再びゲロゲロ。でもお姫様は王子様と領民が努力してくれたことに感謝して実家には帰りませんでした。というわけでカエル行列という行事もあるようです。http://www.buedingen-touristik.de/pdf/Froschparade%202008.pdfお昼御飯は街のレストランでビュッフェ。典型的ドイツ飯のSchnitzelとんかつゆで牛肉Kasselerカッセラー豚肉ひき肉とキャベツの煮込み血のソーセージ酢キャベツジャガイモ団子クリーム味のイモえんどう豆のピューレ白わさびソース飲み物は好きなものを頼めます。タヌキはずっとスペインで仕事していたし、家ではドイツ飯は作らないので懐かしのドイツ飯。ブランデンブルク州時代の社員食堂定番、別名『死んだおばあちゃん』こと、血のソーセージが皿に載っています。おいしいけど、みな塩気がきつい。真っ白な御飯がほしい・・・・・。御飯の後は市内観光の続き。ある石造りの家の壁にはイノシシの頭が飾ってある。鼻なんて禿げてる古そうなもの。この家は狩人が住んだ家で、あるとき狩の前日に奥さんが悪い夢を見た。お願いだから狩に行かないで、と泣くので仕方なく狩人の親方は家にいた。ところが皆が帰ってきて獲物を並べて点検している時につまづいて、イノシシの牙に突かれた傷がもとで亡くなってしまった。奥さんの悪夢は現実のものとなってしまった。そのイノシシが壁に飾ってあるのだそうな。・・・ちょっとそれ、趣味悪くありませんか・・・・・?城壁には中世のトラ箱もあります。酔っ払いとか軽微な罪を犯した人を2-3日ぶち込んでおく石牢で、トイレ用の穴が開いています。すごく狭いのに3-4人入れられたとか。冬はさぞ寒く、夏はさぞ臭かったことでしょう。Evangerischプロテスタントの教会も見学。魔女狩りの嵐が吹き荒れた時代、教会には住民が毎日お祈りに来ているか監視する係がいて、来ない人には魔女の疑いがかけられ、城壁にある塔に押し込められた。自白させるため拷問をかけられたが死んでしまってはいけないので医師がつきそって死なない程度に加減して、魔女裁判は大変時間がかかった。というのは魔女の生活費と裁判費用は親族が払わないといけないので、魔女関連産業の裁判官刑務所は長引かせて稼いだのだと・・・・払えないからさっさと火刑にしてくれ、と思った家族もあっただろうか?この市内観光案内はグループごとにお願いできるそうです。他のグループでは魔女裁判のお芝居付きだったそうで、各種のコースが選べます。http://www.buedingen-touristik.de/inhalt/i_stadtfuehrungen.cfm子供の宝探しコースなど、誕生会に利用すると親が楽をできて良いんじゃないでしょうか。子供たちは遊び場で自由に遊んで待っていました。この時点でお天気はすごく良くなっていて、子供達は喉がかわいたお水が欲しいという。こういう展開を予想していなかったので、水筒を車においてきてしまった。突然バスが迎えに来ました。えっ、こんなこと聞いてないよ。不思議に思いながら乗るとバスは街を出て森へ。森の散歩道の入り口で降ろされて、目的地がよくわからないまま歩く・・・・ひたすら歩く。鹿が飼われているのを見ながら奥へ奥へ。やっと着いた場所には中世衣装の一団が。中世の踊りを披露してくれました。一緒に踊りましょうとスカウトされる弟子一号。やる気まんまんの娘(5歳)は『いやなら踊らなくていいよ。』と声を掛けて、かわりに自分が踊りたそうな様子。背が足りないよ、残念だね。そのあと、彼女は完璧に振り付けを覚えて再現してくれました。バレエ少女の意地。そのあとケーキとカフェが用意されていました。同時に弓矢を体験できるので子供達は喉がかわいたにもかかわらず並んでいます。娘は最初に行ったにもかかわらず大きい男の子たちが別に列を作ってしまったので最後尾に。どうせ待つんだから先に水を飲んでから、といっても聞きません。ついにケーキは食べず最後まで弓矢にはまる双子。その結果、帰りのバスに待ってもらうために必死で歩き、弓矢を堪能してからおもむろに『おしっこ~』とトイレに駆け込んだ子供達をつれたタヌキの到着をヤキモキして待つことに。散歩教信者のドイツ人は、(こんなに素晴らしい散歩コースがあるから紹介しなくては)と思ったようですが、ほとんどの日本人は、これだけの距離を歩くのを楽しいとは思いません。特にバギー卒業したてのお子さんは疲れて眠ってしまって、抱っこして歩くお母さんは大変そうでした。駐車場までバスで送ってもらって解散。まだ何かあるのかと思って街まで戻った人もいて多少混乱しましたが、盛りだくさんで楽しい休日でした。おまけにガソリンが葡萄酒村より8セントも安かった。帰りの車では運転した人以外疲れて爆睡。この費用はすべて市の負担だったそうです。市長さん太っ腹。公爵も別の意味で太っ腹・・・。
2008.05.25
コメント(0)
-
マウスでチェロを弾こう@ベルリンフィル
爆笑ゲーム@ベルリンフィル公式サイトhttp://philharmoniker.web-feedback.de/indexde.aspマウスでサンサーンスの白鳥を弾きます。黒丸にうまくマウスの白丸を当てて弓を使うだけなんですが、へたくそだと弓がぎーぎー鳴ります。三代目の第一回スコアは2855点、その後、コンサートの切符が当たる懸賞に応募できるようになっています。User Nameを登録すれば自分の順位も見られます。つい二回目に挑戦、3652点。弓使いを暗譜したらもう少し伸びるかな。順位は9261位に。上位はチェロ弾きかゲーマーか。気になるなあ。若者に来てもらうよう一生懸命なBPO。それでも実際にホールにいるお客さんは平均年齢高いですね。三代目がベルリンで学生だったころに比べて切符も高くなったし、このままだとドイツ音楽文化は聴衆高齢化のため死に絶えるかも。教会に座っている人も平均年齢高いし、宗教音楽もやばいかも?
2008.05.21
コメント(0)
-
へぼ黒子 鼻から牛乳 右往左往
タイトル575になったのは、最近双子が日本語補習校で俳句の暗唱の宿題を貰ってくるから影響されて・・・。花輪君オルガンコンサート@宝石研磨の街 い~だ~お~ば~しゅたいんワインの産地、モーゼル川より南、メノウが産出されることから宝石研磨が発達した山間の小さな街。石が乏しくなったころブラジルに移民した人たちが偶然鉱山を発見したことから、輸入した原石を研磨することで寂れかけた街が復活したのが140年前・・・・ここで研磨された石があなたの指を飾っているかもしれません。Idar ー Obersteinそれほど遠くないので一度行ってみたかった宝石の街。ベルリンで雑談中、こんど弾きに行くと花輪君が教えてくれたので、アシスタント(黒子)に立候補、しかも練習した曲が3曲もプログラムに入っています。ラッキー。どんな音色を選ぶか勉強させてもらおうと思いました。三代目は山奥の教会で10時にカトリックとプロテスタント合同のPfingsten礼拝で、BuxtehudeのC Dur プレリュードだけを最初に弾き、最後は弟子1号にSchubertを歌わせ仕事終了。メゾからソプラノに変えて二年近く。テクニックが安定してから人前に出すようにしています。誰にも快く聴こえる声に整ってきました。牧師や会衆に喜んでもらえたようです。弟子を駅で降ろしてから空港へ、ベルリンから到着した花輪君をピックアップ。マインツ経由でIdar Obersteinへ。自分が弾かないせいか、今日は素晴らしい天気です。もっともこの時期のオルガンコンサートの大敵は良すぎる天気だったりします。音楽を聴きに行くよりグリルパーティーに走る人が多いですから、雨女の三代目が降らせた方がいいくらいかも。今日はBuxtehude(愛称・福助ふーで)とBach(バッハとは小さい川なり)の比較というテーマ。福助さんのC Dur BuxWV137のあとに小川さんのC Dur BWV564。福助さんのコラール Nun bitten wir den heiligen Geist。福助さんのD Dur BuxWV139のあとに小川さんのD Dur BWV532。福助さんのコラール Komm、Heiligen Geist, Herr Gott小川さんの「ちゃらり~鼻から牛乳」ことToccta Und Fuga BWV565BuxWV 137と139、BWV565は練習したので、どこでレギスターを変えたいかわかるので黒子としては平常心で臨めました。弾いている本人は間違ったら黒子にばれるから嫌かも・・・・!?オルガンはベルリンZehlendorfのSchukeのもの。教会の建物自体は典型的な60年代コンクリート建築で、へっぺんはいむのプロテスタント教会とステンドグラスのデザインといい電気シェードといい、どれもこれもソックリ。モダンチェンバロが置いてあることまで同じです。さすがにメーカーは違いましたが、同じような色で同じようなペダルがついています。こちらのはNeupert製でした。Registerはよくあるパターンで引っ張る方式のが左側にペダル、Brustwerkの二列、右側にHauptwerk一列。いろいろなオルガンで演奏している花輪君の楽譜には様々な色の丸いシールが張ってあって番号が書き込まれています。今日は1曲目と2曲目が青いシール、次は緑のシール、それから黄色・・・・と言われて混乱する三代目。使っていない鍵盤の場合は引っ張ったり戻すのに余裕がありますが、特定の音の前後で出し入れするのが緊張します。両側にすることがある場合は本人に余裕があれば分担、そうでなければ右往左往・・・・。弾きながら足元のカプラー(Kopplungって車のクラッチと同じ単語なので、マニュアル車を運転できる運動神経があればオルガンを弾ける、と思い・・・ません?)を出し入れするのが大変な時には、足も使ってお手伝い。一年前に比べると自分が弾くのに慣れたので、黒子をするにも少し余裕が。本番前に地元白ワインの炭酸割りWeissweinschorleを飲んでリラックス。しっかり冷えていて美味しかったです。ちなみに演奏する本人は飲んでません。黒子だけ。Registrierungの後、怖いもの知らずにも花輪君と同じ曲を弾いてアドバイスを求めた三代目。自分の師匠と違う考えを聞いてみたかったのです。三代目の場合、速く弾くと破綻する危険があるという事情もありますが、ゆっくりめにフレーズを丁寧にという方針でやっております。花輪君は・・・・ムチャ速い。ガソリン高騰の折、高いドライブをしてしまいましたが、行って良かった。宝石博物館の前の炭火グリルレストランで昼飯を御馳走になりましたが、ここのステーキは美味しかったですよ。祝日でもお土産屋さんは開いていました。ただし高級な石は歩行者ゾーンでなく、山の中の工房にあるようです。花輪君は日帰りできないのでお泊り。三代目は行きに空港経由で2時間かかったのに、帰りは150kmの距離を80分で家に帰れました。知らない場所は日没前に通りたいので演奏会の後すぐに失礼してきました。この季節、日が長いので快適でした。9時半までは明るいので、日没前に家に着きました。
2008.05.12
コメント(0)
-
ひさしぶり 夫婦ででえと DSO
昨夜(5月20日)ボヤ騒ぎがあったベルリンフィルハーモニー。ニュースによると通行人が携帯から『黄色い建物から煙が出ている』と通報したらしい。観光客だな、通報者。ベルリーナーが『カラヤンのサーカス小屋』(この別名もう古いかも)を知らぬ訳はない・・・と思うが若者だったらどうかな~。話は先月末に戻りますが、ベルリン滞在中タヌキの希望でコンサートに行きました。三代目は国立オペラのDon Giovanniがよかったんですが、タヌキはオケの方がいいと主張。(たぶんオペラはオケより長いからにちがいない・・・。)「久しぶりに文化~。」とタヌキ。そういえば三代目は一人で・弟子と一緒になどチョコチョコ行ってたけど、相方と一緒に行くのは久しぶりです。(言われないと気がつかない・・・・たらーっ)タヌキがネットで探し出したのはDSOドイツシンフォニーオーケストラ。残念ながらお友達は今回里帰り中でのってません。会場は御馴染みフィルハーモニー。ネット予約の際に「A、B?」と聞くタヌキ、多くの一般のお客さん同様高いのが良い席だと思っています。しかし三代目的に面白いのはEやF、指揮者の顔が良いときはG、Hです。バランスは真横や後ろは良くないですが、オケの中で起こっていることを一緒に体験できる感じがします。(事故や内輪受けを含む。)最前列だったらGeige隊(がいげとはびよろんのことなり)の後ろのプルトの楽譜が読めます。ちなみにブロックAの前方だと頭の上を音が通り越す感じがするのでBの方が好き。しかし世の中にはAにしか座れない人がいます。それは物理的な理由。でぶ。Aのシートは他より広めなのです。あのヘルムート コール元首相でも座れるゆったりサイズ。EはAよりだいぶ安いこともあってブロックE 左を購入。左と言うのはベートーベンのピアノ協奏曲5番『皇帝』がプログラムのメインであったから鍵盤が見えやすい方にしたかったのです。ヴォーン・ウィリアムスが前半。スコットランド風?もしくは中世っぽい音楽なんだけれど、日本の時代劇の劇伴に使えそうな雰囲気。おお~ここは大奥っぽい、と妙な受け方をしてしまう三代目。いい曲ですがコンサートの前半にしたのは納得。『皇帝』の後だと盛り下がってしまいます。休憩後いよいよピアノ協奏曲。おおっ、この配置は!えっとぉ~今日は弾き振りじゃなかったよな・・・・と当惑。Steinwayのフルコンの屋根(ドイツ風に言うと羽)をはずして演奏者がAブロックにオシリを向けフルート奏者と目が合う配置は、いままでダニエル君(ばーれんぼいむ)が弾き振りした時以来です。よく見るとピアノの先端部分の左側に指揮者用の譜面台が取り付けてあります。指揮者の海苔豚卿(Sirのりんとん)とソリスト・えまにゅえる斧(あっくす)登場。えっ・・・・15年ほど前に誰かのリサイタルの伴奏者としてアックス氏を見て以来ずいぶん経ったとはいえ、髪は白く身体はコロコロになり、名前の斧のようなシャープな演奏と言う当時の評論家の表現とはイメージが全然違うお姿。いかにも人のよさそうなオッちゃん風。オケのTuttiでノリノリのオッちゃん。全身で楽しんでますね。ぜったい指揮者と仲が良くて信頼しあっているに違いありません。でないと、こういうピアノの配置を指揮者が許さないと思うな。体格がいいので音は自然に豊かに鳴る、むしろ繊細なPPに細やかな神経を使っているのが凄いソリスト。この曲は日本で何十回も聴かされましたが(自発的に聴きに行ったわけではないのも多く・・・第9の前プロというとんでもないのもあった。)印象に残る演奏はあまりなし。しかし、アックス&DSOはナマで聴いた中でのベストです。とかく協奏曲というと『競争』になりがち、もしくはソリストに余裕がなくてオケを聴いてないのが特に日本で若いお嬢ちゃんが弾くとありがちなパターンですが、アックスのソロは室内楽的。オケと対等というよりはオケの一員。一流の伴奏者ならではの協奏曲、感動的です。人寄せパンダの見かけのいいお嬢ちゃんお兄ちゃんピアニストに苦々しい思いを持っている方なら、この感動をわかっていただけると思います。聴衆も大いに盛り上がり、何度も舞台に呼び戻されたアックス氏、オケの皆さんの見守る中でアンコール曲を演奏。知らない曲でしたが、しっとりとした素敵な演奏でした。
2008.05.03
コメント(0)
-
大阪のオケを救え!
わが故郷大阪、今度も困った知事を選んでしまったようです。知事公邸を取り壊すと発言したとか。今度はオケを壊すつもりのようです。誕生した時には大阪府音楽団を壊してオケができてしまったので、??!!と思わないではありませんでしたが、赤ちゃんが大人になるくらいの年月をかけて育てた後で破壊するのは問題外。同業から回ってきたメール、緊急事態でもあるので貼り付けます。最後の楽団員の署名のみ削除してあります。ご協力いただける方、どうぞご回覧ください。三代目敬白********************************************************こんにちは、突然のメールで申し訳ありません。切実な緊急なお願いがあります。橋下府知事就任に伴い、私が契約しています大阪センチュリー交響楽団の母体である文化振興財団がワッハ上方も含め、存続危機にあります。大阪府からの補助金を廃止する案が出ていますが、廃止されてしまっては、府民を越え皆様に楽しい素敵な音楽お届けする事は難しく、センチュリーの存続さえは難しくなります。その為、補助金の継続を求める署名をお願いしたいのです。署名用紙のダウンロードアドレスです。(パソコンから見て下さい。)http://osaka-century.sakura.ne.jp/署名要望書をダウンロードし、署名し下記に4/17までに、郵送又は、FAXお願いできないでしょうか。一人でも多くの方々の署名を集めたいです。お手数ですが、よろしくお願いします。〒530-0003大阪市北区堂島2-1-5 サントリーアネックス1201 河内厚郎事務所内 大阪センチュリー交響楽団を応援する会FAX 06(6345)8272 http://www.osaka-century.sakura.ne.jp/
2008.04.16
コメント(2)
-
二台のピアノのためのソナタ
O君(スタインウェイ180cm)が部屋に入って2ヶ月以上が経過、調律に来てもらいました。いつもオルガンを練習している教会のすぐ傍に工房を持っているマイスター。自分の工房にあるSteinwayより良いと言ってくれて、まずは安心。しかし。前の持ち主がやり直したという塗装がいまいち下手らしい。ペダルも素人くさい修理の跡あり。すっきりしたところで、ピアニストのお友達に遊びに来てもらって連弾大会。前のピアノ・かるまん君もあるのでモーツァルトの二台のピアノのためのソナタに挑戦。のだめと千秋先輩が弾いた、モーツアルトがピアノのうまいブスのために作曲したアレです。ベルリンで学生してた時、副科ピアノで練習して以来です。いちおう練習していた三代目と初見だった友達とレベル同じです~。のだめが二人状態でした。でも楽しかった~。かるまん君が出て行くまでのお楽しみ。ペダルを修理に持っていこうとした矢先、譜面台を折りました。ああ、痛い、財布が。
2008.02.28
コメント(0)
-
レオンスカヤ・ピアノリサイタル
灰出山(はいでるべるく)の南にはLoch穴がつく地名があります。 Wieslochの他にもNussloch(胡桃の穴)という村があります。 Tigerlochがあれば面白いのにな、でもドイツにはトラいないし虎の穴はないか。 その穴場?ヴィースロッホへピアノを聴きに行きました。 Elisabeth Leonskaja レオンスカヤ女史はGeorgien生まれ、御歳62歳。 ゲオルギエンは日本語ではグルジアだと昨夜初めて知りました。 このコンサートを発見してくれた、こもさと氏ありがと。 演奏会は公会堂、地下駐車場は良心的なお値段でした。 そしてチケットは世界的クラスの演奏家にしては特価の20Euro。 定期会員でホールは一杯、一般売りのチケットは20枚しか出なかったそうです。 来られなかった定期会員の席へ開演直前ほふく前進。 前半はBeethovenのソナタ30番と31番。 俗名「ベートーベンの電話帳」ヘンレ版ソナタ集第二巻を持参して広げると、のしのしと歩いてレオンおばちゃん登場。 ぢつは三代目、ピアノ曲はなんちゃらの何番と番号がついているのが苦手です。 番号が覚えられない・・・ 聴いたら知ってる曲だったりするのに、何番の何調、と言われてもピンとこないんです。 30番E Dur。 あっ、知ってる。 「そこ、どこ、ここ、どこ・・・・中略・・・いや、だめ。」 ↑冒頭のメロディー、某在京オケ主席びおら奏者さんが学生時代たいへん上手にエロティックにお歌いになったという・・。 31番As Dur。 これは知らなかった。 ちょっと冒頭部分がFigaroの伯爵夫人のアリアPorgi amorに似てるなあ。 曲を良く知らないから譜面を見て良かったです。 ベートーベンというと厳格なイメージがありますが、実は弾き手が自由に出来る部分が結構あるって気が付きました。 そういうところが難しい。 ルートヴィッヒ君の父ちゃんはテノール歌手であったということを思い出させてくれるカデンツァ。 (そのわりに歌曲はイマイチだけど・・・) 技術的には高校生にも弾けちゃうけど、この年齢になって到達する深さというものを感じました。 ソナタというより幻想曲のようだ。 休憩後 Schubertの即興曲2つ あ~~これ高校時代に練習したわ~。 自分には結構辛い時代だったのを思い出してしまった・・・。 Chopinのスケルツォ2つ、間にノクターンを挟みます。 あの有名な 「え~ところてん、ところてん。 ニッポーン、文化国家!! ところてん、ところてん。」 というScherzoです。 三代目が(おお~)と思ったのと同時に 隣のこもさと氏の肩が揺れたような。 有名曲が来ると聴衆の方も揺れているような。 ちなみに聴衆、平均年齢高いです。 我々より若い人、ほとんど見ませんでした。 学生は田舎のコンサートに来るための車を持っていないか、 マンハイムのカツァリスに行ったか。 こういう曲は、昔はもっと弾けたのでしょう。 切れそうになるとハラハラしましたが、内面的な部分と盛り上がる時の落差の大きさが魅力的です。 若いピアニストに指がもっと回る人は一杯いるでしょう。 でも指が回るだけで聴いていて何も残らない人が多いのも事実です。 だからピアノリサイタルは滅多に行かなくなったのですが、これは本当に行って良かった、そしてまた聴きたいピアニストです。 アンコールは超有名Chopinのノクターン作品15の1。 (番号合ってる・・よね。) そういえばベルリン時代の弟子ギゼラ、ウィーン在住の友達がレオンスカヤの追っかけやってると言ってました。 確かに追っかけたくなるピアニストかも。 終演後楽屋に行ってBeethovenソナタ第二巻にサインを貰いました。 三代目「和音の色の変化が素晴らしかった。」 レオンおばちゃん「そうできたらと望んでいます。」 三代目「ベートーベンは自由にできる部分を与えていると気付きました。そしてあなたは、その自由を使いこなしていました。」 おばちゃん「彼の書いた事に従えばね。」 サッパリした気性で控えめな方のようです。 のしのし歩きの通りで。 ??なのは会場のピアノ。 Steinway フルコン。 古そうです。 最後の方では調律が狂っていたような気がするし、 時々PPで スカ・・・・・・っと 鳴らない音があったのはピアノのせいではあるまいか。
2008.02.12
コメント(1)
-
効果ないんじゃないかな
楽天がスパム防止に禁止ワードを導入したそうですが、変なカキコミが無くなるとは思えません。ここに気軽に書きこんでくださったお友達もろとも雑談所を引越しして以来、ここは倉庫同然になっておりますが、たまにカキコミ制限を外すと掃除が大変で・・・・。アフィリエイトなる余分なものがあるのも、うっとうしい理由のひとつです。しばらく様子を見たいと思います。本気で対策をしないなら、ここは閉めるかもしれません。
2007.11.02
コメント(0)
-
ピアノ売ります
1997年に購入したGruenderzeitのグランドピアノ、Goers und Kallmann 160cm、推定1890年製造、とお別れする時がきました。ベルリン芸大で個人売りの張り紙を見て電話を掛けたら知り合いのダンナさんだった。一回見て、二回目には調律のアンドレアスに一緒に来てもらって決めたピアノ。塗装をアンドレアスに直してもらって綺麗にしてもらいました。予定より早く次の楽器を買ってしまったので、お嫁に出さねばなりません。いや、Der Fluegelだからお婿に行くのか。(笑)良い人に買ってもらえるかドキドキ・・・・。
2007.10.23
コメント(1)
-
オルガンだけだと晴れる@結婚式
ブリュッセルの曇天の後では、とーっても有難く感じるドイツのトスカーナの太陽。本日は素晴らしい天気で、朝食はテラスででした。前日の金曜日、夏休み明け一回目のオルガンレッスンでした。木曜の夜には師匠のコンサートがあり、Ein feste Berg ist unser Gottというコラールに付けられた作品というテーマで福助ふーで、もといBuxtehudeJ.S.BachZolt?n G?rdonyiMax Regerの作品を演奏してくれました。Zolt?n G?rdonyiはハンガリーの人で20世紀の作曲家。古代君の弟子。面白い和音を使うなあ、と感心。RegerはメロディーがD DurとB Durを行ったり来たりするのが面白い!Zolt?n G?rdonyiの息子Zsolt(1946生)のGrand Choeur傑作です!最初はガマ蛙を押し込めるみたいな奇天烈な和音で印象的に始まり、後半はノリノリのメロディーを反復。アンコールは同じコラールのジャズ風アレンジで、これにはお客さんもノリノリでした。レッスンの始めに昨夜の感想。三代目が気に入ったハンガリーの父子、いい曲なのにあまり知られていないそうです。オルガニストの皆さん、いかがですか~?例のトッカータとブクステフーデのD Durのプレリュード。前日に見てもらえて良かったです。ちなみに師匠にも土曜に結婚式で弾く予定が入っていたのに、ドタキャンだったそうです。「すごく若い人だったから、多分考え直したんだと思う。」うちはドタキャンはないでしょう、結婚式のついでに第1子の洗礼もするみたいだから。「それも最近のトレンドだねえ。」さて、素晴らしく晴れた結婚式。今まで三代目が結婚式で弾いた時は、泣き出しそうな天気が多く、内心ごめ~ん、と思うことが多かったのに雨女ジンクスを振り払う快晴。気温も上がり、女性はけっこう薄着です。鐘が鳴り止んで、それいくぞ。プレーノ全開、よ~そろ~。(宇宙戦艦ヤマト発進!!)ちゃらり~~鼻から牛乳~J.S.Bach Toccata D Moll2小節目で洗礼を受ける赤ちゃんが泣き始めました。激しく落ち着かない雰囲気の中、とにかく弾き切りましたけど、赤ん坊には激しく向かない曲ではありませんか。本当にバッハのトッカータで良かったんかい?赤ちゃんが落ち着くまで時間がかかり、即興の多い牧師でぃるく、段取りを間違えないかドキドキ。HP(ほーむぺーじの略でなくヘッペンハイムの車のナンバー)精霊教会のオルガンには鏡が付いていないので祭壇が見えにくく、自分で鏡を張ってやろうかと切実に思う。賛美歌は歌謡曲みたいなノリの20世紀の曲が2つあった(結婚式は本人のリクエストによりポピュラーな賛美歌が多い)ので楽勝。赤ちゃん、トッカータで泣いて気が済んだのか、洗礼の水をかけられても泣きません。Mendelssohnで締めくくり。(ここの楽器にはトランペットが付いていないので残念。)花嫁&ママに「おめでとう。あのトッカータで本当に良かったんですか?」と確認。洗礼も兼ねているので、いかにも結婚式という曲で始めたくなかったんですって。晴れていたから良かったけど、この曲で外は雨だったら果てしもなく暗かったかも。今日は歌わなくてオルガンを弾いただけだったから降らなかったのかな。
2007.09.24
コメント(0)
-
ブリュッセル4・雨女記録演奏会
ブリュッセルの観光名所グランプラスから徒歩数分の教会で練習。教会に足を踏み入れるとカトリックの匂い。(お香のかおり)ここのオルガンは王様の「修理の費用出したげて。」の一声で銀行が援助してくれて2000年に修復が完成したというロマンティックオルガン。以前に電気式に変えられていたのを建造当時に戻したというのです。そういえば、この規模で機械式のオルガンって初めて見たような気がします。ユリママさんが演奏するとカタカタという音がします。カプラーや足元で操作するレバーは、ちょっと熟練が必要な感じ。ちょこっとレーガーを弾かせていただきましたが、ペダルの感覚が楽器毎に違うので慣れないと下手なのが更に悲惨になります。ポジティフの後ろから顔を出すように立って練習開始。下でバランスを聴いてくれる人が最初はいなかったので、声がオルガンに覆われていないかと気になります。後でユリパパさんに聴いてもらって調整、やはり楽器の側で聴くのと下で聴くのとは違うようです。自分で音を減らして伴奏しつつ練習していたのとは違い、やはり二人で演奏するってイイ感じ。微妙なテンポや強弱を調整します。作曲家には楽譜にびっちり書き込むタイプの人(プッチーニやRシュトラス、山田耕筰など)と、演奏家が知っているべきことはわざわざ書かないよ(シューマン)という人がいます。メンデルスゾーンはAve Maris StellaとSalve Reginaの中でテンポが変わる部分への移行部分について指示をしていません。そこをどう扱うかについて話し合った時、ユリママさんと三代目の辿ってきた道のりの違いを感じました。ユリママさんのおっしゃった古典舞曲のテンポの変化、恥ずかしながら三代目には解りませんでした・・・。多分オルガニストのよく知っている曲の90%を知りません・・・おほほほほ。三代目は「4小節のうち2小節はまだ興奮していて2小節で鎮めて次に入る。」とオケやオペラでの扱いのようにと考えたのでした。同じことを言うにも受けてきた教育の違いで例えが全然違ってくるものです。そういうことがあるから合わせって面白い!教会の響きは長すぎず音が鮮明に伝わる感じです。お付き合いしてくれたユリちゃん、譜めくりもしてくれました。いいな~我が子の譜めくりなんて。充実した合わせの後、近所に途上駐車したTwingoに戻るとBach Toccataニ短調、さあ皆さん御一緒にちゃらり~鼻から牛乳鍵穴をこじ開けてダッシュボードに入れてあった新品ナビ子が連れ去られていました。固定するためのアームがあったからナビがあると見破られたんだろうな。しまった。とりあえず戻ってから警察へ。ユリママさんが付き添ってくれたお陰でスムーズに届出。翌日はユリパパさんがルノーに一緒に行ってくれて修理も完了。こういうことを一人でできた自信はありません。私のフランス語は公文式で現在完了形まで独習したのみ。言っていることはある程度理解できても、音楽など興味のあることについてはある程度読めても、話すのは買い物がどうにかできる程度です。とっさにイタリア語になることも多々。それにしてもドイツのナンバーを付けた車からナビを盗っても、ソフトがドイツ語だからフランス語圏で売れないと思わなかったんだろうか、泥棒。それとも外国車を狙ったのか。Twingoの前後にもっと高級そうな車があったのに。それともTwingoが特別簡単に開けられるのか。損害額はナビ本体より修理費用の方が上。賢い泥棒だったらこんなの盗らないぞ、と思うので犯人は子供かな。どういう生活しているんだろう。お金持ちも多い物価の高そうなブリュッセルで貧富の差が激しいのかな。トラブルですっかり遅くなって戻るとユリパパさんが手巻き寿司の用意をして待っていてくれました。すばらしい、うちのタヌキなんて何も出来ないのに。感謝感謝。翌日は車を修理に出した後、歩いて教会へ。曇り空が普通のブリュッセルではまあまあだという天気。ラインベルガー、メンデルスゾーン、合間にオルガン曲でこの二人の作曲家以外にバッハも参戦。最後の曲のシューベルトのOffertoriumはユリパパさんも連弾で参加、豪華なトリオとなりました。下に降りてお客様に御挨拶。教会のドアの外を見ると雨信じられない。また三代目が歌うと降りました。Twingoで旅行に出た前回のドルトムントでも雨が降ったし現地のルノーに修理を頼む事態になったっけ。ああ、もうTwingoで演奏旅行には行かない方がいいかも。雨の少ない地方の皆さん、どうか記録を止めるために三代目を演奏会に呼んで下さい。しかしドバイの雨を経験した三代目のことですから嵐を呼ぶことになるかもしれません。
2007.09.18
コメント(0)
-
ブリュッセル3・蚤の市
がらくた市愛好家の三代目、ブリュッセルでも蚤の市に行けたらなと狙っておりました。するとユリママさんが子供用自転車をお友達の出店するガラクタ市で売る為に持っていくという耳寄りなお話。一緒に連れて行ってもらいました。そこの住民が家の前に不用品を並べて売るという、不用品処分市。ガレージなしのガレージセールみたいな感じです。ユリママさんはカールおじさんのリンゴ他をお友達の陣中見舞いにおすそわけ。丁度お腹が空いていたらしいお友達、リンゴや骨せんべいをバリバリ。干物をバリバリ美味しそうに食べる欧州人って珍しいかも、かなりの日本食通とみました。そこに埃まみれで置いてあった椅子、三代目の1880年代ピアノと同じ脚のデザインです。居間にある家具も全部このスタイル・グリュンダーツァイトなのに食卓の椅子は戦後の平凡なモノなので、時代を揃えたいと最近椅子を2個拾って自分で修復しようと思っていたところ。布を上から張れば充分使えそうです。値段を聞いたら「友達からはお金は貰わない、持っていって」とのこと。初対面なのに。友達の友達は皆友達だ。なんて優しい・・・。後で受け取りに行った時にプファルツの醸造所で買った白ワインを一本持って行ってお礼に渡しました。わらしべ長者?翌日は地元の蚤の市で椅子に張るのに丁度いいゴブラン布を見つけました。スペイン製だけど、どうもカーテンとして使われていたらしく2枚あるうちの片方にペンキのしみが。1枚20なので両方で30にして、とアフリカ系のマダムに交渉。閉店間際のせいか、あっさり商談成立。ここには大女優・香取犬Deぬーぶ(すごい字だわ)もお忍びで現れるそうです。お忍びなのにバレルほどお美しいとか。見たかったわ。ガイド役をしてくれたユリちゃん、古着やアクセサリーを熱心にチェック。なんと安い服や帽子を改造してしまうのだそうです。画家のブリューゲルにちなんだブリューゲル祭りが開催されていて、賑やかな行列が通ります。張りぼての人形とブラバンには各国のチームがあるらしく、スペイン隊はドンキホーテの張りぼて。フランス隊はオーベリックス。(漫画)スコットランド隊はバグパイプ行列。三代目は演奏しに行ったんじゃなかったっけ、と思った皆さん。練習はこの後やりました。(笑)
2007.09.18
コメント(0)
-
ブリュッセル2・ショコラ
ベルギーといえばチョコレート。ユリママさん一家がブリュッセルで一番とお勧めのマルコリーニでオレンジピールのチョコがけとパンに塗るチョコクリームを買いました。このお店、日本でも出店しているそうです。黒のパッケージが御洒落でお値段もノーブル。マカロンも気になりましたが、パステル調の色をどうやって着けているのかが気になって購入せず。私の前にいたイタリア人のオヤジと奥さんは、「これ2つずつ、あっ、これも。そうそうコレもいいねー。」ってな調子でバンバン総額300Euro以上お買い上げ。ロータリーに路肩駐車する度胸といい、マフィアさんでしょうか・・・?チョコレートのお土産を約束した子供たちの為にはマルコリーニは大人向けすぎるので、近所のスーパーでも物色。ユリちゃん御推薦のクマちゃんワッフル(ゴーフル)、ユリママさん推薦のオーブンで焼いてトロっとしたところが美味しいというチョコスフレとチョコチーズケーキ。実は今これを書きながらチョコチーズケーキを食べていますが、チョコスポンジの台、チーズケーキ、ミルクチョコガナッシュの三層が濃厚な味わいの三和音を奏でる優れものであります。バー型プラリネはユリパパさんからのおみやげ。レモンピールチョコがけは健康的なファストフード店でユリママさんが買ってくださいました。ユリパパさん、「明日のチョコ買ってきた。」。えっ・・・・明日の朝?なんとユリファミリーの朝食には板チョコがつくのです。東ドイツのオルガンコンクールで出会ったお二人、朝食の席で彼がポケットから何かゴソゴソ出して口に入れているのを不思議に思ったら、なんとチョコレートでびっくりしたそうです。普段と同じように食べないとコンクールで調子が出ないと、チョコレートを持ち込んだ若き日のユリパパ。可愛いですね~。
2007.09.16
コメント(0)
-
ブリュッセル1・迷走
街乗り車Twingoで演奏旅行は二度目。昨年の夏、花輪君とTp.のTweetyちゃんと一緒にバッハのBWV51ほかを演奏した時にはアウトバーン上でマフラーを落とし、ちびっこ暴走族のごとく疾走したので、今回は万全を来してボンネットを開けて点検。冷却液が少なくなっていたので、あやうく水を入れそうになりました。(おいおい)タヌキに確認してルノーで補充、エンジンオイルも足してもらって、これで現地のルノーを探す羽目にはならないだろう、と張り切って出発・・・・のはずがコートを忘れたのに気づき家に帰る。後で実感しましたが、取りに帰って良かった・・・・。ベルギーはドイツのトスカーナより寒いです。タヌキが買ってくれたナビ、A君のビルトインは地図が出ないタイプなのに比べると見やすいけど、うるさい・・・。制限速度を10km超すとAchtungカーブがあるとAchtungもっともA君で遠出の時に工事区間で30kmオーバーを今年既に2回しているので免許証のために自重せねばなりませぬ。プファルツからナーエと、ワイン生産地を抜ける道は風景が綺麗です。コブレンツ方面にさしかかると、1992年8月に一ヶ月ゲーテインスティトゥートに行った思い出の街Boppardが・・・。坂道を転げそうな急な斜面、暑い夏、ワイン。懐かしい思い出の街がこんなに近いなら、来年は子供たちを連れて行ってみようかな。ケルン方面に入るとF1ファンには御馴染みのニュルブルクリンクシューミ兄弟の出身地ケルペンフレンツェンの出身地メンヒェングラートバッハを通り過ぎます。ぼうっとしてきたのでアーヘンでトイレ休憩、ユリママさんに「あと1時間くらいかな」と強気な計算をしてSMSを送ったら、「1時間半はかかります。」というお返事が。あっはっは、ついA君テンポで考えてしまいましたが今日はTwingo、元Twingo乗りのユリママさんが正しかった。一瞬オランダを通過、急に標識の文字が意味不明になる。ベルギー入国、でも依然としてオランダ語の標識。オランダ語圏に囲まれたフランス語圏の首都って、東ドイツに囲まれた西ベルリンを彷彿とさせます。ブリュッセル市内に入るまでは順調、1時間10分くらいでしたが、ここからが問題。目標地点は右なのに左に曲がれというナビ。一方通行のせいなのか、と従って走りましたが、ブリュッセル市民の運転マナーは故郷大阪の「強引ぐマイウェイ」に近いものがあります。それでなくても市電の走る道は怖い。ここは銀座かというブランド店も並ぶ通りの土曜午後の混雑も重なり、ナビの指示を三代目が誤解したり、ついに車を止めて地図を確認。シンプルに行けるはずだったのに、迷走。ようやく辿り着いたのに、道の細さにビビって曲がり損ねて再び街区を一周。車を止めてベルを押すと扉を開けてくれたのはユリちゃん。はじめまして~。でも初めて会ったような気がしません。荷物を運び込むうちにユリママさんがお買い物から帰ってこられました。国生さゆりを優しげにしたような(国生さゆりさん、失礼!)可愛い人です。ブログで見たことのある猫ちゃん、テラス・・・・。旦那さんはドイツ語ができます。ユリちゃんは日本語よりフランス語の方が得意のようですが、日本語も大したもの。お陰で三代目の体当たりフランス語でも不自由なく過ごすことができました。お土産は、受けそうなものを調査済み。「いわしの骨せんべい」カールおじさんのリンゴ畑(写真)からもぎたての省農薬りんごりんごおじさんが手入れに来ないので、虫食いのあるリンゴ。宴会セット(さきイカ類、せんべい)ドイツビールワインのどぶろくしかし真面目な我々は?!結局宴会はしなかったのであります。つづく
2007.09.16
コメント(0)
-
ユリママデュオ@ブリュッセル
ネットでお友達になっていただいたユリママさんと初デュオの演奏会があります。ベルギー・ブリュッセルの聖フィニスティール教会。HPでオルガンの偉容が見られます。ロマンティックオルガンということなので、ロマン派プログラム。ドイツの作曲家ラインベルガーメンデルスゾーンと御馴染みウィーン少年合唱団OB?!シューベルト入場は無料。詳細はこちらでどうぞ。http://plaza.rakuten.co.jp/villamusica69469/2001今回の裏のお楽しみはドイツ対ベルギー、ビール対決。愛車にビールと地元ワインを積んで参上いたします。
2007.08.13
コメント(0)
-
唱歌『蝶々』国際伝言ゲーム
文部省唱歌『蝶々』、そみみ~ふぁれれ~どれみふぁそそそ~。大抵の楽譜には『スペイン民謡』と書かれています。ところが、この原曲はドイツ民謡『H?nschen klein ちいさなハンスさん』。http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4nschen_kleinドレスデンの学校の先生、フランツ ヴィーデマン(1821-1882)の作詞だそうです。そんなに古くないですね。メロディーは詩より古く、18世紀初頭であったかもと推測されています。1番ちいさなハンス(へんすひぇん、ハンスの愛称。ちなみにお菓子の家をかじって魔女に捕まるヘンゼルも本名ハンス。)は杖と帽子を持って広い世界に一人で旅に出ます。でもママは泣いている。『幸運がありますように。』と言いながら、目は(すぐに帰ってきて)と語っている。2番ハンスが旅に出て7年。故郷に帰ろうと決めて家路を急ぐハンスさん、もう子供じゃありません。日に焼けて大きくなったハンスを、見分けることができるでしょうか。3番通りすがりの人たちにはハンスが誰だかわかりません。妹もわからない。でもお母さんは一目でわかって、『ハンス!!神様、これは私の息子です。』と言いました。日本版『蝶々』が花から花へと遊んでいるのと違って、どうやらハンスは修行の旅に出ていたようです。現代も職人が研修に行く制度があるくらいですから、きっとハンスも立派な職人になるため、放浪の旅をしていたのでしょう。最後にお母さんの元に帰る場面は、息子を持つ母としては、うるうる感動ドラマ。でも、なぜ日本に『スペイン民謡』として伝わったのでしょう。文部省が音楽取調掛を設置して、学校で西洋音楽を子供たちに教えるための教材=唱歌を、西洋の曲に日本語の歌詞を載せたり新しく創作したりする時に、多くのヨーロッパの曲がアメリカ人メイソンによって伝えられました。この時に、おそらく英語訳のH?nschen kleinが間違ってスペイン民謡と書かれた楽譜が使われたのではないでしょうか。英訳Little JohnHe has goneOut to see the world aloneStaff and hat,原語H?nschen kleinGeht alleinIn die weite Welt hinein.Stock und HutSteht im gut,・・・というのがKomononesato氏の推測です。台湾に詳しい氏によりますと、中国・韓国・台湾でも『スペイン民謡』と書かれているそうです。日本にアメリカから間違って伝わった伝言が、そのままアジアのお隣に伝わってしまったという訳です。
2007.07.10
コメント(0)
-
三代目天賞堂、初依頼原稿。仮想インタビュー『椿姫』
トスカニーニ オペラ アソシエーション発行の情報誌『タクトゥス』にて、三代目天賞堂が連載を始めました。『オペラの小部屋』第一回はヴェルディ作曲の『椿姫』の主人公ヴィオレッタ ヴァレリー嬢を迎えて三代目がK柳T子女史のノリでインタビューします。他の記事はレッスンのイタリア語、オペラの歴史など真面目で為になりますので、一服の清涼剤として。東京のヤマハで買えるという噂もあります。よろしくお願いします~。
2007.07.05
コメント(0)
-
D管のオルガン
なんちゃらスタン、と語尾の付く国の人たちには、けっこうショウユ顔がいます。今回の演奏会のオルガニスト・みるらん。三代目の頭の中で漢字変換されて『美蘭』と思い込み、女性だと思って楽譜を送ったらおっさんでした。いや、私よりは若いんですけど。(爆笑)秋葉原とか天王寺とか歩いてそうな顔です。親近感。出身地が赤い三日月の国に迫害されている国だから、難民かと心配したら、エリートでした。ごめん。6歳で才能のある子供を収容する全寮制の音楽学校(旧ソ連では御馴染み才能青田刈り)に入り、モスクワで勉強し、コンクールに入り、奨学金を貰ってベルリンに着地。居つく。妻(ドイツ人)子(かわいい娘)あり。人柄が温厚そうで、それをいいことに彼の前任者はリタイア後10年経っても教会を我が物顔・・・。わざわざ我々の合わせの時間に教会にやってきて、工作します。電気ドリルなどを駆使して楽器を載せる台を製作。横の部屋に入るという気の利くこともせず、目の前でうぃぃぃーーーーん。がしんがしん。その時に歌っていた歌詞がs??e Ruh甘き憩い(静けさ)だったもんで、噴出しそうになるのを堪えるのが大変でございました。ヴィヴァルディとヘンデルのアリアと二重唱。本番は車で2時間、田舎に似合わず壮大かつ華麗な教会。昔は巡礼が訪れたのでしょうか。日曜の午後、なんと今日が新任第一日目だというオルガニストしゅてふぁん氏が弾きながら我々を待っていました。ベルリンSpandau区某所と兼任らしい。楽器の裏にあるスイッチの操作を説明してもらいながら、ふいごが実際に動く様子が見えました。あまり時間がないので急いでテンポあわせ。じゃあ曲順の通りにと、みるらんが弾いた最初の和音。あれっ、この曲G Durだけど?弾いてるよ。でもA Durじゃん。がががががーーーーーーーん!!全音高いっす。ぎゃぼーん。私は絶対音感があるので、楽譜を読み替えないと歌えません。何て不便。みるらんは『ぼくは幸い絶対音感がないので弾ける。』と言ったくせに、本番でヴィヴァルディの詩篇109、コロラトゥーラのアリアのどーってことない和音で行方不明になりました。おいっ、落ちるな、せめてバスくらい弾けー。バロックはあまり音域が高くないので、上がること自体は歓迎なのでありますが、音が上がると色が変わります。柔らかい感じで歌いたいのに、明るくなりすぎたり。聴衆サービスに、世俗のアリアも入れました。超メジャー曲、Ombra mai fuみるらんがソロでオーボエを使いました。リード管は大抵の教会では狂っています。ご多分にもれず、すごい音痴。気がついたら他の音栓に変えればいいのに、そのまま続行。『しゅてふぁんは調律してあるって言ったのに。』そのまま信じないでほしい・・・・。メゾのカレン、二重唱でソプラノと上下が入れ替わる箇所がきつそうだったのに、全音高くなったので、かなり気の毒。後で、みるらんが、『高いって言わなければ彼女は気づかずに歌えたと思う。』と言いました。すいません、騒いで・・・・。この話をしたら、管楽器奏者の友達が『D管みたいなもん?』と言いました。(楽譜にドと書いていたら実際に鳴るのはレの音。)おお、D管オルガン。実は息子の風邪をうつされて体調が万全ではなく、(それでも歌えるのはアドレナリン効果?)ベルリンに戻ってから熱が出ました。息子を生きたユタンポとして抱きかかえ、娘に手を握って暖めてもらいながら寝たお陰で翌日には回復して600kmを運転して無事帰りました。次回は子供は置いていくぞ・・・・。
2007.07.01
コメント(0)
-
ハイリゲングラーベ宗教音楽コンサート
ハイリゲンダム(G8会場)ではなく、ハイリゲングラーベです。どこよ、それ?と皆さん思うでしょう。私もどこか知りませんでした。ベルリンからアウトバーンをハンブルク方面に112km。旧東ドイツの田舎で、中世からの由緒ある女子修道院です。長い歴史の間には領主に無理矢理カトリックからプロテスタントに替えられちゃったり、ペスト流行時に人数が激減したり、30年戦争で避難してたり、いろいろあったそうです。名前の由来は聖なるHeilige穴Grabe。小さな礼拝堂が中世の遺跡の上に建てられています。写真だと後方のドアの前にある柵の下にあります。ベルリンの北西にあるSバーンの駅でメゾのKとオルガニストのHを拾ってA君(めるせです)で出発。工事区間も順調に通過したのはいいけれど、途中で60kmに落としてノロノロ運転(100kmでトロトロであるアウトバーンでは極めて低速)せざるを得ない、バケツを引っくり返したような集中豪雨。後で聞くと、ヒョウが降った地域もあったとか。雨女記録、また更新ですぅぅ。なぜ私が歌う日には雨が降る!?2005、2006年には二年連続7月7日に演奏会があり、豪雨とスコールのごとき激しいにわか雨が降ったのでした。断水直前の沖縄に着いた日に豪雨、年間降雨日数5日という噂のドバイでも降られた三代目、人道援助でアフリカにでも送ってくださいな。(本当に降ったら笑うしかありません。)余裕の開演2時間半前到着。礼拝堂に雨が入ったのを関係者が片付けているところでした。若くて綺麗な女性も働いています。もしかして修道院の方ですか・・・・俗世に未練はありませんか・・・・?院長様は演奏会を仕切って30年というベテランのおばさまです。ここのオルガンはパイプが壁掛けタイプです。ストップ10、一段鍵盤カプラーなし。きびしい!でも壁にはミュシャっぽい絵が書いてあったりして、かわいい礼拝堂です。代々の院長様の名前が壁に書いてあったりして、15世紀から1900年代初頭まで続いています。貴族の名前が多いですね。やっぱり持参金が多かったんだろうか。(俗世の憶測)ヘンデルから始めてバッハ、メンデルスゾーンなどの ほぼドイツプロ。バッハのロ短調ミサの二重唱などをはさんでメゾとソプラノのアリアを交互に歌います。バッハのカンタータ『Meinem Hirten beleib ich treu』は、詞が今年生誕400年のPaul Gerhardt(プロテスタントの賛美歌を多数書いた重要人物)ということを演奏前にお話しました。この修道院はプロテスタントなので院長様は大きくうなづかれました。(選曲にはマーケティングも重要なのでございます。)ハイドン『天地創造』5日目よりガブリエルのアリア。これは元ネタがBishop卿の『きけひばりを』であろうと三代目は睨んでいるのでございますが、ハイドンのソナタのメロディーに歌詞を付けて歌いました、というような器楽的なアリア。一番受けたのはメンデルスゾーンの『パウルス』の『聞けイスラエル』。ラテン語のミサと違ってドイツ語のせいか、盛り上がりまくる曲のせいか、うわーっと拍手がきます。合間にKが歌うメゾアリアはしっとりタイプ、ソプラノアリアが騒々しいので程よいコントラストです。H君のソロはバッハのプレリュードとフーガ。番号失念。三代目は譜めくりしました。アシストはストップが少ないので不要でした・・・。最後にはスタンディングオベーションもしていただき、盛り上がりました。田舎なので院長様が新聞に載せてもらうほか、キャンプ場にチラシを置いたり、地道な広報活動の結果、人口の割りに人が入るのだそうです。オランダ人のグループも来てくれて、演奏終了後オルガンを興味深く見たり、教会を見学していました。我々は院長様心づくしの軽食とお茶をいただき、独り者のH君は残りのパンを包んでお持ち帰り。ちなみに彼は天井改修工事の為に取り壊しの危機に瀕した村の教会のオルガンを自分が撤去して無料でお持ち帰りして、2間のアパートにパイプを積み上げているそうです。組み立てる為に広い部屋に引っ越すか、単に部屋を片付けるだけで済むのか微妙だそうな。
2007.06.04
コメント(0)
-
宗教音楽のアリアと二重唱@ハイリゲングラーベ
代役第二弾、ドイツ、ブランデンブルク州ハイリゲングラーベの僧院でオラトリオ、ミサ、カンタータからアリアと二重唱を歌います。Heiliggrabkappelle礼拝堂にて5月26日 19時から。お問い合わせはこちらAdresse und InfosKloster Stift zum HeiligengrabeStiftsgel?nde 116909 HeiligengrabeTelefon: 033962 - 8080Fax: 033962 - 80830klosterstiftzumheiligengrabe@t-online.dewww.klosterstift-heiligengrabe.de翌朝にはベルリン大聖堂で8時半練習10時本番。片道100kmを自分でA君(めるせです)と移動、ちょっとハードな週末になりそうです。
2007.05.23
コメント(2)
-
学生同盟松明行列@葡萄酒村
制服フェチの皆さん、こんにちは。(えっ!?)わが葡萄酒村には城がふたつあります。ひとつは中世の城Windeckヴぃんとえっく古城の例にならい過去の戦争で破壊された廃墟です。もう一つは20世紀初頭(1908ころ)に建てられたWachenburg ヴぁっへんぶるく。これは城としては新築の部類に入ります。Wachenburg城ではコンサートなどの催しもありますが、学生同盟の持ち物?であり、毎年この時期に全国からメンバーが集まって大会を開きます。http://www.vacw-wiesbaden.de/40342.html?*session*id*key*=*session*id*val*この学生同盟のホームページの真ん中あたりに城の写真が出ています。学生同盟、なにそれ?というお方。『アルト ハイデルベルク』『しまりんごシリーズ』でもお読みくださいませ。アルトハイデルベルク時代のイメージって、こうかな。http://www.lwl.org/LWL/Kultur/Aufbruch/popups/kult/wohnen_kleiden/guestphalia/index_print_htmlちょっと右翼でかなりマッチョな男子学生親睦団体、さすがに現代は女性版もあるそうです。昔は決闘でほっぺたに傷をつけるのがオシャレだったのだそうですよ。生涯続く友情だけあって、HPの写真に登場するメンバーには現役時代は戦前っぽい爺様もいらっしゃいます。http://www.vacw-wiesbaden.de/15101.htmlたいていのパーティーは夫人同伴の国で、オジサマばかりの宴会写真はちょっと異様です。それはさておき、昨夜は大会最終日のトリを飾る松明行列がありました。山の上にある城から制服に身を包んだ現役の若い衆と気が若い衆が松明を持って麓へ行進、マルクト広場に集合してセレモニーがあります。マルクト広場は旧市街の中心、カーニバルなど祭りの中心会場はココです。広場にはレストランや居酒屋がテラスにも席を並べて、行列が見える席は街の人々や観光客で一杯。葡萄酒村に移り住んで3年になる三代目一家、昨夜はじめて見物しました。行列が城を出発した21時30分すぎ、日が暮れた山には松明の灯りがチラチラ見えます。駐車場に苦労してマルクト広場に歩いていく途中、駐在員一家が送別会帰りで戻るところに遭遇。今からいいところなのに帰っちゃうとは勿体無い。美味しいイタリア料理店La Cantinaで、席はないかと聞くと中なら開いてるとのこと。ちょうど窓側でドアを開放して広場が見える席が開いていました。ラッキー!IKEA帰りで喉がかわいた双子は駆けつけ一杯リンゴジュースの炭酸割り あぷふぇるしょーれ。大人はキアンティ辛口に炭酸水あっくあみねらーれがっさーた。(突然イタ語)子供にはラビオリ・リコッタチーズ詰めを半分ずつ。タヌキはタイのロースト、三代目は仔牛のローストトスカーナ風。ありがちなドイツ風にアレンジされたなんちゃってイタリアンではなく、本当のプロの味です。食事が進んだころ、行列がブラバンの演奏と共に到着。支部の地名を書いたプラカードを持って行進。あああ・・こういう時に携帯の電池が死んでます。断末魔の叫びを無視して3枚だけ撮影成功。セレモニーの最後は国家斉唱。(右翼ですから。)ハイドンによる旋律は知っているけど、いまだに歌詞を全部覚えていない三代目、もそもそと一緒に歌います。うちのタヌキが工科大に通っていたころ、学生同盟の集まりに行ってみたそうです。でも新人がやらされるゲームがアホらしくて入会しなかったそうな。そういう馬鹿をやって楽しむっていう部分も必要かもと三代目は思うのですが、クールな性格のタヌキには自分には合わないと思えたそうです。楽隊とマネージャーの違いって、そこなんでしょうかね。さて、セレモニーが終わると我々見物人は帰りますが、参加者たちはビールを飲みに繰り出します。客が入れ替わってお店の賑わいは続きます。昔は剣で決闘、今はビールの飲み比べで決闘なんだそうな。平和な時代です。
2007.05.19
コメント(0)
-
学生同盟松明行列@葡萄酒村
制服フェチの皆さん、こんにちは。(えっ!?)わが葡萄酒村には城がふたつあります。ひとつは中世の城Windeckヴぃんとえっく古城の例にならい過去の戦争で破壊された廃墟です。もう一つは20世紀初頭(1908ころ)に建てられたWachenburg ヴぁっへんぶるく。これは城としては新築の部類に入ります。Wachenburg城ではコンサートなどの催しもありますが、学生同盟の持ち物?であり、毎年この時期に全国からメンバーが集まって大会を開きます。http://www.vacw-wiesbaden.de/40342.html?*session*id*key*=*session*id*val*この学生同盟のホームページの真ん中あたりに城の写真が出ています。学生同盟、なにそれ?というお方。『アルト ハイデルベルク』『しまりんごシリーズ』でもお読みくださいませ。アルトハイデルベルク時代のイメージって、こうかな。http://www.lwl.org/LWL/Kultur/Aufbruch/popups/kult/wohnen_kleiden/guestphalia/index_print_htmlちょっと右翼でかなりマッチョな男子学生親睦団体、さすがに現代は女性版もあるそうです。昔は決闘でほっぺたに傷をつけるのがオシャレだったのだそうですよ。生涯続く友情だけあって、HPの写真に登場するメンバーには現役時代は戦前っぽい爺様もいらっしゃいます。http://www.vacw-wiesbaden.de/15101.htmlたいていのパーティーは夫人同伴の国で、オジサマばかりの宴会写真はちょっと異様です。それはさておき、昨夜は大会最終日のトリを飾る松明行列がありました。山の上にある城から制服に身を包んだ現役の若い衆と気が若い衆が松明を持って麓へ行進、マルクト広場に集合してセレモニーがあります。マルクト広場は旧市街の中心、カーニバルなど祭りの中心会場はココです。広場にはレストランや居酒屋がテラスにも席を並べて、行列が見える席は街の人々や観光客で一杯。葡萄酒村に移り住んで3年になる三代目一家、昨夜はじめて見物しました。行列が城を出発した21時30分すぎ、日が暮れた山には松明の灯りがチラチラ見えます。駐車場に苦労してマルクト広場に歩いていく途中、駐在員一家が送別会帰りで戻るところに遭遇。今からいいところなのに帰っちゃうとは勿体無い。美味しいイタリア料理店La Cantinaで、席はないかと聞くと中なら開いてるとのこと。ちょうど窓側でドアを開放して広場が見える席が開いていました。ラッキー!IKEA帰りで喉がかわいた双子は駆けつけ一杯リンゴジュースの炭酸割り あぷふぇるしょーれ。大人はキアンティ辛口に炭酸水あっくあみねらーれがっさーた。(突然イタ語)子供にはラビオリ・リコッタチーズ詰めを半分ずつ。タヌキはタイのロースト、三代目は仔牛のローストトスカーナ風。ありがちなドイツ風にアレンジされたなんちゃってイタリアンではなく、本当のプロの味です。食事が進んだころ、行列がブラバンの演奏と共に到着。支部の地名を書いたプラカードを持って行進。あああ・・こういう時に携帯の電池が死んでます。断末魔の叫びを無視して3枚だけ撮影成功。セレモニーの最後は国家斉唱。(右翼ですから。)ハイドンによる旋律は知っているけど、いまだに歌詞を全部覚えていない三代目、もそもそと一緒に歌います。うちのタヌキが工科大に通っていたころ、学生同盟の集まりに行ってみたそうです。でも新人がやらされるゲームがアホらしくて入会しなかったそうな。そういう馬鹿をやって楽しむっていう部分も必要かもと三代目は思うのですが、クールな性格のタヌキには自分には合わないと思えたそうです。楽隊とマネージャーの違いって、そこなんでしょうかね。さて、セレモニーが終わると我々見物人は帰りますが、参加者たちはビールを飲みに繰り出します。客が入れ替わってお店の賑わいは続きます。昔は剣で決闘、今はビールの飲み比べで決闘なんだそうな。平和な時代です。
2007.05.19
コメント(0)
-
中世古城騎士の祭り@オーデンの森 ニーベルンゲンシュトラーセ
中世ファンの皆様こんばんは。ダルムシュタットより南に降りた街ベンスハイムより始まる街道・ニーベルンゲン シュトラーセの終点近くにある古城・リンデンフェルスにて、先週末『騎士の祭り』がありました。母の日でもあった日曜日13日、三代目は隣町でミサの伴奏(洗礼付き)を終えて、子供たちと弟子1号をA君に乗せて祭りに繰り出しました。お友達とお嬢ちゃんたちとは現地集合。城は葡萄酒村より大きいとはいえ、山の中の村。狭い場所に近郊の人々が集まるので駐車場探しは厳しかった・・・。山奥なので携帯の電波は調子悪いし。お友達と落ち合って、いざ城へ。周囲には中世の服装、しかも庶民っぽい格好の人がうろうろ。中世というより当世風のゴシック(ロリ抜き)の男女も少なくありません。その謎が入り口で解けました。仮装をしている人は入場料4Euroが半額になるのです。110cm以下の子供は無料。坂道を登って城門をくぐるまでの間にも、中世コスプレの人々が、いろんなお店を出しています。ガラスビーズ、ケルト系装飾品、中世の衣装、衣装の作り方を書いた本や生地(厚い!!)、動物の角をくりぬいたコップに皮ホルダー(ワインを中世風に飲みたい貴男にお勧めのアイテム)、石の当たるルーレット。子供は石が好きなので、やらせてあげました。娘には水晶、息子には金箔が当たりました。一回2Euroなり。ちなみに当たりにはダイヤモンドというのもあり、それは研磨していない黄色っぽい原石0,3カラット、ケース入り。ダイヤが当たった子供は『ぼくの石ちいさい~』と泣いたそうです。ハープやリュートの弾き歌いもあり、市場が立つ賑わいとはこういう感じだったのかと思わせてくれます。さて、城門をくぐると、そこには食べ物の匂いが。まずは腹ごしらえ。タルト フランベ(アルザス風薄焼きピザ)は、この地方の祭りには欠かせません。りんご酒、りんごジュース。中世の城は、どこも昔の戦争で破壊されています。建物の土台だけ残った部分が舞台のようになっていて、そこでアトラクションがありました。火を吹く芸人。この芸自体はよくあるものですが、中世の服装をしている芸人さん、ギャグをかましながら楽しませてくれます。『だれかポケットドラゴン持ってない?』といって客からライターを借りたり。中世の楽師たち。楽器博物館に納まっている『ハーディーガーディー』、現物の演奏を聴くのは二度目でした。バグパイプ、タイコ、リュート。楽師達は足に鈴を巻いています。足踏みすると鳴る仕掛け。歌も楽器も楽しいのですが、野外でマイクなし、しかも真横で鍛冶屋が実演中・・・・客は食べたり飲んだり・・・聴こえません~。以前パーティーの余興で聴いた時は、よく響いてたので、野外でがやがやしている場所には厳しいですね。子供たちに鳴り物をやらせてくれた最後の曲は大うけでした。中世風アレンジのTV主題歌『長靴下のピッピ』。騎士の戦闘実演。騎士が大声でなにやらわめく。金髪の女性が少々訛ったドイツ語で通訳。中世ドイツ語を現代語に訳しているようには聴こえない。なんだろう、あれっ、演奏旅行でエライ目に遭ったときに聴いたことのある響き・・・もしかして・・・・。ポーランドから来た欧州で一番古い殺陣のグループ・・・だそうです。満足しての帰り道、5Euroの1Kgはあろうという重い焼きたてパンを購入。手作りビーズ屋さんで、3,5Euroのビーズを皮ひもに通してもらう。なかなかしゃれたアクセサリーになります。娘と色違いでお揃い。息子も欲しがったが、あんたはすぐ壊すからと却下。(そういう問題ではないが・・・)お友達も母子で購入。墓場の横に止めたA君(メルセデス)に向かう途中の骨董屋さんで、Hohnerのハーモニカと鍵盤ハーモニカを子供たちが欲しがったので、店の人に『まけてくれたら両方買いたいけど・・でもうちがやかましくなるわね、はっはっは。』と交渉、思ったより下がったので購入。子供用のオモチャと違って音がいいです。世渡り上手の娘、『ありがとう、連れて行ってくれて。』と言いました。4歳というと、そろそろ記憶が残っても良い頃。三代目は2歳半の時に弟が生まれたことを覚えています。騎士祭りのこと、思い出に残るかな。もしかして中世ファンになるかな?
2007.05.13
コメント(0)
-
代役
急な代役でペルゴレージのスターバト マーテルとヴィヴァルディ他を歌います。ベルリンの壁からちょっと外のFalkenseeの教会で、日曜の10時半からです。(朝ですよ~)http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/10910459/61759/家には弟子たちが留守番、歩く生物兵器の双子を連れて、これから行ってきます!というわけでしばらく書き込み停止させていただきます。
2007.04.20
コメント(0)
-
チェロ奏者石坂団十郎
イケ面三連戦、最終日は日系ドイツ人チェロ奏者の石坂団十郎君。いえ、別に意図したわけではなく偶然なんっすよ。ベルリンフィルのお二人に比べるとグッと若い1979年生まれ。今夜の会場はHeppenheimの旧市街にあるKurf?rstensaal選帝侯の大広間。この村の教会で三代目は代理オルガン弾きをしています。教会では時々読書会をやっていて、時々参加しているのです。今までドイツの現代文学の他にオランダなどの翻訳物、村上春樹のドイツ語版などを読みました。そこに参加しているメンバーに、この室内楽コンサートシリーズの主催者がいるので情報をキャッチ。当日券で大丈夫だろうと出かけてきたら満席、定期会員の席で余っているところに入れてもらいました。(案外高くて、パユの最低料金と同じ。あっちはオケ伴奏、こっちはピアノ伴奏・・・・)広間の壁には歴史を説明する文章が書かれています。それによると建物の基礎はカール大帝の時代、ロルシュ修道院の傘下に入ったり、プファルツになったり、今はヘッセン州。時代は変われど役所として使われてきた場所のようです。壁には天使のフレスコ画、ピアノの横にある暖炉にはお鍋がかかっています。まさか本当にシチューを炊いたりしないでしょう。こういう豪華な広間で演奏するから室内楽というんですね。Kammermusikを日本語に訳する時に、もうちょっと適当な言葉は無かったのかなあ・・・・。満員の客席には団十郎さんのご両親もお見えです。最初の曲はシューベルトの「アルペッジォーネ ソナタ」。三代目はこの曲を暗譜しているほど好きです。楽譜を買ってピアノパートを練習して伴奏の押し売りをしたくらいです。PUKUちゃん、その節はどうも。だから、どうってことない和音の色のニュアンスを出すのがどんなに難しいか、よぉぉぉく知っています。この作曲家は見た目は簡単そうなところが難しいんですよね。伴奏者ホセ君(Jos? Gallardo)、うまい人だと思います。実は終演後、ホセ君に声をかけてその話をしたら、隣にいた団十郎君のお母様(ピアノを弾かれます)も、「最初の和音が難しいのよね。」とおっしゃいました。三代目は「誰よりも高い声を歌うパート」なので、競合する高音楽器(フルート、ヴァイオリン)より低音楽器の方が好きです。チェロ、トロンボーン、ホルン、クラリネット・・・・。チェロのように柔らかい声で歌いたいという理想を持っています。今日も(ああ、こういう風に歌いたい)と思う場所がありました。器楽奏者はカッコいい場所で目を閉じて忘我の境地で弾いていることがありますよね。あれ、歌手はやっちゃいけないことなので、かえって憧れます。聴衆へのコンタクトを閉ざすうえ、目を閉じると共鳴腔が開かないという技術的な問題もあります。(初心者がアガルとやりがちな間違いだったりして。)(ちなみにオペラの演技で目を閉じるのと実際に閉じるのとは違います。)ピアノもちゃんとコントロールして、かつ燃えてます。三代目が弾くと自分も興奮して燃え上がって大火事を出してしまうところ。ホセ君を聴いて、ベルリンのピアニスト「おケンちゃん」を思い出しました。団十郎君の持ち味は情熱的な演奏。このようなロマンティックばりばりの曲では、むしろ抑制がきいている方かもしれません。音のニュアンスにベルリンフィルの中年の王子様たちに通じるものを感じました。次のゾルタン コダーイ(今日も古代君だ)のソナタOP.8の方が更に温度が高かったかもしれません。ハンガリーの民謡の要素が入る、技巧的な速い曲。無伴奏です。パプリカもニンニクもたっぷり入ったハンガリー名物グーラッシュのごとく、火を吐くごとく。高音の重音奏法、よくこんなの弾けますね・・・。ここで休憩が入ります。 休憩時間、地元のワインを1Euroで試飲できました。ここHeppenheimには州立醸造所があります。ハイデルベルクからダルムシュタッとまで南北に連なる山の斜面にはブドウ畑。村ごとにローマ時代の古城。村の旧市街には木組みの家並が残っています。うちの双子は「へっぺんはいむ」に山があり、その上にお城があることから何か勘違いしていて、山のてっぺんにオルガンがあると思い込んでいます。「ママはお山のてっぺんの てっぺんはいむ でお練習するの~。」ちゃうちゃう。それはさておき、試飲したのはBlauer Sp?tburgunder 200513,5%若いワインなので、正直(薄い)と思いました。3-5Euroのワインを買ってきては地下室で5年くらい寝かせて飲んでいるので、若いワインはモノ足りません。さて後半。Webern チェロとピアノのための2つの作品これ、この作曲家としては異常に普通の曲です。同じくWebernのソナタ、世界最短チェロソナタ?です。まあ、この作風で長くやられるときついかも。またもWebern チェロとピアノのための3つの小品演奏したら難しくて面白いんですが、それでもあえて言おう、Webernとその一味は音楽の女神をバラバラにしました。(言ったぞー、はあはあ。)この作品を演奏した人たちも偉いが、真剣に聞いた聴衆も偉い。三代目は休憩で飲んだワインが災いして朦朧としていました。ブラームス ヴァイオリンソナタNr.1 ト長調チェロ版普通チェロだと移調して演奏するのが普通なのだそうです。団十郎さんは原調の方がいいと判断して演奏。混濁する意識、ああこのまま寝てしまえたらどんなに幸福であろうか。ショパン 序奏と華麗なるポロネーズハ長調Op.31団十郎さんが「サロン音楽です。」と宣言した通りの曲。サロン音楽を例えて言うと、頭の悪い超美人のよう。綺麗で誰もがハッと目をひかれる。中身がないので飽きられる。でも他の曲がマジだっただけに一服の清涼剤でした。プログラムに内臓されたアンコールのようです。鳴り止まぬ拍手。「皆さんが満足して家路につかれるように。」とアンコール曲はバッハ。この演奏会は6月7日15時5分からラジオhr2で放送されます。ヘッセンにお住まいの方はどうぞ。www.kammerkonzerte.hr-oline.de演奏終了後、昨年Darmstadtでの演奏会の時にお話したことのある御両親に御挨拶。御本人とはCDサイン会終了後に御挨拶。昨年はドイツ語でお話して、「日本語を習わなくて後悔しています。お子さんには日本語を続けさせてください、将来きっと感謝します。」と言っていた団十郎君、今回は全部日本語で話をしました。一年ですごく上達してるじゃありませんか。主催者のオバちゃんにも御挨拶。時々参加している読書会で会う人なのですが、すぐにピンとこなかったみたい。今月の読書会で読む「リスボンへの夜汽車Nachtzug nach Lissabon」の著者(Mercier)が来る文学の夕べが会合の翌週にあるらしい。「あなた切符持ってる?もう売り切れなのよ。」はー、そうですよね、ベスト10に入るくらい売れてますもんね。(500ページくらいあるのにまだ50pしか読んでない三代目、読書会までに読破は絶対無理。日本語だったら500ページは3日で読めるんだが・・・。真面目な高校教師離婚歴アリが、ポルトガル人女性とぶつかったのがキッカケで突然夜行列車に乗って出奔する話・・・まだ面白いのかどうかわかりません。)「そうなってほしくなかったのに。読書会のメンバーの分の切符がなくなって困るわ。契約したのは一年前で、まさかこんなに売れるとは思ってなかったのよ。」おいおい・・・・・。
2007.04.16
コメント(0)
-
フルート奏者 エマニュエル パユ
灰出山(はいでるべるく)の春音楽祭、本日のソリストは普段の職場では先週のオーボエ奏者アルブレヒト マイヤーの隣に座っている人、フルート奏者エマヌエル パユでございます。ベルリンフィル団員最年少記録を更新した22歳で1992年、アッバードに採用された、ということはマイヤー氏と同期ですね。ブレーメンの音楽隊、ならぬ「ドイツ室内フィルハーモニー ブレーメン」の最初の曲は古代君ことハンガリーの作曲家ゾルタン コダーイ の「ガランタ舞曲」(1933年)。「ごろんた舞曲」でも「がらくた舞曲」でもありませんよ。先週の地元オケの3倍くらい人がいるせいか、遠くから来たからか、本日のチケットの方がずいぶん高いです。そのせいか、平日のせいか、先週のように満席にはなりませんでした。曲順は新しいものから時代がさかのぼる構成。・・・と言っていいのかな。というのは2曲目のモーツアルトは1756年生まれ、次に来るハイドンは1732年生まれ、と生まれ年はさかのぼっているけど、没年は長生きしたハイドンの方が後。さて、指揮者登場。白髪交じりの髪ぼさぼさの小柄なオッちゃんです。名前をチェックしていなかった三代目、まあいいや、どうせ知らない人だろうし。最初の一振りが印象的でした。手首90度に曲げてます。ちょこっと猫背。あれだ、あれ。「リング」のミーメ。猫じゃありません。「リング」といえば「Lord of the Ring」でしょ、と思っている方の為に追記しますと、クラシック界でリングといえば「ニーベルンゲン」。ワグナーの4つに分かれた3部作です。なぜ4部作といわないかというと、最初の「ラインの黄金」は「序夜」とカウントするんだそうです。その「リング」のヒーロー、ジークフリートの育ての親の小人がミーメです。それはさておき、指揮者ミーメ、なかなかいいではないの。盛り上がってきたら機敏な動きがボクシングになってきました。戦うミーメ。それいけミーメ。人数は少ないけど一人一人の音がはっきりわかるのではなく、溶け込んでいる感じの豊かな響き。賑やかに、そして時々野蛮に田舎の踊り、とっても楽しい。思い切り発散した後にモーツァルトのフルート協奏曲ト短調。そっれーれれーれー(上の)れどどーしどれどしら・・・・ってテーマね。ソリストまぶしいです。いえ、そりこみ深くなった額のせいでなく、楽器が頭部管だけでなく全部金です。今の世の中、頭部管(吹き込み口のある管)だけでも金じゃないと吹いてらんない、と若いフルート奏者がぼやいてました。おっ、でもブレーメンの音楽隊のフルートのオバちゃんは全部銀だぞ。・・・・お給料の差かな。まずはTuttiを一緒に吹いて、まばゆい金の楽器を縦に持ちつつ出だしを待つたたずまい。この姿は・・・・笛を吹く王子様タミーノ(オペラ『魔笛』のテノール役)だっ!!そういえばト長調の音階上行形が曲に出てきますが、これは『おおこれはパパゲーノの笛』といって魔法の笛を吹く場面と同じ。理想のタミーノ王子は笛吹きパユさんであったか。先週のアルブレヒトもそうでしたが、フレーズを吹ききった時のアクションや間奏の立ち姿、オケのメンバーとセッションするかのような姿勢が大オペラ歌手のようです。Tenutoでの表情の付け方、PPの繊細なコントロール、同僚同士影響しあうのか、大指揮者たちに教えられ影響され積み上げてきたものなのか。音楽には楽譜という記録に残るものがあるけれど、実は口伝(?)で大芸術家から次代の芸術家に受け継がれていくものなのでしょう。ここで休憩。 さて、休憩時間にはサイン会。三代目は迷った末、モーツアルトのフルート協奏曲ト短調、ハープとフルートの為の協奏曲とクラリネット協奏曲(バセットホルン・ザビーネ マイヤー)というカップリングのCDを購入しました。オケはBPO指揮はアッバード。鳴り止まない執拗な拍手に答えて演奏してくれたアンコール曲の作曲家の名前を質問しました。Joachim Andersen、曲芸のような超絶技巧の曲でした。彼の録音はないそうです。演奏会のポスターにもサインをして貰いました。さて、後半。前半はパルケットの真ん中(が開いていたので移動・・)で聴いたので、二階席に移動。満席じゃないと、こういうことが可能です。ハイドン、シンフォニー、ニ長調104番。あれっ、本当に古典派?最初の古代君みたいに活気があって現代的、と思う箇所あり。モーツアルトの先駆者だなあと思うときあり。ブラームスに繋がるものを感じたり。楽しくて元気な古典です。ブレーメンの音楽隊のフルートのオバちゃんも、オーボエの人も、普通に上手な人です。管楽器奏者は皆ソリスト、でもそのオケのランクによって経験値が違ってくるんだろうなあ。でも、このミーメは良い指揮者だと思う。(名前知らないけど。)先週の室内オケと個人の技量は変わらないんだろうけど、指揮者の差かなあ。それにしてもパユさんやアルブレヒトの音色は特別だ。第一楽章で盛り上がると繰り返されるフレーズ、ある有名な民謡に似ています。『お坊さんも通る、兵隊さんも通る。』「アビニョンの橋で」のこの部分、れれれれみーれ、れれれみーれ。一度気になったら歌詞の幻聴が止まらない。盛り上がりでひたすら「お坊さんも通る、兵隊さんもとーる、とーる、・・・」いやあ、良かった、面白かった。こんな活き活きしたハイドンは初めて。駐車場からさっさと出る為に階下へ。でも気になる人の顔を近くで見るために舞台に近い方に入りなおす。その人はタイコ(ティンパニ)のお兄さん。長い手足を折り曲げるように座り、鋭い視線をミーメに向けて、反射神経良さそうな撥捌きが気になっていました。東欧系らしい黒髪。ドミ兄の髪を肩で切ったような容姿、といえば同志にはピンときていただけるでしょう。盛り上がる拍手に答えてアンコール。なにかわからないけど、古代君の「がらんた舞曲」と雰囲気の近い楽しい曲でした。シンバルとタンバリン、タイコも活躍。タイコの叩き方が面白くて笑い取ってます~。ああ、いい演奏会だった。駐車場からも素早く脱出して、ネッカー川のほとりをA君疾走、アウトバーンに乗って20分で帰宅。ベルリンフィルから森の中の家に帰るより速い。田舎暮らしも悪くない、物価高を除けば。家に帰って、ポスターをチェンバロの上に広げる。ここで三代目の目が点。指揮者ミーメ、トレヴァー ピノックでした。ごめんなさ~~い!!(だって写真のイメージと違ったんだもん。)
2007.03.28
コメント(0)
-
オーボエ奏者アルブレヒト マイヤー
灰出山(はいでるべるく)Stadthalle 公会堂にて、「プラハの春」ならぬ「灰出山の春」という音楽祭の一環として「アルブレヒト マイヤーとクアプファルツ室内オーケストラ」という 「ほぼモーツァルト」プログラムがありました。会場は故郷大阪の中ノ島公会堂を思い出させるレトロな建物。うちのタヌキに言わせればベルリンのWittenbergplatz駅に似ているそうです。地下鉄の駅に似てるって、それ失礼じゃあ・・・。レトロでも地下駐車場から傘不要というのはポイント高いです。Kongresshalle会議場という名前がついているし、Ballsaal舞踏場 だの、Kammermusiksaal室内楽ホール だの、他の設備もあるようです。内部は・・・・・主な目的は舞踏会ですか?というデザインながらオルガンが。でも演奏台が見えない。まさか見せかけだけの飾りではあるまいな。開演30分前、本日のソリスト正面入り口より入場。このホールには楽屋口がない?そういえばオケの人たちも正面入り口脇のトイレに出入りしています。満席の会場で、なんと隣に数少ないHDでの知り合いが座りました。世の中狭いですね。最初の曲はAnton Fils(1756-1760)のシンフォニート短調作品2の2。この作曲家、知りません。マンハイム楽派に属し、チェリストであったがシンフォニーを作曲、そこそこ名が売れていて、アマデウス君がマンハイムに来る3年前に亡くなったそうであります。ぶっちゃけていうと「ご当地作曲家」でしょうか。プログラムには彼の出身地である村の名前が書いてありました。私は他所から来た人なので、その村がどこなんだかわかりません。ヴァイオリン・ヴィオラが4人ずつ、チェロ2人、コンバス1人という編成、一人一人の音がクリアに聴こえます。生き生きとした演奏だから聴けるけど、今となっては平凡な曲。まあモーツアルトの初期程度には面白い曲かな。次は前半のクライマックス、というか実は演奏会自体のハイライトであったモーツアルトのオーボエ協奏曲。ソリストのアルブレヒト マイヤーは1992年からベルリンフィルのオーボエ奏者です。実は三代目もこの年にベルリンにやってきました。1997年に芸大を卒業するまで、立ち見券や当日に出る学生券を求めて行列したり、多い年には全体の3分の2くらいを聴きました。貧乏席や行列でいつも会う人たちと話をするようになって鑑賞仲間が出来ました。そしてアッバードの時代が終わるころ、そうやって通う時間がなくなってしまいました。思い出深いベルリンフィル。アルブレヒトがその前に在籍したバンベルクに住んでいたTが彼と面識があったことから、なんとなく応援していた奏者でもあります。舞台に登場、階段につまづいてます~おいおい。最初のTuttiから一緒に吹くアルブレヒト。もしかして音だし兼ねてますか?彼はこの曲の影の指揮者でした。本人の多彩な音色はオケからも繊細な色を引き出していきます。(だって最初の曲とは違うもんね。)最初の音は、ハッとするくらい静かで美しい音でした。オケのオーボエとの掛け合いでは後ろを向いての「セッション」。オーボエという楽器を通した歌を聴いているようです。クレッシェンド、ディミヌエンド、ピアニッシモの微妙なコントロールが、まるで偉大な歌手のようなのです。コロラトゥーラ唱法と同じで、すべての音が均一で磨きぬかれた玉のよう。ほんのわずかなTenutoに洗練を感じます。テンポはゆっくり気味。終楽章などは、よくあるタイプの速い演奏とは対極。速く演奏すると見落としがちなニュアンスを丹念に、しかし勢いを失ったり活気をなくしたりすることなく、小編成のオケに相応しいバランスであったと思います。場所とオケにあわせて調整していますね、きっと。この後に休憩。その後でモーツアルトのアンダンテKV315。オケが舞台に乗って待っている静寂のとき、裏から音出ししているのが丸聞こえ。お客に失笑が。三代目も楽屋で出番寸前まで発声練習している神経質なテノールを思い出して笑っちゃいました。寸前までチェックを怠らない姿勢は立派。かといって演奏は全然神経質じゃないんです。なごみ系のアンダンテの後、モーツアルトの交響曲40番。指揮者、すみません。オケの人も一生懸命なのに悪いけど、この曲いりません。前半をアンダンテと40番にして、オーボエ協奏曲でプログラムを終わって欲しかったです。すごく頑張ってるんだけど、あの協奏曲の後ではシンフォニーが雑に聴こえます。でもお客さんは三代目より優しい。拍手に答えてアンコール。さて、演奏会場ではアルブレヒトのCDが販売されていました。http://albrechtmayer.com/1024/Start.htm↑写真も掲載されています。けっこう男前なので、知らない方はぜひ御覧ください。(笑)三代目はバッハ作品集Lieder ohne Worteを購入。バッハを再発見したメンデルスゾーンの有名なピアノ曲集のタイトルをいただいたようです。声楽曲やオルガン曲をオーボエで演奏した小曲集。気になる曲が沢山あります。そして終演後にサイン会。三代目がサインをしていただいた時に、バンベルクのコンサートでチェンバロを調律なさったwaji sanの日記を読んで即切符を買ったとお話したら、握手を求められました。すごく喜ばれたようです。バンベルク時代の知り合いTも一緒に来たかったんだけど・・・と言ったら、もう一回握手。「よろしく言っといて。」すっかり大家になっても気さくな感じは15年前のままでした。というのは15年前ベルリンフィルの楽屋口で三代目が「このあいだのメンデルスゾーンのソロ、良かったです。」と声を掛けた時にも、気さくにお話してもらったのでした。調子に乗った三代目、「アッバードの時代、BPOのプロの3分の2を聴きました。」と言いましたら、ここだけの話ですが、「今もアッバードが一番・・」みたいなことをつぶやかれました。アッバードに採用された人ですから、感性が合うんでしょうね。別に西門卿に異議があるわけじゃないんですが、三代目が通ったのはアッバードの時代。フィルハーモニーとオペラの貧乏席に通った時代を懐かしく思い出した夕べでした。そういえばその時代に聴いた指揮者の中で、鬼籍に入ったマエストロが少なくありません。ショルティチェリビダケシノーポリカルロス クライバー(ジュリーニ、まだ生きてましたっけ?)そのうち彼らを聴いた事がトシ自慢みたいになるんでしょうね・・・。それはさておき、あまでうす君が生きていたらアルブレヒトの演奏を聴いて、喜んであと2-3曲オーボエ協奏曲を書いたんじゃないかな。写真、思いっきりブレてます。無念。 モーツアルト12歳の時の作品アレグロ。あああぁぁ、Anton Fils、12歳のアマデ君に負けてます。初期(10代)に負けるご当地作曲家、このアンコールで最初の曲は要らん曲だったとバレてしまいました。
2007.03.24
コメント(0)
-
箱買い@トルコバザール@ドイツ
大家族庶民の味方、トルコマーケット@ドイツ。ここはドイツの中のイスタンブール(行ったことないけど多分・・・)。大家族のトルコ家庭の胃袋を支える格安野菜、食材のかずかずが、高度成長以前の日本を彷彿とさせる粗末な市場に満載。野菜は早く使わないと危ない感じのものが激安で出ていることもありますが、たいていはドイツの普通のスーパーのものより新鮮でお買い得。オリーブ、白チーズ、羊肉などトルコならではの食材、香辛料もオリエントならではのものが安く手に入ります。ちょっとなあ・・・と思うのはお菓子類。半端でなく甘いです。ジャムも情け容赦なく甘い・・・でも、今回好奇心に負けて買っちゃいました。バラジャム。バラの花びら15%、残りは砂糖、糖類。子供達がはまっていますが、二度と買うことはないでしょう・・・・・。なんだか耽美なイメージがありますが、実際は強烈です。ホウレン草1箱3,99Euro。初日・ホウレン草入りラザニア2日目 ホウレン草と白チーズの「すぱなこぴた」ギリシャ料理です。薄い皮に中身を包んで、溶かしバターとミルクを混ぜたものを塗りながら重ねて、パリっとオーブンで焼きます。ここで息子から苦情が出ました。「なんで毎日ホウレン草なの。」ほとぼりが冷め、残りを使うチャンスを伺っております。栗5KG袋5,99。オーブンに突っ込んで焼き栗。渋皮が剥けにくく、お菓子に使うというもくろみは挫折。庭に植えてやろうかしらん。レモン1箱5Euro。英国特産レモンカード、娘がレモン好きで赤ちゃんのころから生でかじったくらいなので当然大好き。買うと1壜4Euroくらいするので手作りに挑戦。レモン6個卵6個に砂糖、バターで1KGできます。安物の市販品より断然美味しいし、作り方は湯煎でひたすら混ぜるだけ。日曜に雨の中、旧市街をパレードしたので風邪をひかないようホットレモンでも、と子供の幼稚園に8個ほど寄付。本日、安物の蜂蜜を4Kg購入。はちみつレモンを作る予定。それでもまだ半分は残るので、週末はレモンパイ、あとは・・・・!?。
2007.03.22
コメント(3)
-
どらい、つヴぁい、あいんす、まいんす
さっきの日記で画像を埋め込むのを忘れました。これが現物。電脳蚤の市eBayで購入した家具。見た感じより実際には小さいです。
2007.03.16
コメント(0)
-
3,2,1,Meins
eBayerの皆様こんばんは。タイトルでお解かりのように落札いたしました。昨年の靴箱に続く大型商品。Sekretaer mit Aufsatz棚付きセクレタリーこれでピアノの上に積み上げたモノがすっきり片付くはず・・・なんだけど、逆に収納場所が増えたことに安心してモノが増える恐れもあり・・・・。そもそも最初は下宿人の部屋に机を探していたのですが、店に入ると化学薬品の匂いがして気分が悪い。きっとろくでもない薬を使っているに違いない。そうだ、ピアノの前にあるアンティークテーブル(といえば聞こえはいいが、単なる古いテーブル。)なら勉強机にしても茶を飲むにしてもお洒落でいいではないか。(本当か。)私がPCで楽譜を清書する時にピアノの上にノートブックを載せるとグラグラするのが嫌だったから、テーブルのかわりにセクレタリーか机を置いて体の向きを変えればピアノに迎えるようにしよう、と路線変更。アンティークカテゴリーで粘ること3週間。あれいいな、これは場所が遠いな、高いな、etc.沢山見て、入札しても予算オーバーして諦めていくうちに、だんだん考えが固まってきました。安く買えても送料が高く付いたら何にもならないので、自分で取りに行ける場所を条件に、ええ、一杯探しましたとも。聞いたことも無いような地名が全国にわんさか。おまけに同じ地名が複数あったり。田舎に住んでいる人ほど我が町が有名だと思い違いしているのか、郵便番号PLZ書いてくれてないし。(自分ちと番号が近かったら見当を付けやすいんです。)その度にVia Michelinで検索して、ドイツの地理に詳しくなったような気がします。(そのわりには何度も同じ街を検索した・・・。)ご予算に限りがなければピアノと同じ時代とスタイルの家具が欲しかったんですけど、いずれピアノは買い換えたいので断念。それに1880年ころの家具って、収納力の割りに異様に場所を取るんですよね。予算と機能の妥協案、中途半端なアンティークに落ち着きました。
2007.03.16
コメント(0)
-
代役おるがん@山奥の教会
代役ダブルヘッダー第一ミサ、ヘッセンの山奥Kirchhausenのカトリック教会にてプロテスタントの間借り。カトリックは10時からなので8時45分開始です。いつもの教会のある街から山へ向かって走る、・・・走る・・・・えっ、まだ走るのか・・・と心配になったころ村に到着。三代目の地図で切れている場所にある教会、絶対わかると言われたけどわからない。人を見かけたので車を止めて訊ねる。「この通りを曲がった奥。」と少々不審そうに言われたはず、Kirchstrasseというそのものの通りが目の前。やったー、迷わなかったぞ。8時15分到着。おはようございます~。おお、山奥なのに立派な教会。レッスン受けている教会よりデカイです。オルガンは祭壇に向かい合う演奏台、でも遠くてよく見えません。Vater unserで落ちた話をしてくれた女性牧師カリンに、会衆が10人しかいないから静かに弾くようにと言われました。さて、とオルガンバッグを開けると最初と最後の奏楽に弾くつもりだったバッハの楽譜がないっ!!!金曜日のレッスンの時に教会に忘れてきたんだ。ががががーん。土曜は2週間ホームステイ&レッスンに来るメゾを空港に迎えに行ったのでオルガンの練習ができず、楽譜を忘れたことに気が付かなかったのです。どうしよう、他の楽譜もあまり持ってない・・・Passionにふさわしい曲・・・Bachの超有名曲Wachet auf ruft die Stimme・・・これいこっか~。カリン「次に移動しないといけないから長い曲は無理。」カットも難しいし、じゃあ、Boellmannのゴティック組曲の最初の2ページでいこう。これは本来次の曲にアタッカで続くので余韻があり、前に弾いた時は終わりだと気づかなかった牧師が延々と待って、沈黙が30秒続いた曰く付き。「終わりっぽくないけど、こういう終わり方」と説明しておきました。最後は、咳も直ったことだし、ビゼーのAgnus Deiを弾き歌いにしよう。さて、数えてみると会衆は9人。でも力強い歌が下から響いてきます。真面目な信徒さんたち、平均年齢が高そうです。この人たちがいなくなったらミサが成立しない時代がくるのかな、と気になりました。最後のビゼーが終わったら拍手がきました。受けて良かった。(ホッ)速攻で片付けて、次の教会に移動。私の方が先に出たのに駐車場を探しているうちにカリンに先を越されてしまった。念の為にトイレに行き、(説教の途中で行きたくなると困る・・・)オルガン靴に替える。今はローファーだから簡単だけど、本格的なオルガン靴を買ったら時間がかかるなあ。どうしよう。こっちの教会は小さい建物だけど寒々しくない程度に人が詰まります。なのに、声は9人の会衆より小さいぞ。あまり歌に元気がないと伴奏が悪いのかと気になります。先週のレッスンで満タン師匠(名前がVollだから訳して満タン)に、「メロディーのキャラクターが明るいけど歌詞は楽しい内容ではないので、テンポは早く取らないでユックリ。」と注意された賛美歌、つとめてユックリ弾きましたら、会衆に追い越されました。気持ちはわかるよ~私も遅く弾きたくなかったもん。ミサの後のカフェで、いつも途中で消え、外でモク吸っているカリン曰く。「あっちの会衆は音楽的で素晴らしい。こっちは沢山いるのに歌う気がない。」素晴らしい山奥の会衆に拍手。
2007.03.11
コメント(6)
-
代役ダブルヘッダー・のだめ的ネタ
今度オルガンの仕事が入っているのは復活祭の月曜日。ゆっくり練習できると思って、のんびりHeute Triumphiert Gottes Sohnを倍速(ゆっくりの2倍)でキッチリさらっていました。(Tempoだと悲惨なことに・・・)夜中に牧師さんから電話。「Frau Mが転んで指を折ったので3月4日弾いてくれませんか。」えっ・・・・道凍ってないけど、転ぶ?まず頭をかすめたのは昨年Ceciliaさんを襲った災難。Frau Mは学生で常連の代理奏者。今日は専属?のマリオンが急遽弾くけど来週は休暇に入るとか。「できます。」ではなくて「努力します。Ich versuche es.」と言って承諾した私・・・。歌だったら2時間前とかでも平気だけど、本格的に習いだして1年ちょっとのオルガンは2日前とかはきつい。教会暦にふさわしい曲のレパートリーが増えるまでは、この状態が続きそうです。信者じゃないから賛美歌もあんまり知らないし、勉強することばかり。(復活祭にどの賛美歌が当たるかなって、今からヤマかけてるし。) 結局4日のミサは大した事故もなく済みました。ここの教会ではミサの後、となりの建物でカフェがあるのです。深~い溜息をついたら女性牧師さんが、あなたも終わったらホッとする?私もよ、と言いました。Vater Unserなど寝てても言えるような文句がフッと消えることがあるんだそうです。落ちても信者さんたちが続けて言うので、追いつくことができるけど、葬式はこわい、普段教会に行かない人が多かったりすると誰も続きを言えないから、葬式では絶対、式次第に全部印刷するのだそうです。うーん、まるで暗譜を忘れる指揮者のようだ。オケがプロ(熱心な信者)ならカバーするけど素人(葬式の参列者)だと崩壊する。「のだめ」のネタみたいです。 指を折ったFrau M、3月中は弾けない(1ヶ月くらいで治るのだろうか)ので代役が次の日曜も回ってきました。三代目初のダブルヘッダー。一回目は8時45分です。(うっきゃー)終わったら速攻で次の教会に移動。二回目は10時です。幸い牧師も賛美歌も同じ。昨年Passionの時期に弾いたので知っている曲もあり、賛美歌はどうにかなりそう。問題は最初と最後のソロ。レパートリーありませ~ん。最後を弾き歌いにするにも、咳がまだ取れません。何と一回目のミサはプロテスタントのミサ@カトリック教会なんだそうな。千人入るような広い教会でオルガンも立派で、会衆は10人・・・らしいです。
2007.03.06
コメント(2)
-
カーニバルのお菓子
カーニバルで幼稚園は半ドン、近所の店も閉まります。街の衆はどこに集まるのか疑問に思いながらボウッと過ごした昨年。今年は旧市街に仮装して乗り込みました。本日の仮装は「ドバイのお姫様」と仮装抜き「忍者」、つまり羽織を拒否した息子は刀だけ持ち歩きました。娘の中近東ドレスは母とお揃いの本物、ドバイで買いました。母もセーターとジーンズの上から着たのですが、仮装というより本物に近くなってしまったかも。ドバイで「ウズベキスタン人」といわれたもんな~。国籍不明の怪しい人にすぎなかったかも。娘は巻き毛なのでいかにもカーニバルらしく、こういう仮装は珍しいので受けてました。カーニバルといえばボンボン投げ。あまり出かけるのに乗り気でなかった双子、「あめ拾いに行こう。」と言われて渋々?着いて来たのですが、普段与えられていない飴を拾い放題、当然燃えておりました。さささっと目ざとく拾いに行く娘、ひとつ拾って嬉しそうに「ひろったー」と得意満面の息子。将来金持ちになるのは娘の方かもしれません。去年はマイナス15度だったというカーニバル、今年の気温はプラスでした。さて、カーニバルのお菓子といえばプファンクーヘン(クラプフェン)、全国的にはベルリーナーと呼ばれるジャム入り揚げドーナツです。我々はベルリン子なので(三代目は大阪生まれのベルリン子のつもりでおります。)意地でもベルリーナーとは呼びません。ハンバーガー、ヴィーナーカフェ同様、地元では全国的な呼び方をしない名物であります。(カッセルの人に聞きたいのですが、肉のKasslerってカッセルでも同じ名前でしょうか・・・?)そのプファンクーヘン、うちの近所では異様に高くて安い店で2つ1,10、徒歩圏のパン屋では1個90セントから中身がクリームだと1,50とかします。今日の午前中は幼稚園が11時30分までなので練習に行っても落ち着かないので、プファンクーヘンを作ってみました。人肌に暖めた牛乳100mlに生イースト1個(スーパーで9セントで売ってるサイコロ大)を溶かし、小麦粉(Typ405・中力)150gで種生地を作り25分発酵。それに牛乳150ml、砂糖40g、小麦粉350g、全卵2個、卵黄2個、バター50g、塩ひとつまみを加えてもう一度生地を作り25分発酵。30gを取り丸く成形、布をかけて45分置く。170度の油で揚げ、穴をあけて絞り袋でジャムを詰め、粉砂糖を振る。ジャムはベリー系の赤いものや、ベルリンのスタンダード・Pfraumenmouse。カスタードクリームを煮て仕上げに卵のリキュールを入れたもの、更に溶かしチョコを加えたもの、のクリームバージョンも作りました。(買ったら高いんだもん。)結果・・・シンプルなジャムの方が美味しかった。見た目はともかく、売っているものより美味しくできます。市販品は絶対こんなに卵が入っていないと思います。すごく簡単なので子供のいる家庭では自作する価値あり。
2007.02.21
コメント(2)
-
カーニバル
今日はRosenmontagカーニバル初日でした。幼稚園児をお持ちの在欧家庭の皆さん、お宅の仮装は何でしたか~?小さい子がかわいいのは動物系、うさぎ、ペンギン、リス・・・。個人的に大うけしたのは双子の兄弟ユリウス君とユストゥス君の「くまのプーさん」と「ティガー」でした。やっぱり双子は関連性のあるテーマが一番。娘には昨年バレエ衣裳風のテントウムシを着せましたが、他の女の子がことごとく御姫様ですので、今年は念願をかなえることにしました。しかしFasching用の衣装はぺらぺらでちゃちい割りに高い。かといって手作りする暇はなし。なので、シーズンオフに格安パーティードレスを仮装用に買っておいた母。本物の方が仮装より安いのだー。ネックレスは大人用、Wellaの景品だった。ドバイで買ったティアラもどうだっ!!これだけ決めても足元がキティちゃんの運動靴だったりする。(笑)でも、さすが女の子、普段と歩き方が違います。さりげなくルルベ。スカートの裾持ってるよ~。一方双子の息子は王様ならぬ「悪魔の大王ルシファー」、関連性はお伽噺の主役と悪役ということで・・・。彼は昨年、仮装を拒否して、悪魔の槍だけ持って行きました。(あっ、仮装しなくても悪魔は地でいけますから。)と言い訳した母であった。今年は衣装を奮発、黒いズボンに真紅の凶悪そうなマント。「・・・・Kちゃん、ズボンだけきる~。マントいや~。」プツン。・・・・どうにか説得してマントを着せ、いざ幼稚園に出陣。あれ・・・槍どこにしまったっけ。槍の捜索に10分、記憶容量の少ない母である。すまん、息子よ。カーニバル、明日に続く・・・・。
2007.02.19
コメント(2)
全153件 (153件中 1-50件目)
-
-

- 今日聴いた音楽
- ☆乃木坂46♪本日「Mステ」に出演、新…
- (2025-11-28 12:41:27)
-
-
-

- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪本日「Mステ」に出演、新…
- (2025-11-28 12:40:00)
-
-
-

- コーラス
- 町の文化祭で発表(11/10)
- (2025-11-26 21:03:53)
-