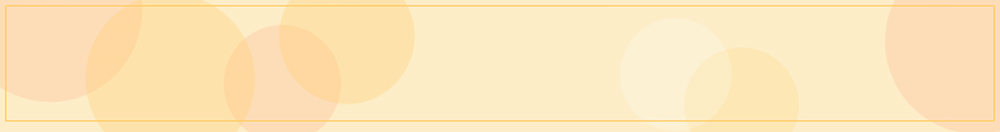-
1

ストーリーテリング「あくびがでるほどおもしろい話」
図書ボランティアの会合に出ました。今月は2回目。がんばってます! 11月に4年生全クラスを集めて行う「読み聞かせスペシャル」に向けての打ち合わせです。 テーマは「星」ということで、星に関する絵本と、星座のブラックパネルがメイン。(ブラックパネルって私はこのボランティアで初めて知ったんですが、部屋を暗くして黒いパネルに光る素材をのせ、ブラックライトという灯りをあてて見せるもので、とってもファンタジック。プラネタリウムみたいです!) ところで私の担当は、メインの読み聞かせの間にはさむ、ちょっと息抜きタイムに、「あくびがでるほどおもしろい話」(松岡享子)というのを話すこと。絵本ではなくて、ストーリーテリング。東京子ども図書館編集のロングセラー『おはなしのろうそく』シリーズに入っています。 ここから北へ北へとすすんでいったある南の国に、たいへんかしこい、ばかな男がすんでいた。ある朝、夜が明けてあたりが暗くなったので、男は目をさました。外はすばらしくよいお天気で、雨がザアザア降っていた… ――『おはなしのろうそく5』 というふうに、さかさ言葉をわざと連ねてある、おかしなお話なのです。「すまして語ること」と注意書きにあります。ぼーっと聞いていると、おかしなところも聞き流してしまいますから、子どもたちがどこで「あれこの話ヘン!」と気づくかがポイント。 「最後までだれも気づかなかったら、シーン… だね」と、一抹の不安が残るので、一度読んだあと、出だしの部分を紙に大きく書いたものを見せて、どこがヘンか探させることにしよう! と決まりました。 で、間違えずに、わかりやすく、すまして語るのが私の役目です。11月は、ひさしぶりに、緊張しそう! 絵本と違って暗記しないとだめだし。最近、記憶力に自信がないので、少しずつ練習しなくては。
September 26, 2006
閲覧総数 1720
-
2

おばあちゃんは魔女――『西の魔女が死んだ』
タイトルがなかなかすごいのですが、私はどうも「西の魔女」というと『オズの魔法使い』に出てくる西の魔女(悪役)を思い出してしまいます。でも、この物語の「魔女」はよい魔女で――というか、主人公まいのおばあちゃん(イギリス人)なのです。 ファンタジーというよりは、感受性の強い少女まいの心の目を通して見た日常、という感じです。でも思春期の少女は、自分は大人や他人とは異なるいう「強烈な「異種」感覚」(河合隼雄『猫だましい』より)を持っているので、そういう異種の目から見た現実社会は、ほとんどファンタジーなのかもしれません。 登校拒否になったまいは田舎のおばあちゃんの家でしばらく暮らすことになりますが、このおばあちゃんが「本物の魔女」だというのです。けれど、それはおばあちゃん自身が説明するように、 「身体を癒す草木に対する知識や、荒々しい自然と共存する知恵。予想される困難をかわしたり、耐え抜く力。…そういう知識に詳しい人たち…人々はそういう人たちのところへ、医者を頼る患者のように、教祖の元へ集う信者のように、師の元へ教わりに行く生徒のように、訪ねて行ったのです…そういうある特殊な人たち」 ――梨木香歩『西の魔女が死んだ』つまり、魔性の妖女ではなくて、はるか昔から共同体に存在した賢女とかまじない女とかそういう女性のことでした。 このような女性は結構いろんな物語に出てきます。たとえばポール・ギャリコ『トマシーナ』に出てくる「赤毛の魔女」ローリ。彼女は、無神論者で合理主義者の獣医と、思春期の彼の娘の心をつなぐ役目をします。 それからメリング『妖精王の月』に出てくるインチ島のおばば(「妖精のお医者」)は、妖精の呪いを受けた少女グウェンを介抱します。 学校で心が傷ついたまいも、おばあちゃんの所へ癒しを求めて滞在するのです。まいは感受性が強く繊細で潔癖で神経質ですが、これは多かれ少なかれこの年頃の女の子にはありがちな傾向だと思います。 そんなまいが、おばあちゃんから魔女のトレーニングと称して、精神力をきたえるように、それにはまず規則正しい健康な生活をするように、などと教わり、戸外で野いちごをつんだりニワトリの世話をしたりします。 そんなことが魔女の修行につながるのかしら、と思うまい。けれど、私は同じような場面をコミックスで知っていました。めるへんめーかー『夢狩人』に出てくる夢使い(これも一種の魔法使い)の修行です。 「野良仕事、トリの世話…! おれの修行ってやつはいつになったら始まる?」「これも修行のひとつよ…死や夢を扱うにはまず生を知らなくては」――『夢狩人』 そうなのです。『西の魔女が死んだ』でも、次に出てくるのは、まいが「死」を恐れ悩み、おばあちゃんが「死」について語ってくれる場面です。自分の体を動かして生をはぐくむ日々を送ってこそ、「死」についての理解も深まるのかもしれません。 おばあちゃんは死を否定的にとらえません。また、飼っていたニワトリが殺され、それとかかわってまいの生活に影を広げていく近所の「ゲンジさん」についても、否定的にとらえません。 おばあちゃんの家に出入りするゲンジさんを、まいは最初から直感的に、黒い影、不吉なもの、自分とおばあちゃんの世界から疎外し忌むべきものとしてとらえていますが、結局、ゲンジさん(の犬)がニワトリ殺しの犯人がどうかは、物語の結末になっても明らかにされません。 ここが、キリスト教的二元論ぽい欧米の物語とはちがって、何とも日本的、というか多神教的な感じがするのですが、おばあちゃん(そして最後にはまい)は、影の部分の多いゲンジさんをも、最初から最後まで受け入れています。そして、まい自身もかんぺきな存在ではなく、自分でもそれがわかっていて、 わたしの全体を知って、おばあちゃんはがっかりしないだろうか。――『西の魔女が死んだ』などと心配したりしているのです。 まいにとっては得体の知れない恐怖と影の人物だったゲンジさんも、「魔女」としてのおばあちゃんにとっては、カウンセラーの所へ相談に来るクライアント(来談者、患者)の一人だった、のだと思います。 最後におばあちゃんは死んで、それをまいは否定的でなくとらえることができ、ゲンジさんも急に良いイメージをまとって出てきます。この一件落着ぶりがちょっとできすぎというか、現実社会としては割り切れすぎているような気がしたのですが、要はまいが一歩大人になった、ということなのかもしれません。
April 30, 2006
閲覧総数 1249
-
3

少女が語る良質ファンタジー『ふしぎな虫たちの国』
本屋さんの児童書コーナーに行くとよく、なぜか気になってしかたない本があります。私を呼んでいる本、どうしても欲しくなってしまう本。この『ふしぎな虫たちの国』も、小学生のころそんなふうにして中味もあまり確かめず、ねだって買ってもらいました。 13歳の少女マリスが、別世界に入りこみ、虫や小動物と力を合わせて恐ろしい「けもの」に立ち向かい、至高の存在である「あの人たちの国」に至ったあと、現実に還ってくるというファンタジー。 こう書いてしまうと、ファンタジーにはよくあるパターンです。けれどこの物語は、別世界を徹底してマリスの視点からのみ描いていて、しかも前半では世界の構成や探求の目標などがまったく説明されません。読者はマリスと一緒に、この先何があるかさっぱりわからないまま、てさぐり状態で冒険の旅を続けてゆきます。 はじめ、マリスは不思議な石を見つけます。この石がとても魅力的。 石は、クルミくらいの大きさで、ふしぎなことに、指先でさわってみると、ビロードみたいにやわらかなの。よく見ようと思って持ち上げると、それがまた、びっくりするほど重くて、落っことしそうになりました。あたしはすっかりこの石に夢中になってしまったの。色は青みがかったこい緑色だけど、外がわだけじゃなく、中もその色なの。すっかり透明とまではいかなくて、花粉みたいな色の筋がうずを巻いたようになっていて、中のほうでなにか動いているような感じなの。 ――シーラ・ムーン『ふしぎな虫たちの国』山本俊子訳 こんなふうに、物語全部は、13歳のマリスの“語り”のような文体で訳されています。原書は知りませんが、訳者さんが少女の心をうまく表現する、それでいて現代風にくずれすぎてもいない、ちょうどいい日本語を使っていると感じます。まるで、質のいい少女漫画の独白のセリフのよう… カブトムシやイモムシなどと一緒に旅をすることになったマリスは、初めは石、のちには未来を見せる「マンティッドの鏡」を持つ者として、寄せ集めの旅の仲間(『指輪物語』や『冒険者たち』と同様です)に加わりますが、指導者になるでもなく、料理や力仕事やいろんな役割を、おっかなびっくり果たしていきます。 と思ったらいきなり「けもの」が襲ってきて仲間がさらわれ、マリスたちは救出に向かいます。けものの領域に入りこんでの救出劇も、全体の状況はなくて、マリスが見聞きし感じたものだけを語っていくので、ほんとに先が見えず、ハラハラドキドキ、もう途中で本を置くことはできません! それから、けものの捕虜だった男の子ジェットサムが登場します。野性味あふれた、でもまだ子どもっぽい彼に対し、マリスも恋愛感情とか乙女心とかは全然なく、「仲間」として接していきます。この関係も、私は好きなんです。 登場人物の年齢がもうちょっと上がると、どうしても男女の間柄に恋愛的要素が入ってきて、純粋な友情とか仲間関係じゃなくなってしまいます(それはそれでおもしろいと思えるようになったのは、私の場合、すっかり大人になってからでした)。 旅の仲間はチョウたちの国「オパールの谷」でようやく探求や使命の説明を受け、谷の宝物オパールを魔法のアイテムとして託されます。そしてキャンプを作って、いよいよ「けもの」と対決。といっても、欧米のファンタジーとしては珍しいことに、「けもの」を滅ぼそうとするのではなく、つかまえて「あの人たち」のもとへ連れ帰る(「けもの」は昔「あの人たち」から造反したのです)、というのが目標。 そこで「けもの」をおびき出して落とし穴に落とすことになるのですが、やはり最後には戦いがあります。ジェットサムは心も体もヒートアップしますが、女の子であるマリスには、体力的にもかなり苦しい場面となり、それゆえここでも全体の状況がつかめず、修羅場をさまよいます。このあたりも、いわゆる勧善懲悪の大活劇、とは趣を異にしていて興味深いです。 そして、戦いが終わり、犠牲者をとむらいます。死のおそろしさ、生命の重み、みたいなものをはしょらずそのままマリスが語っています。 …あたしの心には、失ってしまったものへの悲しみ、これまであったものがどうして今はないのだろうというあのおそろしい疑問がおそいかかって来たの。 ――『ふしぎな虫たちの国』 そして、自分がやりすぎたためか、と自責の念におしつぶされそうになるジェットサムの姿が。彼の心が救われるまで、マリスは彼を見守り続けます。 この辺りで、物語はだいたい終わりかな、と思うと、そうではありません。一行は死者と負傷者を連れて、洞窟や不可思議な景色の中を「あの人たちの山」へと登ってゆきます。マリス自身の心の奥を迷いながらたどるようなこの最後の旅のあと、神域のような「あの人たちの国」に着き、「けもの」の浄化を見届けて…ここで前触れなく霧の中をすべり落ちて、現実に戻ります。 マリスは何事もなかったかのように帰宅します。 一度、ふりかえってうしろを見てみました。…浜の向こう、ずっと遠くに、体の細い人が、向こうに歩いて行くのが見えるの。ジェットサムかしら? そうかもしれないわ。あたしは手を上げかけましたが…でもあたしは手をふらず、その遠くの人が、光る砂浜の上を見えなくなるまで、じっと見送り、その人を待っているもののところへ行かせてあげたの。 ――『ふしぎな虫たちの国』 冒険を終えた後の余韻と感傷。そして、いつもの町や家族の光景が、多くの体験をしたマリスの目にはなつかしくもみずみずしく映っているようです。これもまた、ファンタジーの効用のひとつ。 以上、思い入れもこめて長々と書いてしまいました。かなりマイナーな本ですが、荒俣宏が『別世界通信』のおすすめ本の一つに挙げています。その他には、この本を読んだ人を私は知りません。 作者はアメリカの精神科医・心理学者だそうです。あとになって私が河合隼雄の心理学にハマったのも、こんなところに原点があったのかも。
April 11, 2006
閲覧総数 918
-
4

『最後のユニコーン』出版から50年ーー赤い牡牛やハーピイのこと
このブログでもご紹介したファンタジー『最後のユニコーン』の研究をなさっている、黒田誠さん(和洋女子大准教授)から、先日(といっても2ヶ月ほど前)、コメントをいただきました(!)。 黒田先生によりますと、『最後のユニコーン』は今年、出版から50周年 これを記念して、アニメ『The Last Unicorn』関連の展示会や講演会が行われたそうです(残念ながら関西の私は行けなかったのですが…)。 さらに、「ビーグル、トップクラフト研究推進委員会」が設立され、今後もシンポジウムの開催などが計画されているそうです。 (トップクラフトというのはジブリの前身とされるアニメ制作会社で、『最後のユニコーン』のほかにも、バクシ監督のアニメ『指輪物語』の続き(私は観ていませんが)を作ったりしています。) 講演会の資料をいただいて読んでみますと、『最後のユニコーン』に出てくる悪役「赤い牡牛」(レッド・ブル)に関する考察や、アニメ版にのみ登場するカラスの意味するもの、など、興味深い話題がいっぱいです。 それで、久しぶりに原作を読み返してみました。 主人公ユニコーンに対する敵役「赤い牡牛」は、何度読んでもすごく強烈な印象で、そのくせ最初から最後までつかみどころのないキャラクターです。 これは黒田先生のブログへコメントさせていただいた中にも書いたのですが、ユニコーンが存在感があり、登場当初から細かに描写されて、シュメンドリックたちや読者の愛・憧れを受けていくのと対照的に、 赤い牡牛Red Bull は名のみ明かされ、なかなか登場せず、やっと登場したと思ったら幻像のように不気味に実在感がなく、動作も不可解。あとの城の場面でも長らく気配のみで詳細は不明。それなのに、いや、不明だからこそよけいに読者をふくむみんなの恐怖感をあおるのです。 訳者あとがき(by鏡明)を見ると、作者に物語のインスピレーションを与えたのは、一角獣と牡牛が戦っている絵だそうで、だとすると牡牛にはもっと具体的な描写(存在感)があってもいいのに、と思うのです。 でも、詳細があいまいだったり実在が疑われたりする方が、よりミステリアスで怖い、ということもあります。決まった形のお化けが必ず出てくるつくりもののお化け屋敷より、お化けの噂だけがある荒れ果てた廃屋の何もない空間のほうがよほど怖いということです。 大きさも実在性も出自もあやふやな「赤い牡牛」は、矛盾するいくつかの噂だけだからこそ、いっそう皆の想像力をかきたて、怖いのでしょうね。 ユニコーンの白と、牡牛の赤。そんな対比も、強烈です。しかも、白は白でもユニコーンの白は月夜の雪の白。牡牛の赤は、古い血(静脈血)の赤。どちらも年を経て古く、不変/普遍な感じがします。 もう一つ、いま前半を読んでいて印象的なのが、「黒」を意味する名を持つハーピイ(人面鳥)のセラエノ(ケラエノ)です。ギリシャ神話に出てくる怪物で、牡牛とは別の形で、ユニコーンの対極として登場します。 私の感じるところでは、ユニコーンが月のよう(彼女の描写には月がよく使われています)だとすれば、ハーピイは蝕(日食とか月食とかの「蝕」)の魔物です。日食や月食は、太陽や月を魔物が食べてしまう/覆い隠してしまうから起こる、という神話伝説がよくあります; 日輪を喰い銀輪を屠るもの ーーあしべゆうほ『クリスタル・ドラゴン』 日蝕(エクリプス)が栖(す)から跳びだし、黄金の鞠〔=太陽?〕に躍りかかると前足でそれを捉えた。 ーーロード・ダンセイニ『ペガーナの神々』荒俣宏訳 空を飛ぶもの(鳥)であり、「翼で空を暗くさせ」たり月を隠したりまた出したりしているところからも、また不気味に髪の毛や翼が光っているところ、ユニコーンと対になって「連星」のようにぐるぐる回るところからも、セラエノは天空の闇の精エクリプス(蝕)で、月の精であるユニコーンのライバルだなと思うのです。
April 15, 2018
閲覧総数 1088
-
5

『哲夫の春休み』斎藤惇夫の時をさかのぼる新作。
『冒険者たち――ガンバと十五ひきの仲間』の斎藤惇夫氏の新作、という新聞広告を見てびっくり、慌てて購入しました。処女作『グリックの冒険』が1970年、次の『冒険者たち』からかなりの年月を経て『ガンバとカワウソの冒険』が出たのが1982年でした。3作でガンバや個性的な彼の仲間たちはかなり描きこまれた感があり、しかも最後のテーマが相当重いものだったので、読者の私としても“完結した”気持ちがしていました。 でも、作家は(いや人間はみな)新しい分野にチャレンジしていくものなのでしょう。ロフティングが「ドリトル先生」シリーズをいったん終わらせ(るつもりになっ)たあと、ジャンルのちがう『ささやき貝の秘密』を書いたように、斎藤さんもまた別の物語を語りはじめようとしていたのだそうです。 それが28年後の今年ようやく出版された、というのです。 ところで、『冒険者たち』の冒頭には、「哲夫と竜太に贈る」という著者の献辞があります。だから私は新作のタイトル『哲夫の春休み』を見た時も、知らない人でありながらなつかしい「哲夫」くんに、数十年ぶりに再会したような気がしました。 物語は小学校を卒業し中学になる前の春休み、哲夫くんが父の故郷へ一人旅をするというもの。子供時代を終えたけれど、大人世界の住人にはまだなっていない、若者の旅。彼の目の前に開ける広い時空。それは、以前私がこのブログでとめどなく垂れ流していた『冒険者たち』シリーズに共通するイメージと重なっていて、ガンバの物語でなくてもこれはやはり斎藤さんのお話なんだなあと思いました。 折しもちょうど今年の夏、『児童文芸』誌上に、私がブログをまとめたものがひっそりと掲載されたもんですから、何てタイムリー!と個人的に盛り上がってしまいました。 哲夫くんの旅は、ガンバというよりは、「ぼくのほんとうのうち」である北の森を目指すシマリスの旅(『グリックの冒険』)により近いものがあります。哲夫くんは列車の中や長岡の町で、父の子供時代、若者時代にタイムスリップを繰り返します。それもそのはず、哲夫くんは作者の息子さんであり、作者は息子の姿や心を借りて、この物語の中で自分のふるさとと人生とをたどりなおしているのです。 だから、哲夫くんが歩いている道の風景がいつの間にかふっと過去のものにだぶったり、昔の人物がそのまま自然に現在の人物につながったりします。 そのオーバーラップの容易さは、典型的なタイムスリップもの(たとえば『トムは真夜中の庭で』)のように、現在と過去がはっきり分かれていて境目を超えるのに何か儀式(時計が13時を打つとか)が必要な物語とは、夢の本質が違うことをも示していると思います。 つまり、哲夫の行き来する過去の世界は、まだ完結していないのです。過去は、現在の登場人物ひとりひとりに何かしら影響を及ぼし、封印してきた思いを解き放つようにと働きかけています。過去をもう一度体験するというタイム・ファンタジーを通して、その解放が為されると、最後には癒しが訪れます。 つらい思い、未消化な思いがそうやって解き放たれ癒されて、はじめて人は前へ進むことができる。逆に言うと、将来へ向かっていくためには、過去をときほぐす必要があるというわけです。 『グリックの冒険』でも、吹雪の中で立ち往生した時、ヒロインののんのんが死んだ母の思い出を語ります。グリックはそれを聞いて、夢うつつにその話を反芻し、やがて再び立ち上がって旅を続けるのです。 同じように、哲夫くんも彼と知り合った人々も、過去の再体験によって未来へと踏み出す力を得、物語は前へ向いて終わります。 と、こんなふうにこの物語を一気に読み終えて、あとがきを読んだ時、私は初めて、斎藤惇夫氏の息子の哲夫さんが2年前に亡くなったことを知りました。私とほぼ同世代で、『冒険者たち』の献辞でその名を見て以来、まるで知っている人のように私が感じてきた哲夫くんは、お父さんを残して先に旅立ってしまっていたのです。 現実の哲夫さんが逝ってしまった後、作者の心の中で20年以上も眠っていた12歳の哲夫くんがようやくふるさとへ、時をさかのぼる旅に出たのです。それを知ると、今度は、この物語はお父さん自身の心の旅であると同時に、やはり哲夫くんの旅――父惇夫氏の心の中の哲夫くんの旅でもあるということが、わかりました。 そしておそらく、時をさかのぼる旅をやりとげる=この物語を書きあげるということで、作者の心も癒されたのだろうと思います。 この物語の舞台であり斎藤惇夫氏のふるさとである長岡市は、私の母方の祖母の故郷でもあります。子供のころ疎開していたという母と一緒に、私も若い頃、見知らぬふるさとである長岡を訪ねたことがありました。哲夫くんのように、タイムスリップはできなかったですが・・・
December 3, 2010
閲覧総数 2477
-
6

『勇者の剣』――ネズミの本のベストセラー
ネズミ年なので1月にはネズミの本を読もう!と思いましたが、読み終われずとうとう2月になっちゃいました。イギリスのベストセラー「レッドウォール伝説」シリーズの第1巻『勇者の剣』です。 邦訳された当時からとても気になっていた本でした。・イギリスの人気ファンタジー・ネズミが主人公の冒険活劇・時代モノの大長編と、私の好みの条件が揃っていたし、荻原規子などの長編ファンタジーを次々に出している徳間書店のイチオシだったからです。 それなのに、今まで読まずにいたのはなぜか? それは、こんな書評を目にしてしまったからです。 「正直に言えば同じネズミ達が恐ろしいイタチを相手に活躍する斎藤惇夫氏の『冒険者たち~ガンバと十五匹の仲間』の方が重く、ネズミ達の個人個人も深くそして内容もリアルで展開が読めないためどきどきさせられた。」 ――某ネットショップのレビュー、kazeiさん。 この一文が私には百のほめ言葉を上回って決定的だったので、書店でも図書館でも『勇者の剣』を手に取りませんでした。ガンバに劣る=読む価値無し!という独断と偏見の判断です。 ですが、とうとう読みました。うん、悪くない。なるほど人気の出そうな作品です。善玉は清く正しく美しいし、悪玉は極悪非道・冷酷無比の血なまぐさい独裁者です。誰もがレッドウォール修道院を守るためにがんばる主人公マサイアス(修道士見習い)に声援を送り、敵に囲まれはらはらどきどき。 場面展開もてきぱきして、長編にありがちなだらだら感は感じられず、謎解き、城攻め、探索、異種族との出会い、最後の一騎打ちなど、ファンタジーや冒険活劇のツボを押さえたエピソード満載です。長編アニメにしたら、楽しそう。 でも、先入観のせいか、いくつか気になる点もありました。 まず、舞台設定です。人間はどこにいるのか? レッドウォール修道院は、ネズミの修道院なのです。じゃあネズミが建てたのか? にしては、人間の建物にそっくりなんです。でも人間はいないみたい。他にも、石切場とか農場とか、これらは人間の廃墟なのでしょうか? それから、修道士たちがたくさん出てくるのに、お祈りをしません。ネズミだからキリストを拝まないのなら、ネズミの神様とかに祈るんじゃないのかしら。宗教的なものを(多分作者が意図的に)いっさい排除した“修道院”や“修道士”って、何か変な気がします。伝説の戦士マーティンは尊敬されていますが、まさかマーティンをまつった神社じゃあるまいし。 神様が出てこないので、レッドウォール修道院が精神的に何をよりどころとしているのか、不明です。それなのに、最後に院長は主人公マサイアスを修道士とせず、戦士となって妻を持つようにと言います。つまり、修道士は結婚しないとかいう戒律だけはあるみたいなんですね。 (これらの疑問点は、もしかすると続巻を読めば説明されているのかもしれません。続きも人気の高い作品のようなので、そのうち読もうと思います) 対する悪の権化、ドブネズミ「鞭のクルーニー」。なかなか恐ろしげに描かれていて迫力満点ですが、ガンバに出てくるイタチのノロイと比べてしまうと、どうも暴力的で美しくないぶん、格下なんですね。 思い直してみると、『冒険者たち』はあれだけのすさまじい緊迫感を持った戦いながら、残虐シーンはほとんどないのです。ノロイは悪の権化ですが、外見にも中身にも一種の美意識が感じられます。 奇っ怪な仮面をかぶりカブトムシの角をかぶとにつけ、毒針を仕込んだ尾をふりまわすクルーニーも、それなりの美学?なのかもしれませんが、どうもがさつで品がありません。いじめられたりなぶり殺しにされる部下たちの死にざまも、悪趣味。ノロイよりも、『ウォーターシップダウンのうさぎたち』の悪玉ウーンドウオート将軍に近いものがあります。 ただ『ウォーターシップダウン』の良さは、野生動物の本当の生態をもとに描かれているため、流血の戦いや死傷する場面にも、陰湿な残虐性は(まったくとは言えないけれど)あまり感じられない点。 『勇者の剣』でも、もう一人の最強最悪の敵、毒蛇アズモデオスには、それほど反発を感じないのは、クルーニーと違って蛇は蛇の生き方を守っているだけにすぎないからかもしれません。 ともあれ、若僧だったマサイアスは、謎を解き、スズメやトガリネズミなど異種族を味方につけ、毒蛇を倒し、伝説の剣を手に入れて、立派に成長します。そして、死闘のすえ、最後にクルーニーを倒すと、レッドウォール修道院に平和が戻ります。めでたしめでたし。
February 4, 2008
閲覧総数 752
-
7

PPMの「♪パフ」が絵本に!――『魔法のドラゴンパフ』
♪Puff the magic dragon lived by the sea And frolicked in the autumn mist in a land called “Honah Lee”・・・ ♪パフ 魔法の竜が暮らしてた 海に秋の霧たなびくホナリー ・・・ (野上彰訳) PPMの名曲「パフ」がCD付き絵本として出ているのを、今日、本屋さんで見つけました。『魔法のドラゴンパフ』、訳はさだまさし。 PPMというと70年代のフォーク・グループの大御所で、私も大好きなんですが、中でも「パフ」は中学校の音楽の教科書に載っていたこともあって、歌詞を一生懸命覚えました(原詩もわりとやさしい英語です)。現在では小学校で習うらしく、息子も(私が習ったのとは違う日本語の歌詞で)歌っていました。 物語調のこの歌、どうやって誕生したかには色々ナゾもあるらしいし、麻薬でトリップする歌だとか、反戦歌だとか、世間の批評もさまざまだったとか。でも私は純粋に、ジャッキー少年とステキな竜のファンタジーだと思いたいです。 ジャッキーとパフのコンビが海をゆくと、王様や王子様さえお辞儀をし、海賊たちも旗を下げた、というくだりが特に好きで、王様よりも海賊よりも“すごいやつら”である二人の得意そうな様子が、目に浮かぶようでした。 歌詞の後半ではジャッキーが大人になって竜と遊ばなくなり、竜がしょげてしまったというちょっと寂しい(苛酷な)状況が歌われています。すばらしき子供時代は必ず過ぎ去ってしまい、二度と帰らない。不死の竜パフはその象徴なんですね。子供は大人になってしまうけれど、子供時代の楽しかった思い出は永遠に生き続けるのでしょう。 そう思うと、『くまのプーさん』のラスト、魔法の丘で永遠化されるプー(=クリストファー・ロビンの幼年時代)なんかを思い出したりします。 ところで、今回の絵本には、さらに後日談というか、オチがついていました。以下ネタバレですが、ジャッキーが去ってずいぶん経ってから、今度はジャッキーによく似た女の子がパフのところへやってくるのです。そして再び黄金の子供時代がよみがえります。 なるほど、こうやって親から子へ、世代から世代へと、すてきなファンタジーが受け継がれてゆくというのは、一つの理想形ですね。 2番目の画像はむか~し私が描いてみたパフ&ジャッキーです。パフ太りすぎ・・・
March 19, 2008
閲覧総数 2999
-
8

『わんぱくだんのたからじま』――ビー玉の中の海
ほんとの海賊の物語『宝島』は怖くて血なまぐさいんですが、ここからロマンと冒険のエッセンスを借りているお話は、たくさんありますよね。 ゆきのゆみこ・上野与志作、末崎茂樹絵の「わんぱくだん」シリーズの初期の1冊、『わんぱくだんのたからじま』もその一つ。 けん、ひろし、くみの仲良し3人組が公園の砂場で海賊ごっこをするうち、ほんとうの海に乗り出して宝島へ行くお話で、エノコログサで作った船長のひげ、まるめた紙の望遠鏡、ダンボールの船、砂でつくった怪獣などが、別世界では生き生きとしたホンモノになって動きだすところは、ファンタジーの典型的な展開です。 中でも、お話をつらぬくステキな魔法のアイテムは、青いビー玉。 いつのまに はいっていたのでしょう。 くみのおもちゃばこに、みたことも ない あおい きれいなビーだまが はいっていました。 ビーだまの なかを のぞくと、ちいさな しまが うかんで みえました……。 ――ゆきのゆみこ・上野与志作、末崎茂樹絵『わんぱくだんのたからじま』 まるで映画のイントロみたいな、わくわくする始まり方です。 昔からあるおもちゃの小物の中でも、ビー玉は、その重さといい透明な美しさといい、何か特別大切な感じがしませんか。 色もさまざまで、ただ一色のものもありますが、中にはこの絵本のビーだまのように、真ん中に紡錘形の模様がちょっと立体的に見えるものもあって、透かしてみるとそれは何だか宇宙とか世界とかそんな球体の中に浮かぶ陸地のようにも思えたりして・・・ 出自の分からない魔法のビー玉を、砂場に作った「たからじま」の「たからもの」として置いた瞬間、主人公たちは別世界へトリップします。そして、ホンモノのたからじまで宝=ビー玉を掘り当てた=再発見した瞬間、またもとの世界へ戻ってくる。 ビー玉は別世界への扉として、彼らにとって本当の「宝」なのです。 この絵本を読むと、思わず自分も手持ちのビー玉(もしあれば中に模様の見えるヤツ)をのぞきこんでみたくなる、すてきなファンタジーです。
July 7, 2007
閲覧総数 421
-
9

ホフマン『黄金の壺』――愛の幻想
前々回にアイルランドの『小人たちの黄金』を再読しましたが、小人がお宝をためておく黄金の壺というアイテムは、ヨーロッパ共通のものらしく、ドイツ・ロマン派のE・T・A・ホフマンにもずばり『黄金の壺』というタイトルの幻想物語があります(絶版です)。 以前ホフマンの『ブランビラ王女』の日記では書き漏らしましたが、この人、「くるみ割り人形」(チャイコフスキーのバレエ)の原作者でもあるんですね。 200年近く昔の作品ですから、文章は(訳文で読んでも)古風でまわりくどいところもあります。しかし気にせず進んでいくと、実は少女漫画かライトノベルにもできそうなキャラクターが、甘くてちょっとコミカルなストーリーを展開しています。 主人公は、何をやってもドジってしまう貧乏学生アンゼルムス。素直でまじめだけど夢見がち、周囲からういている。物語冒頭でも、お祭の日に屋台につっこんで、積んであったりんごをばらまいてしまい、店のお婆さんにさんざんののしられています。 ところがそのすぐ後に、川のほとりで彼は不思議な体験をするのです。緑色にきらきら光る小さな蛇がクリスタルの鈴の音のような声で愛をささやく・・・何だか唐突な気もしますけど、これが彼の運命の出会いなんです。 あとで分かりますが、蛇は美しい乙女の化身で、名前はゼルペンティーナ。なんとハーレクイン小説的に魅力的な名前でしょう。主人公アンゼルムスは世俗的にはうだつがあがらないけれど、純粋無垢な性格ゆえに、彼女に選ばれたのです。 しかし、世間の人はそんなアンゼルムスを精神的に病気なのだと思い、馬鹿にしたり警戒したりします。クリスタルの鈴~などと口走る彼の、就職を心配した教頭先生が、古文書の筆写の仕事を紹介してくれ、彼は王室文書管理役リントホルスト氏の家を訪ねます。 最初は、玄関のノッカーに魔女(祭の日のりんご売り)の顔が現れて呪いの言葉を吐くので、アンゼルムスはぶっ倒れ、あわや失職するところでした。(余談ですが、ディケンズの『クリスマス・キャロル』にも、亡霊の顔がドア・ノッカーに現れますが、欧米ではノッカーはそういうアイテムなのでしょうか?) ようやく回復して仕事場を再訪すると、そこは奇妙な屋敷で、熱帯植物園のような庭や風変わりな家具があり、オウムが話しかけてきたりします。リントホルスト自身も突然ファンタジーな服装になったり指先から炎を出したり、ただ者ではありません。 実はリントホルストこそ、蛇乙女ゼルペンティーナのお父さんなのでした。しかも彼は実は実は“火の精”で、アトランティス王国の廷臣だったのが、百合の花から生まれた緑蛇と禁断の恋をしたために罰せられ、人界に落とされて人間の暮らしにあまんじなければならないというのです。しかし、 人類が堕落してしまって、自然のことばが通じなくなり・・・(中略)・・・そんな不幸な時代がおとずれたら、火の精の火は、また燃えあがるのだ。 ―――ホフマン『黄金の壺』神品芳夫訳 というアトランティス王の予言があり、まるで、来るべき大いなる時まで眠り続けるアーサー王や英雄たちのように、火の精リントホルストも本性を眠らせたまま、ドイツの片隅で文書管理役などをやっているというわけです。 リントホルストにはゼルペンティーナを含めて三人の娘(お母さんが蛇ですから、娘もみんな蛇)がおり、それぞれに純粋無垢な夢見る人間のお婿さんが見つかれば、アトランティスの楽園に帰れるんだそうです。 時空を越えたロマンですねえ。・・・でも何だかおとぎ話にしてはご都合主義っぽい理屈ですが、まあとにかく、アンゼルムスは栄えあるお婿さん第1号に選ばれたということです。 その後、教頭先生の娘との世俗的な恋に目がくらんだアンゼルムスが瓶にとじこめられるという波乱がありますが、これも恋愛ものとしてはお定まりのライバル出現!てな感じで。 結局、娘は別の男と婚約し、敵対勢力の魔女も打ち負かされ、アンゼルムスはゼルペンティーナと結ばれて、めでたくアトランティスに行ってしまいます。 この時、二人の永遠の愛のあかしとして示されるのが、昔アトランティスの地霊が予言成就の助けにとリントホルストに贈った「黄金の壺」。タイトルになっている割には、この壺がストーリーに何か影響を及ぼすことはありません。ただ現世を超越した世界のすばらしさ・完璧さを象徴しているだけかも? ともあれ、現実界ではドジでだめ男のアンゼルムスは、愛ゆえに現世を解脱してアトランティスの詩人になりました。お婿さんが3人揃ったら火の精復活で何か現実界へも新たなアプローチがあるのかもしれませんが、その時まで、彼は蛇姫と黄金の壺とともにアトランティスに行ったきり、現世には戻ってきません・・・ それでホントにいいのかアンゼルムス? とつっこみたくなる気もしますが、多分これで十分なんでしょうね。
August 2, 2008
閲覧総数 422
-
10

ネシャン・サーガ1巻『ヨナタンと伝説の杖』
もはや「近ごろの」作品と言えるかどうか…、「ハリポタ」と同時期の作品です。私は1巻だけしか持っていません。 トールキンの『指輪物語』の成功以来、欧米では異世界ファンタジーが雨後のタケノコのように出版され、いくつかは“指輪物語を超える”みたいな帯文句とともに邦訳が出ました。しかし、ファンタジックな異世界を舞台にした若者の成長物語が多く、似たり寄ったり。 それはそれでいいのですが、たとえば『石と笛』、ドラゴンライダー・シリーズ、グウィネド王国、リフトウォー・サーガ、ファーシーアの一族、ベルガリアード物語、力の言葉、他にもタイトルが思い出せないあれやこれや・・・みんな1巻目はまあ面白く読んだのですが(『石と笛』は全部読んだし、リフトウォーも何巻も読んだ)、続きを買いたいと思うほどではなく、今となってはどれがどれやら。 つまり、王道の異世界&成長物語に何かプラスアルファがないと、インパクトが弱いということなんです。 ハリー・ポッターが(私はあまり好かないですけど)、さすがに強烈に印象に残るのは、学園モノとの絶妙のカップリングだと思います。魔法や修行をする主人公は定番ですが、そこへ現代に通じる学園生活を持ってきたのは、アタリでしたね。 で、やっと『ヨナタンと伝説の杖』です。異世界の分身の冒険を夢に見る、車椅子の少年という「枠」の設定が、この物語の個性的な特徴でしょう。 それから、キリスト教。これはクリスチャンでなければ日本人にはとっつきにくいですね。異世界の成り立ちのベースにキリスト教の原理がはっきりとあって、C.S.ルイスの「ナルニア」でもそうですが、この部分が受け入れられないと、楽しんで読めません。 私は現実世界では、車椅子のジョナサンとおじいさんとの心の交流に心温まりましたし、異世界ではヨナタンと友人ヨミの会話や雨林の住民ディン=ミキトの一風変わった生活も楽しかったです。しかし2つの世界のかかわりがよくわからないまま、1巻は終了し、以下2・3巻ネタバレ→ ジョナサンがネシャンの方へ行ってしまったままになってしまうのが、以前とても残念でした。 せっかく枠設定を最初にしっかりと持ってきているのに、それはキリスト教とネシャン世界をつなぎあわせるための導入という意味だけだったんでしょうか? うーん。 そういえばナルニアも、ラストはほぼみんな現実世界で死んでナルニアに来て、本当のナルニア(天国)へ行っちゃうところが、どうしてもなじめなかったのですが、つまり、ファンタジーの重要な機能としての現実世界へのフィードバックというのがないからなのです。 結末が分かって再読すると、1巻のジョナサンが切ないのです。祖父はジョナサンがまた元気になる日を信じていたでしょうに・・・。主人公が、自分で選んだのかもしれないけれど、天に召される的に異世界に参入してしまう大団円は、うーん。俗な感覚では理解し得ないのかもしれません。そのうーんを埋め合わせる感じの3巻の派手な異世界ハッピーエンド、なんていう言い方は、よくないんだろうなあ、と思いつつ。
June 29, 2018
閲覧総数 603
-
11

おんな「アーサー王物語」!――『アヴァロンの霧』
マリオン・ジマー・ブラッドリーの、読み出したらやめられない大河小説です。 井辻朱美はこの物語のことを「武勲の書『アーサー王物語』を『源氏物語』にしてしまった」と書いていますが、王朝恋愛モノというよりはむしろ、アメリカ版・橋田壽賀子「おんな太閤記」と言う方がぴったりだと思います。 つまりこの話は、騎士道・戦い・キリスト教がテーマの、男性的な英雄アーサー王の伝説を、探索も戦いもしない女性キャラの立場から、そして、父権的な一神教であるキリスト教ではなく、母権的な多神教(ドルイド教)の立場から、徹底して語っているのです。 「まさか! たった一人の神がすべてを治めることができるなんて!」 … 「キリスト教徒はこう信じているのよ…女神なんていないんだって。女の体現する原理は悪の原理で、悪も女を通じてこの世に入ってきたんだって」 … 「人が運命の過酷さに絶望し、天国に導いてくれるキリストにひざまずくようになるのをキリスト教徒は願っておるのかもしれんな」 ――「アヴァロンの霧」第1巻『異教の女王』岩原明子訳 ・・・こんなふうに作者は、キリスト教文化圏外の日本人が読んでもタジタジとなるようなキリスト教批判を、随所で登場人物に語らせます。 そしてまた、伝説の英雄たちも、作者にかかるとみんな、いかに姿が立派でも武勇にすぐれていても、中身は人間くさい男でしかありません。騎士道のスーパーヒーローというべきラーンスロットは、優柔不断な優男。アーサー王でさえ、主人公の妖姫モーゲンから見ると、いくつになっても世話の焼ける小さな弟。 女性たちも、騎士道で賛美される理想的なお姫様ではなく、ひとりひとり違う性格に応じて悩んだり苦しんだり、仲良くしあったりねたみあったりしながら、家族や客をもてなし、糸を紡ぎ、おしゃべりし、子供を産み・・・つまり人間として生活していく様子が語られます。 そして、タイトルにもある、すべてを覆う「霧」のように、ドルイド教世界の神秘と魔法が物語を包んでいます。 全編にフェミニズムの匂いがぷんぷんしていますが、それを上回るストーリー展開の面白さ、5世紀イギリスの歴史的背景の描写、リアルな神秘体験の記述がすばらしく、読み始めたら寝不足確実な大長編です。
December 11, 2006
閲覧総数 531
-
12

『フィオナの海』――ケルト版“羽衣伝説”
今日はセント・パトリック・デー(アイルランドの守護聖人の祝日)なので、アイルランドな映画を観ました。・・・と言ってもだいぶ昔に衛星映画劇場を録画したものを家で観たんですけど。映画館で観たのは、十年ほど前のアイルランド映画祭でした。 原作はスコットランド北西部の孤島が舞台のようですが、映画ではアイルランド北西部という設定になっています(原題「ローン島の秘密」)。 主人公の美少女フィオナ(オーディションで選ばれたそうです)があんまり可愛すぎて、周囲の深みのある俳優たちや辺境の海辺という舞台の中ではちょっと浮いているかも?ですが、演技はナチュラルでステキ。 フィオナの一家は一族が長くくらしてきた孤島を捨てた時、赤ん坊だったフィオナの弟を失います。弟は、アザラシの精(セルキー)の血を引くとされる黒髪で、ゆりかごごと海にさらわれたのです。 やがて本土の海辺で暮らす祖父母のもとにひきとられたフィオナは、弟が生きているのではないかと思い始めます。島に遊びにゆくと昔の家には今も誰かが居るような形跡があるし、アザラシとともにゆりかごを船のようにして海を漂う子供を見たという噂も聞こえてきます。 人々が去った無人島の景色が、目にしみるほど静かで美しく、昔旅したアイルランド西部のアラン諸島を思い出させます。 海や霧、岩や草原など荒涼とした自然の中で昔ながらの暮らしを営む人々、彼らと生き物たち(アザラシやカモメ)の交流などが、今も生き続ける伝説に、リアリティを与えています。 その伝説というのが、日本の羽衣伝説にとてもよく似ているのです。もっと広義でいうなら、異種女房譚(人間の男と人外のものとの結婚、その血をひく子孫たち。河合隼雄『昔話と日本人の心』より)。 ケルトの伝説には、妖精や精霊と人間との交流はよく出てきて、 黒髪の者には妖精の血が混じっているのだそうな ――あしべゆうほ『クリスタル・ドラゴン』 などと言われますが、一説によるとケルト人(紀元前にアイルランドやイギリスに移住)よりももっと古い土着民が黒髪だったようで、そういう先住民がのちに精霊とか妖精になって記憶されたのかもしれません。 フィオナの親戚である黒髪のタッドが語る、一族のルーツの物語によると、彼らの先祖に、アザラシの精である娘と結婚した男がいました。彼は、アザラシが皮をぬいで美しい娘の姿になるのを目撃して、一目惚れし、皮を隠したのです。 二人は結婚して何人か子供も生まれますが、ある時、上の子供が母に尋ねます、「お父さんはなぜ古い皮を大事に隠しているの?」この言葉で、アザラシの皮の存在を知った母親は、すぐさま皮を取り戻し、アザラシの姿に戻って海に去っていってしまうのです。まるで、羽衣を取り戻した天女のように。 日本人である私が、アザラシの精を祖先に持つこんな話を聞くと、昔話が新たに生き生きとよみがえったような、妙な気持ちを味わいます。 そういえば、アイルランドには、浦島太郎そっくりの伝説(妖精の美女に連れられて海の向こうの楽園にゆき、戻ってくると何百年も経っていたというオシアンの話)もあります。 ユーラシア大陸の東の果てと西の果て、二つの島国には、不思議な共通点があるんだなあ、と思いながら、映画を観て、久しぶりにアイルランド気分に浸りました。 原作もぜひ読んでみたいものです(矢川澄子の訳だし)。
March 17, 2008
閲覧総数 1049
-
13

新しいパソコンが来ました ほか
とうとう買い換えました! といってもまだこの日記は古いので書いています。 XPから7にしたので、新しいのに慣れるまでだいぶかかりそうです。その間、2つになってしまったPCをどこに置くか、それが大問題。 私の部屋は無秩序に増加する本や、未整理の子供の写真、古い服などでいっぱい。 部屋を整理してから新しいモノを買うようにしないといけないのですが・・・ で、またまた日記がとどこおっております。 最近読んだ本のメモ: やっと届いた『バムとケロのもりのこや』。私にしては速攻で注文したのに、届いたのは第2刷でした。相変わらず楽しい絵本です。本に付いているバーコードから出版社のサイトのフリー画像を携帯にいただきました。待ち受け画面にすると、島田ゆかさんの絵の色合いがいかにキレイか、よく分かります! 前回の日記にとりあげた本の続き、『女騎士アランナ2 女神に守られて』。まあまあですね。男装して騎士の修行をしているアランナは、恋なんかしないわ!とつっぱって頑張っていましたが、そのわりにはこの巻であっさりと王子と恋人同士になっちゃいました。まあ、周りにすてきな男性がいっぱいいるから、予想通りの展開ですけど。 原書に挑戦『霧のラッド』(Lud-in-the-Mist)。でもやっぱり挫折かも。翻訳を何度も読んで話が分かっているので、ついつい面白いところだけとばし読みしてしまいます。 雪どけの季節から始まる、わたりむつこ『はなはなみんみ物語』。今度、感想を書きたいです。 あと、最近の噴火さわぎの影響か、珍しく夫が石黒耀『死都日本』という本を知人から借りて、私のところへ回してきました。宮崎の火山が大噴火したら、というパニック小説らしいです。何だか怖くてまだ読み始めていないんですが・・・
February 21, 2011
閲覧総数 32
-
14

戯言シリーズの「いーちゃん」て実は作者だと思う
この夏『零崎曲識の人間人間』につづき、娘が借りてきた「人間シリーズ」をおおかた読んで、とくに『零崎人識の人間関係(戯言遣いとの関係)』読後に思ったんですが、とかくナゾの多い主人公「いーたん(いーちゃんと言うより私はこちらが好き)=戯言遣い」は、物語世界での作者西尾維新さん本人ですね、きっと。本名も、NISIOISINに1~2文字加えたものじゃないかしら。ほら、一般人の俊希(としき)が殺人鬼になると人識(ひとしき)という名になったように・・・ って、「戯言シリーズ」本編未読で、西尾維新の他の作品群もまるで知らないのに、断言的な書き方をしてしまいました。でも、読んでいて直感的にそう感じましたから、そう感じさせる要素があるということですよね。 いや、ここまで書いて、まるでハズレだったら笑って終わりますけど。 ていうか、私が知らないだけで、いーたん=作者説なんてのは、この作家の愛読者の人たちには定説?の一つなのかもしれませんが。以下ネタバレ少々。 この物語はタイトルに「戯言遣いとの関係」とあるのに、ストーリー本筋には二人の関係がまったく出てきません。殺人鬼人識が起こした「京都連続殺人事件」のあらましが語られるだけです。いーたんは、警察の事情聴取でちらりと登場しますが、死人のように無反応・無感動で、その無のオーラが常識人の刑事をびっくりさせます。つまり、彼は常識外ってこと。 住んでいる骨董アパートも、一種空間がゆがんだエアポケット的場所に思えます。 このシリーズ世界は、前にも書いたように、すべてを仕組み操ろうとする立場の人物が居て、その代表が西東天(どうもこの姓は私に、俳人の西東三鬼を思い起こさせます)ですが、この人は因果の外にあって物語世界を壊そうとして壊せず、世界終焉のキーパーソンをいーたんである、としています。 人外魔境な登場人物が次々出てくる中で、いーたんは一見ごく地味な一般常識人(自分の興味が向かない世界への無反応も無感動も、世の若者の常とも言えるでしょう)なのに、なぜ物語世界構造のキーパーソンなのか・・・なぜ彼の存在や言動が周囲の調子を狂わせるのか・・・それはやっぱり実は彼が作者だからなんじゃない? いーたんの本名がわざと明かされないのも、◎のついた服を着ているのも、作者の「実は私ですよ」というマーキングじゃないかと私は思ったりします。 ところで、この本に戻りますと、各章のとびら部分に、一見無関係に見える友人の日常的対話があります。何も書いていないけどどうやらこれは人識といーたんの会話。別のところで鏡像関係と言われているように、二人の対照的?な性格が出ているセリフが続きます。でも見方によっては、いーたんとの対話形式を借りた、人識のキャラ設定メモともいえそう。なぜって、他の本や本文で時々作者がキャラにツッコミを入れている、そのスタンスと、いーたんのセリフのスタンスが、私には同じに思えるのです。 ついでに、誰でも気づくことを念のため書いておきますと、作者の名前は維新さんで、いがつくからいーたんとも言える。いーたんは関西人で鹿鳴館大学に在籍(のちに中退)、作者はたぶん関西人で立命館大学在学中にデビュー(のちに中退)。 シリーズ本編では語り手の「ぼく」(一人称)だから、ふつうに考えて作家の分身。 この話では、殺人事件に接点がないのに、犯人から聞いた形で事件の動機解明のカギを哀川潤に話した。結果、彼女はウラワザ的に--まるで推理小説の作者に謎解きしてもらったみたいに--事件を解決することができた。 物語末尾にはタイトル「戯言遣いとの関係」の答えとして「無関係」と記されています。鏡像であり友人なのに「無関係」なのは、作者がこのシリーズでかなり中心的に描き込んでいるため作者自身の分身とも言える零崎人識の、鏡像は、つまり作者だから。 創造者と被創造者という近いのに触れあわない関係(無関係)。それを作中に持ち込んでできあがったのが、いーたんという特殊なキャラクターなのかな、などと。
October 4, 2016
閲覧総数 2139
-
15
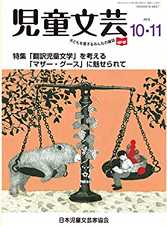
「児童文芸」誌にエッセイが載りましたv
昨年にひきつづき、雑誌「児童文芸」10・11月号の特集「翻訳児童文学」にエッセイを1ページ書かせていただきましたv 子どものころから翻訳モノが大好きだった私。昔はファンタジーというジャンルは圧倒的に洋物が多かったのです。書くことが決まったとき、どれについて語ろうか迷ってしまいました。結局、たとえば岩波書店の児童書のような有名どころではなく、隠れた?名作みたいなのを選んでみました。シーラ・ムーン『ふしぎな虫たちの国』です(といっても、すでにこのブログでは紹介していますし、某読書メーターや、復刊ドットコムなどでも語っています!)。 書くにあたって訳者さん(山本俊子)について調べました。検索したらミステリー作品をおもに訳している人のようで、私はそのジャンルはとんと読まないのでこの人の訳文の特徴などは分かりません。 『ふしぎな虫たちの国』の訳文にはミステリーっぽさはみじんも無く、どうして児童書を訳することになったのか知りませんが、13歳の少女が語るという内容に合った文体で、子どもの私を魅了しました。大人になって読み返してもいつも、うまいな~! と感心します。 ところで、原書(Knee Deep In Thunder)も少し読んでみました。この物語では旅の仲間に昆虫が何匹もいたりするのですが、小さくて口をきかず、マスコットのような役割のネズミ(名前はローカス)も出てきます。 主人公が最初、いなくなったペットの犬(♂)のかわりにかわいがるので、私はずっとローカスも♂だと思っていました。ところが原書では she でした。ローカスは♀(女の子)だったんだ! 訳の文体が主人公の語り口調なので、sheも「彼女は」ではなく「ローカスは」となっていました。うーん、ローカスという名前も女の子っぽくないし、何しろしゃべらないので、長年♂と信じてきたのです。原書を読んで最大の発見でした! 興味をお持ちの方は、こちらに雑誌の詳細があります。また、アマゾン等にも出ています!
October 3, 2019
閲覧総数 167
-
16

ヴァイキング・マイブーム――『ヴィンランド・サガ』など
このところ久しぶりにヴァイキングの本に凝っています。 きっかけは古書店で入手した『バイキング王物語』(山室静)。これはノルウェーのオラヴ・トリグヴァソン王(960年代~1000)の波乱の生涯を紹介した本で、わかりやすく楽しく読めます(拷問とか残虐シーンもありますが、史実らしいのでしかたないですね)。 ノルウェーで初めてキリスト教を受け入れた王なのですが、古来の神々を信じる人々に「改宗しなければ皆殺し」的な広め方をするところが、何というかいかにもヴァイキングです。 彼が大海戦の末まるで平知盛のように海に身を投げて死んだのがちょうど西暦1000年で、覚えやすい年ですね。そしてそのすぐ後の時代から始まるのが、今年アニメ化された『ヴィンランド・サガ』(幸村誠)(アニメ観てないけど)。 コミックスの方は何年も前に少し読んで、冒頭からがっつり歴史物で面白かった(船をひきずって山越えする戦法は、コンスタンチノープル陥落のオスマントルコ軍を思わせましたけど)。 (今23巻まで出てヴォルスンガ・サガも取りこんでるみたい・・・どれだけ続くか分からないから買い揃える勇気がありません)。 アシェラッドの最期でアーサー王伝説がからんできて、ケルト・フリーク魂を揺さぶられましたし、本筋のストーリーも非常に興味をそそられました。 何しろ、タイトルの「ヴィンランド」(葡萄樹の国)とは中世アイスランド文学の「赤毛のエリクのサガ」などに出てくる北米大陸東岸のことなのです。コロンブスより先にヴァイキングが北米を発見・上陸したというのは、世界史では結構有名な話のようです。 主人公トルフィンのモデルは、実在の北米入植者ソルフィンThorfinn・カルルセフニだそうですが、最初気づきませんでした。『ホビット』のトーリンThorinもそうですが、Thの音はカタカナにするとき「ト」になったり「ソ」になったり訳者によるからです。 しかし、彼にヴィンランドへ行った体験を語り聞かせる陽気なおやじレイフは、すぐ気づきました、「赤毛のエリクのサガ」の主人公であるレイヴ・エリクソン! 興味深いのは、私の手元にある『エッダとサガー北欧古典への招待』(谷口幸男)に出てくる「赤毛のエイリークのサガ」によると、北米に入植したソルフィン・カルルセフニはネイティブ・アメリカンと思われる土着の人々に襲われたりして結局は定住をあきらめてしまうのです。しかし、『ヴィンランド・サガ』のレイフはネイティブの人々と友になったと語り、彼らにもらった羽の頭飾りをかぶっていたりします(ただ、つっこみますと、北米北東岸のネイティブは、平原の諸部族とは違って羽の頭飾りをかぶる文化じゃなかったようなのですが)。 とするとトルフィンはこれから北米にたどりついてネイティブの人々とどんな接触をするのか・・・、夢に見た理想郷ヴィンランドで(史実とはちがって)定住してハッピーエンドになるのか、気になるところです。 あと、『ヴィンランド・サガ』の世界には宗教的な側面があまり出ません。オーディンやトールに祈ったり、キリスト教の神父が出てきたりはしますが、意図して深くつっこんでいないみたい。 たとえばトルフィンの父トールズが戦に倦んでヨムズ・ヴァイキング団を抜けた理由。私が読んだ最初の数巻限りだと、はっきりしません。当時のヴァイキングの信じるところ(戦場で雄々しく死んで天上のワルハラへ迎えられるのが理想)と正反対で、家族友人への危険も伴う。若くして不殺の誓いーーこの決断をするのに、精神的な大転換(たとえばキリスト教に改宗する、とか!)があってよいはずと思うのですが。 眼前で父を殺され復讐に執着する少年トルフィンは、父親への尊敬や愛をさっぴいても、神話(『エッダ』)や数々の伝説(サガ)で知れる北欧人の愛憎激しく執念深い気質がうかがえて、良いですね。悲劇的な荒々しさ、衆になじまない孤独感にとりつかれていて、「グレティルのサガ」なんかのどこまでも暗く激しい感じを思いだしました。 北ヨーロッパ特有のこの鬱屈した精神が、激しいヴァイキング気質となって噴出するのでしょうけど、その根底には、暗く長い冬という自然環境があって、みんな南をめざすんでしょうね。トルフィンも、太陽が照り実り豊かであれば平和で平等に暮らせるだろうと考え、理想郷ヴィンランドをめざすーーま、宗教心がなくて理屈っぽい(=近代ぽい)けど、ちょうど古代の多神教とキリスト教との転換期だし、進歩的な考え方のヴァイキングがいても、いいか(と書くとやはり『小さなバイキングビッケ』を思いだします!)。 進歩的といえば、現実主義な反面、最後の審判やラグナロクを憂えるアシェラッドも、ひどく現代的・無神論的な考え方で人類史を俯瞰し、諸行無常・盛者必衰的な発言をします。そこがカッコいいんですけど、ちょっと違和感を覚えるのも確かです。 まあ、宗教精神が入りこむと現代の大多数のニッポン人には、わかりづらくうっとうしい。諸行無常に持って行く方が我々の感性には響くのかもしれません。 でも中世ヨーロッパですから、本当はキリスト教やそれ以前の土着の宗教の影響が、現代とは比べものにならぬほど、あらゆる人々の精神のすみずみに及んでいたと思われます。わたし的には、アシェラッドのアイデンティティーを支えたアーサー王伝説、その深みにある、不屈のウェールズ、魔法に満ちたケルト魂にぜひもっと触れてほしかったですね!(アシェラッドに夢見すぎ?) そんなこんなで、機会があればもっと読みたい『ヴィンランド・サガ』でした。
November 30, 2019
閲覧総数 217
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 雑誌『映画秘宝 2026年 1月号』 ガメ…
- (2025-11-26 21:00:05)
-
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去
- (2025-04-08 00:00:18)
-
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『汐風と竜のすみか』1~2巻
- (2025-11-30 00:00:12)
-