読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20
読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15
読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16
読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5
映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6
[読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて] カテゴリの記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
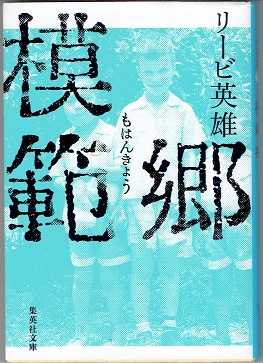
週刊 読書案内 リービ英雄「模範郷」(集英社文庫)
リービ英雄「模範郷」(集英社文庫) 「天路」で思い出したリービ英雄を続けて読んでいます。今回の案内は「模範郷」(集英社文庫)という作品集です。目次「模範郷」 7「宣教師学校五十年史」 83 「ゴーイング・ネイティブ」119「未舗装のまま」 145 上の目次のように四つの短編が所収されていますが、同じテーマで書き継がれている連作といっていいと思います。後ろの数字はページです。 台湾の西側、つまり台湾海峡の中央あたり、台中なる地方都市の町外れの「模範郷」という場所に、その家はあった。「模範郷」は中国の國語(グオユー)でモーファンシャン、そこに住んでいたアメリカ人の間ではModel Villageと呼ばれていた。一九五六年、そのアメリカ人の父母に連れられて六歳の時そこに住みついたぼくはたぶん、英語の呼び方を最初に覚えて、そのすぐ後に、ペディキャブで家に帰るときにその車夫に告げる自分の家の住所として「モーファンシャン」を覚えた。 その町を創り、一九四五年までその町の住人たちだったはずの日本人の、元の呼び方、もはんきょう、とは、十歳のときにそこを離れてから何年も経ち、大人になってからはじめて知ったのであった。 模範郷に並ぶ家は、すべて「日本人建的(ルベンレン ジエン デ)」家なのだと、ぼくの家に出入りする国民党(ナショナリスト)の誰かから、たぶんはじめてその話を聞いた。 その家に住んでいた、六歳から十歳まで、実際の「日本人」には一人も会ったことはなかった。「日本人」は畳部屋が連なる平屋と、鯉が見え隠れする池の背後にある築山を創ってから永久に去ってしまった。顔も声もなく伝説的な過去に生きた存在だった。(P17~P18) 日本語で書かれた「模範郷」というこの作品集を手に取った読者が、おそらく最初に持つであろう疑問、「模範郷って何?」に応えるべく書き込まれたかに見える、格好の解説の一節が、当の「模範郷」という作品の始まりあたりにありました。 この作品の前に読んだ「天路」もそうでしたが、アメリカ、台湾、日本、中国、二つの大陸と二つの島をめぐりながら、英語、日本語、そして、いくつあるのかわからない中国語という、まあ、三つの言語の音の響きに耳を澄ませ、今、現在という時間の中にあって、それぞれの「音」が語り手の脳裏に想起する幻影のような記憶の断片を手繰りよせるように描いていく手つきが印象的な作品でした。 「わたしは、なぜ、ここにいるのか」 そういう問いの向こうに立っている、リービ・英雄(Ian Hideo Levy)という、不思議な名を持つ作家の哀しい孤独な姿が浮かんでくる傑作でした。 ぼくにとって、リービ英雄ぐるいは始まったばかりです。マア、この年になってなんですが、物ぐるいして取り付く甲斐のある作家だと、作品を集めていますが、さて、どこまで行くことになるのでしょうね。それぞれ、読み終えれば報告したいと思います。また、覗いてくださいね(笑)。
2023.02.08
コメント(0)
-
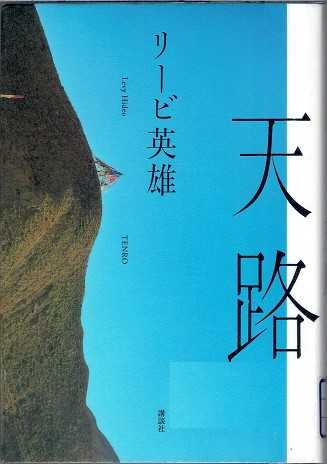
週刊 読書案内 リービ・秀雄「天路」(講談社)
リービ・秀雄「天路」(講談社) 久しぶりに、最初のページから、ページを繰り始めて、次へ次へと素直に読みすすめ、ほぼ最後のページに至って、ジンワリと涙がにじんでくる小説を読みました。 リービ・英雄の「天路」(講談社)という作品です。映画が好きで、最近、よく映画館に通っています。小説を読むのに比べて、読まなくても勝手に話が進んでくれるので便利です。ほぼ、2時間で、結末まで連れて行ってくれます。 小説は、読むのをやめると、そこで止まってしまいます。再び読み始める時には、聞き覚えのある「声」を探して、しばらく戸惑うのですが、再び、その「声」が聞こえはじめると、世界が再び動き始めます。 聞えてくる「声」は語り手のもので、必ずしも登場人物たちの会話や話し声のことではありません。書かれている文章には必ずあるはずだと思うのですが、映画にはありません。映画と小説の違いは、多分そのあたりにあると思いますが、とりあえず、「天路」に戻ります。 カバンには「ロンリー・プラネット」と旅行会社からもらった地図を入れて、かれは早朝に新宿の部屋を出た。東京駅で成田エクスプレスに乗り、第二ターミナルで下りて、東方航空の十時便に何とか間に合った。 乗りこんだとき、飛行機が前より小さくなったのに気がついた。連日のテレビ・ニュースに報道されている領土問題で、乗客が少なくなったのだろう。そのことを予測していたが、小さい飛行機は逆に息苦しいほど混みあい、荷物棚には象印の五万円の電気釜とTOTOの最先端の便座がぎっしり詰められ、前列からも後列からも、ケーラー、ケーラー、ノンラーと上海語がかれの耳に大きく鳴り響いていた。(P6) 語りはじめられた冒頭の描写です。「声」の主は新宿の部屋を出て成田から中国行きの飛行機に乗った「かれ」と、おそらく同一人物なのでしょうが、今、この文章を書いている「声」の主と、上海語の喧騒の中にいる「かれ」は、一応、別の存在です。 このところのぼくには、書かれている文章の「声」の響きに対して、その時、その時にゆらぐ自分を感じることが、どうも、小説、まあ、小説に限りませんが、文章を読むことになっているようです。 で、あらかじめの結論をいえば、この、何気ない旅の書き出しで始まる「天路」という作品は、そのゆらぎの快感が群を抜いていました。 かれは上海で中国の国内線に乗り換え、山東省の地方空港で漢民族の旧友と再会します。 山東省のナンバープレートの上に「日産」とBLUEBIRDという文字が、月光の下で読みとれた。そして黒い皮膚の上に無数の斑点が現れるように、車体のいたるところに赤いスティッカーと「祖国の領土を死守する」というスローガン、そして小さな島にそびえる円錐形の山の後ろの真赤な拳の絵と、「釣魚島は中国のものだ、日本人は出て行け!」という意味の文字のスティッカーだった。 静まりかえった駐車場の中で、叫び声のような文字が妙に目立った。(P8) 空港の駐車場で待っていたのは、まあ、こんな、スティッカーだらけの自動車と友人だったのですが、ここから、中国を縦断し、西安からチベット、作中の友人の言葉でいえば「大西部」への旅が始まります。映画で言えば、ロード・ムービー、「自動車と男と女」ならぬ、「自動車と男と男」の旅です。 大西部の旅のために二日間、山東省から高速道路を走りつづけた。 謝謝你(シェイシェイニー)、とかれは弱々しい声で言った。 いや、あなたこそ遠方よりよく来てくれた。友人の声には、一瞬、おおらかさがもどった。 それからまた独り言を言いつづけた。 但是(ダンシル)、ところが、西安を過ぎて本格的に西方へ入りこんだあたりから、面白いことに気がついた。西へ行けば行くほど、愛国スティッカーが見当たらなくなった。友人はまわりで駐車している何台かの日本車を指さした。 ここまで来ると、そんなものは一つもないでしょう。 ターミナル・ビルのすぐ後ろにそびえる真暗な山脈を友人が指で示した。そして振りかえり、反対側で層をなす山々を指した。 北の山脈の向こうでは砂漠が敦煌までつづき、南の山脈の向こうでは高原がラーサまでつづいていた。 膨大な大西部の中には、日本そのものが三つも四つも入る それで、私は思う、と友人が言った。 一瞬経ってから、私も思う、とかれは答えた。 友人もかれも、ほぼ同時に言い出した。 それでは、剝がしましょう。 激怒の文字がめくれ上がった。「愛国無罪」がとれた。 ウオツリジマの絵がたやすく落ちた。 剥がす音とともに、北方からも南方からも、砂漠と高原の静けさが聞えてきた。 最後の五星紅旗をはがしたとき、ついでに日産の文字もけずりたくなった。母国の星条旗を剝がす自分を想像した。 その時、かれの心には「親」も「反」もなかった。ただテレビ画面からうっとうしいニュースのテロップを引きちぎっているような気持になった。 数分のあとに、ブルーバードの車体が月光の下で黒く輝いていた。 走吧(ヅォーパ)、と漢民族の友人が言った。 さあ行こうか。 走(ヅォー)、と答えるかれの声で、二人はブルーバードに乗りこんだ。 「国家」を剥がされた車は、エンジンが勢いよく、青い鳥の元の軽みを取り戻したように、空港の南方の、チベット高原に向ってすっと走り出した。(P12) 小説は「高原の青い鳥」「西の蔵の声」「文字の高原」「A child is born」の4章で構成されています。上に引用した始まりのシーンは、「高原の青い鳥」の冒頭近くの部分ですが、ここからラーサの寺院まで旅は続きます。語り手の静かな「声」が印象的な作品ですが、実は、なんの事件も起こりません。 友人が「藍天白雲(ランティエンハイユン)」と叫ぶ空の下、二人の自動車の旅が続くだけですが、リービ・英雄という、日本語で書くアメリカ人作家の到達点を感じさせる「声」の美しい作品だと思いました。 生者が死者をおんぶして、天葬の場所へとこの山を登るのだ。 おぼろげな記憶の中から、 死者がたどる天路(あまじ)という古い日本語が頭に浮かんだ。 昔かれはthe path to heavenと翻訳したこともあった。 草の中のこの細い登り道も天路なのだろうか。 表紙の裏に印刷されている断章ですが、本文中からの引用です。 リービ英雄はアメリカでも、有数の万葉学者だそうです。「万葉集」の英訳の仕事は有名です。作品名の「天路」は、中国語ではティエン・ルーと発音するそうです。読み終えて、その発音を声に出して読みなおしたときに、涙がこぼれました。マア、ぼくにとって、そういう作品だったということです。乞う、ご一読!ですね(笑)。
2022.11.18
コメント(0)
-
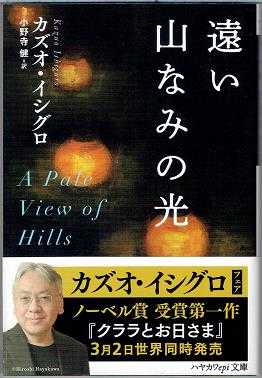
週刊 読書案内 カズオ・イシグロ「遠い山なみの光」(ハヤカワ文庫)
カズオ・イシグロ「遠い山なみの光」(ハヤカワ文庫) カズオ・イシグロです。いわずと知れたノーベル文学賞作家ですが、ぼくはこの人の、あまりよい読者とは言えません。我が家にはこの作家にはまっていた人がいたので、受賞以前の作品がそろっていることもあって、なんとなくそう思います。 受賞後の「忘れられた巨人」(ハヤカワ文庫)と、人造人間というテーマがセンセーショナルだった「わたしを離さないで」(ハヤカワ文庫)を読んだ記憶はありますが、後は憶えがありません。 今回、青來有一の「爆心」(文春文庫)という作品を読んで、長崎の作家つながりというか、陣野俊史という批評家が、その「爆心」の文庫解説だったか『戦争へ、文学へ「その後」の戦争小説論』(集英社)という評論集の中だったか、よく覚えていないのですが、「ポスト原爆文学」というくくりでこの作品をあげていたのに惹かれて読みました。まあ、大した意味はありません。 読んだのは「遠い山なみの光」(ハヤカワ文庫)という作品で、小野寺健という人の訳です。2001年に初版が出た本ですが、実は「女たちの遠い夏」という題で1994年にちくま文庫になっている作品の、同じ訳者による改訳だそうです。 題名が変えられた経緯が、ちょっと気になりますが、カズオ・イシグロがノーベル賞を受賞したのは2017年ですから、受賞とは関係なさそうです。出版社が変わったこともあるのかもしれませんが、もともとの題名は「A Pale View of Hills」です。直訳すれば「山々の淡い光景」でしょうか。 読み終えてみると「青白い」と訳したい気もしますが、小野寺さんが最初の題から「女たちの」を削除されていることに、訳者自身の「読み」の変化を感じて納得しました。 ああ、それから、まあ、余計なことかもしれませんが、ノーベル賞騒ぎの中で、彼を日本文学の作家として持ち上げる雰囲気があるように思いますが、カズオ・イシグロが英語圏の作家だということは忘れない方がいいと思います。ぼくらのような読者には翻訳がないと読めない人なのです。 で、小説はこんなふうに書きだされています。 ニキ、さいごにきまった下の娘の名はべつに愛称ではない。これは、私と彼女の父親との妥協の産物だった。話は逆のようだが、日本名をつけたがったのは夫のほうで、わたしは過去を思い出したくないという身勝手な気持ちがあったのか、あくまでも英国名に固執したのである。夫はニキという名にどことなく東洋的なひびきがあると思って、さいごには賛成したのだった。(P7) 語り手は悦子という名の、おそらく中年の女性ですが、彼女が敗戦直後の長崎で成長し、少なくとも二度結婚し、それぞれの夫との間に一人づつの子どもを生み、この小説を語っている現在はイギリスに居住しています。 ただ、悦子の一度目の結婚の破綻、渡英して二度めの結婚という、読者としてはかなり興味を惹かれる、そのあたりの経緯とか、たとえば、はたして、悦子という名は彼女がこの世に生を受けたときにつけられた名前なのかどうか、誕生日は何年の何月何日だったのか、少なくとも、彼女の姓名の「姓」、つまりが悦子自身の親や家族については、ただの一度も語られないのがこの作品の特徴でした。 小説は、二度目の結婚の夫に先立たれ、イギリスの田舎町で暮らしている悦子が、同居していた長女の景子を自室での首つり自殺で亡くし、その葬儀の後、葬儀に参列しなかった次女のニキが帰宅し、数日間の滞在ののちロンドンに帰って行ったという場面から語り始められています。 今ここであまり景子のことを書こうとは思わない。そんなことをしても何の慰めにもなりはしないから。彼女の話を持ち出したのは、ニキがこの四月に来た事情を明らかにするためと、彼女が滞在しているあいだに、これだけ年月がたった今になって、また佐知子のことを思い出したからである。私には、ついに佐知子がよくわからなかった。というより、わたしたちのつきあいは、もう遠い昔になったある夏の、せいぜい数週間のことにすぎなかったのだ。(P10) ここから、二人の娘がまだこの世にいない頃の遠い記憶として語られるのは、一度目の結婚をした当時の悦子が、夫と長崎市の東部の原爆のために焦土と化していた土地に建てられたコンクリート製のアパートで暮らしていたころ、近所の人として出会った佐知子と万里子という親子連れの話です。 佐知子が現われたときの騒ぎを考えると、この家をよく眺めていたのは、わたし一人ではなかったのだ。ある日この家で男が二人仕事をしているのが見えると、あれは市がよこした作業員ではないのかという噂がたって、わたしも何度か、その二人が水溜まりだらけの空地を歩いてゆく姿を見かけた。 そろそろ夏になる頃だった―そのころわたしは妊娠三ヵ月か四ヵ月だった―わたしはその白塗りで傷だらけの大きなアメリカ車が大きく揺れながら、川に向かって空地を走ってゆくのをはじめて見たのだった。もう日が暮れるころで、その家の向こうにしずみかけている夕日があたると、一瞬キラリと車体が光った。(P12) 荒れるままに放置されていた誰も住まない一軒家に母と幼い娘の親子連れが越してきます。新婚で妊娠したばかりの主婦だった悦子の興味がその二人の様子に惹きつけられていきます。時は1950年代の後半、季節は夏の始めで、場所は長崎の市街を外れた爆心地のあたりです。 小説は、彼女がその夏、その母子と知り合いになり、やがて、別れてしまう経緯の記憶をたどりながら、おそらく、自分だけのためにノートに書きつけていった、日記風のお話でした。 戦後復興が始まったばかりの地方都市に暮らしながら、恋人(?)であるアメリカ兵を頼ってこの町、あるいは、日本からの脱出を夢見ている佐知子と、幼い娘万里子という母子の記憶を、20年(?)後、日本から連れてきた娘景子の自殺に遭遇した悦子が、一人暮らしをしている異国の田舎町で書き綴っていきます。 カズオ・イシグロは彼女の行為でなにを描こうとしているのか、訝しく戸惑いながら読みすすめていて、ギョッとする記述に行き当たりました。もちろん、悦子の記憶の記述です。 記憶というのは、たしかに当てにならないものだ。思い出すときの事情しだいで、ひどく彩りが変わってしまうことはめずらしくなくて、わたしが語ってきた思い出の中にも、そういうところがあるにちがいない。たとえば、あの日心にうかんだやりきれないイメージが、果てしなくつづく空白な時間にわたしの心を去来していた無数の白日夢よりもはるかに鮮烈なまったく別のものになったのは、あの日の午後に虫が知らせたせいだと考えたくなる。どう考えても、あれはそれほどのことではなかった。木からぶらさげられていた小さな女の子の悲劇、これはそれまでの連続幼児殺害事件以上に悲惨なもので、近所の人びともショックを忘れられずにいたのだから、あの夏、こういうイメージに悩まされたのはわたし一人のはずはなかった。(P221~P222) 日記の終盤です。佐知子と万里子のことを思い出していた記憶の中に木からぶらさげられていた小さな女の子のイメージが呼び起こされています。前後に、こういう出来事があったという記述はありません。ぼくが詠み損じているのでなければ、このイメージの記述は唐突です。 可能性は二つかなと思いました。一つはその当時そんな事件が実際にあったが、具体的には記さなかった。もう一つは、今現在の(20年後)の意識が記憶に紛れ込んでいるが、本人は気づいていない。いずれにしても謎ですが、悦子に対する読み手としての「疑惑」(笑)は一気に深まりました。 「このひとにはなにかあるな!?」 まあ、そんな感じです。作家が顔を出したと思いました。思い切った生き方をしてきた女性の、自らの人生に対する、家族にも、もちろん他人にも言えない苦悩と、そこからの再出発の契機を描いているという読み方が普通かもしれませんね。 しかし、ぼくが「凄い」と思ったのは、自分の意識そのものが意識を捏造する中に、人間の生の姿を描いているのではないかというところでした。 ぼくがこだわっている記憶の謎以外に、実は悦子が自分自身については何も語っていないというのが、この手記というか、日記の正体なのですが、そのあたりにも、この作品のわからなさという面白さが潜んでいるのではないでしょうか。 ひさびさに読みごたえを感じる作品でした。やっぱりノーベル賞ですね(笑)
2022.07.13
コメント(0)
-

週刊 読書案内 多和田葉子「百年の散歩」(新潮文庫)
多和田葉子「百年の散歩」(新潮文庫) 多和田葉子は1984年、大学を終えてすぐドイツに渡り、ハンブルグという町に20数年暮らしたそうです。そのあとやって来たのがベルリンであるらしいですね。この「百年の散歩」という作品は「わたし」がベルリンの街を散歩する小説です。エッセイの味わいもあるのですが、やはり、小説だと思います。十の通りや広場をめぐりますから、ある種、短編連作と言えないこともありません。 ベルリンには「人名」がついた通りや広場がたくさんあるようですが、中でも、かなりな有名人の通りを散歩しています。「Berlinはフランス人がつくった町だ、と昨日の夕方「楽しー」の運転手に言われた。そのことがきょうのわたしの聴覚世界に影響を与え続けていTaxiをわたしは「楽し―」と呼んでいて、これは日本語でもドイツ語でも英語でもみんな「タクシー」という苺、イチゴ、一語、に縮んでしまっているモノリンガリズムを崩すために自分で勝手に造った単語である。 ユグノー派の人々がフランスから逃れてこの土地にやって来た時には、まだBerlinという都市があったわけではなく、いくつかの村が集まっていただけだった、と楽しーの運転手は語り始めた。まるで最近の出来事を語るような口調だけれども、実際はもう三百年も前の話だ。(「カント通り」) やたらと繰り返されるダジャレ。次から次へと「連想ゲーム」なのか、「ことば遊び」なのか。慣れない読者にはかなり辛いかもしれません。ここにはタクシー運転手との会話を引用しましたが、なんということはない風景と、湧き上がる言葉遊びを「散歩」と称して綴っているのか?そんな疑いが浮かんでくるのですが、連想は言葉を数珠のようにつなぎながら、時間を遡って、いつのまにかBerlinの歴史を語りはじめたりしているわけです。「百年の散歩」の「百年」が、きっとミソなわけでしょうね。 しょうてんがい、という言葉の響き、てんがい、天蓋、てんがいこどく。しょうてんがいこどく。商店街とは、人がパンを買ったり、トマトを買ったり、鉛筆を買ったり、靴下を買ったりできる区域のことだというならば、ここは商店街ではない。 店の名前をいちいち読まなくても色彩と活字の選び方だけで値段の安さを売り物にしていることが分かるチェーン店がずらりと看板を並べているけれども、いくら店の数が多くても、日々の暮らしに必要なものはそろわない。 ロゴの雰囲気だけで、ああ、あの会社、とわかってしまうのに、自分とは縁のない会社ばかりだ。通りの名前の書かれた古びた標識だけが昔の友達のように懐かしい。(「カール・マルクス通り」) カール・マルクスは、もはや、思い出の中の懐かしい「プレート」にすぎないのでしょうか。どうも、そうではないようですね。「ことば遊び」は、意識の深みへ降りていくウオーミングアップなのかもしれません。やがて、眼前の町の上にカール・マルクスが200年前に見た町が重ねられているのではないでしょうか。 「商品」はあるが「生産」者のいない商店。反政府運動の弾圧で亡命したウイグル人が羊肉の串焼きを売る街角。移民たちが故郷の路地をたたんでトランクに入れて持ってきた横道。それが、今目の前にある町の風景なのです。 「生産」はどこに行ってしまったのでしょう。人間は「疎外」から「自由」になったのでしょうか。 でも、まだまだ、読むには眠い「散歩」です。 たっぷり水分を含んだ葉が熱帯雨林に棲むカエルの背中のようにてらてら緑色に光り、観察者の喉を潤すが、花そのものは鼻糞のように小さいのもいる。のもいる。もいる。いる。る。植物は「いる」ではなく「ある」か。生きているのに。(「マルティン・ルター通り」) 最近、花屋が増えているような気がする。どんな言葉を口にしても相手にわるくとられてしまう袋小路に迷い込んだら、無言で大きな花束を差しだせばいい。そう考える人が増えている。(「マルティン・ルター通り」) 時間が経つと不思議な融合作用が起こる。丁度ベルリンの壁が崩れて二十年が過ぎたころから、町の西側にかつての東側の雰囲気が漂い始めてた。(「マルティン・ルター通り」) アパートの入り口の真ん前にはめ込まれているのですでに無数の靴に踏まれ、字がかすれている。それでもまだ読めないことはない。マンフレッド・ライス、1926年生まれ。殺されたのは1942年、アウシュビッツ。視線をあげると記憶を掻き消すような金剛色の外壁が私の前に聳えていた。扉が急に開いて、厚着の老人がへんなりしたナイロンの買い物袋を提げて外に出てきた。私の方を見ないで、そのまま右に歩き出した。 この交差点でルター通りは終わりだと思う。(「マルティン・ルター通り」) 歩きながら、何層にも重なっている「わたし」の記憶と、「Berlin」がそれぞれの「通り」の底に重ねている歴史が微妙に和音を奏で始めてきましたね。 これで、三つの通りを歩いたわけですが、ようやく、読み手は、次の通りではどんな音が聞こえてくるのか期待を感じ始めます。苦手な人は、とっくの昔に投げ出していらっしゃるに違いありません。 このあたり、ようやく「通り」と「わたし」の輪郭を、少しリアルにイメージしながら「多和田葉子」を楽しみはじめることができますね。眠気もどこかへ去って行きます。 さて、次はベルリン映画祭の、あの「金熊」を彫った彫刻家「レネー・シンテニス広場」です。 初めて多和田葉子をお読みになる方は、ここまでは頑張ってみてください。それでだめなら、仕方がないですね。 ぼくは「コルヴィッツ通り」の「子供たちと母」、「母の太い腕」あたりの描写にあらわれたイメージの奔流には、正直な多和田葉子の姿を見た気がしました。傑作とまではいいませんが、彼女の新境地かもしれませんね。ボタン押してね!ボタン押してね!犬婿入り (講談社文庫) [ 多和田葉子 ]
2020.02.17
コメント(0)
-

週刊 読書案内 カズオ・イシグロ「わたしを離さないで」(早川文庫)
カズオ・イシグロ「わたしを離さないで」(早川文庫) 「カズオイシグロ」、この名前をご存知だろうか。イギリス人作家になった元日本人。1989年、「日の名残り」(中公文庫)という作品でブッカー賞という、イギリス文学界最高の文学賞をとり、二年に一作のペースで作品を発表し続け、そのすべてが英語圏ベストセラーという、現代イギリスを代表する作家。 彼は長崎生まれの日本人だったが、五歳の時に海洋学者の父の渡英に家族で同行、以来イギリスの教育を受け、現在に至っているそうだ。現在の彼は日本語が上手く書けないし、しゃべれないらしい。 年齢は僕と同じ1954年生まれ。国籍はイギリス。2017年、それまで候補として評判だったハルキ・ムラカミを差し置いてノーベル文学賞を受賞して大騒ぎになった。 この不思議な経歴の持ち主であるイシグロの評判の作品「わたしを離さないで」(早川文庫)を読んだ。 読み終えて実は困ってしまった。何とか紹介したいのだが、これから読む人にどうしても教えてはいけないことがある小説なのだ。 原題は「Never Let Me Go」。翻訳は土屋政雄。イギリスで映画化され、日本公開に先立って、作家自身が来日したあたりから、メディアが騒ぎ始めた。NHKでは「動的平衡論」の紹介で評判になった、あの福岡伸一がインタビュアーを勤める特集番組を作って放送した。生物学者を作家カズオ・イシグロのインタビューに起用した所に、この作品が評判になっている理由の一端が垣間見えるわけなのだが、僕としては、それ以上語るわけには行かない。この小説を読み終えて困った理由もそこにある。 もっとも、今(2019年)となっては綾瀬はるか主演のテレビドラマまで作られたわけだから、そんなに気にする意必要はないかもしれない。 ミステリー小説や、映画の紹介をするときのタブーに、プロットを語ってはいけないということがある。推理小説を批評するのに謎解きをばらしてしまってはいけないということだ。「それならば、この小説はミステリー小説なのか」と問われれば、「そうではない」と、僕は答える。しかし、小説がミステリアスであることは間違いない。 この小説について、翻訳家柴田元幸はこう解説している。《この小説は、ごく控え目に言ってもものすごく変わった小説であり、作品世界を成り立たせている要素一つ一つを、読者が自分で発見すべき》で、《予備知識が少なければ少ないほど良い作品なのである。》 実にそのとおりだと思う。何も言わず、まあ読んでみたまえというのが、この小説の案内としては最も正しい。 ただ、この小説はミステリアスだといったけれど、実は最後まで、心に最初に浮かんだ謎は解けなかった。そこの所だけ少し説明してみたいと思う。 たとえば、この小説の表紙にはカセットテープのイラストが書かれている。本文を読めばこのテープが、主人公の宝物であったテープであることは、やがてわかる。しかし、何故そのテープが、それほど大事で、その中の一曲の題名が小説の題名として使われることになるのか、それは今もわからない。 いや、その言い方は少し間違っている。「私を離さないで」という1950年代のイギリスの通俗なラブソングが、幼い主人公によって、意味を取り違えられた結果、主人公が生きるための祈りとでもいうべき象徴性をおびて、小説の中に据えられていることは読めばわかる。しかし、主人公は何に対して祈るのかという疑問に突き当たってしまうと、最後までわからないのだ。それは僕の中で、思考実験のためのひとつの問いのように残ってしまう。 もうひとつ謎をあげてみると、この小説がこう閉じられていることにある。「空想はそれ以上進みませんでした。わたしが進むことを禁じました。顔には涙が流れていましたが、わたしは自制し、泣きじゃくりはしませんでした。しばらく待って車に戻り、エンジンをかけて、行くべきところへ向かって出発しました。」 すべてが、あらかじめ奪われていたことを知った彼女は、死んだ友人との思い出の場所にやってきているのだが、そこで湧き上がってくる空想を自らに禁じて、何処かへ出発しようとして小説は終わる。 しかし、彼女は、いったい、どこへ行くのだろう。それが、ずっと謎を追うように読み進めてきた僕に示された最後の謎だ。答えはまだわからない。 僕はこの小説を案内するために、語ってはならないことを語ってしまったかもしれない。いずれにせよ、読めば考え込まなければならないことに出会うことは間違いないだろう。乞うご一読。(初出2011/05/11)(S)浮世の画家〔新版〕 (ハヤカワepi文庫) [ カズオ・イシグロ ]始めの頃の作品。忘れられた巨人 (ハヤカワepi文庫) [ カズオ・イシグロ ]いちばん最近《?》の作品にほんブログ村にほんブログ村
2019.06.04
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 【中古】 【コミック全巻】幽☆遊☆白…
- (2024-11-22 15:26:17)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- duta89 link daftar terbaik dengan …
- (2024-09-11 01:49:11)
-
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月9日分)
- (2024-11-22 23:52:18)
-







