読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20
読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15
読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16
読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5
映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6
[読書案内「翻訳小説・詩・他」] カテゴリの記事
全53件 (53件中 51-53件目)
-
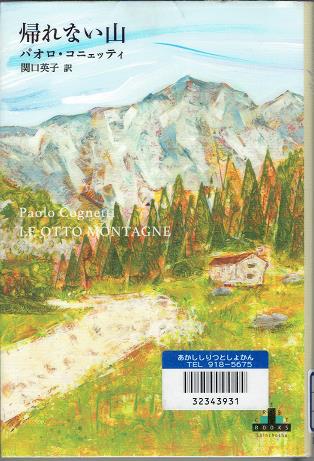
週刊 読書案内 パオロ・コニェッティ 「帰れない山 LE OTTO MONTAGNE」 (新潮クレストブック)
パオロ・コニェッティ 「帰れない山」(新潮クレストブック) 読み終えて、切ないとしかいいようがない、ある感じにとらえられてしばらく座り込んだ。涙をこぼしていたかもしれない。年を取ったのだろうか。 山に登ることを生きていることの証しのように暮らしている父親と父に連れられて山に登り始める少年の独白が小説の始まりであり、やがて、数十年の時が経ち、死んだ父が、かつての少年に語った「人生には時に帰れない山がある。」という言葉を思い出して小説は終わる。 小説の邦題はここからとられているようだが、原題は「Le Otto Montagne」。たぶん「八つの山」というくらいの意味ではないかと思うが、その題名の由来も読めばわかる。 作家自身が、実際に経験した出来事が、自伝的に描かれていると感じさせる作品だが、語り手である「僕」と家族との関係という経糸(たていと)と、町の少年であった「僕」が山の村で出会った山の少年「ブルーノ」との交友という緯糸(よこいと)で織られたテクスチャー=織物であるかのように小説は出来上がっている。 中でも「トムソーヤ―とハックベリー・フィン」の組み合わせのような、この二人の少年の物語の世界は、昨年(2018年)亡くなったエルマノ・オルミの傑作映画「木靴の樹」の世界を彷彿とさせる。 あの映画もこの小説と同じ北イタリアのアルプスのふもとの村が舞台なのだから、当たり前といえば当たり前なのかもしれないが、描かれた時代には、半世紀ほどのずれが歴然とあるはずだ。 にもかかわらず、現代社会から取り残された山の村の、貧しい農夫の息子ブルーノと都会のインテリの一人息子「僕」が出会い、兄弟のような友情で結ばれ、やがて別れる世界は、あの映画のさみしい村の風景や農夫や子供たちの姿に重なり、貧しく、美しく、哀しい。 加えて、この小説が北イタリアのアルプスの山並みを背景にして繰り広げられていることは、この作品を語るうえで忘れてはならないことだろう。読者にとって、この風景の描写は、この作品の特筆すべき魅力だと思う。 僕たちは山頂に座り、持ってきたパンとチーズをかじりながら雄大な風景に見惚れていた。モンテ・ローザのどっしりとした山群が、山小屋やロープウェイ、人工湖、マルゲリータ小屋から降りてくる登山者の隊列まで識別できるほど間近に迫っていた。父はワインの入って水筒の蓋を開け、午前中は一本と決めていた煙草に火をつけた。「この山は薔薇色だからモンテ。ローザという名前がついたわけじゃないんだぞ。」と父は蘊蓄を語りだした。「氷という意味の古語が語源になってるんだ。つまり氷の山だ。」 それから父は、東から西へと順に四千メートル峰の名を挙げていった。毎回決まって最初からくりかえす。実際に登る前に、一つひとつの頂を正確に把握し、長い間憧れを抱き続けることが肝要なのだ。 ジョルダ―ニの控えめな頂、それを上から見下ろすピラミッド・ヴィンセント、ピークに大きなキリスト像が立っているバルメンホルン、稜線があまりに緩やかでほとんど目立たないパロット、さらにはニフェッティ、ズムスタイン、デュフールと、気品の漂う鋭い峰が三姉妹のように並んでいる。次いで、「人食い尾根」と異名をとる尾根で結ばれた二つの頂上を持つリスカム、その隣の双子の山は、優雅な波を描いているのがカストルで、気の荒そうなのがポルックスだ。そしてロッチャ・ネーラの輪郭に、無垢な表情のプライトホルンが続き、一番西には孤高のマッターホルンが屹立している。 父はこの山を、まるで年のいった伯母さんかなにかのように、親しみをこめて「偉大な尖峰」と呼んでいた。一方、南の平野の方角は全くといっていいほど見ようとしなかった。平野には八月の靄が立ちこめている。あの灰色のフードの下のどこかに炎暑のミラノの街があるはずだった。 絵巻物を広げるようにして、繰り広げられる山々の連なる風景描写は、それだけで、山になんて何の関心もない読者をひきつける山岳小説のおもむき十分だが、それだけではない。このアルプスの、一つ一つの山の風景は登場人物たちの心に織り込まれ、それぞれの心模様を作っていて、彼らの生き方をリアルに語るうえで、欠かすことのできない背景となっていることを読み手は実感することになる。そういう意味で、真の山岳小説といえるかもしれない。 「子供時代の山」と題された「僕」とブルーノとの少年時代の生活。青年になった僕と父との、葛藤と和解の物語を描いた「和解の家」。最終章「友の冬」は父亡き後、中年に差し掛かった「僕」とブルーノとの再会と別れを描いている。 中年に差し掛かった語り手、僕の、一見、「自伝風」、「私小説風」の回想は、上記のように章立てされた三つの時間をたどりながら、父やブルーノと登った幾多の山を登り直すことから始まり、アルプスのふもとの山の村の母との生活や家族の思い出を丹念に描きながら、とうとう「帰れない山」が聳えている場所にやってきて、結末を迎える。 「帰れない山」とは何なのかは、読んでいただくほかないが、それが小説の主題を暗示している比喩であることは間違いない。 ここまで読んでいただいて、ある種、「山と人生」とでもいうべき人生論物語風の結末を予想する人もいるかもしれない。残念ながら、その予測は完全に外れている。 この作品が「人生」を定型化することを目論んで書かれた小説ではないことは、お読みになればしびれるような余韻とともに、実感として理解されるにちがいないだろう。 乞う、ご一読。 (S) 追記2019・05・03「父と子」、「母と子」、「家族」、「友情」・・・。この小説から読者が感じ取るイメージのパターンは古典的です。まあ、ありきたりといってもいいかもしれません。しかし、読み終えてみると、どこかに、ある「新しさ」があって、それが多分この小説の魅力なのだと思う。その新しさを解説できれば、プロの書評ですが、残念ながら、ボクにはうまく言えませんね。追記2023・04・27 なんと、映画化されたらしい。まだ見ていないのですが、とりあえず記事の修繕を、と、考えて触りました。映画が楽しみです。追記2023・05・16 映画を見てきました。感想は別に書こうと思いますが、ボクが小説を読んで感じていた「新しさ」を、映画製作者は感じなかったようで、悪くはないのですが、かなり古典的な青春葛藤ドラマとして描かれていて、ちょっと拍子抜けでした。うーん・・・という感じでしたね(笑)ボタン押してね!にほんブログ村にほんブログ村
2019.05.03
コメント(0)
-

週刊 読書案内 レベッカ・ブラウン「家庭の医学」(朝日文庫)
レベッカ・ブラウン「家庭の医学」(朝日文庫)「家庭の医学」(朝日文庫)という変な名前の小説があります。お読みになられるとわかることですが、小説というよりもノンフィクションという印象をお持ちになる作品かもしれません。でも、これは小説です。 元の題名は「EXCERPTS FROM A FAMILY MEDICAL DICTIONARY」。直訳すれば「家庭医学事典からの抜粋」となるのでしょうか。 「家庭の医学」という題名は訳者の柴田元幸が日本で翻訳出版するときに考えた題なのでしょう。訳者というくらいだからこの小説の作者は外国の人です。 レベッカ・ブラウン。1956年生まれ。アメリカのシアトルに住んでいる女性の作家です。新潮文庫にもう一冊「体の贈り物」という短編集があります。これも柴田元幸の訳です。他にもいくつか翻訳されている作品はあるようですが、簡単に手に入るのはこのニ冊です。 目次を開いてみると【貧血】anemia,【薄暮睡眠】twilight sleep、【転移】metastasis,【無能力】incompetence・・・・【幻覚】illusion,【塗油】unction,【火葬】cremationと続いて最終章が【remains】 はたしてこれらのことばが本当に家庭医学事典にあるのかどうか、ちょっと疑わしい気もします。しかし、こうして羅列して読んでみると家族の誰かが病気を患い、闘病生活を送り、やがて死に至ったということは想像がつくと思います。 このいささか風変わりな書名と各章の章名について訳者である柴田元幸はこんなふうに解説しています。 ここにはどういう意味を読みとることができるだろうか。病にせよ死にせよ、いつかは誰にでも訪れるものであって決して特殊な事件でも個人的体験でもないことを「事典」というきわめて非個人的な書物を引用することによって示唆しているのだろうか。 病気、入院、手術、治療、死、葬儀・・・確かにすべては個人的でも特殊でもない、事典的・客観的に記述しうる出来事なのだ。 一患者として、あるいは一患者の家族として、病院である程度の時間を過ごした経験のある人なら、自分や自分の家族が、客観的に見れば、二百人なら二百人いる患者の中の二百分の一に過ぎないことを思い知らされた覚えがあるにちがいない。 本書のタイトルや構成が、そういう厳然たる事実を暗に示していると考えることもできるだろう。だが、この本を読んだあとでは、その全く逆の読みとり方も可能であるように思える。」 あらゆる生き物は死という出来事から自由になることは出来ません。もちろん「人間」も例外ではありません。魂の不滅をいう人や、来世の存在を信じる人がいますが、一人の人間としての考え方や信仰としてそのように信じることを、ぼくは非難することも、バカにすることもしません。 しかし、死ねば「死にっきり」だろうという確信は揺らぎません。人の「死」は「生きている人たち」にとっての問題であって、「死んでしまった人」にとって、何の関係もありません。言い換えれば、人は死んでしまえば、それで終わりというわけです。 そして、人間というものが、そういう存在であるからこそ、レベッカ・ブラウンのこの小説は、読者の心を打つのだと思います。 この作品では、各章の章名が老いた母親の発病から葬儀までの暮らしの中で起こる様々な出来事を暗示しています。母との日常生活の小さなエピソードの集積として描いている小説です。そこでは、かけがえのない家族の死が静かに、そして誠実にとらえられています。 【幻覚】illusionの章にこんなエピソードが記されています。 「荷物はできたの?」「うん、母さんの荷物はね。僕たちみんな行くわけじゃないから、行くのは母さんだけだから。母さんの必要なものは全部揃っているからね。」「まあ、ありがとう・・・じゃあ、土曜日はどう?土曜日なら道もすいているだろうし・・・」 母はその土曜日には死ななかった。誰が思っていたより何日も長く母は生きた。やがて、母が死んだ時、それは安らかでも楽でもなかった。辛い死に方だった。母が死を押し戻そうとしていたあいだずっと、支度はできたよとあのとき母に言いはしたけれど、私たちは支度なんかできていなかった。 命の「かけがえのなさ」とは、幻覚の中でうわごとを発する母と交わされる会話の一言一言がくっきりと記憶されることであり、生きていることの「悲しみ」とは、正気の中にいる家族が、もうろうとしている母に語りかけたことばの嘘を誠実に引き受けることなのだと作家は語っているように、ぼくには思えます。 小説は虚構を書きますが、書いている作家は「嘘」を書いているわけではないと思います。「かけがえのなさ」や「悲しみ」の真実というものがあるのではないでしょうか。 レベッカ・ブラウンのもう一つの文庫本「体の贈り物」はエイズ患者と周りの人たちの世界を描いています。小さな、おだやかな小説ですが、きっと心をうつものがあると思います。是非一度手にとってみてください。(2007/04/23)追記2019 10年以上も昔のことですが、高等学校で国語教えていました。その頃、授業にいっていたクラスで配布していた「読書案内」をリニューアルした2019年版です。「案内」している作品が古いですね(笑)。 今でも新刊書として手にすることは出来るのか調べてみると「家庭の医学」(朝日文庫)は絶版ですが、「体の贈り物」(新潮文庫)はあるようです。「若かった日々」(新潮社)・「私たちがやったこと」(マガジンハウス)という単行本もありました。レベッカ・ブラウン、いい作家だと思います。また案内します。追記2022・05・27 また「案内」するとかいいながら時はたちましたが、いつまでも「また」になりません。昔の「読書案内」を整理しようという目論見も、一向に現実化しません。新しい作品も読むことは読んでいるのですが、「なんだかなあ・・・」という感じのままほったらかしています。 先日、時々お出会いすることのある大学生の女性に「面白い本とか、読めばいいよっていう本、教えていただけませんか。」と声をかけられて、「ああ、そうかあ、でも、ボクが思いつくのは古いんだけどいいかなあ。」と答えながら思い出したのがレベッカ・ブラウンでした。 どうせなら、もう、誰も読んでいないかもしれない「古い作品」を、もう一度読み直して「案内」してみようかと思いました。世の中の変化にあらがうというのが、老人の心意気という気張った気分もないではないのですが、あの頃いいと思った小説や映画を確かめ直してみたいという「自分探し(笑)」の気分もあります。今頃探してどうするというわけでもないのですが、いつまでもわからないのが自分自身だということは、あんまり変わりません。 件の女子大生には、まあ、とりあえず昔の投稿を紹介してみようと思います(笑)。ボタン押してね!にほんブログ村
2019.04.24
コメント(0)
-

週刊 読書案内 フィリップ・クローデル「リンさんの小さな子」(みすず書房)
フィリップ・クローデル「リンさんの小さな子」(みすず書房) フィリップ・クローデルという人のことをぼくは知りませんでした。そのクローデルの「リンさんの小さな子」(みすず書房)という作品は、たしか保坂和志の「試行錯誤に漂う」(みすず書房)というエッセイ集の中で、同じクローデルの「ブロデックの報告書」(みすず書房)いう作品が紹介されていて、読みもしていないのに、この作家の作品を立て続けに買いこみました。その中にあったのがこの作品でした。ぼくは時々そういう本の買い方をするのですが、紹介している人を信用しているか、尊敬している場合に、そういうことが起こります。今回は信用している場合ですね。 結果的にズバリ的中でした。この作品は2016年から2017年にかけてぼくが読んだ小説の中でベスト1といっていいと思います。 「リンさん」はその名の響きから類推すると東南アジアのどこかの国の貧しい農民であるらしいのですが、戦争の中で息子夫婦を失い、戦場となった故国を逃れ、たった一人残された孫、生まれたばかりの小さな女の子を連れてフランスに逃れてきた難民のようです。長い船旅のすえ、ようやくたどり着いたフランスの港町の難民収容所に暮らし始めたところから物語は始まります。 殺伐とした収容所を抜け出し、連れてきた小さな女の子を抱きかかえて街を歩き回る日々の中で、アジアの老人リンさんはフランス人の老人と知り合いになります。 フランスの老人は妻に先立たれたさみしい老後を暮らす身の上であるらしく、海の見える公園まで散歩してベンチに座り込みパイプ煙草をふかしながらボンヤリ思い出の時間を過ごすのが、毎日の日課です。そんなある日、彼はひとりの東洋人の老人と知り合いになるというわけですね。 妻も友達も失った人生の黄昏を生きるフランスの港町の老人と、働いてきた土地も家族も失い、望んだわけでもないのに異国の地に連れてこられたアジアの老人の出会いとお付き合いから、ほんのりとした友情が芽生えてゆきます。 フランスの老人はアジアのどこかの国から来た老人リンさんの言葉を理解できないし、リンさんはリンさんでフランス語が、まったく理解できません。二人は「こんにちは」というそれぞれ国の挨拶の言葉を互いの名前だと取り違えて呼びかけあっています。 実に頓珍漢な会話を交わしながら、互いの寂しさが感応しあい、読者には哀しさの響きが場面が変わるごとに木霊してくるように友達になってゆくのです。 小説は二人の老人の、奇妙といえば奇妙な友情を、淡々と描いてゆきます。友情というのは、本当はこういうものだと沁みってきます。60歳を越えた読者であるぼくは久しぶりに友達や友情について考えながらページを繰ってゆきます。 で、それが「生きる」ということが「いいことだ」 という考え方を支える大切な何かであったことに気づいてゆくのでした。「リンさんは、戦場の故郷で死ななくてよかった。死んでしまいたかったリンさんを支えたのが、残された小さな子の命を守るという文字どおり必死の思いであったのだが、生きていてよかった。」 そんな気持ちが、自然と湧いてくる二人の関係は実に自然なのです。 フランスの老人はリンさんの小さな子のために可愛らしいドレスをプレゼントし、かつて、誕生日には妻とやってくることにしていたレストランでの食事に招待します。リンさんは小さな子にフランスの子供服を着せ、初めて食べるフランス料理やワインがおいしいのか、まずいのかわからない不思議な喜びを味わうのですが、フランスの老人にはそんなリンさんの様子が面白くてしようがない光景です。 しかし、小説はここでは終わりませんでした。やがて、リンさんは、最初に収容された場所から、新しい収容施設への移動を命じられます。同じ町の中にあるらしい、美しく清潔な建物へ自動車で運ばれたリンさんは、そこがどういう場所であるのか、なぜそこに運び込まれたのか、そこにいる人々は何をする人なのか全くわかりません。 読者にも、もちろん、よくわかりません。わかるのは、監視付ではありますが善意の施設であるということだけなのです。リンさんが何故ここへ移送されるか、その理由がよくわかりません。 なんとなく隠されている秘密があります。小説のどこかにあるに違いない謎がほのめかされています。そんな感じが、読みながら漂ってくるのです。しかし、何が謎であるのかは読み取ることができません。 その美しい白亜の建物には門番がいてリンさんは繰り返し外出しようと試みるのですが、行動は監視され、外出は禁じられています。リンさんは友達と会うことができません。意を決したリンさんは、その建物からの脱走を試みます。まんまと施設からは逃げだすことに成功したものの、友達がいつもいるはずの港の見える公園がどこにあるのかわかりません。 しかし、ひたすら街をさまよい続けたリンさんは、ついに、あの友達の姿を見つけるのでした。 友達を見つけた喜びに思わず車道に駆け出したリンさんを、無情にも一台の自動車が跳ね飛ばしてしまいます。瀕死のリンさんと投げ出された小さな子がフランスの老人の目に映ります。 小説はそこで終わります。そこで初めて読者は、二人の老人の悲しみの、本当の深さを知ることになるのでした。作品の哀しみの深さはリンさんの「無残な死」にではなく「小さな子供との生」のほうにあったことに気づくのです。 謎は作品の最初から隠されていた?いや、リンさんの真実の悲惨は、読者のぼくには、あからさまに見えすぎていて気付かなかっただけのことだったのです。謎はリンさんと一緒にずっと見えていたのです。ぼくは驚くべき結末に絶句して座り込んでしまいました。 知られていない作品ですが、傑作! だと思いました。どうぞ、読んでみてください。(S)ボタン押してね!ボタン押してね!
2019.04.24
コメント(0)
全53件 (53件中 51-53件目)











