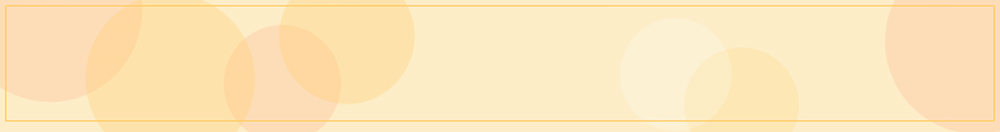カテゴリ: 旅行
筑波山には古くから四面薬師と言われる薬師が四カ所ある。筑波山を四方から守るためのものである。桜川市の椎尾山薬王堂、土浦市の東城寺、石岡市菖蒲沢の薬師堂、石岡市小幡の山寺(現在は廃寺)の四カ所です。今回、奇しくも2カ所を散策することになりました。東城寺は、796年(延暦15年)天台宗最澄の弟子である最仙により創建された寺である。最仙は、行方市にも782年(延暦元年)に西蓮寺を建立しています。写真を見て両者を比較すると、この東城寺の方が立派に見えます。
東城寺の駐車場の場所を探したが見つからなかった。駐車場の位置を示す立て看板等もないのはお粗末である。後から分かったことだが、この山門から続く狭くて薄暗い参道を車で登って行き、成り行きで左へ折れると駐車場がある。
東城寺への参道は結構急である。敷石は段差が大きくガタガタで昇りにくい。これでは、参拝者は敬遠してしまう。
しかし、なぜ筑波山の南側、八郷につながるこの地が平安時代から開けていたのだろうか、不思議である。
796年(延暦15年)最仙の開山により創建された寺で、当初は常陸国における天台宗の拠点のひとつであった。鎌倉時代初期小田氏の尊崇を受け真言宗に改められた。江戸時代には江戸幕府から朱印状を与えられていた(Wikipediaより)。
一方、創建者が徳一法師によるものであると思わせる記述もあります【注】。日本の歴史は出典が明確でなく「言ったもの勝ち」の様相を持つものが多く、あまり好きではありません。昨年のNHKの大河ドラマ「西郷どん」にしても、原作が林真理子というのも可笑しな話である。全てが作り話ですと言うようなものだ。
境内には池を持つ立派な庭があります。池には大きな鯉がたくさんいます。参拝者が極少ないと思わせる程、大口を開けてエサを求めてきました。
立派な鐘楼も残っています。霞ヶ浦も見通せ、いい眺めです。東の国の天台宗の拠点として栄華を極めていた時代を彷彿させてくれます。
東城寺のお詣りを終え、車を置いている日枝神社へ戻り、日枝神社境内を散策。この当たりでは、流鏑馬祭りが有名である。境内も結構な広さである。
昼食は定番の「そば」。朝日トンネルを抜け辻交差点を右折して田舎道をゆくと、「野の花」工房の渡辺氏お薦めのそば処「まいえ」(真家)があります。暖かソバを食べましたが、おつゆの味は絶品でした。
「まいえ」から見る筑波山は初めて見る角度でした。二峰が面白く見えました。
石岡市菖蒲沢の薬師堂のぶらり旅を思いついたきっかけは、陶芸家の渡辺氏の推薦に依る。渡辺氏との出会いは20年以上前の益子陶芸祭りである。それ以来、渡辺氏の 「野の花」 の絵柄の茶碗、湯飲み、お椀などを日常で愛用しています。野の花の素朴な絵柄は最高です。10年前に渡辺氏の工房を見せていただたいたことがあり、山を登ってゆくと薬師堂があるとは聞いていました。今回も渡辺氏の工房に車を駐車させていただいた。参道入り口には、薬師堂のプレートが備え付けられていた。
人家から離れると細いが整備された山道が続いている。
参道脇には、いつくもの石碑や社などが点在している。歴史の古さを物語っている。部落の住まわれている方々は定期的にこの参道を整備されているらしい。また、たいそうな寄附も実施されていることも聞いた。
薬師堂に近づくと山王門跡がありました。いつしか山道から平坦な広い路が続いていた。
山王門を過ぎると、深い谷(10mくらいか)があり、急な石階段を下りてゆきます。谷底には50m四方の池をたずさえた庭があります。しっとりとした霊感を感じさせる空間で、石階段には苔がビッシリと張り付いていました。
この空間で華やかなお茶会でも行われたのではないかと夢想されます。
堀を通り過ぎると、また階段があります。薬師堂へ昇る階段です。
今回の東城寺と菖蒲沢薬師堂の散策をスライドショーにまとめました。
このぶらり旅のお蔭?で、筑波山麓の歴史を少々勉強することになりました。印象に残ったのは、
1)奈良時代後期から平安時代初期に、天台宗の最澄、真言宗の空海、そして奈良時代に隆盛を極めた南都六宗のひとつ法相宗の徳一が力を持っていたこと。
2)徳一はあまり有名でないが、空海と最澄に並び称される程偉い僧だったこと。
3)そして一番頭に残ったことは、当時の日本の最高権力者である天皇に認められることが宗教者にとって一番重要なことだったということであり、宗教の普及は権力執行の裏返しであることが理解できた。
いやな言い方だが、いつの時代も忖度(言い換えればゴマスリ)が重要なのだ。
【注】
奈良時代の後期に、法相宗を学んだ徳一法師は若干20歳位の若い時に、京都から東国にやってきた。そして、常陸国などの主に山岳やその麓に多くの寺を創建していった。その後会津に行き恵日寺を興し、空海など思想論争などをした優れた高僧ですが、今では東国に建てた寺はほとんど別の宗派になっている。
延暦元年(782年)に、 徳一法師 が筑波山に中禅寺を創建し、この寺が筑波神社の隣りにある「大御堂」に発展していったとされます。徳一の開創あるいは徳一が活動したことを伝える寺院が数多くある。陸奥国・会津の慧日寺や勝常寺、常陸国の筑波山・中禅寺(大御堂)、西光院など陸奥南部~常陸にかけて多くの寺院を建立したとされる徳一法師は、万民安楽の祈願として、この筑波山の「中禅寺」の守護のために 筑波山の四面に薬師如来を安置 しました。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[旅行] カテゴリの最新記事
-
2021年の八重桜見物。 タケノコは2… April 11, 2021
-
な・こ・そ 「来ないで」と言われて幾十… August 8, 2020
-
2020/02/20 水戸偕楽園の梅まつり 誕… February 20, 2020
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.