全て
| カテゴリ未分類
| 生活をよくする
| 本の紹介
| 共に生き、共に育つ
| たのしいべんきょう
| 個人的な日記
| 体育
| 音楽♪
| 道徳 等
| 問題解決
| 考え方
| 話し合い・話す・聞く
| 特別支援教育
| 小学校
| 阪神間 地域情報
| PC・デジタル関係
| 教材・教具
| 食育(自立生活・家庭科)・園芸
| 仕事術
| 旅行(温泉含む)
| 英語学習
| 環境保護・エコ
| 作文・書くこと・漢字
| よのなか(社会)
| いのち
| 人間関係・コミュニケーション
| 子育て
| 地震・防災
| 算数
| 心理・カウンセリング・セラピー
| 読む・音読・朗読
| エクセルでのプログラミング
| 北播丹波 地域情報
| 教員免許
| 教育改革
| 休校期間お役立ち情報
| 映画 等
| 創造性をはぐくむ
| プレゼン
| 通級
| 健康
| ゲーム
カテゴリ: 共に生き、共に育つ
これは、4年前の2016年度に、自分の勤務校の個人研究で私案として出したものです。
そのころ僕の勤務校は「道徳」の研究をしていたので、個人個人が研究課題をもって研究を進める、という取組をしていたのでした。
皆さんのお役に立つかもしれないと思い、今までヒミツにしてましたが、公開します。いや、そんな大それたものじゃ、ないですが。 (^^;)
僕のそのときの個人研究テーマは、
でした。
その時に書いた研究レポートから、少し引用します。
勤務市では、ずっと以前から、支援学級在籍の子どもも、道徳の時間を支援学級ではなく 集団の場の中で一緒に学習する ことが主流でした。ただ、4年前の時点では、それによる課題も、散見される状況でした。
ついでに、<問題意識>というところも、引用しておきます。
特に、高学年になると道徳の授業で扱う読み物資料が、長くなり、要点を把握することが難しくなるために、「支援学級で道徳をしたほうがいい」と言われることが増えます。
支援学級在籍であるか否かにかかわらず、その場で初めて目にする道徳資料の読解ができないせいで、授業の核心的話題についていけなくなっている子どもが、少なからずいるようにも、感じています。
実際に、全国的には「道徳」は支援学級で行っているケースのほうが多いと思います。
おそらくその中で優れた道徳実践もたくさんあるのだと思いますが、今回は、インクルーシブ教育の流れの中で、「道徳授業をみんなの中で一緒にやる」ということを前提に、考えます。
一応、分かりやすくするために、支援学級在籍のAさんが、5年生の「道徳」の授業を、通常学級の場の中で受けることについて、考えてみたいと思います。
(現在は、「道徳」は「道徳科」になっています。
また、Aさんは架空の例であり、僕がこれまで経験した情報から想定したモデルケースです。)
Aさんは「国語」の授業はすべて支援学級で学習しており、物語文や説明文の読解には、かなりの支援を必要とします。
ただ、たとえば下学年の内容を特別に用意しておいたとしても、「みんなと同じ勉強がいい」と主張します。本人にもプライドがあります。5年生なのに、3年生の内容をしているなんて、自尊心が許さないのです。そこで、5年生の国語の教科書教材を使いつつ、支援学級で手立てを工夫することにより、国語は日常的に学習を進めています。
「道徳」の読みもの教材についても、「国語」と同様に、高学年の資料になると、内容理解ができないということがよくあります。それでも、本人は、「みんなの中で勉強する」と言います。
そのため、「交流」学級で「道徳」の授業を一緒に受けていますが、実際には資料の内容が分からないので、ほとんど授業に参加できていません。ただ「いるだけ」になっているように見えます。
みんなと一緒にできないのでしょうか?
僕の場合は、 「みんなと同じ」教材や資料をその子も使うことを前提に 、いかにその子に分かりやすく支援するか、を考えて、 補う教材や作戦を準備 していました。
例えば、「道徳」をみんなと同じ場でする場合、以下のような3つの視点で、配慮や支援を考え、事前に用意したり、「交流」の際にその子について下さる支援の先生にお願いしたりしていました。
(実際は、事前の準備が間に合わなかったりもするので、支援学級担任であった僕が「道徳」の時間にその教室に入り込んで支援することも、多かったです。)
(1) 状況理解のための合理的配慮
(ふりがな・絵・実物・実例・見本を示す
・一時的にそばにつく 等)
+
(2) 思いに気づかせるための支援
(表情カード等から選ぶ・具体例に引きつける 等)
+
(3) 思いを場に出すことへの支援
(選択肢、代筆、代弁 等)
状況理解のための合理的配慮 」は、国語の読み取りの授業で行っていることを、道徳の授業の際にも適用します。
教科書そのままでは内容理解が難しい場合などに、本人に合わせてリライトした(書き直した)教材を 「リライト教材」 と呼んだりしますが、そういったものを作ったり、理解を促すための絵を絵本からとってきたり、4コマ漫画的なものを即興で僕が描いたりするなど、抽象的なものを具体的なものに落とし込む工夫をします。
(2)の「 思いに気づかせるための支援 」は、道徳ですので、 登場人物の心情に気づかせる ことを重要視して、そのための支援をすることを指しています。
僕は物語文の読解などで、中心人物の心情を 表情カード から選ばせる手法をとることがありましたので、たとえばそういう手法で、「このときの主人公は、泣き顔だった」「こっちの場面では、笑顔」などを選択して、気持ちに気づかせることができれば、と考えたものです。
(3)の「 思いを場に出すことへの支援 」は、せっかくクラスメイトと一緒に学んでいるので、本人の考えをみんなの中で表現できるように、そのための支援をする、ということです。といっても、例に挙げているのはわりと安直な支援で、 本人が言えないようなら、そばで聞いていた者が、全体の場に代わりに言ってあげる 、などです。僕は声を出すことがなかなか難しいお子さんも担任していたことがあるので、全体の場に本人の意思を伝えることを当たり前にやっていた時期があり、そういうことには抵抗がありません。本人が自分で言えたらいいですが、「代わりに言ってやってもかまわないんじゃないの」と思います。本人は、代弁した後、周りの子が反応してくれるのを、けっこううれしそうにしていることが多いです。やはり、自分の考えに反応がもらえると、うれしいものですね。
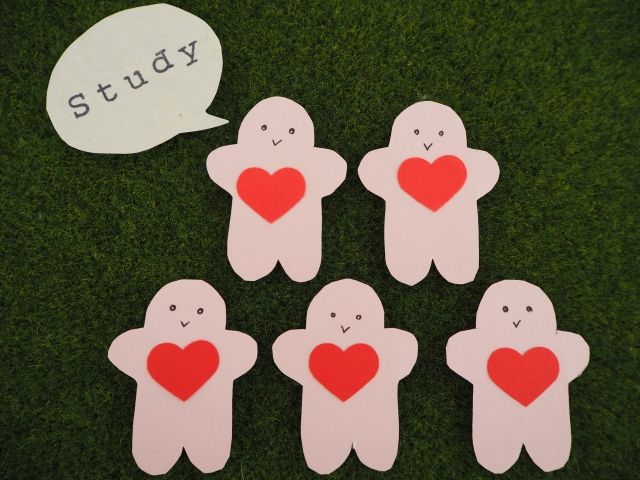
(画像提供:写真AC)
まとめ!
「国語」と違って「道徳」では、物語文の内容をきっちりと読み取る必要はありません。
「○○にどんな思いがこめられているか」に気づくことこそが、大事です。
そこで僕が考えた、道徳で「心が動く」ための手立てが、以上のようなものでした。
もしも皆様のご参考になるところがあれば、幸いです。
P.S.
今回の内容を読むと、僕は「道徳はみんなと一緒にして、国語は支援学級で学習する」という考え方だと思われるかもしれません。
実は、違うんです。
実際は、僕は「国語」も、支援学級ではなく、みんなの中で学習するのが理想だと思っています。
それについては、また別の機会に・・・。
そのころ僕の勤務校は「道徳」の研究をしていたので、個人個人が研究課題をもって研究を進める、という取組をしていたのでした。
皆さんのお役に立つかもしれないと思い、今までヒミツにしてましたが、公開します。いや、そんな大それたものじゃ、ないですが。 (^^;)
僕のそのときの個人研究テーマは、
国語的能力にかかわらず、
誰もが実感を伴って学べる道徳教育
誰もが実感を伴って学べる道徳教育
でした。
その時に書いた研究レポートから、少し引用します。
<概要とその理由>
「国語」と「道徳」はちがうにもかかわらず、国語的能力(読み取りの力、話す力、聞く力など)が前提となって、道徳的活動が計画されていることがあるように思う。
支援学級在籍の子も道徳はみんなと一緒に学ぶので、それをふまえて、国語の力によらない道徳の学習を確立していく必要がある。
それがどのようなものかを研究する。
「国語」と「道徳」はちがうにもかかわらず、国語的能力(読み取りの力、話す力、聞く力など)が前提となって、道徳的活動が計画されていることがあるように思う。
支援学級在籍の子も道徳はみんなと一緒に学ぶので、それをふまえて、国語の力によらない道徳の学習を確立していく必要がある。
それがどのようなものかを研究する。
勤務市では、ずっと以前から、支援学級在籍の子どもも、道徳の時間を支援学級ではなく 集団の場の中で一緒に学習する ことが主流でした。ただ、4年前の時点では、それによる課題も、散見される状況でした。
ついでに、<問題意識>というところも、引用しておきます。
<問題意識>
・特別支援学級の担任や通級の担当をすることが長かった。
それゆえ、通常学級での全体授業の中で、「その子も含めたクラス」「その子も含めた授業」がどれだけ工夫されているかに敏感になっている。
支援学級児童も「道徳」はみんなと一緒に授業を受けることが基本であると思うが、「国語」の授業のようになってしまっては、授業への参加自体が厳しい。
・道徳の時間は非常に重要である。
教師の思いや児童相互の思い・考えを交流し、どんなクラスをつくりたいか、どんな人間になりたいかの方向性をつくるものになる。
ダメな道徳の授業は「お題目」「きれいごと」で終わってしまうもの、心を伴わないものである。
よい道徳の授業は、心が動く授業、授業後の感動がその後の実践意欲につながる授業である。
・特別支援学級の担任や通級の担当をすることが長かった。
それゆえ、通常学級での全体授業の中で、「その子も含めたクラス」「その子も含めた授業」がどれだけ工夫されているかに敏感になっている。
支援学級児童も「道徳」はみんなと一緒に授業を受けることが基本であると思うが、「国語」の授業のようになってしまっては、授業への参加自体が厳しい。
・道徳の時間は非常に重要である。
教師の思いや児童相互の思い・考えを交流し、どんなクラスをつくりたいか、どんな人間になりたいかの方向性をつくるものになる。
ダメな道徳の授業は「お題目」「きれいごと」で終わってしまうもの、心を伴わないものである。
よい道徳の授業は、心が動く授業、授業後の感動がその後の実践意欲につながる授業である。
特に、高学年になると道徳の授業で扱う読み物資料が、長くなり、要点を把握することが難しくなるために、「支援学級で道徳をしたほうがいい」と言われることが増えます。
支援学級在籍であるか否かにかかわらず、その場で初めて目にする道徳資料の読解ができないせいで、授業の核心的話題についていけなくなっている子どもが、少なからずいるようにも、感じています。
実際に、全国的には「道徳」は支援学級で行っているケースのほうが多いと思います。
おそらくその中で優れた道徳実践もたくさんあるのだと思いますが、今回は、インクルーシブ教育の流れの中で、「道徳授業をみんなの中で一緒にやる」ということを前提に、考えます。
一応、分かりやすくするために、支援学級在籍のAさんが、5年生の「道徳」の授業を、通常学級の場の中で受けることについて、考えてみたいと思います。
(現在は、「道徳」は「道徳科」になっています。
また、Aさんは架空の例であり、僕がこれまで経験した情報から想定したモデルケースです。)
Aさんは「国語」の授業はすべて支援学級で学習しており、物語文や説明文の読解には、かなりの支援を必要とします。
ただ、たとえば下学年の内容を特別に用意しておいたとしても、「みんなと同じ勉強がいい」と主張します。本人にもプライドがあります。5年生なのに、3年生の内容をしているなんて、自尊心が許さないのです。そこで、5年生の国語の教科書教材を使いつつ、支援学級で手立てを工夫することにより、国語は日常的に学習を進めています。
「道徳」の読みもの教材についても、「国語」と同様に、高学年の資料になると、内容理解ができないということがよくあります。それでも、本人は、「みんなの中で勉強する」と言います。
そのため、「交流」学級で「道徳」の授業を一緒に受けていますが、実際には資料の内容が分からないので、ほとんど授業に参加できていません。ただ「いるだけ」になっているように見えます。
みんなと一緒にできないのでしょうか?
僕の場合は、 「みんなと同じ」教材や資料をその子も使うことを前提に 、いかにその子に分かりやすく支援するか、を考えて、 補う教材や作戦を準備 していました。
例えば、「道徳」をみんなと同じ場でする場合、以下のような3つの視点で、配慮や支援を考え、事前に用意したり、「交流」の際にその子について下さる支援の先生にお願いしたりしていました。
(実際は、事前の準備が間に合わなかったりもするので、支援学級担任であった僕が「道徳」の時間にその教室に入り込んで支援することも、多かったです。)
(1) 状況理解のための合理的配慮
(ふりがな・絵・実物・実例・見本を示す
・一時的にそばにつく 等)
+
(2) 思いに気づかせるための支援
(表情カード等から選ぶ・具体例に引きつける 等)
+
(3) 思いを場に出すことへの支援
(選択肢、代筆、代弁 等)
状況理解のための合理的配慮 」は、国語の読み取りの授業で行っていることを、道徳の授業の際にも適用します。
教科書そのままでは内容理解が難しい場合などに、本人に合わせてリライトした(書き直した)教材を 「リライト教材」 と呼んだりしますが、そういったものを作ったり、理解を促すための絵を絵本からとってきたり、4コマ漫画的なものを即興で僕が描いたりするなど、抽象的なものを具体的なものに落とし込む工夫をします。
(2)の「 思いに気づかせるための支援 」は、道徳ですので、 登場人物の心情に気づかせる ことを重要視して、そのための支援をすることを指しています。
僕は物語文の読解などで、中心人物の心情を 表情カード から選ばせる手法をとることがありましたので、たとえばそういう手法で、「このときの主人公は、泣き顔だった」「こっちの場面では、笑顔」などを選択して、気持ちに気づかせることができれば、と考えたものです。
(3)の「 思いを場に出すことへの支援 」は、せっかくクラスメイトと一緒に学んでいるので、本人の考えをみんなの中で表現できるように、そのための支援をする、ということです。といっても、例に挙げているのはわりと安直な支援で、 本人が言えないようなら、そばで聞いていた者が、全体の場に代わりに言ってあげる 、などです。僕は声を出すことがなかなか難しいお子さんも担任していたことがあるので、全体の場に本人の意思を伝えることを当たり前にやっていた時期があり、そういうことには抵抗がありません。本人が自分で言えたらいいですが、「代わりに言ってやってもかまわないんじゃないの」と思います。本人は、代弁した後、周りの子が反応してくれるのを、けっこううれしそうにしていることが多いです。やはり、自分の考えに反応がもらえると、うれしいものですね。
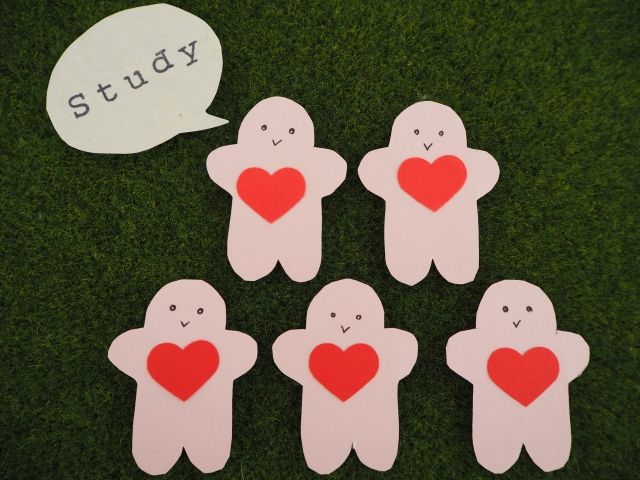
(画像提供:写真AC)
まとめ!
「国語」と違って「道徳」では、物語文の内容をきっちりと読み取る必要はありません。
「○○にどんな思いがこめられているか」に気づくことこそが、大事です。
そこで僕が考えた、道徳で「心が動く」ための手立てが、以上のようなものでした。
もしも皆様のご参考になるところがあれば、幸いです。
P.S.
今回の内容を読むと、僕は「道徳はみんなと一緒にして、国語は支援学級で学習する」という考え方だと思われるかもしれません。
実は、違うんです。
実際は、僕は「国語」も、支援学級ではなく、みんなの中で学習するのが理想だと思っています。
それについては、また別の機会に・・・。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[共に生き、共に育つ] カテゴリの最新記事
-
6/29シンポジウム「インクルーシブ教育の… 2024.05.24
-
矢田明恵「海外のインクルーシブ教育~フ… 2024.05.23
-
ADHDの子どもにとって動くことは必要! … 2024.05.16
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Category
カテゴリ未分類
(57)生活をよくする
(204)共に生き、共に育つ
(174)たのしいべんきょう
(146)体育
(12)本の紹介
(176)音楽♪
(275)道徳 等
(12)問題解決
(104)考え方
(146)個人的な日記
(161)話し合い・話す・聞く
(36)特別支援教育
(188)小学校
(78)阪神間 地域情報
(36)PC・デジタル関係
(328)教材・教具
(24)食育(自立生活・家庭科)・園芸
(15)旅行(温泉含む)
(75)環境保護・エコ
(26)仕事術
(74)英語学習
(26)作文・書くこと・漢字
(20)よのなか(社会)
(47)いのち
(27)人間関係・コミュニケーション
(90)子育て
(33)算数
(11)地震・防災
(16)心理・カウンセリング・セラピー
(30)読む・音読・朗読
(9)エクセルでのプログラミング
(21)北播丹波 地域情報
(4)教員免許
(2)教育改革
(34)休校期間お役立ち情報
(21)映画 等
(15)創造性をはぐくむ
(5)プレゼン
(12)通級
(2)健康
(3)ゲーム
(1)Keyword Search
▼キーワード検索
Free Space
<読書>
※過去の「読書メモ」のリストを作成中。
<ICT活用>
Wordの音声入力が進化していた!
GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」
GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。
GIGA スクール以後の、今後の方向性について
<特別支援教育>
オリジナル標語
自傷行為のある子への取り組み
「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える
運動会のBGMで耳をふさぐ子がいたら、BGMのエフェクトを試してみよう
<「今日行く」ユースフル>
駐車場検索のやり方
三宮格安駐車場
♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク
<「教育」ユースフル>
教材・教具
携帯コミュニケーションボードCoBo(コボ)
※リンク※
★にかとまのホームページ ※NEW
にかとま情報局
エクセル野球シミュレーションゲーム「ダイナミック・ベースボール」のページ
にかとまの音楽のページ
※過去の「読書メモ」のリストを作成中。
<ICT活用>
Wordの音声入力が進化していた!
GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」
GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。
GIGA スクール以後の、今後の方向性について
<特別支援教育>
オリジナル標語
自傷行為のある子への取り組み
「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える
運動会のBGMで耳をふさぐ子がいたら、BGMのエフェクトを試してみよう
<「今日行く」ユースフル>
駐車場検索のやり方
三宮格安駐車場
♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク
<「教育」ユースフル>
教材・教具
携帯コミュニケーションボードCoBo(コボ)
※リンク※
★にかとまのホームページ ※NEW
にかとま情報局
エクセル野球シミュレーションゲーム「ダイナミック・ベースボール」のページ
にかとまの音楽のページ
Calendar
Comments
© Rakuten Group, Inc.




