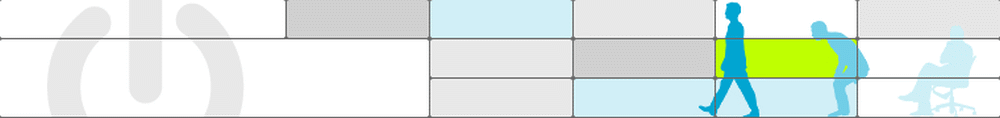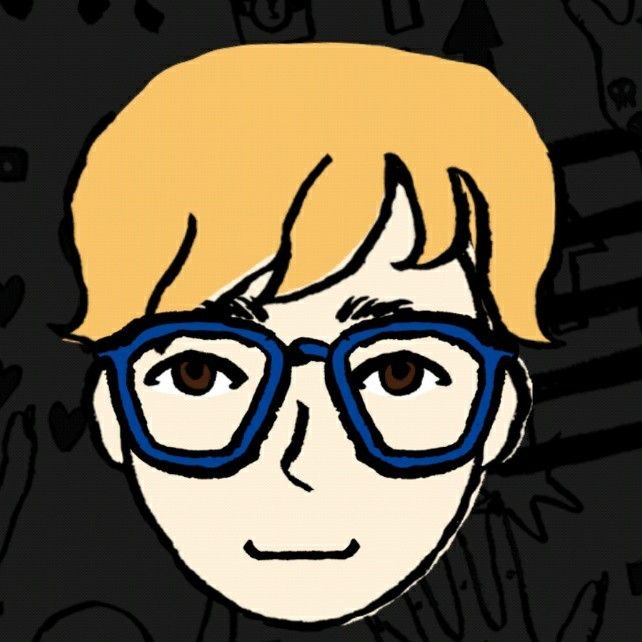PR
X
カレンダー
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
カテゴリ未分類
(42)コンサルタントの仕事
(21)心理学・カウンセリング
(21)ビジネス成功法
(68)ひとりごと
(96)孫子・三国志
(14)子育て・教育
(19)健康・ダイエット
(35)注目楽天商品
(11)フード&ドリンク
(15)職場のメンタルヘルス
(3)音楽
(2) 「光る君へ」第二十…
ayakawa777さん
やまちんWEB あかねママ0208さん
田舎人しょ~きちの… しょ〜きちさん
健康増進 病気予防… 抗加齢実践家てるさん
ママ日記。。。 meidogさん
やまちんWEB あかねママ0208さん
田舎人しょ~きちの… しょ〜きちさん
健康増進 病気予防… 抗加齢実践家てるさん
ママ日記。。。 meidogさん
コメント新着
2024.06
2024.05
2024.04
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02
2024.02
テーマ: 仕事しごとシゴト(23404)
カテゴリ: 心理学・カウンセリング
近頃、産業カウンセリング業界では、メンタル・ヘルスやキャリア・コンサルティングの他に、人間関係開発という分野に力を入れているようだ。
従業員の悩みは、会社での人間関係が一番多い。
男性の場合、上司との人間関係、女性の場合、同僚との人間関係の問題が一番多いようだ。
それに加え、近年、企業はIT化が進み、従業員同士が、直接、話をしなくても仕事ができるようになったり、成果主義によって従業員同士の競争が激しくなったり、従業員が孤立する傾向にある。
このように従業員のメンタルヘルスが悪化し、従業員間のコミュニケーションが不足すれば、企業の生産性も当然低下する。
これは企業にとって深刻な問題。
であれば組織の人間関係に直接アプローチして改善しようという考え方はもっともだ。
では人間関係開発は、どのようなことをするのか?
産業カウンセラー協会の大会の研究発表を見ると、方法論はまだ確立されていないし、それを裏付けるデータも不足してはいるが、いろいろな試みが行われ、それなりに成果が得られていることがわかった。
例1 上下のコミュニケーションが不足している会社
管理職が技術者指向でコミュニケーション下手
カウンセラーが上司と部下それぞれにインタビューを行って、それぞれ相手に対してどのような感情を持っているか聴き、それぞれの誤解を解消する。
上司は部下を飲みに誘ったが、部下が「それは残業がつくのですか?」の質問にショックを受け、コミュニケーションの断絶ができてしまった。しかし、部下に真相を聞いたところ、実は大事な予定が入っていて、旨く断る表現が見つからなかった。
例2 上下のコミュニケーションが不足している会社
顧客からのプレッシャーが大きい
ある部署の人を全員集め、会社の課題について役職とは無関係に自由に意見を言い合う。
役職で呼んでは駄目、他人の意見を批判しては駄目。
話し下手な人がぃる場合はクッションボールなど使って話やすい環境を作る。
例3 管理職同士のコミュニケーションが少なく
セクショナリズムが蔓延している会社。
こういう中で行われるディスカッションは従来の論理中心ではなく、浮かび上がった問題について、気持ちを率直にしてホンネで話し合い、それぞれの気持ちを互いに認め合う体験を得る方法(構成的エンカウンター)が取り入れられている。
JR西日本のような企業の不祥事でもわかるように、従業員は、知識としてわかっていても気持ちがついていかないという問題が浮かび上がっており、企業経営においても論理だけでなく感情というものを、しっかり扱っていかなければならないようだ。
カウンセラーは、こういったワークショップのファシリテーターとしてグループをリードする。
感情面まで旨く引き出し、参加者が共感できるようにする。
このような取り組みによって、ある会社では退職率を大幅に低減し、事業拡大に成功したそうだ。
確かに僕の会社(コンサルティング会社)も、人の入れ替わりが激しく、中途入社が多く、プロジェクト以外の従業員間のコミュニケーションが希薄で、会社全体として結束力が弱い。
何かきっかけを作らないと会社の一員としての意識を共有し、一員としての存在意識を持つことは難しい。
そういう会社は、どんどん増えていくように思う。
こういったトレーニングは、きっと、人間関係改善のきっかけ作りになるだろう。
ただ、これを企業風土までに育てていくには、継続的、発展的に進めていけるプログラムやツールを作る必要があるだろう。
現実には、まだまだ経営者の問題意識は低く、予算面で折り合わないことが多いようだ。
予算面を考えれば、例3のように、まずは経営者層、上級管理職層に対してのアプローチが良いのではないかと思う。
いろいろな事例を増やし、データを蓄積・共有し、方法論化し、ファシリテーター役が務まるコンサルタント(またはカウンセラー)を育成する。
導入効果を定量化(離職率、売上・利益、顧客満足度など)し、アピールできれば、企業はお金を出すだろうし、企業風土の進歩に役立つだろう。
従業員の悩みは、会社での人間関係が一番多い。
男性の場合、上司との人間関係、女性の場合、同僚との人間関係の問題が一番多いようだ。
それに加え、近年、企業はIT化が進み、従業員同士が、直接、話をしなくても仕事ができるようになったり、成果主義によって従業員同士の競争が激しくなったり、従業員が孤立する傾向にある。
このように従業員のメンタルヘルスが悪化し、従業員間のコミュニケーションが不足すれば、企業の生産性も当然低下する。
これは企業にとって深刻な問題。
であれば組織の人間関係に直接アプローチして改善しようという考え方はもっともだ。
では人間関係開発は、どのようなことをするのか?
産業カウンセラー協会の大会の研究発表を見ると、方法論はまだ確立されていないし、それを裏付けるデータも不足してはいるが、いろいろな試みが行われ、それなりに成果が得られていることがわかった。
例1 上下のコミュニケーションが不足している会社
管理職が技術者指向でコミュニケーション下手
カウンセラーが上司と部下それぞれにインタビューを行って、それぞれ相手に対してどのような感情を持っているか聴き、それぞれの誤解を解消する。
上司は部下を飲みに誘ったが、部下が「それは残業がつくのですか?」の質問にショックを受け、コミュニケーションの断絶ができてしまった。しかし、部下に真相を聞いたところ、実は大事な予定が入っていて、旨く断る表現が見つからなかった。
例2 上下のコミュニケーションが不足している会社
顧客からのプレッシャーが大きい
ある部署の人を全員集め、会社の課題について役職とは無関係に自由に意見を言い合う。
役職で呼んでは駄目、他人の意見を批判しては駄目。
話し下手な人がぃる場合はクッションボールなど使って話やすい環境を作る。
例3 管理職同士のコミュニケーションが少なく
セクショナリズムが蔓延している会社。
こういう中で行われるディスカッションは従来の論理中心ではなく、浮かび上がった問題について、気持ちを率直にしてホンネで話し合い、それぞれの気持ちを互いに認め合う体験を得る方法(構成的エンカウンター)が取り入れられている。
JR西日本のような企業の不祥事でもわかるように、従業員は、知識としてわかっていても気持ちがついていかないという問題が浮かび上がっており、企業経営においても論理だけでなく感情というものを、しっかり扱っていかなければならないようだ。
カウンセラーは、こういったワークショップのファシリテーターとしてグループをリードする。
感情面まで旨く引き出し、参加者が共感できるようにする。
このような取り組みによって、ある会社では退職率を大幅に低減し、事業拡大に成功したそうだ。
確かに僕の会社(コンサルティング会社)も、人の入れ替わりが激しく、中途入社が多く、プロジェクト以外の従業員間のコミュニケーションが希薄で、会社全体として結束力が弱い。
何かきっかけを作らないと会社の一員としての意識を共有し、一員としての存在意識を持つことは難しい。
そういう会社は、どんどん増えていくように思う。
こういったトレーニングは、きっと、人間関係改善のきっかけ作りになるだろう。
ただ、これを企業風土までに育てていくには、継続的、発展的に進めていけるプログラムやツールを作る必要があるだろう。
現実には、まだまだ経営者の問題意識は低く、予算面で折り合わないことが多いようだ。
予算面を考えれば、例3のように、まずは経営者層、上級管理職層に対してのアプローチが良いのではないかと思う。
いろいろな事例を増やし、データを蓄積・共有し、方法論化し、ファシリテーター役が務まるコンサルタント(またはカウンセラー)を育成する。
導入効果を定量化(離職率、売上・利益、顧客満足度など)し、アピールできれば、企業はお金を出すだろうし、企業風土の進歩に役立つだろう。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[心理学・カウンセリング] カテゴリの最新記事
-
フォーカシング 心を癒すお気軽な瞑想法 2008.03.25 コメント(6)
-
解決志向とポジティブ思考の違い? 2008.03.14 コメント(2)
-
夢は大きく目標は小さく 2008.03.13 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.