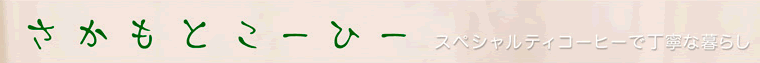カテゴリ: コーヒーの焙煎を考える
急に雨が降ったと思ったら、一気に晴れ上がり、グングン暑くなってきました。今朝の焙煎は今年一番の暑さでした。焙煎終了後のアイシングが気持ちよいです。
そんなこんなで…「コーヒーの焙煎を考える(21)」です。
昔、そうですねー、20年?25年?位前になるでしょうか。
「紅茶は発酵の魅力」って自分の中で答えが出ていたんですが、
「コーヒーの魅力」って、どう捉えたらよいのか?
酸もあるし、苦味もあるし、
なんだか、重い味わいだし、
なかなかまとまっていなかった頃です。
柴田書店の「月刊喫茶店経営」の記事で、
「焙煎は、コーヒーのカラメル化」
うろ覚えですが、そんな言葉があったのがとっても印象的でした。
当時、そんなシンプルな表現が無かったんです。
なんだか訳の分からない目くらまし的表現ばかりで…。
ん?今も?
そこから、自分なりに色々と考えていったのですが、
「カラメル化」だけでは納得できなくて…
出会ったのが…
「乾熱調理」でした。
これで、
コーヒーは農産物で、
抽出したもの…
と、すっきりしました。
で、スペシャルティコーヒーに取り組んでも
そのまま微調整だけで済んでますので、
迷いが無いですね。
「NHK きょうの料理 味のしくみ」
河野友美著
日本放送出版協会
この本は何度も読み返して、料理や味のしくみを学びましたが、
その中の「加熱調理のポイント」で、
「乾熱調理」と「湿熱調理」を知りました。
加熱調理法は、大きくふたつに分けることができて…
-100℃以上、通常180℃付近の熱で行う調理法で、媒体に水を使わない調理法「乾熱調理」といわれる方法がひとつ。(焼く、揚げる、炒めるがこの中にはいる)
-100℃、またはそれ以下の温度で行う調理法で、水を媒体とする調理法「湿熱調理」と呼ばれる方法がもうひとつ。(煮る、ゆでる、蒸すがこの中にはいる)
-このふたつを比べると、湿熱調理では失敗が少ないのに対して、乾熱調理は失敗が多い
-湿熱調理では、媒体が水なので、普通100℃以上に上がることがなく、温度管理が容易である
-乾熱調理は、温度が高すぎれば焦げるし、低ければ水分がでて、べたべたなどして、温度管理が難しいから
-乾熱調理を失敗無く行うポイントは、温度の目安を180℃におくこと
-乾熱調理特有の美味しい香りを出す為にはこの温度が必要
-150℃以下ではこの香りが出ないし、200℃以上になると黒く焦げて嫌な匂いがでてくる
-乾熱調理には蒸す、煮るなどの調理法に比べて、何か魅力のある美味しさを持っている
-焼く調理のポイントは、ことばをかえて言えば、いかに状態の良いおこげをつくるかにある
-それは、大別すると3種の化学変化によって生成された物質が総合されたもの
-糖類のカラメル化
-脂肪の分解によるディープフライフレーバーの生成
-アミノカルボニル反応によってできるメラノイジン
今日はこの辺までです。
今、久しぶりにこの本のこのページを見ると、赤の書き込みだらけです。
コーヒーの焙煎を乾熱調理だと考えたところから、さかもとこーひーの焙煎の考え方がステップアップし、仮説検証を繰り返してきました。
で、スペシャルティコーヒーの焙煎のデベロップにつながったわけです。
そんなこんなで…「コーヒーの焙煎を考える(21)」です。
昔、そうですねー、20年?25年?位前になるでしょうか。
「紅茶は発酵の魅力」って自分の中で答えが出ていたんですが、
「コーヒーの魅力」って、どう捉えたらよいのか?
酸もあるし、苦味もあるし、
なんだか、重い味わいだし、
なかなかまとまっていなかった頃です。
柴田書店の「月刊喫茶店経営」の記事で、
「焙煎は、コーヒーのカラメル化」
うろ覚えですが、そんな言葉があったのがとっても印象的でした。
当時、そんなシンプルな表現が無かったんです。
なんだか訳の分からない目くらまし的表現ばかりで…。
ん?今も?
そこから、自分なりに色々と考えていったのですが、
「カラメル化」だけでは納得できなくて…
出会ったのが…
「乾熱調理」でした。
これで、
コーヒーは農産物で、
抽出したもの…
と、すっきりしました。
で、スペシャルティコーヒーに取り組んでも
そのまま微調整だけで済んでますので、
迷いが無いですね。
「NHK きょうの料理 味のしくみ」
河野友美著
日本放送出版協会
この本は何度も読み返して、料理や味のしくみを学びましたが、
その中の「加熱調理のポイント」で、
「乾熱調理」と「湿熱調理」を知りました。
加熱調理法は、大きくふたつに分けることができて…
-100℃以上、通常180℃付近の熱で行う調理法で、媒体に水を使わない調理法「乾熱調理」といわれる方法がひとつ。(焼く、揚げる、炒めるがこの中にはいる)
-100℃、またはそれ以下の温度で行う調理法で、水を媒体とする調理法「湿熱調理」と呼ばれる方法がもうひとつ。(煮る、ゆでる、蒸すがこの中にはいる)
-このふたつを比べると、湿熱調理では失敗が少ないのに対して、乾熱調理は失敗が多い
-湿熱調理では、媒体が水なので、普通100℃以上に上がることがなく、温度管理が容易である
-乾熱調理は、温度が高すぎれば焦げるし、低ければ水分がでて、べたべたなどして、温度管理が難しいから
-乾熱調理を失敗無く行うポイントは、温度の目安を180℃におくこと
-乾熱調理特有の美味しい香りを出す為にはこの温度が必要
-150℃以下ではこの香りが出ないし、200℃以上になると黒く焦げて嫌な匂いがでてくる
-乾熱調理には蒸す、煮るなどの調理法に比べて、何か魅力のある美味しさを持っている
-焼く調理のポイントは、ことばをかえて言えば、いかに状態の良いおこげをつくるかにある
-それは、大別すると3種の化学変化によって生成された物質が総合されたもの
-糖類のカラメル化
-脂肪の分解によるディープフライフレーバーの生成
-アミノカルボニル反応によってできるメラノイジン
今日はこの辺までです。
今、久しぶりにこの本のこのページを見ると、赤の書き込みだらけです。
コーヒーの焙煎を乾熱調理だと考えたところから、さかもとこーひーの焙煎の考え方がステップアップし、仮説検証を繰り返してきました。
で、スペシャルティコーヒーの焙煎のデベロップにつながったわけです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[コーヒーの焙煎を考える] カテゴリの最新記事
-
プロのつぶやき1105「さかもとこーひーの… 2021.05.02
-
プロのつぶやき1104「スペシャルティコー… 2021.04.25
-
プロのつぶやき1076「さかもとこーひーの… 2020.10.11
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(128)スペシャルティコーヒー
(1414)ニカラグア・エルサルバドル産地巡り
(9)美味しい暮らし
(279)コーヒーのコク研究
(49)コーヒーの焙煎を考える
(61)さかもとこーひー、5つのこだわり
(11)フードペアリングの方程式
(56)僕の好きな紅茶
(34)サンプリング倶楽部21
(23)コーヒービジネスを考える
(77)Comments
© Rakuten Group, Inc.