2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年10月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-

早く行きたいなぁ~
昨日、『アール・デコ展』の案内の記事を載せましたところ、思いがけずたくさんの人にアクセス頂きました。皆さんもけっこう関心が強いんですよね。・・そんなのもあって、私も 一日でも早く観に行って感想を書きたいと、気ははやってますが残念ながら、行くのは4日か5日の滑り込みになりそう~せっかく足を延ばすので、大阪市内に住んでる旧友とも久しぶりに会いたいと思ったら、お互いの日程が合うのがその頃になりそうなんです。一度に二つ楽しもうと欲張ったから、仕方ないか^_^;あ~ 今日は秋晴れなのになぁ~。。。
Oct 31, 2005
コメント(6)
-

『アール・デコ展』― きらめくモダンの夢 ―
「アール・デコ展」―きらめくモダンの夢―http://www.suntory.co.jp/culture/smt/gallery/index.htmlもうすぐ、会期終了だ。11月6日まで(あと1週間)。この春から、東京都美術館を皮切りに、福岡市美術館でも開催されていて、大阪で最後となる。間に合いそうでよかった。(*^^) 各地での反応は、なかなか好評だったようです。観に行ったら、また感想を載せますね。で、今日は案内だけですが。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・この企画は、ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート美術館。2003年にロンドンで開催された 『アール・デコ1910-1939』展 をもとに構成され、日本での「アール・デコ」をテーマとした 初の大規模な展覧会。アール・デコ様式は、1925年にパリで開かれた国際装飾美術展での傾向をとらえて、1925年様式とも言われています。直線と幾何学模様、シンプルでありながら高級指向でもあった「装飾芸術」最後の展開とも言われる当時の作品の数々が展示されている。カルチェ、ラリック、レンピッカ、シャネル・・一流品といわれているものの原点を見ておくのもいいでしょう。 ☆ ☆ ☆11月3日は、ギャラリー、アイマックスシアター、両方とも無料なんです。(サントリーミュージアムの開館11周年記念)エネルギーの豊富な人はこの日をねらうと、すごいお得だと思う。(私はあまりの人混みは疲れてしまうので断念ながら・・)『アール・デコ展』 入場料 1200円(当日券)アイマックシアター 入場料 1000円で、合計 2200円のお得になるね。(*^^)※11月3日以外でも、いろいろ割引があるからこのHPで確認してね。http://www.suntory.co.jp/culture/smt/information/index.html★ 会場への案内はこちらからご覧ください。交通&アクセスhttp://www.suntory.co.jp/culture/smt/information/access.html【会場】サントリーミュージアム[天保山]【会期】~11月6日(日) 【開館時間】10:30~19:30(最終入場は19:00まで) 【休館日】毎週月曜日【HP】http://www.suntory.co.jp/culture/smt/gallery/index.html☆ ☆ ☆●天保山ハーバービレッジのスポット天保山大観覧車http://www.kaiyukan.com/area/ferriswheel.htm海遊館(世界最大級の水族館)http://www.kaiyukan.com/info/index.htmふれあいペットガーデン(天保山アニパ)http://www.kaiyukan.com/market/shop/s3.htm
Oct 30, 2005
コメント(0)
-

出かけてみよう!!
さて、どこに出かけてみようかな?と思案して・・芸術の秋ということで、「アール・デコ展」を見に行くことにしよう!!ベランダから見える木々は、少し色づいてきていますが、紅葉を楽しむために出かけるにはまだ時期尚早だしね。この会場になっている「サントリーミュージアム(写真)」は、安藤忠雄さんの設計によるもので、氏のコンセプトを隅々まで感じることのできる建築物なんです。付近には、海遊館やその他のレジャー的複合施設がたくさんあり、結構、いろいろと刺激を受けながら散策できるいい場所です。それに、私には何よりもデッキに出て、潮風を受けながら海を眺められるのが一番かな。日常にない感覚を呼び覚ませるんです。以前は、気のおけない友達を誘って、仕事の息抜きなどによく出かけたところです。尚、「アール・デコ展」や「サントリーミュージアム」に関しての詳細は、後日記事にしたいと思ってますので、興味のある方は、また見に来てくださいね。
Oct 29, 2005
コメント(8)
-

「馬齢を重ねる」に思う
昨日の日記に、印象に残ったエッセイの表題だけをいくつか書いたが実は、書きそびれたのが一つある。それは、佐藤正午さんという作家の「四十歳」という題のものである。私は四十歳ではないがこの「馬齢を重ねる・・・」の書き出しで始まるこのエッセイがまだ気になっている。特に、「馬齢を重ねる」ということば自体が妙にこころにずしんとすわっている。なぜ昨日、書かなかったのだろう?たぶんこの言葉には、人生に対して否定的な響きを感じて、「私の好むところにあらざる。。」と こころが拒否したのであろう。いや~、今まで「馬齢を重ねてきた」と思えば空しくなるではないか。しかし、妙に気になって仕方がない。昨夜、もう一度 読んでみた。ここで、少し著者の冒頭の文を書き移してみよう。「馬齢を重ねる という言葉があって、手元の辞書で調べてみると、これは 「たいした事をしないうちにただ年をとっただけ」 との意味で、しかも謙遜の表現らしいのだが、べつに謙遜をするわけでもなく、素直な感想として、新たな年の始まりに この言葉を呟いてみたくなる。まったくの話、馬齢を重ねに重ねて ここまでたどり着いた・・・」という始まりである。振り返れば、私も・・誰しもが喜怒哀楽の詰まった人生であろうが・・私にも辛苦は結構あったが、塞ぎ過ぎずになんとかやり過ごし、明朗を看板にして、それなりに懸命に生きてきたという自負も少しはある。だからといって今、その成果や果実をなにかもぎとっているかと問えば、何もないのが現状である。やはり、私も馬齢を重ねてきたのだと思わざるをえないのか。そういえば、「ばか」を漢字では、「馬鹿」と書く。 なるほど・・・妙に納得。納得したら、なぜか奇妙にも こころ安らいできたりする。(笑) しかし・・まだ「馬齢を重ねてきたんじゃない!」と、抵抗したい気持ちと拮抗し合っている。今、妙な気持ちである。^_^
Oct 27, 2005
コメント(4)
-

「こころの羅針盤(コンパス)」を読んで
これは五木寛之が選んだ30人の作家のエッセイを載せたものです。すでに単行本で刊行されていたものを文庫化したものなので、もう読まれているかもしれませんが、意外と面白かったです。「こころの羅針盤(コンパス)」五木寛之選何が面白かったか?というと、こう個性の強い、老若男女の三十人分を一度に読まされると、スタンスの違い、生活感のちがい、文体の異なりかた、・・などなどが、浮き彫りになって楽しめたことです。皆、短文ばかりなので、内容の紹介は省きますがこの中で、私が印象に残ってるのは、「ロールキャベツを遠く離れて」 村上春樹「ハゲについて」 浅田次郎 (※これは大爆笑ものです!!)「Xへの手紙」 辻 仁成「貧乏臭き追放月間」 山田詠美「知る余地のこと」 江國香織「人生観の訂正」 ビートたけしと、こんなところかな。興味あるものからランダムに読んだので、飛ばしてる人のもありそうだけど。☆ ☆ ☆数日前にスーパーに行ったとき、本屋さんに寄って6冊ばかり買いました。読みたかった本はあいにく店頭には無かったので、気分任せの文庫本ばかりです。「こころの羅針盤」を選んだのは、読んでみたい作家名がいくつかあったのと、本のカバーに抜粋されていた著者のまえがきの言葉にのせられて・・「声に出して笑ったり、ため息をついたり、なるほどなぁとうなづいたり、と私自身、人生を三十回生きたような感じがした。才気あり、含蓄あり、厭味あり、教養あり、風格ありと、活字を読む楽しみこの一冊に尽きる。」いや~こういう要素は、三十人も読まなくても、いい小説には一冊でもだいたい含まれているものですよね。マーケティングを意識した、ちょっと大袈裟なことばです。と、今は思うものの・・ 閉店チャイムが鳴って、わずかの選択タイムに走り読みして、まぁ結局、そのキャッチフレーズにまんまと捕まったわけです。^_^;
Oct 26, 2005
コメント(0)
-

こんな大人の三輪車にのってみたい!!
こんなおとなの三輪車をみつけた~!!「歩く効用」をテーマにウロウロしていたら、こんなのが・・。※ 元自動車会社の技術者によって生み出された、新しい三輪自転車のカタチで お年寄りや女性も安心して乗れる、安定性に配慮した設計。 置き場所も通常通り-二輪自転車と変わらない駐輪スペースでよい。http://www.takashimaya.co.jp/shopping/tvm/0009/0054/html/000115_000105808_01.html なぜこんなのを見つけて喜んでいるかというと・・ちょっと、話しは長くなりそうです。かつて、私は大の自転車好きでした。自転車は小学4年のとき、父の介添えがあって乗れるようになって以来、重いものがさげられない私にとっては毎日の生活に手放せないものでした。中学・高校までは、幸い校舎が家の近くに在ったので、ずっーと6年間、自転車通学しました。そのごの学校や会社も、最寄の駅までは自転車でこぎつけていました。そんな私の足代わりであった、超~愛すべき自転車なんですが、成人してからのある時期の何回目かの足の手術を受けたとき後遺症として、膝が曲がらなくなってしまい、それ以来、自転車には乗っていません。このときは大ショックでしたが、新たに自動車の運転を覚えることで、このショック状態から乗り切りました。まだ左右両方の松葉杖がはずれないときから、杖をつきながら教習所に通ったのですから将来に対しての危機感が相当あったのでしょう。やがて、自動車も手に入り、私の行動範囲をより広げてくれました。この新しい生活変化は、正座が出来なくなった悲しみを吹き飛ばしてくれました。ということで、私にとって自動車による恩恵は、なみなみならぬものなんですがこと運動量に関しては、減ってしまったのも確かです。歩行距離の少なさを自転車を漕ぐことによって、運動量を補っていたからです。ひざの屈伸は、幸いにも自転車に乗れるぐらいの角度までは可能なので自転車には、かろうじて乗ることはできるのですが100mぐらい漕ぐと、急に突然ひざの回転がピッタと止まってしまうのです。そうなると、バランスが崩れて一瞬ヒョロヒョロと舞って転倒するわけです。それが、たとえ道の真ん中であろうが変わりはないわけで、危なくて乗るのを止めたんです。私だけが即死ねる事故だったらいいんですけどね。 でも、そこに不幸にも居合わせて、私に偶然危害を加えるはめになった方に申し訳ない。私も死に損ねたら、家族にはより負担をかける存在になるし・・ということで、自転車への愛着をなくなく断ち切ったんです。やはり、話しが長くなってしまいましたが、ようするに、そんなひざの屈伸がままならない私でも、この三輪車なら、安心して乗れそうだなぁと。そこそこ軽快感もあるし。交通量の多いところでは無理でしょうけど、ちょっとした買い物や散歩がてらには使えそうです♪まだ、これを乗ってる人はみかけたことがないので、乗るのには、気恥ずかしくて勇気が要りそうだけど。それに、価格がなんと10万円もするので、もっと安くならないと手が出ません。そのうち、年老いた方などの利用が多くなることを期待したい。価格設定は需要と供給の関係ですものね。自転車に乗れないと思っていらっしゃる方、ぜひこれを利用をしてみませんか!!(さっそく、呼びかけ^_^;) いや、この三輪車では、二輪車のような、カーブをスイッと交わすスリリングさは味わえそうもないけど、ペダルを漕ぎながら風を切る爽やかさとか、まだ知らない路地をちょっと曲がってみるワクワクさとかは叶えてくれそうな気がする。 ぜひ、もう一度味わってみたい。いえいえ、何よりも、ペダルを漕いで運動量を上げたい!!ホントもっと価格が安くなってくれないかなぁ~願わばくは、この三輪車がひろまり、安価になってくれますように!(合唱)☆ ☆ ☆私ごとの話にお付き合いさせてしまいました。ここまで読んで下さった方、ありとうございました
Oct 25, 2005
コメント(8)
-

ウォーキング4― ストレッチ ―
今日は、絶好の秋晴れ!! 私もいつものお散歩コースを歩いてきました。今日は、暑くて汗が・・!! でも、気分は爽やか。皆さんどこを歩かれたのかしら?と言っても、オフィスの中で仕事されている方はままなりませんものね。私もかつて、会社に勤務していたときは、こんな気候が穏やかでお天気の良い日には、窓の外をみつめてはため息ついてました。あ~ 仕切りに入れ込まれた、鶏みたい~(T_T) って。でも、自由になったからって、そうそう歩き回れるもんじゃないですけど。やぱり、人間はないものねだりな生き物なんでしょう。★ストレッチは下記のページを見てくださいね。ウォーキング前のストレッチおまけで・・次のも。^_^腰痛予防のストレッチ☆ ☆ ☆
Oct 24, 2005
コメント(6)
-
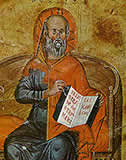
「健康維持には運動」は2400年前から同じ。
おおよそ2400年前、古代ギリシャ時代の「医学の父」と呼ばれるヒポクラテスは「運動すれば生体内の余分なものが燃焼される。食事がどんなに上質で適量でも運動には代えられない」と述べています。この考え方は、運動と生体の反応を科学的に分析できるようになって実証されつつある今日では衆知のことですが、紀元前4世紀にすでに見出していたというのは驚きですよね。私はまだこの偉人については、よく知りません。ただ・・私が三年程前に病気をしたときに、医師側の一方的な対照療法に疑問をもち、少し医療のことなどを調べたことがあります。その際、病気の克服にはさまざまな考え方や治療法があるということを知ったのですが、その中で、自分の病状や体質にとってはどの方法を選ぶのが懸命なのか?・・と探っていくなかで、これは脈がありそうというような手ごたえのある本や記事には、必ずと言っていいほど、この「ヒポクラテス」の名前が登場してきました。「ヒポクラテス」はこういわれているとか、「ヒポクラテスも・・」というような引用が多かったんです。それで、興味はもっていたのですが、当時は、目前の病気を治すための具体的なことがらを吸収するのに精一杯で読み飛ばしていました。今回、「歩く効用」というテーマで探していたら、上記のように、またしてもヒポクラテスの名前が出てきて、その広範囲な影響力に、すごい偉人であったことを知らされます。まだこの人の功績についての詳細は知りませんが、「ヒポクラテスの誓い」というのが載っていたので読んでみました。これを読んだだけでも、この人がどんな精神のもちぬしであったかが、ありありと伺えます。やはり、良いものはよい土台のうえに生み出されるということなのかもしれませんね。最後に、この偉人が最初に言い始めたといわることばを、もうひとつ。「良いアイデアを浮かべるには、歩くのが効果的である」☆ ☆ ☆
Oct 23, 2005
コメント(4)
-
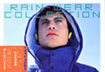
メモ3_ウォーキング― 雨の日の対策 ―
私はもともと歩ける距離が少ないので、雨の日は、買い物を大型スーパーなどにして、その中をいつもより多めに、ぶらぶら歩く程度で済ませます。それに普段の移動は、わが愛用車(!?)でやってるので、レインウェアは必要ないのですが、通勤の帰路を、ウォーキングに利用されている方も多いでようから、ご参考になればと思います。★ レインウエア雨の時は、少し高価ですがゴアテックスのレインウエアが一番良いようです。ゴアテックスは、雨の水滴の大きさは通さないのですが、体から出る汗、水蒸気の大きさの水滴は通すフィルム状のものです。このため汗はかくのですが、他のレインウエアに比べるとむし暑くないようです。他のレインウエアはどうしても汗が内部にこもり体がべとつきます。 ゴアテックスは生地の上にゴアテックスというフィルムをコーティングしてあるものです。洗濯はできるのですが注意が必要です。洗濯機で洗濯をし、脱水までかけてしまったところ、フィルムが部分的に剥離を起こし気泡が入いったようになってしまわれたそうです。そのまま何もしないで使用するのが一番良いとのことです。。見栄えは悪いのですが、レインウエアとしての機能はフィルムにあり効果は同じだそうです。発水効果(水をはじく力)が落ちているようなら、防水スプレーをかければ良いそうです。フィルムがあるので水はしみ込んでこないのですが、水のはじき方は使用と共に落ちてきます。http://www.llbean.co.jp/shop/guidePages/fabric/goretex.html☆ ☆ ☆★ ソックス 昔は綿のものが最も良いと言われましたが、歩く時は別です。歩くと汗が出ます。この汗が靴下に吸収されると、靴下が湿り、足が靴下とこすれ"まめ"のできる原因となります。衣類の項でも説明した、オーロン、ダクロン、ポリプロピレン、クロロファイバー等の化学繊維は汗を吸収しません。従って、足と、こすれることが少なく"まめ"ができにくいようです。 雨の日に歩くと問題は足回りです。まさか長靴で歩くわけにも行きません。防水効果のあるゴアテックスを使用した靴もあるようですが、ゴアテックスでできた靴下を使用するのもいいです。靴下の上にこの靴下を履きます。靴は直ぐ雨でベトベトになるのですが、足は何時間も濡れてきません。快適です。でも余り長時間になると多少濡れてきます。難点は日本では売っている所が殆どないことです。使用されている方は、アメリカのREIから輸入したとありました。Waterproof Socksで検索かければ出てきます。日本語の購入説明もあり、日本にサポートもあり安心だそうです。高価なのが難点とか。私はゴアテックスの回し者ではありませんし(笑)。。ここまで拘るほど歩けませんが。。興味のある人は見て下さいね。SealSkinz の防水ソックス(1)SealSkinz の防水ソックス(2)
Oct 22, 2005
コメント(4)
-

メモ2_ウォーキング― 最適な衣類 ―
もうしばらくは歩きに最適な季節だから必要ないのだけれど、これから冬に向かうので、寒くなったときのための衣類の注意点をメモしておこう。★ インナー 冬は下着に工夫が必要です。汗をかいて休憩すると下着が濡れているため寒くなります。この対策として、オーロン、ダクロン、ポリプロピレン、クロロファイバー等の化学繊維の下着が良いようです。これらは汗を毛細管現象により外に放出し、生地自体は水分を吸収しないので、汗をかいた後でも下着が濡れなくて冷たく感じません。毛細管現象のため、できるだけ身体にあったサイズが良いようです。更にこの生地は冬用を購入すると、薄着ができるほど温かいものです。冬はこれにかぎります。 又この生地は、水分を含まないので洗濯をしても早く乾きます。もう一つ、冬のポイントは重ね着。ジャンバーのように前を開け閉めして体温調節できる衣類を着るのが良いようです。熱い時は、まずジャンバーの前のチャックを開けて、冷たい空気を衣類の間に入れ、温度を調節します。 それでも熱い時は、重ね着している一枚を脱いでリュックの中へ入れます。歩くと冬でも30分位で体温が上昇してきます。常に調節しながら汗をかかないように歩くと良いでしょう。 体温調節がうまくいかないと疲れるため長距離は歩けません。☆ ☆ ☆★ 手袋 一日歩くと、ずっと手を振って、かつ下に向けているためか、手がむくんできます。歩く人たちは、むくみを押さえるために夏でも手袋をしていることがあります。手袋をするとずいぶんむくみがとれます。でも夏場はむくみと、暑さの兼ね合いでしょう。手袋をしていない人も多くいます。冬はほとんど全員手袋をしています。 みなさんが工夫されていることがあれば、何でもコメントに書いてくださいね。
Oct 21, 2005
コメント(0)
-

「ヒポクラテスの誓い」
「ヒポクラテスの誓い」(原文:小川鼎三訳) 『医神アポロン、アスクレピオス、ヒギエイア、パナケイアおよびすべての男神と女神に誓う、私の能力と判断にしたがってこの誓いと約束を守ることを。この術を私に教えた人をわが親のごとく敬い、わが財を分かって、その必要あるとき助ける。その子孫を私自身の兄弟のごとくみて、彼らが学ぶことを欲すれば報酬なしにこの術を教える。そして書きものや講義その他あらゆる方法で私の持つ医術の知識をわが息子、わが師の息子、また医の規則にもとずき約束と誓いで結ばれている弟子どもに分かち与え、それ以外の誰にも与えない。○私は能力と判断の限り患者に利益すると思う養生法をとり、悪くて有害と知る方法を決してとらない。○頼まれても死に導くような薬を与えない。それを覚らせることもしない。同様に婦人を流産に導く道具を与えない。○純粋と神聖をもってわが生涯を貫き、わが術を行う。○結石を切りだすことは神かけてしない。それを業とするものに委せる。○いかなる患家を訪れるときもそれはただ病者を利益するためであり、あらゆる勝手な戯れや堕落の行いを避ける。 女と男、自由人と奴隷のちがいを考慮しない。○医に関すると否とにかかわらず他人の生活について秘密を守る。○この誓いを守りつづける限り、私は、いつも医術の実施を楽しみつつ生きてすべての人から尊敬されるであろう。もしこの誓いを破るならばその反対の運命をたまわりたい。』☆ ☆ ☆
Oct 20, 2005
コメント(2)
-

メモ1_「歩くことと脳の活性化の関係」
人間の歴史は立って歩くことにより脳が発達し、考えて、考えた結果がいまの文明文化を作り上げました。では、歩くことと脳の活性化にはどのような関係があるのでしょうか。その例として赤ちゃんの発育過程で説明すると・・ハイハイ歩きからつかまり立ち、ヨチヨチ歩きから上手に歩く、走る、跳ぶとか...身体のバランスを調整するようになります。この過程は赤ちゃんの脳の進歩を表しています。脳の奥深い脳幹から徐々に脳表面へと活性化され、情報伝達系の回路が発達していきます。そして一歩が足の動き、身体のバランス、接地面の感触、勾配、前方の景色をみる、手をふる、温度差を感じる、匂いを嗅ぐ、音を聞くなど脳のあらゆる分野を働かせて歩くことになります。これらの情報を総合判断して「意志」、「行動」の決定を下します。 ☆ ☆ ☆囲碁、将棋、パソコンとかは脳の一部しか活動していません。歩くこととりわけ楽しく、目的をもって歩くことは脳全体の活性化につながり脳が若くなるといいます。脳は活動させないとどんどん機能低下して若さが失われていくので、毎日または一日おきで歩くことが脳を活性化していきます。やる気がなくなってきたら神経伝達物質ドーパミンが少なくなっているのかもしれません。ドーパミンは快感物質ともいわれ歩くことによって分泌されます。ドーパミンが増えてくると歩く楽しさが増強されます。もう一つの脳内伝達物質でセロトニンは精神安定剤とよく似た分子構造をもっており、興奮や不快感を静める物質ですが、セロトニンは規則正しいリズム運動の中で活性化されます。散歩やブラブラ歩きではなく速歩で分泌され、朝の太陽のもとではさらに分泌されます。セロトニンもドーパミンも歩くことにより分泌され、爽快感、楽しさを引き起こします。よく経験する歩き終わった時に感じるあの気分です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日からの記事は、私がまたウォーキングをサボりたくなったときのために、「歩く効用」を少しメモしていくことにしました。 またよかったら、見に来てくださいね。
Oct 19, 2005
コメント(10)
-

馬鹿な私・・「歩かなくっちゃ!!」
朝夕の散歩の再開始。実は、プログを始めてから散歩をサボってたんです。そのバカな理由とは・・プログを始めてから、パソコンの前にすわることががぜん多くなった。それなのに、体重は46kg ⇒ 45kg以下と、1kg以上も減ったんです(・・?そうなんです。運動量が少なくなったのに体重が減少。あれれ~しかも体脂肪まで減少・・不思議に思いながらもきっと、タイピングには素晴らしい効用があるのかも・・なんて、ちょっとした秘密を見つけたような気持ちでほくそ笑んでいたんです。なにしろ、長年突破できなかった45kgの壁を、難なくクリアーできたんですから。そりゃ、嬉しいですよ!!・・と喜んでいたら、友からのメールで、「それは・・・・・だ!」と、返信が来てガクッ・・↓(真っ逆さま)で、その内容とは、「それは運動不足で筋力が減ったからですよ。 贅肉より筋力の方が重いんですから・・」である。あらら、これはやばいじゃん~(>_
Oct 17, 2005
コメント(16)
-

齋藤孝著「書く力」を読み思ったこと。
昨日まで、『書く力』のシリーズ(1)~(6)を、プログの記事として、自分も学びながらお伝えさせてもらいました。最後として、私の個人的な思いを書いてみました。この本で一番訴えておられるのは、「書く力」は構築力を養うことが一番の近道だというものでした。(構築力とはどういうものかというのは、昨日までの記事に要約して載せさせて頂きましたので、ここでは省かせてもらいます。)しかし、この「構築力」というのは、あくまでテクニックといえるもので、何をどう考えるかという書く人の視点、思考があって、始めて構築力というテクニックが生きてくるのではないかと思うのです。確かに構築力は表現力をアップさせる意味で大切なのでしょうが、ものごとを見抜く力、これが希薄していては話しにならないでしょう。(これは自分に向けたことばである^_^;)その意味で、プログを毎日書き続けていくことは、思考を深めていくよいチャンスになると思っています。なにげない日々の思いを書くときには、その思いをしっかりつかまないと書き言葉として、表現できないのだから・・まずもって自分と向き合うことを日々させられるわけだし、いい訓練になる。また、ちょっとした体験も書くとなれば、それをどうリアルに伝えるかという表現の訓練にはなるし、体験の意味も探るチャンスになるだろう。この文の最初にも書いたように、あることに対して、何をどう捉えるか、どう考えるか、という視点の幅を増やすには、体験とともに、やはり読書が必須だろうと思います。、私は結構たくさん、ジャンルも案外幅広く読んできたほうですが、その読書も、これからは、書く側の観点も視野に入れながら読めそうです。この本にも書かれていたのですが、好きで読書するのと、書くということを前提に読書する場合とは違うといわれています。また、ひとつ楽しみができたようで嬉しい。最後に、subaru_1632さんが励みになるようなコメントを残してくれていますのでご紹介します。「約一年、ここでブログを書いていますが本当に書くことになれてきましたね。慣れてきたことを良いことに、書きっぱなし、読み返さない、等で文章がめちゃくちゃな日もありますが・・・それでも書く力がついたなぁって思うことがあります。職場で広報委員なるものをしていますが、広報誌などに投稿された文章を校正したりするのが、簡単にできるようになりました。ブログもためになるなぁって感じています」私も1年後を楽しみにプログを続けていきたいと思います。『書く力』(1)― 人とつながる ― 『書く力』(2)―「気づき」がおもしろさを生む ― 『書く力』(3)― キーコンセプトは切り口になる―『書く力』(4)―「キーワードからキーフレーズへ」― 『書く力』(5) ― 「話せるから書ける」は間違い ―『書く力』(6) ― 新しい意味を生み出す ―
Oct 16, 2005
コメント(7)
-
『書く力』(6) ―新しい意味を生み出す ―
こんにちは。昨日は、温かいお見舞いの言葉を頂いたり、いつものように見に来て下さったりして、、ありがたいです。嬉しいかったです。ありがとう!!今日は、小雨が降っていますが、心は爽やかです。励まされて心が温かくなっているせいかな*^^)まだちょっと頭はボォーとしていますが、 さぁ今日も『書く力』いってみます。(自分のメモのようなものです^_^;)-----------「書く力」(6回目) 書く力とは構築力である。―「新しい意味を生み出す」―― 『書く力』 齋藤孝 著(P.38~)☆☆☆生命力にあふれている文章というのは、体験だとか、客観的な内容だとかよりも、構築ができている文章であるかどうかで決まる。まず、読んだ側の「それで何なの?」という問いに答えられるかどうか、つまり主題をきちんと打ち出せているかどうかである。☆☆☆書くという行為に偶然などない。まるで自動書記になったかのように感じられるほど、無意識にサラサラと文章が浮かんで作品ができてしまうということはない。自分と正面から向き合って、人ははじめて文章を書ける。☆☆☆☆☆書くという行為は、そのままに放っておけばエントロピー(無秩序状態)が増大していき、ますます退屈で無意味な世界になる日常の中に、意味という構築物を打ち立てていく作業なのだ。☆☆☆☆☆書くという行為は、新しく意味を生み出すことである。意味を生み出すとは、価値を創造することだ。----------(ぴゅあのことば)上記にのせた著書の今日の言葉も「うん、なるほど、、」とうなづけるが、そんなことをいつも深く考えていたら、プログを書くのも負担になりそう・・^_^;やっぱり、プログはまずは自分が楽しんで好きに書かかなくっちゃ続かないや~(ホンネ!)でも、ちょっと客観的に見る目だけは出来たかな、、!?PSなんでも思ったこと、気楽にコメントくださいね。
Oct 15, 2005
コメント(4)
-
体調不調。
今日は朝から、なぜか体調が悪い。ベランダから燦々と陽光が射して、絶好の秋日和なのに。急に体温が高くなったせいだろうか!?※今日は、『書く力』をお休みさせて頂きます。
Oct 14, 2005
コメント(4)
-
『書く力』(5) ― 「話せるから書ける」は間違い ―
こんにちは。昨夜は、テンプレートのデザインを変化させてみました。ちょっと、秋らしい雰囲気になったかなぁ・・。気に入るまで、しばらくはいじりそう~ 日替わりメニューになるかも!?さぁ今日も『書く力』いってみます。(自分のメモのようなものです^_^;)-----------「書く力」(5回目) 書く力とは構築力である。―「「話せるから書ける」は間違い」―― 『書く力』 齋藤孝 著(P.38~)☆☆☆書く方法論として最近「話すように書けばいい」とよく言われる。しかし、本来「話す」ことと「書く」ことはまったく違う行為である。その点を誤解している人が多い。☆☆☆☆☆体験は、そのままにして放っておけば、流れ去ってしまう。書くことの基本的な機能は、体験の意味、経験の意味をあきらかにすることである。☆☆☆書くことをまるでジャズのライブ演奏のように、その場の雰囲気で、そのときの気分や思いつきをとらえて、生で表現すればいいものができると考えたら、それも大違いである。あらかじめ曲が頭の中にイメージされていて、それが舞台に立ったときの雰囲気、緊張感の中で形になり、演奏されるのだ。そのままではないにしても、すでに曲はできていて、それがコンサート会場の雰囲気の中で、形としてあらわれるのである。プロ中のプロの演奏家であってもそうなのだ。☆☆☆☆☆書くことは、無から有を生み出すのではなく、頭の中で構築したものを形にしていくこと、すなわち、構築することなのだ。----------(ぴゅあのことば)夏の終わり頃にこのプログを始めてから、本を読むのはご無沙汰になっているが、私は好きな人や興味のある人などの対談集が出ていたら、けっこう読んできたほうだ。それはなぜか? というと、テレビの生出演ほどではないが、少しはその人の肉声をつまり、生に近いものを感じ取りたいという思いがあったからです。しかし、思い出してみると、対談集は二人のやり取りなどを楽しく読めるし、そのときは、確かになにか吸収したような気持ちになるのですが、案外あとあとまで、心に残っている内容は、少ないように思う。それは、何かを伝えようとして、著者自身がしっかりと構築したものではないからだということが、今日の項目を読んで納得したことです。とはいえ、対談集には対談集のよさもあるので、また読むと思いますが。PSなんでも思ったこと、気楽にコメントくださいね。
Oct 13, 2005
コメント(6)
-
「書く力」(4)>―「キーワードからキーフレーズへ」―
こんにちは。この「書く力」のシリーズは、人に伝えたい何かがあるときに、どう書けば読者を魅了させることができるのか? ということを学んでみようという試みです。今回は―『書く力』齋藤孝著 ― より、プログのような短文にでも適用できそうな箇所をランダムに引き出しながら、お伝えしています。 (自分のメモのようなものです^_^;)-----------「書く力」(4回目) 書く力とは構築力である。―「キーワードからキーフレーズへ」―― 『書く力』 齋藤孝 著(P.117~)☆☆☆全体を構築していく場合。キーワード、キーコンセプトをタイトルになるようなキーフレーズに練り上げていくと、全体が構築しやすくなる。☆☆☆キーフレーズは、多少わかりにくいものでもいい。自分にとっては、それを結論のつもりで書く。最初に言いたいことをきちんと書くのは、自分がこの文章で主張したいことは何かを忘れないという利点がある。☆☆☆言いたいことを過不足なく表現しながら、凡庸に陥らない一文を、最初につくり上げることができれば、読む人の気持ちをつかみ、先を読みたいという気持ちにさせることができる。☆☆☆☆☆その一文を(キーフレーズ)を論理的に説明していくことは、たとえれば思考の解凍作業のようなものだ。一文に凝縮するためには、思考の凝縮があるはずである。それを論理的に説明するように書いていく作業は、凝縮された思考を解凍して、思考のプロセスをすっきりさせていく作業である。だからこそ、書くことは考える力を鍛えることにもなるのである。----------(ぴゅあのことば)このほかに、著書は「はじめの一文で言いたいことを言い切っておけば、時間がなくて中途半端に終わっても、いちばん言いたいことは入っている。」とある。これはプログなど趣味として書いている場合、役立ちそうである。書いている途中に雑用が舞い込んだり、夜だと眠たくなって途中で切り上げたとしてもなんとか自分の言いたいことは伝えられるわけだから。PSなんでも思ったこと、気楽にコメントくださいね。
Oct 12, 2005
コメント(2)
-
「書く力」(3)― キーコンセプトは切り口になる ―
こんにちは。この「書く力」のシリーズは、人に伝えたい何かがあるときに、どう書けば読者を魅了させることができるのか? ということを学んでみようという試みです。今回は―『書く力』齋藤孝著 ― より、プログのような短文にでも適用できそうな箇所をランダムに引き出しながら、お伝えしています。-----------「書く力」(3回目) 書く力とは構築力である。―「キーコンセプトは切り口になる」―― 『書く力』 齋藤孝 著(P.108~)―☆☆☆☆☆キーコンセプトを練って明確にしておけば、文章は書きやすくなる。そのキーコンセプトを背骨にして、他の要素をいろいろと絡めていくことができる。たとえば、途中で拡散しても、そのキーコンセプトに戻ることによって、まとまりのある文章にすることができる。☆☆☆キーコンセプトとは、テーマや主題とはちょっと違う。たとえば、環境問題について書くという場合、「環境問題」という言葉は、テーマであって、キーコンセプトではない。そこで環境問題について、自分が書きたい何かを見つける。その「何か」が、キーコンセプトである。☆☆☆キーコンセプトは斬新なものにこしたことはない。しかし、自分が考えられる範囲で、キーコンセプトを見つけることが書く上での第一歩である。----------(ぴゅあのことば)著者の上記の文章から、この項目の場合のキーコンセプトはと考えると、「キーコンセプトは切り口になる」・・ということになりますね。著者は、おそらくこの「・・切り口になる」というのを練り出したのでしょう。本など、なにげなく目を通していましたが、読者を引きつけるためキーワードやキーフレーズを生み出す為に、汗かいているのですね。「練る」という行為は、時間をかけないと出来ないことですから。直感として出てくるのは一瞬であっても、それまでにさまざまの角度から眺めたり、寝かしたりしているということでしょう。そう考えれば、けっこう安易に文を書いていたし、タイトルもそこまで考えて、つけたことないなぁ~と思う。これからは、このこともちょっと意識してみよう。PSなんでも思ったこと、気楽にコメントくださいね。
Oct 11, 2005
コメント(4)
-
「書く力」(2)―「気づき」がおもしろさを生む―
こんにちは。この「書く力」のシリーズは、人に伝えたい何かがあるときに、どう書けば読者を魅了させることができるのか? ということを学んでみようという試みです。今回は―『書く力』齋藤孝著 ― より、プログのような短文にでも適用できそうな箇所をランダムに引き出しながら、お伝えしています。-----------「書く力」(2回目) 書く力とは構築力である。―「気づき」がおもしろさを生む」―― 『書く力』 齋藤孝 著(P.96~)―☆☆☆☆☆おもしろいとは、それまで頭の中でつながっていなかったものがつながるということでもある。読み手にそういう刺激を与えるラインをつくるのが文章を書くことの醍醐味の一つでもある。☆☆☆頭の中の離れた場所に整理されていたこと、つながっていなかったことが脳の中に電流が流れて、つながっていくような快感である。それが読者にとっての「気づき」の喜びである。☆☆☆書いているうちに、そのつながりのラインが明確になっていく。書く訓練は、そうした思考の粘り強さを鍛える。----------(ぴゅあのことば)この項目のところで、著者は最後に・・「文章の中に、読み手に何らかの「気づき」を与えるものがなくては、読む意味もない。」と手厳しいことばで閉めている。そういえば、読んだり観たりして、後々まで心に残るものがあるときって、意識してなかったけれども、「気づき」を与えられた嬉しさだったと言えそうだ。これまで自分の書いた記事を、こんな視点から客観的にながめたことがなかった。これからは、ちょっと意識してみよう。しかし、頭の中で考えて、つながりがなさそうなもののつながりを捉えることは、かなり訓練が入りそうだ。容易に達成できる課題ではなさそうだけど、発想の訓練にもなるし、ぜひ心掛けてみよう。ところで、今日は「書く力」と「気づき」ということがつながった快感をえられたということかな。(*^^)PSなんでも思ったこと、気楽にコメントくださいね。
Oct 10, 2005
コメント(4)
-
『書く力』(1)-人とつながる
「さぁ~今日から書く力を学んでいくぞ~!」と深呼吸して・・昨日、この本の表紙を改めて見たら、サブタイトルに「原稿10枚を書く力」とありました。 あらら・・・プログでは、普通1枚~3枚位ですよね。 う~ん。まぁいいか~。^_^;役に立ちそうな箇所だけランダムに吸い上げていこうと思います。---------「書く力」(1回目) 書く力とは構築力である。―「書くことで人とつながる」―(1回目) ― 『書く力』 齋藤孝 著(P.68~)☆☆☆ 意識してトレーニングを積み重ねることで、公共的な感覚を持つことができ、どんな場所でも、どんな人ともきちんとつながることができる。それが書くことで獲得する自由なのだ。☆☆☆ 大事なのは、書くときにプライベートなモードとパブリック(公共)なモードを自由に往復できる力を持てるようにトレーニングすることだ。それが書く幅を拡げることにもなる。☆☆☆ 「書く」とは、書いた人間を個人的にまったく知らない多くの人たちに、内容が正しく伝わるということである。---------(ぴゅあのことば)この本の内容は、「受験、就職、仕事」に役立つ極意を書かれているので、日記代わりにプログを使っている人には役立たないかもしれませんね。日記(プライベートな記述)として使うのも、プログの多様な良さだと思います。私はこのプログをトレーニングの場としながら、少しづつでも書く力をつけ書く幅もひろげていけたらと思っています。次回から、トレーニングの方法を探っていきます。
Oct 9, 2005
コメント(4)
-
一歩前進します~
昨日はたくさんのコメント頂きありがとうございました。( 6日の記事)プログを始めて、早や一ヶ月半ほど経ちました。なにげなく始めたプログだけど、徐々に操作にも慣れ・・記事には、自分の想いやみんなに知ってもらいたいなぁと思うことなど思い浮かぶままに書かいてきました。いろんな方からコメントをもらったり、自分も他の人のプログにコメントしたりの充実した1ヶ月半でした。というように、楽しんだり、楽しませてもらったりしてきましたがこの辺で、また一歩前進のために課題を明確にしてやっていこうと思います。.............................................................................................小目標が、2つ。・ひとつは、Webデザインの勉強を一歩進める。・ふたつめは、文章を書く力を一歩向上させたい。具体的な内容としては、一つ目に対しては、CSS,Javascript,Flash画像などの復習と習熟に向けての行動を起こす。これに関しては、FC2プログを立ち上げました。今、テンプレートのデザインをいじっていますが、楽天プログほどには簡単にいかないので、少し手こずってます。二つ目に対しては、文章を書くときの基本的なことを学んでいく。これには、齋藤孝さんの「書く力」から学ばさせてもらうことにしました。昨日、コメントで「楽しい内容で、文章が上手いですね。」という私としては、恐縮してしまうようなコメントを頂きましたが、本人は文章を書くのは苦手意識があって、毎回どう書いたらうまく伝わるかなぁ~と四苦八苦して(これは大袈裟^_^;)。だから、文章を書くときにどういうことに気をつけたらいいのか、基本的なポイントだけでも学んでみることにしました。学びながら、皆さんにもお伝えさせて頂こうと思っています。
Oct 8, 2005
コメント(7)
-
CSS練習_2
テーブルラインの作り方大きなテーブル枠に入れてやってみましたら、連続した表のようなものがつくれそうでしたが、構文が長いせいなのか、指定した数値どおりのものができませんでした。断念ながら、、。
Oct 7, 2005
コメント(3)
-
CSSの練習_1
テーブルラインの作り方下記のように作ってみましたが、枠と枠の間に空間ができ、その空間を埋める方法は?このテキスト記述が自動改行になっているせいかなと思いますが、もしわかる方がいたら、教えてくださいね。<table width="525" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: dotted 2px #666666;"><tr><td style="width:85px; text-align:center; padding:5px; background-color:#CCCCCC; border-right:solid 1px #999999; border-bottom:solid 1px #666666;"></td></tr></table>みなさんこんチハ~(^o^)丿いかがお過ごしですか? 秋の味覚はなんと言ってもマッタケ、栗、などいろいろございます。おひとつ如何でしょうか?<table width="525" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: dotted 2px #666666;"><tr><td style="width:525px; text-align:left; padding:3px; background-color:yellow; border-right:solid 1px #999999; border-bottom:solid 5px #666666;">みなさんこんチハ~(^o^)丿いかがお過ごしですか? 秋の味覚はなんと言ってもマッタケ、栗、などいろいろございます。おひとつ如何でしょうか?</td></tr></table>**~こんにちは**~寒くなりましたね。**~**~
Oct 7, 2005
コメント(5)
-

夢と成功と幸せとに思うこと。
昨日は、プログの記事を書き終えたとき、明日は”天高し秋空” になってほしいとなぜか強く思ってましたが、その望みが叶って、”天よアッパレ!!” と讃えたい気分です。^_^夢と成功というということば、本当にキラキラしていて、何かことばの持つ魔力に引きつけられますよね。望んでいた夢が叶ったら・・、目的達成に成功したら・・どんなに幸せかと、いろいろと想像して幸せな気分になります。でも、ちょっと視点をずらしてみつめてみると...もし夢が叶ったら・・また思い描いていた成功を手にしたら・・それが「その後の人生を必ず幸せなものにするか」...というと、また別物なんだと私は思うんです。確かに、その夢なり、成功なりを手に入れた当初は喜び一杯で幸せな気分ででしょう。でも、長い人生からみれば、それは一瞬の期間でしかありません。たいていの場合、また次の夢や成功を追いかけるでしょう。人間の貪欲さってきりがないんですよね。幸せって、その夢や成功を脳裏に描きながら、それを手に入れようと向かっているときや、待っているときだって幸せでいられるんですよね。だから、もし幸せということを大事にするなら、夢や成功を手に入れようとそんなに急ぐこともないんじゃないかなぁ~って、最近思うんですけど。もちろん、若い人が夢や成功を求めて一途になるのは素敵だし、ぜひ頑張ってほしいし、私にもそんな時期がありました。でも、ある程度、歳をとれば交友や日々の生活を楽しみながら、時には寄り道もしながら、ゆっくり向かうのもいいんじゃないかと・・思うこの頃です。これは能力や力のないもののつぶやきかもしれません。^_^;他のひとの意見も聞いてみたいです。そんなの生ぬるい考えだぞ・・とか、何んでもコメントしてもらえれば嬉しいです。
Oct 6, 2005
コメント(11)
-

秋雨の日の思い
今日は、朝から小雨が降り続き、少し冷えます。みなさんのほうは、どうでしょうか?パソコンに向かっていると腰から下が冷えるので今日は、もう電気座布団を敷いてます。女は冷えが大敵!! 特に私は冷えに弱いもんで(^^;って、まだ衣替えがすんなり出来てないせいなんですが・・・・なんて、すっかり日常生活に目が戻りました。そうなんです。あれから、数日たった今はこの前のできごとが通り雨が過ぎたあとのように静かな空気に包まれています。また、時が解決してくれるだろうと思っていましたがいろいろわだかまっていたようなことも何だったのだろう?、、みたいなまどろんだ知覚の中に今います。もしかしたら、昨日の降りしきった雨が洗い流し今日のほんのり明るい小雨が残ったささやかな戸惑いも静めてくれているのかもしれません。みんなも静かな朝をむかえてくれているといいのだけど、、。
Oct 5, 2005
コメント(8)
-

好きなことば―「人間万事塞翁が馬」―
この二日間はいろいろと考えたいこともあり、記事はお休みしました。いろいろな方とメールでお話する機会も与えれ、なにげなく始めたプログなのに、そのお陰でいっそう濃いプログ生活になって行きそうです。まだ、心の整理が充分にできたわけではないですが、また私なり歩きだします。これからもよろしくね。「人間万事塞翁が馬」私の好きなことばの一つです。このことばが私の脇差しの一つとなってから、もう10年以上なります。私は嫌なことや落ち込むことがあっても、このことばで暗示にかけて、フゥ~とため息ひとつ付いたら、あとは前へ進みます。たんたんと・・。というと、ちょっとカッコ良すぎですね。いろいろ動揺しながらも・・です。^_^;反省すべきところはその時にじっくり考えますが、ある程度やってみたら、そこで一旦止めおきます。歩きながら、問題点が見えて来たりするからです。きっと、別の視点でながめる機会がおとずれるからでしょう。有名なことわざなのでご存知の方が多いでしょうけど。簡単に由来を書いてみます。「人間万事塞翁が馬」(逸話)(にんげんばんじさいおうがうま)塞翁(さいおう)という老人の飼っていた馬が逃げた。が、舞い戻ってきたときには、たくさんの駿馬を連れていた。しかし老人の息子がその馬から落ちて怪我をしてしまう。でもそのケガのおかげで戦争に行かずにすんだ。という、中国の故事「淮南子」から由来することわざです。この話から、幸・不幸、あるいは福・禍は交互に来るものだというとらえ方もありますが、私はこんなふうにこのエピソードを解釈しています。幸福のなかには、不幸の種も宿しているし、また、不幸な状態のなかにも、幸福な種を宿しているものです。だから、どんな状態のときも、たんたんと生きるのがよいと。これに似たことばに「禍福は糾える縄の如し」というのもありますが、私は、この「人間万事塞翁が馬」のほうが好きですね。★この逸話のもっと詳しい筋書きはこちらにあります。
Oct 3, 2005
コメント(11)
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
-

- 私なりのインテリア/節約/収納術
- 手元に現金がなさすぎ問題
- (2025-11-24 00:39:26)
-
-
-

- φ(._.)主婦のつぶやき☆
- 我が家の玄関を格安でスマートロック…
- (2025-11-24 13:10:04)
-
-
-

- 日常の生活を・・
- カラスの大群の低空飛行は不気味です…
- (2025-11-22 19:42:01)
-






